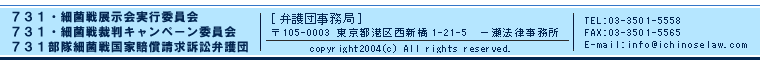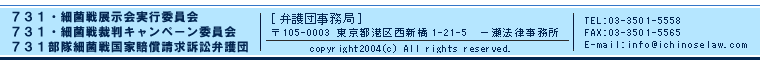�����P�S�N�i�l�j��S�W�P�T��
�T�i�l ���@�G�łق��P�V�X��
��T�i�l�@��
���@���@���@�ʁi�P�j
�����P�T�N�W���S��
���������ٔ�����Q�������@�䒆
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@�@�@�@�@�@�@�@�@��T�i�l�w��㗝�l
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@�{�@�@�@�c�@�@�@���@�@�@�i
�@�@�@�� �@ �@�@���@���@��
�F�@�@�@�J�@�@�@���@�@�@�C
���@�@�@���@�@�@�F�@�@�@�M
���@�@ �@�@�@�@�@���@�@�@�D
���@�@�@��@�@�@�p�@�@�@�m
���@�@�@���@�@�@�@ �@�@�@�W
�ځ@�@��
��P�@���Ɩ����ӂ̖@���Ɋւ���T�i�l��̎咣�ɂ���
�@�P�@�T�i�l��̎咣�̗v�|
�@�Q�@��T�i�l�̔��_
�@�@(�P)�@���Ɩ����ӂ̖@�����m�����Ă��Ȃ��Ƃ����T�i�l��̎咣�ɂ���
�@�@�@�A�@�s���ٔ��@�P�U���ɂ���
�@�@�@�C�@�{�A�\�i�[�h���@���Ă��獑�ƐӔC�K����폜�������Ƃɂ���
�@�@�@�E�@����
�@�@�@�G�@�T�i�l��̎咣�ɑ��锽�_
�@�@�@�@(�A)�@����ɂ���
�@�@�@�@(�C)�@�w���ɂ���
�@�@�@�@(�E)�@���@�҈ӎv�ɂ���
�@�@(�Q)�@�K�@�Ȍ����͍s�g�����Ɋ�Â��Ȃ����Ƃ������_�ɂ���
�@�@(�R)�@���Ɩ����ӂ̖@���̐l�I�E�ꏊ�I���E�������_�ɂ���
�@�@(�S)�@�w�[�O������̍����@���ɂ�鍑�Ɩ����ӂ̖@���̔r���������_�ɂ���
�@�@(�T)�@���݂̖@���߂Ɋ�Â��ٔ����ׂ��Ƃ����_�ɂ���
�@�@�@�A�@�s������Ƃ��ׂ����Ƃɂ���
�@�@�@�C�@�s������Ƃ��ׂ����Ƃɂ���
�@�@(�U)�@�����n�قR�������ɂ���
�@�@�@�A�@�����n�قR�������̊T�v
�@�@�@�C�@��T�i�l�̔ᔻ�̊T�v
�@�@�@�E�@���Ɩ����ӂ̖@���̍����̗������s�\���ł��邱�Ƃɂ���
�@�@�@�@(�A)�@�����n�قR�������̔���
�@�@�@�@(�C)�@���Ɩ����ӂ̖@���ɂ���
�@�@�@�G�@�����@�����U���y�эō��ُ��a�Q�T�N�����Ƒ������邱�Ɠ�
�@�@�@�@(�A)�@�����n�قR�������̊T�v
�@�@�@�@(�C)�@�������@���ɂ����鍑�Ɩ����ӂ̖@���Ɩ��@���߂Ƃ̊W�ɂ���
�@�@�@�I�@�����@�����U���Ɉᔽ���邱��
�@�@�@�J�@�ō��ُ��a�Q�T�N�����ɔ����邱��
�@�@�@�L�@�����n�قR�������̗��R���ɂ�����@��P�P���̓K�p��ے肵�����R�Ɩ��������邱��
�@�@�@�N�@���_
��Q�@���ˊ��Ԃ̓K�p�Ɋւ���T�i�l��̎咣�ɂ���
�@�P�@���@�V�Q�S����i�̖@�I���i�ɂ���
�@�@(�P)�@�T�i�l��̎咣
�@�@(�Q)�@��T�i�l�̔��_
�@�Q�@���ˊ��Ԃ̓K�p�����ɂ���
�@�@(�P)�@�T�i�l��̎咣
�@�@(�Q)�@��T�i�l�̔��_
�@�@�@�A�@�ō��ٕ����P�O�N�����ɂ���
�@�@�@�C�@�����n���ٔ��������P�R�N�V���P�Q�������ɂ���
�@�@�@�E�@�����n���ٔ��������P�S�N�S���Q�U�������ɂ���
�@�R�@����
��R�@�𗝂Ɋւ���T�i�l��̎咣�ɂ���
��S�@�@��P�P���ɂ�菀���@�ƂȂ�Ƃ��钆�����@�Ɋ�Â������ɂ���
�@�P�@���ێ��@�̓K�p�\���ɂ���
�@�Q�@���ێ��@�̖@���W�̐�������ɂ���
�@�R�@�@��P�P���̓K�p�̉\���ɂ��Ă̏���
�@�S�@���{�@�̗ݐϓK�p�ɂ���
�@�@(�P)�@�ݐϓK�p�̓��e�ɂ���
�@�@(�Q)�@���{�@�̓K�p�ɂ���
�@�@(�R)�@�s������Ƃ��ׂ����Ƃɂ���
��T�@���@�s��ׂɊւ���T�i�l��̎咣�ɂ���
�@�P�@�T�i�l��̎咣
�@�Q�@��T�i�l�̔��_
��U�@�s���s��ׂɊւ���T�i�l��̎咣�ɂ���
�@�P�@�T�i�l��̎咣�̗v�|
�@�Q�@��T�i�l�̔��_
�@�@(�P)�@�T�i�l��̎咣����悤�Ȗ@����̍�`�����T�i�l������Ȃ����Ƃɂ���
�@�@(�Q)�@���t���T�i�l��̎咣�����`���̎�̂ƂȂ鍪�������m�ɂ���Ă��Ȃ����Ƃɂ���
�@�R�@����
��V�@�B�ׂ��s�ׂ𗝗R�Ƃ��鍑�Ɣ��������ɂ���
��W�@�������������ɂ���
�@�P�@�{�咣�̎�|
�@�Q�@�����n�ٔ����ɂ���
�@�R�@���������������Ɋւ��鐭�{����
�@�S�@��㏈���̘g�g�݂��Ȃ��T���E�t�����V�X�R���a���ɂ���
�@�@(�P)�@����E����̔������тɍ��Y�y�ѐ������̖��̉����̂����
�@�@(�Q)�@�T���E�t�����V�X�R���a���ɂ������̊�{�I���e
�@�@�@�A�@�T���E�t�����V�X�R���a���̊�{�I���e
�@�@�@�C�@�T���E�t�����V�X�R���a���ɂ�������{�̔����ӔC
�@�@�@�E�@�T���E�t�����V�X�R���a���Ɋ�Â����{��������������
�@�@�@�G�@�T���E�t�����V�X�R���a�������̎���
�@�@�@�I�@���������������ɂ���
�@�@(�R)�@�T���E�t�����V�X�R���a���P�S��(b�j�̉���
�@�@�@�A�@�T���E�t�����V�X�R���a���P�S��(b�j�̖@�I����
�@�@�@�@(�A)�@�A�����̐������ɑ������
�@�@�@�@(�C)�@�A���������̐������ɑ������
�@�@�@�@(�E)�@���ړK�p�̗L��
�@�@�@�C�@�č����{�̈ӌ����ɂ���
�@�@�@�E�@�T���E�t�����V�X�R���a���P�S��(b�j�̕\���ɂ���
�@�T�@���̑��̐�㏈���ɂ���
�@�@(�P)�@�r���}�A�M�Ƃ̊W�ɂ���
�@�@(�Q)�@�C���h�l�V�A���a���Ƃ̊W�ɂ���
�@�@(�R)�@���I�X�y�уJ���{�f�B�A�Ƃ̊W�ɂ���
�@�@(�S)�@���\���B�G�g�Љ��`���a���A�M�Ƃ̊W�ɂ���
�@�@(�T)�@���̑��̏����Ƃ̊W�ɂ���
�@�U�@�䂪���ƒ����Ƃ̊Ԃ̐�㏈��
�@�@(�P)�@�T���E�t�����V�X�R���a���Ƃ̊W�ɂ���
�@�@(�Q)�@���{�Ɓu���ؖ����v�Ƃ̊Ԃ̏����ɂ���
�@�@(�R)�@���{�ƒ��ؐl�����a���Ƃ̊Ԃ̏����ɂ���
�@�@�@�A�@�����������������Ɏ���o�܂ɂ���
�@�@�@�C�@�������������T���ɂ���
�@�@�@�E�@�č��ɂ�����ٔ��̐��ړ��ɂ���
�@�V�@�������{�̌����ɂ���
�@�W�@����
�@��T�i�l�́C�{�������ʂɂ����āC�T�i�l��̂Q�O�O�R�N�i�����P�T�N�j�S���Q�P���t����P��������(�ȉ��u�T�i�l���P�������ʁv�Ƃ����B)�ɂ�����咣�ɑ��C�K�v�ƔF�߂�͈͂Ŕ��_����B
�@�Ȃ��C�����́C���ɒf��Ȃ�����C�]�O�̗�ɂ��B
�@

��P�@���Ɩ����ӂ̖@���Ɋւ���T�i�l��̎咣�ɂ���
�@�P�@�T�i�l��̎咣�̗v�|
�@�T�i�l��́C���@�V�O�X���Ȃ������@�V�P�P���܂��͖��@�V�P�T���Ɋ�Â��Ė{�i�������F�߂���ׂ��|�咣���C�{���ɂ����ẮC�u���Ɩ����ӂ̖@���v�͓K�p����Ȃ��Ƃ��āC�v�|���̂Ƃ���咣����(�T�i�l���P�������ʂQ�O�Ȃ����T�U�y�[�W)�B
�@(1) ���Ɩ����ӂ̖@�����m�����Ă��Ȃ�����
�@���Ɩ����ӂ̖@���ɂ��Ď���@��̍����͑��݂����C���ᗝ�_�Ƃ��Ă��C�����̊w���ɂ���Ă��C���@�҈ӎv�ɂ���Ă��m�����Ă��Ȃ������B
�@(2) �K�@�Ȍ����͍s�g�����Ɋ�Â��Ȃ�����
�@���Ɩ����ӂ̖@���́C���Ƃ̍s�ׂ������̂��߂̌��͍�p�ł���ꍇ�ɁC���Y������ی삷�邽�߂̂��̂ł����āC���Y�s�ׂ������̂��߂̌��͍�p�ɓ�����Ȃ��ꍇ�ɂ́C���̍s�ׂɂ��Ă����@��̕s�@�s�אӔC���������邱�ƂR�̂��ƂƂ��Ă�����̂ł���Ƃ���C�{���̍ې�́C�K�@�Ȍ����͍s�g�����Ɋ�Â��Ȃ�����C���Ɩ����ӂ̖@���͓K�p����Ȃ��B
�@
�@(3) ���Ɩ����ӂ̖@���̐l�I�E�ꏊ�I���E
�@���Ɩ����ӂ̖@���́C���Ƃ̓������ɕ����Ȃ��҂ɑ��Ă͓K�p����Ȃ��B
�@
�@(4) �w�[�O������̍����@���ɂ�鍑�Ɩ����ӂ̖@���̔r��
�@�w�[�O������͍��ۊ��K�@�Ƃ��Đ����������@�����Ă�������C�����@�͂���ɓK������悤�ɉ��߂���Ȃ���Ȃ炸�C���Ɩ����ӂ̖@���͓K�p����Ȃ��B
�@
�@(5) ���݂̖@���߂Ɋ�Â��ٔ����ׂ��Ƃ̎咣
�@���Ɩ����ӂ̖@���́C�葱�@��̗��R�������ƂȂ��Ă���ɂ������C�s���ٔ������p�~����C�i�ׂ��i�@�ٔ����Ɉꌳ������Ă�����{�����@�̉��ɂ����ẮC���Ɩ����ӂ̖@����K�p���鍪���͂Ȃ��C���Ƃ̊L�U�ܐӔC�ɂ��Ă͌����_�ł̖@���߂Ɋ�Â��ׂ��ł���B
�@
�@�Q�@��T�i�l�̔��_
�@
�@(1) ���Ɩ����ӂ̖@�����m�����Ă��Ȃ��Ƃ����T�i�l��̎咣�ɂ��čT�i�l��́C���Ɩ����ӂ̖@���ɂ��Ď���@��̍����͑��݂����C���ᗝ�_�Ƃ��Ă��C�����̊w���ɂ���Ă��C���@�҈ӎv�ɂ���Ă��m���������_�ł͂Ȃ��|�咣����B
�@�������C�ȉ��ɏq�ׂ�悤�ɁC�s���ٔ��@�y�ы����@�́C���Ɩ����ӂ̖@���Ɋ�Â��Đ��肳�ꂽ���̂ł���C�s���ٔ��@�Ƌ����@�����z���ꂽ�����Q�R�N�̎��_�ŁC���Ƃ̌��͓I��p�ɂ��Ă̍��Ɩ����ӂ̖@�����̗p����Ƃ�����{�I�@���m���������̂ł���(����G�E�s���@�U(����)�Q�Q�Q�C�Q�Q�R�y�[�W�C�F�ꍎ��E���ƐӔC�@�̕��͂S�O�X�Ȃ����S�P�P�y�[�W)����C�T�i�l��̎咣�͎����ł���B
�@
�@�A�@�s���ٔ��@�P�U���ɂ���
�@
�@(�) �������@�́C�s���ٔ����x�Ɋւ��C�u�s�������m��@�����j�R�����������Q�Z�����^���g�X���m�i�׃j�V�e�ʃj�@�����ȃe�胁�^���s���ٔ����m�ٔ��j���X�w�L���m�n�i�@�ٔ����j���e�X���m���j�݃��X�v�ƋK�肵(�U�P��)�C�s���ٔ����i�@�ٔ���蕪�����C�s���i�ׂ�R�����邽�߂ɕʂɍs���ٔ�����݂��邱�Ƌy�т��̍\���͖@���������Ē�ނׂ����̂Ƃ̌������f�����B
�@�Ƃ���ŁC�s���ٔ��@�P�U���́u�s���ٔ����n���Q�v���m�i�׃��Z�X�v�ƋK�肵�Ă��邪�C���̍s���ٔ��@�Ă��쐬����ɓ�����C�挈�I�ɉ������ׂ����Ƃ��āC�����Ȃ��肪��������C���������ꂽ���ɂ��ẮC�ɓ��������Ҏ[�����u�����W�����v�����́u�s���ٔ����ݒu�m���v�Ƒ肷�鎑��(����Q�U����)�ɂ�������邱�Ƃ��ł���(�s���ٔ����E�s���ٔ����\�N�j�E����Q�V���Q�U�Ȃ����Q�X�y�[�W�C�a�c�p�v�E�s���ٔ�(�@�̐��m����)���{�ߑ�@���B�j�R���P�P�P�y�[�W)�B
�@����ɂ��ƁC�u�s���ٔ������݃N���j�n���m�ލ��m��胒����X�����v�X�B�v�Ƃ��āC�s���ٔ�����ݒu����ۂɌ������ׂ����_����Ă��邪�C��R���́u�v���m�i�n�[�ʃj�����ٔ��j�����x�L�J�C���n���������j�����s���ٔ��j���e�|���X�x�L���B�v�Ƃ������_�ɂ��āC���̂悤�Ȍ��_�������Ă���B
�@���Ȃ킿�C�u�N��n�s�P��ਃX�R�g�\�n�Y�B�̃j���{�m��܃j�˃����|�u�n�v���m�Ӄj�C�[���g�n��ʃj���@�{�m���F�X�����i���o�C�l���n��l�g�V�e�����m�̑��|�u���i�ցC�����ٔ����j�v���X�������N�O�C�s���L������惊�v���m�i��ਃX�m�܃A���R�g�i�V�B�A�V�@���j�˃����{�n�����m�Ӄj�C�Y�x�L�R�g�������V�^������(��ᢗ߃m�@�V)�j���e�n�C�s���ٔ����n�v���m�i���X���R�g�����x�V�B���s���ٔ����j���e����X���m�s���|���j�˃��C���ڃj���Y�x�L���Q�m�����n�s���L�j���e�V�������X�x�L���m�g�X�B(�A�V���p�߃j�����m�i���i�@�ٔ����m�܌��j���V�^���K�@�L�����A���҃n���m���j�݃��Y)�v�Ƃ��Ă���B(����Q�U���R�U�V�C�R�V�O�y�[�W)
�@����ɂ��C�s���ٔ��@�̐���ߒ��ɂ����āC���{�̎匠�Ɋ�Â����u���Ȃ킿�����͂̍s�g�ɊY������[�u�ɂ���Đ��������Q�ɂ��ẮC���@�w�㓖����ʂɐ��F����Ă������Ɩ����ӂ̖@���ɂ��C�l�́C�����Ƃ��čs���ٔ����ɑ��đ��Q�����̑i�����N�ł��Ȃ��Ƃ����̂ł���B
�@
�@(�) �܂��A�s���ٔ��@�Ă̌��Ă��쐬�������b�Z�́C���̕s�@�s�אӔC��ے肵�C�i�@�ٔ����݂̂Ȃ炸�C�s���ٔ����ɂ����Ă��B���ƐӔC��₢���Ȃ��Ƃ��Ă����B
�@�@�@���Ȃ킿�C���b�Z�́C�u���m���@�㑹�Q�����`���j�փX���ӌ��v�Ƒ肷�铚�c�ɂ����āC����������̊������s���ꍇ�ɂ́C���͖��@�ɏ]�ĐӔC���C�����ٔ����ɑ��Q���������i�ׂ��N���邱�Ƃ��ł���Ƃ���(�X�ցC�d�M�C�S�����Ɋւ��C���ʂ̐ӔC�K�肪����C����͖��@�ɗD�悵�ēK�p�����)���C���������������s����ɍۂ��C�`���ᔽ�̏��u�Ⴕ���͑Ӗ��ɂ���O�҂ɉ��������Q�ɑ����Y��ӔC��Ȃ��Əq�ׂĂ���B���������āC���b�Z�́C�����͎�̂Ƃ��Ă̍��ƂƎ��o�ώ�̂Ƃ��Ă̍��Ƃ���ʂ��C�O�҂ɂ��Ă͖����ӁC��҂ɂ��Ă͎��l�Ɠ��l�̐ӔC���Ƃ������߂��̂Ă����̂ł���(�F�ꍎ��E���ƐӔC�@�̕��͂S�O�X�y�[�W�C�S�P�X�C�S�Q�O�y�[�W�C����Q�W���C�S�V�S�Ȃ����S�V�V�y�[�W�E�u���b�Z�����m���@�㑹�Q�����`���j�J�X���ӌ��v)�B
�@
�@(�) �ȏ�̂悤�ɁC�s���ٔ��@�P�U���́C���Ɩ����ӂ̖@���R�̑O��Ƃ��āC�s���ٔ����̑��Q�������������ɌW�鎖���NJ��͈̔͂��߂����̂Ƃ�����B
�@
�@(�) �܂��C���Ɩ����ӂ̖@���́C�����Q�R�N�ɐ��肳�ꂽ�ٔ����\���@�̐���̍ۂɂ��ѓO����Ă���B
�@���Ȃ킿�C�ٔ����\���@�́C�����Q�O�N�T���Ƀ��h���t�����S�ƂȂ��đ��Ă��N�����C�@���撲�ψ���Ō����C�����āC�����Q�R�N�ɖ@���Ƃ��ꂽ���̂ł��邪�C���̖@���撲�ψ����(�鍑�i�@�ٔ����\���@����)�̂R�R���ŁC�u�n���ٔ����n�����i�׃j���e���m�����j�t�ٔ������L�X�v�Ƃ��āC�u���@���R�g�V�e(�)���z��N�n���z�j�S���X���{(�������{�g���z���m�����g����n�X)�����׃V���n�V�j�V�e�׃X���e�m�����@(�)���z��N�n���z�j�S�n���X�����j�V�e�׃X���e�m�����A���������������N���^�����j�����@(�)������ٔ�����N�n���ʍٔ����j�ꛢ�X�����m�����L���e�m�����v�Ƃ���Ă���(���R�l��E�l���ƍs���~�ϖ@�U�W�y�[�W)�B
�@�@�@�Ƃ��낪�C���B���ӌ������o���C��L�̂����C���ƐӔC�Ɋւ���i�ׂ����閾���̋K�肪���Ă���폜����邱�ƂƂȂ�(�c������ҁE�̌n���@���T�R�U�T�y�[�W�ȉ�)�B�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@
�@�@�@���̈��B�̈ӌ���(�ٔ��\���@�Ĉӌ��E���B�̎j���ё��U�P�S�y�[�W�E����Q�X����)�ɂ́C���̂悤�Ȉӌ���������Ă���B�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���Ȃ킿�C�u���@���j���X���i�׃m���@�u���N�X�g�������ܕщ]�n�N���j���X���i�׃n�����g嫃��V�����i�X�R�g�\�n�X�W�V���m�@�@���������ٔ��X���m�@�܃i�P���n�i���g�̃j�p���j���e�N��y�q���{�j���X���m�i�׃n�B�X����j�R���e���b�m�������^����n���e�ٔ�����N���R�g�����@�����甪�S�O�\��N�\�l���m�t�߉]�n�N�N��m���i�j���e�b���g�m��j�ٌ����v�X���m�ܗ��m�������X���m���i�N���V�����ٌ��X���m�܌��A���ٔ����n�S���j�ꃂ���X���R�g�i�V�g�@���{�j���X���i�׃n�Ո�j���e���܃g���ʃV�^�����Y��m�i�����V�^���m�~�j�V�e�d���j���X���i�׃g�V�e�V�������V�^���u�m�v���A���R�g�i�V���{�ēj���X���i�׃��ȃe�ٔ����m�ܓ��jV�^���n���m�c�����U���m�~�i���Y�ꃉ�����O���l�m���{���{�j���X���i�׃mਃj�n��ਃX�҃i���v�C�u��O�@�����m�����j���V�e�n�v���X���R�g�����X���g�i���n���m�����n���܃m�ꕔ�j�V�e���܃n���@��m�ӔC�i�L�҃i���n�i�������j���X���m�v���n���m�����m�����g�V�e�i�t���҃j�����w�V��O�\��(�n)�m�ꍇ�n���@�m�呥�j�w�N���v(���p�Ғ��E��L��O�\�Ƃ́C�鍑�i�@�ٔ����\���@���ĂR�R���ɑ�������B)�Ƃ����B�@�@�@�@�@�@�@�@ ����ɂ��C���B�́C���Ɩ����ӂ̖@���������ɁC���Ɣ��������i�ׂ��i�@�ٔ����ɒ�N�ł��Ȃ��Ƃ����̂ł���C���̈��̈ӌ����q�ϓI�ɒʂ��`�ōٔ����\���@�����肳�ꂽ�̂ł���(���R�E�O�f�l���ƍs���~�ϖ@�U�W�Ȃ����U�X�y�[�W�B���|�������ٕ����P�S�N�R���Q�W�������E����R�O����)�B
�@
�@(�) �ȏ�q�ׂ��悤�ɁC�s���ٔ��@�y�эٔ����\���@�́C���Ɩ����ӂ̖@���������Ƃ��āC�s���ٔ����y�юi�@�ٔ����́C����������Ɣ��������i�ׂ����Ȃ����̂Ƃ����B���̂悤�ɁC���ɑ��锅�������́C��{�I�ɂ́C�s���ٔ����݂̂Ȃ炸�C�i�@�ٔ����ɂ����Ă��ے肷��l���ł������̂ł���C���̊�{�I�Ȗ@�\���́C���͓I��p�Ɋւ������C�Ȍ�C���{�����@�Ɏ�����I�]�̊Ԍp���������̂Ƃ�����(���R�E�O�f�l���ƍs���~�ϖ@�U�X�y�[�W)�B
�@
�@�C�@�{�A�\�i�[�h���@���Ă��獑�ƐӔC�K����폜�������Ƃɂ���
�@
�@(�)�@��L�̂悤�ɁC�s���ٔ��@�y�эٔ����\���@�̗��@�҈ӎv�́C���Ɩ����ӂ̖@���������Ƃ��āC�s���ٔ����y�юi�@�ٔ����́C����������Ɣ��������i�ׂ����Ȃ��Ƃ��Ă����̂ł��邩��C���̖@�ł��閯�@�ɂ����āC���̌��͓I��p�ɂ��Ĕ����ӔC��F�߂���K�肷�邱�Ƃ͖����ł���B���������āC�{�A�\�i�[�h���@���ĂR�V�R�����獑�Ɣ����ӔC��F�߂镶�����폜�����̂́C���Ɩ����ӂ̖@�����̗p����Ă������߂ł��邱�Ƃ͖��炩�ł���B
�@
�@(�) ���̓_�C�@����b���[�i�@�@���������ďC�E���{�ߑ㗧�@�����p���P�O���@�Ҏ[�j���X�����ӌ���趏��R�X�W�y�тR�X�X�y�[�W(����R�P����)�̋L�q�ɂ��C�����@�R�V�R���̐R�c�̉ߒ��ɂ����āC�����Ɂu���m�������m�ӔC�v���K�肵�����R�ɂ��C�N����(�{�A�\�i�[�h)�́C�u��l�J����َ҃m��ਃj�t�L�Ӄj�C�X���g���N���ƕ{�p�����������@�m�K��j�n�q���l�m�Ӄj�C�X�V�����j�t�e�n�Ś������m�����j���e�����^���m�٘_��ਃT�T�����i�����{�j���e�����K�X���J�����̓ƃn�X�ցC�d�M�C�c���^���m�@�L������e�����s�t�ꍇ�j���e���g�p�X���҃m�ƍߖ��n���ƍ߃j�t�L������Ӄj�C�X�w�L�m�~�i���X���m���v���nᢎ˃�ਃX�������n�M�������B�X���R���m�ߎ��������X�����Q�y�q�s�������m�E�ܗ��p�j�������Q�j�t�e�������V�t���Ӄj�C�X�V�g�v�Ɛ��������B���Ȃ킿�C�{�A�\�i�[�h�́C�����͌����c�̂̌��͓I��p�ɂ����@��K�p���ׂ����Ƃ̓t�����X���̑��̏����ɂ����Ă��٘_�̂Ȃ��Ƃ���ł��邩��C���{�ɂ����Ă����l�Ƃ��ׂ��ł���Ƃ����̂ł���B�@�����āC�{�A�\�i�[�h�̂��̒�Ă��āC�����ψ��́C�@���ɐӔC��Ə�����K���u���ȊO�́C�����͌����c�͔̂����ӔC���ׂ��Ƃ̏C���Ă̈ӌ��������C����Ɉ��ψ����C�u���ƃg�l���g�����ʃV�l���n�ِl�m�ߎ��������V�^�����Q�m�ӔC���L�X�������ƃn�V�j���V�����m��s�������V�^�����Q�m�Ӄj�C�Z�X�g�m�@���n�V����ᢌ��X�w�J���T���v�Ƃ̈ӌ��������āC�R�V�R���̕��������̂܂܂ɂ��āC�u���j���ӔC���Ə��X���ꍇ�n�����j�݃��X�v�Ƃ̒A����������ׂ��ł���ƒ�Ă������̂Ƃ���Ă���B
�@�����Ŗ��炩�Ȃ悤�ɁC�{�A�\�i�[�h���@���Ă̐R�c�ߒ��ł́C���@�Ɣ����ӔC��F�߂���K�肷�鍪���Ƃ��āC�����͌����c�̂̌��͓I��p�ɂ����@��K�p���ׂ����Ƃ��t�����X���̑��̏����ɂ����Ă��٘_�̂Ȃ��Ƃ���ł���Ƃ̔F����O��Ƃ��Ă���B
�@
�@(�) �������C�����̖@���ǒ����ł������B(���B�̖@���ǒ����ݔC���Ԃ́C�����Q�P�N�Q����蓯�Q�S�N�T���܂łł���B)�́C�����a�Y�y�юi�@��b�R�c���`�ɑ��āC�{�A�\�i�[�h�̌��������ł��邱�Ƃ��w�E���Ă���B
�@�܂��C���B�́C�����Q�Q�N�U���Q�Q���ɁC�����a�Y�Ɉ��Ă����ȂŁC���̂Ƃ���q�ׂĂ���B
�@�u����C�M���m���Y�N�V�^�����c����m�v�����n�A�Սs���ٔ��m���i���m�~�i���Y�C�����@�O�S���\�O���j�A�e�m�����m����i���x�V�C(���j��C���@�O�S���\�O���j�����m�������g�A���n���Ӗ��ăi���T�����C���{�����ĎO�S��\�O���j���w���A�h�~�j�X�g���V�����m�Ӄi���J�)�}���O�S���\�O���n�C�Ŗ��@��O�S���\�l���j��N���m�i���w�V�g嫁C�Ő�O�S���\�l���n�C�z�N�}�e�j�����Z�Y�C�̃j�{�҃m���n�V�����ƃj�}�e�K�p�X���m�X���A���C���j�M���m�����m�@�V�g嫁C�܌��ٔ����m�����n�C�S�N�����m��`�j�o�C���ƃn�w�����m�|�u�j�t�e�S.�N���m�Ӄj�C�Z�Y�x�g�m�������惊�^���n�C�M���m�f�����n�m�Z�����i���C�p���y�Ě��j�e�n�C���@�㊯���m�g�p�n�C���@�m�㗝�g�S�N���m���R�����N�Z�Y�g�m��`���惊�^���n�C�����őO�m���@���σn�T�Y�C(�Đl�X�g���[���㗝�@�O�S�\���)�Չ��j�e�n�̔��ݎm�ށC���R�m���@�����j�A�e�n���ƃn���Ƀm����(���ܗ��`�����L�X���v�@�l)�g�V�e�C���@��m�����ӔC�A���R�g�j�A�e�n�C�e�h�m�{�Җ�ًc�i�V�g嫁C���܃����s�X�������m�|�u�y�Ӗ��j�t�e�n�C�b�m�{�ҁv�n(�X�^�C���C�U���E�G�[�C���X������)�����m�ꍇ���C���@��m�ӔC�i�V�g���q�C���m�{�҃n(�Q���x���C�}�C�G���C���[�t������)���ꍇ�j���e�ӔC�����X�w�V�g���t�C���V�e���ۃm�ٔ���j���e�n�C���ʃm�@���m�����j���L�V�^���ꍇ�����N�O�C���R�ƃm�����������F���Y�C�v���e���m���@�_�j���e�@���ٓ��A���e���^�d��m���y�����U���j�S���Y�C�䖯�@���ăn��_�j�����ƃ���ԃm���j��ᶃV�e���@�m�͉����j�������g���~�^���n�C�����n�S�Q�j���w�T�����i���C�����n�C�P�ċc�m�@�����҃c�w�V�g嫁C�O�m���R�j�����C�����n�O�m���c�������g�X���m�v���j��X���R�g�\�n�T���m�⊶�����N�m�~�i���X�C���C���@��m���j臃V�C�S�N�M���g�����m�ʒn�j���c�m�s�K�����^���R�g���ɒQ�Z�Y���n�A���Y�C�ڎ�C�v(���B�B�j���ё�l�E����R�Q���R�Q�R�y�тR�Q�S�y�[�W)�B
�@���̏��ȂŁC���B�́C���O���ɂ����ẮC���������s���銯���̏��u�y�ёӖ��ɂ��ẮC�w�҂̐��͏��������邪�C���ۂ̍ٔ���́C�����Ƃ��āC���̔����ӔC��F�߂Ă��Ȃ��Ǝw�E����B���̏�ŁC���B�́C�����ł���ɂ�������炸�C�{�A�\�i�[�h���@���Ăł́C��_�ɂ���Ƃ͔����ӔC���ƋK�肵�Ă��邱�Ƃ͊S�Q�Ɋ����Ȃ��Ƃ��C������u�����m����v���u�ċc�m�@���v���Ƃ炦�Č�������Ƃ��Ă���B
�@
�@(�) ����ɁC���B�́C������{�A�\�i�[�h���@���Ăɑ��錜�O���̎i�@��b�R�c���`�ɑ��Ă��q�ׂĂ���B
�@���́C�����Q�Q�N�U���Q�X���ɁC�i�@��b�R�c���`�Ɉ��Ă����ȂŁC�R�c�ɁC�u���@�O�S��\�O���j�t���ҁC�ًc�n�ʍ����X�Z���ӌ��j������C�����������@��j萌W�V�C�����Ƒ����\��C����������V��n�C�O���l���Ɛ��{�Ƃ̑��c�V�_���Ƒ��������j��w�n�C�X�j��悵��֑����x���]��C�P�Ś��j�����Ă��画����n�{�A�\�i�h���V���Ɩ�������������C��������V�����V暜ߒǁX�j��旗��C�ڎ�C�v�Əq�ׂĂ���(����R�Q���U�R�X�y�[�W)�B
�@���Ȃ킿�C���́C�{�A�\�i�[�h���Ă����Ƃ̔����ӔC��F�߂��_�ɂ��āC�������@��̈����ƂȂ�C�������ɂ��C�O���l�Ɠ��{���{�̖�̑����̘_���ƂȂ�ƌ��O���C����Ƀ{�A�\�i�[�h�̌����́C�t�����X�ɂ�����ٔ���Ƃ���������Ɣᔻ���C���b�Z�ӌ����̖ق��{�A�\�i�[�h�̌����ɔ�����؋����R�c�i�@��b�ɕ�悷��Əq�ׂĂ���B
�@�����āC���́C�����Q�Q�N�W���P�Q���ɁC�ɓ������Ɉ��Ă����ȂŁC�ɓ��ɁC�u�ʎ����@���Đ��{�����ӔC�V���j������ӌ����C�i�@��b�ւ����o��ԁC�d����C�v(����R�Q���P�T�U�[�W)�Əq�ׁC���Ƃ̔����ӔC�Ɋւ���ӌ������R�c�i�@��b�ɒ�o�����Ƃ��������Ă���B
�@
�@(�) ���̂悤�ɁC�����@�̐R�c�ߒ��ŁC�l�X�Ȉӌ����\�����ꂽ���C�ŏI�I�ɁC���ƐӔC�ɖ��@������K�p����咣�́C�Ō�̒i�K�Ŕs�ނ��C�����@�R�V�R�����獑�ƐӔC�̋K��͍폜���ꂽ�̂ł���(�ߓ����O�u�{�A�\�i�[�h�ƍs����̕s�@�s�אӔC�v�@��������S�Q����Q���R�������R�S�P�Ȃ����R�T�R�y�[�W�Q��)�B
�@���B�́C���̗��R���C�����@���z�̗��N�ɔ��\�����u���@���e��O�S���\�O���j���X���ӌ��v(���Ɗw��G���S���T�P���X�U�X�y�[�W�ȉ��C����R�R����)�Ƒ肷��_���ɂ����Ė��炩�ɂ��Ă���B
�@���̘_���ɂ����āC���́C�`���ŁC�u�s���܃n���Ɛ����m���J���{�s�X�����m�i���̃j�����J�����s�X���j�c����߈ꎄ�l�m�ܗ����ʑ��V���v���N�Q�X���R�g�A�����ܗ��ٔ���N�n�i��j�˃��V���X���X���j�~�����ƃn�����Q�����m�Ӄj�C�X�����m�j��X�v�Əq�ׁC���̌��͓I��p�ɂ��Ă͍��͑��Q�����ӔC��Ȃ��|���m�ɏq�ׂĂ���B
�@���Ȃ킿�C���́C���@���ď��e�R�V�R���ƃ{�A�\�i�[�h�̌������Љ����ŁC�u���V���e���m�{���j�l�t���j���@�N���҃m���N���g��j�كi�����m�A�����m暍��m�@�V�v�Ƃ��āC�t�����X�C�x���M�[�C�h�C�c�y�уC�M���X���̊e���̖@���x�y�ъw�����Љ�āC�{�A�\�i�[�h�̗����͐��m�ł͂Ȃ��Ƃ��C�u�ȏ�m��暃g�{���g�j���X���n�^�ď����j���e�s���܃m���J�����s�Z���Jਃ��E�܃A�������m���s�V�^�������j�t�e�n�ݗ߈�l�m�ܗ����ʑ��V��N�n���v���N�Q�X���R�g�A�������n���m�������X���X���j�~�����Q�����m�Ӄj�C�Z�X�B�̔��C���݃m�@�L����m�sਃj���X���g�L��N�n�c���C�X�ցC�d�M�m�@�L���j���გ�ȃe���Q���^�ۃV�^���ꍇ�j��T���n���Ӄj�C�X���R�g�i�V�v�Əq�ׂāC���ď����́C�s�����̎��s�Ǝ�����̍s�ׂƂ������ɋ�ʂ��āC���́C�O�҂ɂ��Ă͑��Q�����ӔC�킸�C��҂ɂ��Ă͑��Q�����ӔC�����̂Ƃ��Ă���Ƃ���B
�@���̏�ŁC���́C�u�E�܃A�������J�s���܃m���J�����s�Z���Jਃ��{�s�V�^�������j�V�e�l���m�\�����ʑ��V��N�n���v���N�Q�V�^���g�L����m��ਃg���V�N���@��m�������K�p�V�e���{���m���Q�����m�Ӄj�C�X�w�V�g�Z�n�Љ�m�����j�n�q�����m���J���ێ��V�l���m�K�������i�Z���Jਃ��X�S����ਃT�X���J���T���s���@�J�nਃj���m�^�z����[�Z�����댯�i�����ʃ���o�X���j�������v�Ƃ��C����̂Ɂu���s���@�j�n���m���i�V�v�Ƃ��āC���Ɩ����ӂ̖@�����̗p���ׂ����Ƃ������ɁC���ƐӔC��F�߂Ă����{�A�\�i�[�h���@���Ă̋K����폜�������̂ł���Ɩ��m�ɏq�ׂĂ���B(����R�R��'�X�V�O�C�X�V�S�C�X�V�T�y�[�W)
�@
�@(�)���̂悤�ɋ����@����ߒ��ɂ����āC�l�X�Ȉӌ����\�����ꂽ���C�ŏI�I�ɂ́C���ƐӔC�ɖ��@��K�p����Ƃ̎咣�͔r�˂���C�����ĂR�V�R���ɋK�肳��Ă������ƐӔC�K�肪�폜���ꂽ�̂ł���B
�@
�@�E�@����
�@�ȏォ�疾�炩�Ȃ悤�ɁC�䂪���̖������{�́C�����ɒ��������s�������̉��������Ɠ��W�Ƃ��āC�{�A�\�i�[�h�ȂNJO���̗l�X�Ȗ@���w�҂̈ӌ����Q�l�ɂ��Ȃ���C�ߑ㍑�ƂƂ��Ă̖@���x�̐�����i�߂Ă����B
�@�����āC���̈�Ƃ��āC�s���ٔ��@�y�і��@�̐����}�����C�ߑ�@�����ƂƂ��Čo����L���Ă��Ȃ��䂪���Ƃ��ẮC�����̖@���x���Q�Ƃ��Ȃ���C�@���̐�����}�炴��Ȃ������B
�@���Ɣ����ӔC�̖��ɂ��Ă��C�����C�{�A�\�i�[�h�̈ӌ��Ɋ�Â��C���Ɣ����ӔC��F�߂�K��@�̋K��ɒu�����Ƃ������C�{�A�\�i�[�h�̈ӌ��́C���̑O��Ƃ��Ă̔�r�@�̎����F���Ɍ�F������C���Ɣ����ӔC�Ɋւ��鏔�O���̖@���x�́C�u�N��n�s�P��ਃX�R�g�\�n�Y�B�v(����Q�U���R�V�O�y�[�W)�𗝔O�Ƃ��āC���Ɣ����ӔC��ے肵�����̂ł������ƁC�܂��C���ɁC�{�A�\�i�[�h�̈ӌ��̂Ƃ���C���Ɣ����ӔC�̖����u��_�j�����ƃ���ԃm���j��ᶃV�e���@�m�͚����j�����v(���B�̍����a�Y�����ȁE����R�Q���R�Q�R�y�[�W)��C�u�����������@��j��W�V�C�����g�����\��C����������V��n�C�O���l���g���{�g�m���c�V�_���g���������v(���B�̎R�c���`�i�@��b�����ȁE����R�Q���U�R�X�y�[�W)�����O���C���ǁC���Ɩ����ӂ̖@�����̗p���C�{�A�\�i�[�h���@���Ă��獑�Ɣ����ӔC�̋K����폜�����̂ł���C�s���ٔ��@�Ƌ����@�����z���ꂽ�����Q�R�N�̎��_�ŁC���Ƃ̌��͓I��p�ɂ��Ă̍��Ɩ����ӂ̖@�����̗p����Ƃ�����{�I�@���m���������̂ł���(����G�E�s���@�U(����)�Q�Q�Q�C�Q�Q�R�y�[�W�C�F�ꍎ��E���ƐӔC�@�̕��͂S�O�X�Ȃ����S�P�P�y�[�W)�B
�@
�@�G�@�T�i�l��̎咣�ɑ��锽�_
�@
�@(�) ����ɂ���
�@
�@a�@�T�i�l��́C�������@���̔���́C�l�X�ȕ���ō��y�ь����c�̂̑��Q�����ӔC���g�債�Ă����̂ł���C�u�����͂̍s�g(���͓I��p)�ɂ�鑹�Q�ɂ��Ă͈�т��č��̔����ӔC��ے肵�Ă����v�Ƃ͑S�������Ȃ��B�ނ���C���͓I��p���܂߁C���Ɩ����ӂ̓K�p�̊���B���ł��邩��C�����C���Ɩ����ӂ̖@�����m������Ă����Ƃ͂����Ȃ��ȂǂƎ咣����(�T�i�l���P�������ʂQ�P�Ȃ����Q�V�y�[�W)�B
�@
�@b�@�������Ȃ���C�T�i�l��̏�L�咣�͎����ł���B
���Ȃ킿�C���������E���Ɋւ��ĂȂ����s�@�s�ׂ́C�傫�����ނ���C���͓I��p�ɂ��ĂȂ��ꂽ�ꍇ�ƁC����ȊO�̍�p�ɂ��ĂȂ��ꂽ�ꍇ�Ƃɕ������B��҂ɂ́C�@�͓I�E���I�Ȍ��s���̍�p(�Ⴆ�C���E�����w�Z�ɂ����鋳�犈���̍�p����ی�Ȃǂ̂����鋋�t�s���̕���ɂ������p�Ȃ�)�C�A���̉c�����̐ݒu�E�Ǘ��̍�p�C�B�H���̎{�s(���̓��H���݂Ȃ�)�⎖�Ƃ̌o�c(�S���E�o�X�E�����E�d�C�E�K�X�Ȃǂ̎��Ƃ̌o�c)�̍�p�C�C���R���鎄�o�ϓI��p(���Ƃ��Ί��������p�i�̍w���E���������̒��Ȃ�)�Ȃǂ��܂܂��B
���̂�������́C(1)���͓I��p�̏ꍇ�ɂ��ẮC��т��āC�@���ɓ��ʂ̋K�肪�Ȃ����薯�@�̕s�@�s�ז@�̓K�p���Ȃ�(���@�͑Γ��Ȏ��l�Ԃ̖@���W�Ɋւ���@�ł���C���Ǝ��l�Ƃ̌��͓I�W�ɖ{���K�p�������̂ł͂Ȃ�)���̂Ƃ��āC���̔����ӔC��ے肵�Ă����B�܂��C(2)����ȊO�̂��̂ɂ��Ă��C�O�L�C�̏ꍇ�͕ʂƂ��āC�Â��͇@�A�B�̍�p���C���̔����ӔC��ے肵�Ă������C�吳�T�N�U���P���̂����铿���s�����w�Z�V���~�؎����̑�R�@�����������w�Z�̎{�݂����r�ɂ�鑹�Q�ɂ��āC���w�Z�̊Ǘ��͍s���̔����ł��邪�C���̊Ǘ����ɕ�܂��鏬�w�Z�Z�ɂ̎{�݂ɑ����L���͌��@��̌��͊W�ɑ�������̂ł͂Ȃ��C�u�S.�N���l�J��L�X���g���l�m�n�ʃj���e����L���׃��m�v�Ɣ������āC���@�V�P�V���̓K�p��F�߂Ĉȗ��C���@�V�P�V���C�V�P�T����K�p���č��̔����ӔC���m�肷����������ǂ��̂ł���(�������E���@(��)�k�V�Łl�Q�V�S�C�Q�V�T�y�[�W)�B
���̂悤�ɁC���͓I��p�ɂ��ẮC���@�̕s�@�s�ז@�̓K�p���Ȃ��Ƃ������Ɩ����ӂ̖@���́C���������R�̑O��Ƃ���Ă������̂ł���B
�@
�@C�@�O�L�̂Ƃ���C�s���ٔ��@�y�эٔ����\���@�́C���������E���Ɋւ��Ă����s�@�s�ׂɂ����͔����ӔC��Ȃ��Ƃ�����{�I�@����Ɋ�Â��Đ��肳�ꂽ�@���ł���C�܂��C�����@�ɂ����āC���Ɣ����ӔC�Ɋւ���K�肪�폜���ꂽ�̂��C���l�̗��R�ɂ�邱�Ƃ͖��炩�ł���B
�@���������āC�����̗��@�����ꂽ�����Q�R�N�̎��_�ł́C���̌��͓I��p�ɂ��͓I��p�ɂ����@�̕s�@�s�K��̓K�p�͂Ȃ��C��ʓI�̔����ӔC��F�߂���̖@��̋K��͂Ȃ������̂ł���B
�@��������ƁC��R�@����̔���́C�����́C���@�҈ӎv�ɏ]���C���o�ϊ����������s����p�C���Ȃ킿���͓I���s���y�є͓I���s���̂��ׂĂ̗̈�ɂ��āC���Ɣ����ӔC��ے肵�Ă����̂��C�吳�E���a�Ɏ��āA�͌��s���̗̈�ɂ��āC���@�̕s�@�s�K��̓K�p�͈͂��g�傷�邱�Ƃɂ��C���̐ӔC���m�肵���Ƃ������ƂɂȂ�B�܂�C���o�ϊ������������Ƃ̍�p�̂����C�吳�E���a���ɁC�͓I���s���̕���ɂ��āC���@�̕s�@�s�K����g�債�ēK�p�������ӔC��F�߂�Ƃ�������@�����`������Ă����̂ł���C�����Ȃ�u�͓I���s���L�ӔC�����v������@���Ȃ����ٔ���̏��Y�Ƃ��Č`�����ꂽ�Ƃ����ׂ��ł���B�O�L�����s�����w�Z�V���~�؎����̑�R�@�������C�u���͍�p�������ӁC���o�ύ�p=���@��̐ӔC�Ƃ�����{�I�Șg�g�݂�ύX�����킯�ł͂Ȃ��C���o�ύ�p�̊O�����g�債�����Ƃǂ܂�B�v(�F��E�O�f���ƐӔC�@�̕��͂S�P�W�y�[�W)�̂ł���B
�@�v����ɁC���͓I��p�ɂ��č��������ӔC��Ȃ����Ƃ́C�ٔ�����܂܂ł��Ȃ��m������Ă���C�ٔ���ɂ��`�����ꂽ�@���ł͂Ȃ��C�ނ���C����܂ō��������ӔC��Ȃ��Ƃ���Ă����͓I���s���ɂ��āC��R�@����ɂ���č��������ӔC���Ƃ���C�����Ȃ�u�͓I���s���L�ӔC�����v������@���Ƃ��Č`�����ꂽ�Ƃł������ׂ��ł���B
�@���������āC���Ɩ����ӂ̖@�������ᗝ�_�Ƃ��Ċm������Ă��Ȃ��Ƃ��āC���@����ے肷��T�i�l��̎咣�́C�O��ɂ����Ď����ł���B
�@
�@d�@�Ȃ��C�T�i�l��́C��R�@����̍ٔ���Ɋւ��C�u�吳�����珺�a�̏��߁C�R�{�݁C�w�Z���Ɋւ��锅���܂��͔����ӔC����F�߂��v�Ƃ��āC�u�R�{�݁C�w�Z���Ɋւ���s�ׂ́C�����͌����͂̍s�g(���͓I��p)�Ƃ�������̂ł���C�����͂̍s�g(���͓I��p)�ɂ�鑹�Q�ɂ��Ă��C���@��K�p���đ��Q�����ӔC��F�߂�悤�ɂȂ��v(�T�i�l���P�������ʂQ�R�C�Q�S�y�[�W)�ȂǂƎ咣����B
�@�������C�T�i�l��̈��p����L���n���ٔ������x���吳�P�R�N�U���T������(�@���V����Q�Q�W�Q���T�Q�X�O�y�[�W)�́C�R�͂̓]�������H���ɂ����ĐE�H���]�����������Ăɂ��āC�u�����J���m�E�����s�j�������l�j���Q�����w�^���ꍇ�j���e�n�@�j���ʃm�K��m���Z�T�������V�J�����m�ӔC�i�V�v�Ƃ�����ŁC�u���ƃm�R���s���m�s���n������W�j���X�g嫃����ƃJ���m�H������V���m�@萃��C�݃V�V�j�H���m�{�H�����V���n�H���{�H�j�t���l�j���V����������ਃX�J�@�L�sਃg�E�H�l�v���ٓ����V���g�p�V�e�H�����{�H�X���sy�H���j�K�v�i������m�ޗ����w���X���J�@�L�sਃg�n�S�R���ʃV�e�l�w�T���w�J���X���`�O�҃n�R�̓m�^�����p�H�����s�mਃ����m�����j���n�Z�V�������m�i���n���@�I�sਃj���X���g����҃n���l�g�����m��W�j���eਃX���m�i���n���@�I�sਃj���X�����m�g�]�n�T���w�J���X�v�Ƃ��āC�����E�H���̎��l���g�p���čH�����s���ꍇ�́C���̍s�ׂ̐����㎄�@�I�s�ׂł��邩�甅���ӔC������Ƃ������̂ł���B
�@�܂��C�T�i�l��̈��p����֓��������@�@�㍐�����a�V�N�V���Q�O������(�@���V����R�T�R�X���W�U�V�T�y�[�W)�́C�얞�B�c��������m(�������R���́u�㍐��m�v)�����n�̏��w�Z�ɂ����ăX�P�[�g�w�����̎��̂ɂ��C�u�얞�B�c�������n�j���P���݊O�w�菬�{�Z�m���玖�ƃn�v�C�u�隠���n�j���P���J�@�N���ƃm�����`�����烒�{�X�w�L���ƃm���ƃ����{�Z�ߎs�������m�K��j�˃��s�����m�S����j���e�{�s�X�����m�g�ك��O���C�����C�呠�m�O��b�m���ߏ��j��L�㍐��m�J�v�m�{�݃�ਃV�����胁�^���K���j�˃����ڃm�ē�ਃV���m��p���ȃe���ȃm���ƃg�V�e�S�c�X�����m�j�V�e���j�Y���ƃ��ȃe���m���ƃi���g���X�w�L�@�K�m���X�����m�i�P���n�i���v�Ƃ��āC���Y���w�Z�̋��玖�Ƃ́C���̋��玖�Ƃł͂Ȃ��얞�B�c��������m�̎��Ƃł���|�������C��������m�ɔ����ӔC��F�߂����̂ł���B
����ɁC�T�i�l��́C��R�@���a�V�N�W���P�O������(�@���V����R�S�T�R���P�O�X�W�R�y�[�W)���u���ƃJ�y�n�����L�V���m�����m�ݒu�Ҏ�V�N�n�ۑ��j���r�A���Jਃ���O�҃m�E���p�܃��N�Q�V�^���ꍇ�i���g���n��@�i���s����p�j������O�҃m�ܗ����N�Q�V�^���ꍇ�i���g�j�����ك����i�V�W�V�s�@�sਃm�ӔC�n���m�s҃m���l�i�����j�����V�������ʃZ�T�����ȃe�i���v�Ɣ��������_�����グ�āC�u����́C�s�@�s�҂����Ƃł��낤�����l�ł��낤����ʂ���Ȃ��Ƃ��āC���@�̕s�@�s�אӔC��F�ߖW�Q�r������������F�e�������̂ł��v��C�u�����͂̍s�g(���͓I��p)�ɂ�鑹�Q�ɂ��Ă��C���@��K�p���đ��Q�����ӔC��F�߂�悤�ɂȂ��v�Ƃ���(�T�i�l���P�������ʂQ�S�y�[�W)�B
�@�������C���̔����́C���̎{������˖x�H���̂��߁C���l�̗L���鉷�p����N�Q���ĂȂ����̏�Ԃ���������Ƃ��ɁC���p���҂����ɑ����̏����𐿋���������(�W�Q�r����������)�ł����āA��L�����͖T�_�ł����C����������˖x�H�������̌��͓I��p�ɓ�����Ȃ����Ƃ��炷��ƁC��L�u�s����p�v�Ƃ͈�˖x�H���Ƃ����͓I��p���������̂Ɖ�����C���������āC���������C���̌��͓I��p�ɂ��āC���@�̕s�@�s�אӔC��F�߂����̂Ƃ͂����Ȃ��B
�@�c����Y���m���C���̔����ɂ��āC�u���̕����̏�ł́C�ꌩ�C��̏�����(���p�Ғ��E���͓I��p�ł��邱�Ƃ𗝗R�Ƃ��č��Ƃ̕s�@�s�אӔC��ے肵������)�ƈق�C�ܗ͓I��p�ɕt�Ă����Ƃ̐ӔC���m�肷�邩�̂₤�Ɍ����邯��ǂ��C����͋��炭�����̖{�ӂł͂���܂��B�Ⴕ�����ʂ�ɉ����˂Ȃ�ʂƂ��Ă��C���ҔV�͕s�@�sਂɊ���Q���������߂������łȂ��C�V�����Ŕ��Ⴊ�n�҂̑ԓx�����߂��Ɖ�����̂����c�łȂ����Ƃ͖ܘ_�ł���B�v�Ƃ���Ă���(�c����Y�E�s����̑��Q�����y�ё����⏞�S�P�y�[�W)�B
�@�ȏォ�疾�炩�Ȃ悤�ɁC�u�吳�����珺�a�̏��߁C�R�{�݁C�w�Z���Ɋւ��锅���܂��͔����ӔC����F�߁v�C�u�����͂̍s�g(���͓I��p)�ɂ�鑹�Q�ɂ��Ă��C���@��K�p���đ��Q�����ӔC��F�߂�悤�ɂȂ��v(�T�i�l���P�������ʂQ�R�C�Q�S�y�[�W)�Ƃ̍T�i�l��̎咣�́C�����ł���B
�@
�@e�@�܂��C�T�i�l��́C��R�@����Ɋւ��C�u���a�P�O�N��ɂȂ�ƁC�������̌����͍s�g�ł���o�[�����Ɋւ��锅���ӔC��F�߂锻�����o�Ă���B�v(�T�i�l���P�������ʂQ�S�y�[�W)�ȂǂƎ咣���C���̌��͓I��p�ɂ��Ĕ����ӔC��F�߂����Ⴊ���邩�̂悤�Ȏ咣�����Ă���B
�@�������C�T�i�l��̈��p�����R�@���a�P�P�N�S���P�T������(�@���V����R�X�V�X���P�S�W�W�Q�y�[�W)�́C�����g���̎��������C���g���̑�\�҂ł��鑺�����`��`�p���đg���̎ؓ����Ƃ��đ��l�����������̂����Q�����������Ăł���C�܂��C��R�@���a�P�T�N�Q���Q�V������(���W�P�X���U���S�S�P�y�[�W)�́C�����������̎ؓ����c���o���Ɏؓ�����s���C���l�ɑ��Q�����������Ăł����āC����������@�S�S���ɂ�蔅���ӔC���F�߂�ꂽ���̂ł���B���̂悤�ȋ����̎ؓ���s�ׂ��C���̌��͓I��p�łȂ����Ƃ͖��炩�ł���C�T�i�l�̎咣�͎����ł���B
�@�Ȃ��C���@�S�S�����C���@�l�ɓK�p�ɂȂ邩�Ƃ����_�����ł��邪�C��L��R�@���a�P�T�N�Q���Q�V�������́C�u�E�@���n���@�l�j臃X�����m�i���J�̃j���@�l�j�c�R�K�p�Z���������m�j��T���n�ܘ_�i���g���{���m�@�L�ꍇ�j�V���ސ��K�p�X�w�L�R�g���������m�s�@�s�׃j萃V�J�ԃV�c�@�m����g�X�����i���v�Ƃ��Ă���B
�@
�@f�@����ɁC�T�i�l��́C��R�@���a�P�T�N�P���P�U������(��R�@��������W�P�X���Q�O�y�[�W)�C��R�@���a�P�U�N�Q���Q�V������(��R�@��������W�Q�O���P�P�W�y�[�W)�Ȃǂ����p���C�u���̂悤�ɁC���őؔ[�����Ƃ������͓I��p�ɂ��Ă��C���R�ٔ�������R�@�����ߌ���R�ٔ�������R�@�ƁC���@�l�̑��Q�����ӔC��F�߁C�܂��ے肷��ȂǁC����̎p���́C�u��т��č��̔����ӔC��ے�v���Ă���Ƃ͓��ꌾ���Ȃ��B�v�ȂǂƎ咣����(�T�i�l���P�������ʂQ�T�Ȃ����Q�V�y�[�W)�B
�@�������C��L��R�@���a�P�T�N�P���P�U�������́C�u�������l�v�̔����ӔC�ɂ��āC�u�ؔ[�|���i���g�����n�E�܃m���p�j�V�e�J���E�܍sਃj��T�����m�g���t�w�N�n�e�s�@�sਏ�m�ӔC���ƃ��T�����m�g�X�v�Ƃ��āC�����F�߂����̂ł���C������@�l�̐ӔC�ɂ��Ĕ����������̂ł͂Ȃ��C�܂��C��L��R�@���a�P�U�N�Q���Q�V�������́C�u�}�\���Ɩ��n������铃m�s���m�������܃j��N�ܗ͓I�s���ɂ��e�n���@�^�����@�m�K�胒�K�p�X�x�L�j�A���U���n�������^�U���g�R���i�����ȃe�C�������n�����K���Ɩ��n������铃m�@��g�V�e�E�������s�X���j�c���s�@�j���l�m�ܗ����N�Q�V�V�j���Q���փ��V���^���ꍇ�j���e�C�\�m�E���sਃK�����܃j��N�ܗ͍s�������X�����m�i���g�L�n�C���Ɩ��n������铃g�V�e�n��Q�҃j���V���@�s�@�sਏ�m�ӔC�����t�R�g�i�L���m�g���Z�U���x�J���Y�B�v�Ɣ������āC������@�l�̔����ӔC��ے肵�Ă���C�T�i�l��̑O�L�咣�͎����ł���B
�@
�@(�) �w���ɂ���
�@
�@a�@�T�i�l��́C���Ɩ����ӂ̖@����ᔻ�����n粏@���Y�����́u���{�s���@��v�y�юO��j�����́u���ᖯ���@(���a�P�U�N�x)�v�̔���]�_�̊e�L�q�����p���āC�u�w��C�v�z�ɑ���e�����ł��������������ɁC���Љ�ɂ�����s������(�@�I���`�̎���)���̓I�t�����C���Q�̎Љ�o�ϓI�t�����S�Ȃǂ̎��_�����\�����܂��Ĕ��\���ꂽ���Ƃ��l���ɓ����ƁC��L�̓c����Y�C�n粏@���Y�C�O��j�̊e�w���́C�w�E�̒ʐ��ɂȂ��Ă����Ǝv������v�C�u���������w���̑��݂��݂�C���Ɩ����ӂ̖@���͊m������Ă��Ȃ����Ƃ͖��炩�ł���v�Ǝ咣����(�T�i�l���P�������ʂR�Q�y�[�W)�B
�@
�@b�@�������C���Z���B�g���m�C���X�ؑy�ꔎ�m�y�ѓc����Y���m�Ƃ����䂪���̑�\�I�Ȍ��@�w�҂͑����āC�������@���ł́C���Ƃ̌��͓I��p�ɂ��āC���Ƃ̑��Q�����ӔC���ے肳���Ƃ��Ă���B
�@�T�i�l��́C���Z���B�g���m�̌��������p���Ă��邪�C�T�i�l�炪�����m�̌����Ƃ��Ĉ��p���Ă��镔���́C�u���Ɩ��͌��@�l�̎��Ɓv�̎{�s�Ɋւ��đ��l�ɑ��Q���������ꍇ�ɂ��Ă̂��̂ł���C�����ɂ����āC�����m�́C���̓������̍�p�Ɋւ��āC�u���Ƃ͈�ʂɉ����ē�����铂ł���C�����ē����܂̍�p�͎��l�̍sਂƂ�'�������قɂ����@�̋K��̓K�p������̂ł͂Ȃ�����C�����\�̍�p�ɕt���ẮC��߂���Ɉ˂��@�ɑ��l�̞ܗ���N�Q���邱�Ƃ��L�Ă��C����͖��@�̈Ӌ`�ɉ����Ă̕s�@�sਂɊY�c������̂ł͂Ȃ��C���Ƃ͂���ɕt�����Q�����̐ӂɔC������̂ł͂Ȃ��B�`�ɍs���sਂ�ٔ������̂₤�Ȍ��@�I�sਂ�����͂��ȂĐl�����S���������ł͂Ȃ��C������̍s���ɕt���Ă��C���ꂪ�����܂Ɋ�Â������܂̍�p�ł������C���Ƃ��Ċ������l�Ƃ��Ĕ����ӔC�ӂ��Ƃ͗L�Ă��C���Ǝ��g�͖��@�̓K�p������̂ł͂Ȃ��C笂Ě��Ƃɛ����đ��Q�����𐿋������ׂ����̂ł͂Ȃ��B�v(���Z���B�g�E���{�s���@�㊪(�I���f�}���h��)�R�T�O�y�[�W)�Ƃ���Ă���̂ł���B
�@�܂��C���X�ؑy�ꔎ�m���C�u�����m�s�׃J���@�m�K�p����N�w�L���ƃm�s���g�V�eਃT���^���ꍇ�j�n�C���ƃg��O�҃g�m萌W�n���@萌W�i���B�̃j�E�m�ꍇ�j�����J��O�҃j���Q�����w�^���g�L�j���e�������ƃg��O�҃g�m萌W�n���@萌W�i���B�n�e���m�ꍇ�j���P�����ƃm�����`���m���n�S�N���@��m�@���j�˃��B���@�m�K��j�˃��R�g�����X�B�����E�m�ꍇ�j���P���������m�l�m�����m���J���@��m�@���j�˃��g���v���j�V�e�C���j���@��m�����`���^�����m�i���B�E�m�ꍇ�j���P�����ƃm�����`���j�A�e�n��ʓI�j�V���F���^���K��i�N�C������@�i�N�V�e�c�R�j�V���F�������������m�j��X�B�̃j�����g�V�e���ƃm�����`���i�V�g�]�E�m�O�i�V�B�v(���X�ؑy��E���{�s���@�_���_�W�P�O�C�W�P�P�y�[�W)�Ƃ���Ă���B
�@����ɁC�c����Y�������C�T�i�l��̈��p���闧�@�_�Ƃ��Ă̌����͂Ƃ������C���̖@�I�ɂ́C�u���Қ��Ƃ̕s�@�sਐӔC�̖�肪�^�嗤�������ɑ��̖@�n���ɛ����鏔���ɉ��ē��ɖ��Ƃ����鏊�Ȃ́C��ɂ��q�ׂ��₤�ɁC���ꓙ�̏����ɉ��ẮC���ܗ͂�������隠�ƍ�p�ɕt�ẮC�����Ƃ��Ĉ�ʎ��@�K��̓K�p���ے肹���C���Ƃ̕s�@�sਐӔC�ɕt�Ă��C�������Ǝ�ܗ��_�̉e���̉��ɁC���ƌ��܂�ᢓ��ɛ����Ă͉����̐ӔC�ӂׂ��łȂ��ƍl�ւ�ꂽ���ƂɊ�B���̌��͓I��p�ɕt�Ă̚��Ɩ��ӔC�̌����͒\�Ȃ鐭���I�咣�Ƃ��ĂłȂ��C����@��̌����Ƃ��ď��F����ꂽ�B�v�C�u�ܗ͓I��p�Ƃ͚��Ƃ��l�ɛ����Ė��߂����n�����������p�ł���C�����Ƃ��Ď��@�����̓K�p��r�˂���{�ғI�Ȍ��@��W�ƔF�ނׂ����̂ł���B���̌��͓I��p�ɂ���Ĉ�@�ɑ��l�̞ܗ���N�Q���邱�Ƃ������Ƃ��Ă�����ʂ̋K��̂Ȃ�����ꚠ�ƂƂ��Ă͈�X�ӔC���͂�ׂ��łȂ��Ɖ�����O�͂Ȃ��B���̌��x�ɉ��Ě��Ƃ̓���̒n�ʂ����F������B�v(�c���E�O�f�s����̑��Q�����y�ё����⏞�R�O�Ȃ����R�Q�y�[�W)�Ƃ��C�܂��C�u�]���́C�x�@���E�������E�i�@���E���������̑������͂̍s�g�Ƃ��āC�E�E�E�����͌����c�̂̔����ӔC�Ɋւ����ʓI�ȍ����K��͂Ȃ��C�������C�����͂̍s�g�����p�́C�Γ��ҊԂ̗��Q�����̌��n�����߂�ꂽ���@�̕s�@�s�ׂɊւ���K��̐e���܂Ȃ�����̗̈�ł���ƍl����ꂽ����ł���B�����C���������ł��������͂̍s�g�����p(���͓I��p���͍s���s��)�ł��邩�ɂ��ẮC�w����٘_������C����̕ϑJ���������B�������C�����͂̍s�g�����p�Ɋ�Â����Q�ɂ��āC�����͌����c�̂̔����ӔC��ے肷��Ƃ����_�ɂ��ẮC��т��ĕς�Ƃ��낪�Ȃ������B�v(�u�V�ōs���@�㊪�S�����Łv�Q�O�S�y�[�W)�Ƃ��āC���m�Ƃ̌��͓I�s�ׂɊւ��Ď��@�ł��閯�@�̓K�p���Ȃ��Ƃ��Ă���̂ł���B
�@
�@C�@�O�L�̂Ƃ���C�T�i�l��́C�n粏@���Y�����y�юO��j�����̒���̊e�L�q�����p����(�T�i�l���P�����ʂQ�X�Ȃ����R�P�y�[�W)�C�u���������w���̑��݂��݂�C���Ɩ����ӂ̖@���͊m������Ă��Ȃ����Ƃ͖��炩�ł���v�Ǝ咣����(���������ʂR�Q�y�[�W)�B
�@�������C�ō��ُ��a�Q�T�N�����́C�㍐���R���L�ڂ́u�]�O�̔���w�����{���̔@���ꍇ�ɏ㍐�l�ɐ������Ȃ��Ƃ�����̂����������͎����ł��邪�����Ȃ������������Ƃ���w���������ʐ��K�炸�����^�Ȃ炸�B�v�Ƃ���㍐�l�̎咣�ɑ��C�u���Ɣ����{�s�ȑO�ɂ����ẮC��ʓI�ɔ����ӔC��F�߂�@�ߏ�̍����̂Ȃ��������Ƃ͑O�q�̂Ƃ���ł����āC��R�@���������̈�@�Ȍ����͂̍s�g�Ɋւ��āC��ɔ����ӔC�̂Ȃ����Ƃ����ė����̂ł���B�v�Ƃ�����ŁC�u��������ɘ_�|�̂悤�Ȋw���������Ƃ��Ă��C�����ɂ͂��̂悤�Ȋw���͍s���Ȃ����̂ł���B�v�Ƃ̔F���������Ă���B
�@
�@d�@���������āC�T�i�l���.�咣�͎����ł���B
�@
�@(�) ���@�҈ӎv�ɂ���
�@
�@a�@�T�i�l��́C�s���ٔ��@�P�U���̋K��͒P�ɁC�s���ٔ����ł͖�����̖��͈���Ȃ��Ƃ������Ƃ��߂��ɂ������C���@�I������ے肵���킯�ł͂Ȃ�����C�����́C�u���Ɩ����ӂ̖@���Ƃ͑S�����̊W���Ȃ��C���̑��݂������āC���Ɩ����ӂ̖@���̘_���Ƃ��邱�Ƃ͂��������ł��Ȃ��B�v�Ǝ咣����(�T�i�l���P�������ʂR�S�C�R�T�y�[�W)�B
�@�������C�O�L�̂Ƃ���C�s���ٔ��@�y�эٔ����\���@�͍��Ɩ����ӂ̖@����O��Ƃ��Đ��肳�ꂽ�@���ł���C�܂��C�����@�ɂ����āC���Ɣ����ӔC�Ɋւ���K����폜�����̂́C���Ɩ����ӂ̖@�����̗p�������߂ł��邱�Ƃ͖��炩�ł���B
�O�L�̂Ƃ���C���b�Z���C���̕s�@�s�אӔC��ے肵�C�i�@�ٔ����݂̂Ȃ炸�C�s���ٔ����ɂ����Ă��C���ƐӔC��₢���Ȃ��Ƃ��Ă����̂ł���(�F�ꍎ��E���ƐӔC�@�̕��͂S�O�X�y�[�W�C�S�P�X�C�S�Q�O�y�[�W�C����Q�W���C�S�V�S�Ȃ����S�V�V�y�[�W�E�u���b�Z�����m���@�㑹�Q�����`���j萃X���ӌ��v)�B
�@b�@�܂��C�T�i�l��́C�u�����@�ƌ����@�͑S���ʂł���C�����@���莞�̈��B�́u���@�ҁv�̈ӎv�͊ߖ��@�Ɏp����Ȃ��v(�T�i�l���P�������ʂR�Q�C�R�R�y�[�W)�ȂǂƎ咣����B
�@�������C�@�T������ψ���̎��^���ق̓��e������ƁC���s���@�V�P�T��(���ĂV�Q�R��)�̖@�T������ɂ�����ʒu�Â��́C�T�i�l��̎咣����悤�Ȃ��̂ł͂Ȃ������ƍl������B
�@
�@(a) �@�T������ɂ�����C��ϔ�����
�u�����m�K�p�j�t�e�Țd�j�f�q�^�C�m�f�A���}�X�K���g�p�l�g�g�p�҃j�ナ�e�ēX���l�g�m��W�m�K���g�]�t�҃n���{�g���{�m�g�E���m���������m�g�p�l�j���������K�c���g�]�t��l�w�f�A���}�X�J�h�E�J�g�]�t�R�g���m�J���e�u�L�^�C�ܘ_���@�g�]�t�҃n�[�Ȑl���݃m��W�o�J���f���{�g�[�Ȑl�g�m��W�j�t�e�n�ʃj�K��X���g�]�t�R�g�j�S�N�꓁�_�Ѓj���w�����m�f�A���}�X���o�^�m�i�C�R�g�f�A���}�X�K���n������f���{�g�[�Ȑl�g�m�ԃf�����{���@�l�g�����o������@�m�K�����K�p�T�����g�]�t�c�_���o�҃��E�g�v�t��V���l�i�R�g�����q�}�X�g���K���W�K�ʃV�e���{�K��Ȑl�j���V�e���g�p�l�m�s�@�i���sਃj�˃e���Q�����w�^�g�L�n���{�K��Q�҃j���V�e�ӔC�����t���ۃ��g�]�t�R�g�K�K�Y���j�i���g�v�t�v(���p�Җ�F���̏̓K�p�ɂ��āC�ȒP�Ɏf�������̂ł���܂����C���̎g�p�l�Ǝg�p�҂ɑ��Ċē���l�Ƃ̊W�̋K���Ƃ����̂́C���{�Ɛ��Ȃ̎g���������̑��̎g�p�l�ɂ����̌�����������Ƃ������l���ł��邩�ǂ����Ƃ������Ƃ��m���߂Ă��������B������@���l���݂̊W�������K�肵�C���{�ƈ�l�Ƃ̊W�ɂ��Ă͕ʂɋK�肷��Ƃ����悤�ɑS���꓁���f�Ɍ�������̂ł���^���̂Ȃ����Ƃł���܂����C���邢�͉��ߎ���ŁC���{�ƈ�l�Ƃ̊Ԃł��C���{��@�l�Ƃ݂��͂薯�@�̋K����K�p�����Ƃ����c�_���ł���悤�Ɏv���B�������̂悤�Ȃ��Ƃ������܂��ƁC���̋K�����ʂ����Đ��{����l�ɑ��āC�ӔC�����ۂ��Ƃ������Ƃ��K�����ɂȂ�Ǝv���B)(����R�S���R�S�Q�y�[�W��i�C���i)�Ƃ̎���ɑ��C��ϒd�́C
�u�{���j�t�e���j�n���{�m�����K���E�����s�t�j�ۃV�e��O�҃j���w�^���Q�����j�V�K�c�����ۃ��g�]�t�R�g�K���m�䎿��f�S�U�C�}�X�\���j���V�}�V�e�n��m�����K�A���}�Z�l�o�Ń������{�m���ƃg嫃����@�I��W�j�t�L�}�V�e�n�{�ăn�c���i�P���o�i���}�Z�k�J�����j���ʖ@�K�i�C�ꍇ�j���e�n�{�ăn�c���g�䓚�w�V�i�P���o�i���}�Z�k�K���V�{�ăK�c���K�ǃC�J�����C�J�n���m���f�A���}�X�K���ă��^�e�}�X�g�L�j�����{�m�����K���E�����s�j�t�e�ߎ��K�A�c�^�g�L�j�n���Ӄj�C�Y�����ۃ��g�]�t�Ӟ����u�J�E�J�g�v�q�}�V�^�K���V�V�����@�j�u�L�}�X�m�n�s�K�c�m�ꏊ�f�A���g�l�w�}�X�E�E(����)�E�E���v�㐥�n�h�E�������m�E����m�R�g�f�A���J���ߎ��K�A�c�e���\���n�������T�Z�k���K�X�C�g�]�t�R�g�n�����n��O�f�A�c�e��c�m���ʖ@���ȃe�胀�x�L�����f�A����ʃj�|���R�g�f�i�C�ʃV�e�����n���@�j����W�m�A���R�g�f�A���}�X�J���v�̃j��V�z�m�@�L�R�g�K�A���}�X���o�������n���ʖ@�m���j�K��j�i�����K�X�C���E���j�t�e�ߎ��K�A���g�]�t�g�L�j���e�n�V���p�����l�K���i�E�g�]�t�m�K�����f�A���g�]�t�R�g�n���J�k�R�g�f�A���E�V���胁�e�u�N�K�X�C�g�v�t�����@�j�A���{�m�����K���E�������s�X���j���V�e���w�^���Q�j�t�e�n�ߎ��A���g嫃����Ӄj�C�[�Y�g�]�t�R�g�������L���V�}�V�e�n�h�E�V�e���ݔʃm�R�g�j�c���}�C�������m��L�i�����j�t�e�n�Ń����߃������i�C�g�]�t�R�g���A���}�Z�E����Ȑl��Ȑl�j�t�e���߃������i�C�g�]�t�ꍇ���A���}�Z�E�����n���x�f���v��ꎄ�l�j���f���|�P���m�n�ǃC�R�g�f�n�i�C�K�߃������Y�����R�g�f�A���}�X�J�������E�����P���j�n�����׃J�C�R�g���v���}�Z�E�\���f�T�E�]�t�R�g�n���ʖ@�j�������K�X�C�g�]�t�l�w�f�A���}�X�\���K�i�P���o�{���m�K�肪�c���g�]�t�\���n���z���l�X�x�L�R�g�f�A���v(�����R�S�R�y�[�W��i�C���i)(���p�Җ�F�{���ɂ��āC���ɂ͐��{�̊��������̐E�����s���ɍۂ��đ�O�҂ɉ��������Q�����ɂ��̋K�肪�����邩�ۂ��Ƃ������Ƃ����̌䎿��ł������܂��B����ɑ��܂��ẮC���ɖ����K�肪�Ȃ���C���Ƃ�萭�{�̎��ƂƂ����ǂ����@�I�W�ɂ��܂��Ă͖{�Ă͓�����Ȃ���Ȃ�܂���C���ɓ��ʖ@���Ȃ��ꍇ�ɂ����ẮC�{�Ă͓�����Ƃ��������Ȃ���Ȃ�܂��C�������C�{�Ă�������̂��ǂ����������́C��Q�̖��ł���܂����C���̈Ă𗧂Ă܂��Ƃ��ɂ����{�̊��������̐E�����s�ɂ��ĉߎ��������Ƃ��ɂ͂��̐ӂ߂ɔC���邩�ۂ��Ƃ���������u�������Ǝv���܂������C�������C����@�ɒu���܂��͕̂s�K���ȏꏊ�ł���ƍl���܂��B�E�E(����)�E�E���v��C�����̐E����̂��Ƃł��邩��ߎ��������Ă������������Ȃ������悢�Ƃ������Ƃ́C����͂ǂ����|�O�ł����āC���ʖ@�Œ�߂�ׂ������ł���B��ʂɂ�����邱�Ƃł͂Ȃ��C����͌��@�ɂ��W�̂��邱�Ƃł���܂�����C����̂ɂ������̂悤�Ȃ��Ƃ�����C���̎����͓��ʖ@�̏��ɋK�肳�������悢�B���̐E���ɂ��ĉߎ�������Ƃ����Ƃ��́C�����p����l�����Ȃ��Ƃ����̂������ł���Ƃ������Ƃ͓����ʂƂ���ł��낤�B������߂Ă����̂��ǂ��Ǝv���B�܂��C���@�Ɂu�A���C���{�̊��������̐E�������s����ɑ��ĉ��������Q�ɂ��ẮC�ߎ�����Ƃ����ǂ����̐ӂ߂ɔC�����v�Ƃ������Ƃ��C���������������ɂ��Ă������̂ł́C�ǂ����Ă����ׂĂ̎��Ăɂ͓�����Ƃ͎v���Ȃ��B�Ȃ�قǁu���m��L�i�����v�ɂ��Ă͂��Ƃ���ނȂ��Ƃ������Ƃ�����܂��傤�C�܂���l��l�ɂ��Ă���ނȂ��Ƃ����ꍇ������܂��傤�B����͒��x(�̖��)�ŁC���v��ꎄ�l�ɖ��f��������̂͂悢���Ƃł͂Ȃ����A��ނ���邱�Ƃł����炻�̋�ʂ�t����ɂ�笕��ׂ������Ƃ�(�K�肷��)�K�v������ł��傤�B����ŁC�����������Ƃ͓��ʖ@�ɏ�������悢�Ƃ����l���ł���܂��B���ꂪ�Ȃ���C�{���̋K�肪������Ƃ������Ƃɂ��āC�Ȃ��悭�l����ׂ����Ƃł���B)�Ɠ��ق��Ă���B
�@���̓��ق́C�v����ɁC���{�̊��������̐E�����s���ۂɁC��O�҂ɉ��������Q�ɂ��āC���ĂV�Q�R���ɂ���Đ��{�������`�������Ƃ������Ԃɑ��āC���̎��Ƃł����Ă����@�I�W�C���Ȃ킿�C���̎��@��̍s�ׂƂ����S���E�o�X�Ȃǂ̎��Ƃ̌o�c�⊯�������p�i�̍w���ȂǏ��R���鎄�o�ϓI��p�ɂ��ẮC�{���̓K�p���Ȃ���ςȂ�Ȃ����ƂɏƂ炷�ƁC���ɓ��ʖ@���Ȃ��ꍇ�ɂ����ẮC�{����������Ɠ����Ȃ���Ȃ�Ȃ��悤�ł��邪�C���ǁC���̏Ă̍쐬�ߒ��ɂ����āC���{�̊��������̐E�����s�ɂ��ĉߎ��������Ƃ��ɐӔC�����ۂ��Ƃ�����u�����Ƃ��������Ă݂����̂́C.���@�ł�����K�肷��͕̂s�K�����ƍl�����Ƃ������̂ł���B���Ȃ킿�C���v�㊯���̐E����̂��Ƃł���C�ߎ��������Ă����������Ȃ������悢�Ƃ����̂́C���@�ɂ��W���邱�Ƃł���C���ʖ@�ŋK���݂���̂��K���ł��邱�ƁC�܂��C��ʘ_�Ƃ��Ďg�p�l�ɉߎ�������Ƃ��ɂ͂����p����l(�g�p��)����������̂������ł��邩�炱����K�肵�C���@�ɁC�����������Ƃ��āu�A���{�m�����K���E�������s�X���j���V�e���w�^���Q�j�t�e�n�ߎ��A���g嫃����Ӄj�C�[�Y�v�ƋK�肷�邱�Ƃ��C���ׂĂ̎��Ăɓ��Ă͂܂�Ȃ��Ǝv���邱�ƁC���ɐӔC�킹�邩�ۂ��̋�ʂ́C�ʂ̎��Ăɉ����čׂ��ȋK���݂���K�v�����邱�ƂȂǂ���C���̔����ӔC�ɂ��Ă͓��ʖ@�ɏ���̂��悢�ƋN���ψ��͍l�����Ƃ������̂ł���(�Ȃ��C���̂悤�ȓ��ʖ@�����@����Ȃ��ꍇ�́C�{���̓K�p�����邩���������Ƃ��C����ɂ悭�l���Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ƃ���Ă���B)�B
�@���������āC�N���ψ��́C���{�̊��������̐E�����s�ɂ�锅���ӔC�ɂ��āC���̍s�ׂ����@��̍s�ׂł���ꍇ�ɂ́C�{���̓K�p��������̂ƍl���Ă������C����ȊO�̌��@��̍s�ׂł���ꍇ�ɂ́C�{���̓K�p���Ȃ��C���ʖ@�ɏ���Ƃ����l���������Ă������Ƃ����炩�ł���B
�@
�@(b) ���̂��Ƃ́C�@�T������ɂ����鍂�ؖL�O�Ƃ̊Ԃ̎��c���ق��݂Ă����炩�ł���B
�@���ؖL�O�́C
�u��όN�m����������n���}�V�^�K���m�䓚�j�˃��g���{�g�����g�m�ԃm��W���`�����m�ߎ��sਃn���{�K��c�e�����X���J�h�E�J�g�]��胂�{���j�܃��J�m�@�L�䓚�j�i�c�^���E�f�A���}�X�K���n�T�E�n���V������όN�m�䓚�w�f�n���{�K������V���@�f�����g�p�l���g�c�e���ƃf�����c�e�����g�L�n���`�ē҃g�]�t�҃K�����l�m����g�J�����g�J�]�t�҃K���t���m�f�A���E�g���V�e���c�^�m�f�A���}�X�K��V�T�E�f�i�N�V�e���{�m�����g�]�t���m�K�E�����s�j�t�e��O�ґ��`�l���j���V�e���Q�����w�^�ꍇ�j�������j�˃e���{�K�������m�Ӄj�C�Y�����ۃ��g�]�t�z�E�]�t��胒�����f�Ãj�Ƀ��^���m�g�]�t�R�g�f�A���i���o�����m�����V�e�������m�g�n��̎�ӃK��q�}�X�m�f�����i���o��j���n�_�Y�x�L�����A�������X�x�L�R�g���A���E�g�v�t�����o�^�y�n���p�@�m��W�n�����f�n�[���c���Y�g�v�t�l����t���g�䓚�w�j�i�c�e�������g�Ӗ��K��E�m�f�A���E�g�v�t�������n�c�^�����m�E�����s�j�t�e�l���j���Q�����w�^�g�L�j���{�K�����m�Ӄj�C�Y�����ۃ��g�]�t�@����m���胒�Ƀ��^���m�f�A���J�h�E�J�g�]�t�R�g����j��c�f�q�^�C�v(�����R�S�T�y�[�W���i�C�R�S�U�y�[�W��i)(���p�Җ�F��όN�̌�������������܂��܂������C���̂����ɂ��Ɛ��{�Ɗ����Ƃ̊Ԃ̊W���Ȃ킿�����̉ߎ��s�ׂ͐��{�����Ĕ������邩�ǂ����Ƃ��������{���Ɋ܂ނ��̂悤�Ȃ����ɂȂ��悤�ł���܂����C���͂��̂悤�ɂ͉��߂��Ȃ��B��όN�̂����ł́C���{�����疯�@�ŏ����g�p�l���g�Ď��Ƃł�����Ă���Ƃ��́C�ē҂Ƃ����҂��u���l�̎����Ƃ����Ƃ������҂�(�����ӔC��)�������̂ł��낤�Ɖ����Ă����̂ł���܂����C���������łȂ����Đ��{�̊������E�����s�ɂ��đ�O�҂��Ȃ킿�l���ɑ��đ��Q���������ꍇ�ɁC���̌����ɂ���Đ��{�������̐ӂɔC���邩�ۂ��Ƃ����������̏ňÂɌ��߂����̂Ƃ������Ƃł���Ȃ�C���ǂ��̉��߂��Ă�����̂Ƃ͑�ώ�ӂ��Ⴂ�܂��̂ŁC���̖��Ȃ�Α傢�ɘ_���ׂ����Ƃ�����C�������ׂ����Ƃ����낤�Ǝv���B�����o���y�n���p�@�̗�́C�I���˂����̂ł͂Ȃ��Ǝv���B�܂�C�₤�Ă���Ƃ���Ƃ����ɂȂ��Ă���Ƃ���ƈӖ����Ⴄ�̂ł��낤�Ǝv���B���������������̐E�����s�ɂ��Đl���ɑ��Q�����������ɐ��{�������̐ӂ߂����ۂ��Ƃ����@����̑�������߂����̂ł��邩�ǂ����Ƃ������Ƃ��Ɉ�f�������B)�Ƃ̎���ɑ��C�~�����Y�́C
�u��̑���j�i���}�V�^�K���n�����n���e�@�l�m���m�S�U���f���V�^�R�g�g�v�q�}�X�����|�f�c�_�K�o���m�n�@���K�J�g�v�q�}�X�����{�n�@�l�f�A���}�X�J������Ӟ��j�t�e�ߎ��K�A�c�^�g�J�����m�ӔC�K�A���g�J�]�t�R�g�j�n���i�C�J�����K���K�c�ƃ��k�g�v�t���S�U���m�K��K��ʃm�@�T�j���e�����g���W�l�i�K��j�i�c�e���������V����@�l�m�K��n���_���j�ƃ��k�g�]�t�R�g�n���m�����҃`�}�Z�k�R�g�f���j萃V�e�n���ʖ@�K�o���f�A���}�Z�E�s�@�sਃm�����J���l�w�e�\���J���@�l�m���m�S�U���m�K�胒�l�w�e�����o���j���X�����ʃm�K��K�A���o�c���k�R�g�n������V�������ȃe�胁�i�P���o�������@�l�f�A���J���S�U���m�K��K�ƃ��g�]�t�R�g�n���V�e�����J���k�R�g�g�v�t���V�C�d���\���n���ʖ@�j�˃e�Ƀ��R�g�g�M�W�e�����}�X�v(�����R�S�U�y�[�W��i�C���i)(���p�Җ�F��ϑ���ɂȂ�܂������C���͂��̖��͏��߂Ė@�l�Ɋւ���S�U���Ō��������ƂƎv���܂��B�����ŋc�_���o��̂͂��������Ǝv���܂��B�܂��B���{�́C�@�l�ł���܂����炱�̂P�ӏ��ɂ��ĉߎ����������Ƃ������ӔC������Ƃ������l�ɂ͌��Ȃ�����C���̋K���͂��Ă͂܂�Ȃ��Ǝv���B�����C�S�U���̋K�肪��ʂ̖@�T�ɂ����Ă���Ɠ����l�ȋK��ɂȂ��Ă���B�����������Ȃ���C���̖@�l�̋K��́C���_���ɂ��Ă͂܂�Ȃ��Ƃ������Ƃ͎��̌���҂܂ł��Ȃ����ƂŁC���Ɋւ��Ă͓��ʖ@���o��ł���܂��傤�B�s�@�s�ׂ̌�������l���āC���ꂩ��@�l�Ɋւ���S�U���̋K����l���Ă݂�C���Ɋւ�����ʂ̋K�肪����C������Ȃ����Ƃ͕�����B�����A�����������Ē�߂Ȃ���C�����܂��@�l�ł��邱�Ƃ���C�S�U���̋K�肪���Ă͂܂�Ƃ������ƌ����Ė�������ʂ��ƂƎv���B�������C�����ꂻ��͓��ʖ@�ɂ���Č��܂邱�ƂƐM���Ă���܂��B)�Ɠ��ق��Ă���B
�@���̓��ق̑O��ƂȂ��Ă���@�l�Ɋւ��鑐�ĂS�U���P���́C
�u�@�l�n���������m�㗝�l�K�E�����s�t�j�ۃV�e���l�j���w�^�����Q�������X���Ӄj�C�X�v�Ƃ��Ė@�l�̗������̕s�@�s�אӔC���߂��ł���B�����ɂ��ẮC�����Q�V�N�P���Q�U���̖��@����ɂ����ĐR�c����C���̍ۂɂ��C���������́u�@�l�v�ɓ�����C�����������l�ɑ��Q��^�����ꍇ�������ӔC�����ۂ����c�_���ꂽ���C��ϒd�́C�u���ɃK�@�l�g�i�c�e�����Ƀm�ӔC�����J�n�K�Y�ʃj�K��V�i�P���o�i���k�g�]�t�R�g�j�i���E�g�v�q�}�X�C�v�̃j�{���m���j�n�����c�e�����}�Z�k�v(����R�T���R�O�U�y�[�W��i)�C�u���@�l�m�ܗ��`���g�]�t���m�n�{�@�m�K��j�������k�σ��f�A���}�X�J�����Ɏs�����W�m�@�L���m�����m�ӔC�n�{���j�胁�e�����k�σ����f�A���}�X�v(�����R�O�V�y�[�W��i)�Ƃ��āC���ɂ́C���ĂS�U���̓K�p�͂Ȃ��C�����ӔC��Ȃ��|�������C�����O��Ƃ��Č��Ăǂ��薯�@����ɂ����ĉ����ꂽ�B
�@���������āC�~����Y���C���ĂS�U�������̐ӔC�ɂ��ċK�肵�Ă��Ȃ��̂Ɠ��l�ɁC���ĂV�Q�R�����C�����̐E�����s�ɂ��đ�O�҂ɑ��Q�킹���Ƃ��ɐ��{�ɔ����ӔC�킹�邱�Ƃ��K�肵�����̂ł͂Ȃ��|���ق��Ă���C���{�̊����̐E�����s�ɂ��āC�����̓K�p�͂Ȃ��ƍl���Ă��邱�Ƃ����炩�ł���B
�@
�@(C) �����āC���ǁC�@�T������ɂ����錋�_�Ƃ��ẮC���ؖL�O���C�u���m���q�}�V�^�m�����g�]�t�@�l�K���@��m���ƃm萌W�j�t�e�����K�c���J�c���k�J�g�]�t�R�g�j�t�e���_�c���g�]�t�R�g�j�n���y�m�^�q�K�i�C�����m�捏�\�V�^�����K�E�����s�t�j�ۃV�e���@��m萌W�f�i�N�V�e���܃m��p�g���q�}�X�J�l���ٔ����K�ٔ����X���x�@���K�l���߃w���g�]�t���E�i�R�g���V�j�c���g�]�t���E�i�R�g�j���G�e�n�r�_������V�T�E�]�t���K�V�j�ăc�e�����i���o����_�g�]�t�m�f�A���}�V�e�ܘ_�ٔ����g�x�@���v���f�i�C�n�����m�@�L������l���j���V�e���Q�����w�^�g�]�t���E�i�ꍇ�������m�K�p�K�A���J�g�]�t�g�\�����m�ꍇ�j�n�K�p�X���R�g�K�o�҃k���`���ʖ@���ȃe�胁�����@�j�n�V�����e�����k�g�]�t�R�g�m�N���҃m���������c�e�u�L�^�C�v(����R�S���R�S�V�y�[�W���i)(���p�Җ�F���������܂����̂��C���Ƃ����@�l�����@��̎��Ƃ̊W�ɂ��Ė{���������邩������Ȃ����ƌ������Ƃɂ��ẮC���_������Ƃ������Ƃɂ͈�_�̋^�����Ȃ��C�����C�����捏�\���܂����������E�����s���ɍۂ��āC���@��̊W�łȂ����Č����̍�p�Ƃ����܂����ٔ������ٔ�������C�x�@�����l��߂܂���Ƃ����悤�Ȃ��Ƃ��{���ɓ�����Ƃ����悤�Ȃ��Ƃɕ������ẮC�͂Ȃ͂�����B��������������肪�{���Ɋ܂܂�Ă���Ȃ�Α��肾�Ƃ����̂ł���܂��āC�������ٔ����ƌx�@������ł͂Ȃ��C�n�����̂悤�Ȏ҂���͂�l���ɑ��đ��Q���������Ƃ����悤�ȏꍇ���C�{���̓K�p�����邩�Ƃ����ƁC�����̏ꍇ�ɂ͓K�p���邱�Ƃ��ł��Ȃ��C���Ȃ킿�C���ʖ@�������Ē�߂�C���@�ł͂����̏ꍇ���K�肵�Ă��Ȃ��Ƃ������Ƃ��N���҂ɂ�����������Ă��������B)�Ɗm�F�����߂��̂ɑ��āC
��ϒd�́C
�u�z�E�]�t�m�f�A���}�X�����m�E�����s�m�ꍇ�j�����K�c���K�X�C�g��X�n�Ƀ��e�����k�m�f��X�K�����V�e�����g���g�V�e�n���@�j���C�e���������A���}�X�J�����������J�E�J�g�v�t�e���k�V�e���}�V�^�K�C�d�����ʖ@�K�o�҃��_���E�g�v�q�}�V�^�J���~���^�m�f�A���}�X���ʖ@�K�o�҃k�g�]�t�R�g�����z�V�e���f�˃L�ʃX�g�]�t�m�f�n�i�C��V���ʖ@�K�o�҃i�J�c�^�������K�h�E���׃T�����J�g�]�t�R�g����n���}�X�J�����ʖ@�K�i�C�ȏ�n��w�o�R�̓K��Ȑl�m���̑D�g�Փ˃V�e���D�������^�g�J�]�t�T�E�]�t�l�i�ꍇ�j�������������g�]�t�j�n�����K�c���n�V�i�C�J�g�]�t�䑊�k���V�^�m�f���ʖ@���색�i�C�f�����f���ʃV�e�d���E�g�]�t��P�m���S�n��X�O�l���i�J�c�^�m�f�A�����V��V���ʖ@�K�i�J�c�^���o�����K�c���W�����E�g�]�t�l�w�n�O�l�����c�e�����v(�����R�S�W�y�[�W��i)(���p�Җ�F�����������Ƃł���܂��B�����̐E�����s�̏ꍇ�ɁC�{�����K�p�����̂��悢�Ɖ�X�͌��߂Ă��Ȃ��B��X���������Ă݂�ƁC���Ƃ��Ė��@�ɏ����Ă��鍑������܂�����C��������������Ǝv���đ��k���Ă݂܂������C���ʖ@���ł��邾�낤�Ǝv���܂�������~�߂��̂ł���܂��B���ʖ@���o���ʂƂ������Ƃ�\�z���Ă���œ˂��ʂ��Ƃ����̂ł͂Ȃ��B�����C���ʖ@���o���Ȃ�������C�{�����ǂ����߂���邩�Ƃ������Ƃ����܂�����C���ʖ@���Ȃ��ȏ�C�Ⴆ�ΌR�͂���l�̏����D�ƏՓ˂��Ă��̑D�߂��Ƃ������悤�ȏꍇ�ɁC���������߂�Ƃ����ɂ͖{����������͂��Ȃ����Ƃ��������k�������̂ŁC���ʖ@�����Ȃ��ł���ʼn����ʂ��Ă��܂��Ƃ��������̌��S�͉�X�R�l�Ƃ��Ȃ������̂ł���B�������������ʖ@���Ȃ������Ȃ�C�{���������邾�낤�Ƃ����l���͂R�l�Ƃ������Ă���B)�Ɠ��ق��C����ɑ��C���ؖL�O�́C�u�����m�䓚�f�\�N���J���}�V�^�v(�����R�S�W�y�[�W��i)�Ɠ����Ă���
�@���̍��ؖL�O�ƕ�ϒd�Ƃ̎��^���ق̓��e������ƁC���́C��ςɑ��C�������́u���܃m��p�v�ɂ��E���s�ׂɂ��āC���@�V�P�T����K�p���č��ɔ����ӔC�킹�邱�Ƃ͗l�X�ȕ��Q�������C����ł��邩��C���@�V�P�T���̓K�p�ΏۂƂ͂Ȃ�Ȃ��ƁC�͂��蓚�ق���悤�ɔ����̂ɑ��C��ς́C���@�V�P�T���̓K�p�Ώۂł���Ƃ͌��߂Ă��Ȃ��Ƃ��C���ʖ@�ɂ���Ē�߂鎖��
�ł���C���ʖ@�𐧒肵�Ȃ��ꍇ�ɁC���@�V�P�T���̓K�p�ʼn����ʂ��Ƃ͍l���Ă��Ȃ��Ɠ����C����ɑ��C�����C���̓��قł悭�������Ɠ����āC���̓_�Ɋւ���@�T������̋c�_���I���Ă���̂ł���B
�@���������āC���s���@�V�P�T��(���ĂV�Q�R��)�̖@�T������ɂ�����R�c�̌��ʂ́C���̌��͓I��p���L���C���{�̊������E�����s���ɂ��āC���̐E�����u���@��̊W�v�łȂ��u�����̍�p�v�ł���ꍇ�ɂ́C���s���@�V�P�T��(���ĂV�Q�R��)�̓K�p���Ȃ����Ƃ��m�F����Ă���̂ł���B���̂��Ƃ��炷��C�����@���蓖���̈��B�́u���@�ҁv�ӎv�������@�Ɏp����Ă��Ȃ��Ƃ���T�i�l��̎咣�������ł��邱�Ƃ͖��炩�ł���B
�@
�@c�@�����@�̋N���҂̈�l�ł���~�����Y�́C�����S�P�N�Q�����s�̖@�{�u�ё�P�O����Q���ɂ����āC�����̐E����̕s�@�s�ׂɊ�Â�������̔����ӔC�ɂ��C�u���j�t�e�����m�K��K�i�C�J���g�]�b�e�C���V�P�T���K�p�X���R�g�n�o�҃k�C�J�����j�n�s�@�sਃm�ӔC�i�V�g�_���Z�l�o�i���k�C�A���@�_�g�V�e�n�\�n���j�ӔC�������X���K���C�g�v�t�m�f�A���v(����R�U���S�T�y�[�W)�Ƃ��Ă���C�����̐E����̕s�@�s�ׂɊւ��ẮC���@�V�P�T���̓K�p���Ȃ����Ƃ����Ă���C���@�_�Ƃ��č��ɔ����ӔC�킹��ׂ��ƍl���Ă���|�𖾂炩�ɂ��Ă���B
�@�܂��C�N���҂̈�l�ł���x�䐭�͂��C�吳���N�ɓ����鍑��w�Ŗ��@�̍u�`�����Ă��邪�C���̍u�`�^�̖��@�V�P�T���̉���ŁC���̂悤�ɏq�ׂĂ���B
�@�u���m��(���p�Ғ��E���@�V�P�T��)�j�n�������ƃm�^���j���l���g�p�X���g�A���Cৃj���e�����m���Q�s�׃j���X�����ƃm�ӔC�����m�j�����e�K��V�������m�i�����J�]�n�R�m�ꍇ�j�K�p�X�w�L�K��j�A���X�g�v�t�C���@�n���m���m���胒�s���@�K�j�����l�i���V�J�g�v�n���C�]�n���@���g�V�e�n�J�����@�s�@�s�׃m���j�K��X�w�L�����i���g�l�t�C�s�������m���s�j�ۃV�e���V�^�����Q�i���g�]�t�_�����]�w�n���@���W�i���C�����m���Q�j���X�������`���m���i���̌��������@�m���i���C���V�\���n���^�K��Z���������X�C���s�s���@�n�@���j�i�������J�g�C�E�j�\���n�R�R�j�����X�w�L�����j�A���T�����]�m���X�����j�����n���ʃm�����A����m�ꍇ�����N�O��ʌ����g�V�e�n���ƃj�����m�`���i�V�g�]�t�d�g�j�i�������g�v�t�C�\���n�����m���s�j���V�e�n��j���g�i���R�g�i�������ƃK��ʉc�ƃg�V�e�����w�L���ƃ��i�X�ꍇ�j���������ӔC�i�L�R�g�i�������g�v�t�ٔ��Ⴢ�m�j�A���L�\���n�r�s���i���g�l�t�C���V�J�J�����n�[�N�_�Z�X�v(����R�V���E�x�䔎�m�q�E�܊e�_���P�X�U�C�P�X�V�y�[�W)
�@����ɂ��C�x��́C�����̉��Q�s�ׂɂ��āC���@�V�P�T���͓K�p�����C�s���@�K�Ɉς˂�Ƃ����̂����@��|�ł���C�s���@�̕���ł́C���ʋK�肪���鑼�́C��ʌ����Ƃ��āC���͔����ӔC��Ȃ��Ƃ���Ă���C�����̎��s�ɔ����ӔC�킹�邱�Ƃ͑傢�ɖ�肪���邪�C�����C�c�ƂƂ��Ď��Ƃ��Ȃ��ꍇ�ɂ܂ŁC�����ӂƂ��Ă��܂��͖̂��ł���C�ٔ�������̗l�ɔ������Ă��邪�C����͕s���ł���|�q�ׂĂ���B
�@���������āC�����̖��@�N���ғ�l�̌����ɂ��B����������Ƃ̌��͓I��p�ɂ��āC���@�̓K�p���Ȃ��C���@�_�Ƃ��čs���@�ȂǓ��ʖ@�ɂ���Ē�߂�ׂ��ł��Ƃł��邪�C�s���@�ł͈�ʓI�ɔ����ӔC�킹����ʖ@���߂Ă��Ȃ��Ɛ������Ă��邱�Ƃ͖��炩�ł����āC���Ɩ����ӂ̖@����O��Ƃ��Ă��邱�Ƃ͖��炩�ł���B
�@
�@d�@���̂悤�ȐR�c���o�āC���s���@�V�P�T���͐��肳�ꂽ���C�����̉��߂ɂ��āC�吳�P�O�N�Q���ɑ�P�O�ł����s���ꂽ���R�G�v�́u���{���@(�e�_��)�v�ɂ��C�u�@�l�j�t�e����S�S���m�O��V�P�T���m�K�p�A���n���j�q�x�^���K�@�V�B��V��O�҃j���Q�����w�^���҃K�@�l�m�@�(���������m�㗝�l)�i���g�L�n��S�S�����K�p�X�x�N�C�@��j�A���Y�V�e�d�j��p��W�j�݃��g�L�n��V�P�T�����K�p�X�x�L�i���B�v(�����X�P�S�y�[�W�E����R�W�E����)�C�u�����K���E����ਃV�^���sਃn���`���ƃm�sਃj�O�i���Y�B�̃j���Q�����m���n�����j�t�e�n���[�Y���ƃm�~�j�t�e�V�����Y�B���V�e���sਃK���@��m�sਃ^���ꍇ�j�n���@�s�@�s�׃m�K�胒�V�j�K�p�X�x�N�C���@��m�sਃ^���ꍇ�j�n�V���K�p�X�x�J���Y�B���V�e����m�ꍇ�j���@�㔅���ӔC���F�����Kਃ��j�n���ʃm�K�胒�v�X�B�v(�����W�T�Q�y�[�W)�Ƃ���Ă���B
�@
�@e�@���������āC�T�i�l��̎咣�������ł��邱�Ƃ͖��炩�ł���B
�@
�@(2) �K�@�Ȍ����͍s�g�����Ɋ�Â��Ȃ����Ƃ������_�ɂ���
�@
�@�A�@�T�i�l��̏�L�P(2)�̎咣�́C�v����ɁC���Ɩ����ӂ̖@���͌�����ی삷����̂ł��邩��C���̓K�p�͈͂�ی삷�ׂ��������ۂ��ɂ���ĉ悵�C�T�i�l��ɑ�����Q�s�ׂ́C�@�I�������Ȃ�����ی삷�ׂ����Ƃ̌��͓I��p�Ƃ͂������C���Ɩ����ӂ̖@�����K�p����Ȃ��Ǝ咣������̂ƍl������B
�@
�@�C�@�������C�T�i�l��̎咣�́C���Ɩ����ӂ̖@����S���������Ă��Ȃ����̂̎咣�ƌ��킴��Ȃ��B
�@���Ȃ킿�C��T�i�l���]�O����J��Ԃ��q�ׂĂ���悤�ɁC�u���Ɩ����ӂ̖@���v�Ƃ́C���������E�����s���ɂ��Ă��ꂽ�s�ׂ����Ƃ̌��͓I��p�ɊY���������C���@�̕s�@�s�ׂ̋K��̓K�p���Ȃ��C���ɔ����ӔC��F�߂�K�肪�Ȃ��������ƂɊ�Â����̖@�̖@���ł���B���������āC���Ɩ����ӂ̖@'���̓��e�́C�@���@�̕s�@�s�ׂ̋K��̓K�p���Ȃ����ƂƁC�A���̑������ӔC��F�߂�K�肪�Ȃ����Ƃ��܂ނ��̂ł���B
�@���̂悤�ɁC���Ɩ����ӂ̖@���́C���̔����ӔC��F�߂��K�肪���݂��Ȃ����̓������`����Ȃ��Ƃ������̂ł���C���Ƃ���Ă��錠�͓I��p�ɖ@�I���������邩�ۂ��͑S�����ƂȂ�Ȃ��B
�@���������C�s�@�s��(��@�s��)�́C�@�ɂ�苖����Ȃ��s�ׂł���C�@�ɂ���ĕی삷�ׂ��s�ׂƂ͂������C�ʏ�́C�����y�ьY���ӔC����������̂ł���B�������C�������@���ł́C���̈�@�s�ׂ����Ƃ̌��͓I��p�ł������C���@�̕s�@�s�K��̓K�p��r�����C���ɔ����ӔC��F�߂�K�肪�Ȃ��������Ƃ��獑�̔����ӔC���ے肳�ꂽ���̂ł���B�@
�@���������āC�T�i�l�炪�C�ی삷�ׂ����͓I��p�łȂ������Ƃ��āC���Ɩ����ӂ̖@����K�p�����C���@��K�p���ׂ��ł���|�咣����̂́C��L�̍��Ɩ����ӂ̖@����S���������Ă��Ȃ��؍��ł���B
�@���ɁC�������������s�ׂ��C�@�I�ɕی삳���ׂ��s�ׂł���C����͓K�@�s�ׂł����āC���Q����(���Ɣ���)�̖��͐������C�����⏞�̖�肪������ɂ����Ȃ���(�F�ꍎ��E���ƕ⏞�@�R�y�[�W�Q��)�C�s�@�s�ׂ�����ی삷��K�v���Ȃ��Ƃ����̂ł���C���̌��͓I��p�ɂ��ꍇ�́C���@�̓K�p���r������C���͑��Q�����`����Ȃ��̂ł���B�@
�@���ǁC���������E���Ɋւ��čs�����s�@�s�ׂ����Ɩ����ӂ̖@���̓K�p�ΏۂƂ����邩�ۂ��́C���̍s�ׂ̐��������͓I��p�ł��邩�ۂ��Ō�������̂ł����āC���̍s�ׂɖ@�I���������邩�ۂ��Ō���������̂ł͂Ȃ��̂ł���B
�@���̓_�ɂ��ẮC���ɍō��ٔ������a�Q�T�N�S���P�P���������������Ă���Ƃ���ł���B���Ȃ킿�C�������́C�u�_�|�͌������͖{�i�������͂̍s�g�ɂ�鑹�Q�̔��������߂���̂ł���Ƃ��Ȃ���C���̌��͂��@���Ȃ���@��̖@�K���͏����ɂ���Ċ�b�Â����Ă��邩�𖾂��ɂ��Ă��Ȃ��Ǝ咣����̂ł���B�E�E�E�����āC�㍐�l�͌��R�����٘_�ɂ����Ă����ΉE�j��s�ׂ���@�Ȍ����͂̍s�g�ł��邱�Ƃ��咣���Ă���̂ł����āC���R�����咣�Ɋ�{�i�������͂̍s�g�ɂ�鑹�Q�̔��������߂���̂ł���Ƃ����͓̂��R�ł���B(�����E�j��s�ׂ������͂̍s�g�ł͂Ȃ����_�x�@���̎��l�Ƃ��Ă̍s�ׂł���Ȃ����ɂ��č��ɑ��Q�����𐿋������Ȃ����Ƃ͂����܂ł��Ȃ����ꂾ���Ŗ{�i�����͗��R�Ȃ����̂ƂȂ�ł��炤)�����āC���R�����̔����������R�ɂ���āC�{�i���������p���邽�߂ɂ́C���_�̂悤�ɔ@���Ȃ�@�ߖ��͏����ɍ�����������������K�v���Ȃ��̂ŁC�������ɂ͉�����@�͂Ȃ��B�_�|�͖��������͖{�������͂̍s�g����@�ł��邩�ۂ������Ă��Ȃ��Ƃ����̂ł��邪�C���Ƃ��{���Ɖ��̔j��@�ł����Ă��C���������ӔC���ׂ����̂łȂ����Ƃ͌�q�̂Ƃ���ł��邩��C���ɑ��đ��Q�̔��������߂�{�i�ɂ����ẮC���̕s�@�ł��邩�Ȃ���������K�v�͂Ȃ��̂ł����āC�_�|�͗��R�͂Ȃ��B�v(�������p��)�Ɣ������Ă���B
�@
�@�E�@�ȏ�ɏq�ׂ��悤�ɁC�T�i�l��̎咣�́C���Ɩ����ӂ̖@���y�эō��ُ��a�Q�T�N�����𐳉����Ă��炸�C�����ł���B
�@�����{���ɂ��Ă݂�A�T�i�l��̎咣���鋌���{�R�ɂ����Q�s�ׂ́C�R�̐푈���s�̉ߒ��ōs��ꂽ���̂Ƃ݂�ق��Ȃ��C���̍s�ׂ̐�������C���͓I��p�ł���Ƃ����������Ɍ��͂Ȃ��C���@�̕s�@�s�K��̓K�p���Ȃ�����C���Q�������������������鍪���������B
�@���������āC�T�i�l��̎咣�͎����ł���B
�@
�@(3) ���Ɩ����ӂ̖@���̐l�I�E�ꏊ�I���E�������_�ɂ���
�@
�@�A�@�T�i�l��́C���{���̊NJ��ɕ����Ȃ��O���l�ɑ��č��Ɩ����ӂ͓K�p����Ȃ��Ǝ咣����(�T�i�l���P�������ʂS�X�y�[�W)�B
�@�������C�O���ɂ�����R�l�̍s�ׂ��C���Ǝ匠�Ɋ�Â��s�ׂł��邱�Ƃɕς��͂Ȃ��C�O���ɂ�����O���l�ɑ���s�ׂł��邩��Ƃ����āC���@���R�l�̍s�ׂ����l�̍s�ׂƓ��l�Ɏ�舵�����Ƃ�\�肵�Ă�����̂Ƃ͍l����B���s�̍����@�P���P���́u�����͂̍s�g�v�ɊY�����邽�߂ɂ��̂悤�ȗv����K�v�Ƃ���Ƃ̐��͌�����Ȃ����Ƃ��T�i�l��̎咣�̕s�������������̂ł���B���̌��͓I��p�ɂ��ȏ�C���@�̕s�@�s�K��͓K�p���ꂸ�C���Ɩ����ӂ̖@���ɂ��ׂ��ł���B
�@
�@�C�@�܂��C���ɁC�@��P�P���Q���ɂ����{�@���ݐϓI�ɓK�p�����̂ł���C���{�����ł̎����Ƃ��Ă̂���Βu���������s���C�ꏊ�I�v���͖�������邱�ƂɂȂ�C���Ɩ����ӂ̖@�����l������邱�ƂɂȂ邩��C�H���̓_�ł��T�i�l��̎咣�͖��Ӗ��ł���B
�@���Ȃ킿�C���ɍT�i�l�炪�咣����悤�ɁC�{���ɖ@��P�P���̓K�p���l�����Ƃ��Ă��C�@��P�P���Q���ɂ���āC���{�@���ݐϓK�p����邱�ƂƂȂ�C�@��u�P�P���Q���ɂ��Ȃ����u�s�@�s�גn�@�Ɩ@��n�@�Ƃ̕]���̑Ώۂ��鎖���́C����ɂP�ł���C����́w�O���j���e�����V�^�������x���̂��̂ɂق��Ȃ�Ȃ��B���̎������̂��̂ɁC�s�גn����O���̕s�@�s�ז@�̑���ɁC���{�̕s�@�s�ז@��K�p������C�͂����ĕs�@�s�ׂ̗v�����[�����邩�ۂ������Ȃ̂ł���v�v�C�u�@��P�P���Q���̎�|�ړI�́C�@��R�R���̌������̓����Ƃ���Ă���C���Y�s�҂����̍s�ׂ���{�ōs�����Ƃ�����s�@�s�ׂƂ���Ȃ����̂��C�s�@�s�גn�@�ɂ��Εs�@�s�ׂƂ����Ƃ����Ⴂ�������ɔ�������̂Ƃ��Ĉ�ؗe�F���Ȃ��Ƃ����_�ɂ���Ƃ���Ă���(�ʐ�)�B�v(����Q�S���S�Q�Ȃ����S�S�y�[�W�Q��)�B�����āC�@��P�P���Q���ɂ��C���{���@���ݐϓK�p�����ꍇ�ɂ́C�u�O���j���e�����V�^�������v���C���@�̓K�p������Ƃ���u�������������̂ł���C�{���Ŗ��Ƃ���Ă�����{�R�̊O���ɂ�������͍s�g�̎����́C�u�{���Ŗ��ƂȂ��Ă���̂́C���{���̐ӔC�ł����āC�����Ēu��������̂ł���C�u���{���ɂ����ē��{�̌R�����E�E�v�ƒu��������ׂ��ł���B�v(�����S�T�y�[�W)�Ƃ������ƂɂȂ�B
�@���������āC�@��P�P���Q���ɂ��ꍇ�ɂ́A�ꏊ�I�����͖��Ӗ��ɂȂ�ƍl������̂ł���B
�@
�@�E�@���������C�{���ɂ����Ė��ƂȂ��Ă���̂́C�����C�����Ȃ�҂ɑ��āC���͓I��p���y�ڂ����邩�Ƃ������(�{���ł́C�O���ɂ���O���l�ɑ��C���̓������Ɋ�Â��D�z�I�Ȉӎv�̔����Ƃ��Ă̋����I�E���ߓI��p��K�@�ɋy�ڂ����邩�Ƃ������)�ł͂Ȃ��C�O���ɂ���O���l�ɑ��āC���͓I��p���y�ڂ����ꍇ�ɁC�����C���̍����@��C���Q�����`�������ۂ��̖��ł���B
�@�O�L�̂悤�ɁC���Ɩ����ӂ̖@���́C�����͂̍s�g�ɂ��C���̍s�ׂ̐�������C���̖@�ł��鎄�@�Ȃ������@�̓K�p���̉F�r��������̂ł����āC���̑����̔����ӔC��F�߂�@�ߏ�̍������Ȃ����Ƃ���e�Ƃ���@���ł���C�s���ٔ��@�y�ы����@�����z���ꂽ�����Q�R�N�̎��_�ŁC�����͂̍s�g�ɂ��č��͑��Q�����ӔC��Ȃ��Ƃ������@���m�����Ă������̂ł���(����G�E�s���@�U���łQ�Q�Q�Ȃ����Q�Q�R�y�[�W)�B
�@���������āC���̂悤�Ȗ@������̗p���������̉䂪���̖@���ɂ����āC�O���l����Q�҂ł���ꍇ�ɂ͌��͓I��p�ɂ��C���@�̕s�@�s�K���K�p���č��ƐӔC���m�肵�C���{�l����Q�҂ł���ꍇ�݂̂ɖ��@�̕s�@�s�K��̓K�p��ے肵�č��Ɩ����ӂƂȂ�Ƃ���������̂��Ă����Ƃ͓���l�����Ȃ��B
�@
�@�G�@�ٔ���ɂ����Ă��C�O���ɂ����錠�͓I�s�ׂɂ��āC���Ɩ����ӂ̖@����K�p���Ď��̂悤�Ȕ��f�����Ă���B
�@�Ⴆ�C�������ٕ����P�Q�N�P�Q���U������(����S�O����)�́C�u�T�i�l��́C�T�i�l��Ɠ��{���Ƃ̊Ԃɂ͍��Ɩ����ӂ̌������Ó����鍪���ł���w���ƂƖ@�����̎������x�����݂��Ȃ����獑�Ɩ����ӂ̌����͓K�p����Ȃ��|�咣����B�������C���Ɩ����ӂ̌����̍����͍��Ƃ��ꎩ�̂̎匠���⌠�͐����ɋ��߂���ׂ����̂ł����āC���ƂƔ�Q�҂Ƃ̓������ɂ��̍�����L������̂ł͂Ȃ�����C�T�i�l��̉E�咣�͎����ł���B�v�Ɣ�������B
�@�܂��C�����n�ٕ����P�R�N�T���R�O������(����R�U����)���C���Ɩ����ӂ̖@�����C�u����{�鍑���@���̉䂪���ɂ����ẮC���͓I��p�ɑ��锅���ӔC��F�߂邽�߂̓��ʂ̍����K�肪�Ȃ��C���@�̓K�p���Ȃ���Ȃ������Ƃ������̖@��̗��R�Ɋ�Â����̂ł��邩��C���Y�s�ׂ����͓I��p�ł���ȏ�́C��Q�҂����{�l�ł���ƊO���l�ł���Ɩ�킸�C�s�גn�����{�����ł���ƍ��O�ł���Ƃ��킸�C�܂��C���̈�@���̒��x���킸�C���Q�����������Ȃ����Ȃ������Ƃ����ׂ��ł���v�Ɣ������Ă��Ă���B
�@
�@�I�@�Ȃ��C�T�i�l��́C�u�p�i�C�������ł́C�l���������ɉ����Ă���v(�T�i�l���P�������ʂS�Q�Ȃ����S�S�y�[�W)�ȂǂƎ咣���邪�C�T�i�l��̎咣��������炩�Ȃ悤�ɁC�������́C�P�X�R�V�N�P�Q���P�Q���ɋ����{�R���A�����J���O���C�̓p�i�C�����̊͑D���������Ƃɑ��C����{�鍑���{���C�A�����J���O�����{�ɑ��C��Q�Q�P���h�����x�������Ƃ�������ł���C���ƊԂɂ����ĉ������}��ꂽ����ł����āC��Q�Ҍl�����@�̋K��������ɑ��Q���������߂�����ł͂Ȃ��B
�@���������āC���̎���������āC���Ɩ����ӂ̖@�����O���l�ɑ��錠�͓I��p�ɂ͓K�p����Ȃ��Ƃ��鍪���ɂȂ�Ȃ����Ƃ͖��炩�ł���B
�@
�@(4) �w�[�O������̍����@���ɂ�鍑�Ɩ����ӂ̖@���̔r���������_�ɂ���
�@
�@�A�@�T�i�l��́C�w�[�O������͍��ۊ��K�@�Ƃ��Đ����������@�����Ă�������C�����@�͂���ɓK������悤�ɉ��߂���Ȃ���Ȃ炸�C���Ɩ����ӂ̖@���͓K�p����Ȃ�(�T�i�l���P�������ʂS�X�y�[�W�ȉ�)�Ǝ咣����B
�@���̎�|�͕K���������炩�ł͂Ȃ����C�w�[�O�����C���ۖ@���Q�Ҍl�̉��Q���ɑ��鑹�Q�����������Ȃ����Ӎߐ�������ۏႵ�Ă�����̂łȂ����Ƃ́C���R�ɂ����镽���P�R�N�P�Q���Q�U���t����T�i�l�̏�������(�V)�P�Ȃ����Q�W�y�[�W�ɂ����ďڏq�����Ƃ���ł���C��������p����B
�@�����āC�w�[�O������̋K�肪�C����������Q�Ҍl�̉��Q���ɑ��鑹�Q���������������̓��e�Ƃ��ĕۏႵ�Ă��Ȃ��ȏ�C�w�[�O������̋K�肪�����@�I���͂�L����Ƃ��Ă��C����ɂ�蓖�Y�K�肪�ۏႵ�Ă��Ȃ��l�̑��Q�����������������@�I�ɑn�݂����Ƃ������Ƃ͂��蓾���C���Ɩ����ӂ̖@���Ɖ����G������̂ł͂Ȃ��B
�@���������āC�{���ɂ��ăw�[�O������̍����@�I���͂�_���Ă݂Ă��C����������āC���Ɩ����ӂ̖@�����r�˂���C�T�i�l��̐������@�I�ɍ����Â�������̂ł��Ȃ��B
�@
�@�C�@�܂��C�w�[�O���������@�Ƃ��Ă̌��͂����Ƃ��Ă��C���ꂾ���Œ����ɍٔ������̍��Ƌ@�ւ��������̓I���������̍����@�K�Ƃ��ēK�p�ł���킯�ł͂Ȃ��̂ŁC�O�̂��߁C���̓_�ɂ��ďq�ׂĂ����B
�@���Ȃ킿�A���ۖ@�ɂ��C�u�����̒��ړK�p���\�ł��邩�C���邢�͍������@�����Ȃ�������̒��ړK�p�͂ł��Ȃ����C���Ȃ킿�C�X�̍������E���ۖ@�ڂ̖@�I�����Ƃ��āC���R�ɋ�̓I�Ȍ����Ȃ����@�I�n�ʂ��咣������C���邢�͍����̎i�@�ٔ������C���Ƃƍ������邢�͍������݊Ԃ̖@�I��������������ɂ�����C�E���ۖ@�ړK�p���Č��_�����Ƃ��\�ł��邩�ǂ����Ƃ������ۖ@�̍����K�p�\���̗L���̖��́C�ʓr��������K�v������v(�������ٕ����T�N�R���T������)�B
�@���́C���ۖ@�̈�`���ł��邪�C������������͍̂��Ƃł����āC���ƊԂ̌����`���W��藧���邱�Ƃ����Ƃ���B���̂��߁C����ڍ����@��̌��ʂ����҂��C�����Ɍ�����^���`�����ۂ����Ƃ����ړI�Ƃ���ꍇ�ɂ́C�����Ƃ��āC���̖ړI��B�����邽�ߍ��Ƌ@�ւɗ��@�`�����ۂ����͍s���[�u���̂邱�Ƃ𖽂��C������āC���@�@�ւ��@���𐧒肵�C�܂��C�s���@�ւ��@�߂Ɋ�Â����̌������ɂ��鎖���ɂ��čs���[�u���̂邱�ƂɂȂ�B���������āC���̓��e�����l���݊Ԗ��͎��l�ƍ��ƊԂ̖@���W�ɓK�p�\�Ȃ��̂Ƃ��čٔ������̍��Ƌ@�ւ��S�����邽�߂ɂ́C�����Ƃ��āC��L�̂悤�ȍ����[�u�ɂ��⊮���K�v�ł���C���ɂ��̂悤�ȍ����@���������肳��Ă���B
�@��O�I�ɏ��̋K�肪���̂܂܂̌`�ō����@�Ƃ��Ē��ړK�p�\�ł���ꍇ�����蓾��Ƃ��Ă��C�����Ȃ�K�肪����ɊY�����邩�́C���Y���̌X�̋K��̖ړI�C���e�y�ѕ������тɊ֘A���鏔�@�K�̓��e�������Ă��Ȃ���C��̓I�ꍇ�ɉ����Ĕ��f����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
�@�����āC���̔��f�ɓ������ẮC��P�Ɂu��ϓI�v���v�Ƃ��āC���l�̌����`�����߁C���ړ��ٔ����œK�p�\�ȓ��e�̂��̂ɂ���Ƃ����������̈ӎv���m�F�ł��邱�ƁC��Q�Ɂu�q�ϓI�v���v�Ƃ��āC���l�̌����`���������C�m��I�C���S���ڍׂɒ�߂��Ă��āC���̓��e����̉�����@�߂�҂܂ł��Ȃ��C�����ł̒��ړK�p���\�ł��邱�ƂȂǂ���������B�����̗v�����l�����āC���̎����I���s�̗͂L����F�肷�邱�ƂƂȂ�(�R�{�E�O�f���ۖ@�P�O�T�y�[�W�ȉ��Q��)�B
�@���������āC���������������o�邱�ƂȂ��C����ʂ��������ɂ����Ē��ړK�p�\�ł���Ɖ����邱�Ƃ͐������@���߂Ƃ͂����Ȃ��B
�@�Ƃ�킯�C���ƂɈ��̍�`�����ۂ�����C����̎x�o���悤�ȏꍇ�ɂ́C�����̐�����C�����̔������Ɋւ�����̓I�v���C�����̍s�g���Ɋւ���葱�I�v���������m�ł��邱�Ƃ������v�������B�ٔ���ɂ����Ă��C�u�����I���͂��F�߂�ꂽ���ۖ@�K(���̂ق��C���ۊ��K�@�����܂ށB)�������ɂ����ēK�p�\���ۂ��̔��f��ɂ��čl����ɁC�܂��C���R�̂��ƂȂ�����������̋�̓I�Ȉӎv�@�����d�v�ȗv�f�ƂȂ邱�Ƃ͂��Ƃ��C�K����e�����m�łȂ���Ȃ�Ȃ��B��ƂɈ��̍�`�����ۂ�����C����̎x�o���悤�ȏꍇ���邢�͂��œ��ɂ����ē���̐��x�����݂��Ă���Ƃ��ɂ́C�E�̐��x�Ƃ̐������������\���l�����Ȃ���Ȃ炸�C���������āC���e����薾�m�����ĂɂȂ��Ă��邱�Ƃ��K�v�ƂȂ�B�v(�������ٕ����T�N�R���T������)�Ɣ�������Ă���B
�@���̂悤�ɁC���ۖ@�K�̒���'�K�p�\���́C�O�L�u��ϓI�v���v�y�сu�q�ϓI�v���v��������Ă͂��߂ĔF�߂�����̂ł���B
�@
�@�E�@���̓_�ɂ��Ė{�����݂�ɁC�T�i�l��́C��T�i�l�ɑ��đ��Q�����𐿋����Ă���̂ł��邩��C�l�̉��Q���ɑ��鑹�Q�����������������Â�����������w�E����K�v������Ƃ���C�O�L�̂Ƃ���C���̂悤�Ȑ������������Â���������͑��݂��Ȃ��B�����ł���ȏ�C�O�L�u��ϓI�v���v�y�сu�q�ϓI�v���v��������Ă���Ƃ̎咣����Ȃ��Ƃ��킴����C�咣���̎����ł���B
�@�܂��C�w�[�O������R�̏��Ȃ��������Ɠ��|�̍��ۊ��K�@�́C���Ɩ�̔����ӔC���߂��K��Ɖ�����ق��Ȃ��C�l�̍��Ƃɑ��鑹�Q�������������߂��K��ł͂Ȃ�����C���̂悤�ȋK�肪�����@�I���͂�L���Ă���Ƃ��Ă��C���̂��Ƃ���C�T�i�l��l�������@�I�ɔ������������擾����Ƃ������_�ɂ͂Ȃ蓾�Ȃ��B���Ȃ킿�C������͌l�������̎�̂Ƃ��ĔF�߂����̂ł͂Ȃ��̂ł��邩��C������@�I���͂��F�߂�ꂽ����Ƃ����āC�l�̌������n�݂���邱�Ƃ͂��蓾�Ȃ��B���ƐӔC�Ɋւ���K�肪�����@�I���͂�L���Ă��邱�Ƃ������ɍT�i�l��l�̔�����������F�߂邱�Ƃ́C���߂ɖ����肽���@�ɂق��Ȃ�Ȃ��B
�@���������āC�T�i�l��̂��̓_�Ɋւ���咣���O������������Ƃ����ق��Ȃ��B
�@
�@(5) ���݂̖@���߂Ɋ�Â��ٔ����ׂ��Ƃ����_�ɂ���
�@�T�i�l��̏�L�P(5)�̎咣�́C���Ɩ����ӂ̖@�������̏�̖@���ł͂Ȃ��C�@���߂ɂ����Ȃ����Ƃ�O��Ƃ�����̂ŁC���̑O��ɂ����Ď����Ƃ��킴����C���_�̌���ł͂Ȃ����C�ȉ��̓_�ɂ��C�O�̂��ߕt�����Ă������ƂƂ���B
�@
�@�A�@�s������Ƃ��ׂ����Ƃɂ���
�@�ō��ٔ��������P�T�N�S���P�W����@�씻��(�ٔ��������P�R�R�W���R�y�[�W)�́C�@���s�ׂ����ꂽ���_�ł͌����ɔ����Ȃ��������C���̌�Ɍ������ω������ꍇ�̖@���s�ׂ̗L�����ɂ��āC�u�@���s�ׂ������ɔ����邱�Ƃ�ړI�Ƃ�����̂ł���Ƃ��Ė����ɂȂ邩�ǂ����́C�@���s�ׂ����ꂽ���_�̌����ɏƂ炵�Ĕ��f���ׂ��ł���B�������C������̖@���s�ׂ̌��͂́C���ʂ̋K�肪�Ȃ�����C�s�ד����̖@�߂ɏƂ炵�Ĕ��肷�ׂ����̂ł��邪(�ō��ُ��a�Q�X�N(�N)��Q�Q�R�����R�T�N�S���P�W����@�쌈��E���W�P�S���U���X�O�T��)�C���̗��́C�������@���s�ׂ̌�ɕω������ꍇ�ɂ����Ă����l�ɍl����ׂ��ł���C�@���s�ׂ̌�̌o�܂ɂ���Č����̓��e���ω������ꍇ�ł����Ă��C�s���ɗL���ł����@���s�ׂ������ɂȂ�����C�����ł����@���s�ׂ��L���ɂȂ����肷�邱�Ƃ͑����ł͂Ȃ�����ł���B�v�Ɣ������Ă���Ƃ���ł����āC���̗��́C���Ɩ����ӂ̖@���ɂ��Ó�����̂ł���C�������@���ɂ����č������̂������Ɩ����ӂ̖@������{�����@��O��Ƃ��錻�݂̉��l�ςɂ���Ĕے肵�āC���ʂ̋K�肪�Ȃ��̂ɁC�����ӂł����s�ׂɂ��C�����ӔC��F�߂邱�Ƃ͖@�̉��߂Ƃ��ċ�����Ȃ��Ƃ����ׂ��ł���B
�@
�@�C�@�����@�����U���́u�]�O�̗�v�Ɋւ���咣�ɂ���
�@�T�i�l��́C�����n���ٔ��������P�T�N�R���P�P������(�ȉ��u�����n�قR�������v�Ƃ����B)�����p���C�u�u�]�O�̗�ɂ��v���Ƃ����Ɩ����ӂ�K�p�����鍪���ƂȂ�Ȃ��v�|�咣����B
�@�������Ȃ���B�����n�قR�������́C���Ɩ����ӂ̖@���ɂ��čō��ُ��a�Q�T�N�����̔��f�Ƒ������锻�f��������̂ł����āC����Ɉˋ�����T�i�l��̎咣�͎����ł���B
�@���̓_�ɂ��ẮC�������߂āC��L(6)�ɂ����ďڏq���邱�ƂƂ���B
�@
�@(6) �����n�قR�������ɂ���
�@
�@�A�@�����n�قR�������̊T�v
�@�����n�قR�������́C���{���̒����l�ɑ��鋭���A�s�E�����J�����̂���@�ł���C�܂��C������Ɋ�Â������l�ɑ��鋭���A�s�E�����J���Ɋ֗^�����X�̓��{�R�l�����s�����s�ׂ���@�ł���Ƃ��āC���ɑ��đ��Q�����𐿋��������Ăɂ��C�������̌����炪�C�@��P�P���P���̓K�p�ɂ��P�X�R�O�N���ؖ������@�Ɋ�Â����ɑ��đ��Q�����������咣�����̂ɑ��C�����鍑�Ɣ����������̑��ۂɊւ���@���W�����ێ��@�̓K�p�ΏۂƂȂ�@���W�Ɋ܂܂��Ɖ����邱�Ƃ͂ł��Ȃ��|�������āC�@��P�P���̓K�p��ے肵�C�������̌�����̎咣��r�˂������̂́C�u�𗝏�C�@�����̓��{�����@��K�p���Ĕ��f���ׂ����ƂɂȂ�̂ŁC�Ȃ��O�̂��߁C�����̓��{�����@��K�p�����ꍇ�ɂ������L�������̑��ۂɂ��Č�����������v(�������R�V�y�[�W)�Ƃ�����ŁC���̂Ƃ��蔻�������B
�u�A�@���Ɣ����@�{�s�O�ɂ�����퍐���ɑ��鍑�Ɣ��������̖@�I�������Ɣ����@�{�s�O�ɂ����ẮC��ʓ̑��Q�����ӔC��F�߂閾���̋K���������@�͂Ȃ��C���Ɣ����@�����U��(�}�})�ɂ����āC�u���̖@���{�s�O�̍s�ׂɊ�Â����Q�ɂ��ẮC�Ȃ��]�O�̗�ɂ��B�v�ƋK�肳��C���@�̋K��̑k�y�K�p���ے肳�ꂽ�ȏ�C���@�{�s�O�̌������̌����͂̍s�g�̈�@�𗝗R�Ƃ��鍑�̑��Q�����ӔC�Ɋւ��ẮC���@�̕s�@�s�ׂɊւ���K�肪�������̌����͂̍s�g�ɂ��Ă��K�p�����邩�ۂ��Ƃ������@�̉��߂ɂ䂾�˂��Ă����Ɖ�������ق��͂Ȃ��B�����āC��O�ɂ�����ٔ���y�ъw�������n���ƁC��O�ɂ����锻��E�ʐ��́C���@�̕s�@�s�ׂɊւ���K��́C�������̌��͓I��p�ɂ͓K�p���Ȃ��Ƃ̉��߂��̂��Ă������Ƃ͍ٔ����Ɍ����ł���(�Ȃ��C�ō��ُ��a�Q�T�N�S���P�P����O���@�씻���E�ٔ��W�����R���Q�Q�T�ŎQ��)�B���̓_�ɂ��C������́C���Ɣ����@�{�s�O�ɂ����Ă��C���@�E���@�_��r�����C�������̌����͂̍s�g�ɂ��Ă����@��K�p���āC���̑��Q�����ӔC��F�߂Ă����ٔ��Ⴊ�������Ƃ��w�E���C�������̌����͂̍s�g�ɂ��Ė��@�̓K�p���Ȃ��Ƃ������߂��m�����Ă����킯�ł͂Ȃ��Ǝ咣���邪�C�����炪�w�E����ٔ�����������Ă݂Ă��C�����́C�����͌����c�̂����l�Ɠ����̗���ɗ����čs���o�ϓI�����̐�����тт�s�ׂɂ��āC���@�̓K�p�ΏۂƂ�����߂��̂�ꂽ�Ⴊ���邱�Ƃ����炩�ɂȂ�ɂƂǂ܂�B
�@�������C��O�ɂ����āC��L�̂悤�ȉ��߂��̂��Ă����������K���������炩�ł͂Ȃ����Ƃ͌����炪�咣����Ƃ���ł���C��O�̍ٔ���y�ъw���ɏƂ炷�ƁC�u���Ɩ����Ӂv�Ȃ�s���́u�@���v���m�����Ă���Ƃ̗�����w�i�Ƃ��āC��L�̂悤�ȉ��߂��̂��Ă������Ƃ�������������̂́C�����_�ɂ����ẮC�u���Ɩ����ӂ̖@���v�ɐ������Ȃ�����������������������Ƃ��C�����炪�咣����Ƃ���ł���B���ٔ��������Ɣ����@���{�s�����ȑO�̖@�̌n�̉��ɂ����閯�@�̕s�@�s�ׂ̋K��̉��߂��s���ɓ�����C����@�㖾���̍�����L������̂ł͂Ȃ���L�s���̖@���ɂ���Ď���@�ɂ��̂Ɠ��l�̍S�����C���̍S���̉��ɖ��@�̉��߂��s��Ȃ���Ȃ�Ȃ����R�͌���������B�����āC���@�V�P�T���̕�����́C�������̌����͂̍s�g�������̓K�p����r������Ă���Ƃ͂����Ȃ����ƁC�s���ٔ����@(�}�})�P�U�����u�s���ٔ����n���Q�v���m�i�׃��Z�X�v�ƋK�肵�Ă���C�����̋K��́C���̖@��́C�����͂̍s�g�Ɉ�@�������ꍇ�ɑ��鑹�Q�������������������邱�Ƃ�O��Ƃ��Ȃ���C�s���ٔ��������Q���������i�ׂ����Ȃ��Ƃ����i�ז@��̒�߂�u�������̂Ɖ�����]�n�����邱�Ƃ��l������ƁC���Ɣ����@�{�s�O�ɂ�����C�������̌����͂̍s�g�̈�@�𗝗R�Ƃ��鍑�̐ӔC�ɂ��Ă��C���@�V�P�T���̋K���ɂ䂾�˂��Ă������̂Ɖ�����]�n���Ȃ��Ƃ͂����Ȃ��B�v(�������R�V�Ȃ����R�X�y�[�W)
�@�����n�قR�������́C��L�̂悤�ɔ������āC�����@�{�s�O�ɂ�����C�������̌����͂̌��g�ɂ��Ă����@�V�P�T���̓K�p�̉\����F�߂���ŁC�����Ɋ�Â����Q�����������́C���@�V�Q�S����i�̓K�p�ɂ����ł��Ă���|���������B
�@
�@�C�@��T�i�l�̔ᔻ�̊T�v
�@�������C�����n�قR�������̑O�L���������́C�@�����Q�R�N�ɁC���Ɩ����ӂ̖@���������̖@����Ƃ��č̂�ꂽ�����y�эs���ٔ��@�P�U���C�����@���̗��@�o�܂ɂ��Ă̗���s�����獑�Ɩ����ӂ̖@���̗��������C�܂��A�����@�����U���̉��߂����C�ō��ُ��a�Q�T�N�S���P�P����O���@�씻��(�ٔ��W�����R���Q�Q�T�y�[�W�B�ȉ��u�ō��ُ��a�Q�T�N�����v�Ƃ����B)�Ƒ���������̂ł���C�����ƌ��킴��Ȃ���C�B�����n�قR���������@��P�P���P���̓K�p��ے肵�����R�Ƃ̊Ԃɂ��������Ă���B
�@�ȉ��C�ڏq����B
�@
�@�E�@���Ɩ����ӂ̖@���̍����̗������s�\���ł��邱�Ƃɂ���
�@
�@(�) �����n�قR�������̔���
�@�����n�قR�������́C�@�u��O�ɂ����锻��E�ʐ��́C���@�̕s�@�s�ׂɊւ���K��́C�������̌��͓I��p�ɂ͓K�p���Ȃ��Ƃ̉��߂��̂��Ă����v���C���̂悤�ȁu���߂��̂��Ă����������K���������炩�ł͂Ȃ��v(�������R�W�y�[�W)�C�A�u�s���ٔ����@(�}�})�P�U�����u�s���ٔ����n���Q�v���m�i�׃��Z�X�v�ƋK�肵�Ă���C�����̋K��́C���̖@��́C�����͂̍s�g�Ɉ�@�������ꍇ�ɑ��鑹�Q�������������������邱�Ƃ�O��Ƃ��Ȃ���C�s���ٔ��������Q���������i�ׂ����Ȃ��Ƃ����i�ז@��̒�߂�u�������̂Ɖ�����]�n������v(�������R�W�C�R�X�y�[�W)�ȂǂƔ������Ă���B
�@�������C�ȉ��ɏq�ׂ�悤�ɁC���̔����́C����������Ɩ����ӂ̖@���𐳂����������Ă��Ȃ����̂Ƃ��킴����C�����ł���B
�@
�@(�) ���Ɩ����ӂ̖@���ɂ���
�@���Ɩ����ӂ̖@���́C��T�i�l���]�O����咣���Ă���悤�ɁC�s���ٔ��@�Ƌ����@�����z���ꂽ�����Q�R�N�̎��_�ŁC���Ƃ̌��͓I��p�ɂ��č��͔����ӔC��Ȃ��Ƃ��鍑�Ɩ����ӂ̖@������{�I�@����Ƃ��Ċm���������̂ł���(����G�E�s���@�U(��Q��)�Q�Q�Q�C�Q�Q�R�y�[�W�C�F�ꍎ��E���ƐӔC�@�̕��͂S�O�X�Ȃ����S�P�P�y�[�W)�C����Ɋ�Â��C�s���ٔ��@�P�U���C�����@���̋K�肪�݂���ꂽ�̂ł���B
�@���Ȃ킿�C�䂪���̖������{�́C�����ɒ��������s�������̉��������Ɠ��W�Ƃ��āC�{�A�\�i�[�h�ȂNJO���̗l�X�Ȗ@���w�҂̈ӌ����Q�l�ɂ��Ȃ���C�ߑ㍑�ƂƂ��Ă̖@���x�̐�����i�߂Ă����B�����āC���̈�Ƃ��āC�s���ٔ��@�y�і��@�̐����}�������C�ߑ�@�����ƂƂ��Čo����L���Ă��Ȃ��䂪���Ƃ��ẮC�����̖@���x���Q�Ƃ��Ȃ���C�@���̐�����}�炴��Ȃ������B���Ɣ����ӔC�̖��ɂ��Ă��C�����C�{�A�\�i�[�h�̈ӌ��Ɋ�Â��C���Ɣ����ӔC��F�߂�K��@�̋K��ɒu�����Ƃ������C�{�A�\�i�[�h�̈ӌ��́C���̑O��Ƃ��Ă̔�r�@�̎����F���Ɍ�F������C���Ɣ����ӔC�Ɋւ��鏔�O���̖@���x�́C�u�N��n�s�P��ਃX�R�g�\�n�Y�B�v(����Q�U����)�𗝔O�Ƃ��āC���Ɣ����ӔC��ے肵�����̂ł������ƁC�܂��C���ɁC�{�A�\�i�[�h�̈ӌ��̂Ƃ���C���Ɣ����ӔC�̖����u��_�j�����ƃ��v�ԃm���j��ᶃV�e���@�m�͚����j�����v(���B�̍����a�Y�����ȁE����R�Q����)��C�u�����������@��j萌W�V�C�����Ƒ����\��C����������V��n�C�O���l���Ɛ��{�Ƃ̑��c�V�_���Ƒ��������v(���B�̎R�c���`�i�@��b�����ȁE����R�Q����)�����O���C���ǁC���Ɩ����ӂ̖@�����̗p���C�{�A�\�i�[�h���@���Ă��獑�Ɣ����ӔC�̋K����폜�����̂ł���B
�@�ȏ�̌o�܂ɏƂ点�C�����n�قR�������́u���@�̕s�@�s�ׂɊւ���K��́C�������̌��͓I��p�ɂ͓K�p���Ȃ��v�Ƃ́u���߂��̂��Ă������R���K���������炩�ł͂Ȃ��v�Ƃ̔����͎����ł���B
�@
�@�G�@�����@�����U���y�эō��ُ��a�Q�T�N�����Ƒ������邱�Ɠ�
�@
�@(�) �����n�قR�������̊T�v
�@�����n�قR�������́C���̌��͓I��p�Ɋ�Â��s�ׂɂ��āC���@�V�P�T����K�p���闝�R�Ƃ��āC�u���Ɣ����@�{�s�O�ɂ����ẮC��ʓ̑��Q�����ӔC��F�߂閾���̋K���������@�͂Ȃ��C���Ɣ����@�����U��(�}�})�ɂ����āC�u���̖@���{�s�O�̍s�ׂɊ�Â����Q�ɂ��ẮC�Ȃ��]�O�̗�ɂ��B�v�ƋK�肳��C���@�̋K��̑k�y�K�p���ے肳�ꂽ�ȏ�C���@�{�s�O�̌������̌����͂̍s�g�̈�@�𗝗R�Ƃ��鍑�̑��Q�����ӔC�Ɋւ��ẮC���@�̕s�@�s�ׂɊւ���K�肪�������̌����͂̍s�g�ɂ��Ă��K�p�����邩�ۂ��Ƃ������@�̉��߂ɂ䂾�˂��Ă����Ɖ�������ق��͂Ȃ��B�v(�������R�V�C�R�W�y�[�W)�Ƃ��C�u��O�̍ٔ���y�ъw���ɏƂ炷�ƁC�u���Ɩ����Ӂv�Ȃ�s���́u�@���v���m�����Ă���Ƃ̗�����w�i�Ƃ��āC��L�̂悤�ȉ��߂��̂��Ă������Ƃ�������������̂́C�����_�ɂ����ẮC�u���Ɩ����ӂ̖@���v�ɐ������Ȃ�����������������������Ƃ��C�����炪�咣����Ƃ���ł���B���ٔ��������Ɣ����@���{�s�����ȑO�̖@�̌n�̉��ɂ����閯�@�̕s�@�s�ׂ̋K��̉��߂��s���ɓ�����C����@�㖾���̍�����L������̂ł͂Ȃ���L�s���̖@���ɂ���Ď���@�ɂ��̂Ɠ��l�̍S�����C���̍S���̉��ɖ��@�̉��߂��s��Ȃ���Ȃ�Ȃ����R�͌���������B�v�Ƃ���(�������R�W�y�[�W)�B
�@�������C���̔����́C�������@���ɂ����č��Ɩ����ӂ̖@������{�I�@����Ƃ��č̗p����Ă��������𗝉����Ă��Ȃ������łȂ��C�����@�����U���y�эō��ُ��a�Q�T�N�����ɑ���������̂ł���C�����ł���B
�@
�@(�) �������@���ɂ����鍑�Ɩ����ӂ̖@���Ɩ��@���߂Ƃ̊W�ɂ���
�@
�@a�@�����n�قR�������́C�u���@(���p�Ғ��F�����@���w���B)�{�s�O�̌������̌����͂̍s�g�̈�@�𗝗R�Ƃ��鍑�̑��Q�����ӔC�Ɋւ��ẮC���@�̕s�@�s�ׂɊւ���K�肪�������̌����͂̍s�g�ɂ��Ă��K�p�����邩�ۂ��Ƃ������@�̉��߂ɂ䂾�˂��Ă����v�|��������B
�@
�@b�@�������Ȃ���C�O�L�Q(1)�ŏڏq�����悤�ɁC�����@�{�s�O�ɂ����āC���Ɩ����ӂ̖@���́C�s���ٔ��@�Ƌ����@�����z���ꂽ�����Q�R�N�̎��_�ŁC���Ƃ̌��͓I��p�ɂ��č��͔����ӔC��Ȃ��Ƃ�����{�I�@����Ƃ��Ċm���������̂ł���C���������āC���̌��͓I��p�ɂ��č��������ӔC���|�̖@�K�͐��肹���C�܂��C���@�̕s�@�s�ׂ̋K��́C����ɓK�p���Ȃ��C�Ƃ����@���̗p���ꂽ�̂ł���B
�@���������āC�������������n�قR�������̔�������悤�ɁC�����@�u�{�s�O�ɂ����Ă̌������̌����͂̍s�g�̈�@�𗝗R�Ƃ��鍑�̑��Q�����ӔC�Ɋւ��āv�C�u���@�̕s�@�s�ׂɊւ���K�肪�������̌����͂̍s�g�ɂ��Ă��K�p�����邩�ۂ��Ƃ������@�̉��߂ɂ䂾�˂��Ă����v�Ƃ����O�̂����ł���C�����@�{�s�O�ɂ����ẮC���Ƃ̌��͓I��p�ɂ��đ��Q�������ے肳�ꂽ�̂́C�O�L�̂悤�Ȋ�{�I�@����Ɋ�Â����ɑ��Q������F�߂鍪���K���u���Ȃ����ƂƂ������߂ł����āC���@�̉��ߖ�肪������]�n�͂Ȃ��̂ł���B
�@
�@c�@�Ȃ��C�����@�{�s�O�ɂ����āC���Ƃ̌��͓I��p�ɂ��č��̑��Q�����ӔC���ے肳���̂́C���@�̉��߂݂̂ɂ����̂łȂ����Ƃ͏�L�̂Ƃ���ł��邪�C���@�̕s�@�s�K��̉��߂ɂ��Ă݂��Ƃ��Ă��C�����@�{�s��ɂ����Ă��C�������̌����͂̍s�g�ɂ���Đ��������Q�̔����ӔC�̐��ۂ́C���ς獑���@�P���P���ɂ���Ă��̐��ۂ����f����C���@�̕s�@�s�K��̓K�p�͔r������Ă���̂ł���C���Ƃ̌��͓I��p�ɂ�鑹�Q�����̐��ۂ��C���@�̕s�@�s�K��̉��߂ɂ䂾�˂�Ƃ���l�����͈�т��đ��݂��Ȃ��̂ł���B
�@���Ȃ킿�C���s���@�́C���͂⍑�̌��͓I��p�ɂ��Ă��C���̑��Q�����ӔC��S�ĖƐӂ����邱�Ƃ͖]�܂����Ȃ��Ƃ̐����I���f����C���s���@�P�V�����K�肵�����C�����@�̗v�����������ɒ�߂邩�́C���@���Đ��肳���@���̒�߂�Ƃ���ɂ䂾�˂��̂ł����āC���@�̉��߂ɂ䂾�˂����̂ł͂Ȃ��B����́C�����͂̍s�g�́C�ʏ�C�����̌����`���ɉe����^���鐫����L���邱�Ƃ���C���ʈ�@�𒆐S�Ƃ������@�I�@���W�Ƃ��Ă͋K�����ׂ��ł͂Ȃ��C�ʓr�C����Ɋւ���@���𐧒肷�邱�ƂƂ������̂ł����āC�����ɂ����ẮC���@����ɂ���āC���@�̕s�@�s�אӔC�Ƃ͈قȂ�v�������߂���C���邢�́C�ƐӋK���݂��邱�Ƃ����e�����̂ł���B
�@���̓_�Ɋւ��C�ō��ٔ��������P�S�N�X���P�P����@�씻��(����S�P����)���C�u���@�P�V���́C�u���l���C�������̕s�@�s�ׂɂ��C���Q�����Ƃ��́C�@���̒�߂�Ƃ���ɂ��C�����͌����c�̂ɁC���̔��������߂邱�Ƃ��ł���B�v�ƋK�肵�C���̕ۏႷ�鍑���͌����c�̂ɑ����Q���������߂錠���ɂ��ẮC�@���ɂ���̉���\�肵�Ă���B����́C�������̍s�ׂ����͓I�ȍ�p�ɑ�������̂���͓I�ȍ�p�ɑ�������̂ɂ܂ŋy�сC�������̍s�ׂ̍����ւ̂��������ɂ͎�X���l�Ȃ��̂����蓾�邱�Ƃ���C�����͌����c�̂��������̍s�ׂɂ��s�@�s�אӔC�����Ƃ������Ƃ�����C�������̂ǂ̂悤�ȍs�ׂɂ�肢���Ȃ�v���ő��Q�����ӔC�����𗧖@�{�̐������f�ɂ䂾�˂����̂ł����āC���@�{�ɖ������̍ٗʌ���t�^����Ƃ������@���ɑ��锒���ϔC��F�߂Ă�����̂ł͂Ȃ��B�����āC�������̕s�@�s�ׂɂ�鍑���͌����c�̂̑��Q�����ӔC��Ə����C���͐�������@���̋K�肪�����ɓK��������̂Ƃ��Đ��F�������̂ł��邩�ǂ����́C���Y�s�ׂ̑ԗl�C����ɂ���ĐN�Q�����@�I���v�̎�ދy�ѐN�Q�̒��x�C�ƐӖ��͐ӔC�����͈̔͋y�ђ��x���ɉ����C���Y�K��̖ړI�̐��������тɂ��̖ړI�B���̎�i�Ƃ��ĖƐӖ��͐ӔC������F�߂邱�Ƃ̍������y�ѕK�v���𑍍��I�ɍl�����Ĕ��f���ׂ��ł���B�v�Ɣ������C���s���@���ł��C���͈̔͂ŖƐӋK���u������C���@�̕s�@�s�אӔC�̋K��Ƃ͈قȂ����K���u�����Ƃ����e���Ă���B
�@���������āC���̂悤�Ȋϓ_����������n�قR�������͎����ł���B
�@
�@d�@�����n�قR�������́C�������̌����͂̍s�g�ɖ��@�V�P�T���̓K�p��F�߂�`���I�ȗ��R�Ƃ��āC���@�V�P�T���̕�����C�����r������Ă���Ƃ͂����Ȃ����Ƃ�������(�������R�W�y�[�W)�B
�@�������C���s�@�̉��ɂ����āC���������E����s�����s�@�s�ׂ��C�u�����͂̍s�g�v�ɊY�����Ȃ��ꍇ�ɂ́C���@�̕s�@�s�K�肪�K�p�����̂ɑ��C�u�����͂̍s�g�v�ɊY������C�����@�P���P�����K�p����āC���̗v���Y�����̔��f����C���@�̓K�p���r�������B�����āC�����@�P���P���̈�@�̔��f�ɂ��C���@�V�O�X���̂悤�ɁC�����N�Q�������Ɉ�@�ł���Ƃ������ʕs�@�����ő�����̂ł͂Ȃ��C�s�וs�@�̊ϓ_����C���������X�̍����ɑ��ĕ����Ă���E����̖@�I�`���Ɉᔽ�������Ƃ������āC��@�Ƃ��Ă��邪(�ō��ُ��a�U�O�N�P�P���Q�P����ꏬ�@�씻���E���W�R�X���V���P�T�P�Q�y�[�W)�C����́C�܂��ɁC�������̐E����̖@�I�`���Ɉᔽ���邩�ۂ��̔��f�ɁC��ʎ��@�ł͑�������Ȃ��s�ׂ̐������̔��f���v������邱�Ƃ������Ă���̂ł���B
�@�O�q�̂Ƃ���C���s�̍����@�̗��@�ɓ������Ă��C�������@���̕s�@�s�ו҂��������č��Ɣ����Ɋւ���K���}������Ƃ���Ă����ꂽ�Ƃ���C���E�����c�̂̌����͍s�g�̊W�͎��@�I�@���W�ł͂Ȃ��C���@�ɓ����̂͗��ꂪ�Ⴂ�s�K���Ƃ���āC���@�ւ̕ғ��͂��ꂸ�C�����@�Ƃ����Ǝ��̖@�������肳�ꂽ�Ƃ����o�܂�����(�Í�c���u���Ɣ����@�v�V�y�[�W�Q��)�B����͂܂��ɁC���Ɣ����������̑��ۂ��C��ʎ��@�̊ϓ_����K�������ׂ��W�ł͂Ȃ��C���Ɉ�ʎ��l���s�����Ȃ����͓I��p�ɂ��ẮC���̍s�g�̐������̊ϓ_����C��Ɍ���v������@�I�@���W�ł���ƍl����ꂽ���ƂɊ�Â��Ƃ�����B
�@
�@e�@��T�i�l���]�O����J��Ԃ��q�ׂĂ���悤�ɁC�u���Ɩ����ӂ̖@���v�Ƃ́C���������E�����s���ɂ��Ă��ꂽ�s�ׂ����Ƃ̌��͓I��p�ɊY���������C���@�̕s�@�s�ׂ̋K��̓K�p���Ȃ��C���̔����ӔC��F�߂�K�肪�Ȃ��������ƂɊ�Â����̖@�̖@���ł���B���������āC���Ɩ����ӂ̖@���̓��e�́C�@���@�̕s�@�s�ׂ̋K��̓K�p���Ȃ����ƂƁC�A���̑������ӔC��F�߂�K�肪�Ȃ����Ƃ��܂ނ��̂ł���B
�@�����āC�@�̓_�C���Ȃ킿�C�����͌����c�̂̌����͂̍s�g�ɓ�������������C���̐E�����s���ɂ��āC�̈Ӗ��͉ߎ��ɂ���Ĉ�@�ɑ��l�ɑ��Q��^�����ꍇ�̑��Q�����������̐����v���̔��f�ɂ��ẮC�����@�{�s�̑O����킸�C���@�̕s�@�s�ׂ̋K��̓K�p���Ȃ����C�A�̓_�ɂ��ẮC�������@���ł́C���݂̍����@�̂悤�Ɉ�ʓI�ɑ��Q�����ӔC��F�߂�K�肪�Ȃ����߁C���Ɩ����ӂł��������C���{�����@���ł́C�����@�����݂��邽�߂ɁC���Ɩ����ӂł͂Ȃ��C���Ɣ����ӔC�����ƂƂȂ��Ă���̂ł���B
���������āC�����n�قR�������́C�����@�{�s�O�ɂ�����u�������̌����͂̍s�g�̈�@�𗝗R�Ƃ��鍑�̐ӔC�ɂ��Ă��C���@�V�P�T���̋K���ɂ䂾�˂��Ă������̂Ɖ�����]�n���Ȃ��Ƃ͂����Ȃ��v�Ƃ̔����́C���Ƃ̌��͓I��p�ɂ��Ă̔����ӔC�̐��ۂɊւ��ẮC�����@�{�s�̑O���ʂ��āC���@�̕s�@�s�ׂ̋K��̓K�p���Ȃ��ɂ�������炸�C�����K�p���悤�Ƃ������̂ł���C�����ł���B
�@
�@�I �����@�����U���Ɉᔽ���邱��
�@
�@(�)�@�����n�قR�������́C�����@�����U���ɂ��C�����@�̋K��̑k�y�K�p���ے肳�ꂽ�Ƃ��Ȃ���C�u���ٔ��������Ɣ����@���{�s�����ȑO�̖@�̌n�̉��ɂ����閯�@�̕s�@�s�ׂ̋K��̉��߂��s���ɓ�����A����@�㖾���̍�����L������̂ł͂Ȃ���L�s���̖@���ɂ���Ď���@�ɂ��̂Ɠ��l�̍S�����C���̍S���̉��ɖ��@�̉��߂��s��Ȃ���Ȃ�Ȃ����R�͌���������B�v�|��������B
�@
�@(�)�@�������Ȃ���C�����@�����U���́C�u���̖@���{�s�O�̍s�ׂɊ�Â����Q�ɂ��ẮC�Ȃ��]�O�̗�ɂ��B�v�ƋK�肵�Ă���Ƃ���C���́u�Ȃ��]�O�̗�ɂ��v�Ƃ̖@�ߗp��́C�@�߂��������͔p�~�����ꍇ�ɁC���p���O�̖@�߂��܂߂��@���x�����̂܂܂̏�ԂœK�p���邱�Ƃ��Ӗ�����(�L��t�@���p�ꎫ�T��Q�łP�O�W�V�y�[�W)�B
�@���Ȃ킿�C�����@�{�s�O�̌����͂̍s�g�ɔ������Q���������Ƃ���鎖��ɂ��ẮC�����@���ꎩ�̂̑k�y�K�p��ے肷��݂̂Ȃ炸�C����܂ō̗p���Ă������Ɩ����ӂ̖@�������̂܂ܓK�p����邱�Ƃɂ��C�����͌����c�̂��ӔC��Ȃ����Ƃ𖾂炩�ɂ��C����ɂ��C�\���\���Ȃ����@�I���萫���m�ۂ����|�ł���B
�@���̂��Ƃ́C����ɂ����鍑���@�����U���̐R�c���e�����Ă����炩�ł���B���Ȃ킿�C�����@�Ă�R�c������P��̏O�c�@�{��c(���a�Q�Q�N�W���V���J��)�ɂ����āC�i�@�ψ������i�`�Y�́C�i�@�ψ���ɂ����铯�@�Ă̐R�c�o�߂̕ɂ����āC�u�{�@�Ď{�s�O�̍s�ׂɊ�{�s��ɔ����������Q�ɑ��鏈�u������Ƃ̎��^���Ȃ��ꂽ�̂ɑ��C���܂��͌����c�̂ɔ����ӔC�Ȃ��Ƃ̐��{�̓��قł���܂����B�v�Əq�ׂĂ���C���̌�{��c�œ��c���s���C������Ă���(���O���a�Q�Q�N�W���W����P��O�c�@�c���^�Q�Q���Q�S�W�y�[�W�E����S�Q����)�B���̂悤�ȐR�c���e���炷��C�����́C�����@�{�s�O�̍s�ׂɊ�Â����Q�ɂ��ẮC���̑��Q�̔��������@�{�s�O�����邢�͎{�s�ォ�ɂ�����炸�C�����͌����c�̂������ӔC��Ȃ���|�̋K��ł��邱�Ƃ͖��炩�ł���B
�@
�@(�)�@�܂��C�����n�قR�������́C�u�����_�ɂ����ẮC�u���Ɩ����ӂ̖@���v�ɐ������Ȃ�����������������������Ɓv�������āC�����@�{�s�O�̖��@�̉��߂Ƃ��āC���̌��͓I��p�ɖ��@�V�P�T����K�p�ł���Ƃ��鍪���ɂ��Ă���悤�ł���B
�@�������Ȃ���C���Ɩ����ӂ̖@���́C���ꂪ��{�I�@����Ƃ��Ċm�����ꂽ�������@�̉��ł́C�O�L�Q(1)�ŏڏq�����悤�ɁC���̐������Ȃ������������F�߂��Ă������̂ɍ̗p���ꂽ���Ƃ͖��炩�ł���B�����āC���Ɩ����ӂ̖@���́C�䂪���݂̂��̗p�������ق̖@���ł͂Ȃ��̂ł���B���Ȃ킿�C�č��ł́C�P�X�S�U�N�̘A�M�s�@�s�א������@�����肳���܂ł́C���Ɩ����ӂ̖@�����̗p����Ă���(�A���h���u�e���̍��ƕ⏞�@�̗��j�I�W�J�Ɠ����\�A�����J�v���ƕ⏞�@�̌nI(�P�R�T�y�[�W)�C�p���ł��C�P�X�S�V�N�̍����i�ǖ@�����肳���܂œ��l�ł���(�Í�c���E���Ɣ����@�S�V�y�[�W)�C�h�C�c�y�уt�����X�ł��C�P�X���I�㔼�ɁC���ƐӔC��ʂɖ��@��K�p���悤�Ƃ������݂����������C���ǁC���̓������ے肳��錋�ʂƂȂ���(�F�ꍎ��E���ƐӔC�@�̕��͂S�P�P�y�[�W)�̂ł����āC�����̊e���̗��@��̐����́C���Ɩ����ӂ̖@���ɂ����̂ł������B
�@���������āC���{�����@��O��Ƃ��錻�݂̉��l�ς��猩�āC���Ɩ����ӂ̖@���̍�������ے肷�邱�Ƃ͑S�������̂Ȃ����Ƃł���B
�@���{�����@�P�V���Ɋ�Â������@�����肳�ꂽ���C�����@����̍ۂ̗��@�҂̉��l���f���C�����@�̑k�y�I�K�p��ے肷��ׂ������@�����U���ɋK�肵���悤�ɁC���@�{�s�O�̍s�ׂɂ��Ă͓��@�{�s��ɂ����Ă��C���͔����ӔC��Ȃ����ƂƂ���̂����{�����@�̉��ɂ����Ă������ł���Ƃ������̂ł����āC����͍����I�������ȗ��@���f�ł���B
�@���������āC�u�����_�ɂ����ẮC�u���Ɩ����ӂ̖@���v�ɐ������Ȃ�����������������������Ɓv�������āC�����@�{�s�O�̖��@�̉��߂Ƃ��āC���̌��͓I��p�ɖ��@�V�P�T����K�p�ł���Ƃ���̂͌��Ƃ���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
�@�Ȃ��C�O�L�̂Ƃ���C�ō��ٔ��������P�T�N�S���P�W�������́C�@���s�ׂ����ꂽ���_�ł͌����ɔ����Ȃ��������C���̌�Ɍ������ω������ꍇ�̖@���s�ׂ̗L�����ɂ��āC�u�@���s�ׂ������ɔ����邱�Ƃ�ړI�Ƃ�����̂ł���Ƃ��Ė����ɂȂ邩�ǂ����́C�@���s�ׂ����ꂽ���_�̌����ɏƂ炵�Ĕ��f���ׂ��ł���B�������C������̖@���s�ׂ̌��͂́C���ʂ̋K�肪�Ȃ�����C�s�ד����̖@�߂ɏƂ炵�Ĕ��肷�ׂ����̂ł��邪(�ō��ُ��a�Q�X�N(�N)��Q�Q�R�����R�T�N�S���P�W����@�쌈��E���W�P�S���U���X�O�T��)�C���̗��́C�������@���s�ׂ̌�ɕω������ꍇ�ɂ����Ă����l�ɍl����ׂ��ł���C�@���s�ׂ̌�̌o�܂ɂ���Č����̓��e���ω������ꍇ�ł����Ă��C�s���ɗL���ł������@���s�ׂ������ɂȂ�����C�����ł������@���s�ׂ��L���ɂȂ����肷�邱�Ƃ͑����ł͂Ȃ�����ł���B�v�Ɣ������Ă���Ƃ���ł����āC���̗��́C���Ɩ����ӂ̖@���ɂ��Ó�����̂ł���C�������@���ɂ����č������̂��������Ɩ����ӂ̖@������{�����@��O��Ƃ��錻�݂̉��l�ςɂ���Ĕے肵�āC���ʂ̋K�肪�Ȃ��̂ɁC�����ӂł������s�ׂɂ��C�����ӔC��F�߂邱�Ƃ͖@�̉��߂Ƃ��ċ�����Ȃ��Ƃ����ׂ��ł���B
�@
�@�J�@�ō��ُ��a�Q�T�N�����ɔ����邱��
�@
�@(�)�@�����n�قR�������́C�u���Ɣ����@�{�s�O�ɂ�����C�������̌����͂̍s�g�̈�@�𗝗R�Ƃ��鍑�̐ӔC�ɂ��Ă��C���@�V�P�T���̋K���ɂ䂾�˂��Ă������̂Ɖ�����]�n���Ȃ��Ƃ͂����Ȃ��B�v�Ɣ������邪�C�����锻�f�́C�ō��ُ��a�Q�T�N�����ɔ����邾���Ȃ��C���̌�̍ٔ���ɂ���������قȔ��f�ł���B
�@���Ȃ킿�C�ō��ُ��a�Q�T�N�����́C�����@�{�s�O�ɐ������x�@���̖h��@�Ɋ�Â��Ɖ��j��̕s�@�𗝗R�ɒ�N�������Ɣ������������ɂ��C�u�����͂̍s�g�Ɋւ��Ă͓��R�ɂ͖��@�̓K�p�̂Ȃ����ƌ������̐�������Ƃ���ł����āC�����@���ɂ����ẮC��ʓI�̔����ӔC��F�߂��@�����Ȃ������̂ł��邩��C�{���j��s�ׂɂ��č��������ӔC�����R�͂Ȃ��B�v�Ƃ��C�u�_�|�́C���Ɣ����@�����́u���̖@���{�s�O�̍s�ׂɊ���Q�ɂ��ẮC�Ȃ��]�O�̗�ɂ��B�v�Ƃ̋K��ɂ��āC�]�O�Ƃ����ǂ��������̕s�@�s�ׂɑ��C���������ӔC���ׂ����̂ł����āC�V���@�͂����@���������ɉ߂��Ȃ��Ǝ咣����̂ł��邪�C���Ɣ����@�{�s�ȑO�ɂ����ẮC��ʓI�ɔ����ӔC��F�߂�@�ߏ�̍����̂Ȃ��������Ƃ͑O�q�̂Ƃ���ł����āC��R�@���������̈�@�Ȍ����͂̍s�g�Ɋւ��āC��ɔ����ӔC�̂Ȃ����Ƃ����ė����̂ł���B(��������ɘ_�|�̂悤�Ȋw�����������Ƃ��Ă��C�����ɂ͂��̂悤�Ȋw���͍s���Ȃ������̂ł���B)�{���Ɖ��̔j��͓��{�����@�{�s�ȑO�ɍs��ꂽ���̂ł����āC���Ɣ����@�̓K�p����闝�R���Ȃ��C�����������@�����ɂ���ď]�O�̗�ɂ�荑�ɔ����ӔC�Ȃ��Ƃ��C�㍐�l�̐�����e��Ȃ������͎̂����ł����āC�_�|�ɗ��R�͂Ȃ��B�v�Ɣ������Ă���B
�@���̔�����������炩�Ȃ悤�ɁC�������́C�����@�����U���́u�]�O�̗�v�Ƃ́C�����͂̍s�g�Ɋւ��Ă͖��@�̓K�p���Ȃ��C���̑����̔����ӔC��F�߂�K�肪�Ȃ��������Ƃ���C�����͂̍s�g�ɂ��Ă͍��ɂ͔����ӔC���Ȃ����ƁC���Ȃ킿���Ɩ����ӂ̖@�����Ӗ�����Ƃ��C���̖@���ɏ]���Ĕ��f�����������������ł���Ɣ������Ă���̂ł����āC�����n�قR�������́C�ō��ُ��a�Q�T�N�����ɖ��炩�ɔ�����B
�@
�@(�)�@�����N�����o�g�҂��C���Ƒ������@�̉��ɂ����āC���n�ɋ����A�s���ꋭ���J��������ꂽ�Ƃ��đ��Q���������߂��i�ׂɂ����āC�����n���ٔ��������W�N�P�P���Q�Q������(�ז�����S�S���S���T�O�V�y�[�W)�́C�u�������@���ɂ����ẮC�s���ٔ����ɂ����Ă��C�u���Q�v���m�i�ׁv���ł��Ȃ����̂Ƃ���(�s���ٔ��@�P�U��)�C���Ƃ̔����ӔC���m�肷�ׂ������@�߂��Ȃ������̂ł��邩��C���Ɣ����@�����U���́u���̖@���{�s�O�̍s�ׂɊ�Â����Q�ɂ��ẮC�Ȃ��]�O�̗�ɂ��B�v�Ƃ̌o�ߋK��ɏƂ点�C�����_�ɂ�������߂Ƃ��Ă��C�{���e�s�ד����ɂ����ẮC���@�V�O�X���̋K��ɂ���āC�������̌��͓I��p�ɂ�鑹�Q�ɂ��Ď��l�ɑ��đ��Q�����ӔC�S����Ƃ̉��߂��̗p���邱�Ƃ͂ł��Ȃ����̂Ƃ����ق��Ȃ�(���Ɣ����@�̉E�����́C���@�{�s�O�̍s�ׂɂ��Ă����鋌�@��`���̗p�������̂ɂ������C���̋K�肪�C���@�V�O�X��K�p���̍����ƂȂ���̂ł͂Ȃ��B)�B�v�Ɣ��������Ƃ���C���̍T�i�R�ł��铌�������ٔ��������P�S�N�R���Q�W��(����R�O����)��������ێ����C����ɍō��ٔ��������P�T�N�R���Q�W����@�쌈����C�㍐���p�y�я㍐�s�̌���������B
�@���̂悤���@�����U���́u�]�O�̗�v�����Ɩ����ӂ̖@�����w�����Ƃ́C�ō��ُ��a�Q�T�N�����ȗ��C������т��Ă���(�����n���ٔ������a�T�X�N�P�O���R�O�������E�����P�P�R�V���Q�X�y�[�W�C���������ٔ������a�U�R�N�R���Q�S�������E�����P�Q�U�W���P�T�y�[�W�C���������ٔ��������P�Q�N�P�Q���U�������E�����P�V�S�S���S�W�y�[�W�C���������ٔ��������P�R�N�Q���W������(����Q�R����)�C���ō��ٔ��������P�R�N�P�O���P�U������(�㍐���p�y�я㍐�s����(����S�R����))�C�����n���ٔ��������P�S�N�U���Q�W������(����S�S����)��)�B
�@
�@�L�@�����n�قR�������̗��R���ɂ�����@��P�P���̓K�p��ے肵�����R�Ɩ��������邱��
�@
�@(�)�@�����n�قR�������́C���������u���������ɂ����ĉƑ��Ƌ��ɕ����Ȑ����𑗂��Ă��������炪�C���a�P�V�N�P�P���Q�V���̊t�c����Ɋ�Â��s�����o�ɂ��C���{�R���邢�͓��{���{�̎x�z���ɂ����������R�̕��m(�ȉ��u���{�R���v�Ƃ����B)�ɂ���āC����̈ӎv�ɔ����Ĉ���I�������I�ɓ��{�ɘA�s����C�퍐��Ƃ̊e���Ə��ŋ����I�ɗȘJ���������ʼnߍ��ȘJ���ɏ]��������ꂽ�Ǝ咣���āC�퍐���ɑ��đ��Q���������߂���̂ł����āC�l�����ɑ��Č������̈�@�s�ׂɂ���Ĕ�������Q�̔��������߂�i��(�ȉ��u���Ɣ����i�ׁv�Ƃ����B)�ł���B�v�ƈʒu�Â�����ŁC�ȉ��̗��R�ɂ��C���ێ��@�̓K�p�ΏۂƂȂ�Ȃ��C���Ȃ킿�C�@��P�P���̓K�p���Ȃ��|�������Ă���(�������R�P�Ȃ����R�S�y�[�W)�B
�@
�@�@�@�@���Ɣ����������̑��ۂɊւ���@���W�́C�����͂̍s�g�̓K�ۂ����f�̑ΏۂƂȂ�Ƃ����Ӗ��ŁC���@�I�ȐF�ʂ������Ƃ͔ے�ł��Ȃ��B���Ȃ킿�C�����͂̍s�g�̓K�ۂɊւ��锻�f���C���̌�̍��̍s�����C���@���̍s�g�C����ɂ́C���������ɑ��鍑�̋@�ւ̌����s�g�̂�����ɂ��d��ȉe����^������̂ł����āC���Y���Ƃ̌��v�Ɩ��ڂȊW��L������@�I�ȑ��ʂ������̂ł��邱�Ƃ͖��炩�Ƃ����ׂ��ł���B��������Ȃ�C���Ɣ����i�ׂ̐R���ɂ����āC���̓K�ۂ����Ƃ���Ă�������͂̍s�g�ɂ��āC���Y���Ƃ̖@���Ƃ͈قȂ�K�@�v�����߂鑼���̖@���ɂ���āC���̈�@���̗L�������f�����悤�Ȃ��Ƃ́C���Y���Ƃ̌��v�ɔ�������̂Ƃ����悤(���R�Q�y�[�W)�B
�@
�@�@�A�@�e���̍��Ɣ����Ɋւ���@�������Ă����炩�Ȃ悤�ɁC�e�����C���Ɣ������x�̑��ہC�ӔC�͈̔͂���x�ɂ��C�����S�ʂɂ킽�鑍���I�������f�̉��ɁC�l�X�ȗ��@������̗p���Ă��邱�Ƃ́C���Ɣ����������̑��ۂɊւ���@���W���C���Ƃ̍����S�ʂɂ킽�鑍���I�������f�Ɩ��ڂȊW��L������@�I�F�ʂ����@���W�ł��邱�Ƃ��������̂Ƃ�����B���ɁC�䂪���̍��Ɣ����@�ɂ����Ă��C�퍐���̌��v���l�����������I���f�̉��ɁC���@�̗̈�Ƃ͈قȂ���ʂ̖@���̗p����Ă���̂ł���B���Ȃ킿�C���Ɣ����@�́C�������ɂ������͂̍s�g���ޏk�����Ȃ��悤�Ɍ������l�ɑ������ł���ꍇ�����肵(���@�P���Q��)�C�O���l����Q�҂ł���ꍇ�ɂ́C���݂̕ۏ̂���Ƃ��Ɍ����Ĕ�������(���@�U��)���̂Ƃ��Ă���C�����̋K��͍��Ɣ����̖�肪���Ƃ̌��v�ƒ��ږ��͖��ڂɊW���Ă��邱�Ƃ������Ă�����̂Ƃ�����(���R�Q�C�R�R�y�[�W)�B
�@
�@�@�B�@�{���ɂ����ẮC�ʓI�Ȍ������̌����͂̍s�g�̓K�ۂ����Ƃ���Ă���̂ł͂Ȃ��C�퍐�������v��Nj�����ړI�̉��ō��Ǝ匠�̍s�g�Ȃ������I�Ƃ��čs������L�s�ׂ�̂̐������̑��ۂɂ��Ă̔��f�����߂��Ă���B���̔��f�����Ƃ̎匠�s�g�̐������ɂ������_�ŁC�퍐���̌��v�ɒ��ړI�ȊW��L���C�ɂ߂ċ������@�I�F�ʂ������̂Ƃ�����B�������C���Ƃ̐����I���f�̉��ɁC�L�͂ɍs��ꂽ�펞���ɂ�������{�R���̈�@�s�ׂ𗝗R�Ƃ��Ĕ퍐���ɑ��Q�����`���S�����邩�ۂ��Ƃ������f���C�S�����̕��S�̉��ňێ�����Ă���퍐���̍��ƍ����ɑ��ďd��ȉe����^�����ɂ͂����Ȃ����Ƃ����炩�ł���C���̓_�ɂ����Ă��C�{���ɂ����Ĕ��f�̑ΏۂƂȂ�@���W�́C�퍐���̌��v�Ɩ��ڂȊW��L���C���@�I�F�ʂ������̂ł���B.�{���̂��Ƃ��C���Ƃ̎匠�s�g�̐����������f�̑ΏۂƂȂ�C���̌��ʂ��퍐���̍����ɏd��ȉe����^����@���W�́C���ێ��@�̋K���ɂ䂾�˂�ׂ����@�I�@���W�ł͂Ȃ��C���@�I�@���W�ɓ�����Ɖ�������ق��͂Ȃ�(���R�R�C�R�S�y�[�W)�B
�@
�@(�)�@���̂悤�ɁC�����n�قR�������́C�{���̍��Ɣ����������̑��ۂɊւ���@���W�����ێ��@�̑ΏۂƂȂ�@���W�ɓ����邩�ۂ��Ƃ������ɂ��āC���Ƃ̌��v�Ɩ��ڂɊW���C�ɂ߂ċ������@�I�F�ʂ������Ƃ��l�����āC���@�I�@���W�ł͂Ȃ��C���@�I�@���W�ł���Ɣ������Ă���C���̔����́C�ɂ߂Đ����Ȕ��f�ł���B
�@�Ƃ��낪�C�����n�قR�������́C�������̌����͂̍s�g�̈�@�Ɨ��R�Ƃ��鍑�̐ӔC�ɂ��āC���@�̓K�p�����邩�Ƃ������ɂ��ẮC���@�V�P�T���̋K���ɂ䂾�˂��Ă����Ɖ�����]�n������Ƃ�(�������R�X�y�[�W)�C���Ɣ����l�����̑��ۂɊւ���@���W����ʎ��@�ł��閯�@�̋K���ɂ䂾�˂�]�n������|�������Ă���B
�@����͍��ێ��@�̓K�p�̗L���̖��ł���C�����͖��@�̓K�p�̗L���̖��ł����āC�_�_���قȂ��Ă���Ƃ͂����C����������Ɣ����������̑��ۂɊւ���@���W���C���@�I�@���W�ł��邩�̖��ł��邩��C���҂̌��_���قɂ���̂́C�����Ƃ����ׂ��ł���B
�@
�@(�)�@�ȏ�C�q�ׂ��悤�ɁC�����n�قR�������́C���ێ��@�̖��Ƃ��ẮC���Ɣ����������̑��ۂ̖��́C���Q�̌����ȕ��S�݂̂ł͑�����ꂸ�C���v�Ɩ��ڂɊW���C���@�I�F�ʂ������Ƃ��āC���̐��������@�I�@���W�ł͂Ȃ����@�I�@���W�ł���ƓI�m�ɔc�����Ă����Ȃ���C�����@���W�ɓK�p���鏀���@�Ƃ��āC���Q�̌����̕��S�݂̂𗝔O�Ƃ��鎄�@�I�@���W���K�����Ă��閯�@�V�P�T����K�p���悤�Ƃ�����̂ł����āC���̔��f�ɂ͖���������ƌ��킴��Ȃ��B
�@
�@�N�@���_
�@�ȏ�ڏq�����悤�ɁC�����n�قR�������́C���Ɩ����ӂ̖@���̍������𐳊m�ɗ������Ă��炸�C���̔��f�́C�����@�����U���Ɉᔽ���C�ō��ُ��a�Q�T�N�����ȗ��̉䂪���̍ٔ���ɂ������Ɉᔽ������̂ƌ��킴��Ȃ��B
�@

��Q�@���ˊ��Ԃ̓K�p�Ɋւ���T�i�l��̎咣�ɂ���
�@
�@�T�i�l��́C���@�V�Q�S����i�̓K�p�ɂ��C���Q�����������̏��ł�F�߂邱�Ƃ͒��������`�E�����ɔ�����ȂǂƎ咣����(�T�i�l���P�������ʂT�V�Ȃ����V�S�y�[�W)�B
�@���̂����C���@�V�Q�S����i�̊��Ԃ̋N�Z�_���s�@�s�ׂ̎��ł��邱�Ƃɂ��ẮC���R�퍐��������(�V)�S�X�C�T�O�y�[�W�ŏڏq�����Ƃ���ł��邩��C��������p���邱�ƂƂ��C�ȉ��C���̗]�̓_�Ɋւ���T�i�l��̎咣�������ł��邱�Ƃ��q�ׂ�B
�@
�@�P�@���@�V�Q�S����i�̖@�I���i�ɂ���
�@
�@(1)�T�i�l��̎咣
�@�T�i�l��́C���@�V�Q�S����i�̂Q�O�N�̊��Ԃ̖@�I���i�ɂ��āC�������Ԃ��߂����̂Ɖ����ׂ��|�咣����(�T�i�l���P�������ʂT�V�y�[�W)�B
�@
�@(2)��T�i�l�̔��_
�@�������C�ō��ٔ����������N�P�Q���Q�P����ꏬ�@�씻��(���W�S�R���P�Q���Q�Q�O�X�y�[�W�C�ȉ��u�ō��ٕ������N�����v�Ƃ����B)�́C�u���@�V�Q�S����i�̋K��́C�s�@�s�ׂɂ���Ĕ����������Q�����������̏��ˊ��Ԃ��߂����̂Ɖ�����̂������ł���B�������C���������̑O�i�łR�N�̒Z���̎����ɂ��ċK�肵�C�X�ɓ�����i�łQ�O�N�̒����̎������K�肵�Ă���Ɖ����邱�Ƃ́C�s�@�s�ׂ��߂���@���W�̑��₩�Ȋm����Ӑ}���铯���̋K��̎�|�ɉ��킸�C�ނ��듯��O�i�̂R�N�̎����͑��Q�y�щ��Q�҂̔F���Ƃ�����Q�ґ��̎�ϓI�Ȏ���ɂ���Ă��̊��������E����邪�C������i�̂Q�O�N�̊��Ԃ͔�Q�ґ��̔F���̂�������킸���̎��̌o�߂ɂ���Ė@���W���m�肳���邽�ߐ������̑�����������I�ɒ�߂����̂Ɖ�����̂������ł��邩��ł���B�v�Ɣ������āC���@�V�Q�S����i�̖@�I���i�����ˊ���ł��邱�Ƃ����C�܂��C�ō��ٔ��������P�O�N�U���P�Q����@�씻��(���W�T�Q���S���P�O�W�V�y�[�W�C�ȉ��u�ō��ٕ����P�O�N�����v�Ƃ����B)���C�ō��ٕ������N���������p���āC�u���@�V�Q�S����i�̋K��́C�s�@�s�ׂɂ�鑹�Q�����������̏��ˊ��Ԃ��߂����̂ł���C�s�@�s�ׂɂ�鑹�Q���������߂�i�������ˊ��Ԃ̌o�ߌ�ɒ�N���ꂽ�ꍇ�ɂ́C�ٔ����́C�����҂���̎咣���Ȃ��Ă��C���ˊ��Ԃ̌o�߂ɂ��E�����������ł������̂Ɣ��f���ׂ��ł��邩��C���ˊ��Ԃ̎咣���M�`���ᔽ���͌������p�ł���Ƃ����咣�́A�咣���̎����ł���Ɖ����ׂ��ł���(�ō��ُ��a�T�X�N�P�˂P��P�S�V�V���������N�P�Q���Q�P����ꏬ�@�씻���E���W�S�R���P�Q���Q�Q�O�X�ŎQ��)�v�Ɣ������Ă���Ƃ���ł���B
�@���̂悤�ɍō��ٔ����́C��т��āC���@�V�Q�S����i�̖@�I���i�����ˊ��Ԃł���Ɣ������C�ō��ٕ����P�O�N�����̒���������ɂ����Ă��C�����錩���́u���ᗝ�_�Ƃ��Ă͊m���������́v(�t���ʗǁE�ō��ٔ��������������ѕ����P�O�N�x(��)�T�V�Q�y�[�W)�Ƃ��Ă���B
�@���������āC������i�̖@�I���i�����Ŏ����Ɖ����ׂ��ł���|�̍T�i�l���.�咣�͎����ł���B
�@
�@�Q�@���ˊ��Ԃ̓K�p�����ɂ���
�@
�@(1)�T�i�l��̎咣
�@�T�i�l��́C���ɁC���@�V�Q�S����i�̖@�I���i�ɂ��C���ˊ��Ԃł���Ƃ��Ă��C���̓K�p�����������`�C�����ɔ����C�𗝂ɂ��Ƃ�Ƃ��́C������i�̋K��͓K�p�����ׂ��łȂ��|�咣����(�T�i�l���P�������ʂU�R�Ȃ����V�S�y�[�W)�B
�@
�@(2)��T�i�l�̔��_
�@���@�V�Q�S����i�́C�s�@�s�ׂ��߂�.�錠���W���s�m��̏�Ԃɂ���'���Ƃɂ͏d��Ȗ�肪����C��Q�҂ɑ��ĉy�I���₩�ɋ~�ς����߂����C�@���W�𑁊��Ɋm�肳���悤�Ƃ��邱�Ƃ��@�̈Ӑ}����Ƃ���ł���(�͖�M�v�E�ō��ٔ��������������ѕ������N�x�U�P�Q�y�[�W�Q��)�B
�@�T�i�l��́C����̎咣�̍����Ƃ��āC�ō��ٕ����P�O�N�������̍ٔ���������C�ō��ٕ����P�O�N�����́C���@�V�Q�S����i�����ˊ���ł���Ƃ��Ȃ�����C���`�E�����̊ϓ_����C���̓K�p�𐧌����邱�Ƃ�F�߂Ă���C���̌�̉����R��������l�̗�����̂�|�咣����(���������ʂU�X�Ȃ����V�S�y�[�W)�B
�@�������C�ȉ��ɏq�ׂ�悤�ɁC�T�i�l��̎咣�́C�����ł���B
�@
�@�A�@�ō��ٕ����P�O�N�����ɂ���
�@
�@(�)�@�T�i�l��́C�ō��ٕ����P�O�N�������C���`�E�����E�𗝂ɂ���āC���@�V�Q�S����i�̓K�p����ʓI�ɐ����������̂悤�Ȏ咣�����邪�C�E�咣�́C�������𐳉����Ă��Ȃ��B
�@���Ȃ킿�C�ō��ٕ����PO�N�����́C���@�V�Q�S����i�����ˊ��ԂƔ��������ō��ٕ������N���������p���āC�u���@�V�Q�S����i�̋K��́C�s�@�s�ׂɂ�鑹�Q�����������̏��ˊ��Ԃ��߂����̂ł���C�s�@�s�ׂɂ�鑹�Q���������߂�i�������ˊ��Ԃ̌o�ߌ�ɒ�N���ꂽ�ꍇ�ɂ́C�ٔ����́C�����҂���̎咣���Ȃ��Ă��C���ˊ���̌o�߂ɂ��E�����������ł������̂Ɣ��f���ׂ��ł��邩��C���ˊ���̎咣���M�`���ᔽ���͌������p�ł���Ƃ����咣�́C�咣���̎����ł���Ɖ����ׂ��ł���v�Ɣ������C�����̒�~�Ɋւ��閯�@�P�T�W�����w�E������C�u�s�@�s�ׂ̔�Q�҂��s�@�s�ׂ̎�����Q�O�N���o�߂���O�U�ӌ����ɂ����ĐS�_�r���̏틵�ɂ���̂Ɍ㌩�l��L���Ȃ��ꍇ�ɂ́v�C�u���̐S�_�r���̏틵�����Y�s�@�s�ׂɋN������ꍇ�ł����Ă��C��Q�҂́C���悻�����s�g���s�\�ł���̂ɁC�P�ɂQ�O�N���o�߂����Ƃ������Ƃ݂̂������Ĉ�̌����s�g��������Ȃ����ƂƂȂ锽�ʁC�S�_�r���̌�����^�������Q�҂́C�Q�O�N�̌o�߂ɂ���đ��Q�����`����Ƃ�錋�ʂƂȂ�C���������`�E�����̗��O�ɔ�������̂Ƃ��킴��Ȃ��B��������ƁC���Ȃ��Ƃ��E�̂悤�ȏꍇ�ɂ����ẮC���Y��Q�҂�ی삷��K�v�����邱�Ƃ́C�O�L�����̏ꍇ�Ɠ��l�ł���C���̌��x�Ŗ��@�V�Q�S����i�̌��ʂ𐧌����邱�Ƃ͏𗝂ɂ����Ȃ��Ƃ����ׂ��ł���B�v�Ɣ��������B���̔����́C�u�s�@�s�ׂ̎�����Q�O�N���o�߂���O�U�ӌ����ɂ����ĉE�s�@�s�ׂ������Ƃ��ĐS�_�r���̏틵�ɂ���̂ɖ@��㗝�l��L���Ȃ������ꍇ�ɂ����āC���̌㓖�Y��Q�҂��֎��Y�鍐���C�㌩�l�ɏA�E�����҂����̎�����U�ӌ����ɉE���Q�������������s�g�����ȂǓ��i�̎������Ƃ��v�ɂƂ����ɂ߂Č��肳�ꂽ�v���̉��ŁC���̌��ʂɂ����Ă��C�����̒�~�Ɠ��l�̏���̊��Ԃ�������Ώ��ˊ��Ԃ̌o�߂��~������Ƃ������x�ɂ����ė�O��F�߂����̂ł���C���@�P�T�W���Ƃ��������̒�~�Ɋւ�������̏����̖@�ӂ����p���ċɂ߂Č���I�ɗ�O��F�߂����̂ł���B
�@���̂��Ƃ́C�ō��ْ������̔������ł��C�u�{�����̎˒��́C�ɂ߂ċ������̂Ǝv����B���@�V�Q�S����i�̓K�p�̌��ʂ�ے肷��ꍇ�Ƃ��ẮC���ˊ��ԓ��Ɍ������s�g���Ȃ��������ƂF���邱�Ƃ��{���̎��ĂƓ����x�ɒ��������`�E�����ɔ����鎖������C�����̒�~�����̍����ƂȂ���̂����邱�Ƃ��K�v�ł��낤�B�͍��ٔ����̈ӌ��̂悤�ɁC���ˊ��Ԑ��ɗ����Ȃ���C���L����O��F�߂邱�Ƃ́C�������N�����ɒ�G���邱�ƂɂȂ�C��@��ɂ����锻��ύX���K�v�ƂȂ�ł��낤�B�v(�t���ʗǁE�O�f�ō��ٔ��������������ѕ����P�O�N�x(��)�T�V�U�y�тT�V�V�y�[�W)�Əq�ׂ��Ă���Ƃ���ł���B
�@���������āC�ō��ٕ����P�O�N�������C��ʓI�ɁC���ˊ��Ԃ̓K�p���u���������`�E�����̗��O�ɔ�����v�ꍇ�ɂ́C���̓K�p��r���ł���Ƃ������̂Ƃ���T�i�l��̎咣�́C���炩�ɓ������̎˒�����������̂Ƃ���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
�@���@�V�Q�S����i�̏��ˊ���̓K�p�����������̂́C���̖@���ɍ��������߂邱�Ƃ��ł���ɂ߂ė�O�I�ȏꍇ�Ɍ�����Ƃ����̂��C�������̐����ȗ����ł���C�ō��ق̊m����������ł���Ƃ���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
�@
�@(�)�@�ō��ٕ����P�O�N�����ɏƂ炵�Ă��C�{�����C���ˊ���̓K�p�𐧌����ׂ���O�I�ȏꍇ�ɊY�����Ȃ����Ƃ͖��炩�ł���B
�@
a�@�{���́u���悻�����s�g���s�\�v�Ƃ͂����Ȃ��B
�@�T�i�l��́C�u�{���ې�̈�@�s�ׂɂ����āC�ɂ߂Č����ȓ����́C��T�i�l���C���ɂ����čې�̎������B�����C���ۓI�����I�ɓ��{�R�̍ې킪���m�̎����ƂȂ��Ă��錻�݂ɂ����Ă��C���̎�������F�߂Ă��Ȃ��Ƃ����_�ł���B�E�E�E�{���T�i�l��̌����s�s�g�́C��T�i�l���ꍑ�̌��͂������čT�i�l��̌����s�g��W�Q���C�s�\�ɂ��Ă������ʂȂ̂ł���B�v(�T�i�l���P�������ʂU�S�C�U�T�y�[�W)�ȂǂƂ��āC�u�P�X�X�T�N���܂ł́C��T�i�l�ɑ��鑹�Q�������������s�g���邱�Ƃ͎�����s�\�ł������B�v(���������ʂU�U�y�[�W)�Ǝ咣����ƂƂ��ɁC�u����ɁC�T�i�l�炪�{���i�ׂ��N���邽�߂ɂ́C�����Ɠ��{�ɁC������x�����C�㗝�l�ƂȂ��Ċ�������ٌ�m���K�v�s���ł������̂ł���C���̂悤�ȕٌ�y�̊��������{�ŋ�̉������̂͑�P���i�ׂ̍T�i�l��͂P�X�X�T�N�ȍ~�ł���C��Q���i�ׂ̍T�i�l��ɂƂ��Ă͑�P���i�ׂ��N�����P�X�V�N�W���ȍ~�ł���B�v(���U�U�y�[�W)�Ǝ咣����B
�@�������C���̂悤�ȍT�i�l��̎咣���C�ō��ٕ����P�O�N�����̔�������u�S�_�r���̏틵�ɂ���v���߁u���悻�����s�g���s�\�v�Ȏ���ɊY�����Ȃ����Ƃ͈ꌩ���Ė��炩�ł���B���Ȃ킿�C�T�i�l��̑O�L�咣�́C���ǂ̂Ƃ���C�i�ב㗝�l�̋��͂邱�Ƃ�����ł������C�܂��C�؋������̎��W���̑i�ג�N�̏���������Ȃ������Ƃ����ɂ����Ȃ��̂ł���B
�@���ɁC���̂悤�ȍT�i�l��̎咣���F�߂���Ƃ���Ȃ�C�T�i�l��ɂ����đi�ג�N�̏������ł����Ƃ��鎞�_��C�ӂɑI�����āC�u�����s�g���\�v�ɂȂ������_���Ƃ���咣���������ƂɂȂ�C�����s�g�����₩�ɂȂ���邱�Ƃ�ړI�Ƃ��Đ݂����C���̌��ʂ����I�ɔF�߂���͂��̏��ˊ��Ԃ̎�|�����v�p���邱�ƂɂȂ�͖̂��炩�ł���B
�@
�@b�@�܂��C�{���̏ꍇ�C�����̒�~���̂悤�ȏ��ˊ��Ԃ̓K�p�𐧌����鍪���ƂȂ���͉̂��瑶���Ȃ��B
�@���@�̎����̒�~�́C���������̎��ɓ������Č̏Ⴊ����C�����҂����f�s�ׂ����邱�Ƃ�����ȏꍇ�ɁC�����̊�����P�\���邱�Ƃɂ��C��~���R���I�����Ă�����̗P�\���Ԃ��o�āC����������������̂ł���(��ȞāE�V�����@�����S�V�S�y�[�W�Q��)�B
�@�����āC�ō��ٕ����P�O�N�����̎��ẮC���ˊ��Ԃ̌o�߂ɓ�����A�s�@�s�ׂ̔�Q�҂����Y�s�@�s�ׂ������Ƃ��ĐS�_�r���̏틵�ɂ���̂Ɍ㌩�l��L���Ȃ��Ƃ������Ăł���C���ɁC���Ŏ����̊��������Ƃ��ꂽ�Ȃ�C���@�P�T�W���̎����̒�~�̋K��ɂ��C�����ԏ��Ŏ����̊������W����ꂽ���ĂŁC�������C�S�_�r���̌�����^�����̂����Q�҂ł������Ƃ�������������B������ꍇ�ɁC���ˊ���̌o�߂ɂ���Č������ł̌��ʂ�F�߂�̂́C�����ɂ������҂ɍ��Ȍ��ʂƂȂ邩��C�����̒�~�Ɋւ��閯�@�P�T�W���������ɁC���̖@�ӂɏƂ炵�āC�ō��ٕ������N�����̗�O��F�߁C������(��Q��)���u�\�͎҃g�׃����n�@��㗝�l�J�A�E�V�^���������Z�ӌ����v�Ɍ���ꎞ�I�ɏ��ˊ��Ԃ��o�߂����Ƃ͂���Ȃ����ƂƂ������̂ł���B
�@����ɑ��C�{���ɂ����āC�T�i�l��́C�����̒�~�Ɋւ��閯�@�P�T�W���Ȃ������P�U�P���̋K��ɑ������錠���s�g��s�\�Ȃ�������Ȃ炵�߂鎖�R��S���咣�����C�ނ���C�����s�g�����悤�Ǝv�����ł��������s�g���邱�Ƃ��\�����Ƃ��������鎖��������āu�����s�g���s�\�v�ł������Ǝ咣���C�����u���������`�E�����ɔ�����v�ꍇ�ɂ́C���ˊ��Ԃ̓K�p����ʓI�ɐ������ׂ��|�咣����݂̂ŁC���ˊ��Ԃ̌o�߂��ے肳���ׂ����̊��Ԃ��咣����Ă��Ȃ��B
�@
�@(�)�@���̂悤�ȍT�i�l��̎咣�́C�����̒�~�̂悤�Ȃ��̖@�ӂ����p�ł��鐧�x�̑��݂���Ƃ��邱�ƂȂ��C�����u���������`�E�����̗��O�ɔ�����v�ꍇ�ɂ́C���ˊ���̐��x����ʓI�ɓK�p���ׂ��ł͂Ȃ��Ƃ����̂ł���C�K�p�𐧌����鍪���ɂ��Ă��C���͈̔͂ɂ��Ă��C�ō��ٕ����P�O�N�����̔�������Ƃ����傫����E���C���̌��ʁC�T�i�l��̎咣�ɂ��C�ɂ߂čL�͂�������ɏ��ˊ���̓K�p������������邱�ƂɂȂ�C�@�I���萫���d�����Ė��@�V�Q�S����i�̏��ˊ��Ԃ�݂����@�ӂɔ����邱�Ƃ͖��炩�ł���B
�@
�@�C�@�����n���ٔ��������P�R�N�V���P�Q�������ɂ���
�@
�@(�)�@�T�i�l��́C���@�V�Q�S����i�̓K�p�𐧌����������R����Ƃ��āC�܂��C�����n�ٕ����P�R�N�V���P�Q������(����^�C���Y�P�O�U�V���P�P�X�y�[�W�C�ȉ��u�����n�ٕ����P�R�N�����v�Ƃ����B)�Ɍ��y����(�T�i�l���P�������ʂV�Q�y�[�W)�B
�@���̔����́C����E��풆�ɒ�������������{�����ɋ����A�s����C�k�C�����̎��Ə�ŋ����J���ɏ]���������C���̋����J�����瓦���ׂ��I�풼�O�Ɏ��Əꂩ�瓦�����C���̌��P�R�N�Ԃɂ킽��k�C���̎R���Ő������Ă����Ƃ��钆���lX�̑����l�����ˊ��Ԃł���Q�O�N���o�߂��ē��{��(Y)��퍐�Ƃ��Ē�i�������Q�������������ɂ��C���ˊ��Ԃ̓K�p�Ɋւ��C�u���ˊ��Ԑ��x�̓K�p�̌��ʂ��C���������`�C�����̗��O�ɔ����C���̓K�p�𐧌����邱�Ƃ��𗝂ɂ����Ȃ��ƔF�߂���ꍇ�ɂ́C���ˊ��Ԃ̓K�p�𐧌����邱�Ƃ��ł���Ɖ����ׂ��ł���B�v�Ƃ�����ʓI���藧������ŁC�uY�ɑ��C���Ɛ��x�Ƃ��Ă̏��ˊ��Ԃ̐��x��K�p���āC���̐ӔC��Ƃꂳ���邱�Ƃ́CX�̔������Q�̏d�傳���l������ƁC���`�����̗��O�ɒ����������Ă���ƌ��킴��Ȃ����C�܂��C���̂悤�ȏd��Ȕ�Q������X�ɑ��C���ƂƂ��đ��Q�̔����ɉ����邱�Ƃ́C�𗝂ɂ����Ȃ��Ƃ����ׂ��ł���B����āC�{�����Q�����������̍s�g�ɑ��閯�@�V�Q�S����i�̏��ˊ��Ԃ̓K�p�͂���𐧌�����̂������ł���B�v�Ɣ��������B
�@
�@(�)�@�������C�����n�ٕ����P�R�N�����́C�ō��ٕ����P�O�N�������u���������`�E�����̗��O�ɔ�����v�ꍇ�ɂ́C���ˊ��Ԃ̐��x��K�p���ׂ��ł͂Ȃ��Ƃ̈�ʖ@�������������̂Ƃ̗����̂��ƂɁC��������̂܂ܓ��Y���Ăɓ��Ă͂߁C���������`�E�����̗��O�ɔ�������̂Ƃ��āC���ˊ��Ԃ̓K�p��r�����Ă��邪�C���̂悤�ȗ����͍ō��ٕ����P�O�N�����𐳉�������̂ł͂Ȃ��C�ނ��듯�����̎�|�E�˒�����������E������̂ł���B
�@���Ȃ킿�C�O�L�̂Ƃ���C�ō��ٕ����P�O�N�����́C�u�S�_�r���̏틵�����Y�s�@�s�ׂɋN������ꍇ�ł����Ă��C��Q�҂́C���悻�����s�g���s�\�ł���̂ɁC�P�ɂQ�O�N���o�߂����Ƃ������Ƃ݂̂������Ĉ�̌����s�g��������Ȃ����ƂƂȂ锽�ʁC�S�_�r���̌�����^�������Q�҂́C�Q�O�N�̌o�߂ɂ���đ��Q�����`����Ƃ�錋�ʂƂȁv�邱�Ƃ́C���������`�E�����̗��O�ɔ�����Ƃ��Ă��邪�C����́C�O���܂Ŗ��@�P�T�W���̖@�ӂ����ˊ��Ԑ��x�ɂ��������ނ��߂̗��R�ɂ������C�����ƂȂ鑼�̖@�����Ȃ��̂ɁC��ʓI�ɒ��������`�E�����̗��O�ɔ�����ꍇ�ɂ͏��ˊ��Ԃ̓K�p��r���ł���Ƃ������̂łȂ����Ƃ͖��炩�ł���B
�@���������āC�ō��ٕ����P�O�N�������C��ʓI�ɁC���ˊ��Ԃ̓K�p���u���������`�E�����̗��O�ɔ�����v�ꍇ�ɂ́C���̓K�p��r���ł���Ƃ������̂ƍl���邱�Ƃ́C���炩�ɔ���̎˒�����������̂Ƃ���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
�@�܂��C�ō��ٕ����P�O�N�����̎���ł́C�S�_�r���̏틵�����Y�s�@�s�ׂɋN������ق��́C���ڍ����̍s�ׂ����ɂ���Ă���킯�ł͂Ȃ��C�ނ���C���Y�s�@�s�ׂɋN������S�_�r���̏틵�ɂ���āC�Q�O�N�ȓ��ɑ��Q������������N���邱�Ƃ��ł��Ȃ����Ԃ������炳�ꂽ���Ƃ��u���������`�E�����̗��O�ɔ�����v�Ƃ������̂ł���B����ɑ��āC�����n�ٕ����P�R�N�����ł́C���{���̌�������X�ɑ��čs������A�̍s�ׂ������ɁC���̂悤�ȏꍇ�ɏ��ˊ��Ԃ�K�p���邱�Ƃ́u���������`�E�����̗��O�ɔ�����v�Ƃ��Ă��邪�C���Ȃ��Ƃ��������̍s�ׂɂ����X�ɂ�鑹�Q���������̒�N������Ȃ炵�߂�����(���@�P�T�W���̖@�ӂ��y�ڂ��ׂ�����)�͈�ؔF�肳��Ă��Ȃ��B
�@�����āC�������́C���ˊ��Ԃ̓K�p�𐧌����鎖��Ƃ��āCX�̂P�R�N�Ԃ̂킽�铦���́CY�̍s���������A�s�C�����J���ɗR�����CY�͂���Ɋւ��鎑�������Ē�������s��Ȃ������Ƃ����s�@�s�ׂ̈�������X�̔������Q�̏d�傳���w�E���Ă���B�������C���̂悤�Ȏ���́C�����������@�P�T�W���̖@�ӂ��y�ڂ��ׂ�����Ƃ����Ȃ��B�܂��C�����̎���́C�]���C�M�`���ᔽ���邢�͌������p�ɂ�鏜�ˊ��Ԃ̓K�p�𐧌����鎖��Ƃ��Ď咣����Ă������̂ł���C���������g���C�u�����P�O�N�����́C���ˊ��Ԃ̓K�p���M�`���ᔽ���邢�͌������p�ł���Ƃ����咣�́C�咣���̎����Ƃ��Ă��邪�C����͏��ˊ��ԂƉ�����ȏ㓖�R�̌��_�ł���ƍl���v����Ƃ��C���ˊ��Ԃ̓K�p�𐧌����鎖��ɂȂ�Ȃ��Ɣ�����������ł���B��������ƁC���������f���鎖��ɂ���āC�u���������`�E�����̗��O�ɔ�����v�Ƃ��邱�Ƃ́C���炩�ɍō��ٕ����PO�N�����ɔ�������̂Ƃ���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
�@
�@(�)�@�����n�ٕ����P�R�N�����́C�����I�ɂ́C��Q�̐r�傳�Ȃǂ𗝗R�Ƃ��ď��ˊ��Ԃ̓K�p��ے肵�����̂ɑ��Ȃ�Ȃ����C�ō��ٕ����P�O�N�����́C���̂悤�Ȕ�Q�̐r�傳�𗝗R�Ƃ��ď��ˊ��Ԃ̓K�p��ے肷����̂ł͂Ȃ��B
�@���̓_�ɂ��āC�������ٕ����P�Q�N�P�Q���U�������E�����P�V�S�S���S�W�y�[�W���C�u�E����(���p�Ғ��E�ō��ٕ����P�O�N����)�́C�w�s�@�s�ׂ̔�Q�҂��s�@�s�ׂ̎�����Q�O�N���o�߂���O�U�ӌ����ɂ����ĉE�s�@�s�ׂ������Ƃ��ĐS�_�r���̏틵�ɂ���̂ɖ@��㗝�l��L���Ȃ������ꍇ�x�Ƃ�������߂Č��肳�ꂽ�����W�̉��ŁC���@�P�T�W���̋K��̓K�p�������̏ꍇ�ɂ��ĉ\�ł���̂ɏ��ˊ��Ԃɂ��Ă͕s�\�ƂȂ邱�Ƃɂ��s�ύt�������l���̏�C�����ǂ���̖@�K�̓K�p���@�S�̂��x�z���鐳�`�E�����̗��O�ɒ�������������̂Ɣ��f���C���@�P�T�W���̒�߂���Ԃ͈͓̔��Ō����s�g�����邱�Ƃ����e�������̂ł���C��Q���r��ł��邱�ƁC���邢�͌����s�g������ł��邱�Ƃ𗝗R�Ƃ��ď��ˊ��Ԃ̉�����e�F������̂ł͂Ȃ��C���̂悤�Ȃ��Ƃ͏��ˊ��Ԃ��߂����@�̎�|�ɔ�����Ƃ����ׂ��ł���B�v�Ɛ����ɔ������Ă���B
�@�܂��C���Q�̈��������Q�̏d�含���𗝗R�Ƃ��āC���ˊ��Ԃ̓K�p�𐧌����ׂ��ł���Ƃ̌����ɑ��āC�L���n���ٔ��������P�S�N�V���X������(����S�T����)�́C�u���Q�̈��������Q�̏d�含���̓_�ɂ��ẮC���ˊ��Ԑ��x��݂���ɓ������ē��R�ɘb��ɏ��ׂ������ł���Ȃ���C���̓_�Ɋւ�炵�߂�K��@���̂���݂ؐ��Ȃ�����(��l�ԓI�s�ׂ̍ł���E�l�ɂ��Ă���S���G��Ă��Ȃ�)���Ƃ�C���@�V�Q�S����i�̎�|���炵�āC���ˊ��Ԃ̓K�p�Ɋւ��čl���̑ΏۊO�Ɖ�����̂������ł���C�����̎����������ɏ��ˊ��Ԃ�K�p�̓��ۂ�_���邱�Ƃ́C�������Q�ґ��̐S��ɗ����ꂽ���ӓI�ȉ^�p���������Q�����O����C�Ó��Ƃ͂����Ȃ��B�v(���������Q�O�W�y�[�W)�Ǝw�E���Ă��邪�C�ɂ߂đÓ��Ȏw�E�ł���B
�@
�@�E�@�����n���ٔ��������P�S�N�S���Q�U�������ɂ���
�@�T�i�l��́C���@�V�Q�S����i�̓K�p�𐧌������ٔ���Ƃ��āC�����n���ٔ��������P�S�N�S���Q�U������(����^�C���Y�P�O�X�W���Q�U�V�y�[�W)�ɂ����y����(�T�i�l���P�������ʂV�R�y�[�W)�B
�@���̔����́C����E��풆�ɒ�������������{�����ɋ����A�s����C�O��z�R������m���o�c����Y�z�ŋ����J���ɏ]��������ꂽ�Ƃ��钆���lX�炪���ˊ��Ԃł���Q�O�N���o�߂�����C��(Y�P)�y�юO��z�R(Y�Q)��퍐�Ƃ��đ��Q�����𐿋��������ĂɊւ��C���ˊ��Ԃ̓K�p�ɂ��C�u���ˊ��Ԑ��x�̓K�p�̌��ʂ��C���������`�C�t���̗��O�ɔ����C���̓K�p�𐧌����邱�Ƃ��𗝂ɂ����Ȃ��ƔF�߂���ꍇ�ɂ́C���ˊ��Ԃ̓K�p�𐧌����邱�Ƃ��ł���Ɖ����ׂ��ł���B�v�Ƃ�����ʓI���藧������ŁC�u�O�L�{�������A�s�y�ы����J���̎�����l������ƁCY�Q�ɑ��C���@�V�Q�S����i��K�p���Ă��̐ӔC��Ƃꂳ���邱�Ƃ́C���`�C�t���̗��O�ɒ�����������Ƃ��킴����C���̓K�p�𐧌�����̂������ł���B�v�Ɣ��������B
�@�������C���̕����n�ٔ����ɑ��Ă��C�O�L�����n�ٕ����P�R�N�����ɑ���ᔻ�����̂܂ܑÓ�����Ƃ����ׂ��ł���B
�@���Ȃ킿�C���̕����n�ٔ������C���`�E�t���E�𗝂Ƃ�����ʏ������珜�ˊ��Ԃ̓K�p�𐧌����邱�Ƃ��ł���Ƃ��邪�C�O�q�̂Ƃ���C�ō��ٕ����P�O�N�����́C���ˊ��Ԃ̓K�p�����ɂ��Ă��̂悤�Ȉ�ʓI���藧�������̂ł͂Ȃ��̂ł����āC�ō��ٕ����P�O�N�������C��ʓI�ɁC���ˊ��Ԃ̓K�p���u���������`�E�����̗��O�ɔ�����v�ꍇ�ɂ́C���̓K�p��r���ł���Ƃ������̂ƍl���邱�Ƃ́C���炩�ɔ���̎˒��̗�������������̂Ƃ���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
�@�����āC���̕����n�ٔ������C�����I�ɂ́C��Q�̐r�傳�Ȃǂ𗝗R�Ƃ��ď��ˊ��Ԃ̓K�p�𐧌��������̂ɂق��Ȃ�Ȃ��B�O�L�̂Ƃ���C�ō��ٕ����P�O�N�����́C���̂悤�Ȕ�Q�̐r�傳�𗝗R�Ƃ��ď��ˊ��Ԃ̉�����e�F������̂ł͂Ȃ��C���̕����n�ٔ������ō��ٕ����P�O�N�����Ɉ�w���邱�Ƃ͖��炩�ł���B
�@
�@�R�@����
�@�ȏ�̂Ƃ���C���@�V�Q�S����i�̂Q�O�N�̊��Ԃ̐����y�т��̓K�p�����Ɋւ���T�i�l��̎咣�́C�ō��ٔ��ᓙ�𐳉����Ȃ����̂ł����āC�O��ɂ����Ď����ł���B
�@

��R�@�𗝂Ɋւ���T�i�l��̎咣�ɂ���
�@
�@�T�i�l��́C�u�𗝂Ɋ�Â��Ӎߋy�ё��Q���������v�Ƒ肵�āC�T�i�l��̏𗝂Ɋ�Â����Q�����y�ё����⏞��r�˂����������́C�Љ�I���`�ɏƂ炵�ē��ꐥ�F�������̂ł͂Ȃ��Ƃ��āC�����������_���(�T�i�l���P�������ʂW�Q�Ȃ����P�O�P�y�[�W)�B
�@�������Ȃ���C�T�i�l��̏�L�咣�́C�����I�ɏ]�O�̎咣�̌J��Ԃ��ł����āC���̎咣�������ł��邱�Ƃ́C��T�i�l�����R�퍐��������(�V)�T�U�Ȃ����U�O�y�[�W�ŏq�ׂ��Ƃ���ł��邩��C��������p����B
�@

��S�@�@��P�P���ɂ�菀���@�ƂȂ�Ƃ��钆�����@�Ɋ�Â������ɂ���
�@
�@�T�i�l��́C�u�������@�ɂ��ƂÂ��Ӎߋy�ё��Q���������v�Ƒ肵�āC�{���ɂ��@��P�P���P���͓K�p����Ȃ��Ɣ������������������_���(�T�i�l���P�������ʂP�O�Q�Ȃ����P�Q�P�y�[�W)�B
�@�������Ȃ���C�ȉ��ɏq�ׂ�悤�ɁC�T�i�l��̏�L�咣�͎����ł���B
�@
�@�P�@���ێ��@�̓K�p�\���ɂ���
�@
�@(1)�{���ōT�i�l�炪�咣�����T�i�l�̉��Q�s�ׂ́C���ɍ��Ƃ̌��͓I��p�ł���C�ɂ߂Č��@�I�F�ʂ̋����s�ׂł����āC���Ƃ̗��Q����藣���čl���邱�Ƃ��ł����C������s�ׂɂ��āC���@�̓K�p��F�߁C���@�K��̒�G�̖��Ƒ����C��ʒ�G�@�K�ł���@���K�p���邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B
�@�����͍s�g�����Ɣ����Ƃ����@���W�ɂ��ẮC�䂪���̍��Ɨ��v�����ڔ��f�����@���W�Ƃ������Ƃ��ł��C���ێ��@�̓K�p�ΏۂƂ͂Ȃ�Ȃ��ƍl����̂������ł���(���r�Ǖv�E���ێ��@�u�`�R�P�y�[�W�Q�ƁC�����n�ٕ����P�O�N�P�O���X�������E�����P�U�W�R���V�V�y�[�W�C�����n�ٕ����P�P�N�X���Q�Q�������E����S�U���X�Q�y�[�W�ȉ�)�B
�@
�@�A�@����̍��ێ��@�ɂ����ẮC���ƂƎs'���Љ�Ƃ͐藣�����Ƃ��\�ł���C�s���Љ�ɂ͓���̍��Ɩ@�������ՓI�ȉ��l�Ɋ�Â����@���Ó����Ă���C����͂ǂ��̍��ł����݂ɓK�p�\�Ȃ��̂ł���Ƃ̍l�������ێ��@�̑O��ɂ���B
�@�������ɁC���@�̗̈�ł����ɂ���Ė@�݂̍�����قȂ邱�Ƃ͂����܂ł��Ȃ��B�������C��ʓI�ꐫ�i�ɒ��ڂ���C���@�̗̈�ł́C���Ɨ��v�ɒ��ڊW���Ȃ����Ƃ���C��ʂɖ@�̌݊����������C���̂悤�Ȏ��@�̗̈�ɂ����ẮC�A���_����ď����@���߂邱�Ƃɍ�����������B
�@����ɑ��āC���Ƃ̗��v�����ڔ��f����C'�ꍇ�ɂ���Ă͏����ŗ��ł�����邱�Ƃ�������@�̗̈�ɂ��ẮC���ƊԂ̗��v�����Η����C����̍��Ɨ��v�������ՓI���l�Ɋ�Â����Ɩ@�Ȃ���̂�z�肷�邱�Ƃ��邱�Ƃ�����ł��邽�߁C����̍��Ɩ@�𑊌݂ɓK�p�\�Ƃ��邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B�@�̒�G�Ƃ������́C���@�̗̈�ɂ��Ă������邪�C��L�ŏq�ׂ��Ƃ���C��ʓI�Ȗ@�̌݊�����O��Ƃ��鎄�@�̗̈�Ƃ́C���̐������傢�ɈقȂ邱�Ƃ���C���@�̗̈悪���ێ��@�̎���͈͂��珜�O����邱�ƂɂȂ�B���̂��Ƃ́C���ێ��@�̒ʐ��ł�����(�r���G�Y�E���ێ��@(���_)�P�P�y�[�W�C�R�c�`��E���ێ��@�P�T�y�[�W)�B
��L�ŏq�ׂ��Ƃ��납�炷��ƁC���ێ��@���ΏۂƂ���@���W�́C��ʂɖ@�̌݊����������C���Ƃ̗��v�ɒ��ڊW���Ȃ��̈�ɑ�����@���W(�ȉ��C�u���@�I�@���W�v�Ƃ����B)�ɂƂǂ܂�Ƃ���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�����āC���Ƃ̗��v�����ڔ��f�����@���W(�ȉ��C�u���@�I�@���W�v�Ƃ����B)�́C���ێ��@�̊W����́C���@�̗̈�ɑ�������̂Ƃ��Ď�舵���邱�ƂƂȂ�C���̑ΏۊO�ɂ��������̂Ƃ���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
�@
�@�C�@��L�̊ϓ_����C�����͂̍s�g�ɂ����Ƃ������ӔC�����ۂ��Ƃ����@���W����������ƁC���̂悤�Ȗ@���W�́C�����͂̍s�g�̓K�ۂ����f�̑ΏۂƂȂ�Ƃ����Ӗ��ŁC���@�I�@���W�̑��ʂ�L���邱�Ƃ͖��炩�ł���B���Ȃ킿�C�����͂̍s�g�̓K�ۂɊւ��锻�f���C���̌�̍��s�����C���@���̍s�g�C����ɂ́C���������ɑ��鍑�̋@�ւ̌����s�g�̂�����ɂ��d��ȉe����^������̂ł����āC���Y���Ƃ̗��v�Ɩ��ڂȊW��L���邱�Ƃ͖��炩�ł���C�܂��C���̓K�ۂ����Ƃ���Ă�������͂̍s�g�ɂ��āC���Y���Ƃ̖@���Ƃ͈قȂ�K�@�v�����߂鑼���̖@���ɂ���āC���̈�@���̗L�������f�����悤�Ȃ��Ƃ́C���Y���Ƃ̗��v�ɔ����邱�Ƃ����炩�ł���B
�@�䂪���̍����@���݂Ă��C�������ɂ������͂̍s�g���ޏk�����Ȃ��悤�Ɍ������l�ɑ������ł���ꍇ�����肵(���@�P���Q��)�C�O���l����Q�҂ł���ꍇ�́C���ݕۏ̂���Ƃ��Ɍ����Ĕ�������(���@�U��)�Ƃ��C���@�̗̈�Ƃ͈قȂ���ʂ̖@���̂��Ă���B�����́C���Ɣ����̖�肪���Ƃ̗��Q���̂��̂Ɛ[���W���Ă��邱�Ƃ̏؍��ł���B���ɁC�����@�������鑊�ݕۏ؎�`���̗p�����Ƃ������Ƃ́C�����͂̍s�g�Ɋ�Â����Q�����ӔC�̗̈�́C���@�̗\�肷�鑹�Q�����ӔC�̗̈�Ƃ͈قȂ�C���̗��Q�ɒ��ڊW����̈���\�����邱�Ƃ��������̂ł���(�R�c�E�O�f���ێ��@�P�U�P�C�P�U�Q�y�[�W)�B
�@
�@�E�@����ɉ����C�����@����O�̉䂪���̖@�̌n�����l���ɓ����K�v������B���Ȃ킿�C�{�����Q�s���̑���{�鍑���@���ɂ����ẮC�����͌����c�̂̌��͍�p�ɂ��āC���@�ł��閯�@�̓K�p�͂Ȃ��Ƃ���C����Ɋ�Â����̑��Q�����ӔC�͔ے肳��Ă���(���Ɩ����ӂ̌���)�B��R�@���a�P�U�N�Q���Q�V������(��R�@��������W�Q�O���P�P�W�y�[�W)�́C���̓_�Ɋւ��C�u�Y���j�}�\���Ɩ��n������铃m�s���m�������܃j��N�ܗ͓I�s���ɂ��e�n���@�^�����@�m�K�胒�K�p�X�x�L�j�A���U���n������^�U���g�R���E�E�E���Ńm�ؔ[�����n������铃^�����K���ƃ����t�^�Z�����^���������j��N�ܗ͍s���i�����ȃe�C�V�j��V�e�n���@���K�p�X�x�L�����j�A���U���o�E�E�E�v�Ɣ������Ă���B���̂悤�ɁC���̌��͓I��p�ɂ��Ĉ�ʎ��@�ł��閯�@�̓K�p���ے肳���Ƃ��铖���̖@���x���݂Ă��C�����͂̍s�g�ɔ����s�@�s�ׂɂ��ẮC�䂪���̖@�����C���Ɨ��v�����ڔ��f����C��ʎ��@�ƈقȂ�̈�ɑ�����@���W�Ƃ��ė�������Ă������Ƃ����炩�ł���(���|�ō��ُ��a�Q�T�N�S���P�P����O���@�씻���E�ٔ��W�����R���Q�Q�T�y�[�W)�B
�H�@�ȏ�ɂ݂��Ƃ��납�炷��ƁC�����͍s�g�ɔ������Ɣ����Ƃ����@���W�ɂ��ẮC�䂪���̍��Ɨ��v�����ڔ��f�����@���W�Ƃ������Ƃ��ł��C���ێ��@�ɂ����ẮC���@�̗̈�ɑ�����@���W�Ƃ��Ď�舵���邱�ƂɂȂ�C���ێ��@�̓K�p�ΏۂƂ͂Ȃ�Ȃ��Ɖ�����̂������ł���(���r�E�O�f���ێ��@�u�`�R�P�y�[�W�Q��)�B
�@
�@�I�@����ɑ��C�T�i�l��́C���Z�����m�̒���ɂ����āC�����͂̍s�g�Ɋւ��锅���`�������@��̋`���ł���Ƃ���Ă��邱�Ƃ���C���Ƃɑ��锅�������Ƃ����@���W�͎��@�W�ɑ�������ł���Ǝ咣����(�T�i�l���P�������ʂP�O�T�[�W)�B
�@�������Ȃ���C�T�i�l��̏�'�L�咣�͎����ł���B
�@���������C���ێ��@�̓K�p�ΏۂƂ��Ďg�p�����ꍇ�́u�@���W�v�Ƃ�����́C�u�@������Ƃ����W�C���Ȃ킿�@���̋K���̑ΏۂƂȂ鐶���W�v���Ӗ�����ɂ������C�u�����ꂩ�̖@���̓K�p�ɂ���Ė@���W�Ƃ��Đ��������W�v�������̂ł͂Ȃ�(���r�E�O�f���ێ��@�u�`�P�P�y�[�W)�B���̂悤�ɁC���ێ��@�̓K�p�ΏۂƂȂ鎄�@�I�@���W�Ƃ́C�����`���̔��������ƂȂ�@���W�����Ɨ��v�ƒ��ڊW���Ȃ������W�̂��Ƃ��������̂Ɖ������̂ł����āC����@���̓K�p�̌��ʂƂ��Ĕ������������`���W�̖@�I��������Ƃ��Ă���̂ł͂Ȃ��B
�@�ȉ��C�T�i�l��̉E�咣�ɂ��ċ�̓I�ɔ��_����B
�@
�@(�)�@�������ɁC���Z�����m�̒���ɂ͍T�i�l��̎w�E����L�q������B�������C����́C�@�K�p�̌��ʔ�������u�����`���v���ꎩ�̖̂@�I�ꐫ������Ƃ����L�q�ɂ����Ȃ��B���̂��Ƃ́C���Z�����m���C�u�����`���m�@����m�����j�t�C�e�n���m���@�I�m�������L�X�����m�i���R�g�n���ăi���x�V�v�Ƙ_���Ă��邱�Ƃ�������炩�ł���B
�@����ɑ��C���ێ��@�̓K�p�ΏۂƂ̊W�Ŗ��Ƃ����ׂ��u�@���W�v�Ƃ́C����@�����K���ΏۂƂ��Ă��鐶���W�̂��Ƃł����āC����@���̓K�p�̌��ʂƂ��Ĕ������錠���`���̐����ł͂Ȃ��B
�@���Z�����m�͍T�i�l��w�E�̏�L�L�q�̌�ɁC�u�����m��p�j��N���ƃm�����ӔC�m���j�t�C�e�n�C���@�m�K��n�c�R�V�j�K�p�X���R�g�����X�B���������`���J���m��������@�j���X���Jਃj��X�B�����`�����m���m�n���@��m�`���^���R�g�n�O�j�q�w�^���J�@�V�g嫃��C���m�`���J���m���̓m��p�j�����V�eᢐ��X���ꍇ�j���e�n���@�m�K��n�V�j�K�p�X���R�g�����T�����m�^���i���B���@�n�B���m�s�@�sਃ��K��Z���m�~�C���m���̓j��N�s�@�sਃn���@�m��X�����j��T���i���B�v�Əq�ׂĂ��邪(���Z���B�g�E���{�s���@(�㊪)�X�R�O�y�[�W�ȉ�)�C�����Łu�����m��p�j��N���ƃm�����ӔC�m���j�t�C�e�n�C���@�m�K��n�c�R�V�j�K�p�X���R�g�����X�B�v�Ƃ��Ă���_�ɒ��ڂ��ׂ��ł���B
�@���Ȃ킿�C���̋L�q�ł́C�u�����m��p�j��N���ƃm�����ӔC�v�����Ƃ���鐶���W�ɂ����ẮC���̌����s�ׂ������͂̍s�g�Ƃ����u���@��m�s�ׁv�ł��邱�Ƃ��疯�@�̓K�p���Ȃ��Ƃ��Ă���̂ł����āC���Ɣ������F�߂���ׂ����ۂ��C�F�߂���Ƃ��̗v�����ǂ����邩�Ƃ������@���W(�����W)�́C���ێ��@�̊ϓ_����͌��@�I�@���W�ł���Ƃ����T�i�l�̎咣�ƋO����ɂ���B
�@���������āC�����m�́C���̌����͂̍s�g�ɂ��Ė��@�͓K�p����Ȃ��Ƃ������_���炵�Ă��C��T�i�l�Ɠ���̗�����̗p���Ă���C�T�i�l��̎咣�̍����ƂȂ���̂ł͂Ȃ��B
�@
�@(�)�@���ɁC�Y�싳���̌���(�T�i�l���P�������ʂP�O�U�y�[�W)�́C���Ƃɑ��鑹�Q���������i�ׂ͖����i�ׂł���Ƃ���Ɏ~�܂���̂ł���B
�@
�@(�)�@�܂��C���������̌���(���P�O�U�C�P�O�V�y�[�W)�́C�u���Ɣ����@���C���@���x�̒��ŁC���@�̓��ʖ@�̒n�ʂɂ�����̂ƔF�ނׂ��v�Ƃ��Ă͂�����̂́C����������@���K�p���ꂽ���ʔ������锅���`����������̂��̂ł��邱�Ƃ��w�E����ɂƂǂ܂�C���@�̋K������@���W(�����W)�����Ɨ��v�ƒ��ڊW���Ȃ����Ƃ܂ňӖ�������̂ł͂Ȃ��C�T�i�l��̎咣�̍����ƂȂ蓾����̂ł͂Ȃ��B�܂��āC�R�������̌���(���P�O�V�y�[�W)�͍��������̌��������p������̂ɂ����Ȃ��B�@�����āC�u���͍�p�Ɋ�Â��s�@�s�ׂɖ��@�̓K�p���Ȃ��Ƃ��ꂽ�̂́C���@���̂̓��ݓI�_���̋A���Ƃ��������C���Ɩ��ӔC�̌����ƁC�s�����Ɛ��x�ɗR�����錵�i�Ȍ��@�E���@�_�ɗR��������̂ŁC���̌��O����Ȃ����e�����ꂽ���s���x�̉��ɂ����ẮC���@�̓K�p�������I�ɔr�����ׂ������͎���ꂽ�ƌ��Ă悢�Ǝv���B�v(�����E���ƕ⏞�@�W�U�y�[�W)�Ƃ����L�q���炷��C�������������@���ɂ����ẮC���Ƃ̔����ӔC�̂����@���W�����@�̕���ɑ����Ă������Ƃ����R�̑O��Ƃ�����̂Ɖ�����C���̓_�ɂ����Ă��C�T�i�l��̎咣�����̂܂܍����Â�����̂ł͂Ȃ��B
�@
�@(�)�@���ǁC�����͂̍s�g�ɔ������Q�����ӔC�ɂ��Ă̖@���W�́C���ƓI���v�Ƃ̌��т������łȂ��̂ł����āC���Ƃ��ƌ��@�I�@���W�ɑ����Ă���C���@�I�@���W�ɂ͑����Ă��炸�C���̂悤�Ȗ@���W�́C�{���C���@�̓K�p���Ȃ����̂ł����āC�����@�P���P���ɂ����Ē�߂�ꂽ���̔����ӔC�́C��L�̂悤�Ȍ��@�I�@���W�ɂ��Ă̍��̐ӔC��n�ݓI�ɔF�߂����̂ƍl����̂������ł���B
�@�����āC���̂悤�ȍ����@�̌��@�I���ʂ́C���̗��@�ߒ��ɂ��[�I�ɕ\���Ă���B���Ȃ킿�C�����@�̗��@�ɓ������ẮC�����C���@���̕s�@�s�ו҂��������č��Ɣ����Ɋւ���K���}������Ƃ���Ă����ꂽ�B�Ƃ��낪�C���C�����c�̂̌����͍s�g�̊W�͎��@�I�@���W�ł͂Ȃ��C���@�ɓ����̂͗��ꂪ�Ⴂ�s�K���Ƃ���āC���@�ւ̕ғ��͂��ꂸ�C�����@�Ƃ����Ǝ��̖@�������肳�ꂽ�̂ł����āC�����������@�̌o��(�Í�c���E���Ɣ����@�V�Ȃ����X�y�[�W)�ɏƂ炵�Ă������@�̗\�肷��@���W�́C���@��̂���ƈقȂ邱�Ƃ͖��炩�ł���B
�@
�@(2)�Ƃ���ŁC�T�i�l��́C�����@�Ɋ�Â����Q���������������@��̋��K���ł���Ƃ����ō��ٔ������a�S�U�N�P�P���R�O������(���W�Q�T���W���P�R�W�X�y�[�W)�����p���C����̎咣�̍����Ƃ���(�T�i�l���P�������ʂP�O�V�y�[�W�j
�@�������C��L�ō��ٔ����͍����@��K�p�������ʂƂ��Ĕ����������Q���������������@�I�K���ɕ�������̂Ƃ������̂ł����āC���̐ӔC�������K�����鍑���@�����@�����@���ɂ��Ĕ��f�������̂ł͂Ȃ�(���̓_�ɂ��������ɂ��Ă̖�c�G�E�ō��ٔ������������a�S�U�N�x�����тS�Q�T�y�[�W�Q��)�B�����ł��T�i�l��́C���ێ��@�̓K�p�Ώۂ��悷����̂Ƃ��Ắu�@���W�v�Ƃ�����̈Ӗ������Ⴆ�ė������Ă���̂ł���B���������āC��L�ō��ٔ������������@�����@�K��ł���Ƃ������Ƃ͂ł��Ȃ��B
�@
�@(3)�܂��C�T�i�l��́C���Ɣ��������̖�肪���@�I�@���W�ł���Ƃ���ƁC���@�̑��n�I�K�p�̌������Ó����C�ɂ߂ĕs�����Ȃ��ƂƂȂ�Ǝ咣����(�T�i�l���P�������ʂP�O�W�y�[�W)�B
�@�������Ȃ���C�T�i�l��̗��_��O��Ƃ���ƁC�����͂̍s�g�ɔ������Q�����̖��ɂ��āC�@��P�P���P�����K�p����C���̌��ʁC�s�@�s�גn�ł��铖�Y�O���̖��@���K�p����邱�ƂɋA�����邪�C���̂悤�Ȍ��_�́C�䂪���̍��ƌ��͂̔����̈�@�����ɂ��āC�䂪����P�Ȃ�ꎄ�l�ƌ����Ă���C�����̎��@��������ق����Ƃ��Ӗ�����B�������Ȃ���C���̂悤�Ȍ��_�́C�䂪���̖@�̌n�݂̍���C���Ȃ킿�C�����͂̍s�g�ɔ������Q�s�ׂɂ��ẮC���@��̕s�@�s�ׂƈقȂ�@�I�戵��������Ă��邱�ƂɏƂ炷�Ɠ���l�����Ȃ����Ƃł���B�T�i�l��̎咣�́C�{���d�������ׂ����Ɨ��v�Ƃ̌��т��y�т��̒��x�Ƃ������_��������̂ł����Ď����ł���B
�@�ȏ�̂Ƃ���C�����͍s�g�ɔ������Q�����̖����@��P�P�����K�p�����ׂ����@��̕s�@�s�ׂ̖��ł���Ƃ���T�i�l��̏�L�咣�͎����ł���B
�@
�@(4)�Ȃ��C�T�i�l��́C���������C�����@�U���́u���݂̕ۏv���K�肵�Ă��邱�Ƃ́C�����@�����Ƃ̗��Q�Ɛ[���W���Ă��邱�Ƃ��������̂Ɣ����������Ƃɑ��C���ݕۏ؋K��́C���@��̌����ł��閳�̍��Y���Ɋւ�������@�Q�T�ɂ���߂��Ă��邩��C���ݕۏ؋K�肪���邱�Ƃ������āC���@�̗̈�ƈقȂ邱�ƂɂȂ�Ƃ͂����Ȃ��Ǝ咣����(�T�i�l���P�������ʂP�O�X�y�[�W)�B
�@�������Ȃ���C�T�i�l��̏�L�咣�͌������y�є�T�i�l�̎咣�𐳉����Ȃ����̂ł���B��T�i�l�́C�P�ɍ����@�U���ɑ��ݎ�`���߂�K�肪���邩�獑���@�ɂ�����@���W�͌��@�ł���ȂǂƎ咣���Ă���̂ł͂Ȃ��C�����@�̑��ݕۏ̋K�肪���Ɨ��v�̊m�ۂƂ����ϓ_����݂���ꂽ���̂ł��邩����@�ł���Ǝ咣���Ă���̂ł���B���Ȃ킿�C���Ɣ������x�͔����ɂ�莖��I�ł͂��邪�����͂̍s�g�݂̍����}�������p���c�ނ��̂ł���̂ɑ��C�����@���̋K��͌����͂̍s�g�݂̍�����K��������̂ł͂Ȃ��B�����@�̑��ݕۏ̋K��́C���Ƃƍ��Ƃ̖�ɂ����鍑�Ɣ������x�̓��e(�����͍s�g�̗}���݂̍��)�̋ύt��}��C�����đ����ɑ��ē��{�l��Q�҂��~�ς��闧�@�������悤�Ƃ����@����Ɋ�Â����̂ł����āC���ɁC���Ɣ��������Ƃ̗��Q���̂��̂ɐ[���W���Ă��邱�Ƃ̏؍��Ƃ����ׂ��ł���B
�@���������āC�T�i�l��̏�L�ᔻ�͎����ł���B
�@
�@�Q�@���ێ��@�̖@���W�̐�������ɂ���
�@
�@(1)���ɁC�@��P�P��K�p�̗L������������ɓ������ẮC�����ɂ����u�s�@�s�ׁv�Ƃ����@���T�O���C�T�i�l��̎咣����@���W���ۂ��邩�ǂ�������������Ȃ���Ȃ�Ȃ��B��������C�����ɂ����u�s�@�s�ׁv�Ƃ����@���T�O����L�̂悤�Ȗ@���W��ΏۂƂ��Ă��Ȃ��̂ł���C������K�p����]�n�͂Ȃ�(�r���E�O�f���ێ��@(���_)�X�T�y�[�W�C�R�c�E�O�f���ێ��@�S�U�y�[�W)
�@�@��P�P���́u�s�@�s�ׁv�Ƃ����@���T�O�̎����I�K�p�͈͂���肷�邱�Ƃ́C���ێ��@�ɂ�����@���W��������̖��ł��邪�C���̖��́C�u�s�@�s�ׁv�Ƃ������ێ��@�K��̉��ߖ��ł����āC��̓I�ɂ́C�e���ێ��@�K��̐��_�E�ړI�Ȃ�����|�Ƃ����Ƃ���ɏ]���C�e�������@�̔�r��������ʂ��Č��肳��鎖���ł���(�r���E�O�f���ێ��@(���_)�P�P�T�y�[�W�C�R�c�E�O�f���ێ��@�T�Q�y�тT�R�y�[�W)
�@�����āC���̍ۂɂ́C�O�q�̌���̍��ێ��@�����Ɨ��v�ɒ��ڔ��f�������@�̗̈�����킸�C���@�̗̈�݂̂����̑ΏۂƂ��Ă���Ƃ������ێ��@�ŗL�̍l�������\���ɍl�����ׂ��ł���B
�@
�@(2)�����ŁC��r�@�I�Ȋϓ_����e���̎����@�����������Ă݂�ƁC�{���̂悤�Ȍ����͂̍s�g�ɔ����s�@�s�ׂɂ��ẮC���̂悤�ɁC��ʕs�@�s�ׂƂ͈قȂ�戵��������Ă���B
�@
�@�A�@�A�����J���O���ł́C�P�X�S�U�N�ɘA�M�s�@�s�א������@����������܂ł́C�匠�Ɛӂ̖@���ɂ��A�M���ӔC�����Ƃ͂Ȃ��C����ȍ~���C���@�Q�U�W�O���ɂ����āu�����Ȓ��ӂ����@�ߎ��s�s�ׂ��邢�͍ٗʌ��\�̍s�g�E�s�s�g�C�X�֊W�C�d�ŁE�ł̕��ے����C�C�������C�G���ʏ��K���C���u�C�\�s�E���ŁE��@�S�ցE��@�ߕ߁E���ӂ���i�ǁE�i�葱�̗��p(�ȏ�̂U��ɂ��Ă͌x�@�����ɂ����̂�����)����і��_�ʑ��E�s���\���E���\�E�_���̌����ɑ��銱���C���ɂ̉^�c���邢�͋��Z�@�ւ̋K���C�펞�̌R���̐퓬�s�ׁC�O���ɂ����鎖���C�e�l�V�[�k�J���m�̊����C�p�i�}�^�͉�m�̊����C�A�M�y�n��s���̊����ɂ��ẮC�P�R�S�U��(b)�k�w��㗝�l��:�����͘A�M�n���ٔ����̊NJ����ɂ��Ă̋K��ł���B�l�Ɩ{�͂̋K��͓K�p���ꂸ�C�A�M���{�͐ӔC��Ȃ��B�v�Ƃ���Ă���(�A���h���E�u�e���̍��ƕ⏞�@�̗��j�I�W�J�Ɠ�����A�����J�v���ƕ⏞�@�̌nI�P�R�T�y�[�W)�B
�@
�@�C�@�ŋ߂̍��Ɣ����@�ł��钆�ؐl�����a�����Ɣ����@(�P�X�X�S�N�T���P�Q�����z�C�P�X�X�T�N�P���P���{�s)�R�R���́C�@�u�O���l�C�O����Ƌy�ёg�D�����ؐl�����a���̗̈���ɂ����Ē��ؐl�����a���̍��Ɣ���(���@�V���ɂ��C���m�ɂ͍��ł͂Ȃ������`���@�ւƂȂ�B)�𐿋�����ꍇ�ɂ́C���̖@����K�p����B�v�C�A�u�O���l�C�O����Ƌy�ёg�D�̏����������ؐl�����a���̌����C�@�l���̑��̑g�D�̓��Y���̍��Ɣ��������̌����ɂ������ی삹���C���͐������Ă���ꍇ�́C���ؐl�����a���́C���Y�O���l�C�O����Ƌy�ёg�D�̏������ƑΓ����������s����B�v�ƋK�肵(�@����b���[�i�@�@���������E���ďC�E���s���ؐl�����a���Z�@�P�R�X�y�[�W)�C���ݕۏ؎�`���̗p���Ă���B
�@
�@�E�@��ؖ����̍��Ɣ����@(�P�X�U�V�N�@����P�W�X�X��)�́C�X���ɂ����āC�����R�c��̔������x���̌�����o����łȂ���Α��Q�����̑i�ׂ��N���邱�Ƃ��ł��Ȃ��Ƃ��āC�����R�c��O�u��`���̗p���Ă���Ƃ����(�Í�c���E���Ɣ����@�W�S�Ȃ����X�O�y�[�W�B)
�@
�@�G�@�C�M���X�̍��Ɣ����ӔC�@�Ƃ��ẮA�P�X�S�V�N�ɐ��肳�ꂽ�����i�ǖ@������(����ȑO�͎匠�Ɛӂ̖@���ɂ�荑�͐ӔC��Ȃ������B).���C���̗�O�Ƃ��āC�i�@���̍s�g�ɂ�鑹�Q�ɂ��Ă͐ӔC�킸�C�R���̍s���ɂ�鑹�Q�ɂ��ẮC�ɂ߂ĐӔC���ꍇ����������Ă���ق��C�����匠�Ƃ��Ă̖Ɛӂ�����Ƃ���C�܂��C���ɑ����Q�����F�e�����͎��s�ł��Ȃ��Ƃ���Ă���(�Í�E�O�f���Ɣ����@�S�V�Ȃ����T�W�y�[�W)�B
�@
�@�I�@�X�C�X�ɂ����鍑�Ɣ����@�Ƃ��ĘA�M�ӔC�@�����邪�C���@�ɂ����ẮC�R���ɏ�������҂ɂ�鑹�Q�́C���@�̓K�p�͂Ȃ��C���Q�������̌R�����K�����͌����̎��ɐ���������ɂ����ĕʂ̖@�߂̒�߂ɏ]���ĘA�M���ӔC���Ƃ���Ă���ق��C�A�M�ӔC�@��̐����́C���@��̐����Ƃ���C�܂��C�呠�ŏȂ���������̂Ƃ���C���Ȃ��C�������p�����邩�C�R�����ȓ��ɏ������Ȃ��ꍇ�A�s�����̋p���錾����U�����ȓ��ɁC�s���ٔ����Ƃ��Ă̘A�M�ٔ����ɒ�i�ł���Ƃ���Ă���(�Í�E�O�f���Ɣ����@�V�U�Ȃ����W�Q�y�[�W)�B
�@
�@�J�@���̂悤�ɁC���O���̍��Ɣ������x�����Ă��C���ݕۏ؎�`�C�s���@�ււ̑O�u��`���e���Ǝ��̍��Ɨ��v�f�����@���x���̗p����Ă��邱�Ƃ����������,��ʂ̎��@�ƈقȂ�戵��������Ă��邱��,�y�т��̌��ʂƂ��Ĉ�ʓI�Ȗ@�̌݊��������݂��Ȃ����Ƃ����炩�ł���B
�@
�@(3)�܂�,���Ɣ����Ɋւ��鏔�O���̍ٔ�����݂Ă�,�����h�C�c�ł�,�������̍��O�ɂ�����E���ᔽ�ɂ��Ă�,���h�C�c�@�̓K�p������Ƃ���,���̑�,�t�����X,�C�^���A�y�уI�[�X�g���A�ł����l�Ƃ���Ă���(�R���҉�E�u���Ɣ����@�Ƒ��݂̕ۏv�O����S�I(��O��)�ʍ��W�����X�g133��256�[�W)�B
�@
�@(4)������,�䂪���̌����͍s�g�ɋN�����鑹�Q�����Ɋւ���@�̎��ɂ��Ă�,�O�L1(1)�C�ŏq�ׂ��Ƃ���ł��邪,��L�̔�r�@�I���_�����������������,�@���W�̐�������Ƃ���,�����͍s�g�ɔ������Ɣ����̖@���W��,�@��11���ɂ����u�s�@�s�ׁv�T�O�ɕ�ۂ���Ȃ����̂Ƃ��킴���,�{���ł�,�@��11�����K�p�����]�n�͂Ȃ��Ƃ����ׂ��ł���B
�@
�@3�@�@��P1���̓K�p�̉\���ɂ��Ă̏���
�@
�@�ȏ�q�ׂ��Ƃ��납�炷���,�{���ōT�i�l�炪�咣�����T�i�l�̍s�ׂɂ��Ă�,�@��11���̓K�p��,�����O��Ƃ��钆�������@�̓K�p���Ȃ��B
�@����������,�������@�������Ƃ���T�i�l��̐�����,�{���K�p����Ȃ��@�߂Ɋ�Â������ł���,�@�I�������������̂Ƃ��Ċ��p��Ƃ�Ȃ��B
�@
�@4�@���{�@�̗ݐϓK�p�ɂ���
�@
�@(1)�ݐϓK�p�̓��e�ɂ���
�@
�@�A�@��L�ɏq�ׂ��Ƃ���,�{�������ɂ��Ă�,�䂪���̖@���Ɋ�Â��Ă��̍�������v���������咣�����ׂ��ł��邪,���ɍT�i�l��̎咣����悤�ɖ@��11���̓K�p������Ƃ��Ă�,�ȉ��ɏq�ׂ�Ƃ���,�s�@�s�ׂ̐����ɂ͓����Q��,�R���ɂ��,���{�@���ݐϓK�p����邩��,������ɂ��Ă�,���{�@�̗v�������̎咣,�����������Ƃ͂ł��Ȃ��B
�@���Ȃ킿�A�@��1�P��1����,�u�E�E�E�s�@�s�ד�����e���X�����m�����y�q���̓n�������^�������m�����V�^���n�m�@���j�˃��v�ƒ�߁C�s�@�s�ׂ̐����y�ь��͂Ɋւ��邷�ׂĂ̖��ɕs�@�s�גn�@��K�p����Ƃ��Ă���B����C�����Q���́C�u�O���m�K��n�s�@�s�׃j�t�e�n�O���j���e�����V�^�������J���{�m�@���j�˃��n�s�@�i���T���g�L�n�V���K�p�Z�X�v�ƒ�߁C�s�@�s�ׂ̐����ɂ��Ė@��n�@�ł�����{�@�̓K�p���K�肷��B���̂悤�ɖ@�Ⴊ�s�@�s�ׂ̐����ɂ��C�P���ɂ����ĕs�@�s�גn�@��`���̂�Ȃ���Q����u���C�@��n�@��`�Ƃ̐ܒ���`���̂����̂́C���������̗��ꂩ��C���{�@�ɏƂ炵�ĕs�@�s�ׂłȂ��s�ׂ�s�@�s�ׂƂ��ċ~�ς�^����K�v���Ȃ��Ƃ�����̂ł���B���Ȃ킿�C�@��̋K��́C�s�@�s�גn�@�Ɠ��{�@�Ƃ̈�ʓI�ȗݐϓK�p��F�߂����̂Ƃ��āC���҂̗v�����Ƃ��ɋ�����Ȃ���Εs�@�s�ׂ��������Ȃ��Ƃ�����̂ł���(�R�c�E�O�f���ێ��@�R�Q�R�y�[�W�C�����n�ُ��a�Q�W�N�U���P�Q�������E�����W�S���U���W�S�V�y�[�W���|)�B
�@�܂��C�O�L�̂悤�ɁC�@��P�P���P���́C���͂Ɋւ�邷�ׂĂ̖��ɂ��Ă��s�@�s�גn�@�ɂ��Ƃ��Ă���B�������͂Ɋւ�����Ƃ��ẮC���Q�������������擾����҂͈̔́C���Q�����͈̔͋y�ѕ��@�Ƃ����������͂��Ƃ��C�����������Q�����������̏��n���C�������C�������̖�蓙������(�R�c�E�O�f���ێ��@�R�Q�Q�y�[�W)�B�������C���̖͂��ɂ��Ă��C�����R���́C�u�c��Q�҃n���{�m�@���J�F���^�����Q���������m�����j��T���n�V�������X���R�g�����X�v�ƋK�肵�C�s�@�s�ׂ̌��̖͂��S�ʂɂ��āC���{�@��ݐϓI�ɓK�p������̂Ƃ��Ă���B�����āC���̂悤�ȋK���u�����@��̎�|�́C���ǁC���{�̍ٔ��������{�@��s�@�s�ׂł���ƔF�߁C���{�@�̔F�߂�͈͓��ɂ����Ă̂ݕs�@�s�ׂɂ��~�ςɏ��͂���Ƃ������Ƃɂق��Ȃ�Ȃ�(�R�c�E�O�f���ێ��@�R�Q�S�y�[�W)�B
�@�ȏ�̂Ƃ���C�@��P�P���P���������Ƃ���T�i�l��̐����ɂ��ẮC�����Q���C�R�����K�p����邱�Ƃɂ��C�s�@�s�ׂ̐����y�ь��ʂ̑o���ɂ��āC�s�@�s�גn�@�Ɩ@��n�@�Ƃ��ݐϓI�ɓK�p����邱�ƂɂȂ�B
�@���������āC�T�i�l��́C���̎咣����s�ׂ����Q�����������̔��������Ƃ��Ă̕s�@�s�ׂɊY������Ƃ������߂ɂ́C���Y�s�ׂɌW����{�@�̗v�������ɂ��Ă��咣�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
�@
�@�C�@����ɑ��C�T�i�l��́C�@��P�P���R���̓K�p�͈͂́C���Q�����͈̔͋y�ђ��x�Ɍ����C�����y�я��ˊ��Ԃ̖��͊܂܂�Ȃ��Ǝ咣����(�T�i�l���P�������ʂP�P�T�y�[�W)�B
�@
�@(�)�@�������C�@��P�P���Q���y�тR���ɂ��ẮC�O�L�̂Ƃ���C�s�@�s�ׂ̐����͂��Ƃ��C���ʂ̖ʂɂ����Ă����{�@���ݐϓK�p�����Ƃ���̂��ʐ��ł���(����r��Y�E��{�@�R�������^�[�����ێ��@�V�Q�y�[�W�Q��)�B���̂��Ƃ́C���슰�E�u�@��ɂ�����s�@�s�ׂ̏����@�ꌻ��Ɖۑ�v(�W�����X�g�E�P�P�S�R���T�P�y�[�W)���C���ێ��@�̒ʐ��́C�@��P�P���Q���C�R���̋K�����{�@��s�@�s�ׂƂ���Ȃ����̂ɂ��Ă܂ŕs�@�s�ׂɂ��~�ς�F�߂�K�v���Ȃ����Ƃ����������̂Ɨ������A�s�@�s�ׂ̐����ƌ��͂̑S�ʂɂ킽���ē��{�@���ݐϓK�p�������̂Ɖ����Ă��邱�Ƃ�������炩�ł���B
�@
�@(�)�@�R�c�������C�u�s�@�s�ׂ̐����ɂ��ē��{�@�̊���S�ʓI�ɔF�߂�@��̎�|���炷��C���͂ɂ��Ă��Ō�̐�(�w��㗝�l��:���Q�����̕��@�����ł͂Ȃ����Q�����̊z�����������Ă���Ƃ����)��Ó��Ƃ��ׂ��ł��낤�B�v�Ƙ_���Ă����C�����Q���y�тR���̋K��̐����Ɍ��y���C�u�@�Ⴊ�ܒ���`���̂�C�@��n�@�̊���F�߂�̂́C���{�̍ٔ��������{�@��s�@�s�ׂƔF�ߓ��{�@�̔F�߂�͈͓��ɂ����Ă̂ݕs�@�s�ׂɂ��~�ςɏ��͂���Ƃ�����|�ł���B�v�Ƙ_���Ă���̂ł�����(�R�c�E�O�f���ێ��@�R�Q�S�y�[�W)�C�����̘_�q�ɏƂ点�C�R�c�������C�@��P�P���Q���y�тR���ɂ��āC�s�@�s�ׂ̌��͂̂����C���Q�����̕��@�y�ъz�����Ɍ��肷���|�ł͂Ȃ��Ƃ����ׂ��ł���B
�@
�@(�)�@�܂��C�@��P�P���P���ɂ����s�@�s�ׂ̌��ʂɊ܂܂�鎖���ɂ��āC�]��p���E�u���ێ��@�v�Q�T�O�y�[�W�́C�u�@��͕s�@�s�ׂ̌��͂ɂ��Ă��s�@�s�גn�@(���������n�@)�ɂ��ׂ����Ƃ������Ƃ��Ă���B�]���āC�s�@�s�ׂ̌��͂Ɋւ��邷�ׂĂ̖����܂Õs�@�s�גn�@�̓K�p����B�v�Ƃ��C���̎����Ƃ��āC�u�s�@�s�ׂɂ���Ĕ����������̉^�����s�@�s�ׂ̌��̖͂��ɑ��Ȃ�Ȃ��B�]���āC�s�@�s���̏��n���C���������͏��Ŏ����̋q�̂ƂȂ邩�C�܂����̍��Ƒ��E�����邩���̖��v(�����Q�T�P�y�[�W)�������C���̏�Ŗ@��P�P���R���ɂ��āu�s�@�s�ׂ̌��͂ɂ����{�@�̊�����ʓI�ɔF�߂����́v�Ƃ̐��𐳓��Ƃ��Ă���B�܂��C���r�E�O�f���ێ��@�u�`�R�X�O�y�[�W�ɂ����Ă��C�u���������Ȃ鎖�R�ɂ����ł��邩�́C���̌��͂̈�ԗl�ł��邩��C�����Ƃ��āC���̍��̏����@�ɂ��ׂ��ł���B���������āA���̏��Ō����ƂȂ�ׂ��ٍρC���E�C�X���C�Ə��C���Ŏ����Ȃǂ̗v���y�ь��͂́C�����Ƃ��āC���̍��̏����@�ɂ��B�v�Ƃ��C���̏�ŁC�@��P�P���R���ɂ��āC�u�{���̎�|�́C�s�@�s�ׂ̌��͂Ɋւ��đS�ʓI�ɓ��{�@�ɂ�鐧����F�߂����̂Ɖ�����̂����R�ł���Ƃ�������v(�����R�V�V�y�[�W)�Ƃ��Ă���̂ł���B
�@��������ƁC�@��P�P���R���ɂ���đS�ʓI�ɗݐϓK�p�����ׂ��s�@�s�ׂ̌��͂ɂ����鎖���ɂ́C�ʏ���̏��łɂ����鎖�����܂܂�ċc�_����Ă���Ƃ����ׂ��ł���B�����āC���̌��͂̈ꎖ���Ƃ��Ă̍��̏��łɂ����鏀���@���@��P�P���P���ɂ�茴���Ƃ��ĕs�@�s�גn�@�ł���O���@�ɂ�邱�ƂɂȂ���̂́C���{�@��s�@�s�ׂƂ��ċ~�ς�F�߂�K�v���Ȃ����̂܂ŊO���@�̏����@�ɂ�邱�Ƃ͂Ȃ��Ƃ��������R���̎�|���炷��C���̌��͂̈ꎖ���Ƃ��Ă̍��̏��łɂ����鎖���ɂ��Ă��C���{�@�̗ݐϓK�p��F�߂�ׂ����ƂɂȂ�B
�@
�@(2)���{�@�̓K�p�ɂ���
�@
�@�ȏ�̂Ƃ���C�T�i�l��̐����́C������ɂ��Ă����{�@�̗v�����[�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
�@������Ƃ��C�@��P�P���Q���ɂ��C�s�@�s�ׂ̐����ɂ��ĕs�@�s�גn�@�Ɠ��{�@�Ƃ��ݐϓI�ɓK�p����邱�ƂƂȂ�B�{���ɂ����čT�i�l�炪�咣���鋌���{�R�l��������̍s�ׂ́C���Ƃ̌��͓I��p�ł����āC�䂪���̍����@�{�s�O�ɂ����ẮA���̌��͓I��p�ɂ��Ă͖��@�̕s�@�s�ז@(�V�O�X���ȉ�)�̓K�p�͔r������C���̑��Q�����ӔC�͔ے肳��Ă���(���Ɩ����ӂ̖@��)�B�����āC���̌�C���{�����@�P�V���Ɋ�Â����肳�ꂽ�����@�����U���́C�u���̖@���{�s�O�̍s�ׂɊ�Â����Q�ɂ��ẮC�Ȃ��]�O�̗�ɂ��B�v�ƒ�߂�����C�����@�{�s�O�̋����{�R�l�̍s�ׂɊւ��鑹�Q���������͍��Ɩ����ӂ̖@���ɂ��C���̖@�I�������������̂Ƃ����ق��Ȃ��B
�@�܂��C���ɁC�{���ɂ����čT�i�l��̎咣����悤�ɖ@��P�P���̓K�p���l���Ă݂Ă��C�����R���̓K�p�ɂ��C�s�@�s�ׂ̌��͂ɂ��ĕs�@�s�גn�@�Ɩ@��n�@�Ƃ��ݐϓI�ɓK�p�����B�����āC�T�i�l��̐����́C���̎咣�ɌW��s�@�s�ׂ̎�������ɂQ�O�N�ȏオ�o�߂�����ɂ��ꂽ���̂ł��邩��C�@��n�@�ł���䂪���̖��@�V�Q�S����i�ɂ�肻�̐����������ł��Ă���B
�@�T�i�l��́C���Ɩ����ӂ̖@���y�і��@�V�Q�S����i�̓K�p�ɂ��C���咣���邪�C�T�i�l��̎咣�������ł��邱�Ƃ͊��ɏq�ׂ��Ƃ���ł���B
�@
�@(3)�s������Ƃ��ׂ����Ƃɂ���
�@
�@�Ȃ��C�T�i�l��́C�u������(�d��F���p�Ғ�)�K�p���ׂ��́C�ٔ����̖@��n�@�ł���B�Ȃ��Ȃ�C�ٔ��ɂ����Ē�G�����ƂȂ�@��n�̌����́C���R�C�ٔ����̌����ł���C�ٔ����̌����Ɗւ��̂́C�ٔ����̖@��n�@������ł���B�v(�T�i�l���P�������ʂP�P�O�y�[�W)�Ƃ��C�u�@��P�P���Q���ɂ����{���@���ݐϓK�p�����Ƃ��Ă��C�E�E�E�K�p�����̂́C�ٔ����̖@��n�@�ł���C���Ɩ����ӂȂ���̂��K�p�������̂ł͂Ȃ��v(���P�P�S�y�[�W)�ȂǂƎ咣����B
�@�������Ȃ���C�O���̂Ƃ���C�ō��ٔ��������P�T�N�S���P�W����@�씻���́C�@���s�ׂ����ꂽ���_�ł͌����ɔ����Ȃ��������A���̌�Ɍ������ω������ꍇ�̖@���s�ׂ̗L�����ɂ��āC�u�@���s�ׂ������ɔ����邱�Ƃ�ړI�Ƃ�����̂ł���Ƃ��Ė����ɂȂ邩�ǂ����́C�@���s�ׂ����ꂽ���_�̌����ɏƂ炵�Ĕ��f���ׂ��ł���B�������C������̖@���s�ׂ̌��͂́C���ʂ̋K�肪�Ȃ�����C�s�ד����̖@�߂ɏƂ炵�Ĕ��肷�ׂ����̂ł��邪(�ō��ُ��a�Q�X�N(�N)��Q�Q�R�����R�T�N�S���P�W����@�쌈��E���W�P�S���U���X�O�T��)�C���̗��́C�������@���s�ׂ̌�ɕω������ꍇ�ɂ����Ă����l�ɍl����ׂ��ł���C�@���s�ׂ̌�̌o�܂ɂ���Č����̓��e���ω������ꍇ�ł����Ă��C�s���ɗL���ł������@���s�ׂ������ɂȂ�����C�����ł������@���s�ׂ��L���ɂȂ����肷�邱�Ƃ͑����ł͂Ȃ�����ł���B�v�Ɣ������Ă���Ƃ���ł����āC���̗��́C���Ɩ����ӂ̖@���ɂ��Ó�����̂ł���C�������@���ɂ����č������̂��������Ɩ����ӂ̖@������{�����@��O��Ƃ��錻�݂̉��l�ςɂ���Ĕے肵�āC���ʂ̋K�肪�Ȃ��̂ɁC�����ӂł������s�ׂɂ��C�����ӔC��F�߂邱�Ƃ͖@�̉��߂Ƃ��ċ�����Ȃ��Ƃ����ׂ��ł���B
�@

��T�@���@�s��ׂɊւ���T�i�l��̎咣�ɂ���
�@
�@�P�@�T�i�l��̎咣
�@
�@�T�i�l��́C��T�i�l�̓w�[�O������R���Ɋ�Â����ۖ@��̍��ƐӔC�Ƃ��đ��Q�����ӔC������C�u�ې��Q�̋~�ςɊւ��闧�@�s��ׂ́C��L�ō��ٔ���(�ō��ُ��a�U�O�N�����̂��ƁF���p�Ғ�)�̔��f��ɏƂ炵�Ă��C�܂��ɍō��ٔ���̂����u��O�I�ȏꍇ�v�ɊY������v(�T�i�l���P�������ʂP�Q�T�y�[�W)�Ƃ��āC���@�s��ׂ���@�ł���|�咣����(���P�Q�Q�y�[�W�ȉ�)�B
�@
�@�Q�@��T�i�l�̔��_
�@
�@�������C�T�i�l��̎咣�������ł��邱�Ƃɂ��ẮC��T�i�l�̌��R�퍐��������(�V)�U�O�y�[�W�ȉ��ɏq�ׂ��Ƃ���ł��邩��C��������p����B
�@�T�i�l��́C���̎咣�̍����Ƃ��āC��T�i�l���w�[�O������R���Ɋ�Â����ۖ@��̍��ƐӔC�Ƃ��đ��Q�����ӔC���Ƃ��邪�C���̂悤�ȍ��ƐӔC�𗚍s���邽�߂̋�̓I�Ȗ@���𗧖@���ׂ���`���́C���@��C�����������Ē�߂��Ă��炸�C�܂��C���@���ߏ�C���̑��݂���`�I�ɖ����Ƃ������Ȃ�����C���̗��@�s��ׂ���@�Ƃ����]�n�͂Ȃ��B
�@�Ȃ��C�T�i�l�炪���R�ɂ����Ĉ��p�����R���n���ٔ������֎x�������P�O�N�S���Q�V������(������]�R�Ԉ��w���ɑ���⏞���@�̕s��ׂɊւ������)�́C�L�����ٕ����P�R�N�R���Q�X������(�����P�V�T�X���S�Q�y�[�W)�ɂ��������ꂽ�Ƃ���C����ɁC����ɑ����R������ɂ��㍐�y�я㍐�̐\���Ăɑ��āC�ō��ٔ�����O���@��́C�����P�T�N�R���Q�T���C�㍐���p�y�я㍐�s�̊e������s�����B
�@���̂悤�ɁC���@�s�ׂɂ��Ă̍��Ɣ����@�̈�@�����f��Ɋւ��锻��̘g�g�݂͊m���������̂Ƃ�����B
�@���������āC�T�i�l��̎咣�͎����ł���B
�@�Ȃ��C�������������Ɋւ���T�i�l��̎咣�ɂ��ẮC��L��W�Ŕ��_����B
�@

��U�@�s���s��ׂɊւ���T�i�l��̎咣�ɂ���
�@
�@�P�@�T�i�l��̎咣�̗v�|
�@
�@�T�i�l��́C�u�ې�����s������T�i�l�́C����̔Ƃ����푈�ƍ߂�^�ɔ��Ȃ��C��㒼���Ɏ����������Ȃ���Q�҂���~�ς���[�u���Ƃ�˂Ȃ�Ȃ������B�v(�T�i�l���P�������ʂP�T�T�y�[�W)�C�u��T�i�l�̍s���@�ւł�����t�E�E�E�́C�Ƃ肤��~�ϑ[�u��������(��㒼��ɂ����Ă����Ȃ��Ƃ����������𖾂��邱�Ƃ͉\�ł�����)�ɂ�������炸�E���̋~�ϑ[�u���Ƃ�Ȃ��������肩�C����Ƃ����ې�̐푈�ƍ߂��B�����������̂ł���B�v(���P�T�U�y�[�W)�C�u��T�i�l���t�̏�L��`���̕s���s�ɂ��C�T�i�l��ɂ́C�P�X�S�O�N��̖{���ې�ɂ���Q�̂ق��ɓ�Q�Ƃ������ׂ��ʌ̐V���Ȕ�Q(���_�I��ɂ̔{��)���������Ă���B�v(���y�[�W)�ȂǂƎ咣���邪�C�����̍T�i�l��̎咣�͗v����ɁC�T�i�l��̎咣����펞���̋����{�R�̈�@�s�ׂ��s�s�ׂƂ��āE��T�i�l���@����̍�`�����Ƃ�����̂Ǝv����B
�@�������Ȃ���C�T�i�l��̎咣�́C���ꎩ�̎����ł���B
�@
�@�Q�@��T�i�l�̔��_
�@
�@(1)�T�i�l��̎咣����悤�Ȗ@����̍�`�����T�i�l������Ȃ����Ƃɂ���
�@�������ɁC��s�s�ׂɊ�Â���`���������C�s��ׂ̈�@�s�ׂ��F�߂���ꍇ������(�Ⴆ�C���[���̒u���s�ׂɊւ���ō��ُ��a�U�Q�N�P���Q�Q����ꏬ�@�씻���E���W�S�P���P���P�V�y�[�W�B�ȉ��u�ō��ُ��a�U�Q�N�����v�Ƃ����B)�B
�@�������C�T�i�l��̑O�L�咣�́C�ō��ُ��a�U�Q�N�����̂悤�Ɂu��s�s�ׂɂ���đ��Q��������댯���������ҁv���u���Q�̔�����h�~����`�����v���ƂƁC�T�i�l�炪�{���ɂ����Ď咣����悤�Ɂu��s�s�ׂɂ���Ċ��ɔ�Q���������ҁv���u��Q�g���h�~����`�����v���ƂƂ��������Ă���B���Ȃ킿�C�O�҂͕s��ׂɂ��s�@�s�ׂ̖��ƂȂ邪�C��҂ɂ����ẮC���̐�s�s�ׂȂ���͕̂s�@�s�ׂ��̂��̂ł���C�g�呹�Q�ɂ��āC���ꂪ���Y�s�ׂƎ����I���ʊW�̂��邱�Ƃ�O��Ƃ��āC����ɑ��Q�����`�������ǂ����͑������ʊW(�ی�͈�)�̗L���̖��ƂȂ�̂ł����āC�s��ׂɂ��s�@�s�ׂ͖��ƂȂ�]�n���Ȃ��̂ł���B
�@�T�i�l��́C��s�s�ׂƂ��ċ����{�R�ɂ��ې�Ƃ�����T�i�l�̌��͓I�s�ׂɂ��s�@�s�ׂ��咣���Ă���̂ł��邩��C�{������҂̖��ł��邱�Ƃ͖��炩�ł���B
�@�����āC�T�i�l��̎咣�����`���͐�s�s�ׂ̑��݂�O��Ƃ�����̂ł���Ƃ���C���̍�`�������̍����ƂȂ��s�s�ׂƂ͕s�@�s�ׂ��̂��̂������̂ł��邩��C���ǁC�T�i�l��̐�s�s�ׂɂ���`������b�Ƃ��鍑�Ɣ����ӔC�̎咣�́C���Ɩ����ӂ̎���ɂ����錠�͓I�s�ׂɂ��s�@�s�אӔC���`��ς��Ď咣���Ă���ɂ����Ȃ����̂ł���B���̂悤�Ȏ咣�́C���Ɣ����@�����U�����u���̖@���{�s�O�̍s�ׂɂ��ƂÂ����Q�ɂ��ẮA�Ȃ��]�O�̗�ɂ��B�v�Ƃ��āC���Ɣ����@�{�s�O�̍s�ׂɊ�Â����Q�ɂ��č��Ƃ��ӔC��Ȃ����Ƃm�ɂ�����|�ɔ����邱�Ƃ͖��炩�ł����āC�����ł���B
�@
�@(2)���t���T�i�l��̎咣�����`���̎�̂ƂȂ鍪�������m�ɂ���Ă��Ȃ����Ƃɂ���
�@��L�̂Ƃ���C�T�i�l��́C�s���s��ׂɊ�Â������@��̑��Q���������ɂ������`���̎�̂́u���t�v�ł���Ǝ咣����B
�@�������Ȃ���C�T�i�l��́C���t�̍s�ׂ̍����@��̈�@���������邱�ƂȂ��C�u���v�̍�`����z�肵�C�������t�Ɋ���U�������ʁC���t��{���ɂ������`���̎�̂ł���Ǝ咣������̂ł����āC���̂悤�ȗ����͍����@�̊�{�I�Ȗ@�\���ɔ�������̂ł���C�����Ƃ��킴��Ȃ��B
�@���Ȃ킿�C�����@�P���P���͍����͌����c�̂̑�ʐӔC���K�肵�����̂ł��邩��C�������̍s�ׂ��������邱�ƂȂ��C�����g����s�I�ɋ`���S���邱�Ƃ͂��蓾�Ȃ��B����͊m����������̗���ł���(�ō��ُ��a�U�O�N�P�P���Q�P�������E���W�R�X���V���P�T�P�Q�y�[�W��)�C�����ł���ȏ�C�������̌X�̍����ɑ���E����̖@�I�`���̗L���y�ѓ��e�̊m��ƁC���̋`���ɌW��`���ᔽ�̗L���ɂ���āC���Y�������̍s�ׂ̈�@�����f�������ׂ��Ȃ̂ł���B
�@�܂��C�������̕s��ׂ������@�P���P���ɂ����Ĉ�@�Ƃ���邽�߂ɂ́C���Y�������ɍ�`��������(�ō��ٕ����R�N�S���Q�U����@�씻���E���W�S�T���S���U�T�R�y�[�W)�C���C���Y��`�����C�����������Y�����ɑ��ĕ����ʋ�̓I�ȐE����̖@�I�`���ƕ]���ł�����̂łȂ���Ȃ炸�C�s���̓����I��`���ł�������C�P�Ȃ钊�ۓI��ʓI�Ȃ��̂ł͑���Ȃ�(�Í�c���u���Ɣ����@�̗��_�v�V�X�y�[�W)�B
�@���������āC�T�i�l�炪�C���t�̕s��ׂ������@��̈�@�Ǝ咣����̂ł���C���t�������̋�̓I���ɂ����āC���Y�������ɑ��ĕ����ʋ�̓I�ȐE����̖@�I�`���Ɉᔽ�������ƁC���Ȃ킿�C���t�ɁC�X�̍T�i�l��ɑ���W�ŁC���̎��_�ł����Ȃ�{����̂�ׂ��@�I�`��������C���̋`���ᔽ�����������ɂ��āC���t�̐E�������Ɋ�Â��Ď咣���邱�Ƃ�v���C�����������T�i�l��̎咣�͎����ł���B
�@
�@�R�@����
�@
�@�ȏ�̂Ƃ���ł��邩��C��T�i�l�̍s���s��ׂ������T�i�l��̎咣�͎����ł���B
�@

��V�@�B���s�ׂ𗝗R�Ƃ��鍑�Ɣ��������ɂ���
�@
�@�T�i�l��́C�u�B���ɂ�錠���s�g�W�Q�̕s�@�s�ׁv�Ƒ肵�āC�T�i�l��̐�����r�˂��������������_���(�T�i�l���P�������ʂP�V�U�Ȃ����P�X�S�y�[�W)�B�@�������C�T�i�l��̏�L�咣�������ł��邱�Ƃ́C��T�i�l�̌��R�퍐��������(�V)�V�V�Ȃ����W�P�y�[�W�ŏq�ׂ��Ƃ���ł��邩��C��������p����B
�@

�@
�@�P�@�{�咣�̎�|
�@
�@���ɍT�i�l��̎咣���鋌���{�R�̍s�ׂɂ��C�T�i�l��ɉ��炩�̐����������������Ƃ��Ă��C���{���ƒ��ؖ����Ƃ̖�̕��a���(�ȉ��u���ؕ��a���v�Ƃ����B)�P�P���y�ѓ��{���Ƃ̕��a���(�ȉ��u�T���E�t�����V�X�R���a���v�Ƃ����B)�P�S��(b)�ɂ��푈�̐��s���ɓ��{���y�т��̍������Ƃ����s�����琶�������������̐������́C���ɂ���āu�����v����Ă���B���{�����{�ƒ��ؐl�����a�����{�̋�������(�ȉ��u�������������v�Ƃ����B)�T���ɂ����u�푈�����̐����v�́C������u�������v���܂ނ��̂Ƃ��āC���ؐl�����a�������́u�����v��錾�������̂ł���B
�@���������āC���̂悤�Ȑ������́C�T���E�t�����V�X�R���a���̓���������A�����̍����̐������Ɠ��l�ɁC���ɂ���ĕ�������Ă���C����Ɋ�Â������ɍL���ׂ��@����̋`�������ł��Ă���̂ŁC�~�ς����ۂ���邱�ƂɂȂ�B
�@���̓_�Ɋւ��ẮC�����P�S�N�S���Q�U���C�����n���ٔ����ɂ����āC�������������ɂ��Č���������̉��ɔ��f������������(�����n�ٕ����P�S�N�S���Q�U�������E����^�C���Y�P�O�X�W���Q�U�V�y�[�W�B�ȉ��u�����n�ٔ����v�Ƃ����B)���o����C�܂��C�T�i�l��́C�������������Ɋւ��C�Ǝ��̎咣��W�J���Ă���(�T�i�l���P�������ʂV�S�y�[�W�ȉ��C�P�Q�W�y�[�W�ȉ��Q��)���Ƃ���C��T�i�l�́C�{�������ʂɂ����āC�䂪���̐��O���̊�Ղ��Ȃ��C�u���{���ƒ��ؐl�����a���Ƃ̊Ԃ̕��a�F�D���v(�ȉ��u�������a�F�D���v�Ƃ����B)�y�уT���E�t�����V�X�R���a��Ɋւ��C���̖@�I�Ӌ`�ɂ��Ė��炩�ɂ��邱�ƂƂ���B
�@�Ȃ��C�T�i�l�炪�咣���鑹�Q�����������́C���ۖ@��������@����@�I������L���Ȃ��Ƃ����̂���T�i�l�̈�т����咣�ł���C�������������ɌW��咣�́C�{���i�ׂɂ����ẮC�\���I�Ȃ��̂ł���B
�@
�@�Q�@�����n�ٔ����ɂ���
�@
�@(1)�����n�ٔ����́C��������O��z�R������m(�ȉ��u�O��z�R�v�Ƃ����B)���o�c����Y�z�ɋ����A�s����J����������ꂽ�Ƃ��钆���l�炪�C���ƎO��z�R�ɑ��đ��Q�����𐿋��������ĂɊւ�����̂ł��邪�C���������̑��Q�����������Ɠ������������y�ѓ������a�F�D���Ƃ̊W�ɂ��āC�v�|���̂悤�ɔ��������B
�@
�@�@�@�@�������������T���́C�u���ؐl�����a�����{�́C����������(�}�})�̗F�D�̂��߂ɁC���{���ɑ��鑹�Q����(�}�})�̐�����������邱�Ƃ�錾����B�v�Ƃ���C�������a�F�D���ɂ����āB�������������̂T���̐錾�����i�ɏ��炳���ׂ����Ƃ��m�F����Ă���B
�@�@�A�@�������C�����C�T���E�t�����V�X�R���a�����������C�����́A�������������{�����{�ɑ��āC�����푈�ɂ����Ĕ�������Q�̔����𐿋�������Ƃ̗�����̂��Ă���C�܂��C���a�U�Q�N���납��C���������ł́A���{�����{�ɑ��ď�L���Q�̔������s������Ƃ̌������x�������悤�ɂȂ�C�����́u�K���T�����O���v(�}�})���C�����V�N�R���X��(�}�})�C�������������ŕ��������̂́C���ƊԂ̔����ł����āC�l�̔��������͊܂܂ꂸ�C�⏞�����͍����̌����ł���C���{�͊����ׂ��ł͂Ȃ��|�̌��������������ƂȂǂ̎�����l������ƁC�������������y�ѓ������a�F�D���ɂ��C���������ŗL�̑��Q�������������C�������{�ɂ���ĕ������ꂽ���ɂ��ẮB�@�I�ɂ��^�`���c����Ă������̂Ƃ��킴��Ȃ��B
�@�@�B�@���������āC������̑��Q�������������C�������������y�ѓ������a�F�D���ɂ��A�����ɕ������ꂽ���̂ƔF�߂邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B
�@
�@(2)�������Ȃ���C�����n�ٔ����́C�����������������������̉��߂ɂ��C�������������̓����҂ł�����{�����{�̌����𐳉������C������l�����Ă��Ȃ�����łȂ��C�������{�̌������������l�������ɁC�����炪�E�������킸���ȖT�ؓI�C�f�ГI�Ȏ���݂̂Ɉˋ����āC�����Ԃ̊O���W�̊�Ղ��Ȃ����������������̏����ӓI�ɉ��߂������̂ŁC���̔��f�͎����Ƃ��킴��Ȃ��B
�@
�@�R�@���������������Ɋւ��鐭�{����
�@
�@�䂪�����{�̌����́C��̑��ɌW�锅�����тɍ��Y�y�ѐ������̖��ɂ��ẮC�T���E�t�����V�X�R���a��̑��Ԃ̕��a���y�т��̑��֘A�����ɏ]���Đ����ɑΉ����Ă��Ă���Ƃ���ł���C������̓������Ƃ̊Ԃł͖@�I�ɉ����ς݂ł����āC���{�ƒ����Ƃ̊Ԃ̐������̖��ɂ��Ă��C�P�X�V�Q�N(���a�S�V�N)�X���Q�X���ɏ������ꂽ������������(�������T���́C�u���ؐl�����a�����{�́C�������������̗F�D�̂��߂ɁC���{���ɑ���푈�����̐�����������邱�Ƃ�錾����B�v�Ƃ���Ă���B)���o��C�l�̐������̖����܂߂đ��݂��Ă��炸�C���̂悤�ȔF���́C�������{�����l�ł���ƔF�����Ă���Ƃ������̂ł���B
�@���̂悤�Ȑ��{�̌����́C����̐R�c�ȂǗl�X�ȋ@��ɁC�J��Ԃ����炩�ɂ���Ă���Ƃ���ł���(����S�V���Ȃ�����T�O����)�C�܂��C�������������ɂ��ẮC�u���������Ɏ����ꂽ�����������i�ɏ��炳���ׂ����Ƃ��m�F���C�v�������a�F�D��������ꂽ���̂ł���(�����O��)�B
�@
�@�S�@��㏈���̘g�g�݂��Ȃ��T���E�t�����V�X�R���a���ɂ���
�@
�@(1)����E����̔������тɍ��Y�y�ѐ������̖��̉����̂����
�@
�@�A�@���������푈�ɂ���Q�́C�푈�̏��s�Ƃ͖��W�ɁC�푈�������݂̂Ȃ炸�C���̓��������݂̍����̍L�͈͂ɔ���������̂ł���C���ɑ�ꎟ���E����̋ߑ�̐푈�́C���ƊԂ̑S�ʐ푈�̌`�Ԃ��Ƃ�C���̔�Q�́C�S��������錋�ʂƂȂ��Ă���B
�@������푈�s�ׂɂ���Đ�������Q�̔������́C���̍u�a���ɂ���ĉ������}���邪�C��ʓI�ɔ������̑��푈�W���琶�����������̎�̂́C���ۖ@��̑��̍s�ׂ�萶�����������̎�̂Ɠ��l�C��Ƃł���C��O�I�ɏ��ŁC��Q�҂ł��鍑���l�ɑ��āC�������҂Ƃ��Ē��ڕK�v�ȑ[�u���Ƃ���@��݂����ꍇ�ȊO�́C�����l�̎���Q�́C���ۖ@�I�ɂ͍��Ƃ̔�Q�ł���C���Ƃ����荑�ɑ��ČŗL�̐��������s�g���邱�ƂɂȂ�(���]�[�l�Y�E���{�u�a����̌����Q�S�W�y�[�W�Q�ƁE����T�P����)�B
�@��ꎟ���E����ɒ������ꂽ�x���T�C�����ɂ����ẮC�h�C�c�́C�����ԓ��ɁC����C�C��y�ы̍U���ɂ�蓯���E�A�����̍����₻�̍��Y�ɑ��ĉ�����ꂽ��̑��Q��⏞���ׂ����̂Ƃ���(�����Q�R�Q��)�C���Ɩ�̔����ӔC���F�߂�ꂽ�ق��C�������ٍٔ����̐��x���K�肵�C�����l���h�C�c�ɑ��āC�������ٍٔ����ɒ�i���āC�l�I�ȕ��I���Q�̔������������邱�Ƃ�F�߂�(���]�E�O�f���{�u�a����̌����Q�S�X�y�[�W�Q�ƁE����T�P����)�B
�@�������C�����ɂ�锅���ӔC�́C�P�ɓ����E�A�����̔�������Q�������悤�Ƃ����ϔO�ɂƂǂ܂�C�h�C�c�̌o�ϔ\�͂Ȃǂ��������̂ł��������߁C�������z�͋��z�ƂȂ�C���̌��ʁC�h�C�c�o�ς̔j�]�C�q�b�g���[�����̏o���������C�x���T�C����̂��̂��������ĕ����̉Ύ�����̌�Ɏc�����ʂƂȂ����B
�@
�@�C�@����E����ɂ����ẮC���̂悤�ȃx���T�C�����ɂ����鎸�s�̔��Ȃ���C��㔅�����̉����ɓ������āC�����������̗��Q��������ŁC�����������Ƌy�т��̍������������Q����̂Ƃ��ĂƂ炦�C���荑�Ɠ���I�Ɍ����邱�ƂƂ��Ĕ������ɍŏI�I�Ȍ�����}�邱�ƂƂ��A���̌��̌��ʁC�����Ɏ���u�a��́C���̍��ۓI�g�g�݂��\�z�����ŁC�K�����Ó��ȉ�����ڂ������̂ƈʒu�Â����C�������y�т��̍����̑��݂̐^�̈Ӗ��ł̘a���̈�Ƃ��āC���̌�̓������y�ё��݂̍����̗F�D�W�̊�ՂƂȂ邱�Ƃ�ړI�Ƃ����B
�@���̂��߁C���̂悤�ȍu�a���̘g�g�݂̉��ł́C��㔅���́C�����Ƃ��č��ƊԂ̒��ڏ����C���͋��������̋��G�����Y�ɂ�閞���̕��@�ɂ�邱�ƂƂ��ĉ������}���C�X�̍����̔�Q�ɂ��ẮC�����Ƃ��āC�����������Y�������̍������Ƃ��āC�e�������̍��̍���������l�����C�~�ϗ��@���s���Ȃǂ��ĉ������}���Ă���(���]�E�O�f���{�u�a����̌����Q�T�O�y�[�W�Q�ƁE����T�P����)�B
�@�Ȃ��C���̂悤�ȋߑ�푈�ɂ������㏈���̘g�g�݂݂̍���ɂ��ẮC�I�����_����������E��풆�ɓ��{�R�̍s�ׂɂ���Ď���Q�ɂ��āC���{���ɑ��đ��Q�����𐿋��������ĂɊւ��铌�������ٔ����̔���(�������ٕ����P�R�N�P�O���P�P�������E�����P�V�U�X���U�P�y�[�W)�ɂ����Ă��C�u���Ƃ݂̂ɑ��Q������������F�߂邱�Ƃɂ���Ă����C�����̖����C��Q�ҊԂɌ����ɁC�܂��C��㐢�E�̎���ɑ����ēK���ɉ������邱�Ƃ��ł���Ƃ����ׂ��ł���B�܂��C�푈�ɂ���Q�̉����Ƃ������̂́C�푈��Ԃ��I��点�āC�푈��Ԃɂ��������Ƌy�т��̍����̊Ԃɕ��a�I�ȊW��z�����߂ɂ������̂ł��邪�C���̂悤�Ȍ��v���������邽�߂ɂ��C���Ƃ���Q����̂Ƃ��ĂƂ炦�āC����I�ɑ��荑�ɔ����𐿋����C�O�������o�āC���ӂɒB���邱�Ƃ̕����C�͂邩�ɂ��̖ړI�ɉ����̂ł���B�����C��Q�҂��C���ꂼ��ʂɐ����ł���Ƃ���ƁC���Ƃ́C�ʂɈϔC�������̂Ɍ���C��Q�҂�㗝���đ��荑�Ƃ̌��ɖ]�܂˂Ȃ�Ȃ��B�������C����ł́C�S�Ă̔�Q�҂̔�Q�ɂ��āC�ꋓ�ɉ������邱�Ƃ��ł��Ȃ��B���̂��߂ɁC�푈��Ԃɂ��������Ƌy�э����̊ԂŐ푈��Ԃ��I��点�邱�Ƃ��C�ɂ߂č���ɂȂ�ł��낤�B�푈��Ԃ̏I���́C��퓖���҂݂̂Ȃ炸�C�����̊W���Ƃ��̍����ɂƂ��Ă��K�v�Ȃ��Ƃł���B����͐�㐢�E�ɂƂ��āC�d�v�Ȍ��v�ł����āC���ꂪ�ꕔ�̎҂̎��v��D�悷�邱�Ƃɂ���āC�Q����Ă͂Ȃ�Ȃ��B��������ƁC��Q�Ҍl�ɉ��Q���ɑ��钼�ڂ̔�����������F�߂邱�Ƃ́C�������Ė��G�ɂ���Ƃ����ׂ��ł���B�v�Ɣ�������(�Y���ӏ������V�O�y�[�W�S�i������V�P�v�W�P�i��)�C���l�̗�����������Ă���B
�@
�@(2)�T���E�t�����V�X�R���a���ɂ������̊�{�I���e
�@
�@�A�@�T���E�t�����V�X�R���a���̊�{�I���e
�@�����́C����E���̘A�����Ɖ䂪���̊Ԃ̐푈��Ԃ��I�������C�A�����ō��i�ߊ��̐����̉��ɒu���ꂽ�䂪���̎匠�����S�ɉ���ƂƂ��ɁC�푈��Ԃ̑��݂̌��ʂƂ��Ė����̖��ł������̈�C�����C�o�ϕ��тɐ������y�э��Y�Ȃǂ̖����ŏI�I�ɉ������邽�߂ɒ������ꂽ���̂ł���(�O���C�P��)�B
�@
�@�C�@�T���E�t�����V�X�R���a���ɂ�������{�̔����ӔC
�@���̂����C�������y�э��Y�Ɋւ������(��T��)�ɂ����āC�푈���ɐ������������Q�y�ы�ɂɑ��āC���{�����A�����ɔ������x�����ׂ����Ƃ����F���ꂽ���C�����ɁC���ׂĂ̑��Q�y�ы�ɂɑ��Ċ��S�Ȕ������s���������ɑ��̍��𗚍s�����邽�߂ɂ́C���{�̎����͏[���ł͂Ȃ����Ƃ����F���ꂽ(�P�S��(a�j����)�B���̂��߁C�䂪���́C�������푈���ɐ������������ׂĂ̑��Q�y�ы�ɂɐ��m�ɑΉ����銮�S�Ȕ������s�����Ƃ܂ł͋��߂�ꂸ�C�ȉ��ɏq�ׂ�`�����𗚍s���邱�Ƃ����߂�ꂽ�B
�@�@�@�@���{���́C���̗̈悪���{�R���ɂ���Đ�̂���C���C���{���ɂ���đ��Q��^����ꂽ�A�����̂����C��]���鍑�Ƃ̊ԂŁC���Y�C���D���g�����̑��̍�Ƃɂ�������{�l�̖���邱��(���������)�v�ɂ���āC�^�������Q�Y�A�����ɕ⏞���邽�߂ɁC���݂₩�Ɍ����J�n���Ȃ���Ȃ�Ȃ�(�P�S��(a)�P)�B
�@�@�A�@���{���́C�O���y�ї̎����Y���C���̗�O�������B�e�A���������̊NJ����ɗL������{���y�ѓ��{�������̍��Y�C�����y�ї��v���������������C���u���C���Z���C���̑����炩�̕��@�ŏ������邱�Ƃ�F�߂Ȃ���Ȃ�Ȃ�(�P�S��(a)�Q)�B
�@�@�@�@���{���́C���{���̕ߗ��ł������Ԃɕs���ȋ��������A�����R���̍\�����ɑ��鏞���������]�̕\���Ƃ��āC���������͘A�����Ɛ푈��Ԃɂ��������ɂ�����{���y�т��̍����̎��Y���͂���Ɠ����̂��̂�ԏ\�����ۈψ���Ɉ����n���Ȃ���Ȃ�Ȃ�(�P�U��)�B
�@
�@�E�@�T���E�t�����V�X�R���a���Ɋ�Â����{�������������������̋K��ɏ]���āC�䂪���́C�A�����ɑ��āC���z�̎x�����s���Ă���B
�@
�@(�)�@���Ȃ킿�C��L�C�@�̂P�S��(a)�P�Ɋ�Â������ɂ��ẮC�t�B���s���y�уx�g�i���Ƃ̊ԂŔ�����������J�n���C�P�X�T�U�N(���a�R�P�N)�T���Ƀt�B���s���Ƃ̊ԂŁC�܂��C�P�X�T�X�N(���a�R�S�N)�T���ɂ̓x�g�i���Ƃ̊Ԃł���������̏����Ɏ���C�����̋���ɏ]���āC�t�B���s���ɑ��Ă͂T���T�O�O�O���h���C�܂��C�x�g�i���ɑ��ẮC�R�X�O�O���h�������̖y�ѐ��Y�������(������茤����ҁE���{�̔����P�P�Ȃ����P�S�y�[�W�E����T�Q����)�B
�@�����C�č��C�p���y�уI�����_���C�{���Ɋ�Â��Ĕ����������Ȃ�����A�����́C��������������������B
�@
�@(�)�@��L�C�A�̂P�S��(a)�Q�Ɋ�Â��A�������ɏ��݂������Y�̕����ɂ��ẮC�A�����̈���ɂ����S�O���h���̓��{�l���Y�͘A�������{�ɖv������C���̎��v�͊e���̍����@�ɏ]���ĘA�����̍����ɕ��z���ꂽ(�Q�O�O�O�N�W���P�V���t���č����{�́u���Q�W�������v�M��W�y�[�W�E����T�R����)�B���̖�S�O���h��(���{�~�ɂ��Ė�P���S�S�O�O���~)�Ƃ������{�l���Y�́C�䂪���̏��a�Q�U�N�x�̈�ʉ�v�̍Γ��ł����W�X�T�S���~���͂邩�ɏ�����z�ł���(�����{���v�NJ��E��T����{���v�N�ӂR�U�S�y�[�W�E����T�S����)�C�č��̏ꍇ�ɂ́C�č��̈���ɂ����č�����������ꂽ��X�O�O�O���h��(�P�X�T�Q�N�̕]��)�̓��{���Y�̂����C��Q�O�O�O���h�����C�P�X�S�W�N�̐푈�������@(the War Claims Act of �P�X�S�W)�Ɋ�Â��~�ϐ��x�Ɋ�Â��Č����ҁC�s���y�ѐ푈�ߗ��̐��������������邽�߂Ɏg�p���ꂽ�B
�@
�@(�)�@�O�L�C�B�̂P�U���Ɋ�Â��āC�䂪�����{�́C�������y�јA�����̓G���ɂ�����{���Y�Ɠ����̎����Ƃ��āC���z�S�T�O���|���h�̌��������ېԏ\�����ۈψ���Ɉ����n���C����͓��ψ����ʂ��āC�I�[�X�g�����A�C�x���M�[�C�J���{�f�B�A�C�J�i�_�C�`���C�t�����X�C�m���E�F�[�C�j���[�W�[�����h�C�p�L�X�^���C�I�����_�C�t�B���s���C�C�M���X�C�V���A�C�x�g�i���̂P�S�����̌v��Q�O���l�̌��ߗ��ɕ��z���ꂽ�B
�@
�@(�)�@����ɁC��q����悤�ɁC�T���E�t�����V�X�R���a���̓������ƂȂ�Ȃ������������A�����P�S��(a)�Q�̗��v����̂Ƃ��ꂽ���Ƃ���C�����̈���ɂ�����{���y�ѓ��{�����̎��Y�̏������F�߂�ꂽ(�����Q�P��)�B
�@
�@(�)�@���N�ɂ��ẮA�T���E�t�����V�X�R���a���Q��(a)�ɂ����āC�u���{���́C���N�̓Ɨ������F���āC�ϏF���C�������y�щT�˓����܂ޒ��N�ɑ��邷�ׂĂ̌����C�����y�ѐ��������������B�v�ƋK�肵�C�����S��(a)�́C�u���{���y�т��̍����̍��Y�ő����Ɍf����n��ɂ�����̕��тɓ��{���y�т��̍����̐�����(�����܂ށB)�Ō��ɂ����̒n��̎{�����s���Ă��铖�Njy�т����̏Z��(�@�l���܂ށB)�ɑ�����̂̏������тɓ��{���ɂ����邱���̓��Njy�яZ���̍��Y���тɓ��{���y�т��̍����ɑ��邱���̓��Njy�яZ���̐�����(�����܂ށB)�̏����́C���{���Ƃ����̓��ǂƂ̊Ԃ̓��ʎ�ɂ̎��Ƃ���B�v�ƋK�肵�Ă����B�݊ؕČR���{�́C�P�X�S�T�N(���a�Q�O�N)�P�Q���U���t���R�ߑ�R�R���Q���ɂ��C���N�����ɂ��������{���y�ѓ��{�����̍��Y�̂����C�R�W�x���ȓ�̂��ׂĂ̓��{���y�ѓ��{�����̍��Y�N�X���Q�T���t���������Ď擾���C���̌�C���̂悤�ɂ��Ď擾�������Y���C�P�X�S�W�N(���a�Q�R�N)�X���P�P���t���́u�����y�э��Y�Ɋւ���Ċ؊Ԃ̍ŏ��̎�Ɂv�T���ɂ���Ċ؍����{�Ɉ����n���Ă����B�����āC�䂪���́C�T���E�t�����V�X�R���a���S��(b)�ɂ��C���N�������ɂ���C�č����{�̎w�߂ɏ]���čs��ꂽ���{���y�ѓ��{�����̍��Y�ɂ��Ă̏����̌��͂����F���Ȃ���Ȃ�Ȃ����ƂƂȂ���(�J�c���Z�ق��E���؏��ƍ����@�̉��(���̖@�߂R�P�V���ʍ�)�U�T�y�[�W�E����T�T����)�B
�@�P�X�S�U�N(���a�Q�P�N)�X���C�O���ȋy�ё呠�Ȃ̋��ǂŐݒu���ꂽ�݊O���Y������ɂ��u�䍑�݊O���Y�]���z���v�v�ɂ��ƁC�I�퓖���C���N�ɑ��݂������{���Y�̋K�͂́C�V�O�Q���T�U�O�O���~�ƕ���Ă���(�˖{�F�E�u���⏞���ꑍ�_(1)�v�����Ə���Q�Q�W���V�y�[�W�E����T�U����)�B���a�Q�P�N�x�̉䂪����ʉ�v�̍Γ��́C�P�P�W�W���~�]��ł���C�����N�x�̉䂪���̍��������Y�́C�S�V�S�O���~�]��ł�����(�O�f���{���v�N�ӂR�T�X�C�R�U�S�y�[�W�E����T�S����)�B
�@�Ȃ��C���̌�C�䂪���́C�؍��Ƃ̊Ԃɂ����ẮC�T���E�t�����V�X�R���a���S��(a)�Ɋ�Â����ʎ�ɂ̒����̂��߁C�������������P�R�N�̒����ɂ킽������o�āC���a�S�O�N�P�Q���ɁC���؊�{���C���ؐ�����������n�߂Ƃ���P���C�S����C�P�����������������Ɏ����B���̓��ؐ���������Ɋ�Â��C�䂪���́C�؍��ɑ��āC�R���h���̖������^�y�тQ���h���̒����ᗘ�̑ݕt�Ƃ����c��ȋ��z�̎������^���s��(���a�S�O�N�P�Q�������C�䂪���̊O�ݏ������͖�Q�P���h��(�������Z���v����P�V�U���k�呠�ȕҁl)�C����ƕ��s���Đ����������ŏI�I�ɉ������邱�ƂƂ��C���ؐ���������Q���P�ɂ����āC�u�����́C�����y�т��̍���(�@�l���܂ށB)�̍��Y�C�����y�ї��v���тɗ����y�т��̍����̊Ԃ̐������Ɋւ����肪�C�P�X�T�P�N�X���W���ɃT���E�t�����V�X�R�s�ŏ������ꂽ���{���Ƃ̕��a����S��(a)�ɋK�肳�ꂽ���̂��܂߂āC���S���ŏI�I�ɉ������ꂽ���ƂƂȂ邱�Ƃ��m�F����B�v�ƋK�肳�ꂽ�̂ł���B
�@�؍��ł́C������āC�P�X�U�U�N(���a�S�P�N)�Q���ɁC�u�����������̉^�p�y�ъǗ��Ɋւ���@���v���C�P�X�V�P�N(���a�S�U�N)�P���ɂ́C�u�Γ����Ԑ������\���Ɋւ���@���v���C�����āC�P�X�V�S�N(���a�S�X�N)�P�Q���ɂ́C�u�Γ����Ԑ������⏞�Ɋւ���@���v�����ꂼ�ꐧ�肵�C�����⏞�����{�����̂ł���B
�@
�@�G�@�T���E�t�����V�X�R���a�������̎���
�@���̂悤�ɁC�A�����݂̂Ȃ炸�������y�јA�����̓G���̗̈���ɂ�����{���Y�̘A�����ɂ�鏈����e�F���C����ɓ��l�ȏ����̌����𒆍��ɗ^����ƂƂ��ɁC���N�ɂ��ẮC�č��R���{�����{���Y�ɂ��čs���������̌��͂����F���Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ƃ����̂́C�ߋ��̓���̏��ɂ͗�����Ȃ����������e�̋K��ł��邪�C���{�����{�Ƃ��ẮC���{�����A�����R�ɂ���̂������ł������Ɨ����C�匠���ƂƂ��āC���ێЉ�ɕ��A������C�A�����ƗF�D��g�W�ɓ��邽�߂ɂ́C������ߍ��ȏ���������邱�Ƃ���ނȂ��ƍl���āC�������������Ɏ������̂ł���B
�@���̂��Ƃ́C�P�X�T�P�N(���a�Q�U�N)�X���V���̃T���E�t�����V�X�R�u�a��c�̑�W��S�̉�c�ɂ�����C��ȑS���̓��t������b�g�c�̕��a����������̒��ŁA�u�����ɒ��ꂽ���a���́C�����I�ȏ�����I�ȏ������܂܂��C�킪�����ɍP�v�I�Ȑ������ۂ��邱�ƂȂ��C���{�Ɋ��S�Ȏ匠�ƕ����Ǝ��R�����C���{�����R�������̈���Ƃ��č��ێЉ�}������̂ł���܂��B�v�u���{�͂��̏��ɂ���đS�̓y�̂S�T�p�[�Z���g�����̎����ƂƂ��ɑr������̂ł���܂��B�W�S�O�O���ɋy�ԓ��{�̐l���͎c��̒n��ɕ����߂��C�������C���̒n��͐푈�̂��߂ɍr�p���C��v�s�s�͏Ď����܂����B�܂��C���̕��a���́C����ȍ݊O���Y����{�����苎��܂��B����P�S���ɂ��ΐ푈�̂��߂ɉ��̑��Q���Ȃ��������܂ł����{�l�̌l���Y��ڎ����錠����^�����܂��B�����̔@���ɂ��ĂȂ����̘A�����ɕ��S�����߂Ȃ��œ���̘A�����ɔ������x�������Ƃ��ł��邩�ǂ����C�r�����O�������̂ł���܂��B�������C���{�͂��łɏ�����������ȏ�͐��ӂ������āC���ꂪ�`���𗚍s����Ƃ��錈�ӂł���܂��B�킽�����́C���{������ȏ����̂��ƂɂȂ����̉~���ȉ����̂��߂ɂȂ���Ƃ���w�͂ɑ��āC�W�����������Ǝx����^�����邱�Ƃ�v��������̂ł���܂��B�v�Əq�ׂĂ���(�����F�Y�E���{�O���j�Q�V�T���t�����V�X�R���a���Q�V�Q�Ȃ����Q�V�W�y�[�W�E����T�V����)���Ƃ�������������m�邱�Ƃ��ł���B
�@���̂悤�ɂ��āC�䂪���́C��̑��ɌW�锅�����тɍ��Y�y�ѐ������̖����������邽�߁C�A�����Ƃ̊ԂŁC�T���E�t�����V�X�R���a��̑��Ԃ̕��a���y�т��̑��֘A�����ɏ]���Đ����ɑΉ����Ă����̂ł���B�Ȃ��C����E���̍ۂ̓������ł������C�^���A�����A�����Ƃ̊Ԃŕ��a����������āC������}���Ă���B�䂪���̐�㏈���ɂ��āC�h�C�c�Ɣ�r����邱�Ƃ����邪�C�h�C�c�ɂ��ẮC��㓌���ɕ��f����Ă������Ƃ�����C�A�����Ƃ̊Ԃŕ��a��������ł����C�䂪���̂悤�ȕ��a���Ɋ�Â����Ə��ł̈ꊇ�����̕����͍̂蓾�Ȃ�����(���݂ɂ����Ă��C�h�C�c�͘A�����Ƃ̊ԂŁv�������̂��߂̕��a����������ĂȂ�)�B���f�����܂ő�����������Ȃ��ɂ����āC�����h�C�c�̓i�`�X�ɂ�锗�Q�̋]���҂ɑ���l�⏞�̌`�ő��z�̎x�����s�����Ƃ����肵�C�����Ɏ����Ă���B���̂悤�ɁC�h�C�c�Ɠ��{�Ƃł́C���ꂼ��u���ꂽ���ۊ����قȂ�̂ł����āC����ꎋ���Ę_���邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B
�@
�@�I�@���������������ɂ���
�@�ȏ�̂悤�ȃT���E�t�����V�X�R���a����̋`���𗚍s����̂ƈ������ɁC�����P�S��(b)�ł́C�u�A�����́C�A�����̂��ׂĂ̔����������C�푈�̐��s���ɓ��{���y�т��̍������Ƃ����s�����琶�����A�����y�т��̍����̑��̐��������тɐ�̂̒��ڌR���o��Ɋւ���A�����̐��������������B�v�ƋK�肳�ꂽ�B
�@
�@(�)�@���̂P�S��(b)�̐������̕����̈Ӗ����߂ɂ��āC�T���E�t�����V�X�R���a��c�ɂ����āC�I�����_��\�c����C�ȉ��̂Ƃ���̖�肪��N���ꂽ(�����E�O�f���{�O���j�R�O�P�Ȃ����R�O�R�y�[�W�E����T�V����)�B
�@���Ȃ킿�C�I�����_��\�c�́C�T���E�t�����V�X�R���a��c�̎������x���̌��ɂ����āC�č��̃_���X��\��ʂ��āC���{��\�ɁC�@���a���P�S��(b)�ɂ��A�����́u�푈���s���ɓ��{���y�т��̍������Ƃ����s�����琶�����v�A�������̐������̕����͍����̎��������ł�������́C���Ȃ킿�C�����v���̌��ʂ������̂ł͂Ȃ��C�I�����_�����͓��{�@��ɓ��{�����{���͓��{������i�ǂł��邪�C�I�����_���{�͏��ケ����x�����鍪���������Ȃ��Ƃ̈Ӗ��ł���C�Ƃ������߂ɓ��ӂ����߁C�܂��C�A�푈���C�I�����_�̓��C���h�œ��{�R�ɗ}�����ꂽ��ʕ����ɑ���⏞���ɂ��āC�I�����_���{�͓�����̗��R����C���_�Ƃ��ĂłȂ��l���_�Ƃ��āC�D�ӓI�ɍl�����邱�Ƃ����ʂŖ��炩�ɂ��邱�Ƃ�v�]�����B
�@
�@(�)�@����ɑ��C�䂪�����Ƃ��ẮC�@�̖��ɂ��āC�@�I�ɏ����ł��Ȃ��|���_���C�T���E�t�����V�X�R���a���P�S��(b)�́C�����̎��������ł�������́C���Ȃ킿�C�����v���̌��ʂ������̂ł͂Ȃ��C�������̌��ʍ����͐���������{�����{���͓��{�����ɑ��ĒNj����Ă��邱�Ƃ͂ł��Ȃ��Ȃ邱�ƂɂƂǂ܂�|�̉��߂��Ƃ�C��������ȂŊm�F����p�ӂ�����|���_���X��\�ɓ`�����B�_���X��\�́C�䂪�����̎咣���āC�u�~�ςȂ��������B�悭���邱�Ƃ��B�v�ƌ����Ȃ���m�[�g���h���t�g�����Ƃ����B
�@���̌�C�I�����_��\���C�䂪���̏��ȈĂɓ��ӂ��Ȃ����Ƃ����炩�ƂȂ�C�_���X��\�ƃI�����_��\���Ƃ̊Ԃ̌����s��ꂽ�B���̌��ʁC�P�X�T�P�N(���a�Q�U�N)�X���T���ƂȂ�C�����I�����_������]�������Ȃ̂��Ƃ������߁C�I�����_��\���c��ŁC��ʒq�̒��ł��̊�]���q�ׁC����ɑ��C�䂪���́C���̍l���C���Ȃ킿�C�@�̖��ɂ��ẮC�䂪���̎咣�ǂ���C�����͂���Nj~�ς͂Ȃ��Ƃ���������\�����C�A�̖��ɂ��Ă͍l�����錾����^���������v�]�̑��݂͔F�߂邱�Ƃ����ʂŐ���ɕԎ�����Ƃ��������ʼn������邱�Ƃɗ�������(�����E�O�f���{�O���j�R�O�Q�C�R�O�R�y�[�W�E����T�V����)�B
�@
�@(�)�@�����ŁC�I�����_��\�ł���X�e�B�b�J�[�O����b�́C�����U���ߌ�̑�T��S�̉�c�̈�ʒq�ɂ����āC�O�L�I�����_�̊�]���q��(�����E�O�f���{�O���j�Q�U�P�C�Q�U�Q�y�[�W�E����T�V����)�C�����V���C���O����b�́C��ȑS���̋g�c�ɑ��C���̂悤�ȏ��Ȃ𑗂����B
�@�u�{��b�́C����{��b�����a��c�̋c���y�ъe����\�ɑ��čs���������̎��̔@����߂ɑ��C�t���̒��ӂ����N�������ƍl���܂��B
�@�A�������������邱�Ƃɓ��ӂ��Ă����P�S��b���́w�A�����y�т��̍����̐������x�̉��߂ɂ��āC��̋^�₪�����܂����B�킪���{�̌����Ƃ��ẮC��P�S��b���́C���m�Ȃ���ߏ�C�e�A�������{���������̎��I�������D���邱�Ƃ��܂��Ă��炸�C�]���Ė{�����C���̎퐿���������ł��邱�ƂɂȂ�Ȃ����̂ƍl���܂��B�{���́C�킪���{���n�ߎ�̐��{�́C�������̎��L���Y�̖v�����͎��p�Ɋւ��錛�@��y�ё��̖@����̈��̐��ɂ��邽�߁C�d�v�ł���܂��B�����{�����{���C�ǐS�Ȃ����ǎ�����X��i�̖��Ƃ��āC�����I�Ɏ���̕��@�ŏ��u���邱�Ƃ�]�ނƎv����C�A�������̂���^�C�v�̎��I������������܂��B���͊t�����{���Ɋւ��C�{��c�I���O�ɁC���̌������q�ׂ���K�r�̎���ƍl���܂��B�v(�P�X�T�P�N�X���V���t���I�����_�E�X�e�B�b�J�[�O�������{�E�g�c���ď��ȁE����T�W����)�B
�@����ɑ��C��ȑS���̋g�c�́C�����W���t���ŁC�X�e�B�b�J�[�O����b�ɑ��āC���̂悤�ȏ��Ȃ𑗂��āC���a���P�S��(b)�Ɋւ���䂪���̉��߂𖾂炩�ɂ����B
�@�u�E�t���̏��Ȃɏq�ׂ�ꂽ���Ɋւ��C�{��b�͎��̂Ƃ���\���q�ׂ���h��L���܂��B
�@�I�����_�����{�̎w�E���ꂽ���@��̖@�I����ɂ��ẮC���{�����{�́C�I�����_�����{���{���̏����ɂ���Ď������̎��I�������D���C���̌��ʖ{�����́C�����鐿�����͂������݂��Ȃ��Ȃ���̂Ƃ͍l���܂���B�������Ȃ���C���{�����{�́C�{���̉��ɂ����ĘA���������́A�����鐿�����ɂ������邱�Ƃ͂ł��Ȃ��ł��낤�Ƃ������ƁC�������I�����_�����{����������@���C���{�����{�������I�ɏ��u���邱�Ƃ���]����ł��낤�A���������̂���^�C�v�̎��I�����������݂��邱�Ƃ��C�����Ɏw�E���܂��B�v(�P�X�T�P�N�X���W���t�����{��ȑS���g�c���I�����_��ȑS���X�e�B�b�J�[�O�����ď��ȁE����T�X����)
�@���̂悤�ȗ�����O��ɁC�A�����y�т��̍����Ɠ��{���y�т��̍����Ƃ̑��݂̐������́C���a���ɂ��C���S���ŏI�I�ɉ������ꂽ�B
�@
�@(�)�@�č��_���X��\�́C���a���̔������ɂ��āC�u���O���́C���{�����̓����o�Ϗ�Ԃ����P���C�������x������悤�ɂȂ邩������Ȃ��Ƃ����\�����\���ɔF�����Ă����B����ɂ�������炸�C���O���y�јA�����́C�P�X�T�P�N�ɁC�A�����̐��{�y�т��̍����̂��ׂĂ̐����������a���Ŋ��S�Ɋ��ŏI�I�ɉ�������邱�Ƃ��S�ʓI�ʼni���I�ȕ��a�ɂ͕K�v�ł���ƌ��肵���B�v�Əq�ׂĂ���(�O�f�č����{�u���Q�W�������v�M��P�W�y�[�W�E����T�R����)�B
�@���̕��a���ɂ���āC�A�����ō��i�ߊ��̐����̉��ɒu����Ă����䂪���̎匠�͉��C���̊�Ղɗ����āC�䂪���͂��̌�̐����I�y�ьo�ϓI���W���ʂ������Ƃ��ł����̂ł���B
�@
�@(�)�@�܂��C�T���E�t�����V�X�R���a���ɂ����ẮC�A�����y�т��̍����ɑ�����{���y�ѓ��{�����̔����������ɂ��Ă��C�����P�X��(a)�ɂ���āC�u���{���́C�푈���琶���C���͐푈��Ԃ����݂������߂ɂƂ�ꂽ�s�����琶�����A�����y�т��̍����ɑ�����{���y�т��̍����̂��ׂĂ̐�����������v�����B
�@
�@(3)�T���E�t�����V�X�R���a���P�S��(b)�̉���
�@
�@�A�@�T���E�t�����V�X�R���a���P�S��(b)�̖@�I����
�@�A�����y�т��̍����Ɠ��{���y�т��̍����Ƃ̑��݂̐������́B�T���E�t�����V�X�R���a���ɂ��C���S���ŏI�I�ɉ������ꂽ���̂ł��邪�C���̖@�I���ʂ̓��e�͎��̂Ƃ���ł���B
�@
�@(�) �A�����̐������ɑ������
�@�A���������{���y�ѓ��{�����ɗL���Ă����������́C�������ɂ���ĕ������ꂽ�B���̐������ɂ́C�펞���ۖ@�ᔽ���ɂ�鍑�ۖ@��̐������݂̂Ȃ炸�C�e�������@�Ɋ�Â������܂܂�Ă���(�����S�����Q��)�B
�@
�@(�) �A���������̐������ɑ������
�@�T���E�t�����V�X�R���a���P�S��(b)�̕�����C�A���������̐�����(�����܂ށB)���A�����ɂ���āu�����v���ꂽ�B���̖@�I�Ӌ`�͎��̂Ƃ���ł���B
�@�@�@�@�܂��C�펞���ۖ@�Ɋ�Â��N���C���ɂ��Ă݂�C�A�������������{���̐펞���ۖ@�ᔽ�ɂ�葹�Q�������Ƃ��Ă��C���ۖ@��C�l�ɂ͖@��̐����F�߂��Ȃ��̂������ł���C�펞���ۖ@�ɂ͗�O�I�ɂ����F�߂�K��͂Ȃ��̂ł��邩��C�A���������́C�펞���ۖ@�ᔽ�𗝗R�Ƃ��āC���{���ɑ��āC���Ƃ��ƍ��ۖ@��̐������s�����Ƃ͂ł��Ȃ��B
�@�@�A�@���ɁC�e�������@�Ɋ�Â��������Ȃ������ɂ��Ă݂�C�A�����������e�������@����{�����͓��{�����ɑ��ėL���鐿�����̕��a���ɂ��u�����v���ǂ̂悤�ȈӋ`��L���邩�͓����̍����@�I���̖͂��ł��邪�C�䂪���ɂ����ẮC���a���̓������ɂ���āC�����̐������Ȃ������Ɋ�Â������ɉ����ׂ��@����̋`�������ł������̂Ƃ��ꂽ�̂ł���C���̌��ʁC�~�ς����ۂ���邱�ƂɂȂ�B
�@���Ȃ킿�C���a��e�������@�Ɋ�Â������܂ސ�����(�����S��(a)�j�y�э��Y�̖����ŏI�I�ɉ������邽�߂ɒ������ꂽ���̂ł��邱�Ƃ��炷���(�O�L(2)�A)�C��L�������Ȃ������ɂ��ĉ���̏��������Ȃ��������̂ƍl���邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B
�@�����āC�O�L�̃I�����_��\�Ɠ��{��\�Ƃ̌��o�߂�����ƁC�䂪���̓I�����_���{�ɁC���̌��ʍ����͐���������{�����{���͓��{�����ɑ��ĒNj����Ă��邱�Ƃ͂ł��Ȃ��Ȃ�Ƃ̉��߂��(�O�L(2)�I(�))�C����ɑ���I�����_��\�̈ӌ��܂��C�ŏI�I�ɂ́C�u���{�����{�������I�ɏ��u���邱�Ƃ���]����ł��낤�A���������̂���^�C�v�̎��I�������v���c��Ƃ��Ă��C���a���̌��ʂƂ��āu�����鐿�����ɂ������邱�Ƃ͂ł��Ȃ��v�Ƃ̉���(�O�L(2)�I�i�))�Ō������C���a�������̒��S�I�l���ł���_���X�č���\���u�~�ςȂ������v�Ƃ��Ė������Ă����̂ł���(�O�L�Q(6)�C)�B
�@���̂悤�ȏ����������̌o�߂��炷��C���a���P�S��(b)�ɂ����u�������̕����v�Ƃ́C���{���y�ѓ��{�������A���������ɂ�鍑���@��̌����Ɋ�Â������ɉ�����@����̋`�������ł������̂Ƃ��āC��������₷�邱�Ƃ��ł���|����߂�ꂽ���̂Ɖ����ׂ��ł���B
�@
�@(�)�@���ړK�p�̗L��
�@���ɁC���������䂪�����̍ٔ����ɂ����Ē��ړK�p�ł��邩�����ƂȂ�B
�@���̋K�肪�䂪���̍ٔ����ɂ����Ē��ړI�ɓK�p�ł���Ƃ������߂ɂ́C��ϓI�v���Ƃ��āC�����������ɂ����Ē��ړK�p��F�߂�ӎv��L���Ă��邱�Ƃ��K�v�ł���C�q�ϓI�v���Ƃ��āC�K����e�����m�ł��邱�Ƃ��K�v�ł���Ƃ���Ă���(�������ٕ����T�N�R���T�������E�����P�S�U�U���T�R�y�[�W�Q��)�B
�@�����ŁC���̓_���P�S��(b)�ɂ��Č���ƁC�O�L���a���̖ړI��I�����_��\�Ɠ��{��\�Ƃ̑O�L���ߒ��y�у_���X�̑O�L����������C�����C�e�����ɂ����āC�������ɂ��C�A���������̓��{���y�ѓ��{�����ɑ��鐿�������₵������̂Ƃ���ӎv�ł��������Ƃ����炩�ł���C����ɁC�������̋q�ϓI�ȕ�������u�����v�Ƃ����p���p���āC���Y���������₵����@�I���ʂ��K�肵�����Ƃ��������m��I�ɔF�߂���B����āC�������ɂ��ẮC�O�L�v�����[������Ă���C���̓��e����̉����鍑���@��҂܂ł��Ȃ��C�䂪���̍ٔ����ɂ����Ē��ړI�ɓK�p���\�ł��邱�Ƃ͖��炩�ł���B
�@���������āC�䂪���ɂ����āC����ɊY������ٔ���̐����́C�������̓K�p�ɂ���ĔF�e����Ȃ����ƂƂȂ�B
�@
�@�C�@�č����{�̈ӌ����ɂ���
�@
�@(�)�@���̂悤�ȕ��a���ɂ�鍑�ƊԂ̐�㏈�����C�������̖��̊��S���ŏI�I�����ł��邱�Ƃ́C�ߎ��C�č��ɂ����āC���풆�ɁC�����{�R�̕ߗ��ƂȂ������č��R�l�炪���{��Ƃ̎��Ə�ŋ����J��������ꂽ�Ǝ咣���āC���{��Ƃ�퍐�Ƃ��āC�č����̍ٔ����ɒ�i���������̑��Q���������i�ׂɂ����āC�č����{�y�ѓ��{�����{�������������ɂ���Ă����炩�ł���B
�@���̑i�ׂ́C�P�X�X�X�N�V���P�T���C�J���t�H���j�A�B�Ő��������u�⏞�Ɋւ��Ė����i�ז@��354��6����lj����C�����ɔ��������ׂ��ً}����錾����@���v(��Ď҂̖����̂�u�w�C�f���@�v�Ƃ����B)�Ɋ�Â��āC�A�����̌��ߗ����тɃt�B���s���C�؍��y�ђ����̖��Ԑl�炪�����ƂȂ�C���{��Ƃ�퍐�Ƃ��Ē�N���ꂽ�i�ׂł���B
�@�w�C�f���@�́C���풆�Ƀi�`�X�������͂��̓������̎x�z���ŋ����J��������ꂽ�҂��A���̘J�����s��ꂽ��Ɩ��͂��̎q��m���ɑ��āC�Q�O�P�O�N�P�Q���R�P���܂ł̊ԁC���Q���������i�ׂ��J���t�H���j�A�B�ٔ����ɒ�N�ł���Ƃ������e�ł���(�w�C�f���@�̑S���̓��{���ɂ��ẮC�˒ˉx�Y�u���⏞���ɓ��ݍ��ޕč��v�@�w�Z�~�i�[�T�R�W���V�U�y�[�W)�B
�@�č������Ȃ́C�Q�O�O�O�N(�����P�Q�N)�W���P�V���C�k���J���t�H���j�A�n��E�T���E�t�����V�X�R�x���A�M�n���ٔ����ɑ��C�u���Q�W�������v���o�����Ƃ���ł��邪�C���̈ӌ����ɂ����āC�č����{�Ƃ��ẴT���E�t�����V�X�R���a���Ɋւ��āC�u�P�X�T�P�N�̓��{���Ƃ̕��a���̖ړI�́C���{���̎匠�����C���{�������Y��`�̋��Ђɑ��Ė����`�I�s��o�ςƂ��ċ@�\����悤�ɂ��C���{���̐��{�y�э����ɑ��邷�ׂĂ̐��������������C�A�����y�т��̍����ɑ�����{�̂��ׂĂ̐��ݓI�Ȑ��������������邱�Ƃł������B�{�ٔ����ŌW�����̑i�ׂɂ����Č������咣���Ă���悤�ȏ����̐푈�������͂��̑��̐푈�֘A�̐������̉\������c���Ă����Ƃ�����C�����̖ړI�͂�������B�����邱�Ƃ��ł��Ȃ������ł��낤�B���̗��R����C���́C���ɕʒi�̒�߂�����ꍇ�������C����E��풆�̍s�ׂ��琶�������{���y�т��̍����ɑ���A�����y�т��̍����̂��ׂĂ̐��������������悤�ɓ��ɋN�����ꂽ�̂ł���B�v�Ƃ̈ӌ���������(�O�f�č����{�u���Q�W�������v�M��Q�U�y�[�W�C����T�R����)�B�����C���{�����{���C���i�ׂɂ����āC�Q�O�O�O�N(�����P�Q�N)�W���W���C�u���č��ߗ����ɂ����{��Ƃɑ���i�ׂɊւ�����{�����{�̌����v�Ƃ��āC�č����{�Ɠ��l�̌������������Ƃ���ł���(�Q�O�O�O�N�W���W���t�����č��ߗ����ɂ����{��Ƃɑ���i�ׂɊւ�����{�����{�̌����E����U�O����)�B
�@
�@(�)�@����痼�����{�̌������āC���ٔ����́C���N�X���Q�P���ɁC������̑i�����p�����锻����������(����U�P����)�B
�@���̔����̒��ŁC�T���E�t�����V�X�R���a���P�S��(b)�Ɋւ��C�u���{�Ƃ̕��a���́C�{���i�ׂɂ����Č������咣���Ă��鐿���̂悤�ȏ����̐������ɂ������ɂ����āC�����̊��S�ȕ⏞�������̕��a�ƈ����������̂ł���B���j�͂��̎���������ł��������Ƃ��ؖ����Ă���B�����Ɍo�ϓI�ȈӖ��ɂ����錴���̋��ɑ��銮�S�ȕ⏞�́C���ߗ�����ё��̖����̐푈�����҂ɑ��Ă͋��ۂ��ꂽ���C���R�ȎЉ��т�蕽�a�Ȑ��E�ɂ�����ނ玩�g�̌v��m��Ȃ������̌b�݂Ɣɉh�́C�����Ƃ������ɑ��闘���̎x���ƂȂ��Ă���B�v�Ɣ������Ă���(����U�P���ؖM��P�Q�y�[�W)�B
�@���ٔ����́C���̌�C���̌�����̑i����S�ċp�����锻�������������߁C������͘A�M�T�i�ٔ����ɍT�i�������C�Q�O�O�R�N(�����P�T�N)�P���Q�P���C�����ق́C�Q�W���̓��{��Ƃ�퍐�Ƃ���i�ׂɂ��āC�w�C�f���@�͘A�M���{�̔r���I�O��������N���ጛ�ł���|�������āC������̍T�i��S�ċp�����锻����������(����U�Q����)�B
�@�܂��C�J���t�H���j�A�B�ٔ����ɌW�����Ă��������̂����C���ĕ��ߗ��������ƂȂ�C�퍐�O�H�}�e���A���ق����퍐�Ƃ��Ē�N���ꂽ�����J���ɂ�鑹�Q�������������ɂ��āC�J���t�H���j�A�B�T�i�ٔ����́C�Q�O�O�R�N(�����P�T�N)�Q���U���C�A�����̍����̐������̓T���E�t�����V�X�R���a���P�S��(b)�ɂ���ĉ����ς݂ł���Ƃ��āC������̑i�����p�����锻����������(����U�R����)�B
�@���̂悤�ɓ��{�����{�̌����́C�č����{�̌����Ɓv�v������̂ł���C�č��̍ٔ����ɂ����Ă��C�x������Ă���B
�@
�@�E�@�T���E�t�����V�X�R���a���P�S��(b)�̕\���ɂ���
�@
�@(�)�@�T���E�t�����V�X�R���a���P�S��(b)�ɂ����ẮC��q�̂Q�O�O�O�N(�����P�Q�N)�X���Q�P���̖k���J���t�H���j�A�n��E�T���E�t�����V�X�R�x���A�M�n���ٔ����ɂ���ĉ����ꂽ�����ɂ���Ƃ���C�u���̏��ɕʒi�̒�߂�����ꍇ�������v�Ƃ̋K��������C�������̕����ɂ��ĉ���̏����I�ȕ������͐������܂�ł��Ȃ����Ƃ���C�P�S��(b)�ɂ��C�A���������������A�����y�јA���������̓��{���y�ѓ��{�����ɑ��鐿�����́C�ɂ߂Ė��m���L�͂Ȃ��̂ł���B
�@
�@(�)�@�Ȃ��C�P�S��(b)�́u�A�����̂��ׂĂ̔����������v�݂̂Ȃ炸�C�u�푈�̐��s���ɓ��{���y�т��̍������Ƃ����s�����琶�����A�����y�т��̍����̑��̐������v�ƋK�肳�ꂽ���R�ɂ��āC���a�Q�U�N�P�P���X���̎Q�c�@�́u���a���y�ѓ��Ĉ��S�ۏ�����ʈψ���v�ɂ����āC�����F�Y�O���ȏ��ǒ��́C���̂悤�ɓ��ق��Ă���B
�@���Ȃ킿�C���{���S�c���́u�����ł���(b)���ɂ��Ďf���Ă��������̂ł����C����͘A�����̔����������Ƃ���܂��āC�A���������̂Ƃ����̂������Ă���̂ł���܂����C����͂ǂ������킯�Ŕ��������̂��B�����́w�y�т��̍����̑��̐������x�Ƃ����̂ŃJ�o�[�������̂��C���̓_���f���Ă����܂��B�v�Ƃ̎���ɑ��C�������ǒ��́C�u���҂��܂ވӖ��ł������܂��B�v�Ɠ��ق��C����ɁC���{�c���́u���҂��܂ނƂ����̂́C����Ƃ���ł͏��������C����Ƃ���ł͏��������Ă��Ȃ��̂͂ǂ������킯�ł����B�v�Ƃ̎���ɑ��āC�������ǒ��́C�u��̐��{�ƍ����Ƃ��I�ɐ\���Ƃ��ɁC���{���ƌ����C���͘A�����ƌ����̂������̊��s�ł������܂��B�Ƃ��ɂ���Ă��̊��s���т���Ă��Ȃ��_������܂��̂́C���������ӂ��Ȍ\�J������̌��ł������܂��āC�e���̒�Ă��W�߂������I����ɂȂ�C�������т��邱�Ƃ��ł��Ȃ������߂��ԁX����̂́C�~�ނȂ�����ł������܂��B�v(�������p��)�Ɠ��ق��Ă���B
�@�����āC�P�S��(b)�ɁC�u�A�����̂��ׂĂ̔����������v�̑��C�u�A�����y�т��̍����̑��̐������v���K�肳�ꂽ���R�ɂ��āC�������ǒ��́A�u���̓_�͂R���̌��Ăł͘A�����̔��������������������̂ł���܂��B����ɑ��܂��āC���ǂ��̂ق�����C����ł͔͈͂��s���m�ł���Ǝ咣�������܂��āC�푈���s�����{�����͓��{�������Ƃ����s�����琶�����A�������{���͘A�������̐������Ƃ������傪����������ł������܂��B�A�����̔����������Ƃ��������ł͌���������₷������C����������Ӗ��ɂ����āC���m�ɂ��Ă�����Ƃ���ł������܂��B�v�Ɠ��ق��Ă���(����U�S����)�B
�@���̂悤�ɁC�푈�����̏�'���́C���R�C���Ƌy�т��̍����̑��荑�y�т��̍����ɑ��鐿�����̏������܂ނ��C�P�S��(b)�ɂ��ẮC����m�ɂ��邽�߂ɁC�����āu�A�����y�т��̍����̑��̐������v�Ƃ���������}�������ɂ����Ȃ��B
�@
�@�T�@���̑��̐�㏈���ɂ���
�@
�@�䂪���́C�T���E�t�����V�X�R���a���̒����������ȊO�̍��Ƃ̊Ԃɂ����Ă��C�T���E�t�����V�X�R���a���Ɋ�Â���㏈���̘g�g�݂ɏ]���C�T���ȉ��̂Ƃ���Ή����Ă����B
�@
�@(1)�r���}�A�M�Ƃ̊W�ɂ���
�@�r���}�ɂ��ẮC�T���E�t�����V�X�R�u�a��c�ɎQ�����Ȃ��������߁C�ʓr�̕��a�������s���C�P�X�T�S�N(���a�Q�X�N)�P�P���T���C���a���y�сu���{���ƃr���}�A�M�Ƃ̊Ԃ̔����y�ьo�ϋ��͂Ɋւ��鋦��v���������ꂽ�B������ɏ]���āC�䂪���́C�P�X�U�T�N(���a�S�O�N)�܂ł̊ԂɁC�Q���h��(�V�Q�O���~)�̔����ƂT�O�O�O���h��(�P�W�O���~)�̎؊��̎��{�������B�Ƃ��낪�C�����������ɁC�r���}���́C�����a���ɑ}������Ă����u�����Č��������v(�T��)�Ɋ�Â��C�����̒lj��x����v�����C���̌��ʁC�P�X�U�R�N(���a�R�W�N)�R���̋���ɂ��C�P���S�O�O�O���h��(�T�O�S���~)�̒lj��I�Ȗ��������ƂR�O�O�O���h��(�P�O�W���~)�̎؊��̋��^���s��ꂽ(�O�f���{�̔����P�Q�C�P�R�y�[�W�A���c���O�E�����{�O���̏،�(��)�P�X�O�Ȃ����P�X�R�y�[�W�C�g�V�����Y�E���{�O���j�Q�X�u�a��̊O��(I)�ΗW(��)�R�Q�V�Ȃ����R�R�O�y�[�W)�B
�@�����āC�r���}�Ƃ̕��a���T���Q�ɂ����āC�u�r���}�A�M�́C���̏��ɕʒi�̒肪����ꍇ�������ق��C�푈�̐��s���ɓ��{���y�т��̍����������s�����琶�����r���}�A�M�y�т��̍����̂��ׂĂ̐�'�������������B�v�ƋK�肳�ꂽ�B
�@
�@(2)�C���h�l�V�A���a���Ƃ̊W�ɂ���
�@�C���h�l�V�A�́C�T���E�t�����V�X�R���a���ɏ����������C�����̔����������Ŕ����L�������Ɠ����瓯�����y���Ȃ������B���̌�C�P�X�T�V�N(���a�R�Q�N)�P�P���ɁC�ݐM����ƃX�J���m�哝�̂Ƃ̊ԂŁC�䂪���̖�P���V�U�X�P���h���̑C���h�l�V�A����_�����ɂ��邱�Ƃ������ɁC�����z���Q���Q�R�O�O���h��(�W�O�Q���W�O�O�O���~)�Ƃ��邱�Ƃō��ӂ����B�����āC���̍��ӂɊ�Â��C�P�X�T�W�N(���a�R�R�N)�P���C�����ԂŁu���{���ƃC���h�l�V�A���a���Ƃ̕��a���v���������ƂƂ��ɁC�Q���Q�R�O�O���h�������̖y�ѐ��Y���̋��^�Ɋւ���u���{���ƃC���h�l�V�A���a���Ƃ̖�̔�������v�C�S���h��(�P�S�S�O���~)�̎؊����^�Ɋւ���u�o�ϊJ���؊��Ɋւ�����{�����{�ƃC���h�l�V�A���a�����{�Ƃ̊Ԃ̌��������v�����������ꂽ(�g�V�E�O�f���{�O���j�Q�X�W�Ȃ����R�O�T�y�[�W)�B
�@�����āC�C���h�l�V�A�Ƃ̕��a���S���Q�ɂ����āC�u�C���h�l�V�A���a���́C�O���ɕʒi�̒肪����ꍇ�������ق��C�C���h�l�V�A���a���̂��ׂĂ̔������������тɐ푈�̐��s���ɓ��{���y�т��̍����������s�����琶�����C���h�l�V�A���a���y�т��̍����̂��ׂĂ̑��̐��������������B�v�ƋK�肳�ꂽ�B
�@
�@(3)���I�X�y�уJ���{�f�B�A�Ƃ̊W�ɂ���
�@���C���h�V�i�R�����C�x�g�i���������C�J���{�f�B�A�͂P�X�T�S�N(���a�Q�X�N)�P�P���ɁC���I�X�͂P�X�T�U�N(���a�R�P�N)�P�Q���ɁC���ꂼ��T���E�t�����V�X�R���a���ɋK�肳�ꂽ�Γ��������������������|�̈ӎv�\�����s���Ă����B�����ŁC�䂪���́C���I�X�y�уJ���{�f�B�A�ɁC���ꂼ��P�X�T�W�N(���a�R�R�N)�P�O���ƂP�X�T�X�N(���a�R�S�N)�R���Ɍo�ϋ��͋����������C���ꂼ��P�O���~�ƂP�T���~�����^����(�O�f���{�̔����P�T�y�[�W)�B
�@
�@(4)���\���B�G�g�Љ��`���a���A�M�Ƃ̊W�ɂ���
�@���\���B�G�g�Љ��`���a���A�M�Ƃ̊Ԃł́C�P�X�T�U�N(���a�R�P�N)�P�O���P�X���C�u���{���ƃ\���B�G�g�Љ��`���a���A�M�Ƃ̋����錾�v�������������C���̓��e�́C�u���{���y�у\���B�G�g�Љ��`���a���A�M�́C�����Ԃ̊O���W�̉��ɓ��ɂ����镽�a�y�ш��S�̗��v�ɍ��v���闼���Ԃ̗����Ƌ��͂Ƃ̔��W�ɖ������̂ł���v(�O��)�Ƃ̗����̉��ɁC���錾�U�ɂ����āC�u�\���B�G�g�Љ��`���a���A�M�́C���{���ɑ���̔������������������B���{���y�у\���B�G�g�Љ��`���a���A�M�́C�P�X�S�T�N�W���X���ȗ��̐푈�̌��ʂƂ��Đ��������ꂼ��̍��C���̒c�̋y�э����̂��ꂼ�ꑼ���̍�,���̒c�̋y�э����ɑ��邷�ׂĂ̐�������,���݂�,��������B�v�ƋK�肵��,���ׂĂ̐������̖����ŏI�I�ɉ����������̂ł���B
�@
�@(5)���̑��̏����Ƃ̊W�ɂ���
�@�펞��,�̈悪���{�R�̐�̉��ɂ�������,�T���E�t�����V�X�R�u�a��c�ɎQ�����Ȃ������C���h��,�P�X�T�Q�N(���a�Q�V�N)�U���ɒ������ꂽ���a���U��(a)�ɂ�蔅�����������������(�g�V�E�O�f���{�O���j�R�R�O�Ȃ����R�S�P�y�[�W)�B
�@�܂�,��Q�����E��풆�ɒ������ł������X�C�X,�f���}�[�N,�X�E�F�[�f��,�X�y�C�����̏�����,�푈��,���{�R��,����n��y�ђ����ɂ�����,���̍����y�і@�l�ɐl�I���I���Q��^�������Ƃ�,���ۖ@�̌�����N�����̂ł���Ƃ���,���̕⏞�𐿋����Ă����B
�@������,�X�C�X�Ƃ̊Ԃ�,�P�X�T�T�N(���a�R�O�N)�P������������,����ɏ]����,�䂪����,�X�C�X�ɂP�R�T�O���t����(��P�P���~)���x����,�X�y�C���Ƃ̊Ԃ�,�P�X�T�V�N(���a�R�Q�N)�P�����������̏������s��,����ɏ]����,�X�y�C���ɑ�,�T�T�O���h��(��Q�O���~)�̎x�����s�����B�X�E�F�[�f���Ƃ̊Ԃɂ�,�P�X�T�W�N(���a�R�R�N)�T�����肪������,����ɏ]����,�V�Q�T���N���[�l(��T���~)���x�����,�f���}�[�N�Ƃ̊Ԃł�,�P�X�T�T�N(���a�R�O�N)�X���y�тP�X�T�X�N(���a�R�S�N)�T���ɋ���������,����Ɋ�Â�,���ꂼ��R�O���|���h(��R���~)�ƂP�P�V���T�O�O�O���h��(��S���Q�R�O�O���~)�̎x�����s����(�O�f���{�̔����P�T,�P�U�y�[�W)�B
�@������,�X�C�X���{�Ƃ̎�ɂR���Q�ɂ�����,�u�X�C�X�A�M���{��,��P���Ɍf������z�̎x�����s��ꂽ�Ƃ���,�����y�ё�Q���Ɍf���鑹�Q�̔����Ɋւ��铯���{�̂��ׂĂ̗v�������������̂Ƃ�,�܂�,�X�C�X������,���̎����Ɋւ���v���������Ȃ���@�ɂ���Ă����{�����{�ɒ�N���邱�Ƃ��ł��Ȃ����̂Ƃ���B�v�ƋK�肳��C�X�y�C�����{�Ƃ̎�ɂR�ɂ����āC�u�P�ɒ�߂���z�̎x���ɂ��C���{�����{�́C�����ɂ������Q�y�ы�ɂ̂��ׂĂ̔��������Ɋւ��邷�ׂĂ̐ӔC�����S���ŏI�I�ɖƂ����B�v�ƋK�肳��C�X�E�F�[�f�����{�Ƃ̎�ɂS���ɂ����āC�u�X�E�F�[�f�����{�́C��P���Ɍf�������z�̓��{�����{�ɂ��x�����ɂ������ׂĂ̐������̊��S���ŏI�I�ȉ����Ƃ��Ď������B�X�E�F�[�f�����{�́C���{�����{�������Ɍf�������z�̎x���̌�́C�O�L�̐����ɑ��邱��ȏ�̂����Ȃ锅�����x�����K�v�͂Ȃ����Ƃ�ۏ��邱�Ƃ����B�v�ƋK�肳��C����Ƀf���}�[�N���{�Ƃ̎�ɂR���ɂ����āC�u��P���Ɍf�������z�̎x���ɂ��C���{�����{�́C����E���(�P�X�R�V�N�V���V������̎x�ߎ��ς��܂ށB)�̊Ԃɓ��{�����{�̋@�ւ��f���}�[�N���{�̋@�֕��тɃf���}�[�N�̎��R�l�y�і@�l�ɗ^�������Q�y�ы�ɂ̂��ׂĂ̔��������ɂ����邷�ׂĂ̐ӔC�����S���ŏI�I�ɖƂ����B�v�ƋK�肳�ꂽ�B
�@
�@�U�@�䂪���ƒ����Ƃ̊Ԃ̐�㏈��
�@���{�ƒ����Ƃ̊Ԃɂ����ẮC�푈��Ԃ̏I���C�������тɍ��Y�y�ѐ������̖��̉����ɂ��ẮC�����̕��G�ȍ��ۏ�f�������]�Ȑ܂����������C�������{�̓w�͂ɂ���āC�T���E�t�����V�X�R���a���ɂ������㏈���̘g�g�݂Ɠ��l�̉������}��ꂽ���̂ł���B
�@
�@(1)�T���E�t�����V�X�R���a���Ƃ̊W�ɂ���
�@
�@�A�@�����́C�A�����̈ꍑ�Ƃ��āC�T���E�t�����V�X�R�u�a��c�ɏ��҂����ׂ��ł��������C���a�Q�S�N�̒��ؐl�����a�����{�̐����⓯�Q�T�N�̒��N�푈�̂ڂ����ȂǓ����̐����I�y�э��ۏ̂��߂ɁC���ؐl�����a�����{�y�сu���ؖ����v���{�̂�������u�a��c�ɂ͏��҂���Ȃ������B
�@�����������Q�P���́C�u���̏��̑�Q�T���̋K��ɂ�����炸�C�����́C��P�O���y�ё�P�S��(a)�Q�̗��v���錠����L�v������̂Ƃ���C���̓������ƂȂ�Ȃ������������C�����̈���ɂ�����{���y�ѓ��{�����̎��Y�̏������F�߂�ꂽ(�����P�S��(a)�Q)�B�����́C�P�X�S�T�N(���a�Q�O�N)�P�O���ɁC�u�������Y�����ٖ@�v�����z���āC���̗̈���ɂ�����{�l�̍��Y��v������(�����V���m�ҁE�Γ����a���Q�R�S�Ȃ����Q�R�T�y�[�W�E����U�T����)�B
�@�P�X�S�U�N(���a�Q�P�N)�X���C�O���ȋy�ё呠�Ȃ̋��ǂŐݒu���ꂽ�݊O���Y������ɂ��u�䍑�݊O���Y�]���z���v�v�ɂ��ƁC�I�퓖���C�����ɑ��݂������{���Y�̋K�͂́C��p�S�Q�T���S�Q�O�O���~�C���ؖ������k�P�S�U�T���R�Q�O�O���~�C�ؖk�T�T�S���R�V�O�O���~�C�ؒ��C�ؓ�R�U�V���P�W�O�O���~�ƕ���Ă���(�˖{�E�O�f�����Ə��Q�Q�W���V�y�[�W�E����T�U����)�B���Ȃ݂ɁC���a�Q�P�N�x�̉䂪����ʉ�v�̍Γ��́C�P�P�W�W���~�]��ł���C�����N�x�̉䂪���̍��������Y�́C�S�V�S�O���~�]��ł�����(�O�f���{���v�N�ӂR�T�X�C�R�U�S�y�[�W�E����T�S����)�B
�@
�@�C�@�Ȃ��C�����ɂ��āC���a���ɂ��ŏI�I�Ȕ����̑O�ɁC�P�X�S�T�N(���a�Q�O�N)�P�Q���̃A�����J�哝�̂ɑ��钆�Ԕ����v��Ɋւ��銩����(������u�|�[���[���Ԉāv)�Ɋ�Â��C�����钆�Ԕ������s���Ă���B
�@����́A���{�̔�R������ړI�Ƃ��āC�]���ȍH�Ǝ{��(���{�ݔ�)��P�����C�������ɃA�W�A�ߗ����ɑ��锅���̈ꕔ�ɏ[�Ă�Ƃ������̂ł���C�P�X�T�O�N(���a�Q�T�N)�T���܂łɁC���v�S���R�X�P�X��̍H��@�B��������P������(�F��l�Y�ҁE���{�Ǘ��̋@�\�Ɛ���R�V�X�y�[�W�E����U�U����)�C���̈����n���������̕]���z�̍��v�́C���a�P�S�N�̉~���i�łP���U�T�O�O���~�C�����̃h�����i�Ɋ��Z���Ė�S�T�O�O���h���ł��������C���̈��捑�ʕ]���z�̂����C�������T�S.�P�p�[�Z���g���߂Ă���(�˖{�E�O�f�����Ə��Q�Q�W���U�y�[�W)�B
�@
�@(2)���{�Ɓu���ؖ����v�Ƃ̊Ԃ̏����ɂ���
�@�䂪���ƒ����Ƃ̊Ԃ̐�㏈���ɂ��ẮC�P�X�T�Q�N(���a�Q�V�N)�S���Q�W���C�䂪���́C�u���ؖ����v�Ƃ̊ԂŁC�u���{���ƒ��ؖ����Ƃ̊Ԃ̕��a���v(�ȉ��u���ؕ��a���v�Ƃ����B)�ɏ��������B
�@���̏��́C���̑O���ɂ���悤�ɁC�u���j�I�y�ѕ����I�̂����Ȃƒn���I�̋߂��Ƃɂ��݁C�P�W�𑊌݂Ɋ�]���邱�Ƃ��l�����C���̋��ʂ̕����̑��i���ѓۂ̕��a�y�ш��S�̈ێ��̂��߂ٖ̋��ȋ��͂��d�v�ł���v�Ƃ����F���̉��ɁC�����Ԃ̐푈��Ԃ��I�������C�����y�ѐ푈�̌��ʂƂ��Đ����������������������̂ł���B
�@���Ȃ킿�C�䂪���ɑ��锅���������ɂ��ẮC�����̋c�菑�P(b)�ŁB�u���ؖ����́C���{�����ɑ��銰���ƑP�ӂ̕\���Ƃ��āC�T���E�t�����V�X�R���a����P�S��(a)�P�Ɋ���{�������ׂ��̗��v�������I�ɕ�������B�v�ƋK�肵�C����ɂ��C�T���E�t�����V�X�R���a���P�S��(a)�P�ɋK�肷�锅������������������B
�@�����āC�u���ؖ����v��\�Ɠ��{����\�Ƃ̖�́u���ӂ��ꂽ�c���^�v�S�ɂɂ��C�u���ؖ����͖{���̋c�菑��P��(b)�ɂ����ďq�ׂ��Ă���悤�ɁC�����������I�ɕ��������̂ŁC�T���E�t�����V�X�R����P�S��(a)�Ɋ�����ɋy�ڂ����ׂ��B��̎c��̗��v�́C������P�S��(a)�Q�ɋK�肳�ꂽ���{���̍݊O���Y�ł���v�Ƃ���C�T���E�t�����V�X�R���a���Q�P���Ɋ�Â��C�������C�����P�S��(a)�Q�̗��v���錠����L���邱�Ƃɂ��Ă��m�F���ꂽ�B
�@�����āC���ؕ��a���P�P���́C�u���̏��y�т����⑫���镶���ɕʒi�̒肪����ꍇ�������O�C���{���ƒ��ؖ����Ƃ̊Ԃɐ푈��Ԃ̑��݂̌��ʂƂ��Đ��������́C�T���E�t�����V�X�R���̑����K��ɏ]���ĉ���������̂Ƃ���B�v�ƋK�肵�Ă���Ƃ���C���̋K��ɂ����u�T���E�t�����V�X�R���̑����K��v�ɂ́C�P�S��(b)�y�тP�X��(a)���܂܂�邩��C���̋K��ɏ]���āC���{���y�т��̍����ƒ����y�т��̍����Ƃ̊Ԃ̑��݂̐������́C��L�̃T���E�t�����V�X�R���a���P�S��(a)�P�Ɋ�Â������������ƕ����āC�����P�S��(b)�y�тP�X��(a)�̋K��ɂ��C���ׂĂ��������ꂽ���ƂɂȂ�B
�@���̖@�I���ʂ́C�O�L�S�C(3)�C�ŏq�ׂ��Ƃ���ł���B���Ȃ킿�C���ؕ��a���P�P���C�T���E�t�����V�X�R�P�S��(b)�ɂ��C���{���y�ѓ��{���������������ɂ�鍑���@��̌����Ɋ�Â������ɉ�����@����̋`�������ł������̂Ƃ��āC��������₷�邱�Ƃ��ł���̂ł���C���̓��e����̉����鍑���@��҂܂ł��Ȃ��C�䂪���̍ٔ����ɂ����Ē��ړI�ɓK�p���\�ł��邩��C�ٔ���̐����́C�������̓K�p�ɂ���ĔF�e����Ȃ����ƂƂȂ�B
�@
�@(3)���{�ƒ��ؐl�����a���Ƃ̊Ԃ̏����ɂ���
�@
�@�A�@�����������������Ɏ���o�܂ɂ���
�@�u���ؕ��a���v������Q�O�N���o�āC���{�����{�͂P�X�V�Q�N(���a�S�V�N)�ɋ��������ɏ��������B���������̌��ߒ��ɂ����Ė��ƂȂ����_�̒��ɁC�푈��Ԃ̏I���┅�����тɍ��Y�y�ѐ������̖�肪����B�����̖��́A���ؕ��a���ɂ��Ă̗����̗���̈Ⴂ�ɋN��������̂ł��邪�C����Ȍ��̌��ʁC�ȉ��ɏq�ׂ�Ƃ���C���������́C�����̗��ꂻ�ꂼ��Ƒ��������̂Ƃ��č쐬����Ă���B
�@�Ⴆ�C�푈��Ԃ̏I���ɂ��ẮC���ؕ��a���P���ɂ����āC�u���{���ƒ��ؖ����Ƃ̊Ԃ̐푈��Ԃ́C���̏���͂�����ɏI������B�v�ƋK�肳��Ă���Ƃ���C�����Ԃ̐푈��Ԃ́C���ؕ��a���ɂ��I�������Ƃ����̂��C�䂪���̈�т�������ł���B����́C�푈��Ԃ̏I���́C��x����̏����s�ׂł���C�@���I�ɂ́C�����������\���鍇�@���{�ł��������ؖ������{�Ƃ̊ԂŁC���ƍ��Ƃ̊W�𗥂��鎖���Ƃ��ď����ς݂ł���Ƃ����l�����Ɋ�Â����̂ł���B����ɑ��āC���ؐl�����a���́C���ؕ��a���͓������疳���ł���Ƃ̗���ł���C�䂪���̍l�����Ƃ͊�{�I�ɈقȂ���̂ł������B�푈��Ԃ̏I���̖��́C���̂悤�ȓ����o���̊�{�I����Ɋ֘A���鍢��Ȗ@�I���ł��������C�����o���̌��w�͂̌��ʁC���������P���ɂ����āC�u���{���ƒ��ؐl�����a���Ƃ̊Ԃ̂���܂ł̕s����ȏ�Ԃ́C���̋������������o�������ɏI������B�v�ƋK�肳��邱�ƂƂȂ����B�u�s����ȏ�ԁv�Ƃ́C����܂ʼn䂪���ƒ��ؐl�����a���Ƃ̊Ԃ̍������Ȃ�������Ԃ��w���Ƃ����̂��䂪���̗����ł���C�����Ԃ̐푈��Ԃ͓��ؕ��a���ɂ���ďI�����Ă���Ƃ̗���Ɖ��疵�����Ȃ��B���̂悤�ȕ\���ɂ��āC�����W�������Ȃ�Ӗ��ɂ����Ă����퉻���ꂽ�Ƃ����_�ɂ��Ă̓����o���̔F���̈�v��}�������̂ł���B
�@
�@�C�@�������������T���ɂ���
�@�������тɍ��Y�y�ѐ������̖��ɂ��Ă��C�푈��Ԃ̏I���Ɠ��l�C���̂悤�Ȉ�x����̏����s�ׂɂ��ẮC���ؕ��a���ɂ���Ė@�I�ɏ����ς݂ł���Ƃ����̂��C�䂪���̗���ł���C���ؕ��a���̗L�����ɂ��Ă̒��ؐl�����a���Ƃ̊�{�I����̈Ⴂ����������K�v���������B���̓_�ɂ��Ă��C�����o���������d�˂����ʁC���������T���ɂ����ẮC�u���ؐl�����a�����{�́C�������������̗F�D�̂��߂ɁC���{���ɑ���푈�����̐�����������邱�Ƃ�錾����v�|�K�肳��Ă���B���������́C�݂��̗���̈Ⴂ���\������������ŁC���̂Ƃ��Ă��̖��̊��S���ŏI�I�ȉ�����}��ׂ��C���̂悤�ȋK��Ԃ�ɂ���v�������̂ł���C���̌��ʂ͓��ؕ��a���ɂ�鏈���Ɠ����ł��邱�Ƃ��Ӑ}�������̂ł���B���Ȃ킿�C�푈�̐��s���ɓ��{���y�т��̍������Ƃ����s�����琶���������y�т��̍����̐������́C�@�I�ɂ͑O�q�̂Ƃ���C���ؕ��a���ɂ��C���ɂ���ĕ�������Ă���Ƃ����̂��䂪���̗���ł���C���̂悤�ȗ���͋��������ɂ���ĕύX����Ă���킯�ł͂Ȃ�(�|���ɗY�O���ȃA�W�A�ǐR�c���̕����S�N�S���V���Q�c�@���t�ψ���ł̓��َQ�ƁE����S�X���V�y�[�W�Q�C�R�i)�B
�@���������āC���������T���́u�푈�����̐����v�݂̂Ɍ��y���Ă��邪�C�����ɂ͐�̑��ɌW�钆�������̓��{���y�ѓ��{�����ɑ��鐿�����̖��������ς݂ł���Ƃ̔F�������R�Ɋ܂܂�Ă���B���̓_�ɂ��ẮC�������{�����l�̔F���Ə��m���Ă���B
�@���̂悤�ɁC���������́C�䂪���̗���Ƒ��������̂Ƃ��č쐬���ꂽ�̂ł���C���������T���̕\�ʏ�̕����݂̂��Ƃ炦�Ē��������̍����@��̐������Ɋ�Â������ɉ�����`�������{���y�т��̍����ɂ���Ǝ咣���邱�Ƃ͎����ł���B
�@
�@�E�@�č��ɂ�����ٔ��̐��ړ��ɂ���
�@�����Ƃ̊Ԃł͐������̖�肪���S�ɉ������Ă��邱�Ƃɂ��ẮC�����J���Ɋւ��C���{��Ƃ���i���ꂽ�č��ɂ�����i�ׂɂ����āC�䂪�����{�Ƃ��Ă̌������C�Q�O�O�O�N(�����P�Q�N)�P�P���P�V���u�T���E�t�����V�X�R���a������̍����ɂ����{��Ƃɑ���i�ׂɊւ�����{�����{�̌����v�Ƃ��ĕ\�������Ƃ���ł���(����U�V����)�B
�@�܂��C�����l���܂ނ����錳�]�R�Ԉ��w�P�T�����C���{����퍐�Ƃ��āC�R�����r�A���ʋ�A�M�n���ٔ����ɒ�N�������Q���������i�ׂɂ����āC���ٔ����́C�Q�O�O�P�N(�����P�R�N)�P�O���S���C�u�t�B���s�����܂ޘA�����C�����y�ъ؍����Ƃ̐푈�������̉����̗��j�͕��G�ł���B�P�X�T�P�N�̓��{�Ƃ̕��a���́C�S�Ắu�푈���s���ɓ��{���y�т��̍������Ƃ����s�ׂ��琶�����A�����y�т��̍����̑��̐����v�����������̂ł���B�E�E�E���Ɋ؍��y�ђ����Ƃ̊Ԃ́C�푈���������������邽�߂̕ʓr�̍��ӂ̌����s�����B��������N���Ă���u�Ԉ��w�v�ɂ��Ă̐����́C���ɂ����̏�ɂ����Ė����I�ɂ͌��y����Ȃ������̂ł��낤���C�푈��ɒ������ꂽ��A�̏���{�ɑ���S�Ă̐푈�������̉�����ړI�Ƃ��Ă������Ƃ͖��m�ł���B�����͔����I�߂���ɁC�����̋c�_���ĊJ���悤�Ƃ��Ă��邪�C�{�@��͂��̓K���ȏ�ł͂Ȃ����Ƃɋ^��̗]�n�͂Ȃ��B����E����̓��{�Ƃ̖�̍��ӂ����{�Ɛ��{�ƃ��x���Œ������ꂽ�悤�ɁC�u�Ԉ��w�v�̐��������{��Œ��ڂɏ��������ׂ��ł���B�v�Ɣ������C������̑i�����p������(����U�W����)�B
�@
�@�V�@�������{�̌����ɂ���
�@�ȉ��ɏq�ׂ�Ƃ���C�������{�̔F�����C��̐푈�ɌW������Ԃ̐������̖��́C���������y�т��̍��Y�Ɋւ�����̂��܂߂āC���������������o�㑶�݂��Ă��Ȃ��Ƃ����䂪���U�{�Ɠ��l�̂��̂ł��邱�Ƃ͖��炩�ł���B
�@
�@(1)�P�X�X�T�N(�����V�N)�T���R���C�������O�V���i���́C�L�҂���u���𐳏퉻�ȗ��C�������{�́C���{�ɑ��锅�������𐳎��ɕ����������C�ŋߖ��ԑg�D�������������N���Ă���B����ɑ��錩��@���B�v�ƊԂ�ꂽ�̂ɑ��C�u�������͊��ɉ������Ă���B���̖��ɂ���������̗���ɕω��͂Ȃ��B�v�|�������Ă���(����U�X����)�B
�@
�@(2)�܂��C�K��?�O�����g�C�P�X�X�Q�N(�����S�N)�R���̋L�҉�ɂ����āC�L�҂�薯�Ԕ��������̓����ɂ��Ă̍l��������ꂽ�̂ɑ��C�u�푈�ɂ���Ă����炳�ꂽ����̕��G�Ȗ��ɑ��C���{���͓K�ɏ������s���ׂ��ł���B�v�Əq�ׂA�푈�����̖��ɂ��ẮC�u�������{�́C�P�X�V�Q�N�̓������������̒��Ŗ��m�ɕ\�����s���Ă���C�����闧��ɕω��͂Ȃ��B�v�ƕ\�����Ă���(����V�O����)�B
�@
�@(3)�P�X�X�W�N(�����P�O�N)�P�Q���̍��`�ɂ�����ɂ��C����?�O���́C�L�҂���C�������{�̖��Ԑl�̑Γ����������ɂ��Ď��₳�ꂽ�ہC�u�����̑Γ������������́C���ɉ����ς݂ł���C���ƂƖ���(����)�͈�̓���̂ł���̂ŁC����(����)�̗���́C���Ƃ̗���Ɠ����ł���ׂ��ł���B�v�Əq�ׂĂ���(����V�P����)�B
�@�ȏ�ɂ��݂�C��̐푈�ɌW������Ԃ̐������̖��ɂ��Ă̓����Ԃ̔F���͈�v���Ă���ƍl����ׂ��ł���B
�@
�@�W�@����
�@
�@(1)�ȏォ�疾�炩�Ȃ悤�ɁC���ؕ��a���P�P���y�уT���E�t�����V�X�R���a���P�S���ib�j�ɂ��C���������̓��{���y�т��̍����ɑ��鐿�����́C���ɂ���ĕ�������Ă���B�������������T���ɂ����u�푈�����̐����v�́C���������̓��{���y�т��̍����ɑ��鐿�������܂ނ��̂Ƃ��āC���ؐl�����a�����{�����́u�����v��錾�������̂ł���B
�@���������āC���̂悤�Ȑ������́C�T���E�t�����V�X�R���a���̓���������A�����̍����̐������Ɠ��l�C���ɂ���āu�����v����Ă���C����Ɋ�Â������ɉ����ׂ��@����̋`���͏��ł��Ă���̂ŁC�~�ς����ۂ���邱�ƂƂȂ�̂ł���B
�@�ȏ�̂Ƃ���C�T�i�l��̐����́C������ϓ_������F�e�����]�n���Ȃ����Ƃ͖��炩�ł��邩��C���₩�Ɋ��p�����ׂ��ł���B
�@
�@(2)�Ȃ��C�O�L�����n�ٔ����̓����Ԃ̐�㏈���Ɋւ����̉��߂ɂ��āCILO����K�p���ƈψ���ł����Ƃ��ꂽ�����łȂ��C�������͑O�L�J���t�H���j�A�B�T�i�ٔ����ŌW�����̎����ŁC�؋��Ƃ��Ē�o���ꂽ���߁C�Q�O�O�R�N�Q���U�������ɂ����p�����Ɏ����Ă���B
�@�����ŁC���{�����{�́C�Q�O�O�Q�N�P�P���CILO����K�p���ƈψ���ɑ��āC�u����K�p���ƈψ���̈ӌ��y�јJ���g������̏��ɑ�����{�����{�����v(����V�Q���̂P�C����V�Q���̂Q)�Ƒ肷��ӌ������o���C�u�����Ԃɂ����ẮC�P�X�V�Q�N�́u���{�����{�ƒ��ؐl�����a�����{�̋�������(�ȉ��u�������������v�Ƃ����B)���o��C��̑��ɌW�鐿�����̖��͌l�̐������̖����܂߂đ��݂��Ă��Ȃ��B�v(���a�V�y�[�W)�Ƃ̓��{�����{�̌�����\��������ŁC�����n�ٔ����̔��f�̌����w�E���Ă���Ƃ���ł���(���a�R�P�Ȃ����R�R�y�[�W)�B�Ȃ��C�����ƈψ�����Q�O�O�O�N�̐��ƈψ���ӌ��ɂ����āC�u�@�I�ɂ́C�⏞�̖��͏��ɂ������ς݂ł���Ƃ̐��{�̎咣�͐������ƔF������B�v�Əq�ׂĂ���Ƃ���ł���(���a�Q�y�[�W)�B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�ȁ@��

|