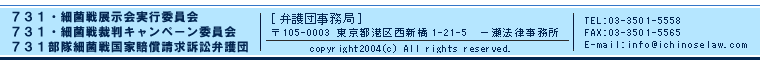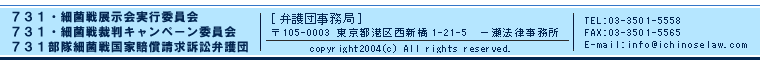�����P�S�N�i�l�j��S�W�P�T��
�T�i�l ���@�G�łق��P�V�X��
��T�i�l�@��
���@���@���@�ʁi�Q�j
�����P�T�N�X���R�O��
���������ٔ�����Q�������@�䒆
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@�@�@�@�@�@�@�@�@��T�i�l�w��㗝�l
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@�{�@�@�@�c�@�@�@���@�@�@�i
�� �@�@�@��@ �@�@���@���@��
�F�@�@�@�J�@�@�@���@�@�@�C
���@�@�@���@�@�@�F�@�@�@�M
���@�@ �@�@�@�@�@���@�@�@�D
���@�@�@��@�@�@�p�@�@�@�m
���@�@�@���@�@�@�@ �@�@�@�W
�@��T�i�l�́C�{�������ʂɂ����āC�T�i�l���2003�N(����15�N)7��31���t����2��������(�ȉ��u�T�i�l���2�������ʁv�Ƃ����B)�ɂ�����咣�ɑ��C�K�v�ƔF�߂�͈͂Ŕ��_����B�Ȃ��C�����́C���ɒf��ق��]�O�̗�ɂ��B
��1�@�ց[�O������3���̕������߂ɂ���
�@1�@�T�i�l��̎咣
�@�T�i�l��́C�ց[�O������3���ɂ͔��������̎�̂����L����Ă��Ȃ��Ƃ���C�t�����X���@�̕s�@�s�K��C�䂪���̖��@709���⍑�Ɣ����@1��1���̋K����C���������̎�̂����L����Ă��Ȃ����C����ɂ�������炸���̎�͔̂�Q�Ҍl�ł���Ɖ��߂���Ă���C�܂��C�����̑Ή��͂Ȃ�ׂ������Ŏx�����ׂ����̂Ƃ���ց[�O����K��52��2���̋K��ɂ��Ă��C�㖾�L����Ă��Ȃ����̂́C�x�����̑�������Z�����ł��邱�Ƃ͖����ł��邱�Ƃ��炷��ƁC�ց[�O������3���̕������߂ɂ���āC���������������̎�̂��Q�҂̏������鍑�Ƃɂ̂ݗ^�����Ɖ����邱�Ƃ́C�������߂͈̔͂���E���Ă���|�咣����(�T�i�l���2��������14�Ȃ���16�[�W)�B
�@2�@��T�i�l�̔��_
�@�������A�ց[�O������3�����C�������߂��炵�Ă��C���ƊԂ̍��ƐӔC���߂����̂ł����āC�l�̑��Q�������������߂����̂łȂ����Ƃ́C��T�i�l�̕���13�N12��26���t�����R��������(7)(�ȉ��u�퍐��������(7)�v�Ƃ����B)18�C19�[�W�ŏq�ׂ��Ƃ���ł��邩��C��������p����B
�@�ց[�O������̑O���̑�2�i���ɂ����ẮC�u���m�����j�˃��n�C�E���K(���p�Ғ�:�����1899�N�ɍ̑����ꂽ�ց[�O����K�����w���B)�n�C�c���ґ��݊ԃm�W�y�l���g�m�W�j���e�C���҃m�s���m�[�ʃm����^���w�L���m�g�X�v�ƋK�肵�āC�l���Ƃ̊W�Ƃ̍s�K�͂ƂȂ邱�Ƃ����ċK�肵�Ă���̂ɑ��C3���ɂ����ẮC�u��퓖���҃n�C�E�E�V�J�����m�Ӄ����t�w�L���m�g�X�v�ƋK�肷��݂̂ŁC�u�l���g�m�W�j���e�v�Ƃ����悤�ȕ�����u���Ă��Ȃ����C2���́C�u�����j�f�P�^���K���y�{���m�K��n�c���ԃj�m�~�V���K�p�X�v�ƋK�肵�C7���́u�{���n�c�����j�V�e�n�c�C���m���̓����X�����m�g�X�v�ƋK�肵�Ă���B
�@�����������@�̕s�@�s�K��͎��l�Ԃ̖@���W���C���Ɣ����@�͍��Ɩ��͌����c�̂Ǝ��l�Ƃ̊Ԃ̖@���W�����ꂼ��.�K�肷����̂ł��邩��C�����������̎�̂����L����Ă��Ȃ��Ƃ��Ă��C���ꂪ���Q���������l�ł��邱�Ƃ͗��̓��R�ł���B����ɑ��C���ۖ@�ł�����́C���ƊԂŒ�������鍇�ӂł����āC�����Ƃ��č��ƊԂ̌����`�����߂���̂ł��邩��C���ƐӔC�ɂ�锅�������̎�̂����ƂƂ����̂ł���B�����ł���C�ց[�O������3���ɁC�����������̎�̂����ɖ�������Ă��Ȃ��ȏ�C�����������̎�͍̂��ۖ@�̌����ɏ]�����ƂƉ�����̂����R�ł���B
�@�܂��C�w�[�O����K��52��3�����C��̌R�ɑ��C�����ɌW��Z�����ւ̋����̎x�����ɂ��ċK�肵�Ă��邩��Ƃ����āC�������l�̖@�I�Ȑ�������F�߁C�l�ɍ��ۖ@��̖@��̐���F�߂��K��ł���Ɖ����邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B���ۖ@�̈�ʓI�ȗ������炷��A�������̋K��́C�������̒��ɑ��C�����̐�̌R�����Ē����̑�����ƂȂ����Z�����ɂȂ�ׂ������������Ďx�����������邱�Ƃ���K��ł���C���ƊԂ̌����`�����߂��K��ł���Ɖ������B���荑�ɑ��ĕ����u�Z�����ւ̎x���`���v�Ɓu�Z�����̎x���������v�Ƃ͎������قȂ�̂ł����āC�O�҂����҂������o�������̂ł͂Ȃ��̂ł���B���̂��Ƃ́C���ɐ�̌R�������̎x�����𗚍s���Ȃ��ꍇ�ɁC�Z�������̗��v��N�Q���ꂽ�Ƃ��č��ۖ@�セ�̋~�ς����߂��i�E���x���݂����Ă��Ȃ����Ƃ�����C�M�����Ƃ��ł���B
�@���������āC�T�i�l��̎咣�͎����ł���C�ց[�O������3���́C���̕������߂��炵�Ă��C�l�̑��Q�������������߂����̂Ƃ͉�����Ȃ��B
��2�@�ց[�O������3���̋N���ߒ��ɂ���
�@1�@�T�i�l��̎咣
�@�T�i�l��́C�ց[�O������3���̋N���ߒ����炷��ƁC��Ď҂̃h�C�c��\�́C�����ɂ���Q�Ҍl�����ډ��Q���ɑ��Q������������Ӑ}��L���Ă���C�R�c�ɉ�������e����\���C���l�̈Ӑ}��L���Ă���C���������āC�����͌l�ɑ��Q������������F�߂����̂ł���|�咣����(�T�i�l���2��������25�Ȃ���28�[�W)�B
�@2�@��T�i�l�̔��_
�@�@(1)�@�퍐��������(7)19�[�W�ȉ��ŏq�ׂ��Ƃ���C��̐R�c�o�߂��Ď҂̈Ӑ}�Ƃ��������̂́C��������܂����͕s���m���̏ꍇ�ɁC�⑫�I�ȉ��ߎ�i�Ƃ��ė�O�I�ɗ��p�����ɂ������C�ց[�O������3���̂悤�ɁA���̕������߂ɂ����č��ƊԂ̌����`�����߂Ă��邱�Ƃ����炩�ł���ꍇ�ɂ́C���̂悤�Ȏ�����l������K�v�͂Ȃ��̂ł��邩��C�N���ߒ����d�����Ă��̉��߂��s���K�v�͂Ȃ��B
�@�������O�̂��߁C�ȉ��ɐR�c�o�߂ɂ��Ĕ��_���q�ׂ�B
�@�A�@�܂��C�T�i�l�炪�C�ց[�O������3���̐R�c�o�߂ɂ�����e���̑�\�̔�������Q�����l�̋~�ς�O���ɒu���Ă��邱�Ƃ������Ƃ��āC�����̐R�c�̍ۂɔ�Q�Ҍl�ɑ��Q������������F�߂���̂Ƃ��ĐR�c����Ă����Ɨ������Ă���̂ł���C���̂悤�ȗ����ɂ͌�肪����B���ۖ@�ɂ����ẮC���ƊԂɌ����`�����ۂ��邱�Ƃɂ���āC�l�̋~�ς����}�邱�Ƃ����邪�C���ۖ@�K���l�̋~�ς�}�邱�Ƃ�O���ɂ����Ă���ƍl������ꍇ�ł��C�l�̋~�ς́C���ƊԂɌ����`�����ۂ���Ƃ����`�ŊԐړI�ɐ}����Ƃ���̂��C���ۖ@�̊�{�I�ȍ\���ł���B
�@���̂悤�Ȋϓ_���炷��C����̏��̎�|���C�l�̋~�ς�ړI�Ƃ�����̂ł����Ă��C����������āC�����ɓ��Y���ۖ@�ɂ����Čl�̍��ۖ@��̐���F�߁C�l�������̎�̂Ƃ�����̂Ƃ��Ē�߂Ă���Ƃ������Ƃ͂ł��Ȃ��B�{���ŁC�ց[�O������3���̐R�c�o�߂���������ɓ������Ă��C�������P�Ɍl�̋~�ς�}��ړI�������ۂ�����������ɂƂǂ܂�̂ł͂Ȃ��C����ɐi��ŁC���Y���ۖ@�K���C�l�ɉ��Q���ɑ��鍑�ۖ@��̑��Q������������F�߂�Ƃ�����O�I�Ȗ@������̗p���悤�Ƃ��Ă������ۂ��Ƃ����ϓ_���猟�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
�@�C�@���̂悤�Ȋϓ_����R�c�o�߂���������ƁC���������C�h�C�c��\�̒�ẮC��1�a��c�ɂ���߂��A��2�ψ�����̕⊮�E���m���̔C�ɓ������Ă������K��ɁC���ُ����������邱�Ƃ�ڎw�����̂ł������̂ł��邩��(�u"ACTES�@ET�@DOCUMENTS"(�ց[�O������R�c�o�߂̔���)�v����19���ؖ�1�C4�[�W)�C���̑O��ƂȂ�ց[�O������y�ѓ��K���̏��K�肪���ƊԂ̌����`�����߂���̂ł���ȏ�C�h�C�c��\�̒�Ă��C�ց[�O������3�������ƊԂ̌����`���Ɋւ���K��Ɣc�����Ă����Ɨ�������̂����R�������I�ł���B�O��ƂȂ鏔�K��ɂ����ẮC���ƊԂ̌����`������߂��Ă���̂ɁC���ُ����ɂ����āC�˔@�Ƃ��Čl���@��̐���L������̂Ƃ��ēo�ꂷ��Ƃ������߂͍������������Ƃ����ق��Ȃ��B
�@�E�@�܂��C�T�i�l��̉��p��.��h�C�c��\�̒�Ă̒��ɂ́C�u���̐ӔC�C���Q�̒��x�C�����̎x�����@�̌���ɓ������ẮC�����̎҂ƓG���̎҂ŋ�ʂ����C�����̎҂����Q�����ꍇ�́A���s�ׂƗ�������ł��v���ȋ~�ς��m�ۂ��邽�߂ɕK�v�ȑ[�u���u����ׂ��ł��낤�B����C�G���̎҂ɂ��ẮC�����̖��̉�����a���̉̎��܂ʼn������邱�Ƃ��K�v�s���ł���B�v�Ƃ��镔��������(�����ؖ�5�[�W)�B���́u���̐ӔC�C���Q�̒��x�C�����̎x�����@�̌���v�C�u�����̖��̉�����a���̉܂ʼn�������v�Ƃ����\���́C������肪���ƊԂɂ����ĉ����������ł��邱�Ƃm�ɂ��Ă�����̂ƍl������(�Ȃ��C�u�x�����@�̌���v�Ƃ����������炵�āC�ٔ����ɂ�����������O���ɒu����Ă��Ȃ����Ƃ͖��炩�ł���B)�B
�@�G�@����ɁC���̃h�C�c��\�̒�Ăɑ��ẮC��퍑�̍����ƒ������̍����Ƃ̋�ʂ�݂����_�ŋc�_�����������C���̒��ŁC�X�C�X��\�̃{�[�����卲�́C�u�����̎҂ɑ��锅���̎x�����́C�ӔC�����퍑����Q�҂̍��Ƃ͕����ɂ���C�܂��C���a�ȊW���ێ����Ă���C�����͂�����P�[�X��e�Ղɂ��x�Ȃ������������Ԃɂ��邽�߁C���̏ꍇ�C�����s������ł��낤�B�c�����������͒����̎҂Ɠ��l�e�X�̌�퍑�̎҂ɂ��Ă������邪�C��퍑���m�̊Ԃł̔����̎x�����́C�a����B�����Ă���łȂ���Ό��肵���{���邱�Ƃ͂ł��Ȃ��ł��낤�B�v�Əq�ׂĂ���B����́C���炩�ɔ����̎x�������ƊԂōs���邱�ƁC��������C�l�̐������ɂ��ẮC�O��ی쌠�̍s�g�ɂ���ĉ��������ׂ����Ƃ�O��Ƃ��Ă������̂Ƃ�����(�܂��C�X�C�X��\�́C���Q�����ӔC�Ɋւ���K������ۓI���ًK��Ɨ������Ă��邱�Ƃ����炩�ł���B����6�[�W)�B
�@�����āC���̃X�C�X��\�̔����ɁC�h�C�c��\�͎ӈӂ�\���Ă����̂ł���(����18����26�Ȃ���29�[�W)�B
�@�܂��C�����h�C�c��\�̒�ĂɎ^���ł��Ȃ��Ƃ��Ă����C�M���X��\���C���̗��R�̒��ŁC�u�������������Ƃ͂��₷�����C�����������ׂ����ƊԂ̗ǍD�ȊW���Q���锽�̐��������N�������ƂȂ��C���̌�����K�p���邱�Ƃ́C��ύ���ł���(����:���p��)�B�v(����7�[�W)�Əq�ׂĂ���C������������͍��ƊԂɂ����ĉ��������ׂ��ł���Ƃ���������O��Ƃ�����̂ł���B
�@�ȏ�ɉ����C�R�c�o�߂ɂ����ẮC�l�ɐ��������Q�̋~�ςɂ��C�����Ȃ���@�ł������̉����������Ă������ɂ��Ă̔������S���Ȃ������̂ł���B
�@�I�@���̂ց[�O��2���c�ɂ����āC�h�C�c��\���������Ă��Ȃ��Ɏ������o�܂ɂ��āC�䂪���̐�O�ɂ�����펞���ۖ@�̑�\�I����ł���M�v�~�����m�́u�D�����ۖ@��v�㊪�v�ɂ��ρC�ȉ��̎���������Ƃ����B
�@���Ȃ킿�C1899�N�̂ց[�O��1���c�ɂ����āC1907�N�̑�2���c�Ɠ��l�ɁC�u����m�@�K����j�փX�����v�y�сu����m�@�K����j�փX���K���v���������ꂽ��(1899�N�̏��ɂ́C1907�N�̗�����3���ɑ�������K��͂Ȃ������B)�C��L1899�N�̗�����1���́C1907�N�̗�����1���Ɠ��l�ɁC�u���n�C���m���R�R���j�V�C�{���j�����X������m�@�K����j�փX���K���j�K���X���P�߃����X�w�V�v�ƋK�肵�Ă����B
�@�Ƃ��낪�C�h�C�c�̎Q�d�{����1902�N�ɐ��肵�ė��R�����ɗߒB�����u���D����v�̓��e�́C1899�N�̂ց[�O����K���Ƒ�����Ȃ����e�ƂȂ��Ă����B���Ȃ킿�C���̃h�C�c�́u���D����v�́C�G���R���ɑ�����Q��i�C�G���̐�̒n�y�яZ���̎戵���C�y�ђ������̌����`����3��15�͂��琬�邪�C���̎w�����O�́C������펞���@��`�ł������B���̗��O�Ƃ́C�u�}���D�͒P�ɓG���̌R���݂̂�Ƃ����C�G���̗L�`�I���݂͂̂����j����Ɏ~�߂��C�����Ă��̐��_�I�З͂����j���v���C�����ēG�̎��L���Y��j�C�G�̏�l�ɚ؋s�����ցC�s�s������C�����C�����̒�ᢂ��s�ЁC�����������߁C�r�������ؗ͘����E�����C���̑��G�ɋ����𑣂��u�a�����������ނ�ɕK�v�Ȃ�@���Ȃ��i�ɑi�ӂ���Ȃ�Ƃ��C�C����̗v������l����`�̔@���͊����������X������O�ɉ߂����ƒf���C�R���I�K�v�̎����`���ɓx�ɗ͐���������̂ł���B�v(�M�v�~���E�O�f355�Ȃ���356�[�W)�Ƃ������̂ł������B����ɁC���́u���D����v�̒��ɂ́C�u�C����̔@���͒P�ɓ��`�I�S���͂�L����ɉ߂����C�Ո헤�R�͎��Ȃ̕X�ɏ]�ДV��������炴����Ȃ�v�Ƃ����Ӗ����L���Ă��������߂ɁC�̓h�C�c�̐��ӂ�傢�ɋ^�����Ƃ���Ă���B�����ŁC�u����͕s�M���̔�������邽�߂��C����C���c�ɂ����āC���D�@�K���ដ��y�ѓ��K���̉������̓��c�ɕ���C������\�͕ʂɁw(��j�������ɂ��Ė{�K��[�{�����̗��D�@�K����K��]�Ɉᔽ������͔̂�Q���ɑ�������ਂ��̋`�����邱��(�������p��)(��)���̈ᔽ�s�ׂɕ����Ă͏������U�{���̐ӂɔC���ׂ����Ɓx�Ɖ]����錾�Ă��o�����B�e���S�܂͛x����ًc�Ȃ��C�S����v�ɂĔV�Ɏ^�����B���̌��ʂ��V����(���s)��O���́w�O�L�K���m�����j�ᔽ�V�^����D�c���҃n���Q�A���g�L�n�V�K�����m�Ӄ����t�x�L���m�g�X�B��D�c���҃n���m�R�����g���X���l���m�[�m�sਃj�t�L�ӔC�����t�B�x�Ƃ��ӕ�����Ɍ���Ȃ��肵�����I���ق̈�K��̑}���ƂȂ����̂ł���B�v�Ƃ���C�h�C�c�́C����1907�N�̗�����y�ѓ��K���ɏ]���C�V���ɌP�߂𗤌R�����ɔ��������C���̌P�߂́u�L��E�̒�c�̐ӔC�ォ��V����̏��K��ƈ�v�����߂��������̂ł������̂ł���B�v(����356�[�W)�Ƃ���Ă���B
�@�@(2)�@�ց[�O�����������ꂽ1907�N�����C�u�l�͍��ۖ@�̋q�̂Ȃ̂ł���v�Ƃ��錩�����ʐ��ł���(����73���E���c�ӌ���1�y�[�W)�C�I�b�y���n�C���́C�ց[�O����������O�̏ɂ��āC�u�ȑO(19���I)�ɂ����Ă��푈�@�K�̈ᔽ�͍��ەs�@�s�ׂƂ���Ă͂����B����������������@�s�ׂɑ��Ĕ�(��)�����s���Ƃ����m���������[���͂Ȃ������B�v�Ƃ��Ă���C�����������ƐӔC���̂��F�߂��Ă��Ȃ��������Ƃ𖾂炩�ɂ��Ă���(����73���E���c�ӌ���16�[�W)�B
�@���̂悤�ɁC�ց[�O�����������ꂽ1907�N�����̍��ۖ@�ɂ�����l�̈ʒu�t���́C�u�l�͍��ۖ@�̋q�̂ł���B�v�Ƃ����������x�z���Ă����̂ł���B�l�����ۂɁC���ۖ@��̎�̂Ƃ��ēo�ꂷ��̂́C��ꎟ���E����̍������ٍٔ����ݒu�ȍ~�̂��Ƃł���C����ȑO�̂ց[�O������������ɂ����āC�l�����ۖ@��@��̐������Ƃ������Ǝ��̂��l�����Ă��Ȃ������̂ł���(����73���E���c�ӌ���1�Ȃ���6�[�W)�B���̂��Ƃ́C�ߗ��̑ҋ��Ɋւ���1949�N8��12���̃W���l�[�����ɂ��Ắu�W���l�[��������V�v(�ԏ\�����ۈψ���)�ɂ����Ă����炩�ɂ���Ă���B���Ȃ킿�C�u���̈ᔽ�s�ׂɑ��镨�I�����ɂ��ẮC���Ȃ��Ƃ������̖@���̉��ɂ����ẮC�ᔽ�s�ׂ��s�����҂��������Ă������ɑ��āC�����҂����Q�ɂ��Ē��ڑi�ׂ��N�����Ƃ��ł���Ƃ͍l�����Ȃ����Ƃł���B�������̐����𑼍��ɑ��čs�����Ƃ��ł��邾���ł����āC���̐����͈�ʂɂ́u�펞�����v�Ə���������̂̈ꕔ�ƂȂ���̂ł���B�v(����74����682�[�W)�Ƃ���C�l�����Q���Ƃɑ����ڂ̑��Q������������F�߂���Ƃ������Ƃ́u�l�����Ȃ����Ɓv�������̂ł���B
�@����̂ɁC�O�L�̂Ƃ���C�h�C�c��\�̒�ĂɊւ��C�X�C�X��\�̃{�[�����卲�́C�u�����̎҂ɑ��锅���̎x�����́C�ӔC�����퍑����Q���ƕ����W���ێ����Ă���C�����͂�����P�[�X��e�Ղɂ��x�Ȃ����������邽�߁C���̏ꍇ�C�����ɍs����ł��낤�B�c��퍑���m�̊Ԃł̔����x�����́C�a����B�����Ă���łȂ���Ό��肵���{���邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B�v�Ɣ������C�����̎x�������u��퍑���m�̊ԁv�łȂ���邱�Ƃ𖾂炩�ɂ��C�h�C�c��\�́C�X�C�X��\�̔����Ɏӈӂ�\���Ă����̂ł���(����18���E�����ӌ���28�y��29�[�W)�B
�@���c���v�������C���̈ӌ����ŁC�u�h�C�c��ẮC�n�[�O���̕t���K���������Ɏ����I�ɗ��s���邩�Ƃ����_�c�̗���̒��ŏo���ꂽ���Ƃɒ��ӂ���K�v������B���ׂĂ̌R���\�����̍s�ׂ����ƂɋA�����邱�ƁA���������Ĉᔽ�s�ׂɂ���đ��Q���������ꍇ�ɂ͍��Ƃ������ӔC�����Ƃ�������3���Ƃ��ċK�肳�ꂽ�̂́C�ȏ�̂悤�ȗ��s�m�ێ�i�̈���@�Ƃ��Ăł������B��������ƁA����̂́C��Q�Ҍl�ɑ��Ăł���{���ɑ��Ăł���C�K���ᔽ�̍��ɔ����ӔC���Ƃɂ������킹�邱�ƂɎ�Ⴊ�������̂ł����āC���̋�̓I�ȕ��@�C���Ȃ킿����������Q�҂Ɩ{���̂�����Ɏx�����邩�Ƃ��C�ǂ̂悤�Ɏx������̂��Ȃǂɂ��āC����S�������Ă���Ƃ͎v���Ȃ��B�N���ߒ��ł́C�h�C�c��Ăɂ����Đ݂���ꂽ���������ƓG�����Ƃ̋�ʂ̐���ɂ��̋c�_�̑������������Ă������Ƃ��z�N����K�v������B���������āC���Ȃ��Ƃ����Ƃ���Q�Ҍl���ŏI�I�ɔ��������闧��ƂȂ邱�Ƃ��z�肳��Ă����Ƃ��Ă��C���ꂪ�����ٔ����ɂ����Ē��ڂȂ����̂��C����Ƃ��{���̊O��I�ی��ʂ��ĂȂ����̂��C���ۍٔ����ɂ����ĂȂ����̂��Ƃ����_�ɂ��āC�N���ߒ�����͂����ꂩ�̌��_���m��I�ɂ݂��т��o����قǖ��m�Ȃ��͉̂��������o���Ȃ��ƌ���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�v�Ƃ���Ă���(����73���E���c�ӌ���15�[�W)�B
�@���������āC�ց[�O������̂��߂̉�c�Q���҂��C���́u�l�͍��ۖ@�̋q�̂ɂ���B�v�Ƃ������R�̌�����O��ɁC�����̋N����c�ɗՂƍl����̂����R�ł���C�ց[�O������3���ɂ��C�l�ɁC���ۖ@��̑��Q������������F�߂�Ƃ����F���͈�Ȃ������Ƃ݂�̂����R�ł���B
�@�@(3)�@���̓_�Ɋւ��C���������ٔ�������13�N10��11�������E�����1769��61�[�W���C�T�i�l��̏�L�咣�Ɠ��|�̓�������R������̎咣�ɑ��C�u�ց[�O�����������ꂽ1907�N�����̍��ۊ��ɂ����āC��Q�҂����ɂ̎�v�҂ł���ׂ��ł���Ƃ��Ă��C���̌����͍��ƊԂ̉����Ɉς˂�����̂ŁC�l�����ڂɔ��������������߂邱�Ƃ͂ł��Ȃ��Ɖ�����Ă����̂ł���(�u�l�̃N���C���̍��Ƃ̃N���C���w�̖v���v)�B���̂悤�Ȓ��A�ց[�O������3���ɂ����āC��Q�Ҍl�ɑ��Q�������������m�F���悤�Ƃ���̂ł���C���̋N���̉ߒ��ɂ����āA�]���̍��ۖ@��̓`���I�ȍ��ƐӔC�̌������C�����ׂ����ۂ��Ƃ����ϓ_����C��X�̋c�_����킳��C�����̋c�_���s�����ꂽ�͂��ł���B�Ƃ��낪�C(����)�ց[�O������3���̋N���ߒ��ɂ����āC�e����\���푈��Q�����l�Ɍ�퓖�����ɑ��钼�ڂ̑��Q������������^���邱�Ƃ��ӎ����ď\���ȋc�_�������Ƃ����悤�Ȍ`�Ղ͔F�߂��Ȃ��̂ł���B���̂悤�Ȏ���炷��ƁC�h�C�c��\�̏�L�̒��(���p�Ғ�:�ց[�O����K���Ɉᔽ���Ē����̎҂�N�Q������퓖���������̎҂ɑ��Ĕ�������ӔC���Ƃ̏�����t��������Ƃ̒�Ă��w��)���C�l�����Q���ɑ��Ē��ڂɑ��Q�����𐿋����邱�Ƃ����e���ׂ��ł���Ƃ̖��m�ȈӐ}�ɂ����̂Ƃ͔F�ߓ�B�܂��C�e����\���C�ց[�O������3���̋N���ߒ��ɂ����āC�ց[�O����K���ᔽ�̍s�ׂɂ���đ��Q�������l�ɉ��Q���ɑ��鑹�Q������������^���邱�Ƃ��Ӑ}���Ă����ȂǂƂ��F�߂��Ȃ��Ƃ����ׂ��ł���B�����̍��ۖ@��̈�ʓI�ȍl�����ɂ��C�ց[�O������3�����C���ƊԂ̔����ɂ��ċK�肵���ɂ����Ȃ��Ƃ����ׂ��ł���B�v�Ɛ����ɔ������Ă���Ƃ���ł���C�ց[�O������3���̂��̂悤�ȉ��߂́C1952�N�����̐ԏ\�����ۈψ���̌���(����75����)�ɂ���Ă��x������Ă���Ƃ���ł���(��L���߂��̂���̂Ƃ��āC�R�{����E�V�x���A�}���i�����Ɋւ��钲������46�[�W(����17����)�A����Y��E�S���V�ō��ۖ@�T�_��470�[�W�C�����n�ٕ���10�N10��9�������E�����1683��57�[�W�C�����n�ٕ���10�N11��26�������E�ז�����46��2��731�y�[�W�C�����n�ٕ���10�N11��30�������E�ז�����46��2��774�[�W�C�������ٕ���12�N12��6�������E�����1744��48�[�W�C�������ٕ���13�N2��8������(����23����)�C�����n�ٕ���13�N5��30������(����40����)�C�ō��ٕ���13�N10��16����O���@�쌈��(����43����)�C�������ٕ���14�N3��27�������E�����1802��76�[�W)�B
�@�@(4)�@���������āC�T�i�l��̎咣�͎����ł���C�ց[�O������3���́C���̋N���ߒ��ɂ��݂Ă��C�l�̑��Q�������������߂����̂Ɖ�����Ȃ����Ƃ͖��炩�ł���B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�ȁ@��

|