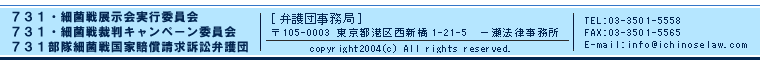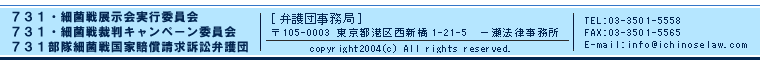�����P�S�N�i�l�j��S�W�P�T��
�T�i�l ���G�łق��P�V�X��
��T�i�l�@��
���@���@���@�ʁi�R�j
����16�N3��18��
���������ٔ�����Q�������@�䒆
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@�@�@�@�@�@�@�@�@��T�i�l�w��㗝�l
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@
�@�{�@�@�@�c�@�@�@���@�@�@�i
�� �@�@�@��@ �@�@���@���@��
�F�@�@�@�J�@�@�@���@�@�@�C
���@�@�@���@�@�@�F�@�@�@�M
�r�@�@�@��@�@�@�`�@�@�@��
���@�@ �@�@�@�@�@���@�@�@�D
���@�@�@���@�@�@�@ �@�@�@�W
��P�@���Ɩ����ӂ̖@���ɂ���
�@�P�@�͂��߂�
�@�Q�@�������ٕ����P�T�N�V�������ɂ���
�@�@�i�P�j�������ٕ����P�T�N�V�������̓��e��
�@�@�i�Q�j�������ٕ����P�T�N�V�������̌��Ɣ�T�i�l�̔��_�̊T�v
�@�@�i�R�j���Ɩ����ӂ̖@���̍����̗������s�\���ł��邱�Ƃɂ���
�@�@�@�@�A�@���Ɩ����ӂ̖@���̍��������炩�łȂ��Ƃ̔����ɂ���
�@�@�@�@�@�@�i�A�j�@�����эו����P�T�N�V�������̔���
�@�@�@�@�@�@�i�C�j�@��T�i�l�̔��_
�@�@�@�@�C�@���Ɩ����ӂ̖@�����i�ז@��̐���ɂ����Ȃ��Ƃ̔����ɂ���
�@�@�@�@�@�@�i�A�j�@�������ٕ����P�T�N�V�������̔���
�@�@�@�@�@�@�i�C�j�@��T�i�l�̔��_
�@�@�@�@�E�@�����@�����@�̕s�@�s�K��̓��ʖ@�ł���Ƃ̔����ɂ���
�@�@�@�@�@�@�i�A�j�@�������ٕ����P�T�N�V�������̔���
�@�@�@�@�@�@�i�C�j�@��T�i�l�̔��_
�@�@�@�@�@�@�i�E�j�@���Ɣ����@�Ă̋N���҂̌��ɂ���
�@�@�@�@�@�@�i�G�j�@����
�@�@�i�S�j�@�����@�����U���y�эō��ُ��a�Q�T�N�����ɔ����邱�Ƃɂ���
�@�@�@�@�A�@�������ٕ����P�T�N�V�������̔���
�@�@�@�@�C�@��T�i�l�̔��_
�@�@�@�@�E�@�ߎ��̍ٔ��ᓙ
�@�@�i�T�j�@���_
�@�R�@�������ٕ����P�U�N�Q�������̑Ó����ɂ���
��Q�@���ˊ��Ԃɂ���
�@�P�@�͂��߂�
�@�Q�@�����n�ٕ����P�T�N�X�������̔�����
�@�R�@���@�V�Q�S����i�̉��ߓK�p�Ɋւ��锻��ᔽ��
�@�S�@����
��R�@���������������ɂ���
�@�P�@�T�i�l��̎咣�̗v�|��
�@�Q�@�T���E�t�����V�X�R���a���̈Ӌ`���ɂ���
�@�R�@�u�T���t�����V�X�R���a���ɂ�����l�̐��������v�ւ���T�i�l��̎咣�̌��ɂ���
�@�@�i�P�j�@�T�i�l��̎咣
�@�@�i�Q�j�@��T�i�l�̔��_
�@�S�@���ؕ��a���Ɋւ���T�i�l��̎咣�̌��ɂ���
�@�@�i�P�j�@�T�i�l��̎咣
�@�@�i�Q�j�@��T�i�l�̔��_
�@�@�@�@�A�@���ؕ��a�������̌o��
�@�@�@�@�C�@�푈��Ԃ̏I���A�������тɍ��Y�y�ѐ������̖�菈��
�@�@�@�@�E�@�t�����������ɂ���
�@�@�@�@�G�@����
�@�T�@�������������Ɋւ���T�i�l��̎咣�̌��ɂ���
�@�@�i�P�j�@�T�i�l��̎咣
�@�@�i�Q�j�@�������𐳏퉻�Ɏ���o�܂ɂ���
�@�@�@�@�A�@�͂��߂�
�@�@�@�@�C�@���ؐl�����a�����{�̌����Ɠ��{���{�̌����ɂ���
�@�@�i�R�j�@�������������̕����ɂ���
�@�@�i�S�j�@���������������o��̓��{���{�̌���\��
�@�@�i�T�j�@����
�@�U�@��T�i�l�̎咣�����ۏ펯�Ƃ��������ꂽ���̂ł���Ƃ̍T�i�l��̎咣�ɂ���
�@�@�i�P�j�@�T�i�l��̎咣
�@�@�i�Q�j�@��T�i�l��̔��_
�@�V�@���_
�@��T�i�l�́A�{�������ʂɂ����āA�T�i�l���2003�N�i����15�N�j12��4���t����3�������ʁi�ȉ��u�T�i�l���3�������ʁv�Ƃ����B�j�ɂ�����咣�ɑ��A�K�v�ƔF�߂�͈͂Ŕ��_����B
�@�Ȃ��A�����́A���ɒf��ق��]�O�̗�ɂ��B
��P�@���Ɩ����ӂ̖@���ɂ���
�@�P�@�͂��߂�
�@�i�P�j �T�i�l��́A�T�i�l���3�������ʂɂ����āA���Ɩ����ӂ̖@���Ɋւ��A�@����23�N�̎��_�ŁA���Ɩ����ӂ̖@�����m�����Ă����Ƃ͔F�߂��Ȃ��i������6�Ȃ���14�y�[�W�j�A�A���Ɩ����ӂ̖@����ے肷��w�������݂����i������14�15�y�[�W�j�A�B���s���@�̗��@�҈ӎv�́A���ʖ@�����肳��Ȃ��ꍇ�ɂ͖��@715�������ɂ��K�p���ׂ��ł���Ƃ������̂ł������i������15�A16�y�[�W�j�A�C�{���́A�ی삷�ׂ������ł͂Ȃ����獑�Ɩ����ӂ̖@���͓K�p����Ȃ��i������17�A18�y�[�W�j�A�D���Ɩ����ӂ̖@���͊O���ł̊O���l�ɑ��錠�͍�p�ɂ͓K�p����Ȃ��i������18�Ȃ���21�y�[�W�j�A�E�w�[�O���̍����@���ɂ���āA���Ɩ����ӂ̖@���͔r�������i������21�Ȃ���24�y�[�W�j�A�F���Ɩ����ӂ̖@���́A���݂̖@���߂Ɋ�Â��Ĕے肳���ׂ��ł���i������24�Ȃ���26�y�[�W�j�A�G�����@����6���́u�]�O�̗�ɂ��v���Ƃ����Ɩ����ӂ�K�p���鍪���Ƃ͂Ȃ�Ȃ��i������26�A27�y�[�W�j�ȂǂƎ咣����B
�@�������Ȃ���A�T�i�l��̏�L�咣�́A��������T�i�l��̏]�O�̎咣���J��Ԃ������̂ɉ߂����A��T�i�l�́A��T�i�l�̕���15�N8��4���t����������(1)(�ȉ��u��T�i�l��������(1)�v�Ƃ����B)1�Ȃ���61�؈�W�ɂ����āA�T�i�l��̏�L�咣��������������ł��邱�Ƃ����ɖ��炩�ɂ����Ƃ���ł���B
�@�i�Q�j �����A�T�i�l��́A�T�i�l���3�������ʂɂ����āA�V���ɓ��������ٔ�������15�N7��22�������i�ȉ��u�������ٕ���15�N7�������v�Ƃ����B�j�̔������e���w�E������A�����������Ƃ��āA�{���ɍ��Ɩ����ӂ̖@����K�p���邱�Ƃ͂ł��Ȃ��Ƃ̎咣��t�����Ă���B
�@�������ٕ���15�N7�������́A�����N�����o�g�҂��T�i�l�Ƃ��邢����]�R�Ԉ��w�y�ь��R���ɂ�鑹�Q�������������Ɋւ��A�������T�i�l��̍T�i�����p���A���ɑ��鐿�������p�������R�������ێ����Ă���A���_�ɂ����Ă͐����ł���B
�@�������A�������ٕ���15�N7�������́A��T�i�l��������(1)�Ŏw�E���������n��3�������Ɠ��l�A���̗��R���̔��f�ɂ����āA���Ɩ����ӂ̖@���ɑ��闝��������Ă���A���̌��ʂƂ��āA�����@����6���Ɉᔽ����ƂƂ��ɁA�ō��ُ��a2�N�����i�ō��ُ��a25�N4��11����O���@�씻���E�ٔ��W����3��225�y�[�W�j�Ƒ������锻�f���������̂ł���B����ɑ��A���̌�ɔ��f�������ꂽ���������ٔ�������16�N2��9�������i����76���A�����������p�����R�����͉���77���B�ȉ��u�������ٕ���16�N2�������v�Ƃ����B�j�ł́A���Ɩ����ӂ̖@���ɑ��鐳����������������Ă���B
�@���������āA�����n��3�������Ɠ��l�A�������ٕ���15�N7�������̑����Ƃ͌�������������������Ƃ��錴����̎咣�͎����Ƃ��킴��Ȃ��B
�@�i�R�j �ȉ��A�������ٕ���15�N7�������̖��_�ɂ��ڏq����ƂƂ��ɁA�������y�ѓ����n��3�������i�ȉ��A���҂��āu�������v�Ƃ������B�j�ɑ���퍐�̔��_��e��āA���Ɩ����ӂ̖@���Ɋւ��鐳�����������������������ٕ���16�N2�������̔������e�𖾂炩�ɂ���B
�@�Q�@�������ٕ���15�N7�������ɂ���
�@�i�P�j �������ٕ���15�N7�������̓��e��
�@�������ٕ���15�N7�������́A�����A�����N�n��Ɏu�蕺���x�y�ђ������x�A���R��W�A�������y�э������p�߂�K�p����Ȃǂ��A�����N�����o�g�҂������{�R�̌R�l�R���Ƃ��A�܂������N�����o�g�҂̏�����������]�R�Ԉ��w�Ƃ������ƂȂǂɑ��A�����N�����o�g�҂��A���ɑ��đ��Q�����������߂����Ăɂ��A�����炪�u��T�i�l�̍s�ׂ́A��l���I�s�ׂł����āA�u�l���ɑ���߁v�ɊY�����A���������������@�ł��邩��A���@��̕s�@�s�ׂ��\�����A��T�i�l�͖��@��̕s�@�s�ׁi���@709���A715���j�Ɋ�Â����Q�����ӔC���v�i������79�y�[�W�j�Ǝ咣�����̂ɑ��A���̂Ƃ��蔻�������B
�@�u���Ɣ����@�i���a22�N10��27�����z�A�����{�s�j�{�s�O�ɂ����ẮA��ʂɍ��̑��Q�����ӔC��F�߂閾���̋K��͂Ȃ��A���Ɣ����@����6���i�}�}�j�ɂ����āA�u���̖@���{�s�O�̍s�ׂɊ�Â����Q�ɂ��ẮA�Ȃ��]�O�̗�ɂ��B�v�ƋK�肳��A���@�̋K��̑k�y�I�K�p���ے肳�ꂽ�ȏ�A���@�{�s�O�̌������̌����͂̍s�g�̈�@�𗝗R�Ƃ��鍑�̑��Q�����ӔC�Ɋւ��ẮA���@(����31�N�{�s)�̕s�@�s�ׂɊւ���K�肪�������̌����͂̍s�g�ɂ��Ă��K�p�����邩�ۂ��Ƃ������@�̉��߂Ɉς˂��Ă����Ɖ�������ق��͂Ȃ��B�v(������79�A80�؈�W)�B
�A�u���@�ߒ��A�w���A������l������ƁA�������@���ɂ����ẮA���̌��͍�p�ɂ��Ă͖��@�̕s�@�s�ׂ̓K�p��ے肵�A���̑��Q�ɂ��č��������ӔC��Ȃ��Ɖ��߂��ꂽ�Ƃ��킴��Ȃ����A�w����A�������͍̔�p�ł��鎄�o�ϊ����ɂ�鑹�Q�ɂ��ẮA���@�ɂ�鑹�Q�����@���̓K�p������Ɖ��߂���A�܂��A��������̂悤�ɉ��߂��Ă����B�v(������80�A81�؈�W)
�B�u�������A��O�ɂ����āA��L�̂悤�ȉ��߂��̂��Ă��������͕K���������炩�ł͂Ȃ��A���ǁA���̌��͍�p�ɔ����s�@�s�ׂɊ�Â����Q���������i�ׂɂ��Ă͎i�@�ٔ����ɂ����Ė����ٔ������ƔF�߂��s���ٔ����ɂ����Ă��s���ٔ������Ƃ��ĔF�߂��A���ɂ��̑i�ׂ����Ȃ��������߁A���̎�̑��Q����������@�I�Ɏ���������@��������Ă��������̂��Ƃł���A���̌��͍�p�ɂ����Q�s�ׂ����̓I�Ɉ�@���������Ƃ��L�Ӑ���Ə�����Ă�����̂ł͂Ȃ������Ɖ����ׂ��ł���B������u���Ɩ����ӂ̖@���v�́A��L�̂悤�ȑi�חv���Ƃ��Ă̌����ی�K�i��ے肷����߂��̂��Ă������Ƃɂ����̂ɂ������A�s���ٔ������p�~����A���@�A���@�W�̑i�ׂ��i�@�ٔ����ɂ����ĐR������邱�Ƃ��F�߂��錻�s���@�y�эٔ����@�̉��ɂ����Ắu���Ɩ����ӂ̖@���v�ɐ������Ȃ����������������o����B���Ƃ��ƍ��Ɣ����@�͖��@709���ȉ��̕s�@�s�ז@�̓��ʖ@�ł��鐫�i���L���A���Ɣ����@�̐��肪�Ȃ���Δ����������̎���@��̍������Ȃ������Ɖ����ׂ��ł͂Ȃ��A��ʖ@�Ƃ��Ă̖��@709���ȉ��̕s�@�s�ז@�������Ƃ��ēK�p�����Ɖ����ׂ��]�n���\���ɂ��蓾�����̂ł���A���@715���̕�����́A�������̌����͂̍s�g�������̓K�p����r������Ă���Ƃ͂����Ȃ����ƁA�s���ٔ��@16�����u�s���ٔ����n���Q�v���m�i�׃��Z�X�v�ƋK�肵�Ă���A�����̋K��́A���̖@��́A�����͂̍s�g�Ɉ�@���������ꍇ�ɍ��ɑ��Q�������������������邱�Ƃ�O��Ƃ��Ȃ���A�s���ٔ��������Q���������i�ׂ����Ȃ��Ƃ����i�ז@��̋K���u�����ɂ����Ȃ����̂Ɖ�����A�����A�i�@�ٔ������O����Ƃ��čs�������������͂̍s�g�̓K�ہA���r�f���Ȃ���Ȃ�Ȃ����́A�s���ٔ����ɂ��s���ٔ��葱��݂�����|�ɂ��݁A���ǎi�@�ٔ��������f�����鎄�@��̖����ٔ������ł͂Ȃ��Ƃ��Č����ی�K�i��F�߂Ă��Ȃ������ɂ����Ȃ��Ɖ�����邩��A���s���@�y�эٔ����@�̉��ɂ����čٔ��������Ɣ����@���{�s�����ȑO�̖@�̌n�̉��ɂ����閯�@�̕s�@�s�ׂ̋K��̉��߁E�K�p���s���ɓ������ẮA�i�葱��̐����~���ꂽ���̂ƍl����̂������ł���(�����Ƃ��A���Ɣ����@(���a22�N10��27�����z�A�����{�s)�{�s�O�ɂ����ẮA�������̌��͓I��p�ɂ�鑹�Q�ɂ��ẮA���@����6���ɂ��u�]�O�̗�ɂ��v���̂Ƃ���Ă�������A�����ی�K�i���F�߂��Ȃ����ߑi�����s�K�@�ƂȂ�Ɖ�����]�n�����邪�A���@����6���������ٔ������ł��邱�Ƃ��ˑR�Ƃ��Ĕے肷��i�葱�K��ł���Ɖ�����̂͋^�₪����B�j�B�v�i������81�A82�y�[�W�j
�C�u�����ŁA���@�ɂ�鑹�Q�����@���̓K�p�̗]�n�����蓾��̂ŁA�Ƃ肠�����A���̕s�@�s�אӔC�̐��ۂɂ��Ĉȉ��ɔ��f���Ă����B�v(������82�؈�W)
�@�������ٕ���15�N7�������́A��L�̂悤�ɔ������āA�����@�{�s�O�̌������̌����͂̍s�g�ɂ��Ă����@715���̓K�p�̉\����F�߁A�����Ɋ�Â����Q�����������̐�����F�߂��B���̏�ŁA�������́A�����鑹�Q�����������́A�u���Y�y�ѐ������Ɋւ�����̉������тɌo�ϋ��͂Ɋւ�����{���Ƒ�ؖ����Ƃ̊Ԃ̋���v(�ȉ��u���ؐ���������v�Ƃ����B)2���́u���Y�A�����y�ї��v�v�ɊY������Ƃ����B���̌��ʁA�݊̊؍��l�̑��Q�����������ɂ��ẮA�u���Y�y�ѐ������Ɋւ�����̉������тɌo�ϋ��͂Ɋւ�����{���Ƒ�ؖ����Ƃ̊Ԃ̋�������̎��{�ɔ�����ؖ������̍��Y���ɑ���[�u�Ɋւ���@���v(���a40�N�@����144��)1���̓K�p�ɂ����ł���Ƃ��A�����A�ݓ��؍��l�̑��Q�����������ɂ��ẮA���ؐ���������2��2(a)�Ɋ�Â����ؐ���������ɂ�����炸�������邱�ƂƂȂ邪�A���ؐ���������̒�����20�N�̌o�߂ɂ��A���@724����i�̓K�p�ɂ���ď��ł����Ɣ��������B
�@�i�Q�j �������ٕ���15�N7�������̌��Ɣ�T�i�l�̔��_�̊T�v
�@�������ٕ���15�N7�������̍��Ɩ����ӂ̖@���̓K�p��ے肷�闝�R�́A��{�I�ɓ����n��3�������Ɠ��l�ł���B
�@���Ȃ킿�A�������ٕ���15�N7�������́A�����n��3�������Ɠ��l�ɁA�@��O�ɂ����āA�ʐ��E���Ⴊ�A���̌��͓I��p�ɂ�鑹�Q�ɂ��āA���@�̕s�@�s�K��̓K�p�����Ȃ��Ɖ��߂��Ă������������炩�łȂ��A�A�s���ٔ��@16���͑i��̋K��ɂ����Ȃ����Ƃ���A���Ɩ����ӂ̖@���́A���Ƃ̌��͓I��p�Ɋ�Â����Q�ɂ��Ė��@�̓K�p��F�߁A���Q�������������������邪�A�P�ɑi�ׂɂ����đi���ł��Ȃ������Ƃ����i��̐���ɂ����Ȃ��A�B���@715���̕�����A�������̌����͂̍s�g���r������Ă��Ȃ��A�C�����@�{�s�O�̌������̌����͂̍s�g�̈�@�𗝗R�Ƃ��鍑�̑��Q�����ӔC�Ɋւ��ẮA���@715���̉��߂ɂ䂾�˂��Ă����Ɖ�������ق��͂Ȃ��Ƃ��A�����āA�������ٕ���15�N7�������́A�D���Ƃ̌��͓I��p�Ɋ�Â����Q�ɖ��@�̕s�@�s�K��̓K�p��F�߂闝�R�Ƃ��āA���s�̍��Ɣ����@�͖��@709���ȉ��̕s�@�s�ז@�̓��ʖ@�ł���A���Ɣ����@�����肳��Ȃ���A��ʖ@�Ƃ��Ă̖��@709���ȉ����K�p����邱�ƂƂȂ�ȂǂƂ��Ă���B
�@�������Ȃ���A�������̂����̎w�E�́A�����n��3�������ɂ��A��T�i�l��������(1)44�Ȃ���61�y�[�W�ŏڏq�����悤�ɁA����23�N�ɁA���Ɩ����ӂ̖@���������̖@����Ƃ��č̂�ꂽ�����y�эs���ٔ��@16���A�����@���̗��@�o�܂ɂ��Ă̗����������A���Ɩ����ӂ̖@�����P�Ɏ葱�@�̖��ɗR��������̂ł͂Ȃ��A���̖@�ɗR��������̂ł��邱�Ƃ��ʼn߂��A���Ɩ����ӂ̖@���̗���������Ă���A�܂��A�����@����6���̉��߂����A�ō��ُ��a25�N�����Ƒ���������̂ł����āA�����ƌ��킴��Ȃ��B
�@�ȉ��A�������ٕ���15�N7�������ɑ��A�����̓_�ɂ��āA����ɖ��炩�ɂ���B
�@�i�R�j ���Ɩ����ӂ̖@���̍����̗������s�\���ł��邱�Ƃɂ���
�@�A�@���Ɩ����ӂ̖@���̍��������炩�łȂ��Ƃ̔����ɂ���
�i�A�j�������ٕ���15�N7�������̔���
�@�������ٕ���15�N7�������́A�����n��3�������Ɠ��l�ɁA�u��O�ɂ����āA��L�̂悤�ȉ��߁i���p�Ғ��E���Ɩ����ӂ̖@���j���̂��Ă��������͕K���������炩�ł͂ȁv���Ɣ�������B
�i�C�j��T�i�l�̔��_
�@�������A��T�i�l��������(1)2�Ȃ���12�؈�W�ŏڏq�����Ƃ���A�䂪���̖������{�́A�����ɒ��������s�������̉��������ƖڕW�Ƃ��āA�{�A�\�i�[�h�ȂNJO���̗l�X�Ȗ@���w�҂̈ӌ����Q�l�ɂ��Ȃ���A�ߑ㍑�ƂƂ��Ă̖@���x�̐�����i�߂Ă����B�����āA���̈�Ƃ��āA�s���ٔ��@�y�і��@�̐����}�������A�ߑ�@�����ƂƂ��Čo����L���Ă��Ȃ��䂪���Ƃ��ẮA�����̖@���x���Q�Ƃ��Ȃ���A�@���̐�����}�炴��Ȃ������B���Ɣ����ӔC�̖��ɂ��ẮA�����A�{�A�\�i�[�h�̈ӌ��Ɋ�Â��A���Ɣ����ӔC��F�߂�K��@�̋K��ɒu�����Ƃ����B�������A�{�A�\�i�[�h�̈ӌ��́A���̑O��Ƃ��Ă̔�r�@�̎����F���Ɍ�F������A�ނ���A���Ɣ����ӔC�Ɋւ��鏔�O���̖@���x�́A�u�N��n�s�P��ਃX�R�g�\�n�Y�B�v�𗝔O�Ƃ��āA���Ɣ����ӔC��ے肵�����̂���ʂł���A�܂��A���ɁA�{�A�\�i�[�h�̈ӌ��̂Ƃ���A���Ɣ����ӔC�̖����u��_�j�����ƃ���ԃm�����ᶃV�e���@�m�͚���������v(���B�̍����a�Y�����ȁE����32����323�؈�W)��A�u�����������@��j���W�V�A�����Ƒ����\��A����������V��n�A�O���l���Ɛ��{�Ƃ̑��c�V�_���Ƒ��������v(���B�̎R�c���`�i�@��b�����ȁE����32����639�[�W)�����O�������Ƃ���A���ǁA���Ɩ����ӂ̖@�����̗p���A�{�A�\�i�[�h���@���Ă��獑�Ɣ����ӔC�̋K�肪�폜���ꂽ�̂ł���B
�@�ȏ�̌o�܂ɏƂ点�A�������ٕ���15�N7�������́u�������@���ɂ����ẮA���̌��͍�p�ɂ��Ă͖��@�̓K�p��ے肵�v�Ă����Ƃ́u���߂��̂��Ă����������K���������炩�ł͂ȁv���Ƃ̔����́A�����n��3�������Ɠ��l�Ɏ����ł���B
�@�C�@���Ɩ����ӂ̖@�����i�ז@��̐���ɂ����Ȃ��Ƃ̔����ɂ���
�i�A�j�������ٕ���15�N7�������̔���
�@�܂��A�������ٕ���15�N7�������́A�u���̌��͍�p�ɔ����s�@�s�ׂɊ�Â����Q���������i�ׂɂ��Ă͎i�@�ٔ����ɂ����Ė����ٔ������ƔF�߂��s���ٔ����ɂ����Ă��s���ٔ������Ƃ��ĔF�߂��A���ɂ��̑i�ׂ����Ȃ��������߁A���̎�̑��Q����������@�I�Ɏ���������@��������Ă��������̂��Ƃł���A���̌��͍�p�ɂ����Q�s�ׂ����̓I�Ɉ�@���������Ƃ��L�Ӑ���Ə�����Ă�����̂ł͂Ȃ������Ɖ����ׂ��ł���B������u���Ɩ����ӂ̖@���v�́A��L�̂悤�ȑi�חv���Ƃ��Ă̌����ی�K�i��ے肷����߂��̂��Ă������Ƃɂ����̂ɂ������A�s���ٔ������p�~����A���@�A���@�W�̑i�ׂ��i�@�ٔ����ɂ����ĐR������邱�Ƃ��F�߂��錻�s���@�y�эٔ����@�̉��ɂ����Ắu���Ɩ����ӂ̖@���v�ɐ������Ȃ����������������o����v�Ɣ�������B
�i�C�j��T�i�l�̔��_
a�@�������ٕ���15�N7�������̂����锻���́A�v����ɁA���̖@��A���̌��͓I��p�Ɋ�Â����Q�ɂ��Ă��A���@�̓K�p������A���Q�������������������邪�A���Ɩ����ӂ̖@���́A�s���ٔ����y�юi�@�ٔ����ɑ��A���̔��������߂�i�ׂ���N�ł��Ȃ��������Ƃɂ��i�ז@��̐���ɂ����Ȃ��Ƃ�����̂ł���B
�@�������A��T�i�l���]�O����J��Ԃ��w�E���Ă���Ƃ���A���Ɩ����ӂ̖@���́A���̌��͓I��p�Ɋ�Â����Q�ɂ��āA���@�̕s�@�s�K��̓K�p���Ȃ��A�����@�{�s�O�́A���Q�����ӔC��F�߂��ʓI�K�肪�Ȃ��������Ƃɂ����̖@��̖@���ł����āi�ō��ُ��a25�N�����Q�Ɓj�A�P�Ȃ�i�א��x��̖��ł͂Ȃ��B
b�@�܂��A�������ٕ���15�N7�������ɂ��ƁA�������@���ɂ����āA���Ƃ̌��͓I��p�Ɋ�Â����Q�ɂ��Ė��@�̕s�@�s�K��̓K�p��F�߁A���̖@��A���Q��������������������ɂ�������炸�A���̂ɍٔ����ɂ����đi���ł��Ȃ������̂��A�����ی쎑�i���Ȃ��̂��ɂ��āA��������I�Ȑ������Ȃ���Ă��Ȃ��B�O�L�̂悤�ɁA���Ɩ����ӂ̖@���́A�u�N��n�s�P��ਃX�R�g�\�n�Y�B�v�Ƃ̗��O�Ɋ�Â����̂ł����āA�ٔ����ɂ����đi���ł��Ȃ��̂́A���̖@�㑹�Q�������������������Ȃ�����ɂق��Ȃ�Ȃ��Ƃ����ׂ��ł���B
c�@����ɁA�������ٕ���15�N7�������́A�u�s���ٔ������p�~����A���@�A���@�W�̑i�ׂ��i�@�ٔ����ɂ����ĐR������邱�Ƃ��F�߂��錻�s���@�y�эٔ����@�̉��ɂ����Ắu���Ɩ����ӂ̖@���v�ɐ������Ȃ����������������o����B�v�Ɣ������邪�A���Ƃ��ׂ��́A���s���@���ɂ����鍇�����ł͂Ȃ��A�s���@�ł��閾�����@���ɂ����鍇�����ł���B
�@�O�L�̂悤�ɁA���Ɩ����ӂ̖@���́A�s���ٔ��@�Ƌ����@�����z���ꂽ����23�N�̎��_�ŁA���Ƃ̌��͓I��p�ɂ��č��͔����ӔC��Ȃ��Ƃ��鍑�Ɩ����ӂ̖@������{�I�@����Ƃ��Ċm����(����G�E�s���@�U(��2��)222�A223�؈�W�j�F�ꍎ��E���ƐӔC�@�̕���409�Ȃ���411�؈�W)�A����Ɋ�Â��A�s���ٔ��@16���A�����@���̋K�肪�݂���ꂽ�̂ł��邪�A��O�ɂ����ẮA�䂪���݂̂Ȃ炸�A�č��A�p�����̐�i���ɂ����āA����������Ɩ����ӂ̖@������{�I�@����Ƃ��Ă����̂ł����āA���̓����̉䂪���̐������f���������E��������L���Ă������Ƃ͖��炩�ł���B
�@�č��ł́A�u���͈����Ȃ����B�v�Ƃ����R�����E���[��̌����������p���A1946�N�ɘA�M�s�@�s�א������@�iFTCA)�𐧒肷��܂ł́A���Ɩ����ӂ��̗p����Ă�����(�A���h���u�e���̍��ƕ⏞�@�̗��j�I�W�J�Ɠ����]�A�����J�v���ƕ⏞�@�̌n�T(135�؈�W))�A���̍��Ɩ����ӂ̍����ɂ��āA1907�N4��8���́uKAWANANAKOA
v. POLYBLANK�v����(205 U.S. 349 (1907))�̘A�M�ō��ٔ�������(�z�[���Y�����j�́A�uA
sovereign is exempt from suit, not because of any formal conception
or obsolete theory, but on the logical and practical ground
that there can be no legal right as against the authority
that makes the law on which the right depends. �i�����҂��i�����Ȃ��̂́A���P�I�ȊT�O�⎞��x��̗��_�ɂ����̂ł͂Ȃ��A���������藧�����ł���@�������o�����͂���Ƃ��錠���Ƃ������̂͂��肦�Ȃ��Ƃ������_�I�Ŏ��ۓI�ȗ��R�Ɋ�Â����̂ł���B)�v�Əq�ׂĂ���B�܂��A�p���ł��A1947�N�̍����i�ǖ@�����肳���܂œ��l�ł���i�Í�c���E���Ɣ����@47�؈�W)�A�h�C�c�y�уt�����X�ł��A19���I�㔼�ɁA���ƐӔC��ʂɖ��@��K�p���悤�Ƃ������݂����������A���ǁA���̓������ے肳��錋�ʂƂȂ����̂ł���i�F�ꍎ��E���ƐӔC�@�̕���411�؈�W)�B
�@�܂��A�T�i�l��̒��ؐl�����a���ɂ����Ă��A���Ƃ��A�l���̍��Ƃł����āA�l���̂��߂ɕ�d���A�l���̗��v�ƍ��{�I�Ɉ�v���邽�߁A�l���̌������v��N�Q���邱�Ƃ͂��肦�Ȃ��Ƃ����u���ƂƐl���Ƃ̗��v�����S�Ɉ�v����v�Ƃ������_���牉㈓I�ɓ����ꂽ�u���Ɩ��ӔC�̖@���v�𗝘_�I�����Ƃ��āA1980�N�㏉���܂ŁA�����Ƃ��Ɂu���Ɩ��ӔC�v�̏�Ԃł������i���E�E�u�����ɂ�����s���~�ϖ@�̗��_�I���E�s����̑��Q�����@���x���߂�����(��)�v���É���w�@���_�W152��108�A109�ŎQ��)�B
�@���̂悤�ɁA�������@���ɂ����鍑�Ɩ����ӂ̖@���́A�����̊e���̗��@��̐����ł����āA���{�����@��O��Ƃ��錻�݂̉��l�ς���݂āA���Ɩ����ӂ̖@���̍�������ے肷�邱�Ƃ͑S�������̂Ȃ����Ƃł���B
�@���{�����@17���Ɋ�Â������@�����肳�ꂽ���A�����@����̍ۂ̗��@�҂̉��l���f���A�����@�̑k�y�I�K�p��ے肷��ׂ������@����6���ɋK�肵���悤�ɁA���@�{�s�O�̍s�ׂɂ��Ă͓��@�{�s��ɂ����Ă��A���͔����ӔC��Ȃ����ƂƂ���̂����{�����@�̉��ɂ����Ă������ł���Ƃ������̂ł����āA����͍����I�������ȗ��@���f�ł���B
�@���������āA�����_�ɂ����āA�u�u���Ɩ����ӂ̖@���v�ɐ������Ȃ����������������o����v���Ƃ������āA�����@�{�s�O�̖��@�̉��߂Ƃ��āA���̌��͓I��p�ɖ��@715����K�p�ł���Ƃ���̂͌��Ƃ���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
�@�Ȃ��A�ō��ٔ�������15�N4��18����@�씻��(�ٔ�������1338��3�؈�W)�́A�@���s�ׂ����ꂽ���_�ł͌����ɔ����Ȃ��������A���̌�Ɍ������ω������ꍇ�̖@���s�ׂ̗L�����ɂ��āA�u�@���s�ׂ������ɔ����邱�Ƃ�ړI�Ƃ�����̂ł���Ƃ��Ė����ɂȂ邩�ǂ����́A�@���s�ׂ����ꂽ���_�̌����ɏƂ炵�Ĕ��f���ׂ��ł���B�������A������̖@���s�ׂ̌��͂́A���ʂ̋K�肪�Ȃ�����A�s�ד����̖@�߂ɏƂ炵�Ĕ��肷�ׂ����̂ł��邪�i�ō��ُ��a29�N(�N)��223����35�N4��18����@�쌈��E���W14��6��905��)�A���̗��́A�������@���s�ׂ̌�ɕω������ꍇ�ɂ����Ă����l�ɍl����ׂ��ł���A�@���s�ׂ̌�̌o�܂ɂ���Č����̓��e���ω������ꍇ�ł����Ă��A�s���ɗL���ł������@���s�ׂ������ɂȂ�����A�����ł������@���s�ׂ��L���ɂȂ����肷�邱�Ƃ͑����ł͂Ȃ�����ł���B�v�Ɣ������Ă���Ƃ���ł���B���̗��́A���Ɩ����ӂ̖@���ɂ��Ó�����̂ł���A�������@���ɂ����č��������F�߂�ꂽ���Ɩ����ӂ̖@������{�����@��O��Ƃ��錻�݂̉��l�ςɂ���Ĕے肵�āA���ʂ̋K�肪�Ȃ��̂ɁA�����ӂł������s�ׂɂ��A�����ӔC��F�߂邱�Ƃ͖@�̉��߂Ƃ��ċ�����Ȃ��Ƃ����ׂ��ł���B
d�@�������@���ɂ����Đݒu����Ă����s���ٔ����́A���a22�N5��3���Ɍ����@���{�s�����ƂƂ��ɔp�~����i�ٔ����@����2��)�A�s���������܂߂Ďi�@�ٔ������ꌳ�I�ɍٔ����s�����ƂƂȂ����i���@76��1���A2���A�ٔ����@3��)�B����ɂ�������炸�A���̌�̍ō��ُ��a25�N�����ɂ����Ă��A���Ɩ����ӂ̖@�����̗p����Ă���̂ł����āA���Ɩ����ӂ̖@�����P�Ȃ�i�ז@��̐���łȂ����Ƃ͖��炩�ł���B
e�@���ǁA�������ٕ���15�N7�������́A�����n��3�������Ɠ��l�ɁA���Ɩ����ӂ̖@���̈Ӌ`�𗝉����Ă��Ȃ����̂Ƃ��킴��Ȃ��B
�@�E�@�����@�����@�̕s�@�s�K��̓��ʖ@�ł���Ƃ̔����ɂ���
�i�A�j�������ٕ���15�N7�������̔���
�@�������ٕ���15�N7�������́A���Ɩ����ӂ̖@���̓K�p��ے肵�A���̌��͍�p�ɑ��閯�@�̓K�p�\�����m�肷�闝�R�Ƃ��āA�u���Ɣ����@�͖��@709���ȉ��̕s�@�s�ז@�̓��ʖ@�ł��鐫�i���L���A���Ɣ����@�̐��肪�Ȃ���Δ����������̎���@��̍������Ȃ������Ɖ����ׂ��ł͂Ȃ��A��ʖ@�Ƃ��Ă̖��@709���ȉ��̕s�@�s�ז@�������Ƃ��ēK�p�����Ɖ����ׂ��]�n���\���ɂ��蓾���v�Ɣ�������B
�i�C�j��T�i�l�̔��_
�@�������A���s���@�́A���@��̍s�ׂɂ͓K�p����Ȃ��Ƃ̗����̂��ƂŐ��肳�ꂽ���̂ł���A���̂��Ƃ́A��T�i�l��������(1)22�Ȃ���34�؈�W�ŏڏq�������s���@715��(���Ăł�723��)�̗��@���̐R�c���e�A���s���@�̋N���҂ł���~�����Y�y�ѕx�䐭�̖͂��@715���Ɋւ��������A�������@����ɂ������\�I�Ȗ��@�w�҂ł��锵�R�G�v�̓����Ɋւ������Ȃǂ��疾�炩�ł���B
�@����ɁA���ꂾ���łȂ��A�ȉ��ɏq�ׂ�悤�ɁA���Ɣ����@���A���@�����@��̍s�ׂɂ͓K�p����Ȃ��Ƃ̗����̂��ƂŐ��肳�ꂽ���̂ł��邱�Ƃ��A���Ɣ����@�Ă̐R�c���e��������炩�ł���B
�i�E�j���Ɣ����@�Ă̋N���҂̌��ɂ���
a�@�����͂̍s�g�ɂ�鍑�Ɣ����̖��Ɩ��@�̕s�@�s�אӔC�̖��Ƃ͐������قȂ邱�ƁA�����@1���́A�����͂̍s�g�ɂ�鑹�Q�ɂ����Ɣ����ӔC��n�݂����K��ł��邱�Ƃɂ��ẮA����ɂ����āA���Ɣ����@�Ă�R�c����ۂɁA���{�ψ��ɂ�薾�m�ɂ���Ă���B
�@���Ȃ킿�A���a22�N7��16���̑�1��O�c�@�i�@�ψ���ɂ����āA����҂́u���Ɣ����@�̑�1����тɑ�2���Ɩ��@�̕s�@�s�ׂɊւ���@�K�ƁA���̗��O�ɂ����Ăǂ����Ⴄ�̂ł��邩�A��̗��@��������ׂ܂��āA���̗��@���O�ɂ��Ă̈قȂ�_���ЂƂٖ��肢�����Ǝv���܂��B�v�Ƃ̎���ɑ��A���쌒�ꐭ�{�ψ��́A�u�䏳�m�̂悤�ɖ��@�ɂ����܂��Ă͎��@�W�̋K��ł���܂��āA�{�@�ɂ����܂��Ă͍��ƌ����c�̂̌����͍s�g�ɂ��ꍇ�̊W�ŁA��������s���̊W�ŁA���@�I�W�ł͂���܂���̂ŁA��͂肱.��@�̒��ɋK�肷��Ƃ������Ƃ͂�͂肻�̎��I�W�A���I�W�Ɨ��ꂪ�Ⴂ�܂��̂ŁA�������ʖ@�ɂ������āA�����ɍ��Ɣ����@�ĂȂ���̂𗧈Ă��������킯�ł���܂��āA���̓��e���ɂ��܂��ẮA��4���ɂ���܂��悤�ɁA��̂����ɋK�肷��ȊO�̎����͂��ׂĖ��@�̋K��ɂ�邱�Ƃɂ��������̂ł���܂��B�����ɂ��ẮA���@�̕s�@�s�ׂɊւ���_���̂܂ܓK�p����邱�ƂɂȂ�܂����A��قǂ��\���܂����悤�ɁA����͌��@�I�ȊW�ł���A���@�͎�Ƃ��Ď��@�I�ȊW���K�肵�Ă���Ƃ����Ƃ���ɍ��ق�����Ƃ����ӂ��ɍl���܂��B�v�Ɠ��ق��Ă���B
�@�����āA����҂́u�������܂��ƁA���@�Ō����͂̍s�g�ɂ����āA�s�@�s�ׂ������Ă����Ƃ����ꍇ�ɂ����ẮA���ƕ��тɌ����c�͖̂��@�ɂ����Ă͐ӔC��ʁA������������߂ł����B���@�ł���͂蕉���̂���Ȃ��ł����B�v�Ƃ̎���ɑ��A���쐭�{�ψ��́A�u�]�����ƌ����͍s�g�ɂ��Ă̕s�@�s�ׂ̏ꍇ�ɂ����ẮA���Ƃ͔����ӔC���Ȃ��Ƃ������_������A�w���ő�̊m������Ă���܂��̂ŁA���x���@�̋K��ɂ�č��Ƃ������ӔC������Ƃ��������������@�����ׂ����Ƃ����@�ŗv������Ă���܂��̂ŁA���Ȃ킿���̖@���ɂ�ď��߂č��Ƃ������̋`�����邱�Ƃ𖾂炩�ɂ����������̂ƍl���Ă���܂��B���Ȃ킿���@�̒��ڂ��̂܂܂̓K�p���A���܂ł̉��߂��猾�ĂȂ��Ƃ������ƂɂȂĂ���܂��̂ŁA���ɂ��̓��ʖ@�Ƃ����܂����A���̖@�Ăɂ�č��Ƃ̔����̋`�����邱�Ƃ𖾂炩�ɂ��������킯�ł���܂��B�v�Ɠ��ق��Ă���i��1��O�c�@�i�@�ψ���c�^��4���E����79����46�؈�W)�B
�@���@�ƍ����@�̊W�ɂ��āA���@�҂́A��ʖ@�Ɠ��ʖ@�̊W�ł͂Ȃ��A�ʌ̖@�̌n�ɑ�������̂ƍl���āA���Ɣ����@�Ă��쐬�����̂ł���i���Ɣ����@������E�䂪���y�я��O���̍��Ɣ������x�̊T�ρi1)�E�@�߉����������12���i1979�N�j124�؈�W�i���V���Y�����j�Q�Ɓj�B
b�@�����āA����ɉ��쐭�{�ψ��́A���Ɣ����@���A�V���ɑn�݂��ꂽ���Ɣ����̈�ʖ@�ł��邱�Ƃ��������Ă���B
�@���Ȃ킿�A���a22�N7��29���̓�����O�c�@�i�@�ψ���ɂ����āA����҂́u���ɑ�5���Ɋւ�����ɂ��Ă��q�˂�\���グ�����Ǝv���܂��B���̍��Ɣ����́u���@�ȊO�̑��̖@���ɕʒi�̒肪����Ƃ��́A���̒�߂�Ƃ���ɂ��B�v�ƋK�肵�Ă������܂��B�Ƃ��낪�ߋ��ɂ����閯�@�ȊO�̔����Ɋւ�����ʖ@��ʗ��������܂���ƁA��̂ɂ����Ĕ��ɂ��̔����̐ӔC�̐�����ꍇ���nj����Ă��邱�ƁA�������ӔC�����Ɍy���ɂ������ꂪ��������Ȃ��悤�Ȍ`�Ɍ��킳��Ă��邵�A���ɋ����ȋK��ɂȂĂ���Ǝv���܂��邪�A��ʖ@�A���ʖ@�̊W����\���܂���ƁA���ʖ@�͈�ʖ@�ɗD�悵�ēK�p�����Ƃ����悤�Ȃ��ƂɂȂ�܂���ƁA�ނ��닷���l�����A�����ɋK�肳�ꂽ���ʖ@�������Ă���Ƃ������ƂɂȂ�ƁA��̂��̍��Ɣ����@�Ƃ̊W��A���̓��ʖ@���ǂ����߂��ׂ����Ƃ������Ƃ��^��ł������܂����A���̓_�ɂ��Ă������肢�����Ǝv���܂��B�v�Ƃ̎���ɑ��āA���쐭�{�ψ��́A�u�{�@�Ă����Ɣ����̈�ʖ@�ɂȂ�A����ɓ��ʖ@��������̓��ʖ@�ɂ��Ƃ������O��5���ł���܂��B�������܂���5���̓��ʖ@�Ɛ\���܂��̂́A�X�֖@�̂��Ƃ����̂��w���Ă���킯�ł���܂����A��w�E�̂悤�ɗX�֖@�͔��ɌÂ��@���ł���܂��āA�܂����̏ꍇ�����z���ɂ��܂��Ă����낢�됧��������悤�ł���܂��āA����͐V�������Ɣ����@�����肳���Ƃ������ƂɂȂ�܂���A�����������ʖ@�ɂ��Ă��A����Ɍ�����v����̂ł͂Ȃ��낤���Ƃ����ӂ��ɍl���Ă���܂��B�v�i��1��O�c���i�@�ψ���c�^��7���E����80����93�؈�W�j�Ɠ��ق��Ă���B
c�@�܂��A���Ɣ����@�Ă̍���ւ̒�o�́AGHQ�̔F���o�ĂȂ��ꂽ���̂ł��邪�A���Ɣ����@�Ăɂ��Ă�GHQ�Ƃ̐Ղ́A���a22�N5������6���ɂ����āA10��ɂ킽���čs��ꂽ�BGHQ���́A�m�{�b�g�j�B��т����S�ƂȂ��č��Ɣ����@�Ă̐R�c���s�����B����GHQ�Ƃ̐Ղ̍ۂɁA���{�����{�́A�@�����͌����c�̂̌����͂̍s�g�ɂ�鑹�Q�ɂ��ẮA���@��̐ӔC�͂Ȃ��A�A�����͌����c�̂̏��R���鎄�o�ϊ����ɂ��ẮA���@�̋K��ŐӔC���A�B���̒��Ԃ̏ꍇ�A�����A�����͂̍s�g�͔���Ȃ������@���������ۂ��^��̏ꍇ��2���ŋ~�ς���Ƃ����l�����������B����ɑ��A���@���@�_���Ƃ�Ȃ��č��ɂƂ��āA���҂̋�ʂ�O��Ƃ������{���̐����͗����ɋꂵ�ނ��̂ł������悤�ł��邪�A�ŏI�I�ɂ́A���ė��@���̊�{�I�\���̑��قƂ������ƂŔ[�����āA�����͂̍s�g�ɂ�鑹�Q�ɂ��Ė��@��̐ӔC���Ȃ��Ƃ������{�����{�̐����𗹏����Ă���i�F�ꍎ��E���Ɣ����@�Ă̗��@�ߒ��E�s���@�̔��W�ƕϊv�����i����G�搶�Ê�L�O�j�����E�Y����318�؈�W�A���Ɣ����@������E�䂪���y�я��O���̍��Ɣ������x�̊T�ρi1�j�E�@�߉����������12��(1979�N)121�؈�W�i���V���Y�����j�Q�Ɓj�B
d�@�ȏ�̐R�c���e�y��GHQ�Ƃ̐Չߒ����疾�炩�Ȃ悤�ɁA��O�y�ѐ���ʂ��āA�����͂̍s�g�ɂ�鑹�Q�ɂ��āA�����ӔC��F�߂���@��̈�ʓI�K��͂Ȃ��A�����Ƃ��Ĕ����ӔC�͔F�߂��Ă��Ȃ������̂ł���A��O�I�ɁA�ʂ̍s������ɂ��āA���ʖ@�ɂ���Ĕ����ӔC���F�߂��Ă����ɂ����Ȃ��̂ł���B����ɑ��A���́A�����@�̐���ɂ��A�����͂̍s�g�ɂ�鑹�Q�ɂ��ẮA�����Ƃ��Ĕ����ӔC�킹�邱�ƂƂ������A�����@5���ɂ��A�ʂ̕���ɂ����āA���������������A���̗�O������������A�����@1���Ƃ͈قȂ����v�����������邱�Ƃ����e�����B���Ȃ킿�A�����͂̍s�g�Ƃ������@�W�̕���ɂ����āA��O�́A���Ɣ����ӔC��F�߂�@�����Ȃ��������Ƃ����̖@��̊�{�����Ƃ��Ĉʒu�Â����A���́A��ʓI�ɍ��Ɣ����ӔC��F�߂鍑���@�����̖@��̈�ʖ@�Ƃ��Ĉʒu�Â����邱�ƂƂȂ����B
�i�G�j����
�@�ȏ�̂悤�Ȍ��s���@�Ă̐R�c���e�y�э��Ɣ����@�Ă̐R�c���e�ɏƂ点�A�������ٕ���15�N7�������́u���Ƃ̌��͓I��p�ɂ�鑹�Q�����̖��ɂ��āA���ʖ@���Ȃ��ꍇ�ɂ́A��ʖ@�Ƃ��Ă̖��@709���ȉ��̕s�@�s�ז@�������Ƃ��ēK�p�����]�n������v�Ƃ̗����͌��ł��邱�Ƃ͖��炩�ł���B
�@�i�S�j �����@����6���y�эō��ُ��a25�N�����ɔ����邱�Ƃɂ���
�@�A�@�������ٕ���15�N7�������̔���
�@�������ٕ���15�N7�������́A�����@����6���ɂ��āA�u���Ɣ����@�i���a22�N10��27�����z�A�����{�s�j�{�s�O�ɂ����ẮA�������̌��͓I��p�ɂ�鑹�Q�ɂ��ẮA���@����6���ɂ��u�]�O�̗�ɂ��v���̂Ƃ���Ă�������A�����ی�K�i���F�߂��Ȃ����ߑi�����s�K�@�ƂȂ�Ɖ�����]�n�����邪�A���@����6���������ٔ������ł��邱�Ƃ��ˑR�Ƃ��Ĕے肷��i�葱�K��ł���Ɖ�����̂͋^�₪����B�v�Ɣ�������B
�@�C�@��T�i�l�̔��_
�@�������A���̂悤�ȉ��߂́A���̑O��Ƃ��č��Ɩ����ӂ̖@�����i�葱��̐���Ɋ�Â��@���ɂ����Ȃ��Ƃ��Ă���_�ŏd��Ȍ�肪����ƂƂ��ɁA�����@����6���̉��߂����A����ɍō��ُ��a25�N�����ɂ�������d��Ȃ�@�߈ᔽ�y�эō��ٔ���ᔽ�̔��f�ł���B
�@���Ȃ킿�A�O�L�̂悤�ɁA�����@����6���́A�����@�{�s�O�̌����͂̍s�g�ɔ������Q���������Ƃ���鎖��ɂ��ẮA�����@���ꎩ�̂̑k�y�K�p��ے肷��݂̂Ȃ炸�A����܂ō̗p���Ă������Ɩ����ӂ̖@�������̂܂ܓK�p����邱�Ƃɂ��A�����͌����c�̂��ӔC��Ȃ����Ƃ𖾂��ɂ������̂ł����āA�������ٕ���15�N7�������́A���̓_�ɂ����āA�����@����6���̉��߂�����Ă���B
�@�܂��A�ō��ُ��a25�N�����́A�u�_�|�́A���Ɣ����@�����́u���̖@���{�s�O�̍s�ׂɊ���Q�ɂ��ẮA�Ȃ��]�O�̗�ɂ��B�v�Ƃ̋K��ɂ��āA�]�O�Ƃ����ǂ��������̕s�@�s�ׂɑ��A���������ӔC���ׂ����̂ł��āA�V���@�͂����@���������ɉ߂��Ȃ��Ǝ咣����̂ł��邪�A���Ɣ����@�{�s�ȑO�ɂ����ẮA��ʓI�ɍ��ɔ����ӔC��F�߂�@�ߏ�̍����̂Ȃ������Ƃ͑O�q�̂Ƃ���ł��āA��R�@���������̈�@�Ȍ����͂̍s�g�Ɋւ��āA��ɍ��ɔ����ӂɂ̂Ȃ����Ƃ����ė����̂ł���B�i��������ɘ_�|�̂悤�Ȋw���������Ƃ��Ă��A�����ɂ͂��̂悤�Ȋw���͍s���Ȃ����̂ł���B�j�{���Ɖ��̔j��͓��{�����@�{�s�ȑO�ɍs��ꂽ���̂ł��āA���Ɣ����@�̓K�p����闝�R���Ȃ��A�����������@�����ɂ�ď]�O�̗�ɂ�荑�ɔ����ӔC�Ȃ��Ƃ��A�㍐�l�̐�����e��Ȃ����͎̂����ł��āA�_�|�ɗ��R�͂Ȃ��B�v�Ɣ������Ă���B
�@���̔�����������炩�Ȃ悤�ɁA�������́A�����@����6���́u�]�O�̗�v�Ƃ́A�����͂̍s�g�Ɋւ��Ă͖��@�̓K�p���Ȃ��A���̑����̔����ӔC��F�߂�K�肪�Ȃ��������Ƃ���A�����͂̍s�g�ɂ��Ă͍��ɂ͔����ӔC���Ȃ����ƁA���Ȃ킿���Ɩ����ӂ̖@�����Ӗ����A���̖@���ɏ]���Ĕ��f�����������������ł���Ɣ������Ă���̂ł���B
�@�ȏ�̂Ƃ���A�������ٕ���15�N7�������́A�����@����6���̉��߂����A�ō��ُ��a25�N�����ɂ��ᔽ����Ƃ����ׂ��ł���B
�@�E�@�ߎ��̍ٔ��ᓙ
�@�ߎ��A�����N�����o�g�҂��A���Ƒ������@�̉��ɂ����āA���n�ɋ����A�s���ꋭ���J��������ꂽ�Ƃ��đ��Q���������߂��i�ׂɂ����āA�����n���ٔ�������8�N11��22�������i�ז�����44��4��507�y�[�W�j�́A�u�������@���ɂ����ẮA�s���ٔ����ɂ����Ă��A�u���Q�v���m�i�ׁv���ł��Ȃ����̂Ƃ���i�s���ٔ��@16���j�A���Ƃ̔����ӔC���m�肷�ׂ������@�߂��Ȃ������̂ł��邩��A���Ɣ����@����6���́u���̖@���{�s�O�̍s�ׂɊ�Â����Q�ɂ��ẮA�Ȃ��]�O�̗�ɂ��B�v�Ƃ̌o�ߋK��ɏƂ点�A�����_�ɂ�������߂Ƃ��Ă��A�{���e�s�ד����ɂ����ẮA���@709���̋K��ɂ���āA�������̌��͓I��p�ɂ�鑹�Q�ɂ��Ď��l�ɑ��đ��Q�����ӔC�S����Ƃ̉��߂��̗p���邱�Ƃ͂ł��Ȃ����̂Ƃ����ق��Ȃ��i���Ɣ����@�̉E�����́A���@�{�s�O�̍s�ׂɂ��Ă����鋌�@��`���̗p�������̂ɂ������A���̋K�肪�A���@709��K�p���̍����ƂȂ���̂ł͂Ȃ��B�j�B�v�Ɣ��������Ƃ���A���̍T�i�R�ł��铌�������ٔ�������14�N3��28�������i����30���j��������ێ����A����ɍō��ٔ�������15�N3��28����@�쌈��i����81���j���A�㍐���p�y�я㍐�s�̌���������B
�@���̂悤�ɍ����@����6���́u�]�O�̗�v�����Ɩ����ӂ̖@�����w�����Ƃ́A�ō��ُ��a25�N�����ȗ��A������т��Ă���(�����n���ٔ������a59�N10��30�������E�����1137��29�؈�W�A���������ٔ������a63�N3��24�������E�����1268��15�؈�W�A���������ٔ�������12�N12��6�������E�����1744��48�؈�W�A���������ٔ�������13�N2��8�������i����23���j�A�������ɂ��ō��ٔ�������13�N10��16������i�㍐���p�y�я㍐�s����A����43���j�B
�@�i�T�j ���_
�@�ȏ�ɏq�ׂ��悤�ɁA�������ٕ���15�N7�������́A���Ɩ����ӂ̖@���̗��_�I�����Ȃ����Ӌ`�𗝉����Ȃ������łȂ��A���m�ȍ������������ƂȂ��A�����@����6���y�эō��ُ��a25�N�����ɂ����炩�ɑ������锻�f�����������̂ł���A�����Ƃ͌���������ł���B
�@�R�@�������ٕ���16�N2�������̑Ó����ɂ���
�@�i�P�j ���̎����́A��p�ݏZ�̏������A��̑�풆�A�����{�R�y�т��̍\�����ɂ���āA��p�����͂��̑��̒n��Ɂu�i�]�R�j�Ԉ��w�v�Ƃ��ĘA�s����A�ċւ��ꂽ�őg�D�I�A�p���I�ɐ��s�ׂ̋��v�����ꂽ���Ɠ��ɂ��A����Ȑ��_�I���Q���������Ƃ��āA���ɖ��@���Ɋ�Â����Q�����������߂������ł���B
�@���́A���̎����ɂ����āA�����n��3�������y�ѓ������ٕ���15�N7�������ɂ����鍑�Ɩ����ӂ̖@���Ɋւ��锻�f�ɂ��A��T�i�l��������(1)��1���y�ёO�L2�i�{�������ʑ�1�A2�j�Ɠ��l�̔��_�����A�������̍��Ɩ����ӂ̖@���Ɋւ��锻���̕s�����𖾂��ɂ������̂ł���B
�@�i�Q�j ����ɑ��A�������ٕ���16�N2�������́A���Ɩ����ӂ̖@���ɂ��A���̂Ƃ��蔻�������i����76���j�B�Ȃ��A���̔��������p���Ă���u��11�Ȃ���17�A23�Ȃ���30�v�Ƃ́A�{���i�ׂŔ�T�i�l����o�����؋��i����27�A26�A29�A32�A33�A30�A42�A34�Ȃ���37�A78�A38�A79�A80���j�ł���i�Ή��W�ɂ��A��T�i�l�̕���16�N3��18���t�؋��������̉���76���̗��Q�Ɓj�B
�@�u�؋��i��11�Ȃ���17�A23�Ȃ���30�j�𑍍����A�l�@����A���̏��_�����炩�ł���B
�@���Ɣ����@�i���a22�N10��27���{�s�j�́A�����͂̍s�g�Ȃǂɂ�鑹�Q�̔����ɂ��Ă̍����͒n�������c�̂̐ӔC���K�肵�Ă���Ƃ���A����{�鍑���@���̉䂪���̖@���x�ɂ����ẮA���̍s�ׂ̂������o�ϓI��p�ɂ��ẮA���@���n�߂Ƃ����ʎ��@�W�̋K���ɕ�������ׂ����̂Ɖ��߂���Ă������A�����͂̍s�g�ɓ����錠�͓I��p�ɂ��ẮA����ɂ�莄�l�ɑ��Q�����������Ƃ��Ă��A���@�̓K�p�͂Ȃ����̂Ƃ���A���@���̑��̖@���ɂ����č��̌����͂̍s�g�ɂ�葼�l�ɑ��Q��^�����ꍇ�̍��̔����ӔC���߂������̋K���u�����Ƃ��Ȃ��������@�ԓx�Ȃǂ���A���͓I��p�ɂ�鑹�Q�ɂ��ẮA�����Ȃ�ꍇ�ł����̔����ӔC�͑��݂��Ȃ����̂Ɖ��߂���A���ꂪ�m�������@���ƂȂ��Ă������Ƃ����炩�ł���A��R�@�̔���́A��т��Č��͓I��p�ɂ�鑹�Q�ɂ��č��̔����ӔC��ے肷��|�����Ă������A���s���ٔ��@�i���a22�N5��3���p�~�j16�����u�s���ٔ����n���Q�v���m�i�׃��Z�X�v�ƋK�肵�Ă������߁A�s���ٔ����̑i�葱�ł������͂̍s�g�ɂ�鑹�Q�̔��������͔F�߂��Ă��Ȃ������B
�@�������A���̂悤�ȍ��Ɩ����ӂ̖@���́A��Ɂu���l���A�������̕s�@�s�ׂɂ��A���Q�����Ƃ��́A�@���̒�߂�Ƃ���ɂ��A�����͌����c�̂ɁA���̔��������߂邱�Ƃ��ł���B�v�ƋK�肷�錛�@17���ɂ���ĉ��߂�ꂽ�Ƃ���ł��邪�A����{�鍑���@���̉䂪���̖@���x�̉��ł́A��L�̂Ƃ���A���̌��͓I��p�ɂ�鎄�l�̑��Q�ɂ��č��͔����ӔC��Ȃ��Ƃ̍��Ɩ����ӂ̖@�����Ó����Ă������̂Ɖ�����ق��Ȃ��̂ł���A���̌㌛�@17�������̖@����p�����č����͌����c�̂̑��Q�����ӔC�̍����𖾂炩�ɂ������Ƃɂ��A�����Ɋ�Â��č��Ɣ����@�����肳��A����ɂ���ď��߂ċ�̓I�ɁA���͓I��p�ɂ�鎄�l�̑��Q�̋~�ς��}���邱�ƂƂȂ������̂ł���B
�@�ȏ�̂Ƃ���A����{�鍑���@���ɂ����č��Ɩ����ӂ̖@�����Ó����Ă����̂́A���̌��͓I��p���A���̗D�z�I�n�ʂɊ�Â����l�ɑ����߂���������Ƃ�����p�ł��邽�߂ɁA�{���I�Ɏ��@�����̓K�p��r�˂��A�Γ��ҊԂ̗��Q�����̌��n�����߂�ꂽ���@�̕s�@�s�ׂɊւ���K��ɐe���܂Ȃ�����Ȗ@�̈�ɑ�������̂ł���ƍl�����Ă������Ƃ�A���͓I��p�ɂ�鑹�Q�ɑ��锅���ӔC��F�߂邽�߂̓��ʂ̈�ʍ����K������@����Ȃ��������ƂɊ�Â����̂ł����āA�P�Ɍ��͓I��p�ɂ�鑹�Q�����ӔC��Njy���邽�߂̎葱�@�����݂��Ȃ��������ƂɊ�Â����̂ł͂Ȃ����Ƃ����炩�ł���B���������āA���Ɩ����ӂ̖@���́A�P�Ɏ葱�@��̖��ɗR��������̂ł͂Ȃ��A���̖@�ɗR��������̂ł���Ƃ������Ƃ��ł���B
�@�����āA���Ɣ����@����6���ɂ́A�u���̖@���{�s�O�̍s�ׂɊ�Â����Q�ɂ��ẮA�Ȃ��]�O�̗�ɂ��B�v�Ƃ̌o�ߋK�肪�݂����Ă���Ƃ���A�����ɂ����u�]�O�̗�v�ɑ����������{�鍑���@���̖@���x�ɂ����ẮA��L�̂Ƃ��荑�Ƃ̑��Q�����ӔC���m�肷�ׂ����̖@��̍����@�߂����݂��Ȃ��������ƂɏƂ点�A���@�y�э��Ɣ����@�{�s��̌����_�ɂ�������߂Ƃ��Ă��A���@�{�s�O�̓��{�R�̍s�ׂł���T�i�l��咣�̖{�����Q�s�ׂɂ��āA�������@�̋K��ɂ���Ă��̌��͓I��p�ɂ�鑹�Q�̔����ӔC�S������̂Ɖ����邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B�v�i������6�Ȃ���8�y�[�W�j
�@�i�R�j ���̂悤�ɁA�������ٕ���16�N2�������́A�������ٕ���15�N7�������y�ѓ����n�ٕ���15�N3�������ɂ����鍑�Ɩ����ӂ̖@���Ɋւ����������f�𐳂��A���Ɩ����ӂ̖@���ɂ��Đ����Ȕ��f�����������̂ł���B
��Q�@���ˊ��Ԃɂ���
�@�P�@�͂��߂�
�@�T�i�l��́A�T�i�l���3�������ʂɂ����āA�]�O�̎咣���l�A���@724����i�̓K�p�Ɋւ��A������i�̓K�p�����������`�A�����ɔ����A�𗝂ɂ��Ƃ�ꍇ�ɂ́A�����K�p���ׂ��łȂ��Əd�˂Ď咣����B
�@�������A�T�i�l��̎咣�������ł��邱�Ƃ́A��T�i�l��������(1)61�y�[�W�ȉ��ŏq�ׂ��Ƃ���ł���B
�@�܂��A�T�i�l��́A�T�i�l���3�������ʂɂ����ẮA�V���ɓ����n���ٔ�������15�N9��29�������i�ȉ��u�����n�ٕ���15�N9�������v�Ƃ����B�b��491���j�����p���āA�T�i�l��̎咣�̍����Ƃ��Ă���i������30�y�[�W�j�B
�@�������A�����n�ٕ���15�N9�������́A���@724����i�͏��ˊ��Ԃ��߂����̂ł���Ɛ����ɔ������Ȃ���i������42�y�[�W�j�A���ˊ��Ԃ́A�u���̓K�p�ɂ���Ĕ�Q�҂̑��Q���������������ł��邱�ƂɂȂ锽�ʂŁA���Q�҂͑��Q�����`����Ƃ�錋�ʂƂȂ�̂ł��邩��A���̂悤�Ȍ��ʂ����������`�A�����̗��O�ɔ����A���̓K�p�𐧌����邱�Ƃ��𗝂ɂ����Ȃ��ƔF�߂���ꍇ�ɂ́A���ˊ��Ԃ̓K�p�𐧌����邱�Ƃ��ł���ƍl����ׂ��ł���B�v�i��43�y�[�W�j�Ɣ������Ă���A���@724����i�̓K�p�𐧌����邱�Ƃ��O�I�ɋ��e�����ō��ٕ���10�N�����̎˒����A�ō��ٕ������N�����y�эō��ٕ���10�N�����ɔ����A���炩�Ɏ���@�̉��߂�����̂ł����Ď����ł���B
�@���������āA�����n�ٕ���15�N9�������̏��ˊ��Ԃ̓K�p�Ɋւ����������f�������Ƃ���T�i�l��̎咣���A�����ł��邱�Ƃ������ł���B
�@�ȉ��A�����n�ٕ���15�N9�������̖��@724����i�Ɋւ��锻�f�̌��ɂ��āA�ڏq����B
�@�Q�@�����n�ٕ���15�N9�������̔�����
�@�����n�ٕ���15�N9�������́A�����{�R���A�|�c�_���錾����O��ɁA�����B�n��i���������k���j���ɁA�ŃK�X�C�e����������A���̌�����u�������Ƃɂ���āA1974�N�i���a49�N�j�ɓŃK�X���o���̎��̂��������A���ꂩ��20�N�ȏ�o�߂��Ē�i���ꂽ���Q���������Ɋւ��āA���@724����i�͏��ˊ��Ԃ��߂����̂ł���Ɛ����ɔ������Ȃ���i������42�y�[�W�j�A���ˊ��Ԃ́A�u���̓K�p�ɂ���Ĕ�Q�҂̑��Q���������������ł��邱�ƂɂȂ锽�ʂŁA���Q�҂͑��Q�����`����Ƃ�錋�ʂƂȂ�̂ł��邩��A���̂悤�Ȍ��ʂ����������`�A�����̗��O�ɔ����A���̓K�p�𐧌����邱�Ƃ��𗝂ɂ����Ȃ��ƔF�߂���ꍇ�ɂ́A���ˊ��Ԃ̓K�p�𐧌����邱�Ƃ��ł���ƍl����ׂ��ł���B�v�i��43�y�[�W�j�Ƃ�����A�{���ɂ����Ĕ퍐�������ˊ��Ԃ̓K�p�ɂ���đ��Q�����`����Ƃ��Ƃ������v���邱�Ƃ́A���������`�A�����̗��O�ɔ����A���̓K�p�𐧌����邱�Ƃ��𗝂ɂ��Ȃ��Ƃ����ׂ��ł��邩��A���ˊ��Ԃ̓K�p�͐�������̂������ł���Ɣ��������i��42�Ȃ���44�y�[�W�j�B
�@�R�@���@724����i�̉��ߓK�p�Ɋւ��锻��ᔽ��
�@�i�P�j ���@724����i��20�N�̊��Ԃ͏��ˊ��Ԃł���A�u��Q�ґ��̔F���̂�������킸���̎��̌o�߂ɂ���Ė@���W���m�肳���邽�ߐ������̑������Ԃ����I�ɒ�߂����́v�i�ō��ٕ������N�����E���W43��12��2209�y�[�W�B�j�ł���B
�@���̂悤�ȏ��ˊ��Ԃ̐�������A�ٔ����́A�����҂��咣�����Ȃ��Ă��A�@�ւ̌o�߂ɂ�萿���������ł����Ɠ��R���f���ׂ��ł���A�܂��A���ˊ��ԂɌW��咣��M�`���ᔽ�A�������p�Ƃ��邱�Ƃ��ł��Ȃ��Ƃ���Ă���i�ō��ٕ������N�����A�ō��ٕ���10�N�����j�B
�@�Ƃ��낪�A�����n�ٕ���15�N9�������́A���@724����i�̋K����A���ˊ��Ԃ��߂����̂Ƃ��Ȃ���A�O�L�̂悤�ɁA���ˊ��Ԑ��x�̓K�p�̌��ʂ��A���������`�A�����̗��O�ɔ����A���̓K�p�𐧌����邱�Ƃ��𗝂ɂ����Ȃ��ƔF�߂���ꍇ�ɂ́A���ˊ��Ԃ̓K�p�𐧌����邱�Ƃ��ł���Ɖ����āA������̐����ɂ��ď��ˊ��Ԃ̓K�p�𐧌������B
�@�������A���̂悤�Ȕ��f�́A�ȉ��ɏq�ׂ�悤�ɁA�ō��ٕ������N�����̍l�����ɖ��炩�ɔ�������̂ł���݂̂Ȃ炸�A���̌�̍ō��ٕ���10�N�����ɏƂ炵�Ă��A����e�F���邱�Ƃ��ł��Ȃ��B
�@�i�Q�j ���Ȃ킿�A�ō��ٕ���10�N�����́A�\�h�ڎ�Бi�ׂɂ��āA�s�@�s�ׂ̔�Q�҂��s�@�s�ׂ̎�����20�N���o�߂���O6�ӌ����ɂ����ĉE�s�@�s�ׂ������Ƃ��ĐS�_�r���̏틵�ɂ���̂ɖ@��㗝�l��L���Ȃ������ꍇ�ɂ����āA���̌㓖�Y��Q�҂��֎��Y�鍐���A�㌩�l�ɏA�E�����҂����̎�����6�ӌ����ɉE���Q�������������s�g�����ȂǓ��i�̎������Ƃ��́A���@158���̖@�ӂɏƂ炵�A���@724����i�̌��ʂ͐����Ȃ��Ɣ��������B�����āA���̗��R�Ƃ��ẮA�S�_�r���̏틵�����Y�s�@�s�ׂɋN������ꍇ�ł����Ă��A��Q�҂́A���悻�����s�g���s�\�ł���̂ɁA�c��20�N���o�߂����Ƃ������Ƃ݂̂������Ĉ�̌����s�g��������Ȃ����ƂƂȂ锽�ʁA�S�_�r���̌�����^�������Q�҂́A20�N�̌o�߂ɂ���đ��Q�����`����Ƃ�錋�ʂƂȂ�A���������`�E�����̗��O�ɔ�������̂Ƃ��킴��Ȃ����Ƃ������Ă���B
�@���̍ō��ٕ���10�N�����́A�u�S�_�r���̏틵�����Y�s�@�s�ׂɋN������ꍇ�ł����Ă��A��Q�҂́A���悻�����s�g���s�\�ł���̂ɁA�P��20�N���o�߂����Ƃ������Ƃ݂̂������Ĉ�̌����s�g��������Ȃ����ƂƂȂ锽�ʁA�S�_�r���̌�����^�������Q�҂́A20�N�̌o�߂ɂ���đ��Q�����`����Ƃ�錋�ʂƂȂ邱�Ɓv�́A���������`�E�����̗��O�ɔ�����Ƃ��Ă��邪�A����́A�����܂Ŗ��@158���̖@�ӂ����ˊ��Ԑ��x�ɂ��������ނ��߂̗��R�ɂ������A��ʓI�ɒ��������`�E�����̗��O�ɔ�����ꍇ�ɂ͉��炩�̖@����̍����Ȃ����ˊ��Ԃ̓K�p��r���ł���Ƃ������̂łȂ����Ƃ͖��炩�ł���B
�@���̂��Ƃ́A�ō��ْ������̔������ł��A�u�{�����̎˒��́A�ɂ߂ċ������̂Ǝv����B���@724����i�̓K�p�̌��ʂ�ے肷��ꍇ�Ƃ��ẮA���ˊ��ԓ��Ɍ������s�g���Ȃ��������ƂF���邱�Ƃ��{���̎��ĂƓ����x�ɒ��������`�E�����ɔ����鎖������A�����̒�~�����̍����ƂȂ���̂����邱�Ƃ��K�v�ł��낤�B�͍��ٔ����̈ӌ��̂悤�ɁA���ˊ��Ԑ��ɗ����Ȃ���A���L����O��F�߂邱�Ƃ́A�������N�����ɒ�G���邱�ƂɂȂ�A��@��ɂ����锻��ύX���K�v�ƂȂ�ł��낤�B�v�i�t���ʗǁE�ō��ٔ����������E�����ҕ���10�N�x�i���j576�y�[�W�j�Əq�ׂ��Ă���Ƃ���ł���B
�@���������āA���̔������A��ʓI�ɁA���ˊ��Ԃ̓K�p���u���������`�E�����̗��O�ɔ�����v�ꍇ�ɂ́A���̓K�p��r���ł���Ƃ������̂ƍl���邱�Ƃ́A�����ɔ���̎˒�����������̂Ƃ���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
�@�i�R�j �܂��A�ō��ٕ���10�N�����̎��Ăł́A�S�_�r���̏틵�����Y�s�@�s�ׂɋN������ق��́A���ڍ����̍s�ׂ����ɂ���Ă���킯�ł͂Ȃ��A�ނ���A���Y�s�@�s�ׂɂ���āA20�N�ȓ��ɑ��Q�����������N���邱�Ƃ��ł��Ȃ����ԁi�S�_�r���̏틵�j�������炳�ꂽ���Ƃ��A�u���������`�E�����̗��O�ɔ�����v�Ƃ��ꂽ���̂ł���B
�@����ɑ��A�����n�ٕ���15�N9�������́A�u���ۖ@�I�ɋ֎~����Ă����ŃK�X����𒆍��ɔz�����Ďg�p���Ă��������{�R���A���ۓI��������邽�߃|�c�_���錾�ɂ��ᔽ���āA�I��O��ɑg�D�I�ɂ������������Ƃ�����@�ȍs�ׂɂ��A���ɂȂ��Ă���Q�̔�����h�~���邽�߂̏����W�⒆���ւ̏��������A1972�N�ɒ����Ƃ̍��������ꂽ����ϋɓI�ȑΉ������Ȃ��ň�����ꂽ�ŃK�X�������u���Ă����v�i������43�y�[�W�j���Ƃ������ɁA���̂悤�ȏꍇ�ɏ��ˊ��Ԃ�K�p���邱�Ƃ́u���������`�E�����̗��O�ɔ�����v�Ƃ��Ă���A�ō��ٕ���10�N�������d�����������s�g��s�\�Ƃ��鎖�R���Ȃ��̂ɏ��ˊ��Ԃ̓K�p�𐧌����Ă���_�ŁA���̔��f�g�g�݂ɂ͖��炩�ɍ��ق�����B
�@�i�S�j �������������n�ٕ���15�N9�������̋������L�̂��Ƃ�����݂̂ł́A���ׂĂ̕s�@�s�ׂɂ��ď��ˊ��Ԃ̓K�p�𐧌����邱�ƂɂȂ肩�˂Ȃ��Ƃ����ׂ��ł��邵�A�����̎���́A�]���A�M�`���ᔽ���邢�͌������p����b�Â��鎖��Ƃ��Ď咣����Ă������̂ł���Ƃ���A���ˊ��Ԃ̓K�p���M�`���ᔽ���邢�͌������p�ł���Ƃ̎咣�́A�ō��ٕ������N�����y�эō��ٕ���10�N�����ɂ����Ă��咣���̎����Ƃ���Ă���̂ł���B���̂悤�Ȏ���Ɋ�Â����ˊ��Ԃ̓K�p�𐧌����邱�Ƃ́A�ō��ٕ���10�N�����̗\�肷��Ƃ���ł͂Ȃ��B
�@�i�T�j �ȏ�ɉ����āA�����n�ٕ���15�N9�������́A�u�{���ɂ����ẮA���ˊ��Ԃ̑ΏۂƂ����͍̂��Ɣ����@��̐������ł����āA���̌��ʂ���̂͏��ˊ��Ԃ̐��x��n�݂����퍐���g�ł���B�v�i������43�y�[�W�j�Ɣ������A���Ɛ��x�Ƃ��Ă̏��ˊ��Ԃ̐��x���A���ȊO�̎҂������҂ł���ꍇ�͓K�p����Ă��A���������҂ł���ꍇ�ɂ͓K�p����Ȃ����̂悤�ɏq�ׂĂ���B
�@�������A�O�������̉��A�@���͍����̑�\�҂ō\������鍑��ɂ����Đ��肳���̂ł����āA�s�����̍s�g�ɑ��Ă��A�@�������̋K��ǂ��蓙�����K�p�����͓̂��R�̂��Ƃł���A���ꂪ���`�����̗��O�ɒ�����������Ƃ����͖̂@����`�ɔ�����B
�@�܂��A�����n�ٕ���15�N9�������́A�u�𗝁v�Ƃ����T�O�ɂ���āA���@724����i�̓K�p�𐧌����Ă��邪�A���������u�𗝁v�́A��ʓI�ɖ@�̌�㞂�₤���̂ł����āA����8�N�̑������z��103���ɂ��A�����@�����K���Ȃ��Ƃ��ɍٔ��̊�Ƃ��ĂƂ肠��������̂ł���i�L��t�E�@���p�ꎫ�T��2��746�؈�W)�A�@�̓K�p��r�����Ė@�̌�㞂����o�����Ƃ̍����ƂȂ���̂ł͂Ȃ��B���������A�u�𗝁v�̖��̉��ɖ@�������邱�Ǝ��́A�𗝂��킵�Ă���Ƃ����ׂ��ł���B
�@���̂悤�ɁA�����n�ٕ���15�N9�������̔��f�́A���炩�Ɏ���@�̉��߂�����̂ł����āA�@���̉��ߓK�p�̖��̉��ɁA���̂悤�Ȕ��f������邱�Ƃ͋�����Ȃ��B
�@�i�U�j ����ɁA�����n�ٕ���15�N9�������́A���̓_�Ɋ֘A���A�Y���i�ז@255��1���̒�߂���i�����̒�~�̍l�����ɍ�����������A�Q�l�ɂȂ�|��������i������44�[�W�j���A�����͌��i�����Ɋւ���K��ł����āA���ˊ��ԂɊւ���K��ł͂Ȃ��B�������̔����́A���i�����Ə��ˊ��Ԃ̍��ق��ʼn߂��A���҂�����������̂ł����Ď����ł���B
�@�����I�Ɍ��Ă��A���i�����̒�~�Ɋւ���K��͍ٔ������@����s�g�ł��Ȃ��ɂ���Ƃ��̋K��ł��邪�A�{���ɂ����ẮA�ٔ������@����s�g�ł��Ȃ������Ƃ�������͑S���Ȃ��A��T�i�l��ɂ����Ē�i�Ɏ�����̍���������ɂ����Ȃ��̂ł���B
�@�S�@����
�@�ȏ�̂Ƃ���A�����n�ٕ���15�N9�������̎��Ăɂ����Ė��@724����i�̓K�p�𐧌����邱�Ƃ́A��O�����e�����ō��ٕ���10�N�����̎˒����A�ō��ٕ������N�����y�эō��ٕ���10�N�����ɔ�����Ƃ����ׂ��ł���B
�@���̓_�ɂ��āA���������ٔ�������12�N12��6�������i�����1744��48�؈�W�j���A�u�E�����i���p�Ғ��E�ō��ٕ���10�N����)�́A�w�s�@�s�ׂ̔�Q�҂��s�@�s�ׂ̎�����20�N���o�߂���O6�ӌ����ɂ����ĉE�s�@�s�ׂ������Ƃ��ĐS�_�r���̏틵�ɂ���̂ɖ@��㗝�l��L���Ȃ������ꍇ�x�Ƃ�������߂Č��肳�ꂽ�����W�̉��ŁA���@158���̋K��̓K�p�������̏ꍇ�ɂ��ĉ\�ł���̂ɏ��ˊ��Ԃɂ��Ă͕s�\�ƂȂ邱�Ƃɂ��s�ύt�������l���̏�A�����ǂ���̖@�K�̓K�p���@�S�̂��x�z���鐳�`�E�����̗��O�ɒ�������������̂Ɣ��f���A���@158���̒�߂���Ԃ͈͓̔��Ō����s�g�����邱�Ƃ����e�������̂ł���A��Q���r��ł��邱�ƁA���邢�͌����s�g������ł��邱�Ƃ𗝗R�Ƃ��ď��ˊ��Ԃ̉�����e�F������̂ł͂Ȃ��A���̂悤�Ȃ��Ƃ͏��ˊ��Ԃ��߂����@�̎�|�ɔ�����Ƃ����ׂ��ł���B�v�Ɛ����ɔ������Ă���i�������ٕ���16�N2���������A���ˊ��Ԃ̓K�p�Ɋւ��ē��l�̔��������Ă���B)�B
�@�������ɂ��A�s�i�����������T�i�l�́A�ō��ٔ����ɏ㍐�̐\���Ă����A�㍐�\�����R���ɂ����āA�{���T�i�l��ƑS�����l�̎咣���������i����82���E�Y������65�Ȃ���69�؈�W)�A�ō��ٔ�����ꏬ�@��́A����15�N12��25���A�u�{���\���Ă̗��R�ɂ��A�{���͖��i�@318��1���ɂ����x�����̂Ƃ͔F�߂��Ȃ��B�v�Ƃ��āA�s�̌���������i����83���j�B
�@���̂悤�ɏ��ˊ��Ԃ̓K�p�����Ɋւ���T�i�l��̎咣�́A���ɍō��ٔ����ɂ����Ĕr�˂��ꂽ�̂ł����āA�����I�ɉ����ς݂Ƃ����ׂ��ł���B
��R�@���������������ɂ���
�@�P�@�T�i�l��̎咣�̗v�|��
�@�i�P�j ��T�i�l�́A��T�i�l��������(1)93�y�[�W�ȉ��ɂ����āA�\���I�咣�Ƃ��āA���ɍT�i�l��̎咣���鋌���{�R�̍s�ׂɂ��A�T�i�l�ɉ��炩�̐����������������Ƃ��Ă��A���ؕ��a���11���y�уT����t�����V�X�R���a���14��(b)�ɂ��푈�̐��s���ɓ��{���y�т��̍������Ƃ����s�����琶�������������̐������́A���ɂ���āu�����v����Ă���A������������5���ɂ����u�푈�����̐����v�́A������u�������v���܂ނ��̂Ƃ��āA���ؐl�����a�������́u�����v��錾�������̂ł��邱�ƁA���������āA���̂悤�Ȑ������́A�T����t�����V�X�R���a���̓���������A�����̍����̐������Ɠ��l�ɁA���ɂ���ĕ�������Ă���A����Ɋ�Â������ɉ����ׂ��@����̋`�������ł��Ă���̂ŁA�~�ς����ۂ���邱�ƂɂȂ�|�咣���i������39�y�[�W�j�A�u�䂪�����{�̌����́A��̑��ɌW�锅�����тɍ��Y�y�ѐ������̖��ɂ��ẮA�T����t�����V�X�R���a��̑��Ԃ̕��a���y�т��̑��֘A�����ɏ]���Đ����ɑΉ����Ă��Ă���Ƃ���ł���A������̓������Ƃ̊Ԃł͖@�I�ɉ����ς݂ł����āA���{�ƒ����Ƃ̊Ԃ̐������̖��ɂ��Ă��A1972�N�i���a47�N�j9��29���ɏ������ꂽ�������������i������5���ɂ����ẮA�u���ؐl�����a�����{�́A�������������̗F�D�̂��߂ɁA���{���ɑ���푈�����̐�����������邱�Ƃ�錾����B�v�Ƃ���Ă���B�j���o��A�l�̐������̖����܂߂đ��݂��Ă��炸�A���̂悤�ȔF���́A�������{�����l�ł���v�i������95�y�[�W�j�Ǝ咣�����B
�@�i�Q�j ����ɑ��A�T�i�l��́A�T�i�l���3�������ʂɂ����āA�u��T�i�l�̎咣�����藧���߂ɂ́A��1�ɁA�T���t�����V�X�R���a���14��(b)�̏ɂ���āA��Q�������A��Q�Ҍl�̐������͊��S�ɏ����������ƁB��2�ɁA���ؕ��a���́A�T���t�����V�X�R���a���̘g���Œ������ꂽ�����̍��@���{�Ƃ̗L���������u�a���ł��邱�ƁB��3�ɁA�������������́A���ؕ��a�����p�����̂ł��邱�ƁA��3�_���O��Ƃ����B�������A��L3�_�́A����������藧���Ȃ��c�_�ł���A������������5�����߂̍������A�T���t�����V�X�R���a���Ɠ��ؕ��a���ɋ��߂�Ƃ�����T�i�l�̎咣�́A���ꎩ�̎����ł���B�v�Ƃ��A�u��T�i�l�̎咣�́A��1�ɁA�T���t�����V�X�R���a���14���̉��߂ɂ����āA��2�ɁA���ؕ��a���̉��߂ɂ����āA��3�ɁA�T���t�����V�X�R���a���y�ѓ��ؕ��a��������������̍����ƂȂ��Ă���Ƃ������߂ɂ����āA�����������Ă���B�v�i�T�i�l���3��������37�A38�y�[�W�j�Ǝ咣���āA��T�i�l�̎咣�����_���B
�@�������A�T�i�l��̂�����̎咣���A�ȉ��ɏq�ׂ�悤�ɁA���̒���������L������{�����{�i���@73��2���A3���j�̌����𐳉����Ă��炸�A�����ł���B
�@�Q�@�T����t�����V�X�R���a���̈Ӌ`���ɂ���
�@�i�P�j �T����t�����V�X�R���a���y�т���Ɋ�Â���㏈���̎����W�ɂ��ẮA��T�i�l��������(1)95�y�[�W�ȉ��ŏڏq�����Ƃ���ł���B
�@���Ȃ킿�A���̍u�a���́A�푈�������݂̂Ȃ炸�A���̓��������݂̍����ɍL�͈͂ɔ��������푈�s�ׂɂ���Đ�������Q�̔�����������������ł���A��ʓI�ɔ������̑��푈�W���琶�����������̎�̂́A���ۖ@��̑��̍s�ׂ�萶�����������̎�̂Ɠ��l�A��ɍ��Ƃł����āA��O�I�ɏ��ŁA��Q�҂ł��鍑���l�ɑ��āA�������҂Ƃ��Ē��ڕK�v�ȑ[�u���Ƃ���@��݂����ꍇ�ȊO�́A�����l�̎���Q�́A���ۖ@�I�ɂ͍��Ƃ̔�Q�ł���A���Ƃ����荑�ɑ��ČŗL�̐��������s�g���邱�ƂɂȂ�i���]�[�l�Y�E���{�u�a����̌���248�y�[�W�Q�ƁE����51���j�̂ł����āA�����l�̎���Q�ɂ��Ă��A�u�a���ɂ���Ă��̔�����肪���������̂ł���B
�@�����āA����E����ɂ����ẮA�x���T�C�����ɂ����鎸�s�̔��Ȃ���A��㔅�����̉����ɓ������āA�����������̗��Q��������ŁA�����������Ƌy�т��̍������������Q����̂Ƃ��ĂƂ炦�A���荑�Ɠ���I�Ɍ����邱�ƂƂ��Ĕ������ɍŏI�I�Ȍ�����}�邱�ƂƂ��A���̌��̌��ʁA�����Ɏ���u�a��́A���̍��ۓI�g�g�݂��\�z�����ŁA�K�����Ó��ȉ�����ڂ������̂Ƃ��Ĉʒu�Â����A�������y�т��̍����̑��݂̐^�̈Ӗ��ł̘a���̈�Ƃ��āA���̌�̓������y�ё��݂̍����̗F�D�W�̊�ՂƂȂ邱�Ƃ�ړI�Ƃ����B
�@���̂��߁A���̂悤�ȍu�a���̘g�g�݂̉��ł́A��㔅���́A�����Ƃ��č��ƊԂ̒��ڏ����A���͋��������̋��G�����Y�ɂ�閞���̕��@�ɂ�邱�ƂƂ��ĉ������}���A�X�̍����̔�Q�ɂ��ẮA�����Ƃ��āA�����������Y�������̍������Ƃ��āA�e�������̍��̍���������l�����A�~�ϗ��@���s���Ȃǂ��ĉ������}���Ă���i���]�E�O�f���{�u�a����̌���250�؈�W�Q�ƁE����51���j�̂ł���i��T�i�l��������(1)96�A97�؈�W�Q�Ɓj�B
�@�i�Q�j ��ɁA�T���E�t�����V�X�R���a���𗝉������ł́A���������A�䂪��������E���̔s�퍑�ł��邱�Ƃɗ��ӂ��ׂ��ł���B
�@�T���E�t�����V�X�R���a���́A�u�a���ƐM���v�̕����Ə̂���邪�A�u�a���ł������A�Ƃ��ɐ폟���Ɛ�s���Ƃ̍u�a���ł������A��̕����Ƃ������Ƃ́A�͂��߂��炠�蓾���A�폟�����L���ȗ���ɗ����A��s�����s���ȗ���ɗ����A���̊Ԃɂ����炩�̕s���������邱�Ƃ́A�폟���Ɛ�s���̍u�a���ł������A���R�̂��Ƃł���A�K�R�ł���i���c��O�Y�E���a����̑��������㊪59�؈�W�j�Ƃ���Ă���B
�@�푈�����̖����A���������ٔ�������13�N10��11�������i�����1769��61�؈�W�E����16���؎Q�Ɓj����������悤�Ɂu�푈��Q�̋~�ς́A�푈�̏��s�𗣂�Ă͑��݂��Ȃ��̂������ł���B�푈�I����A�푈�̌�n���Ƃ��āA�푈��Q�̋~�ςɊւ���O�������s���A�����̏ꍇ�́A�u�a���i���a���j�̈���e�Ƃ��āA�����Ɋւ��鍇�ӂ������B���̊O�����́A�������푈�̏��s�Ƃ��������̉e�����ɍs���邩��A��s�����폟�����甅�����邱�Ƃ͂܂��Ȃ��B�����́A�폟������3���݂̂���s�������̂ł���i���]�[�l�Y�u���{�u�a���̌����v222�Łj�B
�@�s�퍑�ł���䂪���ɂƂ��āA�T����t�����V�X�R���a����������邩�ۂ��́A�����1�����A��������ɉ䂪���ƘA�����Ƃ̐푈��Ԃ͏I�����A�䂪���y�т��̗̐��ɑ���䂪�������̊��S�Ȃ�匠�����F�����|�K�肳��Ă��邱�Ƃ��疾�炩�Ȃ悤�ɁA���̓��e��������ĘA��������Ɨ����邩���邢�͎�������ۂ��ĘA�����ɐ�̂��ꂽ�܂܁i�����6���Q�Ɓj�A�A�����Ƃ̐푈��Ԃ��p�������邩�̂ǂ��炩�̓���I�����邩�Ƃ������ł������B
�@���{�����{�́A�T���E�t�����V�X�R���a����������邱�Ƃ����f���A�O�҂̓���I�̂ł���B
�@�����āA�T���E�t�����V�X�R���a���̏������́A�s�퍑�ł���䂪�����A�A�����Ƃ̐푈��Ԃ��I�������A���S�Ȏ匠�����F����邽�߂ɁA�̓y�̏����A�������тɍ��Y�y�ѐ������̖��̉����ɂ��Ď����ꂽ�A��������̏����ł���A��T�i�l��������(1)99�Ȃ���102�[�W�ŏq�ׂ��Ƃ���A�䂪���́A�T���E�t�����V�X�R���a�������������A�����Ɋ�Â��A�����ɑ��đ��z�̎x�����s���A�����ɑΉ����Ă����Ƃ���ł���B
�@���̓_�Ɋւ��A�O�f���������ٔ�������13�N10��11�������p�i�����1769��61�[�W�E����16���؎Q�Ɓj�́A�T���E�t�����V�X�R���a���14��(b)�ɂ��A�A�������A�����y�т��̍����̓��{���y�т��̍����ɑ��鐿��������������̂́A�u�䂪�����A�s��ɂ��A�C�O�̗̓y�̖v�������łȂ��A�A�������݂̂Ȃ炸�A�����A��p�A���N���ɂ�������ʍ����̍݊O���Y�܂Őڎ�����A����ɒ������ɂ��������{�����̍��Y�܂Ŕ����̌����Ƃ����Ƃ������ߍ��ȕ��S�̌��Ԃ�ł������B�܂��A����͏����ɂ�������{�̕����ƍ��ێЉ�ւ̍v�������҂��Ă̑[�u�ł������v�Ɣ������A���m�Ȏ����F���Ɋ�Â������ȕ]�������Ă���B
�@�i�R�j �T�i�l��́A�u�A�����J�̍u�b����́A�{���̐푈�����Ƃ����ړI�Ƃ͗������A���{���o�ϓI�R�m���I�ɂ�����u�����w�c�v�Ɏ��g�ނ��Ƃ�ړI�Ƃ������́v�ŁA�u���̌��ʁA�T���t�����V�X�R���a���14���ɂ����锅���̌y���E�������}��ꂽ�v�i�T�i�l���3��������41�y�[�W)�Ǝ咣���A���������A�T���E�t�����V�X�R���a���14��(b)�ɂ�鐿�����������A�s���ɉ䂪���̔������y���������̂ł��邩�̂悤�Ɏ咣����B
�@�������A�T���E�t�����V�X�R���a���̏��F���x�������č���@�O���ψ���́A�u�u���炩�ɁA�����Ȃ�䗦�ł����Q���������y�т��̍����̐������̉��z�ɔ�Ⴗ�锅�����̎x�����ɌŎ����邱�Ƃ́A���{�o�ς�j�A���{�����ݗL����ΊO������������A���{�����̐i��̋C����ł��ӂ��A�݂��߂��ƍ��ׂ݁A�����ɕs���̎�Ƌ��Y��`���h����ł��낤�B�v�i��@��No.82-2
2d Sess(1952)�v�i�J���t�H���j�A�B�T�i�ٔ���2003�N2��6�������E����63����9�y�[�W�j�Əq�ׁA�܂��A�u�_���X��\���A�u���{�́A���݁A�����������邽�߂ɕK�v�Ƃ���H�Ɩ��͎d�������邽�߂ɕK�v�Ƃ��錴�ޗ��Y���邱�Ƃ��ł��Ȃ�4�̓��ɏk������Ă���B�v�u���̂悤�ȏɂ����āA���a����{�ɑ�����K����������L���ł���Ƃ��A���͏����t���ő����������ꍇ�A���{�̒ʏ�̏��ƐM�p�͏��ł��A�����̈ӗ~�͉�ł��A�����ē��{�����͐S���I�ȋ�Y�Ɋׂ�A�e�Ղɍ��̉a�H�ɂȂ��Ă��܂��ł��낤�B�v�u���z�I�Ȗ��̎������ő���ɋ��߂āA�A�������ɂ����āA��w����ȋ������N����ł��낤�B�v�ƗJ�������B�v�i�O�f�������ٕ���13�N10��11�������E�����1769��72�y�[�W�E����16����29�A30�y�[�W)�Ƃ����B
�@���������A������ō��@�K���錛�@�����݂��邩��Ƃ����āA�A�����̐�̌R�ɗ̈悪��̂���i�T���E�t�����V�X�R���a���6���i(a)�Q�Ɓj�A���{���y�т��̗̐��ɑ�����{�����̊��S�Ȃ�匠���Ȃ���i�����1��(b)�Q�Ɓj�A�u�����̎匠���ێ����A�����ƑΓ��ȊW�v(���@�O���j�ɗ����Ƃ͂ł��Ȃ��̂ł����āA���̊ϓ_������A�T���E�t�����V�X�R���a������̉䂪���̑�����Ղł��邱�Ƃ𐳓��ɗ������邱�Ƃ��K�v�s���ł���B
�@���{�����{�́A����12�N�ɁA�k���J���t�H���j�A��T���t�����V�X�R�x���A�M�n���ٔ����ɌW�����Ă������č��ߗ����ɂ����{��Ƃɑ���i�ׂɊւ��āA�T����t�����V�X�R���a���̈Ӌ`�Ɋւ��Ĉӌ����q�ׁA���ӌ����́A���ٔ����ɒ�o���ꂽ�B���ӌ����ŁA���{�����{�́A�u���j��ł��j��I�Ȑ푈�̈���i���p�Ғ��E�T����t�����V�X�R���a���j�̒����ɂ���Đ����ɏI����������A���{���ƕč��́A���E�ŗނ����Ȃ��悤�ȍł����ݓI�ŗL�v�ȍ��ۓI�p�[�g�i�[�V�b�v�̈��z�����B���̊W�́A���ݑ��d�A�M�����тɖ����`�A���R�s��o�ρA�@�̎x�z�y�ъ�{�I�l���̑��d���̋��L���ꂽ���l�ςɊ�Â��Ēz���ꂽ���̂ł���B50�N�ȏ���O�ɍŏI�I�ɉ��������Ɠ��ė��������ӂ��Ă��锅���̖��������Ԃ����Ƃ��邱�Ƃɂ���āA���̈̑�Ȃ���Y�����e������悤�Ȃ��ƂƂȂ�A�^�Ɉ⊶�ł���B�v�i����60���j�Əq�ׁA�܂��A�č����{���T����t�����V�X�R���a��A�����Ɖ䂪���Ƃ̊W�̊�Ղ��Ȃ����Ƃ����������B
�@�ȏ�ɂ݂���悤�ɁA�č����܂ޘA�������u�a���ƐM���v�̕����ł���A�T����t�����V�X�R���a���̈Ӌ`�𐳂����������Ă���A���ꂪ���䂪���ƘA�����Ƃ́u���ʂ̕����i�������ۂ̕��a�y�ш��S���ێ����邽�߂Ɏ匠��L����Γ��̂��̂Ƃ��ėF�D�I�ȘA�g�̉��ɋ��͂��鍑�Ƃ̊Ԃ̊W�v�i�T����t�����V�X�R���a���O���j�̊�ՂƂȂ������Ƃ͖��炩�ł����āA�T�i�l��̎咣�͎����ł���B
�@�R�@�u�T���t�����V�X�R���a���ɂ�����l�̐��������v�Ɋւ���T�i�l��̎咣�̌��ɂ���
�@�i�P�j �T�i�l��̎咣
�@�T�i�l��́A�O�L�̂Ƃ���A�u��T�i�l�̎咣�����藧���߂ɂ́A��1�ɁA�T���t�����V�X�R���a���14��(b)�ɂ���āA��Q�������A��Q�Ҍl�̐������͊��S�ɏ��ł������Ɓv���O��ɂȂ�i�T�i�l���3��������37�y�[�W�j�Ƃ�����A�u��T�i�l�́A�u�������������ɂ���Ē��������̐��������������ꂽ�v�Ƃ����咣�̑O��ł���A�u�T���t�����V�X�R���a���14���ɂ���Čl�̐����������S�ɏ��ł����v�Ƃ�����T�i�l�̉��߂͐��藧���Ȃ����̂ł���v�i������45�y�[�W�j�Ǝ咣����B
�@�i�Q�j ��T�i�l�̔��_
�@�T�i�l��́A��T�i�l���A�T����t�����V�X�R���a���14��(b)�ɂ���āA�l�̐����������ł����Ǝ咣���Ă��邩�̂悤�ȑO��ɗ����āA��L�咣�����Ă���B
�@�������A��T�i�l����T�i�l��������(1)�Ŏ咣�����̂́A�T���E�t�����V�X�R���a���14��(b)�ɂ����u�������̕����v�Ƃ́A�u���{���y�ѓ��{�������A���������ɂ�鍑���@��̐������Ɋ�Â������ɉ�����@����̋`�������ł������̂Ƃ��āA��������₷�邱�Ƃ��ł���|��߂�ꂽ���̂Ɖ����ׂ��ł���v�i������109�y�[�W�j�Ǝ咣�����̂ł���A�l�̐����������ł����Ǝ咣�������̂ł͂Ȃ��B
�@���̖��ɂ��ẮA���a31�N4��10���A�Q�c�@�O���ψ���ɂ����āA���c���O�O���ȏ��ǒ����A�T����t�����V�X�R�u�a��c�ɂ����āA�I�����_��\�����N���ꂽ���i��T�i�l��������(1)104�Ȃ���106�y�[�W�j�ɂ��āA�u�@���I�ɂ͋`����Ȃ��ŁA���������炩�̖������I�����_���ɗ^����Ƃ������n����A���������I�ɂ��邱�Ƃ�����Ƃ������Ƃɂ������܂��āA����ɂ���āA�Ƃɂ����I�����_�̏�����������킯�ł���܂��B�v�i����84����2�y�[�W�j�Əq�ׂĂ��邱�Ƃ�������炩�ł���A����13�N3��22���A�Q�c�@�O��h�q�ψ���ɂ����āA�C�V���a�O���ȏ��ǒ����u����A�䂪�����咣���܂����_�Ɋւ��܂��ď��ł����Əq�ׂĂ���܂��̂́A�l�̐��������̂��̂����ł����Ƃ����ӂ��Ȍ������͂��Ă���Ȃ��킯�ł������܂��āA14��(b)���ɂ��܂��Ă����̐������A���Ɋ�Â������ɉ����ׂ��@����̋`�������ł��A���̌��ʋ~�ς����ۂ����Ƃ������Ƃ��q�ׂĂ���킯�ł������܂��B�v�i����85���j14�y�[�W�j�Ɠ��ق��Ă���Ƃ���ł���B
�@���������āA�T�i�l�̎咣�́A��T�i�l�̎咣�����������Ŕᔻ�ł���A�O������������ł���B
�@�S�@���ؕ��a���Ɋւ���T�i�l��̎咣�̌��ɂ���
�@�i�P�j �T�i�l��̎咣
�@�T�i�l��́A�O�L�̂Ƃ���A�u��T�i�l�̎咣�����藧���߂ɂ́A�c�c��2�ɁA���ؕ��a���́A�T���t�����V�X�R���a���̘g���Œ������ꂽ�����̍��@���{�Ƃ̗L���������u�a���ł��邱�Ɓv���O��ɂȂ�i�T�i�l���3��������37�y�[�W�j�Ƃ�����A�u���ؕ��a��������ꂽ1952�N4��28���i�����͓��N8��5���j�ɂ����āA���łɏӉ�ΐ����������̍��@���{�Ƃ͂����Ȃ����Ƃ͖����ł���A���Ȃ��Ƃ�1972�N�̓������������̎��_�ŁA���ؕ��a���͖����ƂȂ����Ƃ���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B���ɂ��ꂪ�L���Ȃ��̂Ƃ��Ă��A���̎�����1972�N9��29���i�������𐳏퉻�̓�)�܂łł���A���̗L���͈͂́A�����S�y�ł͂Ȃ��A��p�n��ɂ����y�Ȃ����̂ł���B���̓_�́A��ɂ�������������̐��{���قɂ���āA���{���{���F�߂Ă���Ƃ���ł���A���ؕ��a��̂ɂ��A����������ꍆ�Ƃ����`�Łu���̏��̏������A���ؖ����Ɋւ��ẮA���ؖ������{�̎x�z���Ɍ��ɂ���A��������邷�ׂĂ̗̈�ɓK�p������|�̂����̊ԂŒB���������v�Ɩ��L����Ă���v�ȂǂƎ咣���A�u�u���ؕ��a���́A�T���t�����V�X�R���a���̘g���Œ������ꂽ�����̍��@���{�Ƃ̗L���������v�Ƃ�����T�i�l�̎咣�͐������Ȃ��v�Ǝ咣����i�T�i�l���3��������49�y�[�W�j�B
�@�i�Q�j ��T�i�l�̔��_
�@�������A�䂪���́A�����A�������\����B��A���@�̐��{�Ƃ��ď��F���Ă������ؖ������{�Ƃ̊Ԃœ��ؕ��a��������������̂ł��邩��A���̏���ۖ@�㍇�@���L���ȏ��ł��邱�Ƃɋ^���̗]�n�͂Ȃ��A�������A
���ؕ��a���ɂ������Ԃ̐푈��Ԃ̏I���y�є������тɍ��Y�y�ѐ������̉����́A��x����̏����s�ׂł��邩��A��������e�̋K��́A����Ɠ����ɍŏI�I���ʂ������A���̌�ɂ�������̑����̗L���ɂ���Ă��̖@�I���ʂ��ς��Ƃ��낪�Ȃ��B
�@�܂��A���ؕ��a���ɕ�������K�p�n��Ɋւ�����������i�ȉ��u�������������v�Ƃ����B�j�́A���ؖ������{�̐�������n���I�Ɍ��肵�����̂ł͂Ȃ��A�푈��Ԃ̏I���┅�����тɍ��Y�y�ѐ������̖�蓙�́A���̐�����A�n���I�K�p�͈͂����ƂȂ���̂ł͂Ȃ��B
�@���������āA�O�L�̍T�i�l��̎咣�͎����ł���B
�@�ȉ��A�����̓_�ɂ��ڏq����B
�@�A�@���ؕ��a�������̌o��
�@����E����̒����ɂ����āA��̍��ƂƂ��Ắu�����ichina�j�v���\���鐭�{�Ƃ��āA���ؖ������{�ƒ��ؐl�����a�����{���݂��Ɏ��Ȃ̐��������咣���Ă����B
�@���̂��߁A�T����t�����V�X�R�u�a��c�ɒ��ؖ������{�A���ؐl�����a�����{����������҂��邩�ɂ��Ė�肪�������B���̖��ɂ��A�A�����̊ԁA���ɕĉp�����̊Ԃňӌ��̑Η�������A���ǁA������������Ȃ��Ƃ������ƂɂȂ������A���̌��ʁA���{�͂�����̐��{�Ɛ��O���W�����Ԃ������ƂȂ�A�č��ɂƂ��Ă����ɑ傫�Ȑ������ƂȂ����B���a26�N���ɁA�č����{�̒��őΓ����a������S������_���X���g���������A�����g���A�g�c�Α�����b�ɑ��āA�䂪�������ؖ������{�ƕ��a�����������̂łȂ���A�T����t�����V�X�R���a��̂��č��c��̏��F���Ȃ��Ɛ����������߁A�g�c����������ɉ����A������g�c���ȁi�����W��{����27�Ȃ���29�y�[�W�E����86���j�o���A���{�͒��ؖ������{�ƕ��a����������邱�Ƃ�����i�I�R����E�������𐳏퉻�E���@74��4��40�y�[�W�E����87���j�B
�@���̂悤�ɂ��āA�䂪���́A���ؖ������{�������āA�������\���鐳�����{�ł���Ə��F���āA���ƂƂ��Ă̒����Ɠ��{���Ƃ̐푈��Ԃ̏I�����̖����������邽�߂ɓ��ؕ��a������������B�Ȃ��A���a27�N�܂łɖ�35���������ؖ������{�����F���A20���������ؐl�����a�����{�����F���Ă����Ƃ����A���ؕ��a�����������̒��ؖ������{�́A���ۘA���ɂ������\����L���A���A����61�����̂����A���ؐl�����a�����{�����F���Ă������́A12�����ɉ߂��Ȃ��������̂ł���i���]�ʉ�E���ؕ��a���̍��@�E�L�����ɂ��āE�@�ƒ�����1��6��41�y�[�W)�B
�@�C�@�푈��Ԃ̏I���A�������тɍ��Y�y�ѐ������̖�菈��
�@�푈��Ԃ̏I���A�������тɍ��Y�y�ѐ������̖��̏����ɂ��ẮA�O�L�̂Ƃ���A���a���̒����ɂ���āA���Ƃƍ��Ƃ̊Ԃʼn��������ׂ����ł���A�䂪�������������T���E�t�����V�X�R���a�����͂��߂Ƃ��āA�e���̎��s���ςݏd�˂��Ă��Ă���i�O�f����14�N12��20���t���O�c�@�c���ߓ�����N��o���N�l�����A�s�E�����J���Ɋւ��鎿��ɑ��铚�ُ��܁E����88����1�y�ё�88����2�j�B
�@�����āA�����Ԃ̐푈��Ԃ̏I���A�������тɍ��Y�y�ѐ������̖��́A���ؕ��a���ɂ���Ė@�I�Ɋ��S���ŏI�I�ɉ��������B���̂悤�Ȗ��̏����́A��x����̏����s�ׂł���A��������2�x���a����������邱�Ƃ͖@�I�ɕs�\�Ȃ��Ƃł���B���̓_�ɂ��ẮA�����v�Y�O���ȏ��ǒ����A���a48�N7��26���A�O�c�@���t�ψ���ɂ����āA�u���{�ƒ����Ƃ̊W�ɂ����āA���̑�\���鐭�{���]���̒��ؖ������{���璆�ؐl�����a�����{�ɏ��F����������Ƃ������j�Ɋ�Â��č�N��������������������킯�ł������܂�����ǂ��A��{�I�ɖ@���W�͓��ؕ��a���ɂ���Ē����Ƃ̊Ԃɂ��ׂď����ς݂ł���A���̑O��Ɋ�Â��Ă�����킯�ł������܂��̂ŁA�V���ɂ܂��@���W�𒆍��Ƃ̊Ԃɒ����������Ƃ������Ƃ͕s�\�ȏ�Ԃɂ������v�i����89����2�y�[�W�j�u�����Ƃ̊Ԃɐ�㕽�a����������܂������������܂��āA���������Ƃ̊Ԃɓ�x���a�����������Ƃ������Ƃ͖@���I�ɕs�\�Ȃ��Ɓv�i������3�y�[�W�j�Ɠ��ق��Ă���Ƃ���ł���B
�@���������āA���ؕ��a���ɂ���āA���{�ƒ����Ƃ̊Ԃň�x�@�I�ɉ������������A�ēx�����Ԃŏ������邱�Ƃ͂��蓾���i��T�i�l��������(1)120�y�[�W�j�A��̑��ɌW�锅�����тɍ��Y�y�ѐ������̖��́A�����Ԃɂ����ẮA���ؕ��a���ɂ���Ė@�I�ɂ͉����ς݂ł���B
�@�E�@�������������ɂ���
�i�A�j�������������ɂ́A�u���̏��̏������A���ؖ����Ɋւ��ẮA���ؖ������{�̎x�z���Ɍ��ɂ���A���͍�����邷�ׂĂ̗̈�ɓK�p������v�Ƃ̋K�肪����Ƃ���A�T�i�l��́A���̕������������̑��݂ɂ��A���ؕ��a������嗤�ɂ͓K�p����Ȃ��|�咣����B
�i�C�j�m���ɁA���ؕ��a�����������A���ؖ������{�́A�����嗤�̎����I�x�z�������A��p�y���O�Ώ������̎����I�x�z�����Ă���ɂ����Ȃ������B���������āA�ʏ��q�C���i���ؕ��a����7���j�A���ԍq��i��8���j�A���Ƌ���i��9���j���A���Y�����̓��e���炵�Č��Ɏx�z���Ă��Ȃ��n���ΏۂƂ��邱�Ƃ��ł��Ȃ��K�肪�{���������������̑ΏۂƂȂ邱�Ƃ́A�^���̂Ȃ��Ƃ���ł���B
�i�E�j�������Ȃ���A�푈��Ԃ̏I���A�������тɍ��Y�y�ѐ������̖��̏����Ƃ������A���ƍ��Ƃ̊ԂōŏI�I�ɉ������ׂ������I�ȏ����́A���ɍ��Ƃƍ��Ƃ̊Ԃ̊W�Ƃ��Ē�߂���ׂ����̂ł����āA���̐�����A�K�p�n������肷�邱�Ƃ��ł��Ȃ����̂ł���B���Ȃ킿�A�`���I�ȁu�푈�v�̊T�O�ɂ��ẮA��ʓI�ɂ́A���ە�������������Ō�̎�i�Ƃ��āA��̍����Γ��̗���ō����̔����Ƃ��ĕ��͂��s�g���������Ƃ������i����11�N3��15���Q�c�@�E�O��h�q�ψ�����a�F���ǒ����فE����90����16�y�[�W�Q��)�A���Ƃƍ��ƂƂ̊Ԃ̊W�Ƃ��ĂƂ炦����ׂ������ł����āA�푈��Ԃ̏I���A�푈�̏������̂��̂ł���푈�ɌW�锅�����тɍ��Y�y�ѐ������̖����A���ۖ@��̓����҂Ƃ��Ă̍��ƊԂɂ����čŏI�I�ɏ��������ׂ������ł���A���Ɠ��ɂ�����K�p�n��ɂ�������鐫���̂��̂ł͂Ȃ��̂ł���B
�@���������āA���ؕ��a���́A�푈��Ԃ̏I���Ɛ푈�ɌW�锅�����тɍ��Y�y�ѐ������̖��Ɋւ����ƂƂ��Ă̒����Ɠ��{�Ƃ̊ԂŊ��S���ŏI�I�ɉ����������̂ł���B
�i�G�j���̂��Ƃ́A���̋K�肩������t������B
a�@���ؕ��a���1���́A�u���{���ƒ��ؖ����Ƃ̊Ԃ̐푈��Ԃ́A���̏���͂�����ɏI������v�ƋK�肷��B
�@�O�L�̂悤�ɁA���ؕ��a�����������A���ؖ������{�́A�����嗤�̎����I�x�z�������A��p�y���O�Ώ������̎����I�x�z�����Ă���ɂ����Ȃ��������A����������p�y���O�Ώ����́A����E��풆�ɂ́A���{���̗̓y�̈ꕔ�𐬂��Ă����̂ł��邩��A���{���Ƒ�p�E�O�Ώ����Ƃ̊Ԃɂ͐푈��Ԃ͑��݂��Ȃ������̂ł���B����ɂ�������炸�A���ؕ��a���1���ɁA�O�L�̋K�肪�u���ꂽ�̂́A������ƂƂ��Ă̒����Ƃ̊Ԃ̐푈��Ԃ̏I���ɂ��Ē����𐳓��ɑ�\���Ă������ؖ������{�Ƃ̊ԂŒ�߂����Ƃ�@���Ɏ������̂ł���B
�@����́A���ؕ��a�����������獡���܂ł̓��{���{�̈�т��������ł���B
�@���Ȃ킿�A���c���O�O���ȏ��ǒ��́A���a27�N6��17���̎Q�c�@�O���ψ���ɂ����āA���ؕ��a���u��꞊�̓��{�Ƃ������ƒ����Ƃ������Ƃ̍��ƊԂ̐푈��Ԃ��I��������Ƃ������Ƃ́A�����Ɏx�z���Ă���n�悪�ǂ��̂����̂Ƃ����������Ƃ͖��W�ȑS�ʓI�Ȗ@���W���Ӗ�����킯�ł���܂��B�]���܂��Ĉ���n��ɁA���₻���łȂ��A�푈��Ԃ͈ˑR�Ƃ��Čp�����Ă���Ǝ咣���鐭�������邩�Ȃ����Ƃ������Ƃ́A�܂莖�����ł���܂��āA���̞���̉��ߘ_�Ƃ��ė����̈ӎv�͖��m�ɂ����ɂ���A��������ߊ肢�����Ǝv���̂ł��v�Əq�ׁA����ɁA�u���̞�������@�I�̌��ʂƂ������̂͂ł��ˁA���R�ɒ����̍��ƂƂ������̂ɋA��������炵�āA���ɂ��̐��{�Ƃ������̂�����������\���鐳���Ȑ��{�Ƃ������̂��ς����A�Ƃ����ꍇ�ɂ��A���̌����`���̊W�͓��R�p����������̂ł��ˁB����͓��R�̂��Ƃ��Ǝv���̂ł����A�O�̂��߁B�v�Ƃ̎���ɑ��A�u���l���̒ʂ肾�Ǝv���܂��B�v�Ɠ��ق����i����91����14�y�[�W�j�B
�@����ɁA���a44�N3��13���̎Q�c�@�\�Z�ψ���ɂ����āA���m����O����b���u�n���I�Ɍ����Β����{�y�ɂ�����܂��Ă��푈��Ԃ͏I�������B���̓��ؕ��a���ɂ����āv�A�u����͂��̓����A�������A�����č���̔�y�����������܂����Ƃ�����́A������т������{�̌����ł���v�Əq�ׂĂ���i����92����10�y�[�W�j�B
b�@���ؕ��a���11���̒�߂�u���̏��y�т����⑫���镶���ɕʒi�̒�v�Ƃ��āA������c�菑�P(b)�́A�u���ؖ����́A���{�����ɑ��銰���ƑP�ӂ̕\���Ƃ��āA�T���E�t�����V�X�R����14��(a)�P�Ɋ���{�������ׂ��̗��v�𔒔��I�ɕ�������B�v�ƒ�߂��B
�@�����ŕ������ꂽ�����Ƃ́A�T���E�t�����V�X�R���a���14��(a)�P�ɂ��A���{���R���ɂ���Đ�̂��ꑹ�Q�������A��������]����ꍇ�ɔF�߂���Ƃ���Ă������̂ł���B
�@����𒆍��Ƃ̊W�ł݂��ꍇ�A���{�Ɠ������{�̗̓y�ł�������p�E�O�Ώ����Ƃ̊Ԃɂ͐푈��Ԃ͑��݂��Ȃ�����A�푈�����̖����������A�������������Ƃ���A����͍����钆�����\���钆�ؖ������{�ɂ�锅���������̕������Ӗ����邱�ƂɂȂ�B
�@���̓_�ɂ��ẮA���a39�N3��11���̏O�c�@�O���ψ���ɂ����āA����Z���ǒ����A�u�c�c�t�����������ŁA�K�p�n��͍������{�����Ɏx�z���܂��͏����x�z����n��ɓK�p�����̂��Ƃ������ӂ�����킯�ł������܂����A����́A�������A���̐�������A���̏����̓��e�̐�������K�p�����Ȃ����̂�����̂��A����́A���Ƃ��Α�1���ŁA���{���ƒ��ؖ����Ƃ̊Ԃɂ͕��a��Ԃ������Ƃ����悤�Ȑ푈�I���̏����A����́A�푈�����Ƃƍ��ƂƂ̊Ԃ̐푈�ŁA��Ԃł���ȏ�A���̏I���Ƃ����̂��n��I�Ɍ��肷��Ƃ������Ƃ͖��Ӗ��ł���A����͍��ƑS�̂ɓK�p���Ȃ�A���ؖ����Ƃ������ƑS�̂ɓK�p�ɂȂ�Ƃ������Ƃ������Ă���܂��B�����ɂ��܂��Ă������悤�Ȑ����ł���̂ł���܂��āA�푈�̌��ʎ��ł��낤���荑�̔����������A�������������Ƃ����̂ɁA�n��I�Ɍ��肵�đ�p�A�O�Γ������ɔ���������������Ƃ����悤�Ȃ��Ƃ͖��Ӗ��ł������܂��B����������p�A�O�Γ��͓��{�̋��̓y�ł���܂��āA����Ɛ푈��Ԃ͂Ȃ������킯�ł���܂��āA�����ɔ����Ƃ������̂��N����Ƃ������Ƃ͂��蓾�Ȃ��킯�ł���܂��B����͂�͂荑�ƂƂ��Ē��ؖ������{����������������Ă���A�����������Ƃɉ��߂�����Ȃ��B�܂�A���ؕ��a���̋K��̓��e�ɂ���āA�n��I�ɓK�p��������͓̂K�p����A�������Ȃ���A���ƑS�̂ɓK�p���ׂ����͍̂��ƑS�̂ɓK�p������Ƃ������Ƃ́A����͓��R�ł���A�����������Ƃ����̓����̐��{�̌�����ł���܂��āA���̌㐭�{�Ƃ��Ă͂�����̎�|�ň�т��čl���Ă���킯�ł������܂��B�v�i����93����10�A11�y�[�W�j�Ɩ��m�ɏq�ׂĂ���B
�@�G�@����
�@�ȏ�̂悤�ɁA�䂪���́A�������\����B��A���@�̐��{�Ƃ��ď��F���Ă������ؖ������{�Ƃ̊Ԃœ��ؕ��a��������������̂ł��邩��A���̏���ۖ@�㍇�@���L���ȏ��ł��邱�Ƃɋ^���̗]�n�͂Ȃ��B
�@�����āA���ؕ��a���ɂ������Ԃ̐푈��Ԃ̏I���y�є������тɍ��Y�y�ѐ������̉����́A��x����̏����I�s�ׂł���B
�@���������āA�����Ԃ̐푈��Ԃ̏I���y�є������тɍ��Y�y�ѐ������̖��ɂ��ẮA�t�����������̋K��ɂ���Č�����邱�Ƃ͂Ȃ��A���ؕ��a���ɂ���āA���Ƃƍ��Ƃ̊ԂŊ��S���ŏI�I�ɉ������ꂽ���̂ł���A������K��̓��e�́A��s�Ɠ����ɍŏI�I���ʂ������A���̌�ɂ�������̑��݂̗L���ɂ���Ă��̖@�I���ʂ��ς�邱�Ƃ��Ȃ��B
�@�ȏ�q�ׂ����Ƃ��疾�炩�Ȃ悤�ɁA�T�i�l��̑O�L(1)�L�ڂ̎咣�́A�����ł���B
�@�T�@�������������Ɋւ���T�i�l��̎咣�̌��ɂ���
�@�i�P�j �T�i�l��̎咣
�@�T�i�l��́A�������𐳏퉻���̌o�܂�������������T���̉��߂Ȃǂ����q�ׂ�Ƃ���A���̎�|�͕K���������炩�ł͂Ȃ����A����������ē������������͌l�̐�������������Ă��Ȃ��|���咣����悤�ł���B
�@�T�i�l��̏�L�咣�́A�T�i�l��̐��������������������ɂ���ĕ�������邩�ۂ�����Ƃ�����̂ł��邪�A����͓������������̈ʒu�Â��������̂ł���B
�@�����ŁA�ȉ��ɁA�������𐳏퉻�Ɏ���o�܋y�ѓ��{�����{�̌������q�ׂ���ŁA�������������̓��e�����{�����{�ƒ��ؐl�����a�����{�̑o���̎咣�𑊗e�����e�Ƃ��ċK�肳�ꂽ���Ƃɂ��Đ�������B
�@�i�Q�j �������𐳏퉻�Ɏ���o�܂ɂ���
�@�A�@�͂��߂�
�@�O�L�̂悤�ɁA���{�����{�́A�����A���ؖ������{�𒆍��̗B��E���@�̐��{�Ƃ��āA���ؕ��a����������A�����ɂ���ē��{���ƍ��ƂƂ��Ă̒����Ƃ̊Ԃ̐푈��Ԃ��I�������A�������тɍ��Y�y�ѐ������̖����܂߂ĉ��������̂ł��邪�A1969�N�ɁA�j�N�\���������a������ƁA�č��̑Β������傫���]�����A���A�ւ̒��ؐl�����a�����{�̏����i���ؖ������{�̒Ǖ��j���̍��ۊ��̕ω�����A���{�ƒ��ؐl�����a���Ƃ̍��𐳏퉻���\�ȍ��ۊ������܂�邱�ƂƂȂ�A�c���p�h���t�ɂ����āA�������𐳏퉻���}���邱�ƂƂȂ����i�I�R�O�f��40�y�[�W�E����87���j�B
�@�C�@���ؐl�����a�����{�̌����Ɠ��{���{�̌����ɂ���
�i�A�j�@�������𐳏퉻�ɂ��ẮA���ؐl�����a�����{�́A���˂Ă��畜���O�����𖾂炩�ɂ��A�������{�����{������邱�Ƃɂ���āA���퉻�������ł���Ƃ���������̂��Ă����B���̎O�����Ƃ́A�@���ؐl�����a�����{�́A�������\����B��̍��@���{�ł���A�A��p�͒��ؐl�����a���̗̓y�̕s���̈ꕔ�ł���A�B���ؕ��a���́A�s�@�ł���A�����ł����āA�j������Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ƃ������̂ł���B
�i�C�j�@���{�����{�Ƃ��ẮA���ؐl�����a�����{�ƍ��𐳏퉻���s������ɓ]�������ȏ�A�����{�𒆍��̗B��E���@�̐��{�ƔF�߂邱�Ƃ͓��R�ł���A���ؐl�����a�����{�����F���邱�Ƃɂ���āA���ؖ������{�Ƃ̊O���W���f�₷��̂͂�ނȂ��Ƃ���������̂�A���������炩�ɂ��Ă��镜���O�����̂�����1����������邱�ƂƂ����B
�@�������A���{�����{�Ƃ��ẮA��2�����y�ё�O�����͓������邱�Ƃ��ł��Ȃ����e�ł������B
�i�E�j�@���Ȃ킿�A��2�����̑�p�̋A�����ɂ��āA���a20�N8���A�䂪������������|�c�_���錾�ɂ����ẮA�J�C���錾�����s������ׂ����Ƃ��������Ă���A�J�C���錾�ɂ́A��p�A�O�Ώ����Ȃǂ����ؖ����ɕԊ҂����ׂ����Ƃ��L�ڂ���A�������p�A�O�Ώ����͒����ɕԊ҂����ׂ����̂ł������B
�@�������A�T���E�t�����V�X�R���a���2��(b)�ł́A��p�A�O�Ώ����ɑ�����{���̂��ׂĂ̌����A�����y�ѐ������̕�����������߂��A���̋A����͒�߂��Ă��Ȃ��̂ŁA�@�I�ɂ́A��p�Ȃǂ̋A����͘A�����ɂ䂾�˂�ꂽ���ƂɂȂ����܂܁A�܂����܂��Ă��Ȃ��Ƃ��킴��Ȃ��i����́A�p�ĕ��Ȃǎ�v�A�������Ƃ��Ă����@�I�����ł���j�B�����āA��p�y���O�Ώ����ɑ��邷�ׂĂ̌����A�����y�ѐ���������������䂪���Ƃ��ẮA���̋A������]�X���邱�Ƃ͂ł��Ȃ��̂ł���i���̖@��802���E����94����10�y�[�W�Q�Ɓj�B
�i�G�j�@���ɁA��O�����̓��ؕ��a���̗L�����ɂ��ẮA�����́A�ȑO����䂪�����������\�Ƃ��鐳�����{�ƔF�߁A���ێЉ�̑����̍������̂悤�ɔF�߂Ă������ؖ������{�Ƃ̊ԂɓK�@�ɒ������ꂽ���ł��邩��A���{�����{���A���̍��@����ے肵�āA���������I�ɔp�����邱�Ƃ́A���ۖ@����A�܂����ؖ������{�ɑ���M�`�ォ���������Ȃ��B���������āA���ؐl�����a�����{�̎咣�𐳖ʂ������邱�Ƃ́A�@�I�ɂ������I�ɂ��s�\�ł������i�I�R�O�f��51�y�[�W�E����87���j�B
�@�������A���ؕ��a����11���́A�u���̏��y�т����⑫���镶���ɕʒi�̒肪����ꍇ�������O�A���{���ƒ��ؖ����Ƃ̊Ԃɐ푈��Ԃ̑��݂̌��ʂƂ��Đ��������́A�T���E�t�����V�X�R���̑����K��ɏ]���ĉ���������̂Ƃ���B�v�ƋK�肵�Ă���B�����ɂ����u�T���E�t�����V�X�R���̑����K��v�ɁA�T���E�t�����V�X�R���a����14��(b)���܂܂�邱�Ƃ́A���ؕ��a���̋c�菑1��������炩�ł���A�����y�т��̍����̓��{���y�т��̍����ɑ��鐿�����́A���ؕ��a����11���ɂ��A�T���E�t�����V�X�R���a����14��(b)�̋K��ɏ]���āA���ƂƂ��Ă̒����ɂ���ĕ�������Ă���B
�@�����āA���ؕ��a���ɂ��푈��Ԃ̏I���┅�����тɍ��Y�y�ѐ������̖��̉����́A������������I���ʂ�L�����x����̏����s�ׂł����āA��������2�x�����e�̏������s�����Ƃ͖@�I�ɂ͕s�\�Ȃ��Ƃł��邵�A���̋K��̓��e�͏���Ɠ����ɍŏI�I���ʂ������A���̌�ɂ�������̑����̗L���ɂ���āA���̌��ʂ��ς�邱�Ƃ��Ȃ����̂ł���B���������āA�䂪���Ƃ��ẮA�������ؖ������{�ɂ���đ�\���ꂽ�����Ƃ̊Ԃ̐푈��Ԃ́A���ؕ��a���1���ɂ���ďI�����Ă���A�������тɍ��Y�y�ѐ������̖��������11�ɂ���ĉ����ς݂ł���Ƃ���������Ƃ��Ă����̂ł���B
�@���̓_�ɂ��ẮA�����v�Y�O���ȏ��ǒ����A���a48�N7��26���A�O�c�@���t�ψ���ɂ����āA�u���{�ƒ����Ƃ̊W�ɂ����āA���̒������\���鐭�{���]���̒��ؖ������{���璆�ؐl�����a�����{�ɏ��F����������Ƃ������j�Ɋ�Â��č�N��������������������킯�ł������܂�����ǂ��A��{�I�ɖ@���W�͓��ؕ��a���ɂ���Ē����Ƃ̊Ԃɂ��ׂď����ς݂ł���A���̑O��Ɋ�Â��Ă�����킯�ł������܂��̂ŁA�V���ɂ܂��@���W�𒆍��Ƃ̊Ԃɒ����������Ƃ������Ƃ͕s�\�ȏ�Ԃɂ������v�i����89����2�y�[�W�j�u�����Ƃ̊Ԃɐ�㕽�a����������܂������������܂��āA���������Ƃ̊Ԃɓ�x���a�����������Ƃ������Ƃ͖@���I�ɕs�\�Ȃ��Ɓv�i������3�y�[�W�j�Ɠ��ق��Ă��邱�Ƃł����炩�ł���B
�i�I�j�@���̂悤�ȓ��{�����{�̌����́A�������𐳏퉻���̍ۂɁA���ؐl�����a�����{�ɑ��āA�`�����Ƃ���ł�����B���Ȃ킿�A���a47�N9��26���̑啽�O���ƕP�Q��O���Ƃ̉�k�ɂ����āA�������ǒ��́A���ؕ��a���ɑ���o���̊�{�I����̑����F�߂���ŁA�푈��Ԃ̏I���y�ѓ��ؕ��a���ɂ��A�u�����������������Ԃɖ@�I�ɐ푈��Ԃ����݂��A���o�����ׂ����������ɂ�ď��߂Đ푈��ԏI���̍��ӂ���������Ƃ���������]�n���Ȃ��\���ɓ��{�������ӂ��邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B�v�A�����̖��ɂ��Ă��A�u�푈��ԏI���̖��ƑS�����l�ɁA���{����p�Ƃ̊ԂɌ����a���i���p�Ғ��F���ؕ��a���j����������A�����ł������Ƃ𖾔��ɈӖ����錋�ʂƂȂ�悤�ȕ\�������������̒��ŗp�����邱�Ƃ͓��ӂł��Ȃ��B���{����Ă̂悤�Ȗ@���I�ł͂Ȃ��\���ł���A�����o���̊�{�I������Q���邱�ƂȂ��A��������������v�i����95����3�y�[�W�A���ʎ��P�u���������������{����Ă̑Β������v�R���ڋy�тP�P���ځj�Əq�ׁA�䂪���̖@�I�Ȍ����𖾂��ɂ��Ă���̂ł���B
�@�����āA�P�O���́A�䂪���̂����錩���ɑ��A�u���������͂�����i���{���̍���͂킩�Ă���Ɓj�������Ă�����̂ŁA���Ƃ��ǂ��Ă��l�������B�v�Ɖ����Ă���i������8�y�[�W�j�A�o�������݂��̗���𗝉�������ŁA�����̗��ꂻ�ꂼ��Ƒ��e�����̂Ƃ��āA�����������������������̂ł���B
�@�i�R�j �������������̕����ɂ���
�@�ȏ�q�ׂ��o�܂́A��T�i�l��������(1)120�y�[�W�ɂ����āA�u���������̌��ߒ��ɂ����Ė��ƂȂ����_�̒��ɁA�푈��Ԃ̏I���┅�����тɍ��Y�y�ѐ������̖�肪����B�����̖��́A���ؕ��a���ɂ��Ă̗����̗���̈Ⴂ�ɋN��������̂ł��邪�A����Ȍ��̌��ʁA�c�A���������́A�����̗��ꂻ�ꂼ��Ƒ��������̂Ƃ��č쐬����Ă���B�v�Ɨv�Ď咣�����Ƃ���ł���B
�@�����ŁA�ȉ��A�������������̑�1�Ȃ���3���y�ё�5���ɂ��āA���{�����{�̗����𖾂炩�ɂ��邱�ƂƂ���B
�@�A�@��1���́A�u���{���ƒ��ؐl�����a���Ƃ̊Ԃ̂���܂ł̕s����ȏ�Ԃ́A���̋������������o�������ɏI������B�v�ƋK�肷�邪�A���́u�s����ȏ�Ԃ́c�I������v�Ƃ́A�䂪�����{�̗��ꂩ��́A�����Ԃ̐푈��Ԃ́A���ؕ��a���ɂ��A���ƂƂ��Ă̒����Ƃ̊ԂŖ@�I�ɏI�����Ă��邽�߁A�����ł����u�s����ȏ�ԁv�Ƃ́A����܂œ��{�ƒ��ؐl�����a���Ƃ̊Ԃɍ������Ȃ������Ƃ�����Ԃ��w���Ƃ������Ƃł���A���������āA�䂪�������ؕ��a��s�@�������ł���Ƃ̕����O�����̑�O���������̂܂��ꂽ�킯�ł͂Ȃ��A�����W�������Ȃ�Ӗ��ɂ����Ă����퉻���ꂽ�Ƃ̓_�ɂ��Ă̓����o���̔F���̈�v��}�������̂ł���B
�@�C�@��2���́A�u���{�����{�́A���ؐl�����a�����{�������̗B��̍��@���{�ł��邱�Ƃ����F����B�v�ƋK�肷�邪�A����͉䂪���������O�����̑�1���������ꂽ���Ƃ��Ӗ�����B
�@�E�@��3���́A�u���ؐl�����a�����{�́A��p�����ؐl�����a���̗̓y�̕s���̈ꕔ�ł��邱�Ƃ��d�˂ĕ\������B���{�����{�́A���̒��ؐl�����a�����{�̗�����\���ɗ������A���d���A�|�c�_���錾��8���Ɋ�Â��������������B�v�ƋK�肷�邪�A����́A��p�̋A���ɂ��Ă̑o���̗���𖾂炩�ɂ������̂ł���B
�@�G�@��5���́A�u���ؐl�����a�����{�́A�������������̗F�D�̂��߂ɁA���{���ɑ���푈�����̐�����������邱�Ƃ�錾����B�v�ƋK�肷��B
�@�䂪�����{�̗��ꂩ�炷��A���ؕ��a���́A���{���ƍ��ƂƂ��Ă̒����Ƃ̊Ԃō��@�L���ɒ������ꂽ���ł����āA�����Ԃ̔������тɍ��Y�y�ѐ������̖��Ɋւ��ẮA���ؕ��a���ɂ���Ė@�I�ɉ����ς݂ł���B�O�L�̑啽�O���ƕP�Q��O���Ƃ̉�k�ɂ����鍂�����ǒ��ƕP�O���Ƃ̂���肩������炩�ȂƂ���A�����o�������҂̗���̈Ⴂ���\������������Ŏ��̂Ƃ��Ă��̖��̊��S���ŏI�I�ȉ�����}��ׂ��A��������������5���̋K��Ԃ�ɂ���v�������̂ł���A���̌��ʂ͓��ؕ��a���ɂ�鏈���Ɠ����ł���B
�@�I�@�ȏ�q�ׂ��悤�ɁA���{�����{�́A�����镜���O�����̑�2�A3�̌��������S�Ɏ��ꂽ�킯�ł͂Ȃ��A�����������o���̗�����\������������œ������������̔��o�Ɏ��������̂ł���B
�@���̓_�ɂ��ẮA���쐴�O�����������y�э����O���ȏ��ǒ����A���a48�N7��26���̏O�c�@���t�ψ���ɂ����āA���m�ɏq�ׂĂ���i����89����7�y�[�W�j�B�������������̑O����5�����u���{���́A���ؐl�����a�����{����N�����u�����O�����v���\���ɗ������闧��ɗ����č��𐳏퉻�̎������͂���Ƃ����������Ċm�F����v�Ƃ��Ă���̂��A�O�����Ɋ��S�ɓ��ӂ����킯�ł͂Ȃ����Ƃ������Ă���B
�@�i�S�j ���������������o��̓��{���{�̌���\��
�@�ȏ�̓��{���{�̌����́A����̐R�c���ɂ����āA�ĎO�����Ă���Ƃ���ł���B
�@�Ⴆ�A���a54�N2��16���A�O�c�@�\�Z�ψ���ɂ����āA�����q���Y�O���ȃA�����J�ǒ������ǒ��́A�u�����Ԃ̐푈��Ԃɂ��܂��ẮA�@�I�Ȍ��n����͓��ؕ��a���ɂ��I�������Ƃ����̂����{�̈�т����l���ł���܂��B�����A�������𐳏퉻�ɍۂ��ẮA������킪���̖@�I����ƒ������̖@�I����̑��Ⴊ����A�������𐳏퉻�Ƃ�����ړI�̂��߂ɁA�o���̖{���Ɋւ����{�I����Ɋ֘A���鍢��Ȗ@�I�����������邽�߂ɁA���������̔��o�������Ă��̐푈��Ԃ̏I���̖����ŏI�I�ɉ�����������ł���܂��B���������āA�����Ԃɐ푈��Ԃ��I�����Ă��邱�Ƃɂ��āA�����������o��A�����o���̗���͊��S�Ɉ�v���Ă���̂ł���܂��B�킪���͏��a27�N�����A�������\���鍇�@���{�����ؖ������{�ł���Ƃ�������ɗ����āA���ؕ��a���ɂ��A�����Ƃ������ƂƂ̐푈��Ԃ��I�����������̂ł���A�푈��Ԃ̏I���̂悤�ɍ��Ƃƍ��ƂƂ̊W�𗥂��鎖���́A�����̓K�p�n��Ɋւ�����������ɂ���Ēn��I����͎Ȃ��Ƃ����_�ɂ��Ă��A�]�����{����������Ă���Ƃ���ł������܂��B����ɑ��āA����Ԃ̖��ԍq��Ƃ��ʏ��W�̂悤�Ȏ����ɂ��܂��ẮA���̌��������ɂ���Ēn��I������Ă�������ł���܂��B���ؕ��a���͓������𐳏퉻�̌��ʂƂ��Ă��̑����̈Ӌ`�͎����A�I�����܂������A������1���ɂ��푈��Ԃ̏I���Ƃ��������I���ʂɉe����^������̂ł͂���܂���B�v�i����96����45�y�[�W�j�Ɛ������A���A�������ɂ��Ă��u�T���E�t�����V�X�R���a����14����(a)��1�̋K��ɂ���āA�A�����́A���{�����̐��Y���A�ɂ�锅�����錠��������킯�ł������܂����A�������ؕ��a���ɂ��܂��āA���̓����̒��ؖ��������̖����̌�������������Ƃ������ƂŁA�킪���̗���Ƃ������܂��ẮA���̔����������̖��͂���ŏ�������Ă���Ƃ����̂��l�����ł������܂��B�v�i��46�y�[�W�j�Ɛ������āA���{���{�̗���𖾂炩�ɂ��Ă���B
�@�i�T�j ����
�@�ȏォ�疾�炩�Ȃ悤�ɁA�����Ԃɂ����Ă͌l�̐������̖�肪��������Ă��Ȃ��Ɖ�����͎̂����ł���B���ؕ��a���11���y�уT���E�t�����V�X�R���a���14��(b)�ɂ��A���������̓��{���y�т��̍����ɑ��鐿�����́A���ɂ���ĕ�������Ă���B��������������5���ɂ����u�푈�����̐����v�́A���������̓��{���y�т��̍����ɑ��鐿�������܂ނ��̂Ƃ��āA���ؐl�����a�����{�����́u�����v���u�錾�v�������̂ł���B���������āA���̂悤�Ȑ������ɂ��ẮA���{���y�т��̍����́A����Ɋ�Â������ɉ�����ׂ��@����̋`���͏��ł��Ă���̂ŋ~�ς����ۂ���A�ٔ���̐������A�F�e�����]�n���Ȃ����Ƃ͖��炩�ł���B
�@�U�@��T�i�l�̎咣�����ۏ펯�Ƃ��������ꂽ���̂ł���Ƃ̍T�i�l��̎咣�ɂ���
�@�i�P�j �T�i�l��̎咣
�@�T�i�l��́A��T�i�l�́u��̑��ɌW�锅�����тɍ��Y�y�ѐ������̖��ɂ��ẮA�T���E�t�����V�X�R���a��̑��Ԃ̕��a���y�т��̑��֘A�����ɏ]���Đ����ɑΉ����Ă��Ă���Ƃ���ł���A�����
��̓������Ƃ̊Ԃł͖@�I�ɉ����ς݂ł���v�Ƃ̎咣�ɂ��āA���{���{�ɂ�����I�Ŝ��ӓI�ȉ��߂ł���A�܂��A���ۏ펯�Ƃ��������ꂽ���̂ł���|�咣����i�T�i�l���3��������59�y�[�W�j�B
�@�i�Q�j��T�i�l�̔��_
�@�������Ȃ���A�ȉ��ɏq�ׂ�悤�ɁA�č��̍ٔ����ɂ����Ă��A��̑��ɌW�锅�����тɍ��Y�y�ѐ������̖��ɂ��ẮA�T���E�t�����V�X�R���a���ɂ��@�I�ɉ����ς݂ł���|�̔������d�˂ďo����Ă���A��T�i�l�̌������A���ۏ펯�Ƃ����ׂ������ł��邱�Ƃ͖��炩�ł���B
�@�A�@��T�i�l���A��T�i�l��������(1)122�y�[�W�Ŏw�E�����悤�ɁA�����l���܂ނ����錳�]�R�Ԉ��w15�����A���{����퍐�Ƃ��āA�R�����r�A���ʋ�A�M�n���ٔ����ɒ�N�������Q���������i�ׂɂ����āA���ٔ����́A2001�N�i����13�N�j10��4���A�u�t�B���s�����܂ޘA�����A�����y�ъ؍����Ƃ̐푈�������̉����̗��j�͕��G�ł���B1951�N�̓��{�Ƃ̕��a���́A�S�Ắw�푈���s���ɓ��{���y�т��̍������Ƃ����s�ׂ��琶�����A�����y�т��̍����̑��̐����x�����������̂ł���B�c�c���Ɋ؍��y�ђ����Ƃ̊Ԃ́A�푈���������������邽�߂̕ʓr�̍��ӂ̌����s�����B��������N���Ă���w�Ԉ��w�x�ɂ��Ă̐����́A���ɂ����̏�ɂ����Ė����I�ɂ͌��y����Ȃ������̂ł��낤���A�푈��ɒ������ꂽ��A�̏���{�ɑ���S�Ă̐푈�������̉�����ړI�Ƃ��Ă������Ƃ͖��m�ł���B�����͔����I�߂���ɁA�����̋c�_���ĊJ���悤�Ƃ��Ă��邪�A�{�@��͂��̓K���ȏ�ł͂Ȃ����Ƃɋ^��̗]�n�͂Ȃ��B����E����̓��{�Ƃ̊Ԃ̍��ӂ����{�Ɛ��{�Ƃ̃��x���Œ������ꂽ�悤�ɁA�w�Ԉ��w�x�̐��������{�ԂŒ��ڂɏ��������ׂ��ł���B�v�Ɣ������A������̑i�����p�������i����97���A�������̉���ɂ��A�R�莡�V�u�A�W�A�l���Ԉ��w�̑Γ��{���{�i�ׂɊւ���č��A�M�n�ٔ����v����98���j�B
�@���̔����ɑ��āA�������̌�����́A�T�i���Ă������A����15�N6��27���A�R�����r�A���ʋ�̍T�i�R�ٔ����́A������̑i�����p���������R�������ێ������i����99���j�B
�@���̍ٔ��ő��_�ƂȂ����̂́AAltmann��Republic of Austria�����̑�9����T�i�ٔ����������A�u�I�[�X�g���A�l�́A�����Ȃ����_���l���Y�̈�@�Ȍ��p�����ɑ��u���b�Ɨ���v�̖��Ƃ��ĖƏ�����������ł��낤�Ƃ������ҁA������m��I���҂������Ƃ͂��肦�Ȃ������ł��낤�v�i��8�y�[�W�j�Ƃ��āA�O���匠�Ə��@1605��(a)(3)�̎匠�Ə��̗�O�K��i�u���ۖ@�Ɉᔽ���Đڎ����ꂽ���Y�Ɋւ��錠�������ƂȂ��Ă���ꍇ�ł����āA���Y���Y���̖��͓��Y���Y�ƌ������ꂽ���Y���A���̊O�������O�����ł������Ɗ����Ɋ֘A���āA���O���ɏ��݂��Ă���ꍇ�A���́A���Y���Y���̖��͓��Y���Y�ƌ������ꂽ���Y�����̊O���̋@�ւɂ���ď��L�Ⴕ���͉^�p����A���A���̋@�ւ����O�����ŏ��Ɗ����ɏ]�����Ă���ꍇ�v�j���A1930�N���1940�N��̃h�C�c���{�ƃI�[�X�g���A���{�̍s�ׂɑk�y���ēK�p���꓾��Ɣ����������Ⴊ�A���̎����ɓK�p�����ׂ����Ƃ����_�ł������B
�@���̑��_�ɂ��A����15�N6��27���̑O�L�R�����r�A���ʋ�T�i�R�ٔ����́A�u��9����T�i�ٔ����̔����́A�ܘ_�A���ٔ������S�����Ȃ��B���ٔ�����Altmann�����̔����ɏ]�����ۂ��ɂ�����炸�A���{�ƘA�����ɂ���ď������ꂽ1951�N�̕��a���̂��߁A���ٔ����͓������̗��R�Â����{���i�ׂɓK�p�����Ƃ͔F�߂Ȃ��B3
U.S.T. 3169�B�A�����J���O�����@�쏕���҂Ƃ��ĕ٘_��ӏ��ŏq�ׂĂ���悤�ɁA���a���́u��2�����E���̐��s���琶�������{�ɑ��邷�ׂĂ̐������́A���{�Ԃ̍��ӂ�ʂ��ĉ��������ׂ��ł���Ƃ����A�����J���O���̊O�𐭍�̌����̌����Ă���v�B���ٔ����́A���a���2�����E��킩�琶���������A�����J���O���i�܂��͂����ꂩ�̏������j�̍ٔ�����������点�邱�ƂȂ���������Ƃ����������̈Ӑ}�����Ă���Ƃ����_�ɓ��ӂ���B������ɂ��Ă��A�A�����J���O�����������a���̉��߂͍����I�ł���BSumitomo
Shoji Am. Inc.��Avagliano�����A���O������W��457���A178�y�[�W�A184-185�y�[�W�i1982�N�j�i�u���a���̋K��̌��Ǝ��s��S�����鐭�{�@�ւɂ���ĕ��a���̋K�肪�L����Ƃ��ꂽ�Ӗ��́A�m��I�Ȃ��̂ł͂Ȃ����A�傫�ȏd�݂�^������v�j�B
�@���a����14���́A���{�ɂ�鐿���̑��ݕ�������ъe�A�����̊NJ��̉��ɂ�����{�̎��Y����������A�����̌����ƈ��������ɁA�u�A�����̂��ׂẮc�c�������A�푈�̐��s���ɓ��{���y�т��̍������Ƃ����s�����琶�����A�����y�т��̍����́c�c�������v���I�ɕ������Ă���B���a���͂���ɁA���{�����̍��A�������Ƃ��̍����̐푈�֘A��������{�����ۂɉ��������̂Ɓu����̖��͎����I�ɓ���̏����Łv�A���Ȃ킿���{�Ԃ̍��ӂɂ��i��26���Q�Ɓj��������ƋK�肵�Ă���B1952�N4��28���̓��{���ƒ��ؖ����Ƃ̊Ԃ̕��a���A138
U.N.T.S. 3�Q�ƁB�܂��A1965�N6��22���̍��Y�y�ѐ������Ɋւ�����̉������тɌo�ϋ��͂Ɋւ�����{���Ƒ�ؖ����Ƃ̊Ԃ̋���Q�ƁB���̌��ʁA�A�����́A���ꂼ��̍��̍����̐�������������A���̍��̍����̐������͐��{�Ԍ��ɂ���ĉ�������Ƃ��������Ȑ����\���������߁A���{�͑�2�����E��킩�琶�����������ɂ��ĘA���������A�����������͊؍������ɂ���ăA�����J���O���̖@��ɂ����đi�����邱�Ƃ�\�����邱�Ƃ͂ł��Ȃ������B�O�𐭍�̖��Ƃ��āA����ɂ����ăA�����J���O�������{�ɑ���A�����J�����̂��ׂĂ̐�������������A�����ɂ����ăA�����J�����łȂ��҂��A�����J���O���̍ٔ����œ��{�ɑ��đi�葱���s�����Ƃ�F�߂�̂͊m���Ɋ�ł���B�h�C�c�܂��̓I�[�X�g���A�Ƃ̊Ԃł͗ގ��̏��͑��݂����A���������ē����悤�Ȋm��I���҂͂Ȃ����߁AAltmann�����̈ӌ��͖{���i�ׂɊW�Ȃ��B�v�i��8�A9�y�[�W�j�Ɣ������AAltmann�����Ɋւ���T�i�R�����͖{���ɓK�p����Ȃ��Ƃ����B
�@���̍T�i�ٔ����̔����́A�h�C�c���䂪���̏ꍇ�ƈ���āA�A�����Ƃ̊Ԃŕ��a����������Ă��Ȃ������𐳊m�ɔF��������ŁA�䂪���ɂ��ẮA�T���E�t�����V�X�R���a���A���ؕ��a��ɂ���āA��̑��ɌW�锅�����тɍ��Y�y�ѐ������̖�肪�@�I�ɏ�������Ă��邱�Ƃ����Ă���B
�@�C�@�܂��A���a���ɂ�鍑�ƊԂ̐�㏈�����A�������̖��̊��S���ŏI�I�����ł��邱�Ƃ́A�ߎ��A�č��ɂ����āA���풆�ɁA�����{�R�̕ߗ��ƂȂ������č��R�l�炪���{��Ƃ̎��Ə�ŋ����J��������ꂽ�Ǝ咣���āA���{��Ƃ�퍐�Ƃ��āA�č����̍ٔ����ɒ�i���������̑��Q���������i�ׂɂ����āA�č����{�y�ѓ��{�����{�������������ɂ���Ă����炩�ɂ���Ă���B
�@���̑i�ׂ́A1999�N7��28���A�J���t�H���j�A�B�Ŏ{�s���ꂽ�J���t�H���j�A�B�����i�ז@354.6���i�ȉ��u���B���i�@354.6���v�Ƃ����j�Ɋ�Â��āA�A�����̌��ߗ����тɃt�B���s���A�؍��y�ђ����̖��Ԑl�炪�����ƂȂ�A���{��Ƃ�퍐�Ƃ��Ē�N���ꂽ�i�ׂł���A���B���i�@354.6���́A���풆�Ƀi�`�X�������͂��̓������̎x�z���ŋ����J��������ꂽ�҂��A���̘J�����s��ꂽ��Ɩ��͂��̎q��m���ɑ��āA2010�N12��31���܂ł̊ԁA���Q���������i�ׂ��J���t�H���j�A�B�ٔ����ɒ�N�ł���ƋK�肵�Ă����i���̑S���̓��{���ɂ��ẮA�˒ˉx�Y�u���⏞���ɓ��ݍ��ޕč��v�@�w�Z�~�i�[538��76�y�[�W�j�B
�@�č������Ȃ́A2000�N(����12�N)8��17���A�k���J���t�H���j�A�n��E�T���E�t�����V�X�R�x���A�M�n���ٔ����ɑ��A�u���Q�W�������v�i����53���j���o�����Ƃ���ł��邪�A���̈ӌ����ɂ����āA�č����{�Ƃ��āA�T���E�t�����V�X�R���a���Ɋւ��āA�u1951�N�̓��{���Ƃ̕��a���̖ړI�́A���{���̎匠�����A���{�������Y��`�̋��Ђɑ��Ė����`�I�s��o�ςƂ��ċ@�\����悤�ɂ��A���{���̐��{�y�э����ɑ��邷�ׂĂ̐��������������A�A�����y�т��̍����ɑ�����{�̂��ׂĂ̐��ݓI�Ȑ��������������邱�Ƃł������B�{�ٔ����ŌW�����̑i�ׂɂ����Č������咣���Ă���悤�ȏ����̐푈�������͂��̑��̐푈�֘A�̐������̉\������c���Ă����Ƃ�����A�����̖ړI�͂�������B�����邱�Ƃ��ł��Ȃ������ł��낤�B���̗��R����A���́A���ɕʒi�̒�߂�����ꍇ�������A����E��풆�̍s�ׂ��琶�������{���y�т��̍����ɑ���A�����y�т��̍����̂��ׂĂ̐��������������悤�ɓ��ɋN�����ꂽ�̂ł���B�v�Ƃ̈ӌ����������i�O�f�č����{�u���Q�W�������v�M��26�A27�y�[�W�A����53���j�B�����A���{�����{���A���i�ׂɂ����āA2000�N(����12�N)8��8���A�u���č��ߗ����ɂ����{��Ƃɑ���i�ׂɊւ�����{�����{�̌����v�Ƃ��āA�č����{�Ɠ��l�̌������������Ƃ���ł���i2000�N8��8���t�����č��ߗ����ɂ����{��Ƃɑ���i�ׂɊւ�����{�����{�̌����E����60����)�B
�@����痼�����{�̌������āA���ٔ����́A���N9��21���ɁA������̑i�����p�����锻�����������i����61���j���A���̔����̒��ŁA�T���E�t�����V�X�R���a���14��(b)�Ɋւ��A�u���{�Ƃ̕��a���́A�{���i�ׂɂ����Č������咣���Ă��鐿���̂悤�ȏ����̐������ɂ������ɂ����āA�����̊��S�ȕ⏞�������̕��a�ƈ����������̂ł���B���j�͂��̎���������ł��������Ƃ��ؖ����Ă���B�����Ɍo�ϓI�ȈӖ��ɂ����錴���̋��ɑ��銮�S�ȕ⏞�́A���ߗ�����ё��̖����̐푈�����҂ɑ��Ă͋��ۂ��ꂽ���A���R�ȎЉ��т�蕽�a�Ȑ��E�ɂ�����ނ玩�g�̌v��m��Ȃ������̌b�݂Ɣɉh�́A�����Ƃ������ɑ��闘���̎x���ƂȂ��Ă���B�v�Ɣ������Ă���i����61���ؖM��12�؈�W�j�B
�@�܂��A���ٔ����́A���̌�A���̌�����̑i����S�ċp�����锻�������������߁A������͘A�M�T�i�ٔ����ɍT�i�������A2003�N�i����15�N�j1��21���A�����ق́A28���̓��{��Ƃ�퍐�Ƃ���i�ׂɂ��āA���B���i�@354.6���́A�A�M���{�̔r���I�O��������N���ጛ�ł���|��������Ȃǂ��āA������̍T�i��S�ċp�����锻�����������i����62���j�B
�@����ɁA�������̌�����́A�A�M�T�i�ٔ����̏�L������s���Ƃ��āA�A�M�ō��ٔ����ɏ㍐�������A�A�M�ō��ٔ����́A2003�N�i����15�N�j10��6���A�㍐�����p�����i����15�N10��7���t�������V���[���A�����t�����{�o�ϐV���[���A�����t�������V���[���E����100���j�B
�@�E�@����ɁA�J���t�H���j�A�B�ٔ����ɌW�����Ă��������̂����A���ĕ��ߗ��������ƂȂ�A�퍐�O�H�}�e���A���ق����퍐�Ƃ��Ē�N���ꂽ�����J���ɂ�鑹�Q�������������ɂ��āA�J���t�H���j�A�B�T�i�ٔ����́A2003�N�i����15�N�j2��6���A�A�����̍����̐������̓T���E�t�����V�X�R���a���14��(b)�ɂ���ĉ����ς݂ł���Ƃ��āA������̑i�����p�����锻�����������i����101���j�B
�@�V�@���_
�@�ȏ�q�ׂ��悤�ɁA�T�i�l��̎咣�́A���������T�i�l�̌������ȉ��������̂��A�S�����R�̂Ȃ����̂ł��邾���łȂ��A�����Ԃ̐�㏈���̘g�g�݂�����咣�ł����āA�����ł���B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�ȁ@��

|