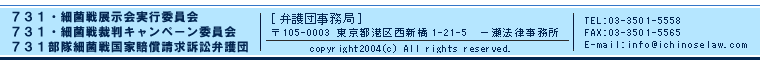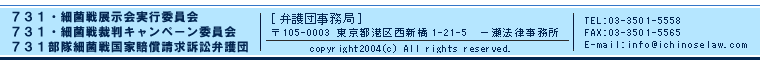|
|
2002年(ネ)第4815号謝罪及び損害賠償請求控訴事件
控訴人(一審原告) 程 秀 芝 外179名
被控訴人(一審被告) 日 本 国
第4準備書面
2004年3月11日
東京高等裁判所第2民事部 御中
控訴人ら訴訟代理人
弁護士 土 屋 公 献
同 一 瀬 敬 一 郎
同 鬼 束 忠 則
同 西 村 正 治
同 千 田 賢
同 椎 野 秀 之
同 萱 野 一 樹
同 多 田 敏 明
同 池 田 利 子
同 丸 井 英 弘
同 荻 野 淳
同 山 本 健 一
被控訴人の平成15年9月30日付け準備書面に対する反論
第1 同書面「第1 ハーグ陸戦条約3条の文理解釈」について
1 被控訴人は,ハーグ陸戦条約2条が「本条約の規定は・・・締約国間にのみ之を適用す」と規定している点を根拠に,同条約3条が国家間の国家責任を定めたもので,個人の損害賠償請求権を定めたものではないと主張する。
2 しかしながら,本条約2条は,交戦国が条約締約国である場合のみにこれを適用し,非締約国には適用しないという,いわゆる「総加入条項」である。
つまり,本条はあくまで本条約が適用される国家の範囲を定めているに過ぎず,本条約の適用を受ける国家と人民との関係とは明らかにレベルを異にする内容の規定である。
本条約むしろ,被控訴人も上記箇所で触れているように,前文第2段において,「交戦相互間ノ関係及人民トノ関係ニ於テ、交戦者ノ行動ノ一般ノ準縄タルヘキモノトス」としているのであり,人民との関係で適用があることが明らかである。
第2 ハーグ陸戦規則52条3項に基づく住民の直接請求について
1 被控訴人は,占領時の徴発にかかる住民等への金員の支払いを規定したハーグ陸戦規則52条3項は,住民等への支払い義務であるとしても,住民等の支払い請求権ではなく,住民がその利益を侵害されたとしても,国際法上訴の救済を求める手段・制度が設けられていないので,直接請求は認められないと主張する。
2 しかし,まず「国際法上訴の救済を求める手段・制度が設けられていない」との主張は,「国際裁判所」における手続きを想定すればその様にみえるが,戦時占領時の財産権等に関する訴訟は,国際法では伝統的には国内裁判所において行われてきたのであって,被控訴人の主張は,伝統的に国内裁判所が国際法を解釈・適用してきた長い歴史を看過した誤った主張である。
すなわち,占領下の押収や徴発に関する戦時国際法(ハーグ陸戦規則52条,53条)に交戦国が違反したとして財産所有者たる私人がその還付や賠償を求め,裁判所がこれを認めた主要国裁判所の事例は多数存在し,国際法の代表的な判例集(国内裁判所が国際法を適用した判例を含む)に収録されている。
たとえば,次のような判例がある。
① ドイツ占領軍のために貸した馬が、その後も返還されず、その後イギリス占領軍、次いでデンマーク政府へと引渡されたため、元の所有者が所有権を主張した事案で、デンマークの西控訴裁判所は1947年、訴えを認め馬の返還を命ずる判決を下した。
すなわち,「ハーグでの第2回国際平和会議で採択された陸戦規則は、53条第2段において、占領軍は、私人に属するものであっても、とりわけ輸送手段を押収することができると定めている。しかし、本条は、そのように押収された財産は、和平の締結時には還付され、また損害賠償が定められなければならないと付け加えている。ドイツ占領軍による馬の処分が、上述の規則に従って行われた押収といえるかどうかは別にして、控訴人の所有権がそれによって失われたとみることはできない」とした(Andersen v.Christensen and the State Committee for Small Allotments,Annual Digest of Public International Law Cases,Year 1947,1951, pp.275-276.)。
② ドイツ軍がオランダを占領中、ドイツの国境税関監視員が、現金支払いも領収証の発行もせずに2台のオートバイを押収した事案につき、オランダの特別破毀院は1950年、たとえ輸送手段として押収の対象になるとしても、ハーグ条約53条第2段が遵守されなければならないとして、押収を違法と認める判決を下した(In re Hinrechsen,H.Lauterpacht ed., Annual Digest of Public International Law Cases,Year 1949,1955,pp.486-487)。
③ ドイツ軍がノルウェーを占領中、ドイツ当局が原告所有の自動車を徴発し、領収証の発行も賠償の支払いもなされなかった事案につき、ノルウェーの控訴裁判所は1948年、ハーグ条約52条による徴発が有効であるためには現金の支払いか領収証の発行がなければならないとして、原告の所有権を認めた(Johansen v. Gross,Annual Digest of Public International Law Cases, Year1949,1955,pp. 481-482)。
④ ドイツ軍がフランスを占領中、フランスの会社である原告から、きわめて不十分な額の支払いをもって軍用物資が押収され、後にフランス政府機関により敵国財産として没収され売却されたため、原告が代金の払い戻しを求めた事案で、フランス破毀院は1957年、ドイツの行為は略奪として違法であり、原告は合法的な所有者として完全な賠償を得る権利があると判示した(Etablissements Bracq Laurent S.A.v.Service Central des Domaines,International Law Reports 1957, 1961,pp.978-979)。
このように,戦時占領時の財産権等に関する訴訟は,国際法では伝統的には国内裁判所において行われてきたのであり,現にそこでは,ハーグ陸戦規則52条や53条に基づいて,被害者住民による加害国に対する直接請求が認められているのである。
3 以上の通り,国際法上の問題に対する管轄権は,「必ずしも国際裁判所その他の国際機関に専属するわけではな」く、「いずれかの国の国内裁判所であっても、その国内法により国際法上の問題(たとえば、戦争犯罪または集団殺害罪に対する刑事責任の追及)に対する管轄権が与えられ、かつ国際法に準拠してこの管轄権を行使している限りは、国際管轄権の行使を分担しているとみなすことができる。」「したがってこの場合は、国内裁判所によっても個人の国際法上の権利義務の実現と執行を担保できることとなり、個人の権利能力取得の条件を充たすのである」(山本草二『国際法(新版)』有斐閣、1994年、166頁)ということができるのである。
このようにしてみると,ハーグ陸戦規則52条3項は住民等の支払い請求権を認めたものではなく,住民がその利益を侵害されたとしても,国際法上訴の救済を求める手段・制度が設けられていないので,直接請求は認められないとの被控訴人の主張は明らかに誤っているといわなければならない。
第3 同書面「第2 ハーグ陸戦条約3条の起草過程」について
1 被控訴人は,ハーグ陸戦条約が締結された1907年当時の国際法における個人の位置づけは「個人は国際法の客体である」という公理が支配していたのであって,個人が加害国家に対し損害賠償請求権を認められるということは考えられないと主張する。
2 しかし,ハーグ陸戦条約3条は,同条約付属規定に違反した国家に損害賠償責任を負わせた規定であるが,当時から,これが損害を受けた個人に賠償を与えることも認める規定であるとする見解が有力であった。
その例として,戦前におけるフランスの著明な国際法学者であるメリニヤック及びフォーシーユの見解がある。
すなわちメリニヤックは,「原則として、訴えを起こす唯一の資格を有しているのは、損害を与えた行為の被害者である」(A. Merignhac,"De la sanction des infractions au droit des gens commises, au cours de la guerre europeenne, par les empires du centre",24 Revue general de droit international public (1917),pp.8-9)と述べ,
また,フォーシーユは,「陸戦の法規慣例に違反した交戦当事国に対し、その不法行為の被害者に対し賠償する(indemniser les victimes)義務を課した1907年10月18日のハーグ条約3条の国際責任は、個人の財産に対して加えられた損害と同様、身体に対して加えられた損害にも適用される」(P. Fauchille, Traite de droit international public,tome II,1921,p.314)と述べている。
さらに,日本の主要な国際法学者では、1931年の上海事変に関連して、信夫淳平は、「支那側及び第三国人の蒙りたる、又は蒙りたると称する、財産損害」につき次のように論じている。
「1907年の陸戦法規慣例條約第3条には、『前記規則ノ條項ニ違反シタル交戦當事者ハ損害アルトキハ之ガ賠償ノ責ヲ負フベキモノトス。交戦當事者ハ其ノ軍隊ヲ組成スル人員ノ一切ノ行為ニ付責任ヲ負フ』とある。前記規則とは同條約に附属する所の陸戦法規慣例規則を指す。故に損害あるに方りて賠償の責を負ひ、將た交戦國政府がその軍隊の組成員の行為に付責任を負ふのは、専ら陸戦法規慣例規則の規定する諸事項の違反行為である。けれども、その故を以て同規則以外の交戦法規の違反に就ては全然責任を負ふに及ばずして可なりといふ結論を伴ふものではない。凡そ國際法たると国内法たるとを問はず、苟も社會の掟則に違反すれば、之に就て責を負ふべきものたることは総ての場合を通じて一貫する原則である。交戦法規はその陸戦に係ると、海戦に係ると、將た空戦に係るとを問はず、総てその違反者に對して之が責任の負擔を要求する。たゝ゛陸戦法規慣例條約は、その凡例として同條約附属の陸戦法規慣例規則の違反に関し特に責任の帰着を明指したまでゝある」そして,「交戦國の違法行為に由りて損害を受けたと認むる私人は、その交戦が如何なる原因に基して起つたものにもせよ、當然救済を求むるの権利がある。」と論じているのである(信夫淳平『上海戦と国際法』1932年、丸善、357-358頁)。
3 以上のように,ハーグ陸戦条約が採択された当時から、いわゆる戦間期においてさえ、同条約3条について、このような有力な見解が内外に存在していた。
第4 ハーグ陸戦条約3条についての赤十字国際委員会の見解に関連して
1 被控訴人は,ハーグ陸戦条約3条についての赤十字国際委員会の1952年の見解も被控訴人の解釈と同様であるとする。
2 しかし,1977年に採択された1949年ジュネーブ条約の第一追加議定書について赤十字国際委員会が発行した注釈書は,条約で保護された者(捕虜,文民など)の状況に不利に影響するような別の取り決めを締約国が締結することを禁止した1949年ジュネーブ4条約の規定について以下のように述べている。
「平和条約の締結にあたっては,当事国は原則として,戦争被害一般に関する問題及び戦争開始に対する責任に関する問題を,適当と考える方法で処理することができる。他方で,当事国は,戦争犯罪人の訴追を控えることや,ジュネーブ諸条約及びこの議定書の規則の違反の被害者が賠償を受ける権利を否定することはできない」(Commentary,p.1055)。
3 さらに,1980年代末から90年代に掛けて,国連人権委員会では,重大な人権侵害の被害者が救済を受ける権利について特別報告者が任命されて国際法の原則に関する検討が進められた,2000年には,「国際人権法及び人道法違反の被害者が救済及び補償を受ける権利についての基本原則及びガイドライン」が人権委員会に提出されるにいたっているが,国連人権高等弁務官事務所が開催した本原則の検討会議で,赤十字国際委員会の代表は,ハーグ陸戦条約3条は被害者への賠償を国家に要求する者であるとの見解を明確に発言しているのである。(E/CN.4/2003/63,paras.50,118)。
4 被控訴人の主張は、このような戦後の国際法理論の明確な展開と確立を無視して、一世紀前の国際法における個人の国際法主体性の認識のみから結論を導いており、現在の時点で被害者に与えられる救済が問われている本裁判において採用されうるものではない。
ハーグ陸戦条約3条は、違反行為により被害を受けた当事国のほか、被害者個人の救済をも目的としたものと解することができるから、細菌戦による同条約違反の事実が明らかに認められ、国家間による適切な解決が図られていない以上、被害者個人に損害賠償が与えられることは、国際法上何ら妨げられないばかりか、同条の趣旨に合致するものと考えられるのである。
以 上

|