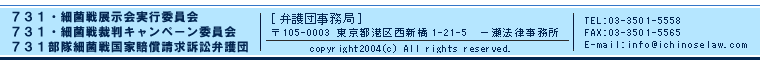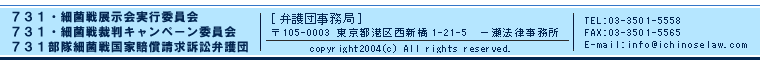2002年(ネ)第4815号謝罪及び損害賠償請求控訴事件
控訴人(一審原告) 程 秀 芝 外179名
被控訴人(一審被告) 日 本 国
第5準備書面
2004年3月18日
東京高等裁判所第2民事部 御中
控訴人ら訴訟代理人
弁護士 土 屋 公 献
同 一 瀬 敬 一 郎
同 鬼 束 忠 則
同 西 村 正 治
同 千 田 賢
同 椎 野 秀 之
同 萱 野 一 樹
同 多 田 敏 明
同 池 田 利 子
同 丸 井 英 弘
同 荻 野 淳
同 山 本 健 一
第1章 行政不作為に関する被控訴人主張に対する反論
第1 本件細菌戦の被害発生と被控訴人の作為義務の成立
1 被控訴人の主張
被控訴人は、「先行行為に基づき作為義務が生じ、不作為の違法行為が認められる場合」について、レールの置き石行為に関する最高裁昭和62年1月22日第一小法廷判決(民集41巻1号17頁。以下、「最高裁昭和62年判決」という)を判断基準として示し、控訴人らの行政不作為義務違反の主張に反論しているが、全く失当である。
以下、控訴人の反論を詳述する。
2 反論(1)ー細菌戦による疫病発生の危険は継続的危険である
レールの置き石行為に関する最高裁昭和62年1月22日第一小法廷判決(判例時報1236号66頁)の事案は、中学生のいたずらによって、レール上に置き石がされたために生じた電車の脱線転覆事故について、自らは置き石をしなかった仲間の不法行為責任が問われたものである。
上記最高裁判決は、当該置き石事案における不作為義務の根拠について、「重大な事故を生ぜしめる蓋然性の高い置石行為がされた場合には、その実行行為者と右行為をするにつき共同の認識ないし共謀がない者であっても、この者が、仲間の関係にある実行行為者と共に事前に右行為の動機となった話合いをしたのみでなく、これに引き続いてされた実行行為の現場において、右行為を現に知り、事故の発生についても予見可能であったといえるときには、右の者は、実行行為と関連する自己の右のような先行行為に基づく義務として、当該置石の存否を点検確認し、これがあるときにはその除去等事故回避のための措置を講ずることが可能である限り、その措置を講じて事故の発生を未然に防止すべき義務を負うものというべきであり、これを尽くさなかったため事故が発生したときは、右事故により生じた損害を賠償すべき責任を負うものというべきである。」と判示している。
しかし、本件細菌戦の事案は,上記の最高裁置き石事件のように結果(脱線等)が発生すれば危険が現実化し,あとは結果との相当因果関係だけが問題になるケースとは、全く事実関係を異にする。
すなわち本件細菌戦の事案では、ペスト等への罹患やそれによる死亡の結果がある被害者に発生しても,それで結果発生の危険は消滅するものではなく、その後も半永久的に細菌による疫病発生の具体的な危険が継続する。現に、現在でも,本件細菌戦被害地では、自然界に残った細菌兵器として用いられたペスト菌などの細菌により,疫病発生の危険は続いている。
このように本件細菌戦の事案は,被控訴人が援用するレールの置き石行為に関する最高裁判決とは全く事案を異にするものであり、被控訴人の上記は事実関係の理解を誤ったものであり全く失当である。
3 反論(2)ー被控訴人は細菌戦被害者に対し「細菌戦の加害事実を調査し真相を公表する被害救済措置義務」を負っている
控訴人らが本件細菌戦に関して主張している行政上の作為義務の根拠は、次のような細菌戦における被害の特質に根ざすものであり、被控訴人の主張は控訴人らの主張を曲解したものである。
本件細菌戦は、そもそも疫病の流行を利用し非戦闘員である中国住民に被害を及ぼすことを意図して実行されたものであるが、被害者側が当該疫病が細菌戦によるものであることを知らされない点で、他の通常の戦争行為とは著しく異なる特質を持っている。
このために細菌戦の被害者は,細菌戦による被害であるという事実すら知らないままでいることが通常である。
本件控訴人らは、研究者の細菌戦に関する研究や元731部隊の隊員であった者らの真相告白などの証拠によって本件裁判を提訴したのであるが、肝心の加害者の立場にある被控訴人が細菌戦の事実を今日まで隠蔽してきたため、控訴人らは現在でも国際法違反の細菌戦によって無惨に殺されたという事実すら公式には認められない状態に放置されている。
本件細菌戦が国際法違反の史上類例のない残虐な非人道的的戦争犯罪行為であるという性質に照らせば、被控訴人は、「細菌戦の加害事実を調査し真相を公表する被害救済措置義務」を負っているというべきである。
被控訴人が上記の行政上の作為義務違反は、控訴人らの人間としての尊厳を新たに侵害するものであり、控訴人らはかかる被控訴人の行政不作為という二次的不法行為によって苦しみを倍化されるという新たな被害を被っている。
控訴人らは、第1準備書面以来、このような意味で被控訴人(内閣)が,行政権を行使して、先行行為による被疑者の真の救済をはかるべき行政上の作為義務を負いながらこの作為義務に違反していることを新たな不法行為として主張しているのである。
以上に述べたとおり、控訴人らが主張している被控訴人の「細菌戦の加害事実を調査し真相を公表する被害救済措置義務」違反の主張に照らせば、被控訴人が引用する最高裁昭和62年1月22日第一小法廷判決の事案は、控訴人らが主張する本件細菌戦の事案とは全く異なるものであり、被控訴人の主張が失当であることは明かである。
4 念のため付加すれば、控訴人らが主張している被控訴人(内閣)の行政不作為責任は,細菌戦当時に限定したものではないから,国家無問責論を論じる余地はなく,国家賠償法が適用されることは明かである。
なお被控訴人は「控訴人らの先行行為による作為義務を基礎とする国家賠償責任の主張は、国家無答責の時代における権力的行為による不法行為責任を形を変えて主張しているにすぎない」と主張しているが,かかる主張は本細菌戦の事案の特質を理解しない浅薄な言い分である。このような被控訴人の言葉の中にも、被控訴人が自らの細菌戦の本質への無理解や理解の浅薄さと根源における不誠実さが露呈されている。
第2 公務員の職務上の義務規定のない本件細菌戦被害救済義務と条理に基づく作為義務の成立
1 被控訴人の主張
被控訴人は、「国賠法1条1項は国又は公共団体の代位責任を規定したものであるから、公務員の行為を検討することなく、国自身が先行的に義務を負担することはあり得ない」(被控訴人準備書面(1)91頁)と主張し、「これは確立した判例の立場であ(最高裁昭和60年11月21日判決・民集39巻7号1512ページ等)」るという。
上記被控訴人の主張によれば、公務員個人や加害行為を特定できない場合には、国家賠償請求を認容する前提に欠けることになる。
しかし、公務運営上の瑕疵に起因して損害が発生していることが明らかであるにもかかわらず、かかる特定ができないことを理由として国家賠償を否定することは妥当でなく、国賠法の立法趣旨、目的に反するものである。
2 公務員の個別具体的な法的義務が特定できない場合の賠償責任
公務員の個別具体的な法的義務が特定できない場合でも、国の最高行政機関たる内閣の瑕疵が明確な時には、当然国がその責任を負うべきであり、被害者は国賠法によって救済されるべきである。
この点につき、最判昭57年4月1日(民集36・4・519、判例時報1048号99頁)は、「国又は公共団体の公務員による一連の職務上の行為の過程において他人に被害を生ぜしめた場合において、それが具体的にどの公務員のどのような違法行為によるものであるかを特定することができなくても、右の一連の行為のうちのいずれかに行為者の故意又は過失による違法行為があったのでなければ右の被害が生ずることはなかったであろうと認められ、かつ、それがどの行為であるにせよこれによる被害につき行為者の属する国又は公共団体が法律上賠償の責任を負うべき関係が存在するときは、国又は公共団体は、加害行為不特定の故をもって国家賠償法又は民法上の損害賠償責任を免れることはできない」と判示し、どの公務員のどのような違法行為によるものであるかを特定することができなくても、国又は公共団体は、国家賠償法又は民法上の損害賠償責任を免れることはできないとされる。
また、同旨の判例は、東京地判昭39・6・19下民15・6・1438、東京地判昭45・1・28下民21・1=2・32、岡山地津山支判昭48・4・24判時757・100、札幌高判昭53・5・24高民31・2・231など多数あり、確立された判例となっているという被控訴人の主張は全く失当である。
なお、被控訴人が判例として確立されたとして引用する最高裁昭和60年11月21日判決(民集39巻7号1512頁、判例時報1177号3頁)は、国会議員の立法行為と国家賠償責任に関する判例であって、被控訴人の公務員の行為を検討することなく、国自身が先行的に義務を負担することはあり得ない上記主張を裏付ける判例ではない。
3 国賠法1条に基づく責任の法的性格
被控訴人は、国賠法1条に基づく責任の法的性格について、「当該作為義務が、公務員が当該国民に対して負う個別具体的な職務上の法的義務と評価できるものでなければならず、行政の内部的作為義務であったり、単なる抽象的一般的なものでは足りない」と主張し、いわゆる「代位責任説」の立場をとる古崎慶長「国家賠償法の理論」(79頁)を参照文献としてあげている。
ところで、国賠法1条の責任の性格については、学説として代位責任説、自己責任説が対立している。代位責任説の立場では、違法性は「行為者である公務員の職務上の義務違反」となるのに対して、自己責任説では、「公権力がその限界をこえて行使されること」であるとされる。すなわち、公務員は、国又は公共団体の手足として行動したにすぎず、不法行為を行ったのは国又は公共団体自身であり、損害賠償責任も第一次的に国又は公共団体に帰属する。
国賠法の立法過程の研究においては、ドイツの職務責任制度を参考にしたといわれており、国賠法の立法過程に参加した田中二郎博士も代位責任説をとっていた。
もっとも、国家賠償法案の司法法制審議会における立法過程で、ドイツの職務責任の場合と同様に「公務員に代わって」という規定の仕方をすることにより、代位責任であることを明示することが検討されたが、結局、それが見送られ学説に委ねられることとされたという経緯があり、起草に携わった委員の間で、代位責任制度を採用することにつきコンセンサスが成立していたというわけでは必ずしもなかった。
今日の国家賠償請求の多くが組織的決定を争うものである以上、自己責任説の方が実態に適合した理論構成であるということができるし、国家賠償法2条が自己責任説に立脚していることとの整合性も確保できる。
また代位責任説の欠陥に対する批判に対しては、自己責任説のほか、折衷的な立場に立つ説も唱えられている。
1970年代には、そもそも「代位責任」という言葉自体が疑義の多いものであるから、代位責任説と自己責任説を対立させるという従来の方法が反省されなければならないという考え方が有力になっているのである。
国賠法の制定に関わり、代位責任説をとっていた田中二郎博士も、こうした議論にふまえて、次のように述べている。
「本条による国の責任の性質については、最近では、国の自己責任だとする説の方が有力である。たしかに、国は公務員を使用して各種の国家活動をし、社会的利益をあげている反面、時には、その活動にあたって特定の者に損害を生ぜしめる危険を内在しているのであるから、このような国家活動に伴う損害については、国が当然責任を負うべきである(自己責任又は危険責任という)ということもできるであろう。国の責任を認めた究極の根拠は、ここにあるといってよい。(中略)国にこういう責任を課している実質的な根拠は、自己責任説のあげているところのほか、国にその責任を負わせることが被害者の救済を図るうえからいって遙かに有効であるという政策的理由にこれを求めることができる。」(田中二郎『新版行政法上巻〔全訂第二版〕』208頁、昭和49年)
4 諸外国、判例の動向
(1) ところで、国賠法の立法過程においては、ドイツの職務責任制度が参考にされたと言われているが、近年、ドイツでもこの職務責任制度が、第一次的には、公務員個人に責任が帰属することが国家責任の理論的前提となるため、主観的帰責要件も必要とされることに対し、代位責任制度の限界として強い批判を浴びている。
国家賠償請求がなされる場合の多くは、個々の公務員の個人的な故意過失により損害が惹起されたというよりは、組織的過失とみるべき場合が少なくない。そのため、理論的には、自己責任説の方が妥当であるとする見方が有力になっている。
その結果、1981年旧西ドイツ国家賠償法は、代位責任制度に立脚する職務責任制度を廃止して、自己責任としての国家責任制度を創設したのである。
(2) 代位責任・過失主義を採る判例においても、救済の機会をできるだけ確保するために、公務の執行に当たっての注意義務を強く認め、それによって過失の範囲を拡げるとか(いわゆる過失の客観化)、事実の推定により、原告の挙証責任を著しく軽減するとかの試みが広く行われている。その典型的な例として、最高裁平成3年4月19日判決は、「予防接種によって後遺障害が発生した場合には、特段の事情が認められない限り、被接種者は禁忌者に該当していたと推定するのが相当である」と説いて接種実施者の過失を認めなかった原判決(札幌高裁昭和61年7月31日判決)を破棄差戻し、差戻後の札幌高裁平成6年12月6日判決は国と市の敗訴を認め、国らは上告を断念した。
なお、これに先立ち、東京予防接種集団訴訟事件第一審東京地裁昭和59年5月18日判決は、国の賠償責任は否定したが、この場合に憲法29条3項の類推適用を認め、国に対し、「正当な補償」を請求することを認めた。しかし控訴審東京高裁平成4年12月18日判決は、一審の賠償責任否定の見解を誤りとするとともに、厚生大臣が禁忌該当者に予防接種を実施させないための充分な措置をとることを怠った過失を認めて国の不法行為責任を肯定した。これは組織過失の法理によるものであるが、この判決に対しても国は上告しなかった。
こうして現在では、自己責任説と代位責任説との違いは、結果においてはほとんどなくなっているともいわれているが、これは後者については名存実亡を認めたものといってよいのではなかろうか。
不作為の違法に当たる場合として、地方公共団体において建築確認を違法に遅延(留保)したことにより建築業者に損害を与えた場合(最高裁昭和60年7月16日判決)などの例がある。また、土地区画整理事業の施行者が、仮換地上の建物の移転または除却を怠った違法な不作為により、土地所有者に損害を与えた場合にも国の責任が認められた(最高裁昭和46年11月30日判決)。
また、最高裁は、公害健康被害補償法(現在の公害健康被害の補償等に関する法律)に基づく水俣病の認定遅延による損害の賠償請求事件において、精神的被害についても賠償責任が生ずることを認めている(最高裁平成3年4月26日判決)。
(3) こうした学説の動向、ドイツでの動向、また判例の動向にもあるように、国賠法1条の解釈において、被控訴人が主張するような、代位責任説を硬直的に適用し、公務員の個別具体的な法的義務が特定されない限り、国の違法性判断はなしえないという主張は全く妥当性を欠くものである。
5 作為義務が認められる要件
(1) 国家賠償法1条は、違法な公権力の行使による損害の賠償責任を認めている。公権力の行使は、公務員がその職務を行うについて遵守すべき法規範に違反したときに違法とされるから、不作為が違法な公権力の行使に当たるというためには、公務員に職務上の法的義務として一定の作為義務が認められることが必要である。
公務員の職務上の義務や権限は、法律やその委任を受けた省令などの法令によって定められているから、この法的義務としての作為義務も、法令によって定められているのが原則である。
しかし、法令上に具体的な根拠規定がない場合であっても、条理により法的義務としての作為義務を認めなければならないことがある。
(2) 本件細菌戦は、国の公権力の行使として実行されたものであり、これによって人の生命や身体に対して危険な状態を作り出したものである。このような先行行為があるにもかかわらず、公務員の職務上の義務を定めた根拠規定がないという理由で、国にはその危険な状態を解消するための作為義務はないと考えることは、正義、公平にかなうものではない。
したがって、このような場合には、国に対し、一定の要件の下に、危険な状態を解消するための作為義務を認めなければならない。
条理により法的義務としての作為義務を認めるということは、その作為義務が履行されない場合に、その不作為を違法と評価するのが物事の道理であると考えることである。
(3) したがって、国の公権力の行使によって危険な状態が作り出されたという先行行為がある場合に、国に法的義務としての作為義務を認めるためには、具体的な事案において、①人の生命や身体などに対する差し迫った重大な危険があり(危険の存在)、②国としてその結果の発生を具体的に予見することができ(予見可能性)、かつ、③作為に出ることにより結果の発生を防止することが可能であること(結果回避可能性)が要件になるものと考えられる。このような場合には、その不作為は違法なものと評価されなければならない。
本件細菌戦による被害が上記①ないし③の要件に該当することは、第1準備書面160頁以下で詳述したとおりである。
この場合、被控訴人としては、その作為義務につき具体的な担当機関が定められていないことを理由に、義務を免れることはできない。
この作為義務は条理を根拠とする義務であるから、そもそも法令上の担当機関の定めは想定できないものである。国としての作為義務が認められる以上は、国のいずれかの機関がその義務を履行すべきことは当然であって、個々的な担当機関の特定は要件にはならない。
6 本件細菌戦被害の救済義務の不作為は、国賠法上の違法にあたる
本件細菌戦の二次被害(精神的苦痛の倍加)は、そもそも被控訴人自身の不作為によって惹起されたものであって、被控訴人自身の責任である。
まして、被控訴人内閣の本件調査救済義務は、日本軍が中国において1940年代に組織的に行った本件細菌戦に起因するものである。その後、日本軍の軍事組織は全面的に解体されて今日に至っているのであるから、実戦使用された細菌兵器について、調査をして、細菌を撒布した時期、場所、撒布した細菌の種類等の情報を現地に伝える義務を負うべき国家組織やその公務員を特定することは不可能といってもよい。
しかし、このような場合に、公務員や行政機関の特定ができないことを理由として責任を否定することは、著しく正義に反する。
しかも、国家行政組織法上、被控訴人が負っている義務を履行すべき機関が存在しないということはあり得ない。現に管理すべき機関を被控訴人が定めていない場合には、内閣府が管理すべきことになる。
したがって、被控訴人の主張は失当である。
第2章 法例11条の適用に関する被控訴人主張に対する反論
被控訴人による控訴人らに対する細菌兵器の実戦使用により控訴人らが被った損害の民事上の賠償責任については、不法行為に基づく損害賠償についての一般抵触法規である法例11条1項を適用し、当時の中華民国法に準拠すべきことは、すでに第1準備書面第4章で詳述したが、以下、被控訴人の第1準備書面に反論するとともに主張を補充する。
第1 法例11条1項の適用
1 被控訴人の主張
被控訴人は、「公権力行使を伴う国家賠償という法律関係については、我が国の国家利益が直接反映される法律関係ということができ、国際私法の適用とはならない」と主張する。
しかし、本件細菌戦に国際私法(法例)が適用されるか否かを検討するに当たっては、何が私的法律関係であり、何が公的法律関係であるのかを抽象的に議論すべきではない。
本件細菌戦のように法例11条の適用が問題になっているのであれば、同条がどのような法律関係を対象としているのかを考察するとともに、公法の属地的適用の原則がどのような法律関係を対象としているのかを考察すべきであり、両者は表裏の関係にあるということができる。
2 法例11条が対象とする法律関係
まず、法例11条がどのような法律関係を対象としているかについて検討する。
そこで法例11条の立法経緯をみると、同条は、旧法例7条と同趣旨の規定であるため、その立法に際して特に説明がされていない。
また、旧法例7条の制定過程は明らかとなっていないので、更にさかのぼり、旧民法草案人事編の中に規定されている不法行為の準拠法に関する法例12条3項の制定過程における説明をみると、同条項は、不法行為が単なる私益のためのものではなく、公益のためのものであり、契約と異なり双方の意思によらないで債権を発生させるものであることを考慮して、不法行為地法主義を採用したことが分かる。
ここで、不法行為による損害賠償請求権が公益のためのものであるというのは、法廷地の公益ではなく、不法行為地の公益を意味している。
そして、国家賠償責任もまた、個人に損害賠償請求権を与えるという点では、私益に関するものであるが、同時に公権力の行使を慎重ならしめるという点では、公益に関するものといえる。しかし、これは法廷地の公益でも、加害国の公益でもなく、まさに不法行為地の公益に関するものということになる。
このような検討からすれば、問題は、本件細菌戦が法例11条1項の「不法行為」といえるかということであるといえる。
そこで、各国の実質法を比較法的にみた場合、法例11条1項の「不法行為」とは、「何らかの行為(作為・不作為)があり、他人に損害が起きて、損害賠償責任を負わせるか否かという問題」を意味すると考えることが出来る。とすると、当該行為(作為・不作為)が違法であるか否か、損害の発生との間に因果関係があるか否か、そして損害賠償責任を生ぜしめるか否かは、実質法レベルの問題であるといえる。
そのため、国際私法は、何らかの行為(作為・不作為)があり、他人に損害が生じて、損害賠償責任を負わせるか否かという問題が発生した場合、それを解決するために、どの国の実質法を適用すべきかを決定することを、その任務とするのであって、行為の違法性、因果関係、そして損害賠償責任の存否を決定するわけではない。
本件細菌戦では、日本軍による細菌兵器の実戦使用という行為があり、中国人市民に損害が発生したので、日本国に損害賠償責任を負わせるか否かという問題が生じているのである。よって、本件細菌戦は、法例11条1項の「不法行為」の定義に当てはまる。
したがって、本件細菌戦は、法例11条の適用対象に当たるといえる。
3 法例11条の適用対象から除外される公法的法律関係
次に、本件細菌戦のような法律関係が、公法の属地的適用の原則が適用されるべき公法的法律関係であるか否かという観点から検討する。
公法的法律関係においては、ある法規の場所的適用範囲の決定は、当該法規自体の明文の規定によるが、明文の規定がない場合には、当該法規の趣旨及び目的に照らし、条理によって、場所的適用範囲を決定する。
上記の条理としては、一般に「公法の属地的適用」の原則が主張されている。ここで、公法の属地的適用の原則とは、公法の適用範囲は、主権の及ぶ範囲に限定され、その問題となった行為が自国の領域内でなされた場合にのみ適用されるべきであり、外国でされた行為には適用されないというものである。
我が国の国家賠償法については、戦前、戦後を通じて、上記のような明文の規定はないから、国家賠償法が公法であるとすると、「公法の属地的適用」の原則によって、場所的適用範囲を決することになる。
国家賠償法が公法であるとして公法の属地的適用の原則を適用すると、日本の国家賠償法は、原則として日本における日本の公務員の不法行為にのみ適用されることになる。つまり、日本の在外公館の職員が自国民の保護を怠ったり、外国人からの査証の申請を不当に却下した場合、日本の国家賠償法が適用されないことになる。
そして、公法の属地的適用の原則には、外国の公法を適用しないという意味もあることから、日本の裁判所は、自国の公法の適用範囲を超えた事件について、外国の公法を適用することはできないから、結局のところ、このような事件については、裁判管轄がないことになる。
さらに、在外公館の職員が自国民の保護を怠ったり、外国人からの査証の申請を不当に却下した場合とは異なり、日本の公務員が外国における行為により、上記のような関係を持たない者に損害が発生した場合、例えば、日本の公務員が外国における公務の執行中に交通事故を起こした場合には、なおさら日本の国家賠償法を適用するわけにはいかないことになる。
他方、日本に駐在する外国の大使館職員が自国民の保護を怠ったり、日本人からの査証の申請を不当に却下したとする。これは、日本における行為であるが、行為主体が外国の公務員であるから、日本の国家賠償法を適用することはできない。
しかも、外国公法不適用の原則によるならば、外国の国家賠償に関する規定も適用することはできず、結局のところ、日本の裁判所において損害賠償請求訴訟を提起したとしても、裁判管轄が否定されることになる。
しかし、以上のような裁判管轄の否定は、妥当とは思われない。
これらの訴訟で求められているのは、刑罰や行政処分の取消ではなく、単なる金銭賠償にすぎない。このような金銭賠償を命じることは、たとえその準拠法が外国法であっても、日本の裁判所の管轄を否定すべきではない。これは、外国法の適用が必要であり、かつ、それが可能な法律関係であるというべきである。
以上のように、外国法の適用を必要かつ可能とする法律関係であるということは、まさにそれが国際私法の対象である渉外的私法関係であることを意味している。
すなわち、本件において求められているのは、違法な行政処分の取消や刑罰権の行使ではなく、損害の賠償(金銭賠償など)であるが、これが具体的に認められるべきであるか否かは、実質法レベルの問題である。国際私法の観点からは、かような損害賠償の有無が問題となっている法律関係であることが重要なのである。
4 国に対する外国法の適用
被控訴人は、「控訴人らの立論を前提とすると、公権力の行使に伴う損害賠償の問題について、法例11条1項が適用され、その結果、不法行為地である当該外国の民法が適用されることに帰着するが、このような結論は、我が国の国家権力の発動の違法性等について、我が国を単なる一私人と見立てた上、他国の私法がこれを裁くことを意味する」と批判する(被控訴人第1準備書面79頁)。
被控訴人は、外国法の適用を、当該外国の主権の発動と理解して、国家が外国の主権に服することは妥当でないと考えるようである。
しかしながら、外国法の適用を当該外国の主権の発動と考えるならば、主権独立の原則により、外国法の適用はすべて否定されることになるはずである。
渉外事件においては、国際的な判決の調和という国際社会全体の利益のために、内外法は平等に適用されるべきであるというのが国際私法の基本である。
日本の裁判所は、当該法律関係と最も密接な関連を有する法として、いずれの国の法が準拠法になるかを審理すべきであり、たとえそれが外国法であったからといって、その適用が、当該外国国家の主権の発動ということにはならない。
以上のように、本件細菌戦は、外国法の適用も可能とする渉外的私法関係であり、これを否定すべき公法関係に当たらない。
5 公務員所属国法説の不適用
以上のとおり、国際私法が適用されるべき法律関係であるとしても、直ちに国家賠償責任について、法例11条1項により準拠法を決定すべきであるということにはならない。
一般の不法行為においては、加害者と被害者とは、不法行為の発生によって初めて債権債務関係に入る。このような場合に不法行為地法を適用すれば、加害者にとっては、自己の行動から生じる責任の存否及び範囲を予測することができるし、また被害者にとっても、自己が期待することができる賠償の有無及び範囲を予測することができる。このような予測可能性ないし正当な期待保護の要請を満たすからこそ、一般の不法行為の場合には不法行為地法主義が採用されたのである。
これに対して、不法行為の発生以前から、加害者と被害者との間に特別な法律関係があり、この法律関係と不法行為との間に密接な関連がある場合には、不法行為についても、むしろこの特別な法律関係を規律する準拠法を適用した方が、両当事者の予測可能性ないし正当な期待保護の要請を満たすことになる。
例えば、法例11条1項の不法行為地法主義によるならば、外国における日本の公務員の不法行為には、常に当該不法行為地法である外国法が適用され、逆に日本における外国の公務員の不法行為には、つねに日本法が不法行為地法として適用されることになる。
しかし、公務員の外国における不法行為には、例えば在外公館の職員が自国民の保護を怠ったり、又は外国人からの査証の申請を不当に却下した場合のように、加害者と被害者との間に特別な法律関係がある場合には、不法行為についても、その法律関係を規律する法を適用することが妥当であると思われる。
この特別な法律関係の準拠法としては、当該公務員の所属する国の法、すなわち公務員所属国法が適用されるべきである。
本件細菌戦においても、控訴人の中国人は中国において日本の公務員に公権力の行使を求めたわけではない。日本軍にとっては公権力の行使であったとしても、控訴人の中国人は日本政府と公法的な関係になかった。
本件は、被控訴人が細菌兵器の実戦使用をした行為が、当該外国の同意もなく、国際法上の根拠もない不法行為であり、このような場合には、不法行為地法以外に両当事者にとって中立的な法は存在しない。
したがって、本件細菌戦は、公務員所属国法説を適用すべき場合には該当せず、原則どおり法例11条1項が適用されるべきである。
なお、本件細菌戦では、この不法行為地が中国であるから、結果的に控訴人である中国人に有利な法が準拠法になったかのような印象を与えるかもしれない。しかし、仮にタイやフィリピンにおいて中国の民間人が日本軍から被害を受けたとすれば、両当事者にとって最も中立的な法はタイ法ないしフィリピン法ということになる。
6 国際私法上の公法・私法の区分に関する被控訴人の誤り
(1) 被控訴人の主張
公権力行使を伴う国家賠償という法律関係について、これが国際私法の適用されない公法的法律関係に属するとする被控訴人の主張は、「現代の国際私法においては、国家と市民社会とは切り離すことが可能であり、市民社会には特定の国家法を超えた普遍的な価値に基づく私法が妥当しており、これはどこの国でも相互に適用可能なものである」との考えを前提とする。
そして、「私法の領域では国家利益に直接関係しないことから、一般に法の互換性が高」いが、公法の領域はそうではないとして、「国際私法が対象とする法律関係は、一般に法の互換性が高く、国家の利益に直接関係しない領域に属する法律関係(以下、「私法的法律関係」という。)にとどまるといわなければならない。
そして、国家の利益が直接反映される法律関係(以下、「公法的法律関係」という。)は、国際私法の関係からは、公法の領域に属するものとして取り扱われることとなり、その対象外におかれるものといわなければならない。」と主張する(被控訴人第1準備書面73ないし74頁)。
すなわち、被控訴人は、国際私法上の公法、私法の区分は、国家利益との結び付き及びその程度から判断されるという基準を立てる。
国際私法上の公法、私法の区分について被控訴人採用する上記基準は、サヴィニーがこのような見解を表明しているということに基づくものと思われる。
(2) 被控訴人の基本的誤り
しかし、被控訴人はサヴィニーの国際私法理論を正しく理解していない。
すなわち、サヴィニーは、被控訴人が主張するような「国家と市民社会とは切り離すことが可能であり、市民社会には特定の国家法を超えた普遍的な価値に基づく私法がある」とは言っていない。
従来の国際私法論が主権的発想に基づき個々の法規の性質から、その適用範囲を決定するという方法を採用していた。これに対し、サヴィニーは、人や物質の国境を越えた移動が多様かつ活発になるにつれて、内外人の平等原則に基づき、内国法と同様に外国法も適用すべきであり、それによって、いずれの国で裁判がされても同一の結果が得られるという国際的な判決の調和が達成され、国際社会の共通の利益が図られるという発想の下に、より普遍的な法律関係の側から、その本拠を探求するというアプローチを採用しているのである。
このようなサヴィニーが、国家利益との結び付きの強弱によって私法と公法とを区別するという法規分類学説のような主張をするはずがない。以下で詳しく述べる。
(3) サヴィニーの国際私法理論
サヴィニーの『現代ローマ法体系第八巻』を参照すると、サヴィニーは、「実質法は、およそ人類全体にとって同じものではなく、民族および国家により様々である。しかし、これは個々の民族において、一部は普遍人類的な法形成力によるものであり、また一部は民族固有の法形成力によるものである。この実質法の多様性(Mannichfaltigkeit der positiven Rechte)こそが各実質法についてその適用範囲を確定すること、すなわち様々な実質法の相互の境界を定めることの必要性および重要性が生じる理由である。この境界画定によってのみ、ある具体的な法律関係の判断において様々な実質法の間で生じうる抵触をすべて解決することが可能となるのである」と述べている。
さらにサヴィニーは、「多数の者は、この問題をもっぱら主権独立の原則によって解決しようと」するが、「様々な民族間の相互交流が多様かつ活発となるにつれ、かの主権独立の厳格な原則はもはや維持することができず、むしろこれと対照的な原則に代えるべきことが望ましいと考えられるようになるであろう。法律関係の処理において望ましい相互主義、およびそこから生じる内外人の平等原則がそれである。
これは、一般に諸民族および個人の共通の利益から求められる。なぜなら、この平等原則により、次のような結果が完全に実現されるに違いないからである。
すなわち、各国において、外国人が内国人よりも不利な扱いを受けないだけではなく(そこには人の平等的取扱の原則がある)、法抵触の事件において、法律関係も、どの国で判決が言い渡されるかにかかわりなく、同一の判断が期待されるのである」と述べている。
(4) 被控訴人の理解の誤り
被控訴人は、「国家と市民社会とは切り離すことが可能」であると述べ、あたかも国家と市民社会の切り離しというものがあって、その結果、国際私法が従来の主権的発想から脱却できたかのようにいう。
しかし、従来の国際私法理論は主権独立の原則から外国法の適用を否定していたが、それでは外国人の権利が無視されることになるため、内外人平等の原則にもとづき、内国法と同様に外国法も適用すべきであり、それによって、いずれの国で裁判がなされても同一の結果が得られるという「国際的な判決の調和」を達成しようとしたのである。
これは、国際社会の共通の利益によるものであり、サヴィニーは、このような利益共同体を比喩的に「国際法的共同体」と称している。
このようにサヴィニーは、国際社会の利益のために、内外法の平等を達成しようとし、また内外法の平等達成のために主権的発想からの脱却を主張したのである。そこでは、国家と市民社会の切り離しというようなことは一言も述べられておらず、むしろ内外法平等のために、積極的に主権的発想からの脱却を主張したのである。
また被控訴人は、「市民社会には特定の国家法を超えた普遍的な価値に基づく私法が妥当しており、これはどこの国でも相互に適用可能なもの」であるというが、サヴィニーは、そうは言っていない。サヴィニーは、むしろ「実質法の多様性」を前提としており、たとえ実質法が国毎に多様であっても、国際私法が「国際法的共同体」の利益のために内外法を平等に適用するのであれば、「国際的な判決の調和」を達成することができると主張したのである。
さらに被控訴人によると、私法と公法の区別は、法の国家利益との結び付きの強弱によることになり、「一般に法の互換性が高く、国家の利益に直接関係しない領域に属する法律関係」であれば私法であり、「国家の利益が直接反映される法律関係」であれば公法の領域に属するものとして取り扱われることとなるというが、これもサヴィニーの見解と大きくかけ離れている。
サヴィニーによると、国家利益から切り離すべきであるのは、各国の私法(実質法)ではなくその適用であった。すなわち、サヴィニーは、従来の国際私法理論が主権的発想にもとづき、個々の法規の性質からその適用範囲を決定するという方法を採用していたのに対して、「国際法的共同体」の観念にもとづきより普遍的な法律関係の側から出発してその本拠を探究すべきであるとしたのである。このようなサヴィニーの理論によれば、個々の法規がどのような性質を有するのかは無関係になる。それゆえ、内外法は平等であり外国法の適用も国家の法的義務としたのである。
これに対して、国家利益との結び付きの強弱によって私法と公法を区別するという被控訴人の主張は、むしろサヴィニーによって退けられた法規分類学説(条例理論)と同じ発想にもとづいているものと評価できる。国家利益との結び付きの強弱は、個々の法規を見なければ分からないことであり、より普遍的に法律関係の側からその本拠を探究しようとするサヴィニーの国際私法理論とは全く相いれない考え方であるといえる。
また、サヴィニーの国際私法理論を理解するにはサヴィニーの抵触法論が登場した時代的な背景を検討することも重要である。
当時、フランス革命を契機として、ヨーロッパでは、人や物の移動が極めて活発となり、それに伴い発生する法律問題も渉外的要素を含むものが増大しつつあった。
しかし、従来の国際私法理論は、多様化する現案と多数の主権国家の独立に対応できるものではなかった。とりわけ、当時のドイツは、プロイセン一般ラント法の地域、フランス法(ナポレオン法典)の地域、普通法(ゲマイネス・レヒト)の地域に分かれ、普通法の地域はさらに様々な変種に分裂していた。
そこでサヴィニーは、ドイツ国内においてすら各地域の法が分裂し、また諸外国においても、独自の「国家法」が生成しつつあったからこそ、新しい国際私法理論の必要性を感じたのであり、たとえ私法が「国家法」として分裂していても、普遍主義的な国際私法の観点から、法律関係の本拠を探究することによって、個々の事件については、どこの国で裁判がなされても同じ結果が得られるという「国際的な判決の調和」を求めたのである。
以上のように、被控訴人は、サヴィニーの国際私法理論を正確に理解していない。サヴィニーは、そもそも「市民社会には特定の国家法を超えた普遍的な価値に基づく私法」があるとは述べていなかった。この大前提が崩れるのであれば、国家利益との結び付きの強弱による私法と公法の区別という結論も誤りということになる。
7 公権力の行使に伴う国家賠償が公法的法律関係であるとして被控訴人が指摘する「根拠」の誤り
(1) 被控訴人の主張
被控訴人は、上記の公法、私法の区分の基準を前提とした上で、公権力の行使に伴う国家賠償という法律関係が公法的法律関係(我が国の国家利益が直接反映される法律関係)であるとする根拠として、
① 国家賠償法の公務員個人への求償権制限、
② 相互保証主義、
③ 戦前の国家無答責の原則
の3点を挙げる。
すなわち、被控訴人は、「我が国の国賠法をみても、公務員による公権力の行使を萎縮させないように公務員個人に対し求償できる場合を限定し(同法1条2項)、外国人が被害者である場合は、相互保証のあるときに限って賠償する(同法6条)とし、私法の領域とは異なる特別の法政策が採られている。これらは、国家賠償の問題が国家の利害そのものと深く関係していることの証左である」とし、また、「国の権力的作用について一般私法である民法の適用が否定されるとする当時の法制度をみても、公権力の行使に伴う不法行為については、我が国の法政策上、国家利益が直接反映され、一般私法と異なる領域に属する法律関係として理解されていたことが明らかである」としたうえで、これらを根拠として 「公権力行使に伴う国家賠償という法律関係については、我が国の国家利益が直接反映される法律関係ということができ、国際私法においては、公法の領域に属する法律関係として取り扱われることになり、国際私法の適用対象とはならないと解するのが正当である」と主張する(被控訴人第1準備書面74ないし75頁)。
(2) 被控訴人の基本的誤り
しかしながら、被控訴人は、自国の実質法の解釈を前提として、国際私法の適用の有無を議論している点において基本的な誤りを犯している。
すなわち、国際私法とは、複数の国が関連する法律関係(渉外的法律関係)について、いずれの国の法を適用すべきかを決定するための法律である。国際私法それ自体は、当事者の法律関係を直接規律するのではなく、これを直接規律するいずれかの国の法を指定するための法律であって、適用規範ないし間接規範とも呼ばれる。これに対して、民商法や民事訴訟法など法律関係を直接規律する規範は「実質法」と呼ばれている。この国際私法と実質法とは、全く異なる次元の法律である。
国際私法の次元において準拠法を決定する際に、実質法を前提として解釈を行うことは誤りである。例えば、準拠法決定の過程において、国家賠償法附則6項を適用し、同項に基づき戦前の日本の実質法が国家無答責を採用していたことを前提に国際私法の不適用とすることは、誤りである。
また、日本の実質法だけを前提として、法例を解釈しようとすることも誤りである。国際私法は、内外法平等の原則に立っており、日本法と同様に、外国法も適用されるからこそ、その存在意義が認められるのである。
以上の基本的立場を前提とすると、上記①ないし③が、国際私法の適用を否定する根拠とはなり得ないのである。
(3) 国家賠償法の公務員個人への求償権制限について
被控訴人は、国家賠償法が公務員個人への求償権を制限していることを、公権力の行使に伴う国家賠償という法律関係が公法的法律関係である根拠とする。
しかし、日本の公務員の不法行為について、外国法が準拠法となり、公務員個人への求償権制限が適用されなかったとしても、どれほどの不都合を生じるというのであろうか。公務員個人への求償権制限は、およそいかなる国のいかなる時代の法によっても普遍的に認められなければならないというほどのルールではない。
たしかに、国際私法を適用し外国法が準拠法となった場合においては、当該国の実質法の立法政策は必ずしも貫徹されるとは限らない。しかし、だからといって外国法の適用を否定したのでは、国際私法は全く無用ということになりかねない。たまたま日本の現行国家賠償法において、公務員個人への求償権制限が規定されているからといって、外国法の適用が排除されると主張するのは、およそ国際私法の基本を無視するものである。
(4) 相互保証主義について
被控訴人は、国家賠償法が相互保証主義を採用していることを、公権力の行使に伴う国家賠償という法律関係が公法的法律関係である根拠とする。
また、被控訴人は、比較法的な観点から各国の実質法等を検討したうえで、「諸外国の国家賠償制度を見ても、相互保証主義、行政機関への前置主義等各国独自の国家利益を反映した法制度が採用されていることがうかがわれ、一般の私法と異なる取扱いがされていること及びその結果として一般的な法の互換性が存在しないことが明らかである」として、「法律関係の性質決定として、公権力行使に伴う国家賠償の法律関係は、法例11条にいう「不法行為」概念に包摂されないものといわざるを得ず、本件では、法例11条が適用される余地はないというべきである」と主張する(被控訴人第1準備書面82ないし83頁)。
しかし、法例11条の「不法行為」の概念は、違法な行為によって他人に損害を与えた者をしてその損害を賠償せしめる制度であって、社会共同生活において生じた損害の公平な分配を目的とするものである(山田鐐一「国際私法」317頁参照)。
この場合の「損害の公平な分担」の内容は、実質法レベルでは各国によって異なることはもちろんである。それゆえ、過失責任、無過失責任、あるいは責任の免除をも含めた概念であるといえるところ、相互の保証による外国人の国家賠償請求の制限も、誰にどの程度の責任を分担させるのかという損害の公平な分担の一態様であるから、この不法行為概念から外れるものではない。
国家賠償法における相互保証の規定は、国家に対する外国人の損害賠償請求権を一定の場合において制限するものであり、外国人の権利をいかなる場合に制限するかは、個々の法律の趣旨に基づいて決められるべき実質法上の問題である。外国人の権利を制限したからといって、当該権利が公法上の権利となるものではないのである。
結局のところ、相互の保証は、外国法が日本国民に対して権利を認めていない限りは、日本においても当該外国の国民に権利を認めないとする立法主義のひとつにすぎないのである。
したがって、国家賠償法が相互の保証を採用しているということは、公権力の行使に伴う賠償責任の存否が公法的法律関係であることを基礎付ける根拠となるものでない。
(5) 戦前の国家無答責について
被控訴人は、戦前において、国家無答責の法理が採用されていたこともまた公権力の行使に伴う国家賠償という法律関係が公法的法律関係である根拠になるとする。
しかし、そもそも、戦前の国家無答責の法理が普遍的な法理として確立していたわけではないことは第1準備書面において詳しく述べたとおりである。
また、法例11条の「不法行為」概念は、損害賠償責任の否定という国家無答責の法理をも含む広いものであり、実質法における立法政策の問題であり、国際私法の適用・不適用を決定づけるものではない。
(6) まとめ
いずれにせよ、被控訴人国が指摘する前記①ないし③の点は、すべて実質法レベルの問題であり、そもそも実現しようとしている正義の観念が国際私法上のものとは異なるのであるから、そこでどのような議論がなされようが、あらゆる国のあらゆる時代の法を前提とする国際私法の適用、不適用を左右するものではないのである。
第2 法例11条1項に基づく準拠法の決定
1 本件細菌戦では、日本軍による細菌兵器の実戦使用という行為があり、中国人市民に損害が発生したので、日本国に損害賠償責任を負わせるか否かという問題が生じているのであり、本件細菌戦は、法例11条1項の「不法行為」の定義に当てはまる。
したがって、本件細菌戦は、法例11条の適用対象に当たるといえる。
2 そして、不法行為については、法例11条1項により、「原因タル事実の発生シタル地ノ法律」(不法行為地法)が適用される。
原因事実の発生地という連結点については、その解釈には幅があり得るが、いずれにせよ、本件細菌戦において日本軍が細菌を散布する等の行為をした地も、被害が発生した地も、いずれも中華民国内であり、かつ中華民国法が実効性を有していた地なのであるから、原因事実の発生地法は、中華民国法である。
3 よって、本件不法行為時の1940年ないし42年当時の中華民国法が適用されるべきである。
第3 法例11条2項について
1 被控訴人は、「法例11条2項により、不法行為の成立について不法行為地法と日本法とが累積的に適用されることとなる。本件細菌戦において控訴人らが主張する旧日本軍人ら公務員の行為は、国家の権力的作用であって、我が国の国賠法施行前においては、国の権力的作用については民法の不法行為法(709条以下)の適用は排除され、国の損害賠償責任は否定されていた(国家無答責の法理)。そして、その後、日本国憲法17条に基づき制定された国賠法附則6項は、「この法律施行前の行為に基づく損害については、なお従前の例による。」と定めたから、国賠法施行前の旧日本軍人の行為に関する損害賠償請求は国家無答責の法理により、その法的根拠を欠くものというほかない。」と主張する(被控訴人第1準備書面87頁)。
2 しかしながら、本件細菌戦のような場合を「不法ナラサルトキ」ということはできないのであるから、本件細菌戦には法例11条2項の適用はない。
(1) 本件細菌戦は、原判決も認めるように、ジュネーブ・ガス議定書を内容とする国際慣習法に違反した違法行為であった。日本軍も違法性を認識し一貫して秘密裏にこれを準備し実行した。
本件細菌戦は、被控訴人の適法な公権力行使とはいえず「保護すべき権力作用」にはあたらないことはいうまでもない。したがって日本法においても「不法ならざるとき」ということはできず、法例11条2項の適用はない。
(2) また、法例11条2項は、「前項ノ規定ハ不法行為ニ付テハ外国ニ於テ発生シタル事実カ日本ノ法律ニ依レハ不法ナラサルトキハ之ヲ適用セス」と規定しているが、本件加害行為は、その態様においても被害の程度においても、歴史上稀有なものであり、あらゆる価値基準からみても到底容認されえない違法行為であることは明らかである。また、加害者の故意があったことに疑いの余地はない。したがって、本件細菌戦が、客観的にも主観的にも、日本法の不法行為に該当するものであり、本件の場合、法例11条2項が適用される余地はない。
(3) さらに、既に控訴人側第1準備書面で述べたとおり、法例11条2項の「不法」の解釈が問題になるのであるが、百歩譲って、日本法の不法行為法が全面的に累積適用されると解する説に立って、法例11条2項により日本民法が累積適用されるとしても、この法廷地法の累積適用は、法廷地の公序を尊重して設けられた規定であるから、適用されるのは、裁判時の法廷地法である。
すなわち、法例11条2項により日本法が累積的に適用されるのは、不法行為というのは公序に関わるものであるので、法廷地の公序を考慮したためであるとされている。法廷地において違法であるとされている行為について不法行為ではないとすることは、法廷地の公序に抵触することになり、不適当であるので、法廷地法を累積的に適用することにしたのである。そして、法例が適用されるということは、法廷地は日本であるので、日本法が累積的に適用される旨が規定された。このように、法廷地法の累積適用は、法廷地の公序を尊重して設けられた規定である。この観点からするならば、ここで適用すべきは、裁判時の法廷地法である。なぜならば、裁判において抵触が問題となる法廷地の公序は、当然、裁判時の公序であり、裁判時の公序と関わるのは、裁判時の法廷地法だからである。
よって、法例11条2項により日本民法が累積適用されるとしても、この法廷地法の累積適用は、法廷地の公序を尊重して設けられた規定であるから、適用されるのは、裁判時の法廷地法であり、国家無答責の原則が適用されるものでない。
3 よって、結局、本件細菌戦のような場合を「不法ナラサルトキ」ということはできないのであって、中国民法の適用を妨げる理由にはならないのである。
第4 法例11条3項について
1 被控訴人の主張
被控訴人は、「法例11条の適用を考えてみても、同条3項の適用により、不法行為の効力について不法行為地法と法廷地法とが累積的に適用される。そして、控訴人らの請求は、その主張に係る不法行為の時から既に20年以上が経過した後にされたものであるから、法廷地法である我が国の民法724条後段によりその請求権が消滅している。」と主張する(被控訴人第1準備書面87頁)。
しかし、これは、法例11条3項の解釈を完全に誤った主張であるというべきである。
2 法例11条3項の規定の文言
法例11条3項の規定による日本法の累積適用が不法行為債権の消滅時効にまでは及ばないのは、法例11条1項が「債権ノ成立及ヒ効力」という文言を使用しているのに対して、同条3項が「損害賠償其他ノ処分」という文言を使用していることをみれば明らかである。
すなわち、法例11条1項は、不法行為債権の「効力」について、これを不法行為地法によらせると規定している。これによれば、不法行為債権の効力に関する問題は、消滅時効の問題も含めて、すべて不法行為地の実質法が適用されることになる。
一方、法例11条3項による日本法の累積適用は、「損害賠償其他ノ処分」にまでしか及ばないと規定されているのであるから、その結果、同項は、不法行為の直接的な効力である損害賠償の額及び方法の問題にまでしか及ばないものと解するほかないのである。
仮に、法例の立法者が日本法の累積適用を不法行為の効力のすべてに及ぼすつもりであったなら、わざわざ2項と3項を分けなかったであろう。例えば、2項において、「前項の規定にかかわらず、日本の法律が認めない不法行為の成立及び効力は認めない」と規定すれば足りたはずである。
ところが、法例の立法者は、このような規定の仕方をしなかった。そして、11条2項と3項を別個に規定し、さらに3項においては、「損害賠償其他ノ処分」という文言を用いている。このことは、法例11条3項による日本法の累積適用の範囲を不法行為の効力の全体に及ぼす趣旨ではないことを意味しており、通説はこれを当然の前提として立論しているのである。
3 立法経過からの考察
(1) 立法経緯
法例修正案理由書(皆木卜一郎編「再版・法例及国籍法附修正案理由書」29頁)によれば、11条2項の趣旨は、外国の法律によれば不法行為として債権の発生原因となる行為であっても、日本の法律によれば合法の行為であるときは、救済を与える理由がないということにある。また、3項の趣旨は、外国の法律が与える救済と日本の法律が与える救済との間で、その処分方法が異なるときは、日本の法律が認めない救済方法を与える理由がないということにある。これを素直に読めば、時効や除斥期間が含まれていると解することはできない。
また、法例議事速記録(「法典調査会・法例議事速記録(日本近代立法資料叢書26)」125頁)において、穂積陳重が11条3項の提案理由を述べている。例えば、オランダ法では、名誉毀損の場合に、法廷で被害者に謝罪をするとか、以前に述べたこと、あるいは書いたことが誤りであったと公言することが救済方法として認められているが、たとえ不法行為地がオランダであったとしても、日本において、このような救済方法を認めることはできないとされている。これによると、法例11条3項は、日本法が認めた以外の損害賠償を認めないという趣旨である。
以上によれば、法例11条3項は損害賠償の方法及び程度にのみ関する規定であり、時効や除斥期間は含まれていないと解するのが合理的な解釈である。
(2) 時効と公序に関する議論
さらに、法例の立法過程において、時効と公序の関係についてなされた議論も参照すべきである。
すなわち、寺尾亨が時効と公序の関係について、起草者の意見を質したところ、穂積陳重は、別段の規定を設ける必要なしと回答したのに対して、梅謙次郎は、外国法上の時効期間が日本法上の時効期間よりも長い場合には、その外国法の適用を排除して、日本法を適用すべきであるとする規定を提案した。しかし、この提案は、賛成が少なく、結局は採用されなかった(法例議事速記録192頁以下)。
その後、大審院大正6年3月17日判決・民録23輯378頁は、準拠外国法が日本法よりも長い消滅時効期間を定めている場合には、国際私法上の公序に反するとして、日本法を適用したが、学説は、一斉にこれを批判し、準拠外国法が定める時効期間が極端に長い場合や、全く消滅時効を認めない場合は、具体的な事件における適用結果を考慮したうえで、法例33条の公序の発動も考えられるが、一般的に時効期間の長短により法例33条を適用すべきではないと主張し(山田鐐一「国際私法」332頁など)、戦後は、これに従った下級審判決も現れている(例えば、徳島地裁昭和44年12月16日判決・判例タイムズ254号209頁)。
以上の経緯は、法例11条3項による日本法の累積適用に時効・除斥期間の問題が含まれないことを示している。仮に、法例11条3項にいう「損害賠償其他ノ処分」の中に時効・除斥の問題が含まれるとしたなら(そのような解釈は文言上無理であるが)、梅謙次郎の提案は、少なくとも不法行為債権の時効については重複することになる。
確かに、法例の立法経緯における議論は、第1次的には契約債権の時効に関するものであるが、梅の提案は、契約債権と不法行為債権を区別しておらず、このような重複は指摘されていない。これは、まさしく法例11条3項による日本法の累積適用に時効・除斥の問題が含まれないことを示している。
また、時効と公序の関係に関する判例は、いずれも契約債権と不法行為債権を区別しないで展開されており、外国法の適用については、単に日本法によった場合と比べて長い時効期間を認める結果になるからといって、その適用が排除されるわけでなく、具体的な事案との関連で法例33条の公序の発動が問題となるにすぎないとしている(なお、国際私法上の公序は、そもそも外国法の適用結果が日本法によった場合と異なることだけを理由とするわけではないから、公序の発動の可能性があるということは、本来は取り上げる必要のない議論である。)。
ここでも、仮に法例11条3項による日本法の累積適用に時効・除斥の問題が含まれるとしたなら、不法行為債権の時効について、上記の議論は成り立ち得ないことになる。なぜなら、公序の発動以前に、日本法よりも長い時効期間を定めた外国法は、すべて日本法の累積適用により排除されることになるからである。しかし、上記の議論は、そのような事態を完全に否定しているのである。
(3) 法例11条3項に関する学説
法例11条3項による日本法の累積適用に消滅時効の問題までは含まれないことは、国際私法に関するどの法律文献を見ても明らかである。すなわち、法例11条3項により消滅時効の問題にまで日本法の累積適用が及ぶとしている学説は、過去から現在に至るまで、どのような著書や論文をみても、ひとつとして存在していない。被控訴人国は、各見解の趣旨とするところを誤解しているとしかいいようがない。
これは、日本の学説が上記の立法経緯を暗黙の前提としているからであろう。
確かに、これらの学説では、丹念に立法経緯を紹介したり、ドイツの立法草案を検討したものは見当たらない。しかし、それは、法例11条3項の文言から、損害賠償の方法及び額についてのみ日本法を累積適用する趣旨であることがあまりにも明白であるために、改めて立法経緯を紹介するまでもないと考えられたからであろう。
4 まとめ
以上のように、法例11条3項の日本法の累積適用によって控訴人らの損害賠償請求権が認められないとする被控訴人の主張は、完全なる誤りである。控訴人らの損害賠償請求権が、被控訴人のいうように、日本民法の除斥期間の経過によって消滅しているということは考えられない。
第3章 「国家無答責の法理」は本件細菌戦には適用されない
すでに、第1準備書面の第2章の第2、第3準備書面第2章で詳述したが、以下、補足して主張する。
第1 明治23年時点での立法者意思について
1 原判決は、「旧民法373条から国家責任に関する字句が削除されたことは、少なくとも公権力の行使に基づく国家責任を否定する立法者意思の表れであるとみる」(23頁)と判示するが、相当ではなく誤解である。
2 この点は、まず、『日本近代立法資料叢書』など、立法過程での議論を少しでも参照すれば明白になる。旧民法制定時に、立法者は国家責任を否定する立場で一致していたわけではなく、要するに、諸種の意見が存在するために、さしあたりボアソナード草案から一歩後退して、何も規定しないというところに落ち着いたのである。
したがって、国家責任を否定する規定も設けられなかったのである。この点は、旧民法制定後に、引き続き国家責任の問題が議論され続けていたことによっても裏付けられる。すなわち、現行民法715条制定時の議論において「官吏ノ過失行為ハ政府ガ代ツテ賠償スルカドウカト云フ問題」が「大問題」として議論されていた(穂積陳重など)のである。
3 次に、原判決は、状況証拠として井上毅の「意見」を挙げているが、井上が立法者を代表していたわけでも、その意見が支配的な見解を形成したわけでもないし、また、井上の「意見」をみても、国家責任を全面的に否定していたわけではない。
彼は、国庫上および私法上の国の行為については賠償責任の成立を認めており、賠償責任を否定すべき「国権ヲ執行スル官吏ノ処置及怠慢」と上記の行為との区別の基準は不明なままであった。
4 さらに、「旧民法373条から国家責任に関する字句が削除されたこと」は、大審院判例にまったく影響を与えなかった。
国賠法における「従前の例」は、原判決では「大審院判例の例」を指すものとして用いられているが、仮に上記のような立法者意思が存在したとしても、「従前の例」ではまったく無視されている。
5 以上、要するに、立法者意思に関する原判決の認定は無根拠かつ誤解であり、また、「従前の例」とはつながりがないものを賠償責任否定の根拠として援用している点で、違法な判断である。
第2 戦前の大審院判例について
1 原判決は、「戦前の大審院判例は、……公権力の行使(権力的作用)による損害については一貫して国の賠償責任を否定していた」(23頁)と判示するが、誤りである。
2 まず、「公権力の行使」という概念は戦後の国家賠償法の下でつくられた概念であり、大審院判例における権力的作用を示す概念(「統治権ニ基ク権力行動」等)は、これと比べると極めて狭い概念であることを確認しておく必要がある。
つまり、大審院判例で国の賠償責任が否定されていたのは、かなり限定的な場合であった。賠償責任が否定されていたのは、個別法の解釈によって「統治権ニ基ク権力行動」等が明確な場合だけであって、原判決のように、この点の検討を行わず、包括的に「権力的作用」を認定するのは大審院判例(=従前の例)に違反する。
3 次に、大審院は決して「一貫して」はいなかった。
たとえば、国の責任を否定した大判1910(明治34年)・2・25(板橋火薬製造所事件判決)は、その後の大審院判決において判例として扱われていない。国側は、その主張においてたびたび板橋事件判決を援用したが、大審院はその援用を拒否してきたのである。
大審院判例を真摯にたどれば、判例と言えるようなものが確立するのは、1941年(昭和16年)のことであって、大審院は、そこに至るまでの間、国に対する損害賠償事件に民法を適用すべきか否か、および何が「権力的作用」に該当するかをめぐって紆余曲折を経てきたのである。
加えて、最三小判1950(昭和25)・4・11は大審院判例を摘示することもなく、またその検討をしてもいないので、「従前の例」の判例とみなすことはできない。
4 以上、要するに、原判決は、大審院判例を自ら確かめることもなく、そして「判例」の内容をまったく無規定のまま判断の根拠としている点で、「従前の例」によるものということはできず、違法である。
第3 権力的作用の非該当性について
1 原判決は、「本件細菌戦は、旧日本軍がその存在目的そのものである戦闘行為として行ったものであるというのであるから、その行為は公権力の行使(国の統治権に基づく優越的な意思の発動としての強制的・命令的行為)そのものであり、当時民法の適用対象となっていた非権力的作用に分類されるということはできない」(24頁)と判断している。
しかし、大審院判例を参照すると、本件のような細菌の使用行為が「国の統治権に基づく優越的な意思の発動としての強制的・命令的行為」とみなせるかどうかは疑わしい。
2 まず、日本軍の行為のすべてが「国の統治権に基づく優越的な意思の発動としての強制的・命令的行為」になるわけではない。大判1932(昭和7)・8・10(軍療養所用鑿井工事事件判決)が示すように、軍隊の行為も国家賠償の対象となる。
3 次に、この種の国際法違反の行為(細菌による人体実験の行為および細菌を散布した行為)について、当時の政府や日本軍がこれを「統治権に基づく行為」と主張することはあり得なかったはずであって、したがって、戦後の裁判所が勝手にこの種の行為を「統治権に基づく行為」だと認定するのは、「従前の例」を踰越している。
少なくとも、この種の行為の性格づけは大審院において「判例」として示されていないのであるから、「従前の例」に含めることはできず、したがって、原判決の判断は「従前の例」に基づかない恣意的な判断といわざるをえない。
4 なお、原判決は、「原告らの主張は、軍隊を土地の工作物(民法717条)や小学校の校庭に設置された遊具と同視するものであって、採用することができない」としているが、これも、「従前の例」に基づかない判断だといえる。
大審院は動産に起因する国の損害責任を認めており(大判1918(大正7)・10・21=小学校梯子転倒事件判決)、また工作物の設置・管理に係る行為についても損害責任を認めている(大判1925(大正14)・12・11=水利組合樋管閉鎖事件判決など)のであるから、軍隊の工作物たる兵器類に起因する被害についての賠償責任は、むしろ国の責任の範囲内に入りうると解するのが大審院判例の素直な理解である。
5 付言すれば、仮に目的が戦闘行為であったとしても、そのことをもって「統治権に基づく行為」とみなす解釈を採らないのが大審院判例の立場である。
大審院判例によれば、法令に基づいて当該行為が「優越的な意思の発動としての行為」とみなせるか否かが国の賠償責任の成否の基準なのである。
本件細菌戦において、このような法令を見出すことはできないし、また原判決はこの点の検討をまったく行っていない。
仮に原判決が大審院判例に即したものであり「従前の例」に合致するものだと主張するならば、原判決は、「公権力の行使はそれぞれの根拠となる我が国の法律に基づいて行われるものである」(20頁)という判断に即して、本件のような細菌兵器の実戦使用が日本のいかなる法律に基づいて行われたのかを論証しなければならなかったはずである。このような論証は原判決中に存在していない。
6 以上、要するに、原判決は、「従前の例」に基づかずに自己固有の判断を下しているにもかかわらず、これを「従前の例」に基づいているかのように偽装している点で違法である。
第4 日本の主権下にない外国人について
1 原判決は、「日本人も外国人も等しく国家無答責の法理の適用を受けていたものと考えられる」としているが、これは国家無答責の法理を誤解したものである。
2 たしかに、日本の主権下にある外国人について「国家無答責の法理の適用を受けていたもの」ということは可能であるが、日本の主権下にない外国人について、このようにいうことはできない。
つまり、外国人一般が問題なのではなく、日本の主権下にある外国人であるか否かが問題なのである。
そして、日本の主権下にない外国人と日本軍との間に公法上の関係が存在していなかったことは明白であるから、国家無答責の法理を適用する余地はない。
3 結局、国家の統治権の及ばない外国人との関係、国家の法秩序の及ばない外国の地には、国家無答責は適用されないのであって、原判決は、問題の設定を誤解して、誤った判断に至っている。
第5 結語
以上の通り、国家無答責の法理の判断に関する限り、原判決は違法なものであって、取り消しを免れない。
以 上

|