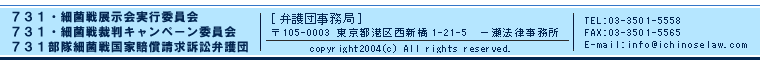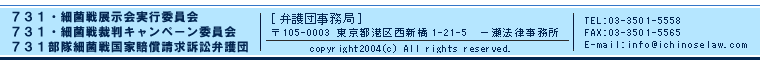|
�Ӓ�ӌ���
���Ӓ�ӌ����̃��j���[�ɖ߂�
�����Ԃ̐푈�������ɂ��Ă̈ӌ���
�|�������O�����j�̌������猩��|
�֓��w�@��w�����@�@�@�u�@�@�@�@���@�@�@�@�R
�ځ@��
��P�@�����������̌�����
�P�@���{���̌����ɂ���
�Q�@�������̌����ɂ���
�R�@���������{�̉��߂̈Ⴂ�ƃR���Z���T�X�̕s��
��Q�@���ؕ��a���̈ʒu�t��
�P�@���ؕ��a���̐��i�\�\�u�a���̐��i�����Ă��Ȃ�
�Q�@���؏��ɂ��푈�I���Ɛ푈�������
��R�@�������������̈ʒu�t��
�P�@���𐳏퉻�O�����Ɠ��؏��̈���
�Q�@�������̏����Ɛ������̖��ɂ���
�R�@�������������́u���r�v
�S�@�������a�F�D���́A���a���ł͂Ȃ�
�T�@�����Ԃ̊O���̖��_
�U�@�푈�ƍ߂ɂ���Q�������̎������Ɛ푈�◯���
��S�@�^�̘a���̂���
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@
�쐬�ҁ@�u���R(Yin�@Yanjun)
1990�N���{���w�A94�N�ꋴ��w���m����ے��C���A95�N���m��(�Љ�w)�擾�A�ꋴ��w�Љ�w������A���{�w�p�U������ʌ�����(Post-Doctoral
fellowship)���o�āA1999�N������J��w�����w�������A2001�N�n�[�o�[�h��w�q��������(Visiting
Scholar)�A2002�N4���Ȍ�֓��w�@��w�������B��U�@���ې����E�����ĊO���j�E���k�A�W�A�n�挤��
��v�ƐсF�����w�����푈�������x(�䒃�m�����[�A1996�N)�A�W�_���u�g�c���ȂƑ�p�v(�w���ې����x110���@1995�N)�A�u�������W�ɂ�������ؕ��a���̈Ӗ��v(�w���j�w�����x1998�N5��)�A�u����p�̈��S�ۏ�ɂ�����č��̐���̕ϑJ�ƒ����̑Ή��v(�w�A�W�A�����x��45��3���@1999�N11��)�ȂǑ����̘_���\�B
��U�F�n�挤���E���ې����E�����ĊW�j�B
���ؕ��a��� (�ȉ����؏��Ɨ���)�������A�������𐳏퉻���Ȃǐ������ĊO���j�𒆐S�ɁA�������d�˂Ă����B
�@�@�@�@�@�@�@
�����{�ƒ����Ƃ̊ԂɁA�����W�ɂ��Ă̏d�v�����͎l����B
�܂�A1952�N4�����{�Ƒ�p����*1�Ƃ̊ԂɌ��ꂽ���ؕ��a���*2�A1972�N9��29�����{�����{�ƒ������{�Ƃ̊ԂŔ��\�����������������A1978�N8��23�����{�����{�ƒ������{�Ƃ̊ԂŌ��ꂽ�������a�F�D���A1998�N11�����\���ꂽ���������錾�ł���B
���̂����A�����Ԃ̐푈�����A�������������ȂǂɊW���Ă��镶���́A�O�̎O�ł���B�{�ӌ����́A�����̕����������Ԃ̐푈�������ǂ̂悤�ɋK�肵�Ă��邩�A�����Ԃ̐푈�����A�������Ȃǂ͉ʂ����ĉ����ς݂ɂȂ����̂��A�ɂ��Č���������̂ł���B
��P�@�����������̌�����
�P�@���{���̌����ɂ���
�����푈�������Ɋւ���{�i�I�Ȍ����͂���قǑ����͂Ȃ������B��ԍŋ߂̌����Ƃ��ĐΈ䖾���ҁw�L�^�ƍl�@�������𐳏퉻�E�������a�F�D���������x(��g���X�A2003�N)������B���̒��̘_���u���ؕ��a����������������𐳏퉻�ցv�ŐΈ䖾���́A�u���؏��������Łw���{�͔�������Ƃ����Ă��邪�A��p�����P�ӂŁA�����������������x�Ƃ�����|�̈ĕ�(��p����)����������Ȃ��Ƃ��āA��������͍Č����w�����A��p���͏������d�ˁA�ŏI�I�ɂ܂Ƃ܂������{���A�c�菑�A���������ɂ͔����Ƃ������t�͓����Ă��Ȃ��B�u���ӂ��ꂽ�c�L�^�v�̍Ō�ɁA�u���ؖ����͖����������I�ɕ��������v�Ə������ɂƂǂ܂��Ă���B
�܂��u���{���͒��ؖ����������嗤�̎匠��L����A�Ǝ����\�������邱�Ƃ͋��ۂ����B�K�p�͈͂ɂ��Ă���p�������������v(362�]63��)�B�u���ؕ��a��������A�����嗤�ł̐푈��Ԃ��I�������A���ؐl�����a���Ƃ̊W���퉻���͂��邱�Ƃ͕s�\�ɂȂ�B�g�c���t�́A�����̒������A�K�p�͈͂����肵�A���ؐl�����a���Ƃ̊W�ɂ����Ă͔����ł���v�Ǝw�E����(368��)�B
����Ɂu���ؕ��a���͕��a���Ƃ������i��A���̍X�V�E�p���̎葱�����߂����Ȃ��B���̂��߁A�O���̋L�҉�ł̐����Ƃ����`���ɂ���Ă������I���ł���A�ƍl�����킯���v�Ɠ��{���{�̍l����_�����B
�܂��c�����F�w�����W�@1945�]1990�x(������w�o�ʼn�A1991�N)�́u���؏��͈�ɑ�p�����Ƃ̊Ԃ̊W�ɂ����Ĉ�v�����̂ł���A���������ɂ��Ă̊W�͂Ȃ��̂ł���܂��v�ƌ��y�����B
���{���ۖ@�w��ҁw���ۖ@���T�x(�����o�ʼn�A1975�N��)�́u���ؕ��a���v�̍��́A�u�ő�̓����͍������{�́g�x�z���Ɍ��ɂ���A�y�э������ׂ����ׂĂ̗̈�h�ɓK�p����Ƃ�����������ł���B���̂��߂ɁA���{�ƒ����̐푈��Ԃ����S�ɏI��������ۂ��ɂ��Ă��^�₪�c���ꂽ�v(����Y��A526��)�Ƃ���B�������w���ۊW�@���T�x(�O�ȓ��A1995�N)�͓��؏��ɂ��āu���؏��ɂ����41�N12��9���̒����̊J��ʍ��ɂ���Ĕ������������Ԃ̐푈��Ԃ͖@�I�ɏI�������v�u������(���͓K�p�͈͏�)�����{�̎x�z���ɂȂ������嗤�Ɋւ��ċ^�`���c�����v(���R�ΗY)�Ƃ���A���{���{�̉��ߖ����������ɂ��Ă���B�܂��u�u�a���v�̍��́u�ϑԓI�ȕ����A�葱�C���{�ƒ��ؖ����Ԃ̍u�a���́A���ؐl�����a�����{�̓������ɂ͋y��(��������1��)�A��ɓ��{�ƌ�҂Ƃ̋����������@��ɐ푈��ԏI���A���𐳏퉻�v(���]�[�l�Y�A239�]40��)�Ƃ��Ă���B
�܂�A���؏��̓K�p�͈͂Ɋ܂܂�Ȃ������嗤�n��Ƃ̐푈��Ԃ̏I����錾���邱�Ƃ͂ł��Ȃ����Ƃ��w�E�����̂ł���B�����u�����������@��ɐ푈��Ԃ̏I�����s�Ȃ����v�Ƃ����\���͞B���ł���A���ۂ̋��������ɂ͐푈��ԏI���̐錾�͂Ȃ������B
�Q�@�������̌����ɂ���
���w���w���㒆���W(1945�]1994)�x(�����o�ŎЁA1995�N)�A�Ѝ��ˁE�g�������w�����R�푹���o�������n���x(���J�l���o�ŎЁA1995�N)�A�������Ғ��w���F�Γ������I���x(�������ە����o�Ō��i�A1997�N)�A�͐��B�w�����ԓI�푈�������x(蟐��l���o�ŎЁA1999�N)�A�������w�����Γ������^�����M�𐳏퉻(1945�]1972�N)�x(�����o�ŎЁA2000�N)�Ȃǂ͂�������������ƊԂ̐푈�������́A1972�N���������������Ă͂��߂ĉ������ꂽ�Ƃ��Ă���B
�����A���Ԕ����������ɂ��ẮA��������Ă��Ȃ��Ƃ����̂���Ș_���ł���B�Ⴆ�Ίnj����u���������������ɂ��Γ������������������Ɋւ��錤���v�Ȃǂł���B�܂��A��ʖ��Ԑl�̊Ԃł́A�������̐푈��������肪�������̂܂܂ł���Ƃ����F���́A��ʓI�ɑ��݂��Ă���B
�R�@���������{�̉��߂̈Ⴂ�ƃR���Z���T�X�̕s��
����܂łɓ��{���{�́A�u��сv���ē��؏��������ē����Ԃ̐푈��Ԃ��I�����A�푈�����Ɋւ��鏔���͓��؏��ɂ������ς݂ł���Ǝ咣���Ă����B����A�������͏I�n��т��āu���؏��v�̖������咣���A���̓��؏��̑��݂ɂ�蒆���W�́A�Q�O�N��(1952�\1972�N)���A���퉻�ł��Ȃ��܂ܐ��ڂ��Ă����B
���{���̎咣�̍����Ƃ��đ啽�O���͍��𐳏퉻������ڂ̎�]��k(1972�N9��25��)�Ŏ��̂悤�ɔ��������B
�u�����������́i���j����s�@�ɂ��Ė����ł���Ƃ̗�����Ƃ��Ă��邱�Ƃ��\�������ł���B�������A���̏��͍���̋c���Đ��{����y�������̂ł���A���{���{���������̌����ӂ����ꍇ�A���{���{�͉ߋ�20�N�ɂ킽���āA�����ƍ�����x���������Ƃ��������������˂Ȃ�Ȃ��B�����ŁA���ؕ��a���͍��𐳏퉻�̏u�Ԃɂ����āA���̔C�����I�������Ƃ������ƂŁA�������̌䗝�������v�B
����ɑ������������́u�c���E�啽����]�́A�������̒����g�����O�����h*1���\�������ł���ƌ������B����͗F�D�I�ȑԓx�ł���*2�v�Ɖ������B
����ڂ̎�]��k�Ŏ����������́u�o���̊O���W�����̖��ɁA�������K�`���(�}�})*3������ƁA��肪�����ł��Ȃ��Ȃ�B�����F�߂�ƁA�Ӊ�������ʼn�X���@�ɂȂ邩�炾�B�����ŁA�����́g�O�����h���\���������邱�Ƃ���b�ɁA���{���{�����ʂ��鍢��ɔz���������邱�Ƃɂ������v�Ɠ��{���ւ̔z�����������B
�����ōł��d�v�Ȃ��Ƃ́A���{���{�́u�����O�����v�ւ̑ԓx�\���ł���B���{���{���������̎O������ے肹���\���������邱�Ƃ́A�����W���퉻�̑�O��ł���A�����W�̊�b�ł������B
���ǁA�������������͒��ړI�ɓ��؏��Ɍ��y�����A�u���{���́A���ؐl�����a�����{����N�����g�����O�����h���\���������闧��ɗ����č��𐳏퉻�̎������͂���Ƃ����������Ċm�F����B�������́A��������}������̂ł���(�O���u�푈�̔��ȁE�����O�����v)�v(�w�Z�@�S���x���)�A�����1972�N9��29�������������������\���ꂽ��A�啽�O���̋L�҉�Łu�������𐳏퉻�̌��ʂƂ��ē��؏��̑��݈Ӗ��͎����I�������v�Ɠ��{���̈���I�ȑ[�u�Ƃ��ē��؏��̏I����錾�����B
�܂����{�O���Ȍ��J�������疾�炩�ɂ��ꂽ�悤�ɁA�������́A�������������ɂ����ē��؏��Ɍ��y���Ȃ����Ƃɓ��ӂ����̂́A���{�����������́u�����O�����v���\���������邱�Ƃ��O��Ƃ������߂ł���A�t�Ɂu���ؐl�����a���́A���̎�|���\������������A�������������ɏ��������v�Ƃ����퍐�̎咣(���{���{�̒����l���Ԕ����i�ׂł̎咣)�ł͂Ȃ����Ƃ��͂����肳���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�u���������\������������v�Ƃ����퍐�̎咣�ɂ́A���̍����i�����j�͂Ȃ��̂ł���B
�����ē��{���̑[�u�ɂ͈ȉ��̈Ӗ�������B
��A���؏����I�������邱�Ƃɂ��A����܂łɌ����������؏��L���̌������т����B�����A���̗L�����́A1952�N8��5��(������)����1972�N9��29���I���܂ł����Ȃ����Ƃ��Ӗ�����B�܂肻�̗L�����͌���I�ł���B
��A���؏��̏I���ɂ��A�������̕����O�������\���������闧��������A�������̗���ɔ��A�ے肵�Ȃ����Ƃ��Ӗ�����B
�O�A���؏��̂�����̓����҂ł����p���ǂւ̔z�������Ȃ��A����I�ȑ[�u�Ƃ��đ���Ƃ̊O���W�����S�ɒf�����̂ł���B���{���ɂ́A���؏����I��������@�I�葱����������Ă��炸�A�@�I�������R�����ƌ��킴��Ȃ��̂ł���B
�ȏ�̕��͂ŕ�����悤�ɁA�����o���ɂ͓��؏��ɑ����{�I�ȔF���ɑ傫�Ȋu���肪����A�Ō�܂Ō����̈Ⴂ��₤���Ƃ͂ł��Ȃ������B
��Q�@���ؕ��a���̈ʒu�t��
�P�@���ؕ��a���̐��i�\�\�u�a���̐��i�����Ă��Ȃ�
�i�P�j�u�܂��͐����Ԃɔ��������푈��Ԃ��I�ǓI�ɏI�~���A���a�̐���W�����A���킹�Ă���Ɋւ����{�I�������߂��u�a���ł���v�ƒ�`�����B�u�a���̗v���Ƃ��āA�푈��ԏI���̐錾�A�̓y�A�����Ȃǂ̏����̏����͕K�v�ł���B
�����������Ԃ̐푈�́A���{�Ƒ�p�Ƃ̐푈�ł͂Ȃ��A���ۂɐ푈��Ԃɂ������̂͒����嗤�Ƃ̊Ԃł���B1949�N10���̒��ؐl�����a���̐����ŁA�u���ؖ����v�̏��ł�錾����A�����Ɋւ���u���ؖ����v�̂��ׂĂ̎匠�A�����Ȃǂ����ł��Ă��܂����B
����A���������ɂ͍u�a���Ƃ��������̏��v�������ׂĖ������������͑��݂��Ă��Ȃ����Ƃ͎��m�̂Ƃ���ł���B�܂��A���؏��̏��K�p�͈͏����ɂ��A�������Ƃ̏����͂Ȃɂ������ł��Ȃ��B���{���́u���؏��̒������ꎩ�̂͗L���ł���v�Ǝ咣���Ă��邪�A�Ō㎩���I�ɂ�����u�I���v�����B�܂莖����̔j���ł���B
���������a���͂��̐��i��A�푈�̍ĊJ���Ȃ�����A�L�����͖������Ȃ��̂ł���A���̈���I�Ȕj���́A�푈��Ԃ̍Đ錾�ɓ��������̂ł���B���������āA�������{���{���{���ɓ��؏������a����ƔF�߂�Ȃ�A�����u�y���v�Ɂu���a���v��j�����A�푈�ĊJ�ɓ������s�ׂ��s�Ȃ����Ƃ͂ł��Ȃ��B
���������u���a����v��j������s�ׂ́A���{�����@�����u�푈���������v�ɂ������Ɉᔽ���邱�ƂɂȂ�B
���������āA���؏��ɂ��ẮA���{���͈���I�ȏI���ɂ��A�݂�������؏��́u���a���v�Ƃ������i��ے肵�����ƂɂȂ�B
�i�Q�j���؏��̏��K�p�͈͏���
���̌���������ꍆ�Ƃ��āA�u���̏��̏������A���ؖ����Ɋւ��ẮA���ؖ������{�̎x�z���Ɍ��ɂ���A�܂��͍�����邷�ׂĂ̗̈�ɓK�p������v�|�̗������������B���̏��K�p�͈͂Ɋւ���Ӗ��A�����̍쐬�ߒ��͎��̂Ƃ���ł������B
���؏��������ɂ�����A���{�����A�����J�����������߂Ă����̂́A���̏��K�p�͈͂̌���ł������B�ŏ��Ӊ�\�\��p�����́A�������S�����́u��\���{�v�ł��闧�ꂩ�狭�����ۂ��A��R�����������A���{�Ə������Ԃ��߂ɂ́A���̂悤�ȁu���J�I�v�Ƃ������������������ꂴ��Ȃ������B
�������M�҂̌����ł́A���̏��K�p�͈͏����́A�Ӊ������쐬���A�A�����J���ɒ����̂ł���B�܂���p���̏��K�p�͈͈Ă��āA�_���X�č��Γ��u�a��g�����{���Ɍ����āA�ŏI�I�ɂ́u�g�c���ȁv(1951�N12��24���t)�̌��e�ƂȂ����̂ł���B
���{���{�͂��̋g�c���Ȃɏ����ꂽ�u���K�p�͈́v�Ɋ�Â��A��p�����Ƃ̏��������ɗՂB�������̒��A���{���S���́A�g�c���Ȃ̓��e�A�܂��̏�����������ꍆ�̓��e�ɂ��Ĉꕶ���̏C���������Ȃ��Ƃ��������p���������A�Ō�܂œ���Ԃ̑傫�ȕ����_�ł������B
���m�̂悤�ɁA���K�p�͈͂ɂ�萧������Ă���ʂ�A��p�����́A���̏��̔�������u�I���v�܂ŁA��p�E�O�Βn�悵���x�z���Ă��炸�A�����{�y�ւ̎x�z�͂Ȃ������B�ܘ_�A���؏��������{�y�ɂ͓K�p�ł��Ȃ����Ƃ͖����ł���B
�܂��A�O�q�̂悤�ɁA���ؕ��a���͌���I���i���K�p�͈͏����ɂ��j�ł���A�����嗤�ɂ͋y�Ȃ����Ƃ͓��{���̍��ۊw�E�ł��F�߂Ă���B���Ȃ݂ɂ��̓��؏�����b�ɂ��āA�S�����Ƃ̐푈��Ԃ̏I����푈�����Ȃǂ̏������������邱�Ƃ�����ł��Ȃ����Ƃ����炩�ł���B
����ɔ퍐�����咣���Ă���悤�ɁA���؏����������g�c�Γ��t�|�ł��̐S�ȏ����������̓��{���{�́A�u��сv���đ�p�����\�\�u���ؖ����v��S�����̑�\���{�Ƃ��ď��F�����̂ł͂Ȃ��A��p������S�ʓI�ɏ��F�������̂ł͂Ȃ��A���؏��͂����܂ł������Ƃ̑S�ʓI�W��One
Step�ƌ��āA��p�����ɑ���S�ʏ��F�͂��Ȃ����������Ă����B�g�c���t�Ƃ��Ă͒����Ƃ̊W���l�����A����Ƃ̊W���P�̗]�n���c�����Ƃ����̂ł���B�����Č�̔��R��Y���t���������������Ă����̂ł���B
�ȏ�̏����Ɋւ���ڂ������́A�ٍe�u�g�c���ȂƑ�p�v(�w���ې����x��110��1995�N10��)�A�u�������W�ɂ�������؏��̈Ӗ��v(�w���j�w�����x1998�N5����)�A�����w�����푈�������x(�䒃�m�����[�A1996�N)�����Q�Ƃ��ꂽ�����A��v�Ȃ��̂Ƃ��Ď��̗�������邱�ƂƂ���B
1952�N5��30���ѕS�Y(���Y)�c���́u�T���t�����V�X�R�u�a����14���Ɋ�Â����{���̒�������́A����͕�������Ƃ��Ȃ������������ؖ����͂����Ă���̂ł���܂����A����͒����嗤�S���ɑ���������������Ƃ������Ƃ������Ă���̂ł����v�Ƃ̎���ɑ��A�Ό����s�Y�O�������́u�d�˂Đ\���グ�܂����A���̏��ɂ͗шψ�������ꂽ�悤�ȗ\���Ɨ\��Ƃ������悤�Ȃ��Ƃ͉��炢�����Ă���܂���v�Ɠ����A�`���p����ǒ��́u���܂��w�E�̋c�菑�P��(b)�̊W�ł������܂����A����͒��ؖ����Ɋւ�����肱���������ӂɂ����Ƃ������Ƃł������܂��v�Ƒ�p�n��Ɍ��肷�锭���������B
6��18���A�Q�c�@�O���ςŁA�]��v(�Љ�}�E�h)�c�����u�g���{�ƒ��ؖ����Ƃ̊Ԃ̐푈��Ԃ̏I�����ǂ�قǂ̌��͂��ǂ̒n��ɑ��Ď����ɂ��āh����������S�ʓI�������͂����肵�����������Ē��������v�Ǝ��₵���̂ɑ��A�`���ǒ��́u�Ⴆ�g���{���ƒ��ؖ����Ƃ̊Ԃ̐푈��Ԃ́A���̏���͂�����ɏI������h�Ƃ������Ƃł������܂�����Ƃ��A���ۖ��Ƃ��āA�����������Ƃ����������ł́A�r�������̏�ԂƗ���Ă��܂��B�Ⴆ�Β��ؖ������{�̎x�z���ɂȂ��n���ɂ����čs�Ȃ�ꂽ���ƁA���͋N�����������Ƃ������Ƃɂ��Ē��ؖ������{���ӔC���Ƃ�Ȃ���Ȃ��Ƃ����悤�Ȃ��Ƃ������邩������Ȃ��B����͎��͍����Ƃ����C����������킯�ł���܂��B�]���Ă��̎x�z���ɂȂ��n��ł����������ƁA��͂肻���������ɂ��Ă͌����̎��ԂɈ����߂��Ă����Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ƃ������Ƃł���܂��āA�K�p�͈͂̂Ƃ���ɁA���������ɂ���܂��悤�Ɍ��肵���Ƃ����悤�Ȃӂ��ɉ��߂����Ă���܂��v�Ɠ������B
����ɉ��菟�j�O���́u����̏��ɂ����܂��ẮA���荑�̓��p�u���b�N�@�I�u�@�`���C�i�Ƃ������̂ŁA���������̑��i�ɂ���̂̓`���C�i�ł���B���������Ⴂ�͉�X���F�߂Ă���܂��B���ꂪ�ǂ������ӂ��ɔ��W���Ă������́A����͈�̐�����ɂ��Ǝv���܂�����ǂ��A�v����ɂ��̋g�c���Ȃ̎�|�ɂ��܂��ă`���C�i�Ƃ̊Ԃɂ͋��ɂɂ����Ă͑S�ʓI�ȊW��ł����Ă����B�����Ō��݉\�Ȃ̂̓��p�u���b�N�@�I�u�@�`���C�i�Ƃ�����W�ɓ��邱�Ƃł���v�Ƒ�p�����ւ̌��菳�F��F�߂��B
6��26���A�]��c���̎���ɑ��A�g�c�Α����́u���؏��̒����͏��������Ƃ̑S�ʓI�Ȑ����I�A�o�ϓI�W�����Ԃ܂ł̃����X�e�b�v�ł���v�Ɠ��ق��A���؏��̌��E��F�߁A�]��c���́u������_�ł��B���̏��ɂ���ē��{���{�͂��̒��ؖ����������{�Ƃ������̂�S�ʓI�Ȓ����̎�l�Ƃ��ď��F�������̂ł͂Ȃ��B���̓_�͑����̂͂����肵�����l�����A�C�G�X�E�I�A�E�m�[�ł������肢�܂��v�Ƌ��߁A�g�c�́u����͏��ɂ��͂����菑���Ă���܂����A���ɒ��ؖ��������̎x�z���Ă���y�n�������ؖ����Ƃ̊Ԃɏ��W�ɓ���B�����͏����ł���܂��B�����ĖړI�͏I���Ɉꒆ���S�̂Ƃ̏��ɓ��邱�Ƃ���]���Ă�܂Ȃ��̂ł���܂��v�Ɠ������B�]��́u�����A����ƌ����A�S�ʓI�ȏ��F�ł͂Ȃ��Ƃ������Ƃł������܂��傤�v�Ƌl�߁A�g�c�u�����������Ƃł��v�Ɓu����̗]�n�̂Ȃ����t�v*1�ő�p�����ւ̌��菳�F��F�߂Ă���B
�܂�A���؏��������{���{�͑�p�����ɑ���S�ʏ��F�ł͂Ȃ��A���菳�F�ł��邱�Ƃ���؏��̌��萫���F�߂Ă����̂ł���B�܂���p����(�u���ؖ����v)�͓��{���{����݂Ă��ŏ����獑�ۖ@��̓����҂Ƃ��Ă��s���i�ł������B
��������u���ؖ����v(��p����)�������̍����Ƃ��ĔF�߂Ȃ����{���{�́A�ǂ����Ă��̐����Ƃ̊ԂŌ��ꂽ�u���v�������đS�����Ƃ̐푈���������ł���̂ł��낤�B�����S�������\�ł��Ȃ��Ȃ����u���ؖ����v(���{���{�����F��������)�ƌ��ꂽ���؏��́A���{�����{�ƒ����̈�n�������\�\��p�����Ƃ̊ԂŁu�n��I�ȁv���i�����Ȃ��̂ł���B���{���{�́u�푈��Ԃ̏I���A�����A���Y�y�ѐ������̖��͈�x����̏����s�ׂ��v�ƍl���A�u���ؖ����v�Ƃ̊Ԃł�������������Ǝ咣�������A����������u���ؖ����v��S�����̑�\���{�Ƃ͔F�߂Ă��Ȃ������B�܂����؏��̓K�p�͈͏����������āA���{���ƒ����Ƃ̊Ԃœ��؏��ɂ��A�푈���������́u��x����̏����v�͂ł���͂����Ȃ������̂ł���B
���؏��̓K�p�͈͐���ߒ����݂Ă�������悤�ɁA���{���{�͂܂��ɂ��̓K�p�͈͂̐ݒ�ɂ��u���ؖ����v�𒆍��̈�n�����{�Ƃ����F�߂��A�����S�����Ƃ̊W���퉻�����߂Ă����\��ł������B���܂���u��т��ē�������v�u���ؖ����v��S�ʏ��F���Ă����Ǝ咣���邱�Ƃ́A����܂ł̓��{���{�̓��ًy�юj���Ƃ͑S������Ă���A���\�Ȏ咣�ł���ƌ��킴��Ȃ��̂ł���B
�u�K�p�͈́v�����̓��e���Ƃ炵�Ă��A�����̒������̂������݂Ă��A���͈̔͂����؏��̂��ׂĂ̏����ɓK�p����邱�Ƃ������߂ł��Ȃ��̂ł���B���̏��K�p�͈͏����́A�����{�̑Β�����́u�����v�Ƃ��Ă��u�g�c���ȁv(1951�N12��24���t)�̊j�S�I���e�ł���A���{���{�����؏��������ߒ��ɂ����čł������������e�ł�����B�������{���{�������u���ؖ����v��S�ʏ��F������肪����A���̏��K�p�͈͏����̐ݒ���Ȃ������̂ł���B
�i�R�j���؏��́u���r�v
���؏��́u���r�v�͖����ł���B
���A�u���ؖ����v�A���Ȃ킿�u�������{�v�Ƃ������\�̏�ɗ������ƒ������������W�𗥂��悤�Ƃ�����ł���B���̋��\���ɂ��āA�������瑽���̔ᔻ�Ƌ^�₪�ĂыN������Ă����B
���A�u���ؖ����v�ɑ��A���ė����́A���K�p���������v���A���؏��̗L�����𐧌������悤�Ƃ����̂ł���B���̌�������ɂ��A���؏��́A�u���ؖ����v�Ɋւ��ẮA�I�n��p�E�O�Βn��Ɍ��肳��A�����{�y�ւ̓K�p�͕s�\�ɂ����B���̏��K�p�͈͏����́A��p���������咣�������̂ł͂Ȃ��A���{�A�A�����J�����������������̂ł���B�܂������ɓ��ɋ������Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂́A���{���́A�������̂Ȃ��ł��A����̏��R�c�̂Ȃ��ł��A���̏��K�p�͈͂ɂ������A���؏��̌��萫���d�v�������̂ł���B
��O�A�����̑�\���{�ł��钆�ؐl�����a�����{�́A���̓��؏��̗L�����ɂ��čŏ����犮�S�ɔے肵�A�����F�߂����Ƃ��Ȃ������B���ۖ@�̑��ݎ�`�̌����ɗ����A�W�Ɋւ�����́A�ꍑ�������F�߁A�ꍑ���ے肷����̂ł���A����͖����ɂȂ�A���Ȃ��Ƃ����̈�����������F������̂������ē����W�𗥂��邱�Ƃ͕s�\�ł���A�@�I�������Ȃ��̂ł���B
��l�A�S�������Ă��Ƃ��A���{���{���咣���Ă�����؏��̗L�������F�߂��Ă��A���̓K�p�͈͏����ɂ��A���{�́A�����̈�u�����{�g�D�v�A�����͈�̒n�������\�\��p�����Ƃ̊ԂŌ��ꂽ�����̈ꕔ���u�n�拦��v�ɂ����Ȃ����Ƃ��Ӗ�����ƌ��킴��Ȃ��̂ł���B
��܁A����ɂ��̂悤�Ȍ���I�ȓ��؏��ł͂��邪�A���{���{�̈���I�ȑ[�u�ɂ��I���������A���{���{�͎��炻�̏��́u���a���v�Ƃ������i��ے肵���̂ł���B
�Q�@���؏��ɂ��푈�I���Ɛ푈�������
�i�P�j�푈��Ԃ̏I���ɂ���
���؏������ɂ́A�u���{���ƒ��ؖ����Ƃ̊Ԃ̐푈��Ԃ́A���̏���͂�����ɏI������v�ƋK�肳��Ă���A�܂�1941�N12��9�����ؖ������Γ����z���������ʂƂ��āA����̐푈�I���錾������Ɗ֘A���Ă��邩�̂悤�Ɍ����A�ꌩ����Ȃ�́u�������v������悤�Ɍ����邪�A�������A���ꂪ�����Ƃ̐푈��Ԃ̏I���錾�ɂȂ�邩�͋^��ł���B
�O�q�̂悤��1949�N10��1���̒i�K�Łu���ؖ����v�̒�����\�������łɂȂ��Ȃ�A���ؐl�����a���͂��̂��ׂĂ̎匠�A�����Ȃǂ��p�������B�ꍑ�̎匠�͕������邱�Ƃ͂ł��Ȃ����Ƃ����ۖ@��̏d�v�Ȍ����ł���B�܂����{�ɂ悭����c�_�ł́A���{�͒��ؖ����Ɛ푈��Ԃɂ���A���ؐl�����a���Ƃł͂Ȃ��Ƃ������Ƃł��邪�A������傫�Ȗ�肪����B�܂�A����{�鍑���{�i1890�N��������{�鍑���@�ɂ��̐��j��1952�N�̎��_�ɂ͑��݂��Ă��炸�A���̌����A�����Ȃǂ��̂��ׂĂ͓��{�����{�ɂ��p������Ă���i1947�N5�������̓��{�����@�ɂ��̐��j�B
����Ɠ����悤�ɁA�����̏ꍇ�A���ؖ������璆�ؐl�����a���ւƐ����̈ڍs�Ɩ@�I�p��(1949�N10��)�͂������B�܂萭�̂̕ω����A���̑�\���鍑�Ƃ�ς��邱�Ƃ͂Ȃ��A���̌p�����{�́A�����o���Ƃ��������Ă���̂ł���B
����ɂ��̒��ؐl�����a���̑O�g�ł��钆�\�r�G�g���a�����{(1931�N�����]���Ȑ���)���������A1932(���a7)�N4��26���ɍ������{���9�N�������A����{�鍑���{�ɑ��A���z�����s�Ȃ������Ƃ͎��m�̒ʂ�ł���B
�����̌��ŕ�����悤�ɁA1952�N8��(���؏��̔���)�̎��_�œ��{���Ƌ��\�ɂȂ����u���ؖ����v�Ƃ̐푈��ԏI���錾�͒����嗤���J�o�[���邱�Ƃ͂ł����A�g�y���ʂ��Ȃ����Ƃ͖����ł���B����ɑS�����匠�̌p�����{�ł��钆�ؐl�����a�����{�Ƃ̊Ԃɍs�Ȃ���푈�I���錾�����A�͂��߂ē����Ԃ̐푈�I���錾�ƂȂ�A���̗L�������S�������J�o�[�ł���̂ł���B�c�O�Ȃ��Ƃɂ��̂悤�Ȑ푈�I���錾�͍����ɂ���������������̊Ԃɂ͍s���Ă��Ȃ��̂ł���B
�@
�i�Q�j�������Ɋւ���\���ɂ���
���؏��c�菑�Pb�ɂ́u���ؖ����́A���{�����ɑ��銰���ƑP�ӂ̕\���Ƃ��āA�T���t�����V�X�R����\�l��(a)�P�Ɋ�Â����{�������ׂ��̗��v�������I�ɕ�������v�ƋK�肳�ꂽ���A����������Ƃ��������������Ȃ������B���̕������A�S�����̑Γ��푈���������������ɓ�����邩�ǂ������A�܂��傫�Ȗ��ł���B
�@�悸�A�O�q�̂悤�Ɂu���ؖ����v�͂��͂�A�S�������\�ł��Ȃ��n�������ɂȂ�A�܂����؏��̓K�p�͈͏����ɋK�肳��Ă��Ȃ��n��\�\��p�����̎x�z���ɂȂ��n��܂ł��̌��͂��ł���Ƃ͔F�߂��Ȃ��B���̖@�I�ȍ�������ϖR�����Ƃ��킴��Ȃ��B
���A�����嗤���x�z���Ă��钆�ؐl�����a�����{�͓��R�A���̂悤�Ȏ挈�߂�F�߂����Ƃ͂Ȃ��B
�@�������A�O�q�̂悤�ɓ��؏��́A�����҂ł���u���ؖ����v���S�������\�ł��Ȃ��Ƃ����A���{���{�������F�߂Ă��鎖���ƁA���؏��̓K�p�͈͂ɂ��A���̂��ׂĂ̏����́A�����嗤�ɓK�p�ł��Ȃ��̂ł���A�����Ԃ̐푈�������������������Ƃ��邱�Ƃ͂ł��Ȃ������B
�����A���؏��̈ʒu�t���́A���̏��K�p�͈͏����ɐ������ꂽ�ʂ�A�����܂ł����{���ƒ�����p�n��̈�n�������Ƃ̊Ԃōs�Ȃ�ꂽ�u�n��v�I�Ȃ��̂ɉ߂����A�����Ԃ̍u�a���\�\���a���ł͂Ȃ����Ƃ͖��炩�Ȃ̂ł���B
�܂��A��㏉���A���{�̑Β�����́A��p�����Ƃ̊ԂŌ��ꂽ���؏��Œ����嗤�Ƃ̐����W��₿�A�A�����J�̑Β��������ߐ���ɉגS�����`�ŁA���\���̂Ȃ��Ɉێ����Ă����B1970�N��͂��߁A�A�����J�̐��E�헪�A�Β����傫���]���������Ƃɂ��i�j�N�\���E�V���b�N�j�A���{���{�����₩�ɂ���܂ł́u���\�v�ł������Β���������߁A����Ȃ�Ɓu���؏��v���I�������A�������{�ƍ��𐳏퉻�����߂��̂ł���B���؏��̏������@������킩��悤�ɁA���̏��ɂ͕��a���̐��i���Ȃ��A�C�ӓI�ɏI���ł��A�j���ł�����̂ɉ߂��Ȃ����ƁA����ɂ��A���{���{��������؏��́u���a���v�Ƃ����@�I�Ȑ��i��ے肵�A�����I�ȐF�����̋ɂ߂ċ��������ł��邱�Ƃ�������F�߂����ƂɂȂ�ƌ��킴��Ȃ��̂ł���B
��R�@�������������̈ʒu�t��
�P�@���𐳏퉻�O�����Ɠ��؏��̈���
�O�����̑�O���ɂ͓�����͔�@�ł���A�j�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��ƂȂ��Ă��邪�A
�������{�́A���{���{�́u����v���l�������`�ŁA���{���̎����I�ȏ����ɔC�����B
72�N9��28����l��ڂ̎�]��k�œc���p�h�����́u��p�͓������𐳏퉻��͐푈��
�Ԃɖ߂�Ƃ����Ă��邩��A���{�̑����Ƃ��Ă͍����Ă���v�ƌ������B�������́u����̋��������ɂ��A�������ŁA�푈��Ԃ̖��ɂ��A�\�����l�����̂́A���̓_�ɔz����������ł���v�Ƒo���̑Ë�����������B
�܂�A���{���́A���؏��̔j���ɂ����ʂ͏\���o�債�Ă���A�u���a���v�j���Ȃ�푈�ɓ��������Ƃł���̂́A�\�����m���Ă���B�܂��������́A���{���́u����v��z�����A�u�s����ȏ�ԁv�Ɋ������̂ł���B
�@���ǁA���{���́A���t�I�ɂ́A���؏���j�������̂ł͂Ȃ��A�I�������Ƃ����������œ��؏��̖����������������Ƃɂ��A�O�����̑�O���̗v���ɉ������̂ł���B�܂��O�����̑�ꍀ�́A����������u���ؐl�����a�����{�͒����̗B��̍��@���{�ł��邱�Ƃ����F����v�ƁA�O������́A����������O���A���ؐl�����a�����{�́A��p�����ؐl�����a���̗̓y�̕s���̈ꕔ�ł��邱�Ƃ��d�˂ĕ\������B
���{�����{�́A���̒��ؐl�����a�����{�̗�����\���������A���d���A�|�c�_���錾�攪���Ɋ�Â��������������v�i�w�Z�@�S���x�Q�Ɓj�ƁA���ꂼ�ꏈ�����A�������̐��퉻�O�����������̂ł���B
�i�P�j �����Ԃ̐푈��ԏI���錾�́u���Ӂv�͂ł��Ă��Ȃ��
�푈��ԏI���̐錾�ɂ��āA72�N9�����𐳏퉻���ɂ����āA���{���́A���؏������ɁA�����Ԃ̐푈��ԏI���̐錾�ɓ�F���������B���̂��߂ɁA�ŏI�I�ɂ͋��������̑O���Ɉȉ��̕������������ꂽ�B
�u�����l���͂���܂ő��݂����s����ȏ�ԂɁA�I�~����ł��Ƃ�ؖ]���Ă���B�푈��Ԃ̏I���Ɠ��������̐��퉻�Ƃ������������̊�]�̎����́A�����W�̗��j�ɐV���Ȉ�ł��J�����ƂƂȂ낤�v�Ƃ������Ƃŗ������������A���́u���ƂƂȂ낤�v�Ƃ����\���́A���ʌ`�ł���A��]�Ɛ����ɂ������A���R�A�푈��ԏI���̐錾�Ƃ͂Ȃ�Ȃ������B
�����A�u�푈��Ԃ̏I���c�Ƃ������������̊�]�̎����́A�����W�̗��j�ɐV���Ȉ�ł��J�����ƂƂȂ낤�v�Ƃ����������́A���̎��_(�����������o���ꂽ���_)�ŁA���������́A���̂悤�Ȑ푈��Ԃ̏I���͂܂����Ă��Ȃ����Ƃ��ӎ���������Ă���A���{���̐푈��Ԃ̏I���ςݎ咣�ւ̔ے�Ƃ����߂���Ă���(�������̎咣)�B
�����������o���̍��ӂ̂Ȃ����؏��ł́A�푈��Ԃ̏I���錾�̓��e�͂����Ă��A���������̍��ƊԐ푈�I���錾�ɂ͂Ȃ�Ȃ��B�܂����{���̈���I�ȉ��߂œ����Ԃ̐푈��Ԃ̏I����錾�������Ƃɂ͂Ȃ�Ȃ��B
����ɓ��{��������I�Ɂu���퉻�̌��ʂƂ��ē��{���͓��؏��̑��݈Ӗ��������I�������v��1972�N9��29���ɓ��؏��̏I���i�����j��錾�������Ƃ́A���؏��̏����u�푈�I���錾�v��ے肷��Ӗ�������ƍl������Ȃ��B�t�ɂ������؏��Ɂu���a���v�Ƃ������i������A���̏I���錾�́A�o�����܂��푈��Ԃɖ߂�Ӗ����܂ނƍl������B
���Ȃ��Ƃ������Ԃ̐푈�������Ɋւ��ẮA�K�����������ς݂Ƃ͂����ȒP�Ɍ�������̂ł͂Ȃ��Ǝw�E���Ă��������B�����o���́A�֘A�����ɑ��鋤�ʂ����R���Z���T�X�͂Ȃ��A�������ƊԂ̐푈��Ԃ̏I���┅�����������ɂ��ẮA���؏��������A���𐳏퉻��������݂Ă��A�o���F���̈Ⴂ�͋ɂ߂đ傫���A�����ς݂Ƃ͔F�߂��Ȃ��B���̖@�I�������R�����B
���{���́A(�푈�I���̎����ɂ���)�������𐳏퉻���ł́u����܂ł̓����W�ɑ���@�I�F���ɂ��Ă̑o���̗���Ɋւ��Č��������邱�Ƃ͕K�v�ł͂Ȃ��A�܂��A�\�ł��Ȃ��B����͂���Ƃ��āA����́A���������ԂɑS�ʓI�ɕ��a�W�����݂���Ƃ����Ӗ��ŁA�푈��ԏI���̎��������邱�ƂȂ��A�I���̎������m�F���邱�Ƃɂ���āA�����o���̗���̗������͂�����Ƃ̍l���ł����v(�����͕M��)�Ɖ�k�O�ł��p�ӂ����u�Β������v(���J�����ʎ��P)�𖾂炩�ɂ����B�܂�A���{���{�Ƃ��ẮA���O����푈��ԏI���ɂ��āA�����o���́u�@�I�F���v����Ɋւ��錈���͕K�v�ł͂Ȃ��\�ł��Ȃ��ƔF�߂��B�܂���������������d��Ȍ����Ƃ��ď���킯�ɂ͂����Ȃ��B���ʂƂ��āA���{���{�́A���݂�1972�N�������������������Đ푈��ԏI���錾���s�Ȃ����Ƃ����������̉��߂ɔ����A�F�߂Ă��Ȃ��̂ł���B���������������̕�����ǂ�ł�������悤�ɐ푈��ԏI���錾�Ƃ͌����Ȃ����A�܂������o���͐푈��Ԃ̏I���̎������m�F�������Ƃ�ǂݎ��Ȃ��B
���{���{�͂��܂��A���؏��Ɠ������������𗼗������A���́u�@�I�������v��ۂ�����Ƃ��Ă���B���������́A���̂悤�ȗ����_�Ɩ@�I�Ȑ������́A�s�\�Ȃ��Ƃł���B����̓����҂ł��钆��(�嗤)���Ƃ��ẮA���̓��؏��̍��@������x���F�߂����Ƃ͂Ȃ��������߂ɁA�����o���ɂ́A���؏��Ɠ������������Ƃ̗������ł��Ȃ�����ł͂Ȃ��A�������̐������͑��݂��Ȃ��ƌ��킴��Ȃ��̂ł���B
�Q�@�������̏����Ɛ������̖��ɂ���
�i�P�j�����̐푈�������������͖@�I�\���ł͂Ȃ��A���̐����u���v�͕����ł��Ȃ������B
�����Ԃ̌�������k�œ��{�����A�������͂��łɓ��ؕ��a���̒i�K�ʼn����ς݂Ǝ咣���A�u�ꍑ�ɓ�x�̔���������F�߂��Ȃ��v�ƁA�������̔����������������u�t���Ȃ��v������\����������������ł̕������߂����āA���{���͈ˑR�Ƃ��ē��؏�L���������Ƃ�������܂ł̖@���_���咣���A����������́u��x�ځv(��p��������)�̔����������̕����ɓ�F���������B���̌��ʁA�u�푈���������̕����A�Ƃ����������́A�������̋����v���ŋ��������ɓ����ꂽ���A�����������́u���v�ɂ��ẮA���{���̋����v�]�ɂ�蕶�͂���폜������ꂽ*1�B
�Ƃ���œ��{���{�Ăƒ������̐����ĂƂ́A���������̓��e�ɈႢ������ꂽ�B���������ɂ��āA���{���{�Ă̑�V���Ƃ��Ȃ�����A�S���Ɋ��ʂ������̂ł���B���̊��ʂɂ��ē��{�́u�Β������v�ɂ͎��̂悤�ɋL���Ă���B�u�����̖��Ɋւ����7���́A�{���䂪�������Ă��ׂ������̎����ł͂Ȃ��̂ŁA�c���{����Ă̂悤���@���I�ł͂Ȃ��\���ł���A�����o���̊�{�I������Q���邱�ƂȂ��A���������������ƍl����v�ƁB����ɂ��������ē��{���{�Ăɂ́A�u���ؐl���a�����{�́A�������������̗F�D�̂��߁A���{���ɑ��āA�����Ԃ̐푈�Ɋ֘A���������Ȃ锅���̐������s�Ȃ�Ȃ����Ƃ�錾����v�Ə�����Ă����B�����ɓ�̖�肪�������肳��Ă���B
��́A���{���{�́A�u�����ς݁v�Ƃ��锅�����ɂ��Ă��A�u�����Ȃ�v�����̐����Ƃ������ƂŐ푈�������́u���S�v���������߂悤�Ƃ����̂ł���B������́A�푈�����������̕����ł͂Ȃ��A�u�����̐������s�Ȃ�Ȃ����Ƃ�錾����v�Ƃ����`�ŁA�������̐푈�����������̑��݂�F�߂邱�Ǝ��̂�����悤�Ƃ����B�܂���{���͂��������������̔��������������F�߂悤�Ƃ��Ȃ������̂ł���B
���ǁA��������������܍��ɂ́u���ؐl�����a�����{�́A�������������̗F�D�̂��߂ɁA���{���ɑ���푈�����̐�����������邱�Ƃ�錾����v�Ə����ꂽ�B�u�푈�����������������v�Ƃ������������́g���h���Ƃ������Ƃɂ��A���ꂪ�@�I�\���ł͂Ȃ����Ƃ��Ӗ������B���̂��ߓ����Ԃɂ����ẮA�푈�����┅����肪�@�I�ɉ�������镶�������݂��Ă���̂��ǂ��������ɂȂ����B
�܂���{�������������ʂ�A���̋L�q�͖@�I�\���ł͂Ȃ��B�u���������͕��������Ƃ͂����Ă��A�������͕������Ă��Ȃ��v�B�܂����������͂܂����邱�Ƃ͂������A����͐������Ȃ��B���������̌�������{���̋����v���ŁA���ۂ�����ꂽ���A�����������̐����̌���������ł��Ȃ��������A�Ɖ��߂��邵���Ȃ��̂ł���B�t�ɂ����u�����������������v�Ɓu�������������������v�Ƃ͓������Ƃ��Ɖ��߂���Ȃ�A�Ȃ������u���������v�������킴�킴���{���{�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��ł��낤���A�Ɩ�킴��Ȃ��̂ł���B
���̌o�܂́A���{���ɂƂ��āA�g���؏��̐������h�̂��߁A�D�s���̂悤�Ɍ����邪�A���ۂɐV���������������B�܂�A���{���̔F���Ƃ��āu�@���I�ł͂Ȃ��\���v�����������̌��y��F�߂Ȃ��Ƃ�������ɂ��A�����������ӂ��ꂽ���������ɂ���푈�����Ɋւ��镶���́A��������u�@���I�ł͂Ȃ��\���v�ɂȂ邱�Ƃ��A���{���{���F�߂����Ƃ��Ӗ����邩��ł���B����������A�����������؏��̖@�I���@����ے肵�A���{�����������������̖@�I�Ӗ���ے肷����߂����邱�Ƃɂ��A�����Ԃ̐푈�������́A�����ɂȂ��Ă��ˑR�Ƃ��Ė@�I�ɂ͖������̂܂܂ɂ���A�o���̍��ӂ��ł��Ă��Ȃ���ԂȂ̂ł���B
�@���̖��Ɋւ��閈�x�̐��{�����̂Ȃ��ŁA�K���Ƃ����Ă����قǁA�u��������������������������v�ƒf�����Ă���̂ł��邪�A����͓��{���{���u��������v�������߂��ǂ����A���{���{�����狁�߂����ʂƂ��Đ����́u���v�������������Ƃ�Y��Ă��܂����̂ł���B���̌��ʁA�����������́u�����v����������@�I�������́A���������������܂߁A�����ɂ��Ȃ��͂��ł���B
�i�Q�j���Ԑ������̕������܂ނ��ǂ����ɂ���
�T���t�����V�X�R�Γ��u�a�����܂߁A���{�����̑��̍��Ƃ̊ԂŐ����������ׂĂ̔������Ɋւ�����⋦��ɂ́A�K���Ƃ����Ă����قǁA���{�y�э����Ƃ���������������A�܂��������������̊��S�����A�Đ����ł��Ȃ��Ȃǂ��߂Ă���B
�������A�������������ɂ́A�悭�m���Ă���悤�ɁA�u���ؐl�����a�����{�v����������A�u�l���v��u�����v�̕����͂Ȃ������̂ł���B���̕\���͌����Ė��Ӗ��ł͂Ȃ��A�傫�ȈӖ����������邱�Ƃ͎����ł���B
�܂�A�������{�̈ӎv�\���́A���Ԕ����������̕����܂łȂ��������̂ł���Ƃ������߂ł��Ȃ��̂ł���B�������̑����̊w�҂������F���������Ă���B����ɑO�q�̂悤�ɁA�������̐����u���v������ł��Ȃ������o�܂��l������A�Ȃ�����ł���B
���Ȃ݂ɓ��{���̔�Q���̖��Ԕ����������܂ł���������Ƃ������́A�����������̖@�I�������R�������̂ł���Ƃ��킴��Ȃ��B
�R�@�������������́u���r�v
�i�P�j �������������͍u�a���ł͂Ȃ��B�������������͐��{����Ƃ��āA���������̍��𐳏퉻�̂��ߒ������ꂽ�����ł���B
���̐��i��̗��R�ŁA������������Ԃ̏����̖@�I���������߂����̂ł͂Ȃ������B�����I�Ë��ɂ�萬�������������������́A�푈�����̏������قƂ�ǐ摗��ɂ����`�ŕЂÂ����B
�@
�i�Q�j�������������ɂ́A�푈�I���錾�͂Ȃ������B
��q�̂悤�ɁA���{���̋������ŁA���������ɂ́A�푈��Ԃ̏I���錾�͓����ꂸ�A�u�s����ȏ�ԁv�Ƃ����\���ŕЂÂ������A����͓��R�A�푈��Ԃ̏I���Ƃ͑S���Ⴄ���̂ł��邱�Ƃ͎����Ȃ��Ƃł���B
���Ȃ݂ɑ�ώc�O�Ȃ��ƂɁA�����Ɏ���܂ŁA�����Ԃɂ́A�푈��Ԃ̏I���錾�͏o����Ă��Ȃ��܂܂ɂȂ��Ă���B�������A�O�q�̒ʂ�A�������{���{�̐���Ɠ��؏������r�ɂ��A���{�����咣���Ă�����؏������ɋK�肳��Ă���푈��Ԃ̏I���́A���ɓ����Ԃ̐푈��ԏI���錾�ɂ͂Ȃ�Ȃ��̂ł���B�������́A�ŏ�����Ō�܂œ��؏��̔ے�ɂ��A���{���̈���I�Ȑ錾���A���K�p�͈͏����ɂ��A�����嗤�Ƃ̊W�ɂ́A�g�y�ł��Ȃ����Ƃ͓��R�̌��ʂł���B
�i�R�j�푈�����������̕����́A���{���̔��ł��́u���v�����������ʁA���Ƃ��ƕ����̈ӎv���������������͑Ë��Ƃ��āA�����u���v�̗��ہA�܂��͐����́u�����v������ł��Ȃ������Ɖ��߂����ł��Ȃ��̂ł���B�������ɂ������Ԃ̐푈�������������̉����́A�ŏI�I�ɂ͂ł��Ȃ��܂܂ɂȂ��Ă��܂����̂ł���B���������́A���{�ԋ���̐��i�ł��邽�߁A���Ƃ��Ɩ@�I�ȈӖ��͔����A�����܂ł��������𐳏퉻���߂̕����Ƃ��Ď�舵�����B
�i�S�j���{���{�́A���؏��Ƃ̖@�I�������ɂ������A���������ɑ�����߂ƔF�����A�B���ł���B���łɌ������悤�ɁA���퉻���̂Ȃ��A���{���́A���؏��́u�������v����邽�߂ɁA���������̕\�����ł������A�@�I�\���ł͂Ȃ��A�����I�\���Ɍ��肳���悤�Ƃ����B
����ɂ���āA�������̓��؏��̔ے�ƕ����āA���ʓI�ɂ́A���K�p�͈͂ƒ�������̓��{���{�̌����ɂ��A���؏��̖@�I��������ے肳��A�������������̂悤�ȏd��Ȗ@�I�����ɂȂ炸�A���܂ł������Ԃɂ́A�����ɂ������Đ푈��Ԃ̏I���錾��u�a���ȂǍł��̐S�ȕ��a�������s�����̂܂܂ɂȂ����̂ł���B
�S�@�������a�F�D���́A���a���ł͂Ȃ�
���a�F�D���̐��i�Ɋւ��āA�O���Ȏj�����J�����Ƃ���܂ł̌������ʂƍ��킹�ĕ��͂���ƁA�������́A���؏��ɑ��āA�ŏ����疳���ł���A�j�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ǝ咣���Ă��������Ɗ֘A���ē����Ԃ̐푈��Ԃ�푈�����Ȃǂ̏�����1972�N�̍��𐳏퉻�܂ňˑR�Ƃ��đ��݂��Ă���ƍl���Ă����B
����A72�N7���̒i�K�ł́u�����}�������ŏ����I�Ȉ�v��������̒i��肪���顈�͋��������ō������A���̌�A���a�����������v�Ƃ������̂ł�����(���ʼn_�A�����O���ȃA�W�A�ǎ����A�|�������ɂ��)��܂�A���{�������؏��̗L�������咣���Ȃ�����A�����嗤�Ƃ����a�������Ԋo��͂������̂ł��顓��{�͒������́u���ؕ��a��s�@�ł���A�j�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��v�Ƃ��������I����ɂ��ď\���������A���d���邱�Ƃ͂��̐��퉻�̑O��ɂ��Ȃ�B�������������͍u�a���ɂ͂Ȃ�Ȃ��B
����������ڂ̎�]��k�ł́A�����������́u���������ō��𐳏퉻���s�Ȃ��A���̌`�����ʂƂ��������Ɏ^������v�Ɣ������A�Ë������B�܂������o���́A���������̒i�K�ł��łɕ��a�F�D���́u�u�a���v�ł͂Ȃ��Ƃ����F����O��ɁA�����������悤�Ƃ����B�����������́u����i���a�F�D���j�ɂ́A���a�܌����Ɋ�Â������̕��a�F�D�W�A���ݕs�N�A���݂̐M�`�d���鍀�ڂ���ꂽ���v�Ɛ������A���a���̐��i��ے肵���B
�܂�A�����Ԃ̏d�v�����ł�����ؕ��a���A�������������A�������a�F�D���A���̂�����������o���Ƃ������ɔF�߂Ă���A�����ȕ��a���(the
Peace Treaty)�ł͂Ȃ����Ƃ́A���炩�ł���*1�B�����ɂȂ��Ă��A�����Ԃɂ����ẮA�o���Ƃ��F�߂Ă���푈�����Ɋւ��镽�a���́A���݂��Ȃ����Ƃ��Ӗ�����B���a���̕s�݂́A�����o���ɂƂ��Č����Ă������Ƃł͂Ȃ��A�푈�◯���̑S�ʉ����ɂƂ��Ă��ɂ߂đ傫�ȏ�Q�ɂȂ��Ă���B
�܂��������a�F�D���(�O��)�́A�u�������������̏����������d�ɑ��d���ׂ��ł���v�ƋK�肵�A�푈�����̍����ƂȂ������A���̏������ɂ́A���R������������̔�������������B�������O�q�̂悤�ɁA���̑���́A���{���{�̋����v�]�Ŕ����������́u���v����A�������{�̔��������̌����𗯕ۂ������̂��A�����ł��Ȃ��������ʂƂȂ�A��������d���Ȃ���Ȃ�Ȃ����ƂɂȂ�B
�T�@�����Ԃ̊O���̖��_
�@��q�̂悤�ɁA�������Ă�����������̊O���ɂ́A�푈�����Ɋւ��Ă����A���ꂼ��̖��Ɓu���r�v�����������߂ɁA���������ɂ́A�@�I�ɓ����W�𗥂�����̂͑��݂��Ȃ����A��������Ă��Ȃ��ɓ�������Ԃɂ���B�����̑傫�Ȗ��_���܂Ƃ߂�ƁA�ȉ��̒ʂ�ł���B
�P�A �����o���ɂ́A�푈�I���錾�̕����͑��݂��Ă��Ȃ����ƁB
�Q�A �����Ԃ̐푈���������𗥂���u���a���v(the Peace Treaty)�����݂��Ȃ����ƁB
�R�A �푈���������u���v�i���Ƃƍ����Ƃ��j����A�����̐������͕����ł��Ȃ��������ƁA���������́u�����v��������������͂Ȃ����ƁB
�S�A ���̂悤�ȋ��������ɂ��푈�����̑e�����ɂ�荑�����x���̕s�M�������������݂��邱�ƁB
�T�A �푈�����̕s���S�ɂ��푈�◯����肪�R�ς��A�܂��܂����o���Ă��邱�ƁA
�Ȃǂ���������B
�U�@�푈�ƍ߂ɂ���Q�������̎������Ɛ푈�◯���
�@�u�\�ܔN�푈�v�Ƃ��Ă�Ă�������Ԃ̒����I�푈�́A���������ɁA���ɔ�Q�ґ��̒����ƍ����ɑ���ȑ�����^���A�N�����ꂽ�����Ƃ��̍����ɐ[�����Ղ��������Ă���B�푈��60�N���o�Ƃ��Ƃ��Ă��鍡���A�푈�◯���́A�ˑR�Ƃ��Đ������c��A�܂��`�`�n���s�̓ŃK�X�R�ꎖ���̂悤�ɁA���{�̑Β��N���푈�ɂ���Q�Ƒ����́A���j������ł͂Ȃ��A�������Ƃ��Ă����݂ł��������Ă���B
�i�P�j�{���\�\�V�R�P�����̍ې�ɂ���Q�i�ׂ́A�܂��Ɉ�ʓI�Ȗ��������ł͂Ȃ��A�푈�ƍ߂ɂ���Q�\�\�ۂȂǂ̎g�p�͐펞�@�ƍ��ۖ@�ɋւ����Ă���ƍߍs�ׂł���B���ۖ@��������l���鎞�A�푈�ƍ߂Ɋւ��鎞�������͂Ȃ��A�����Ɏ����āA�h�C�c��C�X���G���Ȃǂ́A�i�`�X�h�C�c�̐푈�ƍߐl��Njy���Ă���B1970�N�㍑�A���푈�ƍ߂ɑ���Njy�ɂ͎����Ȃ��Ƃ������c���o����Ă���B
���������Ă��̂悤�Ȑ푈�ƍ߂ɂ���Q�������Č��̓��ꐫ���l�����Ă��A��ʓI�Ȗ��������Ɠ����悤�Ɏ�舵�����Ƃ͖��炩�ɍ��ۖ@�I�����A�����ɔw���A���ێЉ�̏펯��������E���Ă���B�����l����w����縍������́A�푈�ƍ߂Ɗ֘A���Ă��������l�����āA�u�������ق����ˊ��Ԃ𗝗R�ɋ����J���Ҕ��������̑i����ނ������Ƃ́A���������@�I�ȍ����̂Ȃ����Ƃł���v�Ƌ����ᔻ���Ă���*1�B
�i�Q�j���ԑ��������������ɂ��ẮA�ꍑ�̐��{�������Ȉӎv�\�����Ȃ�(�O�q�̂悤�ɓ������������ɂ́A�������{�y�э����Ƃ����\���͂Ȃ�)�����������邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B�������{�͑Γ��푈��������������������̂́A�O�q�̂悤�ɁA���̐����u���v�̕����͂Ȃ��A���Ԕ����������܂ł̕����́A�Ȃ����猾���Ȃ��̂ł���B
�������{�́A�����푈�Ɋ֘A���鎖���̋N����x�ɁA���{���̐������K�ȑΉ������߁A���Ԕ������������ɑ���S�̍���������������B�������A�������{�́A�Γ����Ԕ�������������������Ƃ��������Ȕ��\�͈�x���Ȃ��A���ɂ��鍂�����l�I�ɂ��̂悤�ȈӖ��̂��Ƃ��ق̂߂������Ƃ��Ă��A�������{�̌��������ɂ͂Ȃ�Ȃ����A�܂�������؋��ɒ������{�Ɛl���́A�Γ����Ԕ�������������������Ƃ́A�ƂĂ������Ȃ��̂ł���B
�܂��������̈�ʓI�ȔF���Ƃ��āA���Ԕ�Q�҂Ƃ��Ă̑Γ������������̕����͂Ȃ��A���ԑΓ������������͈ˑR�Ƃ��đ��݂��Ă���B�{���̂V�R�P�����ې�ɂ���Q�i�ׂ��A�펞���ɔ������Ă������Ƃł���Ɠ����ɁA��Q�ґ����ې�ɂ��S�g��ɂ́A�����ɂȂ��Ă�������Ă��Ȃ��B
��Q�ҋ~�ςƌ���A�����Đ푈�ƍ߂ւ̒Njy�ȂǁA�����̈Ӗ��ɂ����ĉߋ��̎��ł͂Ȃ��A�ɂ߂Č������̍������ł���B���{���{�́A���ۓI�M�`�u���ۖ@�̏���v�Ɛl�����d�Ƃ������n����������̔ƍߍs�ׂɂ���Q���~�����A����Ɠ��{���ւ̍��ۓI�M���������߂����߂ɐ^���Ɏ��g�ނׂ��ł���B
�i�R�j�����Ԃɂ����Đ푈�◯���́A���̌��������܂��܂����܂��Ă��Ă���B����͂��Đ��27�N��(1945�]1972�N)�̖��O���W�̏�ԂƂ����u�v������A����ɓ��{���{�ɂ��؋��B���A�ӔC����A�~�ϕ����Ȃǂ̐��A�������Ԕ�Q�҂̑��Q�����������̍s�g��啝�ɒx�点�A�W���Ă������ƂɌ���������B
�܂��������̎���Ƃ��āA��Q�҂̑������A��r�I���I�ȏ�Ԃɂ���A���Ă͎��R�ɏo���Ȃǂ��ł�����̂ł͂Ȃ��������Ƃ������ł���B�ޓ��́A�����ɂ͂��̂悤�Ȗ��Ԕ����������̂��邱�Ƃ����m��Ȃ��҂������B����������͔�Q�ґ��ɂ́A��Q���������̈ӎv���Ȃ��Ƃ������Ƃł͂Ȃ��A���̒m���Ɣ\��(�����I�A�@�I)������Ȃ��Ƃ������ƂȂ̂ł���B
�����̉��v�E�J���Ə�A�܂�����ƖL���ɂȂ�ɂ�āA����ɖ@�I�ӎ��Ɛl���ӎ��̌���ɂ��������A�������Ԃ̑Γ��푈���������̍s���͌�������Ƃ��납�A�ނ��낳��ɑ����Ȃ�ƍl������B�܂������̖��剻�ƊJ���x�����̌���ɂ��������A���Ԑl�̈ӎv�\���͂܂��܂������ɕ\��A���{�������̈ӎu�ɂ��������čs�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
�u�\�ܔN�푈�v�Ƃ��������N���̐푈�͂���Ȃ�Ɉ◯��肪�����A��Q�Җ{�l�̎����ȂǂƂ͊W�Ȃ��A���̈⑰�ɂ������p����A�����������Ԃ̎Љ���Ƃ��Ďc��B�Ⴆ�A�u�Ԉ��w���v�ŁA�؍���t�B���s���Ȃǂ̔�Q�҂ɂ́A���{���{�̎�Âłł����u�A�W�A��������v�ɂ��~�ς�������x���s���ꂽ���A�����̔�Q�҂́A�������Ă��Ȃ��B���u���ꂽ�܂܂ɂȂ��Ă���B�����������������u�Ԉ��w�v�͒����ɂ͌����ď��Ȃ��͂Ȃ��B�@���A�l���ψ���́u�Ԉ��w���v�Ɋւ�����{���{�ɑ��銩������݂Ă��A���{���{�̒����u�Ԉ��w�v�ɑ���Ή��́A���̐������������Ă���Ƃ��킴��Ȃ��B
�܂��f�v���ꂽ�����J���ҁA�ې�Ȃǂ̐푈��Q�ҁA�ŃK�X�R�ꎖ���̔�Q�ҁA���̑��̗\�z�ł��Ȃ��֘A�����̐V�K�������K���Ƃ����Ă����قǁA���ꂩ�������B���Q�ґ��̓��{���{�̗ǎ��Ɛ������������B�܂��K���ƌ����Ă����قǁA��Q�������N���邽�сA�V���ȓ��{�̐푈�ӔC��肪�������A���������Ԃɂ�鑹�Q�����������̍s�g���s�Ȃ���B�����͂��������W���h�邪����A�܂��ߋ����܂ޓ��{���{�̑Ή��̑e����������݂ɂȂ�A���{�̍��ۓI�M�p�ƃC���[�W��傫�������A���{�̍��v�ɔw�����ƂɂȂ�B���̂悤�Ȉ��z�́A���ۂ̓����W�ɌJ��Ԃ���Ă���̂ł���B
��S�@�^�̘a���̂���
�@��ʓI�ɂ́A�푈��Ԃɂ����������̊W�ĊJ�́A���a���̒����ɔ������̂ŁA���̂悤�Ȓ����푈��Ԃ𑶑������Ă������������ɂ����ẮA�Ȃ����炱�̂悤�ȍu�a��K�v�ł��낤��������A�������Ƃ��āA�����Ԃ̌���������������x�A�m�F����A�ȉ��̌��ʂɂȂ�B
���@���؏��ɂ��ẮA�������r�̑����Ə��K�p�͈͖�肩��A�����Ԃ̊�{�����ɂ͂Ȃ�Ȃ��̂ł���B�܂������҈���̒�������������S�ے肵�����̂ł��邽�߁A�ԊW�𗥂�����̂ɂ͂Ȃ�Ȃ����Ƃ��O����̈�ʏ펯�ł���B
���@�������������́A���a���̂悤�ȏd��ȋ@�\�������Ȃ��������̂ł���B�ȏ�
�̌������������悤�ɁA�u�������������v�Ƃ��������͂����܂ł������̍��𐳏퉻�̂��߂̐��{�ԋ���ł���A���ł͂Ȃ��A�o���̍���̐R�c�ɂ��������Ă��Ȃ��������Ƃ͂��̌���ł���B
��O�@�u�������a�F�D���v�ɂ��ẮA�����o���Ƃ�����������������i�K�ł���
�ɍ��ӂ��ꂽ�悤�ɁA����͍u�a���ł͂Ȃ��A�����u���I�ȗF�D���ł���ƔF�߂Ă���B
�ȏ�̕��͂ɂ��A�{�ӌ����́A���ɁA�������ē����o���ɂ́A����܂łɁA�u���ؕ��a���v�u�������������v�u�������a�F�D���v�Ƃ������d�v�ȕ������������ɂ�������炸�A���ۂɓ����o���Ƃ��F�߂Ă���悤�ɍu�a���Ƃ����푈�����Ɋւ��錈��I�Ȏ挈�߂͂Ȃ��������Ƃ��w�E���Ȃ���Ȃ�Ȃ��
�����āu���ؕ��a���v�ɂ��āA���{���{�ł�������(�g�c���t)�A���ꂪ�����Ƃ̑S�ʓI�u�a���ł��邱�Ƃ�F�߂Ȃ������̂ł���B1957�N�̊ݓ��t�Ȍ�A�悤�₭��p������S�����̑�\�����Ƃ��ĔF�߂��Ƃ݂��Ă��邪�A���̓K�p�͈͏����ȂLj���ɕς�邱�ƂȂ��A���̒����嗤�܂ł̓K�p�͈͂��s�\�̂܂܂ł���B�܂��A���̓��{���{�́A���؏����������̋g�c���t�ɂ����؏��Ɋւ��鍑��ق����Ɩ������ꂽ���Ƃ͂Ȃ��B
�������͍ŏ�������؏��̍��@���������ے肵�A���̏��́u�I���v�ɂ�����܂ň����F�߂����Ƃ͂Ȃ�����������������̓K�p�͈�*1�����̖@�I���͂��A�����嗤�ւ̓K�p���������������Ă������Ƃ͌������ʂ�ł��顓��{�������؏��œ����Ԃ̐푈�������s�Ȃ����Ǝ咣���Ă�����I�Ȃ��̂ɂ������A�����O����̃R���Z���T�X�ɂ͂Ȃ�Ȃ����A�����������̂悤�ȃR���Z���T�X�͑��݂��Ă��Ȃ��̂ł���B
���������āA�{�ӌ����́A���������ɂ͐^�̈Ӗ��ł̍u�a���͑��݂��Ă��Ȃ��ƔF��������Ȃ��B�����W�ɂ��̏d��Ȍ��ׂɂ��A����܂łɓ��������Ԃɑ����̖�肪�J��Ԃ��������Ă���A�₦�������W��h���Ԃ��Ă���B�����W�̕s����͂��̂悤�ȍu�a���̕s�݂ƁA�����Ė��W�ł͂Ȃ��A�܂��ɂ��̎�Ȍ����ł��낤�B
�{�ӌ����́A�����o���ɂ́A�����o���̃R���Z���T�X�ƂȂ�V�����A���̑��₩�Ȑ��������߁A���u�a���̏�Ԃ̏I�~��������������ł��Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ƃ������_�Ɏ������B
���ɁA�O���Ɗ֘A���āA���a���̂Ȃ��Ȃ��A�����o���́A�푈��Ԃ̏I�����錾���Ȃ������̂ł���B�܂�u���؏��v�͓��{�Ɓu���ؖ����v(������p�n��̈ꔽ���{����)�Ƃ̊Ԃ̐푈��Ԃ̏I����錾�������A���{�������狁�߂����؏��K�p�͈͏����ɂ�蒆���嗤�ւ̓K�p�͂ł��Ȃ��āA����������Ԃ̐푈��Ԃ͌p�����Ă���B���������́u�s����ȏ�Ԃ̏I���v������錾�������A�푈��Ԃ̏I���͂Ȃ������̂ł���B�܂��s����ȏ�ԂƂ����\���͞B���ł���A�ǂ����Ă��푈��Ԃ̏I���Ƃ������߂ɂ͂Ȃ�Ȃ��B���݂̂悤�ɏ����̓x�d�˂������_�Ђ̎Q�q���ɂ����������Ԃ̎�]���ݖK����r�₦�A�����W�͈��́u�s����ȏ�ԁv�ɂ���Ƃ������悤�B
���Ȃ݂������ɂ�1941(���a16)�N12��9���������{���Γ����z���������Đ푈��Ԃɓ������Ƃ������߂́A���{�ł͈�ʓI�ȁu�ʐ��v�ɂȂ��Ă��邪�A�������N�������A1932(���a�V)�N4��26�����\�r�G�g���a���Վ����{�͑Γ����z�����s�Ȃ����B���������̗Վ����{�͌��ǁA1949�N10��1���ɐ����������ؐl�����a���ƂȂ���A�Γ����z���͂���Ȃ�̏d�݂����邱�Ƃ��w�E���Ă��������B�����1949�N10�����ؐl�����a�������l�����{�̐����������āA�����l�����{�́A�����Ɋւ��邩�Ă̒��ؖ����̂��ׂĂ̌����A�������p�����A�����̗B��̐������{�ł��邱�Ƃ́A���ێЉ�ɂ��F�߂��Ă���B�܂�1971�N10��25�����A�ʼn����ꂽ�u���A�ɂ����钆�ؐl�����a���̍��@���������A�Ӊ�Έꖡ��Ǖ����錈�c�v�͂��̍����ł���B�܂�1972�N9��29���ɔ��\���ꂽ�������������ł����{���{�́A���̔F���ɔ����Ȃ����Ƃɂ����B
�O�q�̒ʂ�A���̌����̂Ȃ��A���������̐��̂͋��ɕω����Ă����B����{�鍑�͓��{���ɕς��A���ؖ����͒��ؐl�����a���ɕς�����B���̂悤�Ȑ��̂̕ω��͌p�����{�̐ӔC��ς��鎖�͂Ȃ��A���������{�́A���Ă̐푈�����ւ̏������ӔC������A�������Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�������������̐^�̘a���Ɛ^�̗F�D�̂��߂ɑ��₩�ɂȂ���邱�Ƃ����҂��Ă���B
��O�ɁA�������Ɋւ��ẮA���؏��ł́A�u�T����t�����V�X�R����\�l��(a)�P�Ɋ�Â����{�������ׂ��̗��v�������I�ɕ�������v�Ə����ꂽ���A�����Ƃ������������Ȃ������B�܂����K�p�͈͏����ɂ��嗤�ւ̗L�����͔F�߂��Ȃ��B�܂����������̒i�K�ł́A���{���̋����v�]�ɂ��u�푈�����������v�́u���v�������ꂽ�B���̌��ʁA�푈�����́u�������v������������A���Ȃ������������A�@�I�ɂ͖��m��ȏ�Ԃɂ���܂܂ɂȂ��Ă����̂ł���B���{�����A���܂��炻�̒������̐����u���v����������Ƃ����Ă����̖@�I�����͂Ȃ��̂ł���B�܂������ɂȂ��Ă��푈��Q�ґ��ւ̋~�ς́A���{���̐����ȑԓx�Ɛ��ӂ̂���Ή������߂��Ă���B
��l�ɁA�������𐳏퉻�Ȍ�A�푈�����̏����\�\�����A�s�A�Ԉ��w�A�◯���w����ȂLj◯��肪���o���Ă���B���{���{�́u�Ԉ��w�v���(�A�W�A����������߂̎�����Ȃ�)��◯���w����̏������y�ш◯���w����ɂ���Q�҂ւ́u��Ô�v�A�u������v�Ȃǂ���݂Ă�������悤�ɁA�����̐푈�◯���ɑ��A���{���{�̏������@�Əo��Ȃǖ��ڂ̈Ⴂ���������Ƃ͂����A���{���{�͎����㖯�Ԑl���Q�҂ɔ������x���킴����A�܂��푈�����̈�Ƃ��Ă����̏����������ł��ЂÂ�����̂ł���B
�ȏ�̏��瑎���I�ɍl������A�����Ԃ̐푈�������������́u���łɉ������݁v�A�܂��́u���݂��Ȃ��v�Ƃ́A�@�I�ɂ͌������������̂ł���A�܂��������Ƃ��Ă����̎����Ƃ͑傫���قȂ��Ă���B���������Ĕ퍐���̔������������̉����ς݂Ƃ����咣�̖@�I�����́A�s�[���ł����ƌ��킴��Ȃ��̂ł���B
�ȏ�
|