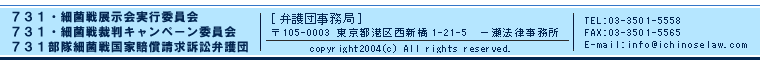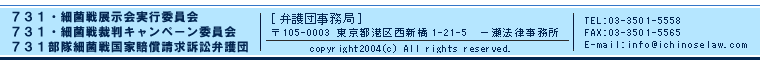|
鑑定意見書
>鑑定意見書のメニューに戻る
『日中共同声明』等の
対日戦争賠償請求権問題に関して
華東政法学院教授 管 建 強
目 次
一,前書き
二、日本政府の《サン・フランシスコ条約》と《中日連合声明》に対する恣意的な主張を検討する
三、日本政府が『日華平和条約』を根拠に『日中共同声明』を否定する法律的地位と効力等に対する研究と批判
四、中国政府の権限及び《日中共同声明》第五項の意味について
五、国家と民間の損害賠償請求権の違いは、早くから国際社会によって認められている
六、日本政府が中国政府の見解に対し偏った理解をしていることに関する問題
結び
�
一,前書き
中国人の一般戦争被害者が日本政府に対する訴訟活動を開始して以来、日本の裁判所は原告の訴訟請求を度々棄却している。その理由とされているものは、次のようなものである。
(1)個人が外国政府に対し、損害賠償を直接請求する権利は認められず、そのような問題は戦後に国家間で締結される平和友好条約によって、一括して処理されるべきものである。
(2)個人の損害賠償請求権を認める國際慣習法に基づいてなされる原告らの請求には理由がない。
(3)国家には答える責任がない。
(4)国に対する損害賠償請求権は除斥期間の満了により消滅した。
以上のような中国人戦争被害者の訴訟請求に対する棄却理由は、日本各地の下級裁判所の判決に依るものであるが、これらと比較しても、日本政府反論における論点は更に謬論であり、それは恣意的解釈の段階に達したものだと言えよう。
日本政府は当初、1972年の中日連合声明 *1 が民間の対日賠償請求権をも放棄したという理由を根拠に、いくらか慎重に反論していた。
ところが、この理由が日中双方の研究者から、対日民間賠償の研究と併せてよく批判されたので、日本政府はこの理由を守る自信を失ったものとみえ、また新しい理由を提出した。それは、
「中国との戦後処理については、1952年4月、‘中華民国’との間で日華平和条約が締結された。日中間の戦争状態は、日華平和条約により終了したというのが、我が国の一貫してとっている立場である。これは戦争状態の終了は一度限りの処分行為であり、法律的には、当時中国を代表する合法政府であった中華民国政府との間で国と国との関係を律する事項として処理済みであるという考え方に基づくものである。…即ち、戦争の遂行中に日本国及びその国民がとった行動から生じた損害に対する中国及びその国民の請求は、法的には前述のとおり、日華平和条約により、国によって放棄されているというのが我が国の立場であり、このような立場は共同声明によって変更されているわけではない。」*2
というものである。
その主張の意味するところは、日華平和条約により,国によって戦争賠償請求権が放棄されているので、中国の一般戦争被害者の対日賠償請求権は存在しない、というものである。
前述の中日連合声明において中国民間の対日賠償請求権を含めた全ての対日賠償請求権が放棄されているという主張や日華平和条約によって中日連合声明の法的地位を否定する解釈に対し、歴史上の事実を根拠に、厳密に中日連合声明及びそれに関連する問題を解釈し、日本政府の間違った結論を正さなければならない。
中国の一般戦争被害者は、法律的救済によって戦後に遺留された問題の解決を図っている。それ故、被告たる日本政府による反論を検討することは、中国人の法律学者の責任であって、それは中国国民の利益となるのみならず、全人類が共有する人権理念の発展、世界平和の実現につながるのである。
筆者は細菌戦被害者原告団の日本の弁護団の依頼を受け1972年中日連合声明とそれに関連する問題を検討しこの意見書をまとめた。
二、日本政府の《サン・フランシスコ条約》と《中日連合声明》に対する恣意的な主張を検討する
東京地方裁判所民事35部における毒ガス被害者孫景霞等13名原告の訴訟の審理、及び東京地方裁判所における、細菌戦被害者王選など180名原告の訴訟において、日本政府が提出した反論の根拠には、サン・フランシスコ条約と日華条約が用いられており、中日連合声明は用いられていない。
日本政府の反論では、以下のように構成されていた。1、日本政府の中日連合声明に対する見解;2、第二世界大戦後の請求権の解決方法;3、日本は“中華民国”との間で請求権を処理すること;4、日本は中華人民共和国との間で戦後処理を行うこと;5、中日連合声明の第五項についての日本政府の見解;6、中国政府官員の見解に関する問題。
まとめて言えば、日本政府の主な論点は次の三方面にわたっている。一、サン・フランシスコ条約は戦後の日中和解の基礎である。二、日華条約において戦後遺留した問題は処理済みである。三、中国政府官員の解釈には日本の立場に賛成するものがある。
以下、日本政府の一連の反論*3と根拠等を具体的に検討する。
(一)日本政府の恣意的な《サン・フランシスコ平和条約》の解釈
反論には、「日華平和条約11条及びサン・フランシスコ平和条約14条(b)により、中国国民の日本国及びその国民に対する請求権は、国によって「放棄」されているのであり、日中共同声明5項にいう「戦争賠償の請求」は、かかる請求権を含むものとして、中華人民共和国が「放棄」しているから、サン・フランシスコ平和条約の当事国たる連合国の国民の請求権と同様に、これに基づく請求に応ずる法律上の義務が消滅している結果、救済が拒否されるのである。従って、原告らの請求に応ずる法律上の義務が消滅している以上、原告らの請求が容認される余地はない。」とある。
サン・フランシスコ平和条約における日本政府の見解を簡潔に言えば次の三点に整理される。:一、日華条約第11条及びサン・フランシスコ条約14(b)項により、中国国民は日本国及び日本国民に対する賠償請求権を国家(中華民国政府)によって放棄された。二、中華人民共和国政府はサン・フランシスコ条約から権益を獲得した。三、サン・フランシスコ条約の構造に基づき、戦後の賠償は国家間で直接処理する、或いは賠償請求国内にある敵国資産により損害を補償する方法で解決し、原則として被害国国民の賠償請求は各被害国の国内問題であり、その被害国は国内経済実力などを考慮して立法等で救済する方法で解決する。
(二) 日本政府の《サン・フランシスコ平和条約》における法的地位の解釈に対する研究と批判
1、サン・フランシスコ平和条約締結の背景と内容
1945年8月14日、日本国はポツダム宣言を受諾した。ポツダム宣言第11条は「日本国は、其の経済を支持し、且公正なる実物賠償の取立を可能ならしむるが如き産業を維持することを許さるべし。但し、日本国をして戦争の為に再軍備を為すことを得しむるが如き産業は、此の限に在らず、右目的の為、原料の入手を許さるべし、日本国は、将来世界貿易関係の参加を許さるべし。」とある。
国際法に照らし合わせて考えると、交戦国との間で講和条約によって戦争状態を終わらせ、その講和条約締結時に、戦勝国が敗戦国、特に侵略戦争を行った国に対して、戦争賠償権を享受することは当たり前のことである。戦勝国の享受する権利はポツダム宣言にも規定されており、日本国の降伏文書でも、その國際法則を認めることが表明された。
米国は1951年7月20日、対日講和草案を起草し、日本国と交戦関係にあるその他の連合国に講和会議への招請を行ったが、戦争犠牲者数の最も多い被害国である、中華人民共和国政府或いは中華民国政府には、対日講和会議の招請状さえ送られなかった。
サン・フランシスコ講和会議は1951年9月4日から8日間、サン・フランシスコにおいて開催され、日本国との平和条約(Peace Treaty With Japan)が調印された。これが所謂サン・フランシスコ条約(San Francisco Peace Treaty )である。ソ連、ポーランド、チェコの三国は会議に出席したが、調印に参加しなかった。その結果、連合国側の署名国は僅か48か国であり、それに戦敗国の日本国を加えて49か国であった。ソ連は調印に欠席した。中国、インド、ミャンマーは会議に出席しなかった。よって、サン・フランシスコ講和会議は、多国間における講和に過ぎず、全世界的な講和とは言えない。
翌年、1952年4月28日当該条約が発効になった。サン・フランシスコ条約第五章(14条から21条まで)に「請求権及び財産」の問題に関しての規定がある。その14(a)により、日本国が戦争中に与えた損害及び苦痛に対して、連合国に賠償を支払うべきことが承認された。しかし、また、存立可能な経済を維持すべきものであるならば、日本国の資源は、日本国が前述したすべての損害及び苦痛に対して完全な賠償を行い、且つ同時に他の債務を履行するためには、充分でないことが承認されている。よって、1、日本国は、現在の領域が日本国軍隊によって占領され、且つ、日本国によって損害を与えられた連合国が希望するときは、日本人を生産、沈没船引揚げその他の作業につかせることによって、その作業にかかる費用を被害国に対する補償費用に資するため、連合国における該当国と速やかに交渉を開始するものとする…。2、各連合国は次に掲げるもの(日本国又は日本国民が所有し、又は支配した団体等)のすべての財産、権利及び利益の中でこの条約の最初の効力発生時にその管轄の下にあるものを差し押え、留置し、清算し、その他何らかの方法で処分する権利を有する…。
14条(b)この条約に別段の定がある場合を除き、連合国は、連合国のすべての賠償請求権、戦争の遂行中に日本国及びその国民がとった行動から生じた連合国及びその国民の他の請求権並びに占領の直接軍事費に関する連合国の請求権を放棄する。
サン・フランシスコ条約は資本主義国と社会主義国の両陣営の冷戦による産物であるにも拘わらず、当該条約では日本国にある程度の賠償責任を規定した。
2、《サン・フランシスコ条約》の中国に対する拘束力は無い
サン・フランシスコ条約に照らし合わせると、中国は“連合国”ではなかった。但し、同条約第25条には「この条約の適用上、連合国とは、日本国と戦争していた国又は以前に第二十三条に列記する国の領域の一部をなしていたものをいう、但し、各場合に当該国がこの条約に署名し且つこれを批准したことを条件とする。」とある。中国の民国政府或いは人民共和国政府両方とも署名、批准しなかった。よって、中国はサン・フランシスコ条約の“連合国”ではないのである。
同条約第25条の後段には、「この条約のいかなる規定によっても前記のとおり定義された連合国の一国ではない国の為に減損され、又は害さるものとみなしてはならない」と規定された。この規定はサン・フランシスコ条約が第三国に対しいかなる拘束も法律上の影響も与えられないことを表明したものである。
サン・フランシスコ条約の第21条は中国及び朝鮮に関する特則であり、「中国は第十条及び第十四条(a)2の利益を受ける権利を有する」と規定した。
よって、中国はサン・フランシスコ条約による全ての利益を受ける権利を有するのではなく、当該条約に規定された範囲内において利益を受ける権利を認められただけに過ぎない。
ところで、サン・フランシスコ条約の規定によると、非調印国は拒絶する権利を享受するのである。条約規則の国際慣習法によって、条約においては、その条約を締結する国自らの同意がその条約の効力の基礎であり、条約は調印国の間に適用し得るのみで、第三国が明示しない限りその国に対する拘束力は無い。条約が第三国を拘束しないとは、古くから公認されている国際法の原則の一つである。
1942年《連合国家宣言》に違反したサンフランシスコ条約
当時サン・フランシスコ条約において、日本に対して集団的形式をもって講和条約を調印しなければならなかった原因として、次の二つが挙げられてきた。一、1942年1月1日、ドイツ、日本、イタリアに対して26か国は共同して抵抗する為に連合国家を結成し、ワシントンにおいて《連合国家宣言》を公布した。その宣言では敵国に対して全面的に決戦を行うことを約束し、また、単独にその敵国と停戦、講和しないと合意した。この《連合国家宣言》の存在により、日本国との戦争状態を終了させるために、宣言に参加した連合国が集団で日本国に対して講和条約を締結しなければならなかった。二、朝鮮戦争の勃発後、政治問題を考慮し、米国は社会主義陣営に対抗するために、日本国を急遽資本主義陣営に組み込む必要に迫られた。そのために採られた手段であった。
前述のように、サン・フランシスコ条約の前提は、1942年1月1日に公布された連合国家宣言であった。しかし、最終的な現実は、当時の宣言諸国である中国、ソ連等の国がサン・フランシスコ講和会談に参加しない、又は調印に欠席した。対日講和において、主要相手国である中国を招請しないことがいかに理不尽であるかは、明らかである。よって、サン・フランシスコ条約は、《連合国家宣言》の合意に違反していたのであり、少なくともその主旨と背離していたのである。
1950年6月朝鮮戦争が勃発した。アメリカの反共政策の為に日本国の戦略基地の役割が益々重要となり、米国の対日講和活動が急激に活発になっていった。1950年中、米国は対日講和の草案を覚書の形式によりソ連に交付した。同年11月、ソ連は米国の覚書に対し幾つかの反対事項を提出した。
中国政府は、ソ連及び米国と交換した外交書類を分析し、そして、同年12月4日に周恩來外相に委託して、対日講和問題について、中国政府の立場を次のように公表した。「対日講和条約は、その内容の如何に拘わらず、講和条項を擬定する準備過程に中国政府が参加し得ないと無効になる。」*4そしてサン・フランシスコの対日講和会議が開催される以前の1951年8月15日、周恩来総理は対日賠償請求権を保留する声明を発表した。1951年9月15日、サン・フランシスコ条約に対する反対声明を発表した。同年9月18日、中国政府総理周恩来は再度中国政府を代表して、講和条約については、「中国はその講和条約を絶対的に承認しない」との声明を発表した。1952年4月28日、講和条約が発効した時、周恩来総理は再び中国政府を代表して、以下のような声明を発表した。「対日講和条約は米国政府の操縦により作られたものにすぎず、決して日本の主権回復や、独立、占領された日本国の地位を改変するものではない。逆に、それは日本国が米国の軍事基地及び付属国として戦備を整えることを約束させられた条約である。」1952年5月5日、中国政府は再び「中国はサン・フランシスコ条約を絶対に承認しない。そして、中国国民を敵視する‘日蒋条約’(日華条約)に対し徹底的に反対する。」*5声明を発表した。
その他にも中日連合声明及び日中平和友好条約において、サン・フランシスコ条約を認める文言或いは意味合いは全く存在しないのである。サン・フランシスコ条約は国際法上非合法であるのみならず、中国に対して拘束力を全く有しない。中日両国の連合声明及び日中平和友好条約は、サン・フランシスコ条約とは一切必然的な関係を有していない。戦後、日本国はサン・フランシスコ条約を他国との間に存在する戦後処理の政策の原則としたが、しかし、当該条約は中日両国の連合声明或いは中日平和友好条約の前提、共通認識或いは母約ではないのである。日本政府はこれを無視して、その反論において「両国政府の努力によって、サン・フランシスコ条約における戦後処理の枠組みと同様の解決が図られたものである」と主張している。その主張の意味するところは、サン・フランシスコ条約が中日両国間に調印された戦後処理協定の前提或いは共同認識であるというものである。事実と全く異なっていることは言うまでも無い。さらに、この主張は、中国の主権及び中国国民に対する冒涜にほかならない。
3、中国政府が《サン・フランシスコ条約》から利益を得たと、日本政府が反論することに関する問題
日本政府の反論によると、中国政府はサン・フランシスコ条約21条によって「この条約の第25条の規定に拘らず、中国は、第10条及び第14条(a)2の利益を受ける権利を有」するものとされ、条約の当時国とならなかった中国が、中国領域内にある日本国及び日本国民の資産の処分をすることも認められた。中国は、1945年10月、「日僑財産処理弁法」を公布して、その領域内にある日本人の財産を没収した、とのことである。その主張に対し、以下の検討を行う。
(1)日僑財産処理弁法について
中国政府は上記日本政府の反論に言うような1945年10月に“日僑財産処理弁法”を公布したとする資料はない。当時の中国政府は、“日偽財産接受、処理弁法”と“華人と日偽合作産業処理規定弁法”等の関連文書は確かに公布した。但し、これらの規定、弁法の主旨は敵国の財産に対して向けられたものであり、日僑の合法的な財産に対するものではない。日本政府は敵国の財産(戦利品等)と日僑の財産を没収することを混同しているのである。
すなわち日本政府は、中国政府の戦争法により敵国の財産を没収する権利とサン・フランシスコ条約にある賠償条項の全く独自の問題を混同している。中国政府が敵国の財産を没収する権利の淵源は、国際法(戦争法)ルールである。中国政府による敵国財産の没収は、「サン・フランシスコ条約が調印される前に行われた。中国に残された敵国の財産を没収することは、サン・フランシスコ条約とは全く無関係である。そして、敵国財産を没収しても、日本国に対する戦後の賠償請求権には何ら関係がない
日本国は中国に対し、15年にわたって侵略し、日本侵略軍は“戦争で戦争を養う(以戦養戦)”という政策に基づき、中国の占領区において、中国国民の財産を略奪及び搾取し、沢山の工場、企業が直接的に占領或いは支配され、そして、その製品も統制を受け、戦争の為に直接服務を行ったのである。偽軍組織の漢奸は、日本軍の勢力を借り、皆国民の財産を略奪し、金持ちになった。
日偽財産を接収処理する弁法は、戦場で戦利品を没収するという特徴を有する。近代国際法の戦争法規により、交戦国が戦場で獲得した敵の公私財産は全て戦利品と見なされた。ところで、ハーグ陸戦条約第4条、第14条及び1949年捕虜公約第18条は武器、馬匹、軍事資料を除き、捕虜に属する個人の全ての財産は彼らに帰属する。よって、国際法に拠ると、交戦国が押収しうる財産は、戦場で発見した価値がある公有財産及び一定範囲内にて戦争行動に直接或いは間接に投じられた私有財産なのである。ソ連は1945年に中国東北に残留していた日本国の公私財産を戦利品として要求した。その主張によると、全ての中国東北に残留し、且つ、日本軍隊に服務した公私財産は戦利品である。そして、ソ連は前述の地域に存在した、大部分の日本の公私財産を戦利品として押収した。*6その後の日ソ共同宣言には両国ともに前述の問題に触れず、その問題に対するそれぞれの立場を表明しなかった。よって、日本政府はソ連の“戦利品”という主張を黙認したことが伺える。つまり、旧ソ連の戦利品という主張が日本政府によって認められたと考えることができる。
1943年12月7日、即ちカイロ会談の1週間後、国民政府は、カイロの米中首脳合意を受け、政府政令の形で「敵産処理条例」を正式に公表した。この中で敵国公私財産の処理方法は国際法に従うほか、当条例に基づくこと(第一条)。敵国の公私財産は軍用品に充てられているものを押収すること、即ち一、不動産。二、輸送機械、船車、軍需品、糧食及びその他の軍需動産。三、現金基金、有価証券及び国家に課税されるべきもの(第三条)。敵国人民の私有財産で軍事用品に使用できるものは押収し、又は破壊すべきこと(第四条)。行政院に敵産の処理に関する「敵産管理委員会」を設け、組織規則を設定すること(第十二条)等の原則が定められた。また1944年1月7日、行政院は「敵産処理条例実施細則」という政令を公表し、敵産の登録及び管理方法を明らかにした。国際法規によると、少なくとも対日講和以前、中国政府によって押収された日本軍用品に充てられていた公私財産は戦利品と認定されるべきであり、これら財産と賠償には直接的な関係はない。
日本政府の主張する「在外資産評価額」の非科学性
さらに指摘しておく必要がある点として、日本政府の反論には以下の主張がある。「1946年9月、外務省及び大蔵省の共管で設置された在外資産調査会による「我国在外資産評価額推計」によると、終戦当時、中国に存在した日本財産の規模は、台湾425億4200万円、中華民国東北1465億3200万円、華北554億3700万円、華中及び華南367億1800万円と報告されている。」その主張には少なくとも次の二つの問題がある。第一に、日本国の推計は実物に照らして統計しておらず、単なる推算に基づく結論には科学上、法律上の意義が欠如していることである。第二に國際的な慣例になっている事実に関する調査方法は、紛争する国の間で共同調査団を設立する、或いは第三国の調査団に委託し、事実報告を作成することである。
米国の大統領は、満州における日本財産の実状調査を求めた。ポーレーは1946年4月30日調査員の初会合を開き、5月10日に来日し、翌11日マッカーサーを訪問し、その使命が書かれた書簡を手渡した。書簡の概要は次のとおり。「朝鮮及び満州で日本が行った工業化の程度と日本産業との結合度を調査し、賠償に充てられうる日本の設備を見出すべきこと。」「1946年5月25日、ポーレーは別途南京で中国政府と会談し、40日もの間、中国東北を視察した。7月22日帰国し、ポーレーはトルーマンに報告書を提出した。ここで注目すべきことは、ソ連は対日参戦で中国東北地方に入ったが、日本敗北後、ソ連軍は計画的に東北にある日本工業設備を撤去し、破壊した。ソ連の理論から言えば、これらの日本資産は全てソ連軍の戦利品であり、撤去するのは当たり前なのである。ポーレー調査団の統計によれば、約20億ドルの日本資産がソ連軍によって撤去され、その五分の四も破壊されており、これにより中国の経済復興は約一世代も遅れることになる。*7
15年にわたる侵略において日本の軍事に補充する為に中国東北に存在した工業基地、産業は、ソ連に押収されるか、又は破壊された。尚、中国の華北、華中、及び華南地域は中日両国の軍事戦場であった。これらの地域における一部分の個人財産を除き、日本側の主な財産は軍事武器であった。勿論、それら武器など財産は敵産であり、戦利品として押収すべきものである。
つまり、日本政府の「我国在外資産評価額推計」により推算された中国領域の日本財産価額には何ら科学性が存在せず、その時の推計した日本国民個人に属する合法財産が押収されたかどうかという実証も存在しない。尚、中国政府に押収された日本側の財産のうち、七十五パーセントが中国において中国国民の財産を略奪したものであった。よって、戦利品として押収された敵産を、日本国の戦争賠償として当て嵌めてはならないのである。
(2)中間賠償の問題について
戦後初期における米国の対日占領政策の基調は、日本の非軍事化、産業の平和化におかれた。賠償政策は直接の武装解除や軍事力の破壊のほか、日本の経済各分野からの戦争潜在力の除去と各戦災国の復興への寄与という形で現われた。1945年12月6日に、米国賠償大使であるポーレーは1週間にわたって中国各地を視察した後、ポーレー自らが策定した中間賠償計画を発表した。「連合国は日本に関して二つの義務を負っている。第一は日本の軍国主義としての再起を不可能にすること、第二は、経済的に安定させ、政治的には民主主義様式を発展させる道を開かなければならないことである。先ず挙げるべきことは、日本において過去に建設された諸施設は侵略戦争遂行の為に建てられた工場であり、支那事変(日中戦争)の間に拡大された施設である。…事実、日本の工業施設は、その大部分が戦争遂行に向けられていたものであり、甚大な破壊にも拘らず、日本の工業施設の多くの設備は、平和時において民需用として使用することが許可しうる限度以上に使用に耐えうる状態にある。かかる余剰は撤去されねばならぬ。」ポーレーは、日本の鉄鋼業生産能力では1931年の満州侵略時の二倍を上回る生産設備がいま尚使用し得る状態にあること、この余剰設備を撤去し関係諸国に移し、それによって諸国民の生活程度を向上させることができ、それが現在の日本人の生活水準を低下させることにならないと判断した。また、余剰設備の撤去が軍国主義の撲滅に係ることを強調し、この撤去によって必ずしも日本の工業力を完全に剥奪するものではないことも明言していた。*8
日本政府の反論には、次のような説明がある。「中国について、平和条約による最終的な賠償の前に、1945年12月の米国大統領に対する中間賠償計画に関する勧告案(所謂「ポーレー中間案」)に基づき、所謂中間賠償が行われた。これは、日本の非軍事化を目的として、余分な工業施設(資本設備)を撤去し、それを特にアジア近隣諸国に対する賠償の一部に充てるというものである。1950年5月までに、合計4万3919台の工場機械が梱包撤去され、その引き渡し済み物件の評価の合計は、昭和14年の価格で1億6500万円、当時のドル価格に換算して約4500万ドルであったが、その引取り国別評価額の内、中国が54.1パーセントを占めていた。」
しかし、これは正しくない。実は1949年5月6日、米国は賠償前渡指令の停止に踏み切っていた。前渡指令に基づき中国に割り当てられた賠償物件の内、重量で46%、価額30%がなお未搬送のまま残存していた(殷176)。*9しかも、54.1パーセント比率にしても、中国の中間賠償は僅か2434万ドルを占めていたに過ぎないのである。
1946年12月国民政府は行政院に賠償委員会を設置し、この委員会は、戦時中に中国の被った損害は以下の通りであると計算した。1,中国・台湾、フィリピンを除く東南アジアの損害は20億ドル、台湾の損害は60億円である。2,日本の在華資産を3億8千万米ドルと評価し、その中75%は中国からの侵奪財産である。3,中国の直接的な損害は金銀・交通設備・道路・船舶・農林・商工・水利・発電・公共家屋・個人財産を合わせて313
.42億米ドルで、間接的な損失も200億米ドル以上ある。*10(全面的な計算ではない)。
1991年11月中国政府国務院新聞弁公室は「中国人権状況」白書を公表し、戦争被害を次のように説明した。「1937年からの日本帝国主義の下に遂行された全面的な侵華戦争による死傷者数は2100万余り、残害致死者数は1000万余り。そのうち、1937年12月13日から後の6週間内に、日本軍は南京で30万人を虐殺した。全面侵華戦争期間(1937年-1945年)、中国地域で930余りの城市が日本軍に占領され、直接経済損失は620億米ドル、間接経済損失は5000億米ドルを超える。……社会財産が劫略し、中国人民は最低限の生存条件が失われた。ところで、以上の数字には、戦争中、日本軍に虐殺された中国同胞の生命の価値は含まれていないのである。」
1994年末に中国軍事科学院歴史研究部は「中国抗戦史」を発表し、その戦争被害について、再び調査し、その結果を次の通り公表した。「尚、近年の調査により、完全ではない統計で、抗日戦争中、中国軍隊死傷者は380万人余り、中国人民の犠牲者は2000万人余り、中国軍民死傷の総数は3500万人以上であった。中国の財産損失は600億米ドル余り(1937年米ドルとのレートで計算)、戦争消耗は400億米ドルで、間接の経済損失は5000億ドルにも達した。」*11
よって、仮に中国がその中間賠償により一部の賠償物件を取得していたとしても、それは至極有限なものであり、言いかえれば、象徴的な賠償ということしかできないのである。
仮に被害国が中間賠償前渡計画により一部の賠償を得ていたとしても、日本国との講和条約を締結する時にその対日賠償の権利を失うことにはならない。よって、中間賠償により利益を直接或いは間接的に獲得した国、例えば東南アジア諸国のフィリピン、ビルマ、インドネシア、マレーシア等は日本国との戦後処理で再び協議を行って、準賠償等の協定を締結した。中間賠償を施行する主な目的とは、軍国主義の撲滅にかかわる余剰設備の撤去であり、中間賠償を全面な戦後賠償に充当することはできないのである。
三、日本政府が『日華平和条約』を根拠に『日中共同声明』を否定する法律的地位と効力等に対する研究と批判
(一) 日本政府が『日華平和条約』をもって、『日中共同声明』を恣に否定する“根拠”
反論において、日本政府は次のように主張している。
「1952年4月28日、我が国と“中華民国”は『日本国と中華民国との平和条約(以下、『日華平和条約』と表記する)』を締結した。我が国に対する戦争補償の賠償請求権の問題に関しては、『日華平和条約』の議定書1(b)の規定によると次のとおりである。
‘中華民国は、日本国民に対する寛厚と善意の表徴として、サン・フランシスコ条約第十四条(a)1に基づき日本国が提供すべき役務の利益を自発的に放棄する。’(『日華平和条約議定書』より引用)
日本国及び日本国民と中華人民共和国及び中国人民双方の請求権、併せて上述のサン・フランシスコ平和条約第十四条(a)1を基礎にした賠償請求権は、上記『日華平和条約議定書』の規定及び『サン・フランシスコ平和条約(『日本国との平和条約』)』第十四条(b)の規定に基づいて考えると、既に放棄されている請求権なのである。」
日本と中華人民共和国間の戦後補償問題に対する反論として、日本政府は次のように主張している。
「共同声明は、当事国両国が各自の立場から、互いに協力して作り出した声明である。例えば、戦争状態の終了に関しては、『日華平和条約』第一条において次のように規定されている。‘日本国と中華民国との間の戦争状態は、この条約が効力を生ずる日に終了する。’(『日華平和条約』より引用)
日中間の戦争状態は、『日華平和条約』によって終了したというのが、我が国が一貫してとっている立場である。これは一度に限られた補償行為であり、法律的観点から論ずると、日本国とその当時の中国における合法政府である中華民国政府、即ち、法律の定めるところの国と国と間における問題は既に解決済みであると、日本政府は考えているのである。これに対し、中華人民共和国の立場は、「『日華平和条約』は始めから無効である」というものであり、この立場は、我が国の立場と根本的に異なっている。戦争状態の終了の問題においては、上述したとおり日中双方とも基礎にする立場が異なっていることにより解決が困難になっている法律的な問題があったけれども、双方の歩み寄った結果、『日中共同声明』第一項において次のように規定したのである。
‘日本国と中華人民共和国との間のこれまでの不正常な状態は、この共同声明が発出される日に終了する。’(『日中共同声明』より引用)
『日中共同声明』第一項において述べている“不正常な状態”とは、我が国の理解では、今まで我が国と中華人民共和国の間に国交がなかった状態であり、『日中共同声明』における見解と、日中間の戦争状態が『日華平和条約』によって終了したという見解は、いかなる矛盾もしていない。この表現は、日中関係のいかなる方面の意義においても正常化の観点からすると、日中双方の認識の一致を図ったものなのである。」
『日中共同声明』第五項に対する反論においては、日本政府は次のように主張している。
「賠償と財産及び請求権の問題と、戦争状態の終了は同じである。賠償と財産及び請求権の問題は一度に限られた補償行為であり、『日華平和条約』を根拠に考えると、法律上は補償問題が解決済みである、というのが我が国のとっている立場であり、我が国の立場と『日華平和条約』の有効性に対する中華人民共和国の基本的な立場が異なっていることに関して、解決を図らなくてはならないと考えている。この問題に関しては、日中双方の度重なる交渉の結果が、『日中共同声明』第五項に次のような言葉により表現されている。
‘中華人民共和国政府は、中日両国国民の友好のために、日本国に対する戦争賠償の請求を放棄することを宣言する。’(『日中共同声明』より引用)
日中両国は、互いの立場が異なることを十分に理解したうえで、自ら進んで現実に即してこの問題の完全且つ最終的な解決を望んだのである。この規定は、我々の見解と一致している。即ち、戦時中における日本国及び日本国民の行動が原因により発生した中国及び中国人民の賠償請求権は、前述したように法律の角度から考えると、『日華平和条約』に基づいて既に放棄されていると考えるのが、我が国の見解である。我が国のこの立場は、『日中共同声明』の道理と何ら変わりはない。よって、『日中共同声明』第五項は、国民の請求権問題は既に完全に解決済みであることを、その内容に含んでいると言うことができる。この一点に関しては、中国政府もまた、我が国と同様の見解と理解を示しているものと考える。」
また、日本政府は『日中共同声明』第五項に対する反論において、次のようにも主張している。
「このような状況の下作成された『日中共同声明』第五項は、我が国の立場と相対する立場の相手が互いに作り出したのである。よって、中国国民の中国国内法に基づいた請求権に対して、日本国及び日本国民がその義務を負う必要が全くないことは、『日中共同声明』第五項の規定によって明白なのである。」
以上のように、「戦争状態の終了」及び、賠償問題については、『日華平和条約』において解決済みという立場を日本政府はとっている。
(二) 日本政府の反論における『日華平和条約』等に関する謬論に対しての批判
1、日本国と中華民国政府の戦後処理の背景
中華人民共和国政府と中華民国政府の不参加にもかかわらず、日本は『サン・フランシスコ平和条約』に調印した。
日本の国会ではサン・フランシスコ条約の締結に関する審議の過程において、野党が団結して中華人民共和国政府と平和条約を締結すべきだ、との主張をした。それに対し、吉田茂首相は、台湾の国民政府は地方政権の一つに過ぎないと回答していた。吉田首相のこの回答は、米国政府と上院の国民政府支持者に大打撃を与えた。
このことがきっかけで、1951年12月、アメリカは再度ダレス(J. F. Dulles:1950年4月6日、米国国務長官に任命される)を特使として日本に派遣した。同月8日に挙行された吉田・ダレス会談の結果、日本は24日にダレス特使に渡した“吉田書簡”の中で、アメリカに次のように伝えた。「中華民国の国民政府が望むのであれば、日本は『サン・フランシスコ平和条約』の原則に従って、国民政府と日中国交正常化に関する条約を締結し、中国共産党政権とは締結しない。*12」と。日本が唯一恐れたのは、米国上院が『サン・フランシスコ平和条約』を批准しないことであり、それ故にアメリカが支持する中華民国と平和条約を締結する決定を下したのである。
1952年2月17日、日本国全権委員・河田烈が台北に赴き、1952年2月20日から正式に会談を開始し、4月28日に『日華平和条約』に署名、調印した。この間に行われた公式会談は3回、非公式会談は18回にものぼる。当初、中華民国は賠償を強硬に要求していたが、それは日本に対して賠償を要求しないと、中国大陸の“国民感情”を抑えることができないと考えたからである。この要求に対し、日本政府は、一度は会談を中止し、代表団を日本に呼び戻そうとすら考えていた。台湾の国民政府がこのように強硬な態度を採ったのは、米国上院の議員の一部を中心とする国民政府支持者たちの支持を期待していたからである。だが、米国上院が『サン・フランシスコ平和条約』を批准したため、国民政府の期待は外れ、賠償の要求を取り下げざるを得なくなった*13。このような背景があるが、形式上は、国民政府が自発的に賠償の要求を放棄する決定をしたことになっており、議定書上には、「中華民国は、日本国民に対する寛厚と善意の表徴として、サン・フランシスコ条約第十四条(a)1に基づき日本国が提供すべき役務の利益を自発的に放棄する。」(『日華平和条約議定書』1(b)引用)と記載されたのである。このようにして、『日本国と中華民国との間の平和条約』(略称は『日華平和条約』である)は1952年4月28日に署名され、8月5日から効力を発することになった。この条約は十四の条文から構成され、この他に議定書、交換文書がある。その中でも、“議定書”は、「(日華平和)条約の不可分の一部を」為している。
日本、台湾会談の経過と結果から考察すると、中国大陸から台湾に後退せざるを得なかった中華民国政府の国際的な地位は降下し、会談において弱い立場に立たざるを得ず、問題を円満に解決し且つ本来の意図に反しないため、堂々、寛厚且つ善意を以って自発的に賠償請求権を放棄したように演じ、これを以って日本が台湾政府を承認するように図ったのである。言うまでもないことだが、日本国と台湾が平和条約を締結することは、日本の国家利益と一致するのである。事実、“怨みを報いるに徳を以ってする”政策により賠償請求権を放棄した台湾の蒋介石政権に相対し、北京の毛沢東政権は頑として賠償を要求する態度をとり続けていた。北京の周恩来新政権の主張によると、中華人民共和国政府が日本に対して要求する賠償金額は、少なくとも500億米ドル(1946年当時の貨幣価値に基づいて日本円に換算すると、18兆円に達する)に相当する。
敗戦国たる日本は、アメリカが台湾を積極的に支持している背景の下、自国の優勢な地位を充分に利用し、地位的に弱い台湾政府を条約締結者として選択し、賠償請求権の放棄を強いたのである。
2、北京政府の『日華平和条約』に対する態度
対日平和条約に関して、1950年12月に北京政府首相・周恩来が声明を発表した。周恩来の声明は、次の三つの内容から構成されている。
① 北京政府こそが中国における唯一の合法政府であり、対日講和条約の参加権を有しているのである。それ故に、台湾の国民政府には中国の代表者たる権利はない。
② 講和条約の基礎となるのはカイロ宣言、ヤルタ協定、ポツダム宣言及び無条件降
伏後の日本の基本政策である。
③ カイロ宣言に基づくと、台湾及び澎湖(ポンス)列島は北京政府に帰属する。
周恩来は、声明によって日本政府の態度を批判すると同時に、アメリカが日本と平和条約を締結するように台湾国民政府を差し向けたことに対しても、批判を加えている。日華平和条約の締結は、新中国の人民の強烈な抗議を引き起こした。1952年5月5日、即ち日華平和条約署名1週間めにあたる日に、首相・周恩来は中華人民共和国政府を代表し、次のような厳正な声明を発表した。
「アメリカが宣布し、効力を発した全ての対日単独平和条約は、絶対的に承認することはできない。中国人民を公の場で侮辱すると同時に敵視した吉田・蒋介石平和条約に対し、断固として反対する。」
同時に、蒋介石の行った“賠償要求の放棄”の承諾を「他人の物で自分の面子を立てる」ものとして激しく非難し、中国政府と中国人民は、蒋介石の承諾を絶対に承認しないと述べた。周恩来は、日華平和条約は違法且つ無効の条約であると、厳正に表明した*14。
3、『日華平和条約』の問題点
筆者は、『日華平和条約』には、以下に挙げる五つの問題があると考えている。
(1)前述したように、サン・フランシスコ講和会議は、戦時下において最大の損害を受け、且つポツダム宣言の構成国であり調印国である中国の参加を招請しなかった。その当時、中国内戦の結果、ポツダム宣言の署名国家の中では旧ソ連とイギリスが、北京政府が中国における唯一の合法政府であることを承認済みであった。したがってアメリカが台湾の国民政府に講和会議へ出席する代表権を与えるすべはなかった。当時の反共政策、中国敵視政策によって、アメリカが圧力をかけたことにより、日本が国民政府と『日華平和条約』を締結することを決定した。
(2)国際法の原則によると、内戦状態の時に革命によって樹立された革命政府の実際的支配が確立する以前に、旧政府と他国とが締結した条約などは、新しく樹立された革命政府に対しても拘束力をもつ。だが、革命政府が国内において実際的な支配を揺るぎないものとして確立した後は、旧政府と他国が締結したあらゆる条約は革命政府に対しての拘束力を失う。『日華平和条約』が締結された当時、新中国政府は中華民国政府が過去に支配していた地域のうち、台湾、澎湖諸島、金門そして馬祖二島の計四箇所を除いて、既に中国の全領域を支配しており、更に、支配地域における有効な支配期間は二年半にも及んでいた。故に、上述した国際法の原則に基づいて考えると、日華平和条約は中国革命後の北京政府に代表される中国に対しては、拘束力がないのである。
(3)『日華平和条約』は中華人民共和国政府に対して拘束力がないばかりか、そもそも無効な条約である。日華平和条約は両国の戦争状態の終了に関しても規定があり、日華平和条約議定書は中国が日本にする戦争賠償請求権を放棄する旨を定めている。言うまでもなく、戦争は国家間の法律状態の一種であり、国家間の戦争状態の終了は当然国家の名義を以って宣言されるべきであり、政府間の名義によって終了を宣言することはできない。政府が国家から権利を授与された場合には、政府は平和条約を締結する権利を有することになる。
だが、『日華平和条約』は締結国双方の国家の名義を以って締結されているため、当時の国民政府が中国全土を代表して日中間の戦争状態を終了させる効力を持つ条約を日本国と締結できるか否か、分析しなければならない。当時、台湾に追いやられた国民政府は、限られた領域を占拠していた或いはそこの住民を支配していたにすぎず、中国本土に反撃する或いは本土を支配することは実質不可能であった。過去の歴史上かつては中国全土を代表する合法政府であったとしても、人民の武装蜂起により、その法律的地位は交戦団体の地位にまで下がってしまった。
一国にはその国の代表としての政府は一つしか存在しないことは、当然のことである。内政の動乱の時期には複数の政府が樹立される可能性はあるが、それは暫時のことに過ぎない。中華民国の憲法の効力は中国の全領土にまで及び、既に台湾国民政府は中国大陸の全領土と住民に対する支配力を完全に失っていた。それ故に、日華平和条約第一条の規定は条約締結の主体たる国家の条約締結能力を備えていない現実である。『条約法に関するウィーン条約(以下、『ウィーン条約法公約』と表記する)』は、国際条約を締結する主体としての国家が条約締結能力を備えている事を前提にして定められている。国民政府が中国全土を代表する資格を備えないで日本国と平和条約を締結したことは明らかであり、故に、『日華平和条約』締結により効力を持つとされる全中国人民の利益の処分に関する条文は、最初から、その効力を持ち得ないのである。
もっとも、日本国も台湾国民政府も、条約締結当時この問題に気づいていのであろう、日華平和条約の関連文書――日華平和条約議定書において、所謂補足説明を行っている。日華平和条約議定書の第一項(a)は、次のように規定している。
「サン・フランシスコ条約において、期間を定めて、日本国が義務を負い、又は約束をしているときは、いつでも、この期間は、中華民国の領域のいずれの部分に関しても、この条約がこれらの領域の部分に対して適用可能となった時から直ちに開始する。」(『日華平和条約議定書』より引用)
日本はこのように強硬な立場を以って、国民政府に対して賠償を放棄するように迫ったのであるが、日本側は国民政府が中国本土における実質的な支配力に欠乏していることを気にかけていた。その上、国民政府の実質的な支配力が欠乏していたため、日華平和条約及びその議定書に署名、調印すると同時に、双方が公文を交換した。日本国全権委員・河田烈は、中華民国全権委員・葉公超に宛てた公文において、次のように述べた。
「書簡をもって啓上いたします。本日署名された日本国と中華民国との間の平和条約に関して、本全権委員は、本国政府に代って、この条約の条項が、中華民国に関しては、中華民国政府の支配下に現にあり、又は今後入るすべての領域に適用がある旨のわれわれの間で達した了解に言及する光栄を有します。本全権委員は、貴全権委員が前記の了解を確認されれば幸であります。以上を申し進めるのに際しまして、本全権委員は、貴全権委員に向かって敬意を表します。」*15(『日華平和条約に関する交換公文』第一号より引用)
中華民国全権委員・葉公超は、日本国全権委員・河田烈に宛てた公文で、次のように返答した。
「書簡をもって啓上いたします。本日署名された中華民国と日本国との間の平和条約に関して、本全権委員は、本日付の貴全権委員の次の書簡を受領したことを確認する光栄を有します。本日署名された日本国と中華民国との間の平和条約に関して、本全権委員は、本国政府に代って、この条約の条項が、中華民国に関しては、中華民国政府の支配下に現にあり、又は今後入るすべての領域に適用がある旨のわれわれの間で達した了解に言及する光栄を有します。
本全権委員は、貴全権委員が前記の了解を確認されれば幸であります。本全権委員は、本国政府に代って、ここに回答される貴全権委員の書簡に掲げられた了解を確認する光栄を有します。
以上を申し進めるのに際しまして、本全権委員は、貴全権委員に向かって敬意を麦します。」(『日華平和条約に関する交換公文』第一号より引用)
議定書及び交換公文において、双方が重点的に解決しようとしている問題点は、「この条約の条項が、中華民国に関しては、中華民国政府の支配下に現にあり、又は今後入るすべての領域に適用がある旨のわれわれの間で達した了解に言及する光栄を有します。」という、正にこの一文にある。
ところで、『ウィーン条約法公約』第二十九条には、次のような規定がある。
「条約は、別段の意図が条約自体から明らかである場合及びこの意図が他の方法によって確認される場合を除くほか、各当事国をその領域全体について拘束する。」(『条約法に関するウィーン条約』より引用)
この条文は、公約が規定する条約の適用地域に関しての基本原則の一つである。一般的には、条約は締結する当事国の領土全域に適用されるものである。条約締結国が条約の適用地域を締結国の領土、領空の一部のみに制限できるとは言え、国家間における戦争状態の終結――特に、日中戦争のように日本・中国両国の間で行われた戦争の終結問題に関して、平和条約を締結することは、双方の国家の全領域に条約が適用されることを前提にして条約を締結するのであり、一国の一部領域にのみ条約の効力が及ぶことなどありえない。仮に、締結した平和条約の効力がその当時において一国の一部領域及び一部の住民にだけ及ぶのであるならば――即ち、交換公文で述べられているように「中華民国政府の支配下に現にあり、又は今後入るすべての領域に適用がある」ならば、このようにその効力が将来にまで約束された条文は、現在の戦争状態を終了させる目的で締結される平和条約に、根本的に違反しているのである。それ故に、このように“平和条約”と名づけられた条約は、締結国全域と交戦国との交戦状態を今すぐ終了させるために締結されたものではないばかりか、交戦状態にある当事国ですらいつになったら戦争状態が最終的な終結を迎えるのか、見当がついていないことを証明している。『日華平和条約』が無効な条約であることの根拠は、結局のところ、日本国との『日華平和条約』締結は台湾国民政府の越権行為であり、日本国は国民政府が中国全土を代表して交戦状態を終了させる平和条約を締結する権利能力を持ち得ないことを知っていたにも拘らず、尚且つ国民政府と平和条約を締結したことにある。よって、未解決の戦後補償問題に関して、日本政府はその責任を承認し、且つ日本政府にはその責任を負う義務があるのである。
『日華平和条約』締結後、交戦状態の終結が中国全土に及んだかどうかの問題に関して、日本政府には動揺が見られる。1970年12月14日の国会において、当時の首相・佐藤栄作はその日の午前の発言で、「日中両国の交戦状態は『日華平和条約』締結により終了したわけではない」と述べている。ところが同日の午後、佐藤は午前に自身が述べた全ての発言を否定している*16。このように、日本政府自身、『日華平和条約』の法律効果に対しての理解が明確ではないのである。
上述した内容から判断すると、日本政府の反論の根拠である、「戦争状態の終了に関しては、『日華平和条約』第一条、「日本国と中華民国との間の戦争状態は,この条約が効力を生ずる日に終了する」ものと認識している」という主張は、完全に合法的な根拠がないのである。
(4)日本政府は、その反論において次のように主張している。
「1952年4月28日、我が国と“中華民国”は『日本国と中華民国との平和条約(以下、『日華平和条約』と表記する)』を締結した。我が国に対する戦争補償の賠償請求権の問題に関しては、『日華平和条約』の議定書1(b)において次のように規定している。
「中華民国は、日本国民に対する寛厚と善意の表徴として、サンフランシスコ条約第十四条(a)1に基づき日本国が提供すべき役務の利益を自発的に放棄する。」(『日華平和条約議定書』より引用)
日本国及び日本国民と中華人民共和国及び中国人民双方の請求権、併せて上述のサン・フランシスコ平和条約第十四条(a)1に基づく賠償請求権は、上記『日華平和条約議定書』の規定及び『サンフランシスコ平和条約(『日本国との平和条約』)』第十四条(b)の規定に基づいて考えると、既に放棄されているのである。」
また、日本政府は次のようにも主張している。
「賠償と財産及び請求権の問題と、戦争状態の終了は同じである。賠償と財産及び請求権の問題は一度に限られた補償行為であり、『日華平和条約』を根拠に考えると、法律上は補償問題が解決済みであるというのが、我が国の見解である。」
しかし、国際法の見地に立つと、『日華平和条約』の主体の一方が条約締結能力を超越した行為をとったことになるため、日華双方の条約締結は両国の交戦状態を終了する権利もないし、台湾の国民政府が北京政府に代って、中国人民の対日戦争賠償請求権を放棄する権利もないのである。中華民国国会が『日華平和条約』を批准する過程においても、その最高権力機関の権力の淵源に内実が何もないことは明らかである。故に、国民政府が条約を締結する資格がないにも拘らず、全中国人民からの特別な権限の委託もなく国家と人民の対日戦争賠償請求権を放棄した行為は非法行為であり、よって無効である。
(5)中華人民共和国成立後、当初は台湾問題を中国の内政問題だと認識し続けていたアメリカであるが、1950年6月、朝鮮戦争勃発後、台湾を極東における戦略基地の一つにしようという目論見もあり、突然中華人民共和国政府を敵視するようになった。その上アメリカは、当初は北京政府と和平会談を行おうとしていた日本国に対して、台湾の国民政府と平和条約を締結しなければサン・フランシスコ条約を批准しないと圧力をかけた。日本政府に、台湾を条約締結国として選択した方が日本の国益につながるという考えがもともと存在したのだが、このような選択の裏には、日本国が台湾を利用することにより国際社会に認められたいという期待もあり、また、和平会談の内容により台湾を追い詰めて服従させ、中国大陸における戦争賠償問題に関しての会談の挙行を回避する、或いは放置しておこうという打算もあった。このような外交戦略は、いわゆる西側陣営の一員に組み込まれようとした、日本の国家利益と一致したのである。その結果、日本政府は北京政府を敵視し、台湾国民政府と講和に関する“吉田書簡”を発表し、併せて最終的に国民政府と平和条約を締結した。要するに、上述した国際法の原則に基づいて考えると、自称中国国家の代表者である台湾国民政府と日本国とが署名、調印した『日華平和条約』には重大な欠陥があり、侵略戦争の被害国である中国に対して、如何なる影響力をも持たないのである。
(三) 『日中共同声明』、『日中平和友好条約』締結の実質的内包
1. 日中平和条約締結の歴史的背景
1972年2月、アメリカのニクソン大統領が訪中し、米中双方が『上海公報』を発表した。『上海公報』は、アメリカが二十数年に及んで採り続けた対中抑止政策の転換を告げている。日本政府は依然として以前のアメリカの対中抑止政策に追従し続けていた。1971年9月22日、当時の首相・佐藤栄作は、中国の国連代表権問題に関して、第26回国連大会でアメリカとともに提出した所謂“逆重要事項指定”及び“二重代表制”を採決することを日本政府は決定したと宣布した。日本政府は台湾当局を国連に引き続き在籍させようと企んでいたのである。ニクソン訪中後、佐藤内閣の中国敵視政策に対する日本の民間レベルでの反発は非常に激しく、日本全国が一丸となって反対の声をあげ続ける中、佐藤内閣はついに退陣に追い込まれた。当時、日本の野党であった社会党、民社党、公明党各政党は先を争って代表団を中国に派遣し、日中国交正常化に関する原則を提出した。1972年4月13日、日本の民社党訪中代表団と中日友好協会代表団とが共同声明を出し、次に挙げる復交三原則を発表した。
(1)世界には一つの中国しかなく、それは中華人民共和国である。中華人民共和国は中国人民を代表する唯一の合法政府である。「二つの中国」、「一つの中国、一つの台湾」、「一つの中国、二つの政府」など荒唐無稽な主張に断固反対する。
(2)台湾は中華人民共和国の領土の不可分の一部であり、しかもすでに中国に返還されたものである。台湾問題は、純然たる中国の内政問題であり、外国の干渉を許さない。「台湾地位未定」論と「台湾独立」を画策する陰謀に断固反対する。
(3)『日華条約』は不法であり、無効であって、破棄されなければならない。(『復交三原則』より引用)
1972年9月25日、日本国首相・田中角栄が政府代表団を率いて訪中した。同年9月29日、中国政府を代表した中国首相・周恩来と中国外務部長・姫鵬飛並びに日本政府を代表した首相・田中角栄及び外務大臣・大平正芳が署名したことにより、ここに日中両国の共同声明が発表されたのである。
日中国交が樹立されたのに伴い、日本と台湾との政府当局間の関係はすべてその法律的効果を失い、民間でのみ台湾との関係が保持されたのである。
1978年7月21日、日中双方は北京にて再び会見を開き、8月12日、日中双方は北京において『日本国と中華人民共和国の間の平和友好条約』(以下、『日中平和友好条約』とする)に、正式調印した。1978年8月16日、中国人民大会常務委員会はこの条約を批准した。10月16日、18日及び20日、日本の衆参両議院が政府に先立ちこの条約を批准した。1978年10月22日から29日にかけて、中国副首相・鄧小平が中国代表団を率いて訪日し、同月23日、日中双方が『日中平和友好条約』の批准書を交換し、ここに『日中平和友好条約』が正式に発効した。
2,日中共同声明』と復交三原則に関する問題
『日中共同声明』では、次のように言及している。
「日本側は、中華人民共和国政府が提起した「復交三原則」を十分理解する立場に立って国交正常化の実現をはかるという見解を再確認する。中国側は、これを歓迎するものである。」(『日中共同声明』より引用)
この記載は、日本政府は中国政府が提出した復交三原則が日中国交正常化の前提条件であることを十分に理解し、日本国が充分な理解に基づいて中国政府との共同声明を発表したと、言い換えることができる。よって、この声明の発表によって、日本政府が中国政府と同じ立場に立つこと――即ち、『日華平和条約』は無効条約であるとする立場に立つことを承諾したのだと、いうことができる。『日中共同声明』のみならず、その後に発表された『日中平和友好条約』においても、「前記の共同声明が両国間の平和友好関係の基礎となるものであること及び前記の共同声明に示された諸原則が厳格に遵守されるべきこと」を重ねて確認している。『日中共同声明』及び『日中平和友好条約』の条文によって、日本政府は“充分に理解する”立場にあるのみならず、諸原則を厳格に遵守しなければならない問題にも直面しているのである。条約が謳っている厳格に遵守されるべき諸原則の中には、『復交三原則』も当然含まれている。
『復交三原則』の第一原則は、「中華人民共和国政府が中国の唯一の合法政府であることを承認する」(『日中共同声明』第二項より引用)ことである。この原則に関しては、日中両国間で討論すべき問題はない。『復交三原則』の第二原則は、「台湾は中華人民共和国の領土の不可分の一部であり、しかもすでに中国に返還されたものである。台湾問題は、純然たる中国の内政問題であり、外国の干渉を許さない」(『復交三原則第二項』より引用)ことである。この問題に関しては、『日中共同声明』第三項の形式により問題の解決が図られているのだが、即ち、「中華人民共和国政府は、台湾が中華人民共和国の領土の不可分の一部であることを重ねて表明する。日本国政府は、この中華人民共和国政府の立場を十分理解し、尊重し、ポツダム宣言第八項に基づく立場を堅持する」のである。『ポツダム宣言』第八項には「カイロ」宣言ノ条項ハ履行セラルベクとあり、『カイロ宣言』では、次のように規定されている。
「同盟国の目的は、…中略…並びに満洲、台湾及び澎湖島のような日本国が清国人から盗取したすべての地域を中華民国に返還することにある。」(『カイロ宣言』より引用)
『カイロ宣言』が指し示すところの“中華民国”は実際の国土としての中国大陸を意味しており、それ故に、北京政府は台湾島が中国の領土であると主張するのである。『復交三原則』の第三原則は、「『日華条約』は不法であり、無効であって、破棄されなければならない。」*17と言うものである。これらの『復交三原則』に照らあわせて、以下、いくつかの問題を考察していきたい。
第一に、戦争状態の終了に関して考察する。『日中共同宣言』第一項に次のように記述されている。
「日本国と中華人民共和国との間のこれまでの不正常な状態は、この共同声明が発出される日に終了する。」(『日中共同声明』第一項より引用)
この項の含意は戦争状態の終了についてであるが、戦争状態に関しては「日本国と中華人民共和国との間のこれまでの不正常な状態」と曖昧に表現されている。また、『日中共同声明』の前文には、次のような表現が見られる。
「両国国民は、両国間にこれまで存在していた不正常な状態に終止符を打つことを切望している。戦争状態の終結と日中国交の正常化という両国国民の願望の実現は、両国関係の歴史に新たな一頁を開くこととなろう。」(『日中共同声明』前文より引用)
また、『日中共同声明』第一項の主語は政府ではなく、他でもない“日本国と中華人民共和国”である。上記の記載から、日中両国政府は『日華平和条約』の締結により日中両国の戦争状態が終了したと認識していないことを示しているのである。これは『日華平和条約』の否定を意味している。
第二に、『日華平和条約』では戦争賠償請求権を放棄していることに関して考察する。『日中共同声明』第五項には、次のような規定がある。
「中華人民共和国政府は、中日両国国民の友好のために、日本国に対する戦争賠償の請求を放棄することを宣言する。」(『日中共同声明』第五項より引用)
ここでは“戦争賠償の請求を放棄する”と規定しているのであり、“戦争賠償請求権を放棄する”と規定しているのではない。この見解に対しては、日本の学者の中でも意見が割れており、中国政府が依然“請求権”を保留していると考える学者もいれば、日本政府が『日華平和条約』を締結した時点で、事実上“戦争賠償請求権の放棄”に関して法的手続は全て完了しており、これを踏まえて考えると、“戦争賠償請求権”は既に存在しないのだから、『日中共同声明』では“戦争賠償の要求の放棄”というように、“要求”を放棄する旨を表明したのである、と考える学者もいる*18。
第1番目の観点では、“戦争賠償の要求の放棄”と“戦争賠償請求権”は完全に切り離されて扱われており、その解釈の違いの中から異なる法律的含意を導き出そうと試みていることがわかる。
第2番目の観点は明らかに復交三原則に違反しており、この問題は『日華平和条約』が無効条約なのか、それとも失効条約なのかと言う問題にまで波及してしまう。よって、この問題に関しては、以下に述べる『日華和平条約』の効力問題に関する討論の中で説明を加えたいと思う。
最後に、『日華平和条約』の効力問題に関して述べる。『日中共同声明』では、『日華平和条約』の効力問題に触れられることが無く、『日華平和条約』に対しては、日本が一方的に終了を宣言したに過ぎない。つまり、日本政府の解釈としては、『日中共同声明』に調印し、同条約が効力を発する前においては『日華平和条約』は有効な条約であるという解釈で、北京政府側はこれに対して軽視的形式を以てし、並びに政治的な方法をもって解決を図るよう強調している*19。
1972年9月26日、魚釣台の迎賓館において挙行された第2回日中首脳会談時に、周恩来は次のように述べた。
「我々は、日本政府首脳が国交正常化問題を法律的でなく、政治的に解決したいと言ったことを高く評価する。政治的な解決は、比較的容易であるし、双方の立場に配慮することができる。仮に条文上でのみ解釈をするならば、時には互いに理解し合えない箇所も出てきて、対立を生じさせてしまうこともあるだろう。日中関係は、米中関係とは異なるものであり、我々双方には既に直ぐにでも国交を回復する準備がある。国交を回復したいのならば、大平外相が述べたように、蒋介石政権との国交を断絶しなくてはならない。…中略…今回、田中首相と大平外相が訪中する運びとなったが、田中・大平両首脳は我々が提出した「復交三原則」を充分に理解すると言った。その基礎の上に立って、中国側は日本側の問題に配慮すると言った。そうでなければ、国交正常化はあやしいものとなる。」(『田中総理・周恩来総理会談記録』参照)9月28日午後、周恩来と田中角栄は最後の首脳会談を挙行した。日本が如何にして台湾問題を処理するかについて話し合いが行われ、その席において周恩来は原則を堅持しながら、融通のきく方法を用いて、次のように述べた。「明日(29日)大平大臣が『日中共同声明』に調印後、田中首相の指示に従って、記者会見で日台外交関係が切れることを声明されると聞いたが、大いに歓迎する。」(『田中総理・周恩来総理会談記録』参照)9月29日午前、『日中共同声明』の調印式が終了した後、大平正芳は田中角栄の指示及び周恩来に向けた承諾に従って、民族文化宮の大広間に設置された北京プレスセンターにて、記者会見を行った。その席において、大平は次のように公言した。「カイロ宣言において,台湾は中国に返還されることがうたわれ,これを受けたポツダム宣言,この宣言の第8項には,カイロ宣言の条項は履行されるべしとうたわれておりますが,このポツダム宣言をわが国が承諾した経緯に照らせば,政府がポツダム宣言に基づく立場を堅持するということは当然のことであります。…日中関係正常化の結果として,日華平和条約は,存続の意義を失い,終了したものと認められる,というのが日本政府の見解でございます。…日中国交正常化の結果といたしまして,台湾と日本との間の外交関係は維持できなくなります。…したがいまして所要の残務整理期間を終えますと,在台日本大使館は閉鎖せざるを得ないと思います。」*20(『大平外務大臣記者会見詳録』より引用)
日中首脳会談及び『日中共同声明』の条文の表現形式及び記者会見における日本政府代表の発言から考えると、日中両国政府は、声明調印後の法律関係を樹立するのに政治的解決手段をとった。だが、前述の『日華平和条約』の法律的地位――即ち、『日華平和条約』は結局、無効条約なのか終了したのかをめぐって、その政治的解決方法は全く明確に処理されていない。日本外務大臣・大平正芳は、「日華平和条約は,存続の意義を失い,終了したものと認められる,というのが日本政府の見解でございます」と補足説明しているが、依然として曖昧である。だが、このような政治的手段が現実の法律問題を解決することは不可能なのである。
『日華平和条約』の終了と同条約の無効の問題に関しては、終了も無効も全て条約の失効を意味する表現であるが、“終了”と“無効”には本質的な意味の違いがある。
まず、条約の終了或いは無効状態を産出する原因に関して考察する。条約無効の原因は原始性であり、原始性とは、条約を締結した当初から原因が存在していたことを指す。その原因は、条約締結権がない或いは条約締結能力を超越した条約締結、誤解、詐欺、賄賂、脅迫、強制法に違反する等である。条約終了の原因は伝達性であり、伝達性とは、条約締結後に原因が発生したことを言う。その原因は、他国の同意、当事者の国際法的人格の喪失、義務の履行が不可能であること、(長期にわたって条約を適用しないこと)、義務の完全なる履行、新しい強制法の産出、一方的な条約締結、条約締結状態の解除、条約からの脱退、戦争状態、一方的な条約違反、情勢の根本的変更等である。
次に、条約の失効の時間に関して考察する。絶対的に無効な条約は始めからその効力を発しないのだが、終了された条約は締結後、法的に終了すべき事由が出現した時に失効するのである。
政治的解決方法では、キーポイントとなる法律問題を解決することができないばかりか、後の世代に曖昧な部分を残してしまう。だが、国際法を根拠に考えると、『日華平和条約』は、無効条約として認定されるべきものである。仮に、日本政府が『日中共同声明』を締結、発表する以前に、台湾国民政府を中国の“正式な政府”であると認識しているとしたら、『日華平和条約』第一条の次の規定がその根拠である。「日本国と中華民国との間の戦争状態は、この条約が効力を生ずる日に終了する。」(『日華平和条約』より引用)
そうすると、1952年8月5日『日華平和条約』が効力を発した日を起算点とし、日中両国の戦争状態は既に終了しているのであって、『日中共同声明』第一項の「日本国と中華人民共和国との間のこれまでの不正常な状態は、この共同声明が発出される日に終了する」(戦争状態の終結を意味する)と言う記述は余計であり、矛盾的である。
同様にして、『日華平和条約』議定書第一項(a)においては、次のように記載されている。「(a)サン・フランシスコ条約において、期間を定めて、日本国が義務を負い、又は約束をしているときは、いつでも、この期間は、中華民国の領域のいずれの部分に関しても、この条約がこれらの領域の部分に対して適用可能となった時から直ちに開始する。」(『日華平和条約議定書』より引用)上記の規定により、『日中共同声明』第五項もまた、余計なものになるのである。「中華人民共和国政府は、中日両国国民の友好のために、日本国に対する戦争賠償の請求を放棄することを宣言する。」(『日中共同声明』より引用)
何故なら、日本国と当時の中国代表としての中華民国双方は、賠償に関する各自の権利と義務の問題を解決済みであり、この権利と義務の対象は既に存在していないからである。よって、既に解決済みの問題に関して、別の国際法的主体に対しても同様な解決法を講じようと言うのは、無効であるのみならず論理的に不可思議である。
『日中共同声明』は『日華平和条約』を直接的に否定しなかったが、『日中共同声明』は日本国側が、中華人民共和国政府が提出した『復交三原則』の立場を充分に理解したことに関して書かれており、その上『日中共同声明』発表後に調印された『日中平和友好条約』においても、再度「前記の共同声明が両国間の平和友好関係の基礎となるものであること及び前記の共同声明に示された諸原則が厳格に遵守されるべきことを確認」しているのである。
そして、『復交三原則』の最後に挙げられている原則が『日華平和条約』を違法であり、条約は無効だとするものである。それ故に、日本政府が『日華平和条約』を無効とする立場を遵守しなければならないことは明白である。
四、中国政府の権限及び《日中共同声明》第五項の意味について
1972年の《日中共同声明》第五項に:「中華人民共和国政府は、中日両国国民の友好のために、日本国に対する戦争賠償の請求を放棄することを宣言する。」と述べられている。この条文の内容を見ると、中国政府が放棄したのは、中国政府の日本国に対する戦争賠償請求にすぎず、中国国民の日本国に対する損害賠償の問題については、少しも触れられていない。よって、この条項の「日本国に対する戦争賠償の請求を放棄すること」の中に、中国国民の日本国に対する損害賠償請求権が含まれていると解釈することは国際的な通例に反するだけでなく、文言上の論理と法律上の根拠も欠けている。
中日両国間において国家名義で調印されたのは《日本国と中華人民共和国との間の平和友好条約》である。そして、《日中共同声明》の正式名称は《日本国政府と中華人民共和国政府の共同声明》であり、この声明の主体は、日中両国政府であり、これは国家名義で調印されたわけではない。事実上、《日中共同声明》第五項の主語は中華人民共和国政府であり、その宣言で放棄した日本国に対する戦争賠償請求は、この条項の主語である主体に属する部分のみであり、即ち、中華人民共和国政府の権限範囲内に属する事物のみに関する賠償請求の放棄にすぎない。
《日ソ共同宣言》と《日中共同声明》の違い
1972年の《日中共同声明》の名称から推測するに、《日ソ共同宣言》の様式を手本としているようである。この両国家間の声明を比較すると、更に、《日中共同声明》が完全に民間の対日賠償請求権を放棄していないことを説明できる。
第一に、指摘する必要があるのが、《日ソ共同宣言》の正式名称が《日本国とソヴィエト社会主義共和国連邦との共同宣言》であり、宣言の前文において明確に1956年10月13日から19日までモスクワで、日本国及びソヴィエト社会主義共和国連邦の全権団の間で交渉が行われた、と説明されている点である。日本国側からは、内閣総理大臣鳩山一郎、農林大臣河野一郎、衆議院議員松本俊一が参加し、ソヴィエト社会主義共和国連邦側からは、ソヴィエト連邦大臣会議議長エヌ・ア・ブルガーニン、ソヴィエト連邦最高会議幹部会員エヌ・エス・フルシチョフ、ソヴィエト連邦大臣会議議長第一代理ア・イ・ミコヤン、ソヴィエト連邦第一外務次官ア・ア・グロムィコ、ソヴィエト連邦外務次官エヌ・テ・フェドレンコが参加した。宣言の引用文と交渉の代表から見るに、これは一つの国家間の宣言であり、両国政府間の宣言ではないことが分かる。ところで、《日中共同声明》の正式名称は《日本国政府と中華人民共和国政府の共同声明》であり、1972年9月27日に毛沢東主席が田中角栄総理大臣と会見した際のものである。しかし、これはただ「双方が真剣かつ友好的な話合いを行った」にすぎず、当時、毛沢東主席は具体的な日中の折衝には参加しなかった。《日中共同声明》の前文には:「田中総理大臣及び大平外務大臣と周恩来総理及び姫鵬飛外交部長は、日中両国間の国交正常化問題をはじめとする両国間の諸問題及び双方が関心を有するその他の諸問題について、終始、友好的な雰囲気のなかで真剣かつ率直に意見を交換し、次の両政府の共同声明を発出することに合意した。」と記述されている。この文書に署名した中国側代表は、国務院総理周恩来、外交部長姫鵬飛、日本側代表は内閣総理大臣田中角栄、外務大臣大平正芳である。よって、《日中共同声明》はまさしく日中両国政府間の声明である。
第二に、《日ソ共同宣言》の第十項に:「この共同宣言は批准されなければならない。この共同宣言は、批准書の交換の日に効力を生ずる。」と規定されている。ここでの批准の主体は各国家の最高権力機構を指している。しかし《日中共同声明》は、批准事項までは話が及んでいない。言い換えれば、日中両国政府の交渉と処分の内容は、各政府の有する権限の中のみであり、超越した部分については無効である。
ローターパクト(Lauterpacht)編著の『オッペンハイム国際法』の中に、戦争の概念について以下のような記述がある。「戦争は国家間が互いの征服を目的として行う武力闘争である。」*21「通常の戦争の終結方式は講和条約の締結もしくは交戦相手の滅亡とする。」*22「但し、もっともよくある戦争の終結方法は、講和条約の締結である。国際法に照らすと、講和条約締結の資格は国家元首に属する。但し、国家元首が締結した講和条約が自国の憲法の制限に反する場合、このような講和条約は元首の越権なので、国家に対して効力を発生しない。ある国家の憲法では、別の方法で以ってこの問題を解決しており、憲法は宣戦と和睦の権利を同一人物に授けるとは限らない。交戦国双方が講和条約の締結を以って戦争終結の準備をしていたとしても、往々にして即刻全ての条項について適切な話合いができるわけではない。このような状況下では、往々にして、先ず、いわゆる初期の講和条約を締結し敵対行為を停止し、その後、正式な講和条約の締結で以って初期の講和条約に替える。この種の初期の講和条約は、それ自身も一つの条約であり、双方が重要と認めるいくつかの和平条件の協議についての締結を含む。初期の講和条約は他の全ての条約と同じく拘束力があるため、必ず批准を得なければならない。」*23(以上 ローターパクト編著『オッペンハイム国際法』より引用) 国家間の締結権は、通常、国家元首が有するが、ある国家の憲法は、多くの事項に関する締約権を政府に任せる形で実行している。この様な状況下で、条約に効力を発生させるには、必ず各締約国の国内憲法が権限を授けることを依拠とする。よって、原則上、国家最高権利機関が権限を授かっていない、もしくは批准を獲得していない場合、締結された講和条約に効力は無い。
《日ソ共同宣言》は正式な講和条約ではないが、少なくとも初期の講和条約であり、宣言の主体は各自が国家を代表する形で締結しており、批准を得て効力が発生している。よって、1956年10月19日に締結した《日ソ共同宣言》第一項に:「日本国とソヴィエト社会主義共和国連邦との間の戦争状態は、この宣言が効力を生ずる日に終了し、両国の間に平和及び友好善隣関係が回復される。」 第六項に:「ソヴィエト社会主義共和国連邦は、日本国に対し一切の賠償請求権を放棄する。日本国及びソヴィエト社会主義共和国連邦は、1945年8月9日以来の戦争の結果として生じたそれぞれの国、その団体及び国民のそれぞれ他方の国、その団体及び国民に対する全ての請求権を、相互に放棄する。」と規定している。《日ソ共同宣言》の、この二つの重要な条項は、それぞれ日ソ両国の国家最高権力機構の批准をそれぞれ獲得している。よって、法律の効力があることは疑いようが無い。
政府間の外交文書の及ぶ権限
戦争がもたらした損害は主に二つの部分で構成される。一つは政府の損害であり、軍隊と国家の公用財産・戦争にかかった費用などが含まれる。もう一つは民間の一般人の損害であり、民間の一般人は非戦闘員であり、戦争中の非戦闘員に対する殺戮と傷害行為は戦争法規に違反し、その戦争犯罪責任を追及すべきであり、同時に、被害者も損害賠償責任を追及する権利を有する。要するに、国家間の戦争損害範囲は、主に政府と民間の戦争損害の二つの部分から構成されるのである。政府が戦争加害国に対する戦争賠償の請求を放棄したとしても、民間の戦争賠償請求権も放棄されるわけではない。
1972年の時点で考えると、《日中共同声明》の中で中国政府が行った放棄に民間の損害賠償請求の権利が含まれるわけは無く、当時効力があり実施されていた中国憲法(1954年憲法)に照らし合わせても、中国政府がその職権を超えて、全国人民代表大会もしくは常務委員会の批准を得ていない状況下で、無断で人民に替わり賠償請求権を放棄することは不可能である。更に、《日中共同声明》の署名者は、中国側代表は、国務院総理周恩来、外交部長姫鵬飛、日本側代表は内閣総理大臣田中角栄、外務大臣大平正芳である。1954年の中国《憲法》第二十一条に:「中華人民共和国全国人民代表大会は国家の最高権利機関である。」、第四十七条に:「中国の国務院は中国国家の最高権力機関の執行機関である。」と規定されている。第二十七条では、「戦争と和平の問題の決定」(第十三項)の職権を全国人民代表大会に授けている。この《憲法》四十一条に:「中華人民共和国主席は対外的に中華人民共和国を代表する。」と規定されている。1954年の《憲法》第四十九条は、中国政府(即ち国務院)が行使する十七項の職権の中に、全国人民代表大会あるいは常務委員会の批准を得ていない権限を授けていない。また、他国との国家間の条約締結あるいは全国人民の根本的で重大な利益に関する職権の行使と放棄に関する権限を国務院に授けていない。日中双方が《日中共同声明》を締結するに際し、日本国政府は中国国務院が有する職権の権限範囲について、認識していた。中国国務院総理の署名した《日中共同声明》が放棄した戦争賠償請求は、その政府の職権範囲内に限られており、よって、民間の対日損害賠償請求権は含まれないことも日本政府は理解できたはずである。
当時の中国政府は、《日中共同声明》が政府間の外交文書であることを考慮していた。故に、権利の処分について極めて控えめに政府の職権を超えないようにしていることは、容易に知ることができる。中国《憲法》の規定では、戦争と和平の問題は人民代表大会常務委員会の行使により決定される。よって、《日中共同声明》の中では直接戦争状態の終結を宣言せず、「日本国と中華人民共和国との間のこれまでの不正常な状態は、この共同声明が発出される日に終了する。」と宣言している。
中国側が不正常な状態の終了という表現を使用したわけは、中国政府が人民代表大会常務委員会から権限を授けられていない、または《日中共同声明》が未だ批准されていない前提の下、政府の職権を超越しないためである。この項の権利は人民代表大会常務委員会が所持し、当時の中国が依然として文革の時期であったこと、法制面の運用が未だ欠如していたであろうことを考慮し、故に両国間の戦争状態の終了という言い方を使用することを回避したのである。これも、当時の中国の指導者がこの問題の処理に対して十分に冷静かつ理知的であったことの現れであり、また、可能な限り政府の持つ職権の権限範囲内で問題処理をするよう努めた具体的表現である。しかし、両国人民の友好と国家利益のために、両国の戦争状態を出来るだけ早く終了させるべく、中国政府は声明の中で慎重に「不正常な状態の終了」という表現を使用した。
ここで言う「不正常な状態の終了を宣言する」とは、日中両国間の戦争状態の終了を意味する。1972年9月9日、日本の友人である古井喜実が、古くからの友人である大平正芳の依頼を受け、日本政府起草の共同声明案を携え北京へ赴き、中国側との最終調整を行った。戦争問題の終結に関しては、以下のような立場を表明した。「日本国と中国の戦争状態の終了は、日台条約の中で既に解決しており、ここで繰り返す必要はない。よって、中国側が再度一方的に戦争状態の終了を宣言する機会を、日本側は確実に与えることとする。」9月20日午後、周恩来は古井喜実と会見し、日本側の準備した共同声明草案に意見を述べた。周恩来は戦争状態の終結と復交三原則を共同声明に書き加えるよう、あくまで主張した。周恩来は:「我々は、中日国交正常化は戦争状態の終了により、ようやくなされ……中日両国の戦争状態は、共同声明の発出される日に終了する、と考えている。」と語った。討論を経て、最終的に、共同声明の中に前言を増やし、不正常な(戦争)状態と復交三原則などの内容を書き加えることに双方が合意した*24。当初、日中共同声明の中に「戦争状態の終了」という表現は使用されておらず、「不正常な状態の終了を宣言する」という表現が使用されていた。これに対し、いわゆる不正常な状態の終了宣言は日中間にまだ外交関係が成立していないことを指しており、戦争状態は日華平和条約が効力を発したときに既に終了している、と考える日本側の学者もいる。この種の観点は法律的依拠が欠如していると言うべきであろう。
同様の理由で、中国政府のこのような職権範囲の背景の下での「日中両国民の友好のために、日本国に対する戦争賠償の請求を放棄することを宣言する」、という宣言は、中華人民共和国政府の“宣言”にすぎず、中華人民共和国の“宣言”ではない。戦後、日本とアジアの各国家が調印した協定は、基本的には、全て国家間の名義であるが、《日中共同声明》は、まさしく政府間の名義である。中国の憲法の規定によれば、政府が国家最高権力機関から権限を授けられていない、または批准されていない状況では、政府は民間に替わって対日賠償請求の権利を放棄する権限はない。また、対日戦争賠償要求の放棄に関して、事前に当時の全中国人民の意見を求めてもいなかったため、全中国人民から特別の権限を授かってもいなかった。よって、日中共同声明の中で、中国民間の対日戦争損害賠償権が既に放棄されたとの考え方は成り立ちえないのである。日中共同声明の中の「中国政府は放棄することを宣言する」との文言からも、当時の中国の指導者が自国の憲法に照らし合わせて、十分に合理的な考慮をしていたことが証明されている。
次に、《日本国政府と中華人民共和国政府の共同声明》と《日本国と中華人民共和国との間の平和友好条約》(以下《日中平和友好条約》)の関係を研究する必要がある。1954年の中国憲法の発布以来、中国《憲法》は、1975年、1978年、1982年に重大な改正が行われた。1978年《憲法》は、この年の3月5日に中華人民共和国第5期全国人民代表大会第一回会議を通過した。1978年8月16日に中国人民代表大会常務委員会は、8月12日に署名された《日中平和友好条約》を批准した。中国の1978年《憲法》第二十五条第九項の規定によると、全国人民代表大会常務委員会は外国と締結した条約の批准と廃棄を決定する権限を有する。一般的に言えば、全国人民代表大会常務委員会は国家と人民の重大な利益問題と外国と条約を締結することができる。但し、人民代表大会を含む全国人民代表大会常務委員会が、未だ人民(戦争被害者)の権利を授かっていない時に、戦争被害者を代表し戦争の損害賠償を放棄する権利を授かっているかどうかについては、憲法上ではいかなる依拠も探すことは出来ない。仮に、人民代表大会常務委員会がこの項の権利を有していたとして、1978年8月16日に、中国人民代表大会常務委員会は《日中平和友好条約》を批准したのである。(同年10月23日、日本政府と批准書を交換した)。よって、《日中平和友好条約》の中では、直接いかなる明確な条文も中国国民の対日賠償の請求の放棄には及んでいない。
《日中平和友好条約》の前文中で、既に「前記の共同声明(1972年の《日中共同声明》)が両国間の平和友好関係の基礎となるものであること及び前記の共同声明に示された諸原則が厳格に遵守されるべきことを確認し」とある。《日中共同声明》の中で表明している原則は三方面であり、それらは“復交三原則”、“平和共存5項の原則”、“国際連合憲章の原則”である。
言い換えると、日中両国の最高権力機関が批准した《日中平和友好条約》は、《日中共同声明》が示している諸原則が厳格に遵守されることのみを要求しており、《日中共同声明》の全ての内容に焦点を合わせているわけではない。日中両国の共同声明と条約の間の相互関係から見ると、たとえ日中共同声明の中で中国政府の宣言が対日戦争賠償要求の放棄に関係したとしても、《日中平和友好条約》の中で直接の確認はされていないのである。また、1954年の中国憲法から見ると、中国政府が有している十七項の職権の中には、政府にその政府の戦争賠償要求を放棄する権利があることが明確にされてはいない。筆者は中国政府が全体の状況を考慮して対日戦争賠償の要求を放棄したことに反対はしないが、中国政府が対日戦争賠償請求を放棄したことは、少なくとも法律の手続上では明らかに不完全であり、検討する価値があると考えている。
1972年9月29日に発表された《日中共同声明》自身には中国民間の戦争被害者を代表して損害賠償を放棄する権限を備えておらず、中国最高権力機構によって批准された《日中平和友好条約》と《日中共同声明》の法律上の関連性の問題は主に、“共同声明に示された諸原則が厳格に遵守されること”にすぎないのである。よって、《日中共同声明》及び《日中平和友好条約》の内容は、いわゆる中国政府の日本国に対する戦争賠償請求の放棄の中に、民間の対日戦争賠償の要求の放棄も含まれているとはいえない、と判断することが出来る。
これらのことから分かるように、日本国東京地方裁判所が2002年8月27日に下した判決文の中で「……日本は国際法に違反した国家責任を負うが、この問題に関しては、既に全て日中共同声明及び日中平和友好条約によって解決している」とする結論には、その理由と法律的根拠がないといわざるをえない。
五、国家と民間の損害賠償請求権の違いは、早くから国際社会によって認められている
《日中共同声明》に署名した際、日中両国の指導者は、ともに民間の損害賠償請求権の問題を見落とし、声明中のいわゆる「放棄」に対する主語に至っては、表現の言葉があまりに足りなかったと考える学者もいるかもしれない。しかし、この種の解釈には根拠がない。実際に、《日中共同声明》第五項の表現は、「中華人民共和国政府は、日中両国民の友好のために、日本国に対する戦争賠償の請求を放棄することを宣言する。」である。この文の主語は「中華人民共和国政府」であり、述語は「宣言する」であり、目的語は「日本国に対する戦争賠償の請求を放棄すること」である。中国政府が《日中共同声明》の中で宣言している「放棄」の主語は中華人民共和国政府であり、その国民は含まれていないことは明らかである。
しかし、日本の裁判所は、何度も、中国民間の戦争被害者が提起した訴訟の判決の中で、以下のような似通った判決を下している。:「……日本は国際法に違反した国家責任を負うが、この問題に関しては、既に全て日中共同声明及び日中平和友好条約によって解決している。」そればかりでなく、日本政府を代表する外務省職員も、同様の態度を表明している。2002年8月28日午前10時、衆議院議員川田悦子の司会の下、衆議院第二議員会館会議室にて、日本政府の責任部門の代表者が、正に、原告側の弁護士・専門家などと質疑応答を行っていた。この間、外務省の女性職員が、筆者の質問に回答した。質問の要点は、:「1972年の《日中共同声明》中の賠償権の放棄に関する条項についてである。中国側は、中国政府の対日賠償請求のみの放棄で、中国民間の対日賠償請求は含まれていない、と認識しており、中国の国家指導者も、この件に対し幾度もそのような態度を表明している。日本政府は、この「放棄」の範囲をどのように理解しているのか?もし、日本政府が、この条項の概念についてはっきりしていないのであれば、中国政府は日本政府に対し、この条項で「放棄」している対日賠償請求に関し、民間の対日賠償請求権を含まないことを正式に通知する必要があるかどうか?」である。 これに対し、外務省の女性職員の回答は、:「私個人の理解としては、1972年当時の日中共同声明中の賠償放棄に関する条項について、中国政府は、中国政府の対日賠償請求権を放棄したと同時に、中国民間の対日賠償請求権も放棄したと考えています。中国政府がこの概念・範疇の問題について正式に日本政府に通知するか否か、それは即ち中国政府の自由であり、私個人の意見の発表は控えさせていただきます。」 ここで言う“私個人の理解”は、実際には、すでに日本の主な裁判官の“共通認識”であり、対日民間損害賠償過程での最大の障害である。
近代の国際法上では、多数の交戦国間で平和条約を締結する時、戦争賠償を国家と民間の二つの部分に細分しておらず、ただ大まかに全ての損害賠償額を提出しているだけである。しかし、理論上、ひいては論理上、戦争賠償を構成する内容は、二つの部分から成り立っており、即ち、国家の損害賠償部分と民間の損害賠償部分である。伝統的な近代国際法の中では、確かに、個人が敗戦国に対し賠償請求をした例もある。しかし多くの場合、個人の戦争損害は戦勝国国家が、併せて敗戦国に請求している。
歴史上の封建国家では、国家は皇帝のものであり、人民は臣民であり、人民の権利は皇帝君主により勝手に剥奪され覆われていた。しかし、各国の民主化の過程が進むにつれ、多数の国家では、国家の権利は既に君主ひとりに属するものではなく、立憲国家において、君主個人が所有し放棄することのできる権利は制限を受けており、更に本来君主に属さない権利の放棄に関する権限も無い。
人民主権を基礎とする立憲国家の中では、政府・国会・人民の権利と義務は、はっきりと分かれている。国際法の発展に伴い、戦争が引き起こした損害の賠償問題の処理において、国家と民間の損害賠償の権利の区別を、よりはっきりさせなければならない。実際日本が第二次世界大戦後にアジア各国と締結した各種の協定中に、国家政府の戦争損害賠償請求権と民間の損害賠償請求権の二種類の異なった権利について規定しているものが、多数ある。
1972年日中両国政府が《日中共同声明》に署名した際、両国政府の指導者の対政府賠償と対民間賠償の区別は非常にはっきりしていたはずである。戦争賠償の問題に関しては、基本的には、国家あるいは政府間の戦争賠償と各被害国民個人の損害賠償の二重構造で構成されており、この権利を区別する表現の依拠は、《サン・フランシスコ平和条約》の中にも見出すことができる。《サン・フランシスコ平和条約》中の、連合国側の戦争賠償請求権放棄の規定である第14条(b)項の内容は、:「この条約に別段の定がある場合を除き、連合国は、連合国のすべての賠償請求権、戦争の遂行中に日本国及びその国民がとった行動から生じた連合国及びその国民の他の請求権ならびに占領の直接軍事費に関する連合国の請求権を放棄する。」である。この条項は十分明確に「連合国のすべての賠償請求権」(英文「all
reparations claims of the Allied Powers」)、及び、「連合国及びその国民の他の請求権」(英文:「other
claims of the Allied Powers and their nationals」)と記している。《サン・フランシスコ平和条約》を締結した大多数の連合国は、対日本国の国家賠償請求権を放棄しただけでなく、同時にその国民の対日賠償請求権も放棄した。この種の条項の中で、はっきりと、国家の賠償請求権と連合国及びその国民の他の請求権を区別した表現は、国際社会が戦争によって引き起こされた民間の損害賠償の固有の権利というものを肯定していることを以下、《サン・フランシスコ平和条約》以後、日本が各国と個別に締結した条約、協定でも、国家の請求権と、国民の請求権が区別されていることを列挙する。反映しているだけでなく、同時に国際社会が既に十分、敗戦国の被害国家あるいは政府に対する賠償と民間被害者に対する賠償は完全に異なる、と認めていたことを説明している。
1956年10月19日にソヴィエトと日本国間で締結された《日本国とソヴィエト社会主義共和国連邦との共同宣言》の中にも、既に国家賠償と民間賠償を区別した先例がある。この宣言の第六条に:「ソヴィエト社会主義共和国連邦は、日本国に対し一切の賠償請求権を放棄する。日本国及びソヴィエト社会主義共和国連邦は、1945年8月9日以来の戦争の結果として生じたそれぞれの国、その団体及び国民のそれぞれ他方の国、その団体及び国民に対するすべての請求権を、相互に放棄する。」と規定している。この外に、日本国とアジア国家の締結した平和条約あるいは協定でも、更にこの問題を説明することができる。
ビルマはサン・フランシスコ講和会議に参加しなかったが、日本国とビルマ連邦は単独で平和条約を締結し、1954年(昭和29年)11月5日、日本・ビルマ両国は「日本国とビルマ連邦との間の平和条約」及び「日本国とビルマ連邦との間の賠償及び経済協力に関する協定」に調印した。日本国は、ビルマ連邦に対し、賠償と借款をすることとなった。日本・ビルマ平和条約第五条第二項に、:「ビルマ連邦は、この条約に別段の定がある場合を除くほか、戦争の遂行中に日本国及びその国民が執った行動から生じたビルマ連邦及びその国民のすべての請求権を放棄する。」と規定されている。
1958年1月20日、ジャカルタで平和賠償条約、即ち《日本国とインドネシア共和国との間の平和条約》が調印された。その第四条第二項に:「インドネシア共和国は、前項に別段の定がある場合を除くほか、インドネシア共和国のすべての賠償請求権並びに戦争の遂行中に日本国及びその国民が執った行動から生じたインドネシア共和国及びその国民のすべての他の請求権を放棄する。」と規定されている。
また、1965年6月22日、日韓両国政府は《日本国と大韓民国との間の基本関係に関する条約》及び4つの協定に調印した。《財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する日本国と大韓民国との間の協定》の第一条第一項に:「日本国は、大韓民国に対し、三億合衆国ドルを無償供与し、二億合衆国ドルを政府へ長期低利で借款するものとする。」第二条第一項に:「両締約国は、両締約国及びその国民の財産、権利及び利益並びに両締約国及びその国民の間の請求権に関する問題が、完全且つ最終的に解決されたこととなることを確認する。」と規定されている。
《日本とシンガポール共和国との間の1967年9月21日の協定》は、事実上、日本国のシンガポール国家及び国民に対する無償供与に関する協定であり、“「血債」協定”との名称がある。この協定の第一条第一項に、:「日本国は、二十九億四千万三千円の価値を有する日本国の生産物及び日本人の役務をシンガポール共和国に無償で供与するものとする。」第二条に、:「シンガポール共和国は、第二次世界大戦の存在から生ずる問題が完全かつ最終的に解決されたことを確認し、かつ、同国及びその国民がこの問題に関していかなる請求をも日本国に対して提起しないことを約束する。」と規定されている。
《日本とマレーシアとの間の1967年9月21日の協定》も、事実上“「血債」協定”である。この協定の第一条第一項に、:「日本国は、二十九億四千万三千円の価値を有する日本国の生産物及び日本人の役務をマレーシアに無償で供与するものとする。」第二条に、:「マレーシア政府は、両国間に存在する良好な関係に影響を及ぼす第二次世界大戦の間の不幸な事件から生ずるすべての問題がここに完全かつ最終的に解決されたことに同意する。」と規定されている。
1951年のサン・フランシスコ講和条約会議以後、日本とタイとの国交が回復し、1955年7月9日、バンコクで、《特別円問題の解決に関する日本国とタイとの間の協定》が調印された。この協定の第一条第一項に、:「日本国は、五十四億円に相当するスターリング・ポンドを、五年に分割してタイに支払うものとする。」第二条に、:「日本国は、九十六億円を限度額とする投資及びクレジットの形式で、日本国の資本財及び日本人の役務をタイに供給することに同意する。」第三条に、「タイ政府は、次の請求権を含む「特別円問題」に関する日本国の政府及び国民に対するすべての請求権を、タイ政府及び国民に代って、放棄する。」と規定されている。
ミクロネシアのパラオ共和国は、第二次世界大戦後、国際連合憲章および信託統治協定により米国の施政下に置かれていた。1969年4月18日、《サン・フランシスコ平和条約》第十四条(a)を基礎とし、日米間で《太平洋諸島信託統治地域に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定》(アメリカとミクロネシア協定)が締結された。この協定の前文に述べられているように、太平洋地域の住人が第二次世界大戦中、日米間の敵対行為によってこうむった苦痛に対し同情の念を表明しつつ、日本国及びその国民に関する請求権、施政当局及び住民の財産・請求権の処理の問題についての両国間の特別取り決めの最終的解決を確認することにつき合意に達した。日本国は施政者であるアメリカ合衆国に対し、三年間、五百万米ドル(日本円十八億円)相当額の生産物及び日本人の役務を無償で供与し、アメリカ政府もこの地域の住民のために、五百万米ドルを拠出する。第三条に、請求権問題に関しては、既に完全にかつ最終的に解決されたことに双方同意することを調印する、と規定されている。
第二次世界大戦で中立国であったスイス、デンマーク、スウェーデン、スペインなどの国は、大戦中、日本軍が南方地域及び中国で、上記の国民の人的・物質的損害に対して、国際法の原則に基づき賠償請求する権利を有する。日本とスイスの間では、1955年1月に協定が調印され、日本はスイスに対し、1350万スイスフラン(約11億日本円)を支払った。;スペインとの間では、1957年1月、公文書が交換され、日本はスペインに対し、550万米ドル(約20億日本円)を支払った。;スウェーデンとの間では、1958年5月に協定が調印され、725万クローネ(約5億日本円)を支払った。;デンマークとの間では、1955年9月及び1959年5月に協定が調印され、日本は30万英ポンド(約三億日本円)と117万5千米ドル(約4億2300万日本円)を支払った。
日本とスイスの協定の第三条第二項に、:「スイス連邦政府は、第一条に掲げる金額が日本側から支払われた際、即、この条及び第二条に掲げる政府の一切の要求を放棄し、スイス国民は、この問題に関して、いかなる請求をも日本政府に対して提起しないことを約束する。」と規定されている。
日本とスペインの協定の第三項に、:「第一項に規定する金額の支払い後、日本国政府は、この条項に述べる損害及び苦痛に関する一切の賠償請求の責任を、完全かつ最終的に免除される。」と規定されている。
日本とスウェーデン政府間の協定の第四条に、「スウェーデン政府は、第一条に掲げる金額をひとたび日本政府が支払った場合、この条項に述べる一切の請求権は、完全かつ最終的な解決を得たと見なすことを承諾する。スウェーデン政府は、日本政府がこの条項に掲げる金額の支払い後、前述の請求以外のいかなる賠償・支払いも請求しないことを保証することを併せて約束する。」と規定している。
日本とデンマークの協定の第三条に、:「第一条に掲げる金額をひとたび支払った場合、第二次世界大戦(1937年7月7日のシナ事変の発端を含む)期間、日本国の政府機関がデンマークの政府機関及び国民と法人に与えた損害及び苦痛に対する、一切の相関する損害賠償請求の責任に関して、完全かつ最終的な免除を得る。」と規定している。
以上述べたことをまとめると、1972年に日中間で《日中共同声明》が締結される以前に、多くの国際外交法の実践により、既に十分、国際習慣法上での国家と国民の戦争賠償請求権に関する明確な区別が存在していたことが説明できる。日中両国の指導者が《日中共同声明》に署名した際、中国の国家指導者が、日本とアジアの被害国が結んだ協定について、収集し研究し対比しなかったと考えることは不可能である。日本とアジア被害国国家が調印した協定の中に、国家と国民二種類の損害賠償の権利がある、との明らかな前提の下で、《日中共同声明》の中では、中国政府は日本国に対する戦争賠償の請求を放棄するとの条文を使用したのであり、その意図は明らかである。よって、共同声明の中で放棄したのは、中国政府の要求のみである。日本国政府の代表である田中角栄首相は、日本の総理大臣として、共同声明中に「中華人民共和国政府は……放棄することを宣言する」という条項を使用することを受け入れたのであり、田中首相にこのような基本的な法律常識が欠如しており、政府の放棄に国民の放棄をも等しく含めてしまったと信じるいかなる理由も存在しない。これ以前に日本政府は、既に《サン・フランシスコ平和条約》、《日ソ共同宣言》及び東南アジア諸国と協定や平和条約を締結しており、その中で国家と国民の権利を区別する外交法を多く実践しているのである。よって、どんなことがあろうと、日本国政府は政府の放棄と民間の放棄が等しくないことを認識しているのである。
このほか、戦後ドイツは、強制労働及びユダヤ人の受けた侵害に対する賠償を行い、カナダとアメリカは、ともに、戦争期間中に抑留された日系カナダ人あるいは日系アメリカ人に対する賠償を行った。
敗戦国の、被害国家あるいは政府に対する賠償と、被害を受けた民間に対する賠償を明確に区別している更に多くの実践例がある。例えば、1991年、国際連合安全保障理事会の下にイラク賠償委員会の管理理事会が設立され、イラク軍の対クウェート侵略により損害を受けた被害者個人(例えば石油会社など)の提起した賠償請求を受理した。この例によると、連合国の実際の行動は、侵略国に対する損害賠償請求権中の個人の請求権が独立部分であることを表明している。連合国のこのようなやり方は、実際上、長きに及ぶ国際法の発展において肯定されているやり方である。
上述した多くの国際法の実践により、以下のように問題をまとめることができる。
第一に、1972年、日中共同声明が発表される以前に、国際社会が、既に、敗戦国に対する戦争賠償を請求する権利の主体を国家と国民に分けていたことは明らかであり、また、既に国際慣例として成立していた。
第二に、日本が戦後に、戦時の交戦国との間で署名した文書は、平和友好条約もしくは賠償協定など、いかなる名称であろうと、均しく国家間の名義で実施されたものである、中日のケースは、政府間の名義で実施されたのに対し、例外である。
第三に、国家が条約あるいは協定の中で放棄する賠償請求権に国民の戦争損害賠償請求権も含まれると明確にしない限り、被害国国民は依然として固有の戦争損害賠償請求権を有している。
1972年に日中共同声明が公布される以前に、国際社会、特に日本と被害国間で締結された平和友好条約あるいは協定は、既に十分明確に国家と民間の二つの異なる損害賠償の権利を区別しており、更に、《日中共同声明》の主体は両国政府間であったにすぎず、両国国家間の協定ではなかった。中国政府が放棄したのは政府の対日戦争賠償要求のみであり、中国憲法の政府に授けられている職権に照らし合わせると、政府は中国民間の対日戦争賠償請求の権利を放棄していないのである。よって、いわゆる政府の放棄した対日戦争賠償要求には民間の対日損害賠償請求の権利も含まれているという説明は、まったくのでたらめな話である。以上のように、中国民間の戦争被害者の損害賠償請求権が中国政府によって放棄されたという説明の根拠が存在しないことは、十分に明らかである。
六、日本政府が中国政府の見解に対し偏った理解をしていることに関する問題
1. 日本政府の中国政府に対する偏った理解に対する解釈
日本政府は、反論の中で、次のように主張している。「その他、以下に述べる各事項が指し示すように、中国国民及び財産に相関する事項を含め、これ以前の戦争に関連する日中両国間の請求権問題に関しては、日中共同声明発表後は、存在しないのである。中国政府も、同様の認識を持っていることを、表明している。」
日本政府の主張の根拠となっている中国政府の認識は、以下のとおりである。
①1995年(平成7年)5月3日、新聞記者の「国交が正常化して以来、中国政府は日本に対しての戦争賠償請求権をすでに正式に放棄しているが、最近は民間の組織が戦争賠償を請求している。これに対し、中国政府の見解はどのようなものか?」という質問に対して、中国外交部プレス部司長・陳健が「戦争賠償の問題は、解決済みである。この問題に関する我々中国政府の立場には、変化がない」と回答している。(反論の乙・証拠第51号より)
②その他、銭其?外交部長が、1992年(平成4年)3月に行われた記者会見の席上で、記者から民間で戦争賠償を請求する動きを見せていることに対する意見を求められた時、「戦争が原因となって引き起こされた数々の複雑な問題に対して、日本政府は適切な処置を採らなくてはならない」と述べている。また、戦争賠償の請求問題に関しては、「中国政府は1972年の日中共同声明で立場を明確に表明しており、その立場に変化はない」と述べている。(反論の乙・証拠第52号より)
③1998年(平成10年)12月、香港のマスコミの報道で、唐家?外交部長が、民間人が日本国に対して賠償請求をする問題に関する中国政府の見解が如何なるものであるか、記者から質問を受けた際、「中国の日本に対する戦争賠償請求権の問題は、完全に解決済みであり、国家と国民とは同じ概念であるのだから、国民の立場は国家の立場と同じであるはずである」と述べている。(反論の乙・証拠第53号より)
日本政府は、上述した内容を根拠に、戦争が原因で発生した日中両国間の賠償請求権の問題に対する日中両国の認識は同じであると、強調している。
2. 1972年『日中共同声明』第五項に対する中国政府高官の解釈の問題
1970年代初頭、日本の周辺国家の戦争被害者たちが、日本に対して民間レベルでの賠償請求運動を開始した。中国の改革開放と民主化の過程の発展に従って、中国人民の人権保護意識は高まり、80年代末には、一般の戦争被害者が日本国に対して民間レベルで賠償請求を行うことを考え、その方法を模索しはじめていた。90年代初め、中国の全国人民代表大会の代表も、国家と国民にとって重大な利益をもたらす対日民間訴訟問題に注目しはじめた。『日中共同声明』で中国政府が戦争賠償を放棄する声明を出したことに対し、中国の国家指導幹部は、次のように釈明してきた。
(1)1992年3月11日、中国外交部のスポークスマンがコメントを発表する際、
「日中戦争において被害を受けた民間人は直接、日本に損害賠償を要求することができる」と述べた。
(2)1992年3月23日、国務委員兼外交部長・銭其?が第七回人民代表大会第
五回会議で行われた記者会見の席で、記者からの中国の一般被害者の損害賠償要求に関する質問に対し、次のように述べた。
「甲午農民戦争で朝鮮の要請を受けて清が出兵してから抗日戦争に勝利するまで、中国は約半世紀もの間、日本の軍国主義によって被害を受けてきた。日本軍の対中侵略戦争が生み出した複雑な諸問題に対し、日本側は善処しなくてはならない。戦後の賠償問題に関しては、中国政府は1972年に調印された『日中共同声明』において立場を明確に表明しており、この立場に変化はない。“人民代表”には議案を提出する権利があり、人民代表大会議長は、規定にのっとってこれらの議案と意見を処理する責任を負っている。」
(3)1992年4月、中国共産党総書記・江澤民が訪日する前、記者からの質問
に、「中国は、国家の日本に対する戦争賠償請求は放棄した。だが、民間の賠償請求に関しては、この限りではない」と回答した。
(4)1992年4月16日、中国外交部のスポークスマン・呉健民が、記者からの
質問に対し、「日本軍が中国侵略戦争を展開していた際に遺棄した大量の生物化学兵器が、中国に存在している。中国は完全なる戦争被害国である。日本側は、生物化学兵器遺棄の責任を負うべきであり、我々は一日でも早
く、この問題に対して満足できる解決を得られることを望んでいる」と回答した。
(5)1992年9月21日の『朝日新聞』(東京ロイター通信社)の報道によると、
中国国務院副首相・呉学謙が訪日以前、北京飛行場で記者に向かって、「国民が正式な手段でもって賠償を要求するのは、正常なことである。我々は、日本政府がこの問題を適切に解決すると信じている」と告げた。
(6)1992年9月、元国務院副首相・呉学謙が、「国民の賠償要求と、政府の
賠償請求は同じではない。戦争で傷つけられた中国人民が、正規の手段で彼らに対する賠償を要求することは、完全に正当である」と公に発表した。
(7)1995年3月、国務院副首相・銭其?が全国人民代表大会会議において、
再び中国政府の立場を表明した。その立場とは、「『日中共同声明』は、中国人民が個人の名義でもって日本政府に対して賠償を請求する権利を放棄したものではない」というものである。
実際のところ、日本政府がその反論において引用した上記の中国政府高官の日中共同声明に対する解釈の中では、唐家?外交部長の発言にのみ、「中国の日本に対する戦争賠償請求権の問題は、完全に解決済みであり、国家と国民とは同じ概念であるのだから、国民の立場は国家の立場と同じであるはずである」ことが明確に述べられているのみである。日本政府側が証拠として提出した陳健プレス部司長の発言は、「戦争賠償の問題は、解決済みである。この問題に関する我々中国政府の立場には、変化がない」と述べているに過ぎない。陳健の「戦争賠償の問題は、解決済みである」という発言の主語が何を指しているのかは明確でなく、「この問題に関する我々中国政府の立場には、変化がない」と言う回答に至っては、中国政府のもとの見解が、中国国民の日本国に対する戦争賠償請求権の放棄を当然含んでいることを証明することはできないのである。
ところで、上記の銭其?外交部長の「中国政府は1972年に調印された『日中共同声明』において立場を明確に表明しており、この立場に変化はない。」と言う発言に対して、考察を行う。結論から言うと、これは、日本政府が自分に都合の良い部分を引用しているに過ぎないのである。仮に日本政府の引用どおりだとしても、やはり、もとの見解が中国国民の日本国に対する戦争賠償請求権の放棄を当然含んでいることを、直接的に証明することはできない。
多くの中国政府の高官が『日中共同声明』において、日本国に対する賠償請求の放棄の主体には一般の戦争被害者は含まないと認識していると言っても、唐家?外交部長のように、少数ながらも国民は国と同じく賠償請求を放棄したのだという見解も確かに存在する。このように、中国政府高官の中でも戦争賠償の問題に関して公に示す立場が一致しない状況においては、どの官僚の解釈を基準にするのかに関して問題が生じる。法治国家が実施している慣例では、同一の問題に対して複数の法律の解釈が衝突し合う時、後に発効した法律の解釈を優先する。同様に、法律の中において下位の法規が上位の法規と同一問題に対して解釈が衝突し合う時は、上位の法規の解釈は下位の法規の解釈に勝るのである。中国の首脳・幹部が『日中共同声明』に対して互いに異なる釈明を行っているこの場合にも、完全に法律の解釈に関する慣例に倣って、誰の解釈が権威性を持ち得るのか識別しなくてはならない。戦争賠償の問題に関しては、上位の官僚から下位の官僚の釈明まで様々であり、よって、最も権威のある釈明には、中国政府高官の中でも最高級の地位にある官僚の立場を選ぶべきである。
1998年(平成10年)12月、唐家?が上記のとおり中国国民における戦争被害者の日本に対する賠償請求権を否定する発言を公の場で述べた時、唐家?は外交部長の職についていた。一方、1992年3月23日、第七回人民代表大会第五回会議において行われた記者会見の席上で、中国国民の賠償請求問題に関する記者の質問に対し、国務委員兼外交部長として、銭其?は次のように回答している。
「…(前略)…日本軍の対中侵略戦争が生み出した複雑な諸問題に対して、日本側は善処しなくてはならないのだ。戦後の賠償問題に関しては、中国政府は1972年に調印された『日中共同声明』において立場を明確に表明しており、この立場に変化はない。“人民代表”には議案を提出する権利があり、人民代表大会議長は、規定にのっとってこれらの議案と意見を処理する責任を負っている。」
1992年9月、中国国務院副首相・呉学謙は次のように述べている。
「国民が正式な手段でもって賠償を要求するのは、正常なことである。我々は、日本政府がこの問題を適切に解決すると信じている。」
「国民の賠償要求と、政府の賠償請求は同じではない。戦争で傷つけられた中国人民が、正規の手段で彼らに対する賠償を要求することは、完全に正当である。」
1995年3月、国務院副総理兼外交部長であった銭其?が、全国人民代表会議の席上で、再び中国政府の立場を、「『日中共同声明』は、中国人民が個人の名義でもって日本政府に対して賠償を請求する権利を放棄したものではない」と、表明している。
中国政府の官僚のうち、2名の国務院副首相が別個に「国民の賠償要求と、政府の賠償請求は同じではない。」(呉学謙の発言より)、「『日中共同声明』は、中国人民が個人の名義でもって日本政府に対して賠償を請求する権利を放棄したものではない」(銭其?の発言より)と、中国国民の日本に対する賠償請求を肯定している状況において、国務院副首相より地位の低い外交部長の発言が副首相の発言と一致しない時、外交部長の発言は無効とみなされるべきであり、法廷における証言としての効力は充分ではないのである。
2002年4月26日、福岡地方裁判所第3民事部の判決では、次のことが認定された。
「当時の銭其?副首相兼外相は、平成7年3月9日、日中共同声明で放棄したのは国家間の賠償であって、個人の賠償請求は含まれず、補償請求は国民の権利であり、政府は干渉すべきではない旨の見解を示したことなどの事情を考慮すると、…(中略)…したがって、原告らの損害賠償請求権が、日中共同声明及び日中平和友好条約により、直ちに放棄されたものと認めることはできない。」(『H14.
4.26 福岡地方裁判所 平成12年(ワ)第1550号、平成13年(ワ)第1690号、同第3862号 損害賠償等請求判決書』より引用)
この法廷において、賠償問題に関する中国政府高官の数ある釈明のうち、最高の地位にある副首相の立場を判決の根拠としたことは、正確な判断であると言える。
客観的な立場に立って見ると、この問題に対する認識と立場は中国政府高官の公の場における発言内容を基準にすべきであるが、中国の官僚の中でも認識と立場が異なっている。これに対し、日本政府は完全に、日中共同声明で問題になっている条文における中国政府の解釈に関し、外交手段を通じて、中国政府が正式な回答を出すように追及することができるのである。日中共同声明は条約の一形式であり、条約とは締結当事国が合意した正式な国際協議であり、原則上は、締結当事国自身によって解釈されるべきものである。条約文に対して異議が存在する時、締結当事国はさらに協議を重ねて、条文の本当の意味を新しく確認することができる。しかしながら、締結国の間で、本国の根本的な利益に大きな係わりを持つ条文の解釈において、重大な意見の不一致が現れた結果、各自が自分の意見を主張するばかりで譲歩せず、条約締結国の間で見解が一致しないことがある。そのような時には、必ず他の機関の解釈を以って当事国の見解の不一致を補わなくてはならない。例えば、国際仲裁機関、或いは国際司法機関の解釈は、当然のことながら、当事国の意思に基づいてなされる解釈である。
日本政府が外交手段を用いる必要があると思うならば、中国政府に対し外交手段によって、中国政府官僚の見解の不一致に関して諮問し回答を得ればよい。だが、日本政府は外交手段を避け、日本政府に有益となる相対的に地位の低い中国官僚の見解を用いることを選択している。よって、このことから、日中間で締結された条約、条文の解釈における問題において、日本政府のとっている態度は明らかに無責任であると言うことができる。
結び
日本政府の反論の対していくつかの異なる角度から検証してきたが、1972年に締結された『日中共同声明』第五項における戦争賠償要求を放棄した中国側の主体の範囲と、同声明の法律的地位の効力問題をめぐって守りの理論を構築しているのが、所謂日本政府の反論である。
日本政府の反論は、中国の一般戦争被害者の合法的な訴訟請求を否定するために、歴史と法律を歪曲的に解釈したものに他ならない。この解釈に基づいて、東京地方裁判所は、原告たる731部隊細菌戦の中国人被害者の訴えを斥けたのであるが、その判決理由で「『日中共同声明』及び『日中平和友好条約』の締結によって、国際法上は日本の国家責任については決着をしたと言わざるをえない」と述べているのは、全くのでたらめである。
『日中共同声明』において放棄した対日戦争賠償請求の中には、中国国民の対日賠償請求は含まれていないのだから、中国の一般戦争被害者には賠償請求権があり、日本政府は権利の違法な侵害に対して責任を負わなくてはならないのである。まして、中国の一般戦争被害者は日本の司法体制の中で法的救済を求めているのだから、日本の裁判所は、法に基づいて審議し、法に基づいて公正な判決を出さなくてはならない。
戦時中の一般被害者の問題をどのように解決するか、その解決策について、日本政府は次のように認識している。
「戦争行為によって生み出された被害者の賠償問題に関する主体、即ち、その戦争関係によって生み出された賠償請求権を行使できる主体と、国際法における戦争以外の行為によって生み出された請求権を行使できる主体は一般的には同一であり、通常は国家である。……戦争が終了した状態において、戦争の被害問題を解決する場合には、被害国が主体となって被害者の問題を提起し、加害国に対し統一して賠償請求を提出し、外交的手段を通じて合意に達する方式でなければならない。仮に被害国の国民が個別に様々な請求を提出できるとしたら、その相手は被害国に限られ、国家が各被害者に委託され、被害者の代理として相手国と交渉を進めるのである。だが、今のところ、このような訴訟事件の方式では戦争被害者に関する問題を一挙に解決することはできない。」
上記の日本政府の言葉は戦争被害者個人の訴訟の権利を理不尽にも燦然と否定するばかりか、同時に、戦争被害者に関する問題は国家によって一挙に解決されるべきである、という立場を表しているのである。
日中両国の間では、中国の一般戦争被害者の損害賠償問題は如何なる協定によっても解決に達しておらず、よって、中国の一般戦争被害者は当然のこととして、個人の名義で以って直接日本国内の司法機関に法的救済を求める権利を享受できるのである。このことは、中国の一般戦争被害者個人が司法機関に救済を求めることを肯定すると同時に、日中両国政府が、戦争が遺留した一般被害者の損害賠償に関する全ての問題を、外交手段を通じて解決することを排斥しない。何故なら、中国の一般戦争被害者の中には、一旦日本において法的救済を得ることができれば、必然的により多くの中国人被害者が日本に赴いて法的救済を求めることになるだろうという考えがあり、同時に、日本には如何に巨大な範囲にわたって将来救済手段を講じなければならないか見積もる方法がないからである。仮に日中両国の間で戦争が遺留した一般被害者の賠償問題を、総括的に解決しようとするならば、それもまた、全被害者に言わせれば、公平な手段による救済の実現がいっそう近づいたことを意味するのである。外交手段を通じて被害者に関する問題を解決するという方法も、考慮する価値のある方法である。
日本は、中国に対する侵略戦争における犯罪行為を徹底的に反省し、また賠償責任をとらなくてはならない。そうでなければ、日本は永遠に各被害国民の恨みを買い続けることになるだろう。しかしながら、戦争が遺留した中国国民の対日賠償請求問題の解決は、法に基づいてなされなければならない。被害者の合法的権利及び利益を擁護することは、人権の尊重に基づく行為である。侵略戦争を発動させた国家や、戦争法規に甚だしく違反した国家はその法的責任を負い、その侵略戦争の“コスト”を支払うことによって、日本を含めた多くの国家に世界の平和を自発的に擁護せしめ、また自発的に基本的人権を尊重せしめるのである。中国国民の日本に対する賠償請求の問題を公平且つ公正に解決できれば、日中両国の友好関係は永遠に維持され、日中両国民の永遠の友好関係が、アジアの平和とアジア経済の繁栄を築き上げることができるのである。
以上
|