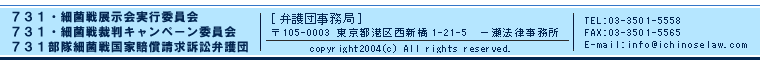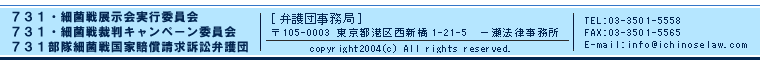|
鑑定意見書
>鑑定意見書のメニューに戻る
細菌戦と国の賠償責任
「国家無答責の法理」による国の免責可能性の検討
南山大学大学院法務研究科教授 岡 田 正 則
目 次
1.はじめに
(1)近年の裁判例における国家無答責の法理の適用
(2)学説の状況(国家賠償法附則6項「従前の例」の解釈)
(3)本稿の課題
2.国家無答責の法理は実定法の根拠を有するか
(1)実定法説の根拠
(2)大日本帝国憲法(1889年)と行政裁判法(1890年)の制定
(3)裁判所構成法の制定過程における国に対する民事裁判の管轄規定の削除
(4)旧民法373条における「公ノ事務所」規定削除
(5)旧民法373条の立案過程における井上毅の役割
(6)民法715条の制定と国の不法行為責任
(7)この時期の裁判所と学説の態度
(8)まとめ
3.大審院判決の推移と判例の形成
(1)はじめに
(2)主要判決の推移
(3)「判例」の内容
(4)最三小判1950・4・11は判例といえるか
(5)学説の状況
(6)まとめ
4.細菌戦と国の賠償責任
(1)細菌戦における国の行為
(2)細菌の散布行為は「統治権ニ基ク権力行動」に該当するか
(3)統治権の及ばない地域での外国人に対する行為は国家無答責の法理の適用対象となるか
1.はじめに
(1)近年の裁判例における国家無答責の法理の適用
国家無答責の法理とは、国家賠償法施行(1947年10月27日)以前の国の権力的行為に係る損害ついて国は賠償責任を負わないとする法理をいう
。1990年代以降に提起された戦後補償請求訴訟において、多くの判決でこの法理が適用され、賠償請求が棄却された。
適用を認めた判決には、実定法説に立つものと、判例法説に立つものとがある。
前者の最近の例として、東京地判2002・8・27(731細菌戦訴訟)、大阪高判2003・5・30(浮島丸訴訟)がある。これらは実定法上の根拠として、?帝国憲法61条と行政裁判法16条の文言からこの法理の存在が推論できること、?旧民法373条制定過程で「公ノ事務所」という文言が削除されたこと(そして、其の立案にかかわったとされる井上毅がこの法理を根拠として削除した旨を論文で解説していること)、および現行民法(715条)にも国家責任規定が設けられなかったこと、を挙げている。また、訴訟での国側の主張では、?国に対する裁判の管轄規定が裁判所構成法案から削除されたこと、も根拠としてつけ加えられている。しかし、これらの判決や主張が信頼にたるだけの立法史の検討を行っているわけではなく、むしろ、史料に基づかない推測によって結論を導いているのが実情である。
一方、判例法説に立つ判決は、たとえば次のような大審院判決を根拠として挙げている。「明治憲法下では、大審院の判例上、国の権力的作用については、公務員の違法行為によって個人に損害が生じたとしても、私法である民法の不法行為に関する規定の適用はなく、一般的に国の賠償責任を認める法律の規定もない以上、国は賠償責任を負わない(国家無答責の原則)とされていたものであり(大審院明治43年3月2日判決・民録16輯169頁、大審院昭和4年10月24日判決・新聞3073号9頁、大審院昭和8年4月28日判決・民集12巻11号1025頁、大審院昭和16年2月27日判決・民集20巻2号118頁、大審院同年11月26日判決・大判全集9輯11号6頁等参照)、最高裁判例も、「国家賠償法施行以前においては、一般的に国に賠償責任を認める法令上の根拠のなかつたことは前述のとおりであつて、大審院も公務員の違法な公権力の行使に関して、常に国に賠償責任のないことを判示して来たのである。」と判示して、明治憲法下の公務員の違法な公権力の行使につき、国の賠償責任を否定する大審院の右判例法理を援用している(最高裁昭和25年4月11日第三小法廷判決・裁判集民事3号225頁)」
。しかし、これらが戦前において本当に判例として扱われていたのかどうかは、不明なままであるし、いかなる意味で判例となるのかも示されていない。むしろ、大審院自身が判例であることを否定した判決(大判1910(明治43)・3・2)や国家無答責の法理とは無関係の判決(大判1933(昭和8)・4・28)が無造作に掲げられているのが実情なのである。また、後に述べるように、最判1950(昭和25)4・11も、大審院判例をまったくふまえていないだけでなく、判例として何らかの指針を提供するものでもないのである。
上記のような裁判例に対して、最近、国家無答責の法理の適用を否定する例が目立つようになっている。たとえば、東京高判2000・11・30(在日「慰安婦」国家補償請求訴訟)は、国家無答責の法理は実定法上の根拠をもっておらず、今日適用できる法理ではないとし、京都地判2003・1・15(中国人強制連行京都訴訟)は、強制連行は国の権力作用として行われたものではないことを理由としてこの法理の適用を否定し、東京地判2003・3・11(中国人強制労働東京第2次訴訟)と東京高判2003・7・22判決(アジア太平洋戦争韓国人犠牲者補償請求訴訟)は、現行憲法・裁判所法の下ではこの法理には正当性・合理性を見出し難いとし、新潟地判2004・3・26(中国人強制労働新潟訴訟)や福岡高判2004・5・24(中国人強制労働福岡訴訟)は、この法理は正義・公平の理念に反するので適用できないとしている。
(2)学説の状況(国家賠償法附則6項「従前の例」の解釈)
国家無答責の法理を適用することについて、学説のほとんどはこれを強く批判している。すなわち、第一に、この法理は実定法上の根拠をもつものではなく、判例法理にすぎないのであるから、今日の時点での制度と理論をふまえて変更されるべきであるという批判
、第二に、国賠法附則6項にいう「従前の例」には法令は含まれるが判例は含まれないので、同条項を媒介として現代の裁判においてこの法理を適用することはできないという批判
、第三に、「生命・身体・自由」といった基本的価値に関する事件であり、精神的損害が継続中の事件において、同項の存在を理由としてあまりにも時代遅れの法理を援用することは、「時際上の公序」に反して許されない
、あるいは「正義公平の原則」に反して許されないという批判 、第四に、「国家無答責」という用語は国・公共団体の活動一般について損害賠償責任を否定する趣旨と誤解されかねないので「公権力無責任の原則」という語を用いるべきであるという批判
などである。また、天皇主権を前提として国の賠償責任を免除する戦前の判例は日本国憲法に反するものであるから、同法98条1項によって無効となるのであって、国賠法附則6項を理由として"下克上"的に違憲の判例を日本国憲法下で適用することは許されない、という批判も可能であろう。
(3)本稿の課題
上記の批判にはそれなりの根拠があるが、本稿では、歴史的な事実を確認することによって、国家無答責の法理が細菌戦のような戦後補償請求訴訟の事案に適用できるのか否かを考察することにしたい。
そこで、本稿は、第一の課題として、国家無答責の法理が実定法上の根拠をもつ法理なのか、それとも判例法理なのかを判定する。そのために、立法史と学説史を確かめることにする。結論として、この法理が、立法者意思、損害賠償制度上の位置、裁判所による運用のいずれの点からみても判例法理であることを明らかにする。
第二の課題は、判例法理として示された国家無答責の法理の内容とその適用範囲を明確にすることである。そのために、大審院判例の検討を行う。結論として、大審院判例は同法理の適用を実定法上の行政処分に瑕疵があった場合および「統治権ニ基ク権力行動」の場合に限定したこと、上記最判1950(昭和25)4・11はとうてい判例とはいえないこと明らかにする。
第三の課題は、大審院判例を基準として「細菌戦」が国家無答責の法理の適用対象とみなせるか否かを判定することである。そのために、細菌戦における「権力的行為」の要素を摘出し、加害者たる軍と被害者との法的関係を検討する。結論として、細菌戦が同法理の適用対象外であり、細菌戦による被害が民法の賠償請求の対象になりうることを示す。
2.国家無答責の法理は実定法の根拠を有するか
(1)実定法説の根拠
実定法説の例として、ここで東京地判2002(平成14)・8・27(731細菌戦国賠訴訟)の該当部分を引用してみよう(下線は引用者)。
「4 日本民法に基づく損害賠償請求について(争点4)
(1) 原告らは,本件細菌戦が,中国現地における細菌戦の研究・開発・実行と日本における細菌戦の研究・開発・作戦指導とが一体となった行為であるから,不法行為が日本でされたものとして日本民法の不法行為法の適用があるとして,日本民法(第1次的に同法709条,710条,711条,第2次的に同法717条又は715条。謝罪請求について同法723条)に基づく損害賠償請求をしている。
しかして,前記3の(2)の説示に照らすと,違法な公権力の行使を原因とする国の損害賠償責任の問題には,それが渉外的要素を有するものであっても,法例の規定を介さずに直接我が国の法律(現在においては国家賠償法)が適用されると解するのが相当である。我が国の国家賠償法(昭和22年〔1947年〕10月22日施行)は,附則6項で「この法律施行前の行為に基づく損害については,なお従前の例による。」としているから,同法施行前の行為に基づく損害に関する法律関係は同法施行前の法令によって判断すべきことになる。原告らの主張によれば,本件細菌戦は1940年(昭和15年)から1942年(昭和17年)までに実行されたものであるから,本件についても国家賠償法施行前の法令によって判断すべきことになる。
そこで,以下において,国家賠償法施行前の関係法令について検討する。
(2) 大日本帝国憲法61条は「行政官庁ノ違法処分ニ由リ権利ヲ傷害セラレタリトスルノ訴訟ニシテ別ニ法律ヲ以テ定メタル行政裁判所ノ裁判ニ属スヘキモノハ司法裁判所ニ於テ受理スルノ限ニ在ラス」と規定し,行政裁判法(明治23年6月30日公布)16条は「行政裁判所ハ損害要償ノ訴訟ヲ受理セス」と規定していた。行政裁判法のこの規定によって,行政裁判所に国家責任訴訟を提起することはできなくなったが,同条は司法裁判所の管轄までを明文で否定したわけではないから,その限りでは,国の賠償責任は司法裁判所により民法その他の法律が認める範囲内で認められる可能性があることになる。
そこで,司法裁判所における裁判規範となる民法についてみると,明治21年に起草されたボアソナードの民法草案393条は,「主人及ヒ棟梁,工業及ヒ運送ノ起作人又ハ其他ノ者,公ケ及ヒ私ノ管理所ハ彼レ等ノ僕婢,職工,傭員又ハ使用人ニ因リ引起サレタル損害ノ責ニ任スヘクアル,彼レ等ニ委託セラレテアル所ノ職務ノ執行ニ於テ又ハ其効果ニ於テ」と定めていた。ボアソナードによれば,同条は公権力の行使による損害についても国に責任を認める趣旨のものであった。ところが,このボアソナード民法草案393条の国家責任規定は,明治23年4月21日に公布された旧民法財産編(明治23年法律28号。ただし,周知のとおり,この旧民法は施行されないまま廃止された。)373条においては削除され,同条は「主人,親方又ハ工事,運送等ノ営業人若クハ総テノ委託者ハ其雇人,使用人,職工又ハ受任者カ受任ノ職務ヲ行フ為メ又ハ之ヲ行フニ際シテ加ヘタル損害ニ付キ其責ニ任ス」と規定するに至った。この間の経緯について,旧民法の立案過程に参加した井上毅は,旧民法公布の翌年に発表した論文「民法初稿第三七三条ニ対スル意見」で,公権力の行使による権利侵害について損害賠償を認めると行政機関の機能に支障が生じることを理由として,旧民法373条が行政権による公権力の行使に起因する損害賠償責任を否定する趣旨である旨を述べている。
前記のとおりこの旧民法は施行されず,明治29年,新たに起草された草案に基づき現行民法(第一編から第三編まで)が公布され,明治31年7月16日から施行された。現行民法にも,旧民法と同様,国の公権力の行使により他に与えた損害の賠償責任を定めた規定はなく,この点に関する特別法も制定されなかった。
この経過によると,旧民法373条から国家責任に関する字句が削除されたことは,少なくとも公権力の行使に基づく国家責任を否定する立法者意思の表れであるとみるのが相当であり,現行民法にもその立法者意思が継承されたといえるから,行政裁判法と旧民法(財産編)とが公布された明治23年の時点で公権力行使についての国家無答責の法理を採用するという基本的法政策が確立したというべきである。
そして,戦前の大審院判例は,非権力的作用については民法の適用により国の損害賠償責任を認めてきたが,公権力の行使(権力的作用)による損害については一貫して国の賠償責任を否定していた。後者の点については,国家賠償法制定後においても,最高裁判例により確認されているところである(最高裁昭和25年4月11日第三小法廷判決・集民3号225ページ)。
(3) このように,戦前においては,公権力の行使による私人の損害については,国の損害賠償責任を認める法律上の根拠がなく,そのことは公権力行使についての国家無答責の法理を採用するという基本的法政策に基づくものであったから,公権力行使が違法であっても被告はこれによる損害の賠償責任を負わないものと解するのが相当である。原告らの主張する本件細菌戦も,国家賠償法制定前の被告の権力的行為であるから,当時の法令に従って,これによる民法709条,710条,711条に基づく損害賠償責任は否定せざるを得ないものというべきである。」
この判断は次のような論理から成り立っているといえよう。(i) 国家賠償法附則6項にいう「従前の例」とは同法施行前の法令を指す、(ii)大日本帝国憲法61条と行政裁判法16条によれば国の賠償責任は司法裁判所により民法等が認める範囲内で認められる可能性がある、(iii)旧民法373条から国家責任に関する字句が削除されたことは公権力の行使に基づく国家責任を否定する立法者意思の表れであり、現行民法にもそれは継承された、(iv)他方、国の賠償責任を認める法律はせいていされなかった、(v)したがって行政裁判法と旧民法が公布された1890年(明治23年)の時点で国家無答責の法理を採用するという基本的法政策が確立した、(vi)それゆえこの法理は民法の損害賠償規定に含まれる実定法理であり、裁判規範として適用できる。
以上のような実定法説すなわち1890年確立説を採用する理由は、一つには、この法理が国賠法附則6項にいう「従前の例」に含まれることを示すためだと考えられる。判例法理だとすると「従前の例」として扱うことができない可能性が出てくるので、そうした余地を残さないための方策である。二つめの理由は、実定法に根拠があるといえれば、大審院判例の検討という面倒な作業を省略できる点にある。事実、上記の東京地判も含めて実定法説に立つ判決は、大審院判決の変遷を顧慮することも、判例とみなせる判決を摘示することも行っていない。上記最判昭和25年4月11日にあっては、実定法の根拠も大審院判決も示さずに、「大審院も公務員の違法な公権力の行使に関して、常に国に賠償責任がないことを判示して来た」としているのである。
しかし、このような実定法説には、一見しただけで、次のような疑問を持たざるをえないであろう。
第一に、立法関係者の指針に過ぎない「基本的法政策」を実定法と同視して裁判規範として適用できるのかという疑問である。現代日本の裁判所は、明瞭な実定法である憲法規範でさえも「プログラムに過ぎない」として裁判規範性を否定しているのであるから、まして不文の「基本的法政策」を裁判規範とみなすのは難しいのではないか、と考えられよう。第二に、ある特定の人物の見解を立法者意思とみなすことができるのかという疑問である。とくに、「明文の規定を設けない」という消極的態度を立法者が選択した場合、通常、対立する多様な見解がまとまらなかった結果だと推測されること、現実に旧民法の立案を担当した法律取調委員会は最終的なまとめにおいて改訂案に対して多様な解釈を示していること、および現行民法の制定過程においても国の賠償責任に関する議論が継続されていることにかんがみれば、井上毅の解説をもって「明治23年の時点で」この法理が確立したというのはきわめて危険であることが理解できよう。付言すれば、井上自身は法律取調委員会のメンバーではなかったのであるから、「旧民法の立案過程に参加した井上毅」(前掲・東京地判2002・8・27)という記述は事実誤認の可能性が高く、また彼の見解を立法者の見解と同一視することの根拠が問われざるをえないと思われる。第三に、仮に「明治23年の時点で基本的法政策が確立した」としても、それは政府の内部にとどまるものであって、裁判所を含む法制度全体の中で確立していたとはいえないのではないか、という疑問である。実際に、当時の裁判所は立法者意思をまったく忖度することなく判断を下していたし、また学説も立法者意思を援用するような議論を行っていない(もちろん井上毅の見解を用いて自説の正当化を行うような判決や学説は存在していなかった)。要するに、「従前の例」に従っているはずの戦前の判例・学説においては、立法者意思はまったく無視されていたのである。それゆえ、この程度の「確立」をもって「従前の例」とみなすことには重大な疑義があるといえよう。
そこで、以下、上記の論点に関連する限りで、大日本帝国憲法、行政裁判法、旧民法、現行民法、裁判所構成法の制定の経緯とその趣旨を検討してみることにする。
(2)大日本帝国憲法(1889年)と行政裁判法(1890年)の制定
大日本帝国憲法61条は「行政官庁ノ違法処分ニ由リ権利ヲ傷害セラレタリトスルノ訴訟ニシテ別ニ法律ヲ以テ定メタル行政裁判所ノ裁判ニ属スヘキモノハ司法裁判所ニ於テ受理スルノ限ニ在ラス」と定めたが、ここにいう「行政官庁ノ違法処分ニ由リ権利ヲ傷害セラレタリトスルノ訴訟」は、今日でいう損失補償を念頭に置いたものであった。それは、同憲法27条1項が「日本臣民ハ其ノ所有権ヲ侵サル丶コトナシ」、第2項が「公益ノ為必要ナル処分ハ法律ノ定ムル所ニ依ル」と定めていることに対応している。すなわち、財産の収容や公用制限に対して「正当な補償」は保障されず、「法律ノ定ムル所」に委ねられたのである。このため補償は個別法により立法政策的に配慮されるに過ぎないこととされた。
そこで行政裁判法の草案段階で、立法者は、次のような規定を置いたのである 。
第6条 凡ソ行政庁ノ処分ニ対スル訴訟ハ法律ニ反対ノ明文アルヲ除クノ外行政裁判所之ヲ裁判ス
第7条 行政裁判所ハ法律ニ拠リ政府ニ賠償ノ義務ヲ負フ者又ハ行政処分ヲ改正シ若ハ取消スニヨリ生スル所ノ直接ノ補償ヲ除クノ外要償ノ訴ヲ受理セス
第9条 行政訴訟又左ノ事件ニ付之ヲ為スコトヲ得
第一 官有財産ト人民トノ間ノ争訟
第二 政府ト官有物買受人又ハ政府ト工業請負人其ノ他諸般ノ契約ニ付テ起ル争訟又ハ国債ニ於ケル政府ト人民トノ間ノ争訟但シ民事裁判ニ付スベキ特約アルモノハ此ノ限ニ在ラス
第10条 行政訴訟ヲ為ストキハ民事訴訟ヲ為スコトヲ得ス
すなわち、第6条で、違法・適法を問わずすべての処分に関連する訴訟は行政裁判所で扱うこととし、第7条で、個別法によって国の賠償義務が定められている対象者と処分の変更ないし取消しにより補償の対象者とされている者に限って、行政裁判所での救済を与えることとした。ここで注意を要するのは、処分により生じる損害だけが取り扱われているのであって、官吏の違法な活動により生じる損害の問題はまったく度外視されている点である。ここでの規定の対象はあくまでも今日でいう損失補償の問題なのである。この点は第9条をみれば明らかだが、草案の検討段階で「法律ニ反対ノ明文アル」例として「郵便電信鉄道等ニ関スルモノ」が、「法律ニ拠リ政府ニ賠償ノ義務ヲ負フ者」の例として「違法ノ逮捕若ハ処刑等ニ関スルモノ」が挙げられていることを考えれば
、今日の国家賠償の問題とはかなり異なる問題が論じられていることが理解できる。
結局、行政裁判法16条は「行政裁判所ハ損害要償ノ訴訟ヲ受理セス」と規定した。上記の賠償・補償に関する訴訟手続の規定が削除された経緯は明らかではないとされるが
、後続の改正作業(「行政裁決及行政裁判権限法」案)やその審議過程での議論を参照する限りでは、行政裁判所が民法(財産法)への対応や要償額の算定をする準備ができていなかったことがその主要な理由だと思われる。この点は、立法者が行政裁判法制定後すぐに「損害要償ノ訴訟」を行政裁判所で受理するための準備を始めたことによって明らかであると思われる。
法律取調委員会第四部委員会は行政裁判法の抜本改正のために「行政裁決及行政裁判権限法」案の検討を進めていたが、1900年(明治33年)2月、「損害要償ノ訴訟」を行政裁判所が受理する旨の規定を審議した。
第66条 左ニ掲グル補償又ハ賠償ヲ受クヘキ者其一部又ハ全部ヲ拒否スル処分ニ不服ナルトキハ訴願ヲ爲スコトヲ得其拒否ヲ違法ナリトスルトキハ行政訴訟ヲ提起スルコトヲ得
一 土地収用法又ハ東京市区改正土地建物処分規則ニ依ル補償
二 河川法及砂防法ニ依リ行政庁ノ処分ニ対シテ受クルコトヲ得ヘキ補償及賠償
三 水利組合条例ニ依リ出水ノ為危険アルトキ徴収シタル現品ニ対スル賠償
四 保安林ノ買上又ハ保安林編入ニ由リ生スル損害ニ対スル補償
五 古社寺保存法ニ依ル国宝出陳ノ命ニ対スル補給金
六 阿片又ハ葉煙草納付ニ対スル賠償
七 戦時若ハ事変ニ際スル場合ヲ除ク外徴発ニ対スル賠償
八 獣疫予防法ニ依リ下付スヘキ手当金
九 航海奨励法ニ依リ認許ヲ受ケタル船舶ヲ公用ノ為ニ使用シタル場合ニ於ケル給与金
十 北海道国有未開地貸付地ヲ公用又ハ公益事業ノ為返還セシムル場合ニ於ケル給与金
十一 其他法令ニ依リ行政庁ノ処分ニ対シ受クルコトヲ得ヘキ補償及賠償
前項ノ補償又ハ賠償ニ関スル行政庁ノ決定ニ対シテハ補償又ハ賠償義務者ト決定セラレタル者ヨリモ訴願又ハ行政訴訟ヲ提起スルコトヲ得
ここから直ちに理解できるように、行政裁判法16条にいう「損害要償ノ訴訟」とは土地収用や公用制限の補償額に関する訴訟のような金銭給付をめぐる訴訟なのである
。
この規定に関連して、一木喜徳郎主査委員は、土地収用に対する補償がこの時点で行政裁判所でなく民事裁判所の管轄とされていた理由を次のように説明している。「要スルニ此権利ハ公法上ノ権利ト看做スモノナリト信ズ果シテ然ラバ何故従来行政裁判所ニ救済ヲ求メシメザルカト云フニ一方ニ於テハ未ダ行政裁判所ニ信ヲ措キ難キモノアルガ為メナラン故ニ今行政裁判ノ方法並組織ヲ改メ以テ整理ヲ加フルコトト為シタリ又行政処分ニ関スル金銭上ノ救済ハ民事ニ譲ラズシテ行政裁判所ニ移シ現行法ノ賠償ニ之ガ救済ノ道ヲ与ヘタルニ過ギズ」
。すなわち、補償請求権は公法上の権利であるので本来行政裁判所で扱うべきものだが、補償額等の算定については行政裁判所が信頼されていなかったので民事裁判所の管轄にされていた、と。
1900年(明治33年)5月には72条として審議されている。同条は上記66条と比べると、11号と12号が付け加えられ、上記11号は13号に繰り下げられた。
第72条 ……
十一 電信法、郵便法及鉄道船舶郵便法ニ依ル賠償報酬其他ノ支給金額
十二 私設鉄道法ニ依リ鉄道及付属物件ノ買上価格
この条項の審議審議の中で次のような議論が交わされている。
穂積主査委員 行政処分ニ対スル賠償ノ訴ハ行政裁判所ニ訴ヲ提起セシメ其他ハ何レノ裁判所ヘ行クベキカハ極メテ曖昧ナリ余輩ハ民事裁判所ニ訴ヲ提起シ得ザル理由ヲ知ルニ苦ムベシ
道家委員 此所ニ列記シタル以上ハ一方ノモノハ賠償ニテ行クトナレバ列記シテ置クベキモノトナラザルカ
穂積主査委員 其場合ハ民事裁判所ノ職権ニ属スベキモノトナルベシ
このように法案の起草を担当していた憲法学者の穂積八束主査委員は、行政処分に対する賠償として列挙された事項以外の補償・賠償は民事裁判所で救済されるべきことを主張している
。神権学派と呼ばれる穂積八束であってもこのような認識をもっていたことは銘記されてよいだろう。
翌6月の審議では、民法学者の穂積重陳委員が同条13号(旧案66条11号)の概括規定を問題視した。「本案行政庁ニ対スル賠償ハ民法ノ賠償ニ対スル特別法ニナリテ行政庁ノ不法行為ニ対スル賠償ハ特別法ニ定メタル場合ニ非ザレバ許サヌコトトナルベシ然ルニ憲法27条……ハ行政処分ニ対スル賠償ヲ許サザル場合ハ特別法ヲ以テ定ムト解釈セザルベカラズ出来損ヒトシテモ憲法ハ憲法ナレバ今日之ヲ如何トモサレヌ然ルニ本案ハ賠償ヲ許ス特別法ト為リテ憲法第27条ト抵触スベシ」、つまり憲法27条は特別法がなければ補償請求を排除できないと解釈せざるをえないが、13号は特別法が定める場合に限って賠償請求を許すという規定であるから憲法27条に違反する、と主張した。これに対し、憲法学者の一木主査委員は「現今ハ行政処分ニ依リ公権ヲ侵サレタル場合ニ賠償ヲ与フト云フ一般ノ法則ナク各場合ニ於テ特別ノ法令ニ於テ之ヲ定メテ居ル」と応じたが、穂積重陳は「特別ノ法規ナケレバ賠償ヲ与フルコトヲ得ザルニ於テハ不都合ナリト思フ」と反論した。結局、13号の概括規定は、出訴が許容されないと解されていた補償請求事件についても裁判的救済の途を拡大する趣旨の規定だという理解の下で、原案通り可決された
。
以上から次のことを確認できる。
[I]行政裁判法16条にいう「損害要償ノ訴訟」とは主として損失補償にかかわる補償請求訴訟である。
[II]「行政官庁ノ違法処分」以外の国の不法行為に係る損害賠償については、立法者内部においても、損失補償の場合と一体として考え、特別法がある場合に限り認められるとする説と、特別法の有無にかかわらず憲法27条や民法によって概括的に認められるとする説とがあった。
(3)裁判所構成法の制定過程における国に対する民事裁判の管轄規定の削除
政府を被告とする訴訟について、1887年(明治20年)11月16日の帝国司法裁判所構成法草案の審議 で、次の条項が提案された。
第33条 地方裁判所ハ民事訴訟ニ於テ左ノ事項ニ付裁判権ヲ有ス
第一 第一審トシテ
(イ)金額若クハ価額ニ拘ラス政府(中央政府ト其配下ノ官庁トヲ問ハス)ヨリ爲シ又ハ之ニ対シテ爲ス總テノ請求
(ロ)金額若クハ価額ニ拘ラス官吏ニ対シテ爲ス總テノ請求但其請求公務ヨリ起ツタル時ニ限ル
(ハ)其他区裁判所若クハ特別裁判所ノ権限ニ専属スルモノヲ除キ總テノ請求
第二 (略)
この日の審議の結果、1887年(明治20年)11月30日の帝国裁判所構成法草案の審議の際には字句修正を施されて、次のような文案となっていた
。
第32条 地方裁判所ハ民事訴訟ニ於テ左ノ事項ニ付裁判権ヲ有ス
第一 第一審トシテ
(イ)区裁判所若クハ特別裁判所ノ権限ニ属スルモノヲ除キ總テノ請求
(ロ)金額若クハ価額ニ拘ハラス政府又ハ官庁ヨリ爲シ又ハ之ニ対シテ爲ス總テノ請求
(ハ)金額若クハ価額ニ拘ハラス官吏ニ対シテ爲ス總テノ請求但其請求公務ヨリ起リタル時ニ限ル
第二 (略)
この文案に対し、法制局長官に着任した井上毅は「裁判所構成法案ニ対スル意見書類」で批判した(傍線原文)。
第一 国ニ対スル訴訟ノ事 ブラクストン氏王権論ニ云ハク、王ニ対スル訴訟ハ民事ト雖モ之レヲナスコト能ハズ、蓋何ノ法院モ国王ヲ裁判スルノ法権ナケレバナリト。故ニ英国ニ於テ君主及ビ政府ニ対スルノ訴訟ハ唯請願ニ由リテ恩恵ノ許可ヲ得タル後始メテ裁判ヲ受クルコトヲ得。普国千八百三十一年十二月四日ノ閣令ニ云ク、君主ノ資格ニ於テ臣民トノ間ニ裁決ヲ要スルノ権利ノ争ヲ生ズルノ理ナク、又之レヲ裁決スルノ権限アル裁判所ハ全国ニ一モ存スルコトナシト。
政府ニ対スル訴訟ハ独逸ニ於テ国権ト区別シタル財産上ノ訴訟ヲ許シタルノミニシテ、単純ニ国ニ対スル訴訟トシテ之レヲ許シタルノ国アルコトナシ。今本案ニ国ニ対スル訴訟ヲ以テ裁判所ノ権内ニ帰シタルハ其ノ当ヲ得ザルノミナラズ、専ラ居留外国人ノ日本政府ニ対スル訴訟ノ爲ニ地ヲ爲ス者ナリ。
第二 (省略)
第三 官吏ノ公務ニ対シテハ要償スルコトヲ得ズ。何トナレバ其ノ公務ハ国権ノ一部ニシテ国権ハ民法上ノ責任ナキ者ナレバナリ。官吏ニ対スルノ要償ハ其ノ官吏ノ私事トシテ訴フル者ニ限ルベシ。第三十二条(ハ)ノ場合ハ国法ノ大則ニ背ク事。
第四 (以下省略)
すなわち、政府に対する訴訟を単純に国に対する訴訟として許した国は存在しないから、国に対する訴訟を以て裁判所の権限内に帰属せしめたのは当を得ないこと、また、官吏の公務は国権の一部であって国権は民法上の責任のないものであるからこれに対して要償することはできないものであり、したがって第32条(ハ)は国法の大則に背くものであること、というのがこの意見書の趣旨である。
この井上意見書に対して、立案にあたっていた法律取調委員会は「井上法制局長官ノ意見ニ対スル弁明」を公表した。
第一 国ニ対スル訴訟ノ事
帝国裁判所構成法第五条ニ官吏ニ対スルト云ヒ国ニ対スルト云フモ其訴訟ハ皆ナ財産権上ノ民事訴訟ノミ同法第二十九条第一号ノ(ロ)(ハ)ヲ一閲セハ疑団ハ必ラス氷解セン抑第五条ニ於通常裁判所ノ有スル権限ハ一己人相互間ニ止ラス無形人ト雖モ苟モ事物ノ性質民事ニ関スルモノハ原告被告ノ身分ニ拘ハラス皆ナ之ヲ同等視スルナリ
国ノ字ニ対シ直チニ国王又ハ政府(主トシテ行政上ヲ指ス)ト解スルハ本法ノ意ニアラス皇族ニ対スル民事訴訟スラ既ニ特種ノ管轄ヲ設ク此ヨリ以上ハ此法律ノ及フ所ニアラサルコト知ルヘシ
本条ノ国トハ各省府県等ノ無形人即チ国ノ代表トシテ財産ヲ処分スル権アル官署ノ謂ナリ
第二 (省略)
第三 官吏ノ公務ニ対シ云々ノ事
帝国裁判所構成法第二十九条ノ主旨タルモノ職務上ノ権限ヲ越ヘ又ハ職務上ノ義務ヲ怠リタルカ爲メニ損害ヲ被ムリタル人民ヨリ財産上ノ訴訟ヲ爲ス場合ナリ苟モ当然ノ行政事務上ヨリ国民タルモノ損害ヲ被ルモ訴権ノ無キコトハ言ヲ待タス今本条ヲ例スルニ某官吏道路敷地ヲ買収スルニ法律ニ違ヘル点アリトセンカ人民ハ請求ノ手続ヲ爲シ猶止ムヲ得サレハ行政裁判ヲ求ム行政裁判ハ唯其官吏ノ行為ハ法律ニ違フ乎否ヲ判決スルノミ果シテ之ヲ法律ニ違ヘリトセハ此ニ於テ人民ハ損害ノ訴ヲ司法裁判所ニ起スコトヲ得此際行政裁判所ハ金銭上ニ付テハ裁判ヲ爲スヘキモノニ非ス故ニ本法ハ決シテ行政事務ヲ毀損スルモノニ非ス
第四 (以下省略)
すなわち、国に対する訴訟といってもそれは財産権にかかわる民事訴訟に限定されている、官吏個人に対する賠償請求は、権限踰越の場合や行政裁判所で違法が確定した場合であるから、行政事務に支障をもたらすものではない、と反論したのである。なお、この時点での第5条は次の通りである。
第5条 通常裁判所ノ裁判権ハ官吏又ハ国ニ対スル訴訟ニ付テモ之ヲ行フ但特別法ニ依テ裁判スヘキモノハ此限ニ在ラス
1889年2月11日に帝国憲法が公布された。裁判管轄に関する規定として、第60条「特別裁判所ノ管轄ニ属スヘキモノハ別ニ法律ヲ以テ之ヲ定ム」と上述の61条があった。これらの規定を受けて、上記の第5条は枢密院の修正で削除され、第2条「通常裁判所ニ於テハ民事刑事ヲ裁判スルモノトス但シ法律ヲ以テ特別裁判所ノ管轄ニ属セシメタルモノハ此限ニ在ラス」にまとめられたとされる
。
1890年2月10日の裁判所構成法の公布の際には、上記の帝国裁判所構成法草案32条は、26条となっていた。
第26条 地方裁判所ハ民事訴訟ニ於テ左ノ事項ニ付裁判権ヲ有ス
第一 第一審トシテ
区裁判所ノ権限又ハ第三十八条ニ定メタル控訴院ノ権限ニ属スルモノヲ除キ其ノ他ノ請求
さて問題は、国および官吏に対する訴訟を定めていた規定がなぜ削除されたかである。この理由について、下山論文は「この井上意見書の影響によるものか否かは詳かになしえぬが、これらの意見が客観的に通った形で裁判所構成法が制定されたことは銘記されねばならない」として井上意見書の影響を示唆している
。また奥田論文は「民法の適用を受ける行為による損害の賠償請求訴訟は、たとえ国家または官吏を相手とするものであっても、司法裁判所の管轄となるが、『金額若クハ価額ニ拘ハラス』地方裁判所の管轄とする必要はなく、『金額若クハ価額』によっては区裁判所の管轄としてよいと判断した結果、裁判所構成法26条から、とくに国および官吏に対する請求に関する規定を削除したのではないか、と推測される」
とし、下山論文とは反対に、井上意見書と上記規定の削除とは無関係だとしている。
以下、検討する。
まず、前記[I]で確認したように、行政裁判法16条にいう「損害要償ノ訴訟」とは主として損失補償にかかわる補償請求訴訟である。井上毅の見解によれば、損失補償の請求訴訟は行政裁判所で処理されるべきであって、実定法で認められていない限り司法裁判所の管轄外とされるべきものであった。このため彼は行政裁判法案の中で損失補償の訴訟に関する条項を入れようとしたのである(また同様の理由から、その後の立法者も同法の改正法案である「行政裁決及行政裁判権限法」案のなかにこれを導入しようとしたのである)。これとの対応関係で、司法権が国に対する訴訟のすべてを管轄することに反対したのである。
つぎに、井上も法律取調委員会も国の財産上の活動(郵便、鉄道等の事業活動)に関する賠償訴訟を司法裁判所が管轄することでは一致していた。井上は、この範囲での司法裁判所への国家賠償訴訟の提起を認めていたのであって、いっさいの国家賠償訴訟を司法裁判所は受理してはならないと主張してはいなかった。また、「行政権ノ原力」等ノ主張で井上が言っていたのは実体法上の国の免責であって、司法裁判所の管轄の否定ではない。
そして、後述の大審院判例の検討によって明らかなように、大審院は、国の権力的行為に関する損害賠償事件も含めてすべての民事事件を受理していた。立法者の意図はどうあれ、裁判所構成法はこのように運用されていたのである。大審院が裁判所構成法2条を根拠として管轄を否定したのは、徴発物に関する賠償請求事件のような損失補償関連の「損害要償ノ訴訟」だけである(後掲・大審院判決[7]参照)。これが「従前の例」なのである。仮に井上が主張したとされる国家無答責の法理が「司法裁判所は国家賠償請求を受理しないもの」とする法理であるとすれば、当該法理はそもそも「従前の例」に該当しないことになる。
以上から次のことを確認できる。
[III]裁判所構成法制定の過程で国に対する民事裁判の包括的管轄規定が削除されたことは、国家無答責の法理が実定法上で確立されたということの根拠にはならない。
(4)旧民法373条における「公ノ事務所」規定削除
この点についての立法者意思は、実はきわめて明確である。
1887年(明治20年)10月、外務省の法律取調委員会が司法省に移管されて、司法省法律取調委員会が発足し、民法・商法・民事訴訟法等の編纂事業は最終段階を迎える。旧民法財産編の立案にあたった法律取調委員会は、損害賠償の規定について、1888年10月の時点ではボアソナード草案に案を決定していた
。
第393条 主人、親方又ハ工事、運送等ノ営業人若クハ公私ノ事務所ハ其使用人、職工、又ハ属員カ受任ノ職務ヲ行フ為メ又ハ之ヲ行フニ際シテ加ヘタル損害ニ付キ其責ニ任ス
委員会の審議では「公私ノ事務所ノ責任」の意義についてかなりの議論が交わされた。「公ノ事務所」の責任について、起案者である今村報告委員は「国家ハ郵便、電信、鉄道運送ノ如キ賃ヲ取テ事ヲ行フ場合ニ於テ其使用スル者ノ犯罪又ハ準犯罪ニ付民事上ノ責ニ任スヘキノミナラス官ノ水夫又ハ発射ヲ爲ス兵卒又ハ親書ヲ送達スル騎卒ノ過失ヨリ生スル損害及ヒ行政官吏ノ職権濫用ニ因ル損害ニ付テモ亦同シフ其責ニ任ス可シ」と説明していた。井上報告委員はこの考え方にほぼ賛成し、「公私ノ事務所ナル一句ハ其儘ニ存シ『但国府県町村ニ付テハ法律ヲ以テ特ニ其責任ヲ免除スル場合ハ此限ニ在ラス』トノ但書ヲ加フルヲ可ナリト信ス」と述べて、「官吏ノ非行ヨリ生シタル損害ノ責」は国が負うべきだと主張した。このほか、官吏の非行について国家は責任を負わないとする見解をとる委員、特別法によって国家の賠償責任の範囲を確定すべきだとする委員、その詳細は学術上の問題に譲り、実際の事柄は裁判官の判断に委ねるべきだとする委員に分かれていた。
委員会の外部では、外国人法律顧問の意見が示されていた 。そこでは、国の私法上の行為あるいは財産権の主体としての行為について国は民法による責任(使用者責任)を負うが、国権の執行にともなう不法行為については、国は責任を負わないとして、393条に対する批判がほとんどであった。また当時法制局長官の職にあった井上毅も関係者の書簡を送るなどして393条を批判した。彼は、まず、法律取調委員会でこの条項の起草を担当していた今村報告委員宛に、見直しを強く求める書簡を送っている。すなわち、「国権ヲ執行スル官吏ノ処置及怠慢」にかかわる国の賠償責任については、各国の裁判例では認められておらず、また各国の学説は一致をみていないにもかかわらず、「我民法草案ハ大胆ニモ国家ヲ一網ノ下ニ打盡シテ民法ノ範囲内ニ入レント試ミ」ていることは承服できない、と
。つづいて井上は、司法大臣山田顕義宛に民法草案393条の見直しを求める書簡を送り、伊藤博文には山田宛に同条に対する意見書を送った旨を報告している
。
「公ノ事務所」という文言の削除を委員会で提案したのは、井上らから批判された今村報告委員であった。とはいえ、この修正の提案は井上らの批判を受容して行われたものではなく、彼の持論を進展させた結果なのである。
民法案第三百七十三条条中「公私ノ」ノ三字ヲ削除シ新タニ左ノ一項ヲ設ク可シ
国、府、県、町、村ニモ本条ノ規定ヲ適用ス但法律ヲ以テ特ニ責任ヲ免除スル場合ハ此限ニ在ラス
修正案の根拠を説示した今村の「国家ノ責任ニ関スル意見」 は、ボアソナードの説にも適宜批判を加えながら各国の学説・判例をし、行政事務を分類して各事務について国の使用者責任を分析した上で、判検事のような例を除き原則としてすべての国の活動について国は賠償責任を負うべきものとした(今村の見解によれば、国家の公有・私有財産の管理、郵便・電信等の事業、官設工事、警察・衛生・兵卒の行為、租税徴収、官営の工業といった行政分野について国家は賠償責任を負い、尋常行政については、その中の「国権ヲ行フモノ」「行政ノ原力」について国家は責任を負わないという説もあるが、官吏に非行があった場合には人選において国に過失があったのであるから、原則として民法が適用される)。「公私ノ」という三文字を削除した理由は、国家も原則としてすべての活動について民法の適用を受けるのであるから、「公私ノ」と表示する必要がなくなったという点にあった。「公私」の区別ではなく、「公」の内部で実定法によって免責される場合に該当するか否かという区別が重要だと判断したわけである。
今村の修正案に対して、各委員が意見書を提出した。西委員は、民法では国家の責任を明示せずに特別法をもって明示すべきだとする意見、松岡委員は、「公私ノ事務所」という文言を掲げず、国の責任についての詳細は学術上の問題に譲り、実際には裁判官の判断に委ねるべきだという意見、磯部委員は、官吏の非行について国家に責任が生じない場合がありうるがその場合については特別法を定めて予告すべきであるから、今村修正案に賛成するという意見、井上報告委員は、官吏の非行について国家に責任は生じないという法理を見出すことはできないので、373条は原案のままにして「特ニ其責任ヲ免除スル場合は此限ニ在ラス」との但書を加えるべきだという意見であった。国の賠償責任を全面的に排除すべきだという意見がないことはもちろん、「国権」や「行政ノ原力」を根拠とする国の免責論も主張されてはいなかった。
これらを総括して、委員会は最終案を次のようにまとめた。
第373条 主人、親方又ハ工事、運送等ノ営業人若クハ総テノ委托者ハ其雇人、使用人、職工、又ハ受任者カ受任ノ職務ヲ行フ為メ又ハ之ヲ行フニ際シテ加ヘタル損害ニ付キ其責ニ任ス
ここで「公ノ事務所」という文言が草案から正式に削除されたのである。そしてこの最終案がそのまま裁可され、1890年4月に公布された。
さて、「公ノ事務所」という文言の削除が「行政権による公権力の行使に起因する損害賠償責任を否定する趣旨である」(前掲・東京地判2002・8・27)といえるのであろうか。同委員会自身は、この削除の趣旨を次のように説明している。
民法報告委員ニ於テハ本条ノ「公私ノ事務所」ヲ削リ「総テノ委托者」ト改メ「属員」ヲ削リ「授[受?]任者」ト改メ公私ノ事務所ノ責任アルコトヲ明言セス単ニ法理上委托者ハ授[受?]任者ノ授[受?]任ノ職務ニ付キ責任アルコトヲ規定シテ足レリト思考ス即チ仏国民法ノ規定ニ因レルナリ……右ノ如ク本条ヲ修正スルニ於テハ政府官庁ノ責任ニ関スル問題ハ直接ニ断定セス然レトモ政府官庁カ官吏属員ニ対シ委托者タルノ資格ヲ有スル場合ニ於テハ官吏属員ノ過失ノ責ニ任ス……如何ナル場合ニ於テ政府官庁カ委托者ナルヤ否ノ問題ハ事実ノ問題トシテ司法官ノ判断ニ委ス
つまり、(i)「公ノ事務所」の責任については明言せず、単に委託者は受託者の受託職務について責任を負うと規定するにとどめる、(ii)官吏が受託者として過失ある行為を行った場合には、政府・官庁は賠償責任を負う、(iii)いかなる場合に政府・官庁が委託者に該当するかという問題は裁判官の判断に委ねる、としたのである。ここから、次のようにいうことができるだろう。すなわち、旧民法の立案者である法律取調委員会の中には、「官吏ノ非行」について原則として国が民法上の使用者責任(賠償責任)を負うべきだという見解から免責される場合がかなりあるという見解まで種々存在したが、免責の範囲について明確な基準を立てることができず、また、「公ノ事務所」という文言がそのために有効に機能するわけではないという共通認識の下で、この文言が削除されたのだ、と
。したがって、「公ノ事務所」という文言を削除した趣旨は、立案者の意識に即していえば、官吏の不法行為について国は賠償責任を負わなくていい場合があるが、どのような場合がそれに該当するかは実定法では明示せずに、判例に委ねるという趣旨であって、けっして「公権力の行使」といった特定の行政活動が存在することを前提として当該活動について賠償責任を否定するという趣旨ではなかったのである
。
以上から次のことを確認できる。
[IV]旧民法373条において立法者が「公ノ事務所」規定を削除した趣旨は、国の賠償責任の範囲を実定法上で画定できないため、これを判例に委ねるという趣旨である。
(5)旧民法373条の立案過程における井上毅の役割
ここで、「旧民法の立案過程に参加した」(前掲・東京地判2002・8・27)とされる井上毅の役割について検討しておこう。
法律取調委員会で報告委員として旧民法の原案作成に当たっていたのは、井上正一報告委員であって井上毅ではない 。一部に両者を同一視する誤解があるが
、前掲・東京地判もその例だと思われる。井上毅は当時、内閣法制局長官として外部から意見を述べていたに過ぎず、立案過程には参加していない。また、法律取調委員会が旧民法373条立案の過程で「公ノ事務所」規定を削除した趣旨は、上述のようにけっして井上の見解に沿ったものではなかった。したがって第一に、彼の見解をもって「立法者意思」ということはできず、むしろ委員会の見解こそが「立法者意思」とみなされるべきなのである。
第二に、井上毅が国の賠償責任を否定する際には、今日私たちが結果責任として考えているような事例や損失補償に該当する事例をおもに念頭に置いていた。無論、国家賠償の例も含めて考えていたのだが、要するにこれらすべてを包括して国家の責任の免除を考えていた。たとえば公用制限において補償がなされない場合、今日ではその根拠を国家無答責の法理に求める者は皆無であろうが、井上の見解によればそれは「行政権ノ原力ノ執行」であるがゆえに補償されないのである。それゆえ、井上毅の見解は国の損害賠償責任問題とは少々ずれたところで成り立っているものなのである。
第三に、井上毅自身も国が私権に基づいて行動する場合には賠償責任を負うことを認めていたが、「職権アル官吏カ行政権ノ原力ヲ執行センカ為メ施行シタル事件」
とそれ以外の事件とを区別する基準を示すことはなかった。仮に彼が国家無答責の法理を法制度の中に導入しようとしていたとしても、その適用範囲は必然的に判例に委ねられざるをえなかったのである。
以上から次のことを確認できる。
[V]井上毅の見解を旧民法373条の立法者意思とみなすことはできない。
(6)民法715条の制定と国の不法行為責任
周知のように、旧民法は施行延期とされ、結局日の目を見なかった。1893年3月には法典調査会が設置され、新規の民法編纂作業が始められることとなった。
国の不法行為責任に関しては、まず、1894年(明治27年)1月の第8回総会審議で、法人の不法行為責任との関係が議論された。
第46条 法人ハ理事其他ノ代理人カ職務ヲ行フニ際シテ他人ニ加ヘタル損害ヲ賠償スル責ニ任ス
審議において、官吏が国庫を代表して職務を行う際に犯罪を行った場合に国庫が賠償責任を負うのかという質問に対して、原案作成者である穂積陳重は、特別法がない限りここにいう法人の中には国庫を含めない趣旨だと答えた。つづいて、府県・郡・市町村・水利組合・区・部落なども本条の対象とならないのか、たとえば市制町村制2条によれば市町村は個人と同じように財産権の主体となるが、このような市町村は本条の法人に該当しないのか、また寄付行為によって成立した中学校や小学校の場合はどうかという質問が提起された。穂積は、それが公法人であればここに入らないが、市制町村制2条が市町村を通常の法人や自然人と同じように位置づけているということであれば、本条の法人に該当する可能性もある、と答えた。
以上のように、国家や公共団体は自動的に民法上の法人には含まれないと位置づけられ、国の不法行為責任の問題は後述の使用者責任の条項に関連して検討されることとなった。とはいえ、後の大審院判決では、民法の類推適用という方法で公法人にも本条(後の44条)が適用されることになる
。
かくして国の不法行為責任の問題は、草案723条の審議において本格的に検討されることになった。
第723条 或事業ノ為メニ他人ヲ使用スル者ハ被用者カ其事業ノ執行ニ付キ第三者ニ加ヘタル損害ヲ賠償スル責ニ任ス但使用者カ被用者ノ選任及ヒ其事業ノ監督ニ付キ相当ノ注意ヲ加フルモ損害カ生スヘカリシトキハ此限ニ在ラス
使用者ニ代ハリテ事業ヲ監督スル者モ亦前項ノ責ニ任ス
前二項ノ規定ハ使用者又ハ監督者ヨリ被用者ニ対スル求償権ノ行使ヲ妨ケス
翌1895年10月の法典調査会において、原案作成者の穂積陳重は、趣旨説明の中で、旧民法373条と本条との違いを次のように説明している
。
「三百七十三条ニ於テハ……主人ガ……ナンデモ其責ニ任ズル總テ其例外ヲ認メナイ之ニ付テぼあそなーど氏ノ説明ヲ読ンデ見ルト矢張リ選任ノ義務ニ帰スルト思ヒマス……其之[受任ノ職務]ヲ行フニ際シテ損害ヲ生ジタラ悉ク其責ニ任ジナケレバナラヌト云フコトニナツテ居ル本案ニ於テハ苟モ其自分ノ為スベキ事業ヲ他人ニサセルトカ他人ニ頼ンデサセルト云フ者ハ其事業ガ適当ニセラルルト云フコトヲ注意スル義務ガアル其義務ヲ怠リ又選任ニ付テモ過失ト称スベキモノガアルトキハ其責ニ任ズルガ注意ヲ加ヘテ選任シタトキハ其責ニ任ジナイト云フ点ハ既成法典トハ余程其主義ヲ異ニシテ居ルノデアリマス」
この説明によれば、旧民法373条との大きな違いは、使用者の免責事由を但書きで挿入した点にある。また、旧民法373条の立法者意思としてボアソナードが引用されていることにも注目すべきだろう。新民法作成者の意識においては、同条も含めて立法者の背後にいたのはボアソナードであって、井上毅ではなかったのである。
さて、穂積陳重による趣旨説明の直後に、穂積八束が「此使用人ト使用者ニ代リテ監督スル人トノ関係ノ規則ト云フ者ハ政府ト政府ノ使ウ所ノ官吏其他ノ使用人ニモ此原則ガ当ルト云フ御考ヘデアリマスカドウカト云フコトヲ確カメテ置キタイ……解釈次第デ政府ト一己人トノ間デモ政府ヲ法人ト見レバ矢張リ民法ノ規則ヲ適用サレルト云フ議論モ出来ヤウト思フ」と質問し、さっそく本条によって政府も賠償責任を負うことになるのか否かという問題が俎上にのせられた。穂積陳重は次のように答えた。
「穂積陳重君 本条ニ付テ第一ニハ政府ノ官吏ガ其職務ヲ行フニ際シテ第三者ニ加ヘタ損害賠償ニ之ガ当ルヤ否ヤト云フコトガ第一ノ御質問デゴザイマスソレニ対シマシテハ一ノ明文ガアリマセネバ固ヨリ政府ノ事業ト雖私法的関係ニ付キマシテハ本案ハ当ラナケレバナリマセヌカラ他ニ特別法ガナイ場合ニ於テハ本案ハ当ルト御答ヘシナケレバナリマセヌガ併シ本案ガ当ルガ良イカ悪ルイカハ第二ノ問題デアリマスガ此案ヲ立テマストキニモ政府ノ官吏ガ其職務執行ニ付テ過失ガアツタトキニハ其責ニ任ズルヤ否ヤト云フ箇条ヲ置カウカト思ヒマシタガ併シ之ヲ民法ニ置キマスノハ不適当ノ場所デアルト考ヘマス一般ノ賠償ノ通則トシマスレバ公ケノコトデアルカラ夫故ニ一己人ニ其職務ノ執行ニ付テ非常ニ損害ガ生ジテモ是ハ御上ノコトデアルカラト言ツテソレハ償ナハヌ斯ウ云フノハ憲法ノ精神ニモ余程戻ルモノデアラウト思フ……官吏ノ職務上ノコトデアルカラ過失ガアツテモソレハ賠償ヲサセヌ方ガ宜イト云フコトハ是レハ例外デアツテ一ツノ特別法ヲ以テ定ムベキ事柄デアル……特別法……ガナケレバ本条ノ規定ガ当ルト云フコトデソレハ尚ホ勘考スベキコトデアル」
すなわち、政府の賠償責任については現在明文の規定はないが、まず、特別法がない限り私法的関係については本条が適用になり、次に、政府の官吏が職務執行について過失があったときについては、賠償を免責するのはやはり例外であって、特別法(官吏個人の賠償責任法など)がなければ本条の規定が該当する、というのが提案者の考えであった。この答えをめぐって若干の意見交換や賛成論があった後、次のような反対論が表明された。
「高木豊三君 ……穂積君ノ御説明ヲ承ハリマシタガ今ノ御答ニ依ルト政府ト官吏トノ間ノ関係即チ官吏ノ過失行為ハ政府ガ代ツテ賠償スルカドウカト云フ問題モ本条ニ含ムカノ如キ御答ニナツタヤウデアリマスガ私ハサウハ解シ兼ル……政府ノ官吏ト云フモノガ職務執行ニ付テ第三者即チ人民ニ対シテ損害ヲ加ヘタ場合ニ此原則ニ依テ政府ガ其賠償ノ責ニ任ズルヤ否ヤト云フ問題ヲ此条デ暗ニ極メタモノト云フコトデアルナラバ私共ノ解釈シテ居ルモノトハ大変趣意ガ違ヒマスノデ其問題ナラバ大ニ是ハ論ズベキ事モアリ研究スベキコトモアラウト思フ」
高木は、官吏の職務執行に関わる政府の賠償責任は本条の対象外だという見解を表明した。これに対し穂積陳重は「若シ官吏ノ職務執行ニ対スル云々ト云フコトガ必要デアルナラバソレハ特別法ヲ出サレル方ガ宜カラウ本案デ是非サウシナケレバナラヌト云フコトデハナイ併シ特別法ガ出ナケレバ裁判官ハ本条ニ依テ裁判ナサレルデアラウト思フ」と述べて、特別法が制定されない限り官吏の職務執行上の過失についても本条が適用されるべきことを主張し、梅謙次郎も、特別法の必要性を指摘しながらも「若シ特別法ガナケレバ此七百二十三条ガ当ルノデアラウト思フ又当ラナケレバ不都合ト思フ……私モ穂積[陳重]君ト同意見デアリマス」と穂積に同調した。高木はこれらの議論に納得せず、次のような質問を続けた。
「高木豊三君 私ノ言ヒマシタノモ国ト云フ法人ガ民法上ノ事業ノ関係ニ付テ此条ガ当ルカ当ラヌカト云フコトニ付テ無論当ルト云フコトハ一点ノ疑ヒガナイ只私ノ先刻申シタ官吏ガ職務ヲ行フニ際シテ私法上ノ関係デナクシテ公権ノ作用ト云ヒマスカ詰リ裁判官ガ裁判ヲスル警察官ガ人ヲ捕ヘルト云フヤウナコトモ之ニ当ルト云フヤウナコトニ聞エテハ甚ダ困ル若シサウ云フ問題ガ之ニ籠ツテ居ルナラバ大問題ダト云フノデアリマシテ……日本ニハ是ハ極マツテ居ラヌノミナラズ欧羅巴ノ法律ニ於テモ未決ノ大問題ト言ツテモ宜イト思フ日本デハ判決例ガ僅ニ一二アルダケデソレモ大審院迄来テ政府ノ官吏ガ職務執行ノ場合ニ人民ニ損害ヲ及ボシタト云フトキハ政府ガ其責任ヲ負フト云フコトノ明カナ判決例ハナイ一般ノ場合ハ官吏ノ職務上ノ過失ハ政府ガ責ヲ負ハナイト云フヤウナ今日ハ傾キニナツテ居リマス只誤ツテ県令ガ人民ニ損害ヲ加ヘタ場合ニ賠償ヲシタト云フヤウナ一二取除ケノコトガアルニ過ギヌノデアリマス」
ここで高木は、はっきりと「公権ノ作用」について政府がその賠償責任を負うのか否かという問題に焦点を合わせ、これを否定すべきだと主張した。そしてこの問題についての結論は日本ではまだ出ていないし、ヨーロッパ諸国の法律でも未解決の大問題だとし、この点についての大審院判例は少ないが政府が賠償責任を負うと判断した判決例はなく、また政府の責任を否定するのが一般的傾向だと紹介した。議論は次のように続く。
「穂積陳重君 斯ウ云フノデアリマス官吏ノ職務執行ノ場合ニ是レガ当ルガ宜イト我々ハ極メテ居ラヌノデ我々ガ研究シテ見ルト時トシテハ民法ニ書イテ居ル国モアリマスカラ是レモ書カウカト思フテ相談シテ見マシタガイヅレ特別法ガ出来ルダラウト思ヒマシタカラ止メタノデアリマス……特別法ガナイ以上ハ例ヘバ軍艦ガ一己人ノ商売船ト衝突シテ其船ヲ沈メタトカ云フサウ云フ様ナ場合ニ賠償ヲ求メルト云フニハ此条ガ当リハシナイカト云フ御相談ヲシタノデ特別法ヲ作ラナイデ是レデ押通シテ仕舞ウト云フ丈ケノ決心ハ我々三人共ナカツタノデアル併シ若シ特別法ガナカツタラバ是レガ当ルジヤラウト云フ考ヘハ三人共持ツテ居ル
高木豊三君 只今ノ御答デ能ク分リマシタ官吏ニ対シテ賠償ヲ求メルト云フコトヲ御書キニナラウカト云フコトデ独逸ノ様ニシヤウト云フ御趣意デアリマスカ
穂積陳重君 サウデス
高木豊三君 ソレナラバ宜イ、サウデハナイ此場合ハドウカト言ヘバ……巡査ガ誤ツテ人ヲ縛ツテ損害ヲ加ヘタト云フノニ損害賠償ヲ与ヘルト云フコトニナツテハ大変デアルサウ云フコトハ言ハレヌト云フコトデアリマスレバ私ハ一向差支ナイノデアリマス」
穂積は、どのような政府の事業が本条に該当するか否かは条文上明確にしていないが、該当しない場合を特別法(おそらくは官吏個人の賠償責任法)で定める方向が望ましいとしている。それがない段階では「軍艦ガ一己人ノ商売船ト衝突シテ其船ヲ沈メタトカ云フサウ云フ様ナ場合」も本条の適用対象になりうることを示唆している。この説明を受けて、高木は、ドイツでのように官吏の賠償責任に関する立法を行うことが国の「公権ノ作用」に関する賠償責任の免除につながるものと理解して、了解したわけである。しかし、穂積が示した軍艦の例のほか、土地収用に関連する損害賠償問題は従来明らかに「公権ノ作用」とされてきた問題であり、いかなる場合に国が免責されるのかという論点はペンディングにされたのである
。
審議の中では、「公権ノ作用」について国が免責される根拠として、「慣習法になっている」(都筑委員)、「判決例で公法上の職務執行の過失による損害の賠償は行わないという例になっている」(同)、「公法と私法の区別」(横田委員)、「政府の賠償責任を認めた大審院判例はなく、これを認めないのが一般的傾向」(高木委員)、「法律違反の行為は一個人の行為であって国の為にやる行為ではない」(同)などの点が挙げられている。けっして「明治23年の旧民法制定時に決着済み」という態度はとられていないし、誰もこれを援用していない。
以上の審議経過から理解できるように、官吏の職務執行に関わる国の賠償責任について、一方では本条の原則的な適用が主張され、他方では民法上の事業に限るべきだとする主張が行われ、一定の場合に国が免責される場合がありうることが想定されていたが、いずれにしても国家無答責の問題はまだ未決着のままであり、大審院の方針も不明確なままであり、将来的に特別法をもって対処すべき問題だという点では一致をみていた、といってよいだろう。
ここから次のことを確認できる。
[VI]国家無答責の法理に関わる問題は現行民法の制定作業の中でも継続して議論されていた。
(7)この時期の裁判所と学説の態度
行政裁判法と旧民法の公布の翌年である1891年(明治24年)の『法学協会雑誌』によれば、学説と判例は次のような状況にあった
。
「行政訴訟と司法裁判権 我国行政裁判法か列記法を採用せし以来行政官庁の違法処分により権利を傷害せられたりとするの訴訟にして行政裁判所の管轄に属せさるものは司法裁判所にて受理するを得へき否やに就ては法学者の説二つに分れ何れも帝国憲法第六十一条を根拠として論陣を張り未た容易に雌雄を決するに至らす……大審院は明かに行政処分に対する訴訟にして行政裁判所の管轄に属せさるものは総て司法裁判所の管轄する所なりとの説を取るものなり」。
すなわち、学説においては、行政裁判法16条に列記されていない事項はすべて司法裁判所に属するという説とどちらの裁判所も管轄できない事件があるという説とが対立し、決着がつかない状況であり、判例(大審院)は、行政裁判所が管轄しない事件すべてを司法裁判所が管轄するという見解を採用しているのである。前掲の東京地判2002・8・27によれば「明治23年の時点で公権力行使についての国家無答責の法理を採用するという基本的法政策が確立した」はずであったが、学説においても大審院の判断においても、立法者意思は考慮されず、その影響さえも窺うことができないのがこの時期の状況であったといえる
。
その後、行政裁判所制度が定着していくにつれて、しだいに公法私法二分論と裁判管轄が結びつくようになっていく。公法関係事件は行政裁判所、私法関係事件は司法裁判所、という管轄区分である
。立法作業にも関わっていた一木喜徳郎は、この問題を次のように処理していた。
「訴訟ヲ起スノ権ハ法ノ認ムルニ由テ存在スルモノナリ如何ナル事件ニ付訴訟ヲ許スヤハ一ニ法ノ定ムル所如何ニ在リ憲法ハ決シテ行政処分ニ対シテハ汎ク訴訟ヲ許スヘキコトヲ規定シタルニ非ス……憲法六十一条ハ一方ニ於テハ行政処分ニ由リ権利ヲ傷害セラレタリトスルノ訴訟ハ皆行政裁判所ニ属スヘキコトヲ規定シ一方ニ於テハ是等ノ訴訟ハ仮令法律ヲ以テスルモ司法裁判所ノ権限トスヘカラサルコトヲ規定セルモノナリ」
一木はこうした憲法解釈に基づいて、民刑事事件は司法裁判所、行政処分による権利侵害事件は行政裁判所、その他の事件については、法令の定めがある場合に限り司法裁判所が管轄すべきだとした
。しかしここでは、行政処分以外の行政活動に起因する権利侵害事件、つまり損害賠償請求事件の位置づけが抜け落ちていた
。一方、違法処分についての賠償請求事件が、公法関係の事件だという理解の下で、年間200件くらい行政裁判所に提起されていたといわれる
。
このような混乱状況に理論的な整理を与えたのが、美濃部達吉である。1906年の論文「国家カ私人ノ利益ヲ侵害シタル場合ニ於ケル賠償責任ヲ論ス」
において、彼は、「適法ノ原因ニ因リ私人ニ損害ヲ加ヘタル場合」と「官吏の職務違反ニ因リ私人ノ利益ヲ侵害シタル場合」とに分け、前者については、責任の有無およびその程度はすべて法規の明文によって定まる、とする。つまり彼は、この場合の請求を「衡平ノ要求ニ基ク」賠償請求と理解し、明文の賠償責任規定がない場合にはこれを否定する(このような限定を設けないオットー・マイヤー説を批判する)。後者については、「官吏ノ職務違反ノ行為ハ国家ノ行為ニ非ラス官吏ノ一個人トシテノ行為ナリ」という説を否定し、公法上の行為については官吏の行為が国家から委任された権限の範囲内のものであれば違法な行為であっても国も官吏個人も賠償責任を負わない、と主張する。すなわち、「[国家からの]権限ノ委任ハ当然ニ其ノ権限カ違法ニ行使セラレ得ベキ危険ヲ包含スルモノ」なので、官吏の職務上の行為はたとえ違法であっても国家の公法上の行為となり(違法行為が国家に帰属すること自体は行政訴訟制度の存在によって裏づけられている)、それゆえ民法の損害賠償規定の適用はなく、国家は賠償責任を負わないとされ、また、官吏が職務上の義務を負っているのは国家に対してだけだという理由で、官吏とは直接の法律関係がない第三者に対する官吏個人の賠償責任も否定されるのである。ここに至ってようやく「官吏の違法な行為は国家に帰属しない」という法治国家原理に基づく国の免責論とは別次元の国家の免責理論、つまりKing
can do no wrongと称される国家無答責の法理が登場したのである 。
ここから次のことを確認できる。
[VII]裁判実務においては「明治23年の時点で公権力行使についての国家無答責の法理を採用するという基本的法政策が確立した」ということはできず、また当時の学説においてもこのような認識は存在しなかった。
[VIII]官吏の違法行為に関する国の不法行為責任について、学説上で明確に国家無答責の法理が用いられたのは1906年(明治39年)である。
(8)まとめ
これまでに得られた小結論を提示する。
[I]行政裁判法16条にいう「損害要償ノ訴訟」とは主として損失補償にかかわる補償請求訴訟である。
[II]「行政官庁ノ違法処分」以外の国の不法行為に係る損害賠償については、立法者内部においても、損失補償の場合と一体として考え、特別法がある場合に限り認められるとする説と、特別法の有無にかかわらず憲法27条や民法によって概括的に認められるとする説とがあった。
[III]裁判所構成法制定の過程で国に対する民事裁判の包括的管轄規定が削除されたことは、国家無答責の法理が実定法上で確立されたということの根拠にはならない。
[IV]旧民法373条において立法者が「公ノ事務所」規定を削除した趣旨は、国の賠償責任の範囲を実定法上で画定できないため、これを判例に委ねるという趣旨である。
[V]井上毅の見解を旧民法373条の立法者意思とみなすことはできない。
[VI]国家無答責の法理に関わる問題は現行民法の制定作業の中でも継続して議論されていた。
[VII]裁判実務においては「明治23年の時点で公権力行使についての国家無答責の法理を採用するという基本的法政策が確立した」ということはできず、また当時の学説においてもこのような認識は存在しなかった。
[VIII]官吏の違法行為に関する国の不法行為責任について、学説上で明確に国家無答責の法理が用いられたのは1906年(明治39年)である。
ここで、以上の小結論がもつ意味を確かめてみる。
第一に、立法者の意識においては、国家無答責の法理は1890年の立法措置(行政裁判法と裁判所構成法の制定および旧民法373条における「公ノ事務所」規定の削除)によって確立した実定法理だとは考えられておらず、むしろその後の判例・学説に委ねられるべきものとされていた(上記[II][III][IV][V][VI])。第二に、1890年の立法措置によって方向性が与えられたのは、今日でいう損失補償の請求訴訟であって、官吏の違法行為に関する損害賠償制度上の位置づけについては、その後も検討が続けられた(上記[I][II][VI][VII][VIII])。第三に、この法理の運用に関して、1890年の時点で「従前の例」とみなしうるような裁判実務が確立していたとはいえない([VI][VII])。
以上から次の結論が得られる。
[IX]国家無答責の法理は、立法者意思、損害賠償制度上の位置、裁判所による運用のいずれの点からみても、1890年の立法措置によって実定法上で確立された法理だということはできない。
3.大審院判決の推移と判例の形成
(1)はじめに
行政裁判法と旧民法の制定以後、国および公共団体の賠償責任について戦前の判例はどのような推移をたどって形成されたのであろうか。まず、主要な大審院判決の一覧を示しておく(「*」印は国家無答責法理の適用が争われた事件で、これを適用しなかった例である)
。
[1]1891明治24・4・7、宮下文十郎外88名対長野県知事事件(裁判雑誌123号)
[2]1896明治29・4・30、河川改修工事過失事件(民録2輯4巻117頁)
[2.5]1898明治31・5・27、国鉄工事事件(民録4輯5巻27頁)
[3]1903明治36・12・14、高知県令官林払下げ事件(民録9輯1406頁)
[4]1904明治37・6・27、水利組合間の原状回復請求事件(民録10輯1149頁)
[5]1906明治39・7・9、水利組合欠陥工事事件(民録12輯1096頁)*
[6]1907明治40・2・22、道路改修工事事件(民録13輯148頁)
[7]1907明治40・5・6、徴発物賠償請求事件(民録13輯476頁)
[8]1909明治42・12・17、国による損害賠償請求事件(民録15輯963頁)
[9]1910明治43・2・25、滞納処分による国の不当利得事件(民録16輯153頁)*
[10]1910明治43・3・2、板橋火薬製造所事件(民録16輯174頁)
[11]1915大正4・4・22、国有林売却事件(民録21輯564頁)
[12]1916大正5・6・1、徳島市立小学校遊動円棒事件(民録22輯1088頁)*
[13]1916大正5・11・27、村長違法免除事件(民録22輯2120頁)*
[14]1917大正6・1・19、水利組合水閘開放行為事件(民録23輯62頁)
[15]1918大正7・6・29、鹿児島市水道工事事件(民録24輯1306頁)*
[15.5]1918大正7・10・21、小学校梯子倒壊児童死亡事件(民録24輯2000頁)*
[16]1918大正7・10・25、築港工事瑕疵汽船沈没事件(民録24輯2062頁)*
[17]1918大正7・12・19、公用物(道路)への抵当権設定事件(民録24輯2342頁)*
[18]1919大正8・10・9、村長立木違法払い下げ事件(民録25輯1783頁)*
[18.5]1920大正9・6・17、汽車転覆事故事件(民録26輯891頁)
[19]1923大正12・4・4、部落間の損害賠償事件(民集2巻201頁)*
[20]1923大正12・6・2、水利組合水門開閉瑕疵事件(民集2巻361頁)*
[21]1924大正13・5・14、郵便局長小切手亡失事件(法律新聞2275号20頁、法律新報5号9頁)
[22]1924大正13・6・19、市下水道設備瑕疵事件(民集3巻295号)*
[23]1925大正14・12・11、水利組合樋管閉鎖事件(民集4巻706頁)*
[24]1927昭和2・11・17、郵便局職員横領窃取事件(民集6巻609頁)
[25]1929昭和4・10・24、特許附与懈怠事件(法律新聞3073号9頁)
[26]1930昭和5・5・24、海峡浚渫瑕疵事件(大審院裁判例4巻民事53頁)*
[27]1932昭和7・3・30、道路法路線認定事件(法律新聞3396号13頁)
[28]1932昭和7・8・10、軍療養所用鑿井工事事件(法律新聞3453号15頁)*
[29]1932昭和7・9・14、滞納処分事件(法律新聞3461号10頁)
[30]1933昭和8・4・28、消防自動車試運転轢殺事件(民集12巻1025頁)=被告:大阪府
[31]1935昭和10・8・31、消防自動車試運転轢殺事件(法律新聞3886号7頁)=被告:国
[32]1936昭和11・2・27、郵便貯金払戻過失事件(民集15巻249頁)*
[33]1936昭和11・6・8、電話加入名義偽造事件(民集15巻928頁)*
[34]1937昭和12・3・31、吏員の職権乱用事件(民集16巻387頁)*→個人賠償
[35]1937昭和12・10・5、町収入役金銭騙取事件(判決全集4輯19号5頁)*
[36]1937昭和12・11・27、滞納処分事件(判決全集4輯23号1168頁)(*→差戻)
[37]1938昭和13・11・29、大阪市違法課税事件(民集17巻2243頁)
[38]1938昭和13・12・23、印鑑証明過失事件(大民集17巻24号2689頁)
[39]1939昭和14・4・26、官吏の不法行為責任(否定)(法律新聞4435号13頁)
[40]1940昭和15・1・16、官吏の賠償責任(肯定)(民集19巻1号20頁)(*→差戻)
[41]1940昭和15・2・27、町長不正借入事件(民集19巻6号441頁)*
[42]1940昭和15・3・15、町収入役横領事件(法律新聞4565号7頁)*
[43]1941昭和16・2・27、東京市等滞納処分事件(民集20巻2号118頁)
[44]1941昭和16・9・26、滞納処分に係る吏員の賠償責任(大審院判決全集8輯32号11頁)
[45]1941昭和16・11・26、土地の違法強制収用事件(判決全集9集11号6頁)
[46]1943昭和18・9・30、滞納処分取消による損害の賠償請求事件(判決全集10輯5号2頁)
以下、主要な大審院判決をたどりながら、「判例」と呼びうるものの内容を析出してみよう。
(2)主要判決の推移
[5]1906(明治39)・7・9、水利組合欠陥工事事件(民録12輯1096頁)
「本件水利組合ノ如キ公ノ法人ト雖モ工作物ヲ占有スル場合ニ於テハ其占有ハ私法上ノ関係ニ於テ存スルコトアルヲ以テ全然同条ノ規定ノ適用ヲ免ルヽモノト謂フヲ得ス」「水利組合カ其ノ目的ノ為メニ工作物ヲ設置スルハ権力行為ニ起因スルトモ其権力行為ニ基キ設置セラレタル工作物ヲ占有スルハ必スシモ一般ノ人ヲシテ其権力ニ服従セシムルカ如キ関係ニ於テスルモノニ非スシテ寧ロ一般ノ人ニ対シ平等ノ関係ニ於テスルモノト謂フ可シ故ニ其工作物ノ占有ハ私法上ノ関係ニ於テ存スルコトアルヤ疑ヲ容レサルヲ以テ其占有者ハ公法人タリトモ民法第七百十七条ノ規定ニ従ヒ一般ノ人ニ対シ工作物ニ存スル瑕疵ニ因ル損害ノ発生ヲ防止スルニ必要ナル注意ヲ為ス可キ責任ヲ免ルヽコトヲ得ス」。
本件は、水利組合が、隧道の欠陥工事によって上告人(寺院)の本堂や鐘楼を傾斜させ、用水溜を枯渇させるなどの損害を及ぼした事件である。大審院は、工作物の設置行為と占有とを区別し、後者は私人と平等な法関係だと判断して、公法人が占有する工作物の瑕疵に起因する損害について民法717条(工作物の占有者の責任)を適用した。後掲[12]判決(徳島市立小学校遊動円棒事件判決)と同様の構成がとられている。行政裁判法や民法の立法過程での議論においては国や公共団体のような公法人には民法は適用されないとする主張もあったが、この時点で克服されていることがわかる。
[7]1907(明治40)・5・6、徴発物賠償請求事件(民録13輯476頁)
「徴発令ハ戦時又ハ事変若クハ演習行軍ノ際国家カソノ存在ノ目的ヲ達スル為メ国家ト臣民トノ権力服従ノ関係ヲ規定シタル一ノ公法ニシテ素ヨリ国家ヲ一私人ト看做シ徴発ヲ課セラレタル一私人トノ間ニ於テ平等衡平ヲ基本トシ其権利義務ノ関係ヲ規定シタルモノニアラサルコトハ之ヲ該令ノ精神ニ徴シ之ヲ其条文ニ照シ毫モ疑ヲ容レス故ニ国家行政ノ機関タル行政官カ該令ニ遵由シテ臣民ノ物件ヲ徴発シ之ニ賠償金ヲ下付スルカ如キ行為ハ総テ公法上ノ支配ヲ受クヘキハ当然ニシテ素ヨリ一私人間ノ権利関係ヲ規定スル私法上ノ支配ヲ受クヘキ理ナキハ言ヲ俟タサル所ナリ然ラハ則チ本案徴発令ニ従ヒ下付スヘキ徴発物ノ賠償ニ関スル請求事件ニ付キ通常裁判所即チ司法裁判所ハ管轄権ヲ有セサルヤ多言ヲ要セサル所ナリ何トナレハ通常裁判所ハ法律ニ明文アル場合ヲ除キ民事即チ私法上ノ訴訟ヲ裁判スルモノニシテ公法上ノ訴訟ヲ裁判スル権限ヲ有スルモノニアラサレハナリ(裁判所構成法第二条参照)」。
本判決は、第一に、国家行政の機関たる行政官が徴発令に遵由して臣民の物件を徴発し賠償金を下付する行為は、公法の支配を受けるべきものであって、私法の支配を受けない、第二に、徴発物件の賠償に関する訴訟は司法裁判所の管轄に属しない、と判示した。行政裁判所と司法裁判所との間の管轄に関する判例としてみることもできる。[3]判決とは対照的に、根拠規定が公法であるという前提から演繹的に「臣民ノ物件ヲ徴発シ之ニ賠償金ヲ下付スルカ如キ行為」はすべて公法上の行為であって私法の支配を受けない、という結論を導き出している。また、このことを理由として司法裁判所の管轄自体を否認している点も本判決の特徴である。しかし、このような判断方法は後の判例においては採用されていない。
[9]1910(明治43)・2・25、滞納処分による国の不当利得事件(民録16輯153頁)
「国税徴収法第十四条ニハ「収税官吏財産ノ差押ヲ為シタル場合ニ於テ第三者其財産ニ就キ所有権ヲ主張シ取戻ヲ請求セムトスルトキハ売却決行ノ五日前マテニ所有者タルノ証憑ヲ具ヘテ収税官吏ニ申出ヘシ」トアルヲ以テ国税滞納処分トシテ差押ヘタル財産ト雖モ苟モ第三者ノ所有ニ属シ国税滞納者ノ所有ニ属セサルコト明ナルニ於テハ国ハ之ニ因リテ不当ニ利得ス可カラサルニ依リ所有者タル第三者ノ請求ニ応シテ之カ取戻ヲ得セシムル法意ヲ推知スヘシ随テ収税官吏ニ於テ之カ売却ヲ決行シタルトキハ国ハ其利益ノ存スル限度ニ於テ不当利得返還ノ責ニ任スヘキハ当然ニシテ国税滞納者ニ対スル財産ノ差押及ヒ売却カ国税滞納処分ノ執行上為ス行政行為タルノ故ヲ以テ如上第三者ノ請求ニ対スル私法的責任ヲ免カレ得ヘキモノニアラス然レハ之ト同一趣旨ニ出タル原判決ハ適当ニシテ本論旨ハ理由ナシ」。
滞納者の所有に属さない財産に対する滞納処分によって国が得た不当利得については、民法に基づいて国は不当利得返還義務を負う、と判断した。「行政行為」の過失に関する事件であっても民法が適用される、と大審院が判断した例である
。
[10]1910(明治43)・3・2、板橋火薬製造所事件(民録16輯174頁)
「国家ト個人トノ関係ニ於テ如何ナル場合ニ国家ハ私法的関係ニ服スルモノナルヤハ現時ノ国法ニ照シテ之ヲ定ムルノ外ナク国家カ個人ニ対シテ命令シ其服従ヲ強制スル場合ハ公法的関係ナルコト疑ナキ所ナルト共ニ国家カ其私経済動作ヲ為ス場合ハ国家カ私法的関係ニ服スヘキ一ノ場合ナルコト亦疑ナシ而シテ国家ノ行為ニシテ主トシテ国家ノ財産上ノ利益ノ為メニスルモノハ乃チ国家ノ私経済的動作ニシテ私法的行為トシテ私法ノ適用ヲ受クヘク之ニ反シテ国家ノ行為ニシテ主トシテ公共ノ利益ノ為メニスルモノハ公法上ノ行為トシテ公法ノ適用ヲ受クヘキモノト謂フヘキナリ」「火薬製造ノ如キハ……所謂軍事的行動ノ一部ニ属スルモノト認ムヘク之ヲ以テ公共ノ利益ノ為メニスルモノト看做スヘクシテ単ニ国家カ財政上ノ利益ノ為メニスルモノニ非サルヤ明ケシ」。
原審(東京控訴院)は、次のように述べて、国法の規定の仕方を基準として公法・私法の区別をした。「国法カ国家ハ私人ト対等ノ関係ニアル権利ノ主体トシテ行動スヘキモノトセルトキハ之ニ関スル国家ノ行為ハ権利上ノ行為タルト事実上ノ行為タルトヲ問ハス凡テ之ヲ私法ノ範囲ニ属セシムヘク之ニ反シテ国法カ国家ハ権力ノ主体トシテ行動スヘキモノトセルトキハ之ニ関スル国家ノ行為ハ権力上ノ行為タルト事実上ノ行為タルトヲ問ハス凡テ之ヲ公法ニ依リテ支配セラルヘキ公法上ノ行為ナリト云ハサルヲ得ス」。
これに対して、本判決の大審院は、行為が「国家ノ財産上ノ利益ノ為ニスルモノ」か「公共ノ利益ノ為ニスルモノ」かという行為の目的を基準として両者を区別し、火薬の製造は後者に属するので、火薬製造所の設置者である国は損害賠償責任を負わない、と判示した。本判決について田中二郎は「其の正当でないことは、多くの学者の屡々指摘したところであり、判例も亦、……大正5年を境として公共事業に基く損害に付ても、国家公共団体の賠償義務を肯定するに至った」と批判している
。後の大審院の判断をたどると、本判決は、後掲[12]判決では「小学校の管理」という面において判例として扱われていたと考えられるが、後掲[26]判決に至って、公共事業一般の判例として適用することが否定されたと考えられる。
[12]1916(大正5)・6・1、徳島市立小学校遊動円棒事件(民録22輯1088頁)
「本件小学校ノ管理ハ上告人主張ノ如ク行政ノ発動タルコト勿論ナレトモ其管理権中ニ包含セラルル小学校校舎其他ノ設備ニ対スル占有権ハ公法上ノ権力関係ニ属スルモノニアラス純然タル私法上ノ占有権ナルノミナラス其占有ヲ為スニモ私人ト不平等ノ関係ニ於テ之ヲ為スニアラス全ク私人カ占有スルト同様ノ地位ニ於テ其占有ヲ為スモノナレハ之ニ因リ被上告人等ニ損害ヲ被ラシメタル本訴ノ場合ニ於テ原院カ民法第七百十七条ノ規定ヲ適用シタルハ毫モ不法ニアラス」。
本判決は、小学校の管理を「行政[権]ノ発動」としながらも、その管理権に包含される設備の占有権を公法上の権力関係ではなく、私法上の占有権と同様のものだと位置づけることによって、当該設備に起因する損害について民法717条を適用した。上告人(市)が、設備の管理も営造物の管理権の一環として「行政法上ノ行為」に該当し、民法の適用範囲外である旨を滔々と論じているのに対し、本判決の判断部分はきわめて簡略である。
注目すべきは、第一に、上告人が前掲[10]判決を示して学校の利用関係は「公法上ノ関係」である旨を主張したのに対し、本判決がこれを基本的に是認しながら、[10]判決が用いていた「公共ノ利益」という判断基準ではなく、個別の法関係を基準として判断した点、第二に、学校の管理全体の法関係と損害が発生した個別局面の法関係とを区別した点、第三に、前者が公法関係であることを是認した上で、後者について──対等関係という法関係に着目して──私法を類推適用したとみられる点であろう
。後掲[15]判決以降、本判決が判例として扱われることになる。なお、大審院は、小学校で梯子が倒れて児童が死亡した事件(大正7・10・21、民録22輯2000頁)において民法709条を適用し、「土地ノ工作物」以外の設備(動産)についても公法人の賠償責任を認めることになる。
[14]1917(大正6)・1・19、水利組合水閘開放行為事件(民録23輯62頁)
「公法人タル高木普通水利組合カ其有スル公権ノ作用トシテ為シタル本件島足沼ノ樋口検査の為メニスル水閘開放ノ行為……ノ如キハ組合員以外ノ者ニ対シテモ公法上ノ行為タルコトヲ妨ケサルヲ以テ原裁判所カ組合ノ有スル公権ノ行使タル職務ノ執行トシテ水閘ヲ開放シ上告人ニ損害ヲ生セシメタルモ執行者ニ賠償ヲ為サシムヘキ特別ノ法規存セサルカ故ニ控訴人(被上告人)根本藤吉ニ於テ賠償スル責任ヲ負フモノト為スコトヲ得サル旨判断シタルハ相当ニシテ上告論旨ハ理由ナシ」。
公法人たる普通水利組合がその有する公権作用としてなした水閘開放の行為は、組合員以外の者に対しても公法上の行為であり、したがってこれにより第三者が損害を受けても組合は賠償責任がない、と判示した。公法関係を理由として賠償責任を否定した事例である。本判決を判例とみなすことはできず、後掲[23]判決に至って修正されたものと考えられる。
[15]1918(大正7)・6・29、鹿児島市水道工事事件(民録24輯1306頁)
「市カ水道条例ニ依リ内務大臣ノ認可ヲ受ケ其公費ヲ以テ布設スル水道其他ノ設備ハ市ノ営造物ニシテ市長ハ同条例及ヒ市制ノ定ムル所ニ従ヒ之ヲ管理スヘキモノナレハ水道ノ設置及ヒ其管理ハ共ニ公権作用タル行政行為ニ属スルコト論ヲ竢タスト雖モ之ト同時ニ其水道設備ニ対スル市ノ所有権又ハ占有権ハ市カ公法上ノ権力関係ニ立チテ之ヲ有スルモノニ非スシテ純然タル私法関係ニ於テ之ヲ有シ私人カ土地ノ工作物ヲ所有シ及ヒ占有スルト同様ノ地位ニ立ツモノトス是レ当院カ市立小学校ノ校舎其他ノ設備ニ付キ判示セル所ナリ(大正五年六月一日第二民事部判決参照)……上告人等主張ノ如ク上告人等ニ斯ノ如キ水利権アリテ而シテ被上告市ノ水道工事カ一定ノ設計ニ適合スル施行ヲ為サレサリシ為メ上告人等ニ損害ヲ加ヘタルモノトセハ民法ノ不法行為ノ適用アルモノト謂フヘシ」。
被上告人(市)が設置した水道施設によって灌漑用水の水脈が枯渇し、田地を畑地とせざるをえなくなったことに関する損害の賠償を上告人ら(田地の所有者)が請求した事件である。原審(長崎控訴院)は水道事業が「公法上ノ支配ヲ受クヘキ行政行為」であることを理由として賠償請求を排斥したが、大審院はこれを破棄した。すなわち、営造物の設置・管理については行政権の発動(公権的行為)であるとしながら、本件の水道工事における設計の瑕疵によってもたらされた損害は土地の工作物の占有権に起因するものであり、純然たる私法関係に属するものだと判断して、民法を適用した。後の判決において、公共工事に関する判例として位置づけられている。
[16]1918(大正7)・10・25、築港工事瑕疵汽船沈没事件(民録24輯2062頁)
「築港事業ハ公共ノ利益ノ為メニ経営セラルル国家行政ノ作用ニシテ国家カ斯ル事業ノ計画ヲ定メ之ヲ遂行スル為メニ公ノ機関ヲ任設シ起業ノ必要上私人ニ対シ公用ノ徴収若クハ制限ヲ為シ又ハ一般公衆ニ対シ作業ニ要スル或場所ノ使用ヲ禁止若クハ制限スルカ如キ行為ハ公法上ノ権力関係ニ属スルコト勿論ナリト雖モ本訴ニ於テ主張スル損害ハ築港作業ノ工事ヲ施行スルニ付テノ不注意ニ因リテ生シタリト云フニ在リテ其工事ノ施行ハ一般ノ私人ニ対シ公法上ノ権力関係ニ於テ為スモノニ非スシテ一般ノ私人ト対等ノ地位ニ立チテ為スモノニ外ナラサレハ私法上ノ関係ニ属スルモノト謂ハサルヲ得ス蓋国家又ハ其他ノ公法人カ公共ノ利益ノ為メニ経営スル事業ト雖モ其事業施行ノ為メニ為ス行為中公ノ権力ノ行使ニシテ私人ニ対シ其権力ニ服従セシムル関係ニ於テ為スモノニ限リ公法上ノ関係ニ属シ然ラスシテ全ク私人ト対等ノ関係ニ於テ為ス行為ハ私法上ノ関係ニ属スルモノト謂フ可ク如上築港ノ作業ハ国家カ自ラ其機関ニ命シ私人ヲ使役シテ工事ヲ為サシムルト将タ其工事ヲ私人ニ請負ハシメテ行ハシムルトヲ問ハス其工事ヲ施設スル行為ハ官公ノ庁舎学校其他公共ノ営造物ヲ建造修築スルト均シク一般ノ私人ト全ク対等ノ地位ニ立チテ為スモノナルコトハ一私人カ其工作物ヲ築造スルト毫モ異ナルコトナク其工事ノ施設行為カ公共ノ目的ヲ達スルニ在ルカ為メニ一般ノ私人ヲシテ公ノ権力ニ服従セシムル関係ニ在ルモノト謂フコトヲ得サレハナリ」。
原審(札幌控訴院)は築港事業が「公法上ノ行為」に属することを理由として、民法による損害賠償請求を否定し、訴え却下の判断を下した。これに対して本判決は、築港事業のうち、公用の徴収または制限などの行為は「公法上ノ権力関係」であって民法を適用できないが、工事の施行は「私人ト全ク対等ノ地位」で行われるものであるから、本訴は民事訴訟に属すると判示し、本件を原院に差し戻した。事業全体から国の行為の性質を演繹するのではなく、各行為の根拠規定に基づいてその性質を認定する、という態度が定着していると理解することができよう。[15]判決とともに、公共工事に関する判例とみなされている。
[22]1924(大正13)・6・19、市下水道設備瑕疵事件(大民集3巻295号)
「市カ下水道法ノ規定ニ依リ内務大臣ノ認可ヲ受ケ為シタル下水道設備ハ市ノ営造物ニシテ其ノ設置管理カ行政行為ニ属スルコト論ヲ俟タスト雖同時ニ其ノ設備ニ対スル市ノ所有権又ハ占有権ハ純然タル私法関係ニ於テ之ヲ有シ私人カ土地ノ工作物ヲ所有シ又ハ占有スルト同様ノ地位ニ立ツモノナルコトハ曩ニ当院カ市ノ水道設備ニ付判示シタル所ニシテ(大正七年(オ)第一三五号大正七年六月二十九日第三民事部判決)従テ上告市カ本件喞筒ノ設置ニ付相当ノ注意ヲ為スコトヲ怠リタルカ為其ノ使用ニ因リ他人ニ損害ヲ生セシメタル場合ニ在リテハ私法ノ規定ニ従ヒ損害賠償ノ責任アルモノト云ハサルヘカラス」。
前掲[15]判決と同旨であり、これを判例として位置づけている。公の営造物の設置管理は「行政行為」に属するものとされている。
[23]1925(大正14)・12・11、水利組合樋管閉鎖事件(大民集4巻706頁)
「普通水利組合カ其ノ基本事務タル灌漑排水ニ関スル事業トシテ為ス行為ハ公権作用タル行政行為ニ属スルコト論ヲ俟タスト雖之ト同時ニ灌漑排水ノ設備ニ対スル所有権又ハ占有権ハ水利組合ニ於テ公法上ノ権力関係ニ立チテ之ヲ有スルモノニ非ス純然タル私法関係ニ於テ之ヲ有シ私人カ土地ノ工作物ヲ所有シ又ハ占有スルト同様ノ地位ニ立ツモノナリ(大正七年(オ)第百三十五号同年六月二十九日第三民事部判決参照)……上告人ニ水利権アリテ而シテ被上告組合カ上告人ノ水利権ニ対スル侵害ヲ防止スルニ足ルヘキ設計ニ適合セサル樋管設備ヲ為シ之カ為上告人ニ損害ヲ加ヘタルモノトセハ民法ノ不法行為ノ適用アルモノト云ハサルヘサラス[ママ]」。
原審(宮城控訴院)は樋管の閉鎖を「公権作用タル行政行為」に該当するものであり、それゆえ本件賠償請求を「公法上ノ請求権ヲ訴訟物ト為スモノ」と解釈して、訴えを却下した。これに対し、本判決は、一方で、前掲[14]判決に倣って、水利組合が事業としてなす行為を「公権作用タル行政行為ニ属スル」としながら、他方で、灌漑排水設備の所有権と他人の水利権との同質性という点に着目し、[15]判決を援用して、工作物の設計の瑕疵に起因する損害については公法人も民法の不法行為責任を負うべきものと判断した。判決の論理をたどると、本判決は、設計の瑕疵を媒介として工作物責任の点から公法人の賠償責任を導いているが、実質上は樋管の閉鎖という行為についての責任を認めたものといえる。
[25]1929(昭和4)・10・24、特許付与懈怠事件(法律新聞3073号)
「特許法ニ基ク特許ノ付与ハ公法上ノ関係タル行政行為タルト同時ニ特許ヲ付与スルニ当リ之ニ制限ヲ付シ若クハ全ク之ヲ付与セス又ハ一旦付与シタル特許ニ制限ヲ加ヘ若クハ之ヲ取消スカ如キモ亦公法上ノ関係タル行政行為ニ属スルコトハ毫モ疑ヲ容レサル所ナリトス国家カ行政行為ヲ為スニ当リ其ノ局ニ当ル官吏カ違法ニ他人ニ損害ヲ加ヘタル場合ニ於テ国家ト其ノ被害者トノ間ニ於ケル国家ノ賠償義務ノ問題ハ全ク民法ノ規定ニ依ルヘキモノニ非ス」。
特許法に基づく特許の付与は行政行為であって、それについての過失については国家は賠償責任を負わない、と判示した。本判決の「行政行為」は、講学上の用語としてのそれであって、前掲[6]判決から[23]判決までの用語法と比べてみれば、その概念が確定されてきたことがわかる。
[26]1930(昭和5)・5・24、海峡浚渫瑕疵事件(大審院裁判例4巻民事53頁)
「曩ニ当院判例(大正十三年(オ)第一七九号同年六月十九日判決)ニ於テ市ハ其ノ営造物タル下水道設備ニ対スル所有権又ハ占有権ニ付テハ私人カ土地ノ工作物ヲ所有シ又ハ占有スルト同様ノ地位ニ立チ其ノ設備ノ一部タル喞筒ノ設置ニ付市カ相当ノ注意ヲ怠リタル為其ノ使用ニ因リ他人ニ損害ヲ生セシメタル場合ニ在リテハ市ハ私法ノ規定ニ従ヒ損害賠償ノ責ニ任スヘキモノト為シタルト同様土地ノ工作物カ国ノ占有又ハ所有ニ属スル場合ニ於テ其ノ設置又ハ保存ニ瑕疵アルニ因リ他人ニ損害ヲ生セシメタルトキハ縦令其ノ工作物カ主トシテ公共ノ利益ノ為使用セラルル営造物ニ属スル場合ト雖国ハ其ノ占有又ハ所有者トシテ民法第七百十七条ニ依リ損害賠償ノ責ニ任スヘキモノト解スルヲ相当トス」。
前掲[10]判決の援用を否定し、前掲[22]判決を判例と位置づけた。本判決では、国が所有または占有する工作物の「設置又ハ保存」に瑕疵があったことによって損害を生じさせた場合に、国は民法の不法行為規定に基づいて損害賠償責任を負う、と判示した。第一に、このような工作物は公共の利益を目的とする営造物であっても民法が適用されると判断して、公共目的を判断基準から外したこと、第二に、設置行為を「公法上の関係」([12]判決)とか「行政行為」([22]判決)と位置づけることをやめて、民法の適用対象としたことが、注目される。
[28]1932(昭和7)・8・10、軍療養所用鑿井工事事件(法律新聞3453号15頁)
「地下水ノ利用ハ温泉ノ如キ場合ニアリテモ法令ニ別段ノ定メナキ限リ其ノ通過スル土地ノ所有者ニ於テ之ヲ利用スル権限ヲ有スルコト勿論ナレトモ其ノ利用ハ他人ノ有スル利用権ヲ侵害セサル程度ニ限ラル可キハ論ヲ俟タス若シ故意又ハ過失ニ因リ他人ノ利用権ヲ侵害シタルトキハ不法行為者トシテ其ノ責任ヲ免レス而シテ不法行為ノ状態ノ存続スルモノアルトキハ被害者ニ於テ其ノ不法行為ノ現状ノ除去ヲ請求シ得ル権利ヲ有スルヤ論ナシ此事タルヤ国家カ土地ヲ所有シ其ノ公物ノ設置若クハ保存ニ瑕疵アルカ為メ第三者ノ右利用権ヲ侵害シタル場合ナルト又ハ違法ナル行政作用ニ因リ第三者ノ権利ヲ侵害シタル場合ナルトニヨリ異ル所ナシ蓋シ不法行為ノ責任ハ其ノ行為者ノ何人ナルヤニヨリ之レヲ区別セサルヲ以テナリ従テ原審ノ説示スル所正当ニアラスト雖モ被上告人ノ本件請求ヲ許容シタル点ニ於テ結局正当ニ帰スルヲ以テ此ノ点ノ不当ハ未タ以テ原判決ヲ破毀スルノ理由ト為スニ足ラス論旨ハ理由ナシ」。
本判決は、軍療養所用の鑿井工事による温泉利用権の侵害は公物の設置・管理の瑕疵にあたると判断して、国(軍)の賠償責任を認めた。前掲[26]判決の延長上に位置づけることができるだろう。公物の「設置若クハ保存」行為が私法上の行為と同等のものと解されるようになってきた
。軍のための行為でも、公益目的から判断されることはなくなったといえる。なお本判決は「違法ナル行政作用ニ因リ第三者ノ権利ヲ侵害シタル場合」についても国は不法行為責任を負う、と述べているが、これはおそらく権力的行為に該当しない行政作用の場合を指したものと解されるべきであろう。いずれにしても、このような大審院の説示から、国や公共団体もかなり広い範囲の行政活動について当然に民法の不法行為責任を負うべきものだという意識が存在していることが理解できる。
[30]1933(昭和8)・4・28、大阪府消防自動車試運転轢殺事件(大民集12巻1025頁)
「大正八年七月勅令第三百五十号特設消防署規程第一条ハ消防ニ関スル事務ニ従事スヘキ職員ヲ定メ同第二条ハ消防署ヲ設置スヘキ府県並其ノ管轄区域等ヲ定メ又同第四条乃至第六条ハ知事警察部長其ノ他国家機関タル官吏カ消防職員ヲ指揮監督スヘキ旨ヲ定ムルニ徴スルモ右ノ規程ニ基キ設置セラレタル消防署カ孰レモ内務省ノ所管ニ属シ其ノ職務トスル消防事務カ総テ国家警察権ノ発動ニシテ内務行政ノ一タルコトハ洵ニ明白ナル事項ナルト同時ニ……平日消防用喞筒自動車ヲ修理整頓シテ之カ試運転ヲ為スカ如キモ亦消防署ノ任トスヘキ消防事務ノ一部ニ属スト做スヘキコト言ヲ竢タス従テ本件ニ於テ大阪府ニ設置セラレタル消防署ノ職員等カ原判示ノ如ク其ノ消防用喞筒自動車ヲ修繕シテ之カ試運転ヲ為セルハ即チ国家警察権ノ一作用トシテ該消防署ノ消防事務ヲ遂行セルモノニ外ナラスシテ自治団体タル大阪府所管ノ職務行為ト称スヘキニアラサルヤ勿論[ナリ]」。
本件の被告は大阪府である。一読すれば理解できるように、本判決は「国家警察権」の権力性を判断してはおらず、単に消防事務が府の事務ではなく国の事務に属するという理由で、大阪府の被告適格を否定しているにすぎない。近年の諸判決や国の準備書面等が本判決を「消防自動車の試運転中の轢殺事故についても権力的作用による損害であるとして、民法の適用を否定している(大審院昭和8年4月28日判決・民集12巻1025ページ)」
などと引用しているのは、まったくの誤解に基づくものであろう。裁判官も国の代理人も本判決の判決文を読まないままで引用しているものと推察される。
[31]1935(昭和10)・8・31、消防自動車試運転轢殺事件(法律新聞3886号7頁)
「府県ノ設置ニ係ル消防署ノ職員等カ其ノ消防喞筒自動車ヲ修繕シテ之カ試運転ヲ為スカ如キハ即チ消防事務ノ遂行ニ外ナラサルヲ以テ国家警察権ノ一作用ニ属スルモノナルコトハ既ニ当院ノ判例トスルトコロナリ然リ而シテ国家ノ警察権ハ公法上ノ権力ナルコト勿論ナルカ故ニ之カ行使ノ任ニ当ル職員ニ於テ其ノ行使ニ際シ故意又ハ過失ニ因リ他人ノ私法上ノ権利ヲ侵害シタリスルモ法令ニ特別ノ規定ナキ限リ国家ニ於テ之カ賠償ノ責ニ任スヘキモノニ非サルコト亦当院ノ判例トスルトコロニシテ今尚之ヲ変更スヘキ理由ヲ発見セス」。
[30]事件と同じ原告が国を被告として提起した損害賠償訴訟の上告審判決である。上告人側は、消防自動車の試運転は修繕行為の一部またはその延長であって国家の経済的行為にあたると主張したが、大審院はこれをしりぞけ、当該行為を「国家警察権ノ一作用」であり、それゆえ「公法上ノ権力」の行使にあたると認定して、法令に特別の規定がない限り国は賠償責任を負わない、と判示した。判決文を読む限り、本判決がこれまでのいかなる判決を「当院ノ判例」と位置づけたのかは不明である。消防自動車の試運転を権力的行為の例として挙げるのであれば、国や裁判所は[30]判決ではなく本判決を示すべきであろう。周知のように、本判決は強い批判を受けたが
、『大審院民事判例集』に掲載されなかったこともあって、後の判決においては判例として扱われていないものと思われる。
[38]1938(昭和13)・12・23、印鑑証明過失事件(大民集17巻24号2689頁)
「市ニ於ケル印鑑簿整備ノ事務即チ私人ノ印鑑簿ノ保管並印鑑証明ニ関スル事務ハ市制第二条ニ所謂「従来ノ慣例ニ依リ市ニ属スル事務」ニシテ市長カ印鑑証明願ヲ受理シ之カ印影ト印鑑簿ノ印影ト相違ナキコトヲ確カメ之ヲ証明スル行為ハ所謂公証行為ノ一種ニ属シ其ノ本質ハ公共団体ノ支配権ニ基ク作用即チ権力作用タル行政行為ニシテ専ラ市ノ公法的活動ノ範囲ニ属シ毫モ私人ト対等ノ関係ニ立ツ経済的活動ノ性質ヲ帯フルモノニアラサルヤ疑ヲ容レサルトコロトス而シテ該事務ハ一私人ニ対シ強制力ヲ及ホスモノニアラサルコト所論ノ如シト雖モ強制力ヲ伴フコトハ権力作用ノ必然的要素ニアラス公証行為ノ如キ単ニ人民ニ供与スルニ過キサル行為モ亦権力作用タリ得ヘキモノナルヲ以テ……毫モ権力作用タルノ本質ニ反スルモノニアラス」。
上告人は、印鑑証明は事実的認証だから権力作用ではないと主張したが、本判決は、印鑑証明が市制第2条の所轄事務であり、公証行為の一種であり、公共団体の支配権に基づく権力作用、「純然タル公法関係ニ立ツ行政行為」であるという理由から、証明の瑕疵によって損害が生じても民法の適用はなく、市に対して賠償請求できない、と判示した。「強制力ヲ伴フコトハ権力作用ノ必然的要素ニアラス」と判断した点も本判決の特徴であろう。必然的要素が何かといえば、それは根拠法規(市制2条)に基づく行政行為であることだと考えられる。「支配権ニ基ク作用」としている点は、後掲[43]判決に通じるものだといえる。
[41]1940(昭和15)・2・27、町長不正借入事件(大民集19巻441頁)
「借入金ヲ自己ニ領得スル為ニ為シタルモノナルカ故ニ固ヨリ真正ナル職務行為ニ非スト雖之ヲ町長ノ主観(留保セラレタル心裡自己ノ為ニスル意思)ヨリ切離シ客観的行為自体ヨリ之ヲ観レハ完全ニ町長ノ権限ニ属スル職務行為タルニ外ナラスカカル行為ニヨリ他人ニ損害ヲ加ヘタル場合ハ民法第四十四条ニ所謂職務ヲ行フニ付キ云々ト云フニ該当スルモノト解スルヲ相当トスヘク又右法条ハ私法人ニ関スルモノナルカ故ニ公法人ニ当然適用セラルルモノニ非サルハ勿論ナレトモ本件ノ如キ場合ニ之ヲ類推適用スヘキコト町収入役ノ不法行為ニ関シ繰返シ当院ノ判例トスル所ナリ」。
民法44条(法人の不法行為能力)の適用が争われた事件である。本判決は、町長の権限に属する職務行為について、「客観的行為自体ヨリ之ヲ観レハ完全ニ町長ノ権限ニ属スル職務行為タルニ外ナラスカカル行為ニヨリ他人ニ損害ヲ加ヘタル場合ハ民法第四十四条……ヲ類推適用スヘキコト町収入役ノ不法行為ニ関シ繰返シ当院ノ判例トスル所ナリ」と判示して、町の不法行為責任を認めた。第一の注目点は、公法人への民法の類推適用という方法を初めて示したことである。前掲[12]判決ではこの方法は必ずしも明瞭に採用されてはいなかったが、本判決でこの点が明示されたものと考えられる。同趣旨の判例として、大判1941(昭和16)・2・28(大民集20巻5号264頁)がある。第二の注目点は、権限規範の解釈に基づいて、町長の個人責任ではなく、その行為の責任が公共団体に帰属することを認定した点である。
[42]1940(昭和15)・3・15、町収入役横領事件(法律新聞4565号7頁)
「本件ト全ク同様町村ノ収入役カ金員ヲ自己ニ領得スル目的ヲ以テ町村長ノ代理名義ヲ冒用シ町村債名義ノ下ニ他人ヨリ金銭ヲ詐取シ之ニヨリ其ノ他人ニ損害ヲ蒙ラシメタル場合ニ付民法第四十四条ノ準用ニヨリ町村カ其ノ責ニ任スヘキモノナルコト当院ノ繰返シ判例トスル処ニシテ(昭和九年(オ)第一五四三号事件同年十一月三十日判決、昭和十一年(オ)第一三四九号事件同年十一月十一日判決、昭和十二年(オ)第七五二号事件同年十月五日判決)今尚之カ変更ノ要ヲ見ス」。
町収入役の横領に関する判例が示されている。前掲[41]判決とともに、国および公共団体の法人としての不法行為能力を確認した判決である。
[43]1941(昭和16)・2・27、東京市等滞納処分事件(大民集20巻118頁)
「凡ソ国家又ハ公共団体ノ行動ノ中統治権ニ基ク権力的行動ニツキテハ私法タル民法ノ規定ヲ適用スベキニアラザルハ言ヲ俟タザルトコロナルヲ以テ、官吏又ハ公吏ガ国家又ハ公共団体ノ機関トシテ職務ヲ執行スルニ当リ不法ニ私人ノ権利ヲ侵害シ之ニ損害ヲ蒙ラシメタル場合ニ於テ、ソノ職務行為ガ統治権ニ基ク権力行動ニ属スルモノナルトキハ、国家又ハ公共団体トシテハ被害者ニ対シ民法不法行為上ノ責任ヲ負フコトナキモノト解セザルベカラズ。……然レドモ町税ノ滞納処分ハ公共団体タル町ガ国家ヨリ付与セラレタル統治権ニ基ク権力行動ナルヲ以テ、之ニ関シテハ民法ヲ適用スベキ限リニアラザレバ、本件滞納処分ヲ担当セル吏員タリシ上告人加藤ニ不法行為上ノ責任アレバトテ、公共団体タル千住町ニハ不法行為上ノ責任ヲ生ズルコトナク、従ツテ同町ノ地位ヲ承継シタル上告人東京市ニモ何等ノ責務ナキモノト謂ハザルベカラズ。原審ガ町税滞納処分ヲ目シテ恰モ民法第七百十五条ニ所謂「事業」ニ該当スルモノト解シタルガ如キハ失当ナリ。従ツテ又上告人横山ガ同条第二項ニ基ク監督者ノ責任ヲ負フベキ理由モ存スルコトナシ」。
前掲[36]判決および[40]判決の対象となった事件の再上告審判決である。原審(差戻審)は、本件滞納処分が無効であるとして滞納処分担当吏員には個人賠償責任を、町長には民法715条2項の監督者責任を、同町を合併した東京市には同条1項の使用者責任を認定し、三者に賠償責任ありと判示した。これに対して本判決は、「統治権ニ基ク権力的行動ニツキテハ私法タル民法ノ規定ヲ適用スベキニアラザルハ言ヲ俟タザルトコロ」と述べて、町税の滞納処分は統治権に基づく権力的行為(町が国より付与された統治権)だと判断し、町長と東京市の責任を否定した。本判決の第一の特徴は、「統治権ニ基ク権力的行動」という概念を用いて国の賠償責任を否定したことである。原審のように徴税行為を民法715条の「事業」とみなすことを否定し、主権的な行為に属することを強調して、国を免責した。第二の特徴は、詳細な事実認定を行ったことであろう。被害事実と当該行為との関連性、官吏の個人責任との関係、などについての判断を示したことも重要である。第三に、原審が滞納処分を無効と判断したのに対して上告人ら(東京市ほか)は「行政処分の効力についての判断は司法裁判所の権限を超越する」旨を主張したが、この点に関連して、司法裁判所は行政行為を無効とする判断を下すことができる、と判示したことも本判決の特徴である。「差押ガ当然無効ナル以上ソノ然ラザルコトヲ前提トシテ原審ノ判断ヲ目シテ司法裁判所ノ権限ヲ超越シタルモノト論難スル[上告人ノ]論旨ハ理由ナシ」と判示した。
[46]1943(昭和18)・9・30、滞納処分取消による損害の賠償請求事件(大審院判決全集10輯5号2頁)
「官吏又ハ公吏カ国家又ハ公共団体ノ機関トシテ職務ヲ執行スルニ当リ不法ニ私人ノ権利ヲ侵害シ之ニ損害ヲ蒙ラシメタル場合ニ於テ其ノ職務行為カ統治権ニ基ク権力行動ニ属スルモノナルトキハ国家又ハ公共団体トシテハ被害者ニ対シ民法不法行為上ノ責任ヲ負フコトナキモノト解セサルヘカラサルコト当院ノ判例トスル所ニシテ(昭和十五年(オ)第六二六号同十六年二月二十七日判決)之ヲ変更スルノ理由ナク又其必要ナキモノト認ム」「而シテ右ノ自動車ノ差押公売処分ノ取消等ハ何レモ国税徴収法ニ係ル滞納処分トシテ行ハレタルモノト解スヘキモノニシテ旧東京市ニ採リテハ[ママ]統治権ニ基ク権力行動ニ属スルモノナルコト明カナルヲ以テ原審カ右ニ因リ上告人カ該自動車ノ所有権ヲ侵害セラレ財産上ノ損害ヲ蒙リタリトスルモ右処分行為ノ担当者ノ責任ハ別問題トシテ旧東京市ハ公共団体トシテ不法行為上ノ責任ナキモノト判定シタルハ正当ナリトス」。
「国税徴収法ニ係ル滞納処分」であることを理由として国を免責した。法的根拠から権力的行為であることを導くという解釈方法が定着しているといえるだろう。前掲[43]判決を判例として引用している。また、権力的行為を言い表す用語が「統治権ニ基ク権力行動」に定まりつつあったと考えられる。
(3)「判例」の内容
以上のところから、次の諸点を大審院の「判例」とみなすことができよう。
第一に、損害賠償事件については、たとえ権力的行為に起因する場合であっても司法裁判所がこれを管轄する、ということである。この点は[36]判決をはじめとして、大審院判決の全体から読みとることができるであろう
。司法裁判所が行政行為の効力について審理することができ、無効の判断を下すことができることについては、[9]・[18]・[37]判決が暗黙裡に判示していたが、[43]判決が明瞭に確認した。
第二に、国の使用者責任(民法715条)や不法行為責任(同44条)を認めている点である。そして、この責任が成立するのは、純粋な私法上の関係にとどまらず、従前は「公法関係」とみられていた領域にまで広がっていたことがわかる。たとえば、[12]判決では学校設備の占有権を「私法上の占有権」としていたが、[41]判決では民法の類推適用という方法を明示的に用いて民法の適用領域を広げた。
第三に、大審院がいくつかの解釈方法の変更を通して、権力的行為の範囲を限定してきたこと、逆にいえば国の行為に対する民法の適用範囲を広げてきたことも理解できたであろう。すなわち、(a)大審院は、権力的行為を統治権(主権ないし支配権)に由来する権限の行使([43]・[46]判決)および講学上の行政行為ないし行政処分([25]・[38]・[45]判決)に限定するようになった。国の免責される範囲が国賠法1条1項にいう「公権力の行使」よりもかなり狭いことは明らかだろう。(b)判断基準を行為の目的から法的根拠(とくに権限規範)へと移すことによって「権力」性の認定を厳格に審査するようになったことである。たとえば、公共事業については[12]判決が、軍事関連事業については[28]判決が、水利組合については[23]判決が画期をなすものとみられる。職権濫用に該当するか否かについても、権限規範に基づいて判断されていた。(c)全体としての法関係が「公法関係」だとされる場合でも損害の原因となった個別的法関係を析出し、これが対等当事者間の関係と同質だとみなせる場合には民法を適用するという方法を採用したことである。この点は[12]判決以降のすべての判決において踏襲されている。(d)工作物の場合だけでなく官吏等の行為に起因する損害についても国の賠償責任を認めるようになってきたことも確認できる。[12]・[15]・[16]判決から[23]判決を経て[26」・[28]判決へというのが、その流れである。
第四に、いずれの事件においても国・公共団体の行為態様および被害事実等に関する事実認定は省略されていない(とくに[36]判決参照)。近年、いくつかの事案において国家無答責の法理によれば請求権が成り立たないとして事実認定が省略されているが、これらはまさしく「従前の例」を無視した判例違反の判断に他ならない。
第五に、大審院の自己認識によれば、「国の権力的行為に係る損害ついて国は賠償責任を負わない」という意味の国の免責法理が「従前の例」と位置づけることのできる程度にまで概念的に確立されたのは[43]判決以降である。この点は、[46]判決によって明らかである。同判決は、このような法理が「当院ノ判例トスル所」としたうえで、その変更可能性を認めながらも「其ノ必要ナキモノト認ム」と、この法理を判例法として維持すべきものと判断している。また、この法理の適用対象とされるべき行為が「統治権ニ基ク権力行動」と定まった用語で表現されるようになったことも、この法理の「確立」を示す指標だといえよう。
ここから次のことを確認できる。
[X]大審院自身は、国家無答責の法理について、判例法説を採用している。
[XI]判例の内容は、(i)国や公共団体の権力的行為に関する損害賠償事件も司法裁判所の管轄に属する、(ii)非権力的な関係においては国の不法行為責任(民法715条、同44条等の適用)が認められる、(iii)国が免責される活動は「統治権ニ基ク権力行動」ないし「行政行為」に限定され、しかもこれに該当するか否かは実定法規定を基準として審査される、(iv)国家無答責の法理を適用する場合であっても事実認定は不可欠である、ということである。
(4)最三小判1950・4・11は判例といえるか
警察官の防空法に基づく家屋破壊の不法を理由とする国家賠償請求事件に関し、前掲の最判1950(昭和25)・4・11は「本件家屋の破壊行為が、国の私人と同様の関係に立つ経済的活動の性質を帯びるものでないことは言うまでもない。而して公権力の行使に関しては、当然には民法の適用のないこと原判決の説明するとおりであって、旧憲法下においては、一般に国の賠償責任を認めた法律はなかったのであるから、本件破壊行為について国が賠償責任を負う理由はない」と判示した。このような判断が戦前の判例をふまえていないことは、もはや明らかであろう。すなわち、まず、家屋の破壊行為の法的性質(権力性)が根拠法規に基づいて審査されていない点、次に、「公権力の行使に関しては、当然には民法の適用のないこと」はその通りだとしても、国賠法1条にいう「公権力の行使」にあたる行為のすべてが「民法の適用のないこと」とされていたわけではなく、判例ではこのうちの権力的行為が「民法の適用のないこと」とされていたにすぎない点、さらに、「経済的活動」以外の国の行為も民法の適用対象とされていたわけであり、「経済的活動の性質を帯びるものでないこと」(事業活動)のゆえに「民法の適用のないこと」となるわけではない点(いうまでもないが、経済的活動だけでなく非権力的公行政についても国の賠償責任を認めるのが判例であった)
、などである。したがって、「大審院も公務員の違法な公権力の行使に関して、常に国に賠償責任がないことを判示して来た」(同最判)というのは、明らかに誤った一般化であり、恣意的な論断だといわざるをえない。またそれゆえ、近年の判決において、大審院が「公権力の行使」全般について国の賠償責任を否定していた証明としてこの最判を示すものが多いが、これは完全な誤用である。
ここから次のことを確認できる。
[XII]最三小判1950・4・11が先例としての意義を有するのは、せいぜい大判1941・2・27あたりで確立したと考えられる判例法理が「従前の例」に含まれるということ、にすぎない。
(5)学説の状況
補論として、この時期の学説の状況に触れておく。
美濃部達吉は、国家無答責の法理にあたる学説を次のように説明した。
「国家は一面に於いて統治団体であり、而して統治権の作用は私人の行為とは性質を異にし民法の規定の適用を受くるものではないから、統治権の作用に付いては、仮令それに依り違法に他人の権利を侵害することが有つても、それは民法の意義に於いての不法行為に該当するものではなく、国家はそれに付き損害賠償の責に任ずるものではない。啻に行政行為や裁判判決のやうな公法的行為が公定力を以つて人民を拘束するばかりではなく、事実上の行動に付いても、それが統治権に基づく強制権の作用である限り、時として官吏が個人として賠償責任を負ふことは有つても、国家自身は民法の適用を受くるものではなく、随つて国家に対して損害賠償を請求し得べきものではない。」
「統治権の作用」という説明は、1940年頃の大審院判決で用いられるようになっていた([43]判決など)。当時頻繁に引用されていた美濃部説の影響と考えてよいと思われる。他方、「事実上の行動」についても国の賠償責任が免責されるとしている点は、大審院判例とは異なるといえよう。判例によれば、事実上の強制力は権力的行為のメルクマールとはならないのであって
、権限の根拠となる規範に照らして、その範囲内の行為であってはじめて免責される、ということになると思われる。
佐々木惣一は、公法と私法に関する「生活説」に基づいて、国の損害賠償責任について次のように説明した。
「官吏ノ行為ガ公法ノ適用ヲ受クベキ国家ノ行動トシテ為サレタル場合ニハ、国家ト第三者トノ関係ハ公法関係ナリ。従テ此ノ場合ニ於ル国家ノ賠償義務ノ問題ハ全テ公法上ノ法理ニ依ル。民法ノ規定ニ依ルコトヲ得ズ。是レ右ノ場合ニ於ル官吏其ノ人ノ賠償ノ問題ガ公法上ノ法理ニ依ルト同一ノ理ニシテ、共ニ公法上ノ賠償義務タルモノナリ。右ノ場合ニ於ケル国家ノ賠償義務ニ就テハ一般的ニ之ヲ認メタル規定ナク、且実定法ナクシテ当然ニ認ムルヲ得ルモノニ非ズ。故ニ原則トシテ国家ノ賠償義務ナシト云フノ外ナシ」
。
教科書という性格によるものであろうが、国の賠償責任を免責する「公法上ノ法理」が存在する、と述べているに過ぎない。「公法関係」のすべてが「賠償義務ナシト云フノ外ナシ」といいうるわけではないのだから、「公法関係」内部の分析が必要だといえよう。
この点で、田中二郎の研究は優れたものであった。彼は戦前における判例の流れを総括して次のように述べている。
「不法行為に基づく損害賠償の問題については、権力的作用(公権力の発動たる作用)と非権力的作用とを区別し、後者に基づく損害については、判例により、漸次、私法の不法行為法の適用範囲を拡大し、国又は公共団体の責任を肯定する例が多くなって来ているが、前者に基づく損害については、特別の規定のない限り、私法の不法行為法の規定は適用されないとして、一貫して国又は公共団体の賠償責任を否定し、ただ現実の行為者たる官公吏の責任について、一方、公法上の職務行為に基づく損害については、仮令故意過失に基づく場合に於いても、特別の規定のない限り、一般に、賠償責任を否定すると共に、他方職務外の行為については勿論、形式上職務行為に属するものであっても、職権を濫用し、故意に他人の私権を侵害する場合には、損害の賠償責任を肯定する傾向に在ったのである」
。
判例が国の非権力的(行政)作用について民法の適用範囲を拡大してきたことは先にみたとおりである。他方で、戦前においても、国の賠償責任を認めるべきだとする主張が徐々に広がりつつあった。渡辺宗太郎、三宅正男などである
。いずれにせよ、「統治権の作用」とか「公法関係」と呼ばれる行為や法関係については国は賠償責任を負わないという考え方が通説として存在していた、ということは可能であろうが、それがいかなる範囲で成立するのかという問題に関する研究はわずかであり、学説において確たる共通認識ができあがっていたわけでもない、ということもまた確かであろう。
ここから次のことを確認できる。
[XIII]有力説であり判例に対しても影響力を持ったと考えられる美濃部説は国の免責の範囲を次第に限定し、免責されるべき活動を「統治権の作用」と定式化した。
[XIV]学説は公法私法二分論の教義によって国家無答責の考え方を根拠づけていたのであり、実定法説をとっていなかった。
[XV]「統治権の作用」とか「公法関係」と呼ばれる行為や法関係について国は賠償責任を負わないという考え方が通説として存在していたといいうるが、それがいかなる範囲で成立するのかという問題に関する研究はわずかであり、また学説において確固たる共通認識ができあがっていたわけでもない。
(6)まとめ
これまでに得られた小結論を提示する。
[X]大審院自身は、国家無答責の法理について、判例法説を採用している。
[XI]判例の内容は、(i)国や公共団体の権力的行為に関する損害賠償事件も司法裁判所の管轄に属する、(ii)非権力的な関係においては国の不法行為責任(民法715条、同44条等の適用)が認められる、(iii)国が免責される活動は「統治権ニ基ク権力行動」ないし「行政行為」に限定され、しかもこれに該当するか否かは実定法規定を基準として審査される、(iv)国家無答責の法理を適用する場合であっても事実認定は不可欠である、ということである。
[XII]最三小判1950・4・11が先例としての意義を有するのは、せいぜい大判1941・2・27あたりで確立したと考えられる判例法理が「従前の例」に含まれるということ、にすぎない。
[XIII]有力説であり判例に対しても影響力を持ったと考えられる美濃部説は国の免責の範囲を次第に限定し、免責されるべき活動を「統治権の作用」と定式化した。
[XIV]学説は公法私法二分論の教義によって国家無答責の考え方を根拠づけていたのであり、実定法説をとっていなかった。
[XV]「統治権の作用」とか「公法関係」と呼ばれる行為や法関係について国は賠償責任を負わないという考え方が通説として存在していたといいうるが、それがいかなる範囲で成立するのかという問題に関する研究はわずかであり、また学説において確固たる共通認識ができあがっていたわけでもない。
ここで、以上の小結論がもつ意味を確かめてみる。
第一に、「従前の例」の実例とみなされるべき戦前の実務においては判例法説が採用され、学説もこれと軌を一にしていた(上記[X][XIV])。第二に、この法理は、裁判管轄(司法裁判所と行政裁判所の権限配分)、行政権と私人との間の法関係の性質、国と官吏(被用者)との間の法関係の性質、行政活動の法的性質の審査方法、損失補償制度との関連など多様な論点の組み合わせによって成り立っている。このため裁判実務での使用に耐えられるだけの「法理」は一朝一夕には形成されなかったのであって、相応の時間を要したのである(上記[XI][XIII][XV])。第三に、このような点をふまえていない最三小判1950・4・11は、まったく無内容であるから判例とはいえない(上記[XII])。
以上から次の結論が得られる。
[XVI]国家無答責の法理は判例法理である。
[XVII]最三小判1950・4・11を国家無答責の法理に関する判例として援用することはできない。
4.細菌戦と国の賠償責任
(1)細菌戦における国の行為
国家無答責の法理の具体的な適用場面を検討するために、第二次世界大戦中に日本軍が中国で行ったとされる細菌戦を取り上げてみよう。
前掲の東京地判2002・8・27が認定した同法理の適用対象行為は、次の通りである。
「 ア ……
(ア) 731部隊の前身は,昭和11年(1936年)に編成された関東軍防疫部であり,これが昭和15年(1940年)に関東軍防疫給水部に改編され,やがて731部隊の名で呼ばれるようになった。同部隊は,昭和13年(1938年)ころ以降中国東北部のハルビン郊外の平房に広大な施設を建設してここに本部を置き,最盛期には他に支部を有していた。同部隊の主たる目的は,細菌兵器の研究,開発,製造であり,これらは平房の本部で行われていた。また,中国各地から抗日運動の関係者等が731部隊に送り込まれ,同部隊の細菌兵器の研究,開発の過程においてこれらの人々に各種の人体実験を行った。
中国各地には他にも同様な部隊が置かれたが,その中で有力な部隊が南京に置かれていた中支那防疫給水部(「栄1644部隊」又は「1644部隊」)である。<証拠略>
(イ) 1940年(昭和15年)から1942年(昭和17年)にかけて,731部隊や1644部隊等によって,次のa,f,g,hのとおり中国各地に対し細菌兵器の実戦使用(細菌戦)が行われた。
a 衢県(衢州)
(a) 1940年(昭和15年)10月4日午前,日本軍機が衢県上空に飛来し,小麦,大豆,粟,ふすま,布きれ,綿花などとともにペスト感染ノミ(小袋に入ったものもあった。)を空中から撒布した。当日午後には,県知事の指示で,住民を総動員して散乱している投下物の収集・焼却が行われた。
……
f 寧波
(a) 1940年(昭和15年)10月下旬,日本軍機が寧波上空に飛来し,中心部の開明街一帯にペスト感染ノミ(後にインドネズミノミと鑑定された。)の混入した麦粒を投下した。
……
g 常徳
(a) 1941年(昭和16年)11月4日,731部隊の日本軍機が常徳上空に飛来し,ペスト感染ノミと綿,穀物等を投下し,これが県城中心部に落下した。
……
h 江山
(a) 日本軍は,1942年(昭和17年)6月10日ころから江山県城を占領し,約2か月後に撤退したが,この撤退の際,コレラ菌を使用した細菌戦を実行した。その方法は,主として,井戸に直接入れる,食物(餅状のもの)に付着させる,果物に注射するなどというものであった。
……
(ウ) これらの細菌兵器の実戦使用は,日本軍の戦闘行為の一環として行われたもので,陸軍中央の指令により行われた。
……
イ 次に,原告らの主張する被害についてみてみる。
原告らは,旧日本軍の本件細菌戦により別紙3の「原告らの主張」の別紙「原告及び死亡親族一覧表」記載のとおりの被害(ペスト又はコレラへの罹患やこれを原因とする死亡)を受けたと主張し,立証としてこれに符合する陳述書を甲号証として提出し<証拠略>,一部の原告ら(<略>)が本人尋問においてその旨を供述している。……」
(2)細菌の散布行為は「統治権ニ基ク権力行動」に該当するか
さて、上記の行為は法的にはどのように評価されるであろうか。
これらの行為が、実行当時いずれの国の法令からみても犯罪行為・違法行為であったこと、そして国際法違反の行為であったことは疑いない。それゆえ、一方では、この種の行為はもはや職務とは無関係の公務員個人の行為であるので、その違法性は国家に帰属しない、という見解が成り立ちうるようにみえる。つまり、行為実行者個人の賠償責任の問題にはなっても、国家の賠償責任は生じないという見解である。しかし、このような行為が一個の行政組織として組織的に、故意に、しかも国家機関の外形を用いて行われた場合には、組織体としての国家の責任が問われざるをえないであろう。
他方で、この種の行為が国家の行為だとみなされるならば、それは戦争行為の一環として行われたものであるので、「統治権ニ基ク権力行動」に該当し、それゆえ国家は国家無答責の法理に基づいて損害賠償責任を免除される、という見解が成り立ちうるようにみえる。以下、この見解を検討してみよう。
前掲の東京地判2002・8・27は、「本件細菌戦は、旧日本軍がその存在目的そのものである戦闘行為として行ったものであるというのであるから、その行為は公権力の行使(国の統治権に基づく優越的な意思の発動としての強制的・命令的行為)そのものであり、当時民法の適用対象となっていた非権力的作用に分類されるということはできない」(24頁)と判断している。しかし、大審院判例を参照すると、本件のような細菌の散布行為が「国の統治権に基づく優越的な意思の発動としての強制的・命令的行為」とみなせるかどうかは疑わしい。
まず、日本軍の行為のすべてが「国の統治権に基づく優越的な意思の発動としての強制的・命令的行為」になるわけではない。この点は、大審院の[28]判決が示すように、軍隊の行為も国家賠償の対象となる。なお、[10]判決のように、火薬の製造について「所謂軍事的行動ノ一部ニ属スルモノト認ムヘク……」という理由から軍事的行動について賠償責任を免責したような判断もみられる。しかし第一に、この判決は、大審院自身によって判例としての位置づけが否定されている(たとえば[26]判決参照)。第二に、そもそも火薬製造所における火薬の製造という行為自体は適法な行為であって、細菌の散布行為のような犯罪行為に類推できるものではない。これ以上の例証は行わないが、軍の行為についても賠償責任が成り立つ場合がありうることは明らかである。
次に、行為の目的が戦闘・戦争であったとしても、そのことをもって「統治権に基づく行為」とみなす解釈を採らないのが大審院判例の立場である。大審院判例によれば、法令に基づいて当該行為が「優越的な意思の発動としての行為」とみなせるか否かが国の賠償責任の成否の基準なのである(前述の小結論[XI](iii)参照)。本件において、このような法令を見出すことはできないし、また東京地判2002・8・27はこの点の検討をまったく行っていない。仮に東京地判2002・8・27が大審院判例に即したものであり「従前の例」に合致するものだと主張するならば、東京地判2002・8・27は、「公権力の行使はそれぞれの根拠となる我が国の法律に基づいて行われるものである」(20頁)という自分自身の言明に即して、本件のような人体実験および細菌の散布行為が日本のいかなる法律に基づいて行われたのかを論証しなければならなかったはずである。このような論証は本判決中に存在していない。したがって、細菌の散布行為の目的が戦闘・戦争ということにあったとしても、そのことを理由として賠償責任が免除されるわけではない。
そして、行為の態様が強制的なものであったとしても、それゆえに「統治権に基づく行為」に該当するわけではない。大審院の[38]判決において明瞭に示されているように、「強制力ヲ伴フコトハ権力作用ノ必然的要素ニアラス」つまり事実上の強制力があることは統治権とは無関係なのである。このことは、公務員の暴力的な行為と権力的な行為とがまったく異なる意味であることさえ理解できれば、容易に納得できよう。大審院判例の基準によれば、「統治権に基づく行為」に該当するか否か([38]判決の文言に即していえば権力作用に該当するか否か)は、あくまでも法令によって権限が付与されている行為だったのか否かで判断されるのである(法令で付与された権限を行使した結果が違法であった場合に、国は免責されるのである)。このような基準に照らしてみると、細菌の散布行為は、法令によって付与された権限の行使ということはできず、むしろ裸の暴力に他ならないのであって、とうてい「統治権に基づく行為」に該当するものということはできない。
さらに、この種の国際法違反の行為(細菌の散布行為)について、当時の政府や日本軍がこれを「統治権に基づく行為」と主張することはあり得なかったはずである。つまり、現在の時点おいても当時においても、このような集団的犯罪行為を「統治権に基づく行為」と位置づけることはできないのであって、このことは賠償規定の有無とはまったく無関係なのである。したがって、戦後の裁判所が勝手にこの種の行為を「統治権に基づく行為」だと認定するのは、恣意的な判断といわざるをえず、日本という国家の名誉のためにもこのような認定はなされるべきではない。
なお、東京地判2002・8・27は「原告らの主張は、軍隊を土地の工作物(民法717条)や小学校の校庭に設置された遊具と同視するものであって、採用することができない」としているが、これも、「従前の例」に基づかない判断だといえる。大審院は動産に起因する国の損害責任を認めており(前掲[15.5]判決)、また工作物の設置・管理に係る行為についても損害責任を認めている(前掲[23]判決など)のであるから、軍隊の工作物たる兵器類に起因する被害についての賠償責任は、むしろ国の責任の範囲内に入りうると解するのが大審院判例の素直な理解であろう。
以上から次のことを確認できる。
[XVIII]細菌の散布行為は「統治権ニ基ク権力行動」に該当しない。東京地判2002・8・27は、この点も含めて、「従前の例」に基づかずに自己固有の判断を下しているにもかかわらず、「従前の例」に基づいているかのように偽装している点で違法であり、取り消しを免れない。
国家無答責の法理は判例法理なのだから、今日の憲法体系の下では変更されるべきだ。仮に「従前の例」 としてこの法理を適用したとしても、大審院判例を基準にすれば、細菌戦についてはこの法理によって国が免責されることはありえず、民法に基づいて国は賠償責任を負うものと考えられる。
(3)統治権の及ばない地域での外国人に対する行為は国家無答責の法理の適用対象となるか
東京地判2002・8・27は「日本人も外国人も等しく国家無答責の法理の適用を受けていたものと考えられる」としているが、これはこの法理を誤解したものである。
たしかに、日本の主権下にある外国人について「国家無答責の法理の適用を受けていたもの」ということは可能であるが、日本の主権下にない外国人について、このようにいうことはできない。つまり、外国人一般が問題なのではなく、日本の主権下にある外国人であるか否かが問題なのである。そして、日本の主権下にない外国人と日本軍との間に公法上の関係が存在していなかったことは明白であるから、国家無答責の法理を適用する余地はない。
結局、「国家の統治権の及ばない外国人との関係、国家の法秩序の及ばない外国の地には、国家無答責は適用されない」(141頁)という原告の主張は正当であって、東京地判2002・8・27は、問題の設定を誤解して、誤った判断に至っているのである。
いずれにしても、この論点もここでは詳論できないので、後日あらためて述べることにしたい。
|