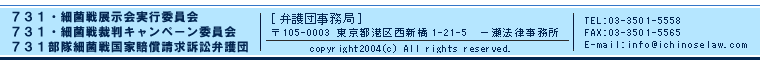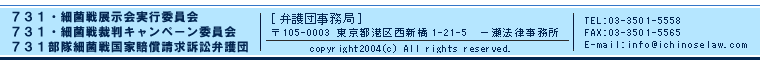|
�Ӓ�ӌ���
���Ӓ�ӌ����̃��j���[�ɖ߂�
�Ӂ@���@��
�R�w�@��w�������@�\�@��
�P�@�͂��߂�
�Q�@�n�[�O���3���̉��߁\��T�i�l�������ʂ̎咣�𒆐S��
�i�P�j�u���Ԃɂ̂݁v����K�p����Ƃ��������2���̎�|
�i�Q�j�����ɂ�����Z�����ւ̋����̎x�����K�肵�������52��3���́A�Z�������x�����������߂鍑�ۖ@��̎�i��݂��Ă��Ȃ��Ƃ̎咣�ɂ���
�i�R�j�����3���̋N�������̍��ۖ@���_�ɂ���
�i�S�j�����3���̉��߂Ɋւ���ԏ\�����ۈψ���̌����ɂ���
�R�@���ېl���@�ᔽ�̔�Q�҂̑��Q����������
�i�P�j���ېl���@�ɂ����鎄�����d�̌����̊m��
�i�Q�j�n�[�O���3���̈Ӌ`
�i�R�j�����̓K�p�\���ۓI��@�ƍ����I��@
�i�S�j�ԋ���ƌl�������̊W
�i�T�j���ېl���@�y�ѐl���@�ᔽ�̔�Q�҂��~�ς��錠��
�S�@����
�P�@�͂��߂�
�@�{���́A�����{�R������E��풆�ɒ����嗤�ɂ����ē����̍��ۖ@�Ɉᔽ����ە����p�����퓬�s�ׁi�ې�j���s���A�܂���������Ɋւ���~�ϑ[�u�����Ȃ��������Ƃɂ��āA��Q�҂���T�i�l�炪���Q�����𐿋����Ă��鎖�Ăł���B�T�i�l��͐����̍����Ƃ��āA���{���@�̕s�@�s�K��A���Ɣ����@���̂ق��A1907�N�̗���̖@�K����Ɋւ�����i�n�[�O������A�ȉ��A�n�[�O���Ƃ���j3���Ȃ����������e�Ƃ��銵�K���ۖ@�����̒��̈�Ƃ��Ă���B���R��2002�i����14�j�N8��27�������n�ٔ����́A�����{�R�������e�n�ōs�����ƔF�肳���ە���̎���g�p�i�{���ې�j��1925�N�̃W���l�[�u�E�K�X�c�菑�i�u�������K�X�A�Ő��K�X���͂����ɗނ���K�X�y�эۊw�I��i�̐푈�ɂ�����g�p�̋֎~�Ɋւ���c�菑�v�j�ɂ����u�ۊw�I�푈��i�̎g�p�v�ɂ����邱�Ƃ͖��炩�ł���Ƃ�����ŁA�W���l�[�u�E�K�X�c�菑�̂悤�ȏ��Ȃ����������Đ������銵�K���ۖ@�ɂ��Q�G��i�̋֎~���n�[�O����K���i�ȉ��A�n�[�O�K���j23��1���ɂ����u���ʃm��ȃe�胁�^���֎~�v�ɊY�����A����č��ɂ̓n�[�O���3���̋K�����e�Ƃ��銵�K���ۖ@�ɂ�鍑�ƐӔC�������Ă����Ƃ������i38�`39�Łj�A���Q���������ɂ��ẮA�n�[�O���3���͌l�̉��Q���Ƃɑ��鑹�Q������������n�݂��邱�Ƃ��Ӑ}���Ă����Ƃ͂����Ȃ����Ɓi16�Łj�A�n�[�O�K��52�A53�����l�����荑�ɑ����ډ��炩�̐����������邱�Ƃ�F�߂����̂Ƃ͉������Ȃ����Ɓi17�Łj�A�{���ې�ɂ����鍑�̍��ƐӔC�͓��������������ɂ�蒆���Ƃ̍��ƊԂŏ�������Ă��邱�Ɓi39�`40�Łj�A���Ɣ����@�{�s�O�̍s�ׂɂ��Ă͍��Ɩ����ӂ̖@�����m�����Ă������Ɓi43�Łj�����炱���ނ��Ă���B�{�ӌ����́A�{���ő����Ă��鑈�_�̂����A���ۖ@�̉��߁E�K�p�ɂ�����鎖���ɂ��āA���ۖ@�w�҂Ƃ��Ă̌�����\���q�ׂ���̂ł���B
�@�ȉ��ł́A�܂��A�u��T�i�l�������ʁi2�j�v���ō�����o���Ă���咣�ɂ��A�������������`�ŁA�n�[�O���3���̉��߂ɂ��ďq�ׁA����܂��A�{���ې�̔�Q�҂����Q�����𐿋����錠���ɂ��čl�@���邱�ƂƂ���B
�Q�@�n�[�O���3���̉��߁\��T�i�l�������ʂ̎咣�𒆐S��
�@�n�[�O���́A�����̃n�[�O�K���ɂ����Đ�̍��̋`�����ɂ��ċK�肵�A�R���ɂ����Ĉȉ��̂悤�ɒ�߂�B
La partie belligerante qui violerait les dispositions du
Reglements sera tenue a indemnite s'il y a lieu. Elle sera
responsable de tout actes commis par les personnes faisant
partie de la force armee.�i�����A����j
�@A belligerent Party which violates the provisions of the
said Regulations shall, if the case demands, be liable to
compensation. It shall be responsible for all acts committed
by persons forming part of its armed forces.
�@�u�O�L�K���m�����j�ᔽ�V�^����퓖���҃n�A���Q�A���g�L�n��V�J�����m�� �����t�w�L���m�g�X���퓖���҃n����m�R�����g���X���l���m��m
�s�׃j�t�ӔC�����t��
�@�����ł́A��T�i�l�E�����u��T�i�l�������ʁi2�j�v�ɂ����āu��1�@�w�[�O������3���̕������߂ɂ��āv�A�y�сu��Q�@�w�[�O������R���̋N���ߒ��ɂ��āv�Ƃ��ēW�J���Ă���咣�ɂ��āA�K�v�ɉ����đ��R�����̔����ɂ����y���Ȃ���A���ꂼ�ꌟ������B
�i�P�j�u���Ԃɂ̂݁v����K�p����Ƃ����n�[�O���2���̎�|
�@��T�i�l�́A�n�[�O���Q�����A�u�{���m�K��n�D�D�D���ԃj�m�~�V���K�p�X�v�ƋK�肵�Ă���_���A�����R�������ƊԂ̍��ƐӔC���߂����̂ł����Čl�̑��Q�������������߂����̂ł͂Ȃ����Ƃ̗��R�̈�ƂȂ�A�Ǝ咣����i�������ʁi�Q�j�Q�`�R�ŁB�����͓����ʂ̂܂܁B�ȉ��A��T�i�l�̎咣�Ƃ��Ĉ��p����Ő��͂��ׂē��������ʂ̕Ő��j�B
�@�������Ȃ���A�{���Q���́A��퍑�������ł���ꍇ�ɂ̂ݒ��Ԃɏ���K�p���邱�Ƃ��߂��A������u�����������v�ł���i���ۖ@�w��ҁw���ۊW�@���T�x�O�ȓ��A1995�N�A505�Łj�B������������19���I�㔼�����ꎟ���܂ł̊Ԃɒ������ꂽ�푈�@�K�Ɋւ�����̑����Ɋ܂܂�A�n�[�O�����Q���ł�����K�肵�Ă����i�Ȃ����̌��ʁA�푈�ɂ����Ă��ׂĂ̌�퍑�����ł���Ƃ��Ɍ����K�p����A��퍑�̂�����J���ł����������ΐ푈�S�̂ɂ��ď�K�p���Ȃ����ƂɂȂ邪�A�n�[�O���̏ꍇ�͑��펞���łɊ��K���ۖ@�����Ă����Ƃ݂Ȃ���A�{�����R�����ł����K���ۖ@�Ƃ��Ẵn�[�O����O��Ƃ��Ă��邽�ߑ����������͖��Ƃ���Ă��Ȃ��j�B�܂�A�{���͂����܂Łu����v�Ƃ̊W�Łu���v�Ƃ��Ă���ɂƂǂ܂�A�l���Ƃ̊W�ɂ�����K�p�̖��Ƃ̓��x���̈قȂ���e�̋K��ł���B
�@�]���āA�Q���̋K��́A�R���ɂ���Čl�����Q������������L���邩�ǂ����̖��Ƃ͒��ڊW���Ȃ��A��T�i�l�̎咣�͍����������B�{���͂ނ���A��T�i�l����L�ӏ��łӂ�Ă���悤�ɁA�O����Q�i���ɂ����āu��푊�݊ԃm�W�y�l���g�m�W�j���e�A���҃m�s���m��ʃm����^���w�L���m�g�X�v(these
provisions, ... are intended to serve as a general rule
of conduct for the belligerents in their mutual relations
and in their relations with the inhabitants) �Ƃ��Ă���̂ł���A�S�̂Ƃ��āA���Ƒ��̌�퍑�݂̂Ȃ炸���Ɛl���Ƃ̊W�œK�p�����邱�Ƃ����炩�ɈӐ}����Ă�����ł���B
�i�Q�j�����ɂ�����Z�����ւ̋����̎x�����K�肵�������52��3���́A�Z�������x�����������߂鍑�ۖ@��̎�i��݂��Ă��Ȃ��Ƃ̎咣�ɂ���
�@�{�����R�����́A�n�[�O�K��52���E53���̋K��̉��ł͐�̌R�������̎x�������Ȃ��ꍇ�ɏZ�������̋~�ς����߂邽�߂̍��ۖ@�̎�i�͂Ȃ��A�����̋K��́A��������̍s�ׂ����ƊԂō��ӂ������̂Ɖ�����̂��Ó��ł����āA�����̋K��������Čl�����荑�ɑ����ډ��炩�̐����������邱�Ƃ�F�߂����̂Ɖ����邱�Ƃ͂ł��Ȃ��Ƃ��Ă����i17�Łj�B��T�i�l�����l�ɁA�������ʁi�Q�j�ɂ����āA��̎��̒����ɂ�����Z�����ւ̋����̎x�����K�肵���n�[�O�K��52���̋K��́A�Z�����ւ̎x���`���ł���Ƃ��Ă��Z�����̎x���������ł͂Ȃ��A�Z�������̗��v��N�Q���ꂽ�Ƃ��Ă����ۖ@�セ�̋~�ς����߂��i�E���x���݂����Ă��Ȃ��Ǝ咣���Ă���i�R�Łj�B
�@�n�[�O���́A��̌R�ɂ��Z��������̌��i�����y�щۖ��A���тɉ����ɂ��āA���K��52���E53���ňȉ��̂悤�ɒ�߂�B
52�� Requisitions in kind and services shall not be demanded
from municipalities or inhabitants except for the needs
of the army of occupation. They shall be in proportion to
the resources of the country, and of such a nature as not
to involve the inhabitants in the obligation of taking part
in military operations against their own country.
Such requisitions and services shall only be demanded on
the authority of the commander in the locality occupied.
Contributions in kind shall as far as possible be paid for
in cash; if not, a receipt shall be given and the payment
of the amount due shall be made as soon as possible.
�@�@�@�u���i�����y�ۖ��n�A��̌R�m���v�m�׃j�X���j��T���n�A�s�撬���� �n�Z���j�V�e�V���v���X���R�g�����X�B�����y�ۖ��n�A�n���m���̓j
�����V�A���l�����V�e���m�{���j�X����퓮��j�����m�`�������n�V ���T�������m���m�^���R�g���v�X�B�E�����y�ۖ��n�A��̒n���j���P��
�w�����m���������j��T���n�A�V���v���X���R�g�����X�B���i�m���� �j�V�e�n�A�����w�N�����j�e�x���q�A�R���T���n�̎����ȃe�V����
���X�w�N�A�������w�N���j�V�j�X�����z�m�x�������s�X�w�L���m�g �X�B�v
53�� An army of occupation can only take possession of cash,
funds, and realizable securities which are strictly the
property of the State, depots of arms, means of transport,
stores and supplies, and, generally, all movable property
belonging to the State which may be used for military operations.
All appliances, whether on land, at sea, or in the air,
adapted for the transmission of news, or for the transport
of persons or things, exclusive of cases of governed by
naval law, depots of arms, and, generally, all kinds of
munition of war, may be seized, even if they belong to private
individuals, but they must be restored and compensation
fixed when peace is made.
�@�@ �u��n������̃V�^���R�n�A���m���L�j���X�������A����y�L���،��A ��������A�A���ޗ��A�ɕi�y�Ɩ����m�����e��퓮��j���X���R�g��
���w�L���L���Y�m�O�A�V�������X���R�g�����X�B�C��@�j�˃��x�z�Z�� �����ꍇ�����N�m�O�A����A�C��y�j���e�m�`�����n�l��n��
�m�A���m�p�j���Z��������m�@�ցA�������푴�m���e��m�R���i�n�A ���l�j���X�����m�g嫃��A�V�������X���������B�A�V�A���a�����j�����A
�V���ҕt�V�A���V�J����������X�w�L���m�g�X�B
�@���̓_�A�u���ۖ@�セ�̋~�ς����߂��i�E���x���݂����Ă��Ȃ��v�Ƃ̑��R�����y�є�T�i�l�̎咣�́A���ێi�@�ٔ����̂悤�ȁu���ۍٔ����v�ɂ�����葱��z�肷��A���̂悤�Ɍ������邪�A���ۂɂ́A�펞��̉��̍��Y�����Ɋւ���i�ׂ́A���ۖ@�ł͓`���I�ɂ͍����ٔ����ɂ����čs���Ă����̂ł����āA�����ٔ��������ۖ@�����߁E�K�p���Ă����������j���ʼn߂������̂ł���B��̉��̒����≟���Ɋւ����L�̃n�[�O�K��52�E53���Ɍ�퍑���ᔽ�����Ƃ��č��Y���L�҂��鎄�l�����̊ҕt�┅�������߁A�ٔ����������F�߂���v���ٔ����̎���͑������݂��A���{�ł�������w�͂��ߑ����̑�w���������鍑�ۖ@�̑�\�I�Ȕ���WAnnual
Digest of Public International Law Cases�i��ɉ�������International
Law Reports.�e���̍����ٔ��������ۖ@��K�p����������܂ޑ����̍��ۖ@����N�f�ڂ���j�Ɏ��^����Ă���i�Ȃ��A���Y���E����������퍑����ɂ���p�������Ɠ��ɂ��A�i�ׂ̌`�������l�Ύ��l�Ȃ��������ɂȂ��Ă�����̂�����j�B��Ƃ��āA�ȉ��̂��̂���������B
�@�@�h�C�c�R�ɂ��ݕ������Ԃ���������A�Ή��̎x�������̎��̔��s���Ȃ���Ȃ��������Ăɂ��A�t�����X�̃��[�A���T�i�ٔ�����1947�N�A���̂悤�ɔ������āA���̏��L�҂ł��郍�[���ւ̕Ԋ҂�F�߂��B�u�h�C�c�̍s�ׂ͒����ł͂Ȃ��A�n�[�O���53���ɂ��������ł������B�{���́A���l�ɑ�����A����i�̉����́A�푈�@�ɂ���ĔF�߂���ꍇ�ɂ́A�����̌l���珊�L����D�����̂ł͂Ȃ��A�P�ɉ������ꂽ���Y�̎g�p����D���݂̂ł���ƒ�߂Ă���B���Y���Y�́A���̏I����A�ҕt����Ȃ���Ȃ�Ȃ��v(Mortier
v. Lauret, H. Lauterpacht ed., Annual Digest of Public International
Law Cases, Year 1947, 1951,pp.274-275)�B
�@�A�h�C�c��̌R�̂��߂ɑ݂����n���A���̌���Ԋ҂��ꂸ�A���̌�C�M���X��̌R�A�����Ńf���}�[�N���{�ւƈ��n���ꂽ���߁A���̏��L�҂����L�����咣�������ĂŁA�f���}�[�N�̐��T�i�ٔ�����1947�N�A�i����F�ߔn�̕Ԋ҂𖽂��锻�����������B�u�n�[�O�ł̑�2�ە��a��c�ō̑����ꂽ����K���́A53���2�i�ɂ����āA
��̌R�́A���l�ɑ�������̂ł����Ă��A�Ƃ�킯�A����i���������邱�Ƃ��ł���ƒ�߂Ă���B�������A�{���́A���̂悤�ɉ������ꂽ���Y�́A�a���̒������ɂ͊ҕt����A�܂����Q��������߂��Ȃ���Ȃ�Ȃ��ƕt�������Ă���B�h�C�c��̌R�ɂ��n�̏������A��q�̋K���ɏ]���čs��ꂽ�����Ƃ����邩�ǂ����͕ʂɂ��āA�T�i�l�̏��L��������ɂ���Ď���ꂽ�Ƃ݂邱�Ƃ͂ł��Ȃ��v(Andersen
v. Christensen and the State Committee for Small Allotments,
Annual Digest of Public International Law Cases, Year 1947,1951,
pp.275-276.)�B
�B�h�C�c�R���I�����_���̒��A�h�C�c�̍����Ŋ֊Ď������A�����x�������̎��̔��s��������2��̃I�[�g�o�C�������������Ăɂ��A�I�����_�̓��ʔj�ʉ@��1950�N�A���Ƃ��A����i�Ƃ��ĉ����̑ΏۂɂȂ�Ƃ��Ă��A�n�[�O���53���2�i�����炳��Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ƃ��āA��������@�ƔF�߂锻����������(In
re Hinrechsen, H.Lauterpacht ed., Annual Digest of Public
International Law Cases,Year 1949,1955,pp.486-487)�B
�C�h�C�c�R���m���E�F�[���̒��A�h�C�c���ǂ��������L�̎����Ԃ����A�̎��̔��s�������̎x�������Ȃ���Ȃ��������Ăɂ��A�m���E�F�[�̍T�i�ٔ�����1948�N�A�n�[�O���52���ɂ�钥�����L���ł��邽�߂ɂ͌����̎x�������̎��̔��s���Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ƃ��āA�����̏��L����F�߂�(Johansen
v. Gross, Annual Digest of Public International Law Cases,
Year1949, 1955, pp.481-482�j�B
�D�h�C�c�ɂ��f���}�[�N�̐�̒��ɑ���̎x�����Ȃ���������A���C�M���X�R����f���}�[�N���{�̎�ɓn����2���̔n�ɂ��A���̏��L�҂����L�����咣�������ĂŁA�f���}�[�N�̃R�y���n�[�Q�����n���ٔ�����1947�N�A���̂悤�ɏq�ׂČ����̎咣��F�߂��B�u��Q��n�[�O���a��c�ō̑����ꂽ����K����53���2�i�́A�������̂����R���͂Ƃ�킯�A���l�ɑ�������̂ł����Ă��A�A����i���������邱�Ƃ��ł���ƒ�߂Ă���B�������A�����́A�������ꂽ���Y�́w�a���̒������Ɋҕt����A���������肳��Ȃ���Ȃ�Ȃ��x�ƕt�������Ă���B���̂��ƂɏƂ点�A�T�i�l�̏��L�������ł����Ɛ��肷�邱�Ƃ͂ł��Ȃ��v(Statens
Jordlovsudvalg v. Petersen, H.Lauterpacht ed., Annual Digest
of Public International Law Cases, Year 1949,1955, pp.506-507.��Ƀf���}�[�N�ō��ق�������x���j�B
�@�E�C�M���X��̌R�̖��߂ɂ�蒥�����ꂽ�I�[�g�o�C�����̌�A�ȑO�ɒ��������҂ɑ��Ĕ����Ƃ��ēn����A���̎��傪�n�[�O���53���2�i�������ɏ��L�����咣�������ĂŁA�I�[�X�g���A�ō��ق�1951�N�A1907�N�n�[�O���Ƃقړ����e��1899�N�n�[�O�������p���āA�����̎咣��F�߂��B�u�n�[�O�K����53���1�i�ɂ��A��̌R�́A���̍��̏��L�ɑ�������̍��Y�����邱�Ƃ��ł���B��������Y�͂���ɂ���̍��̍��Y�ɂȂ����A���l�̋K���́A53���2�i�Ɍ��y���ꂽ�l�╨�̗A����i���܂ގ��L���Y�ɂ͂��Ă͂܂�Ȃ��B�Ȃ��Ȃ�A�����鎄�L���Y�́A�a���̒������ɕԊ҂���A�܂������̖������肳��Ȃ���Ȃ�Ȃ�����ł���B�D�D�D�I�[�g�o�C�͎��l�̍��Y�ł���������A��̍��́A�n�[�O�K���ɏ]���A�����ɂ���Ă��̏��L�����擾���Ă͂��Ȃ��D�D�D�]���Č����́A�����y�т��̌�̈ړ]�̌��ʂƂ��āA�I�[�g�o�C�ɑ��錠���������Ă��Ȃ��v(Requisitioned
Property (Austria)(No.1) Case, H. Lauterpacht ed., International
Law Reports, Year 1951, 1957, pp.694-695)�B
�F�č��ɂ��h�C�c�̐�̒��A�ČR�ɂ���Ē������ꂽ�����Ԃ��A�ʂ̎҂̎g�p�Ɋ��蓖�Ă��A���̎҂��g�p���Ă���Ԃɓ���ɂ��������������߁A���L�҂����Y�̈편�ɂ��đ��Q���������߂����ĂŁA���h�C�c�A�M�ō��ق�1952�N�A�g�p�҂������ӔC�����Ƃ�F�߂锻�����������B�ٔ����́A�n�[�O�K��53���Ɍ��y���Ĉȉ��̂悤�ɏq�ׂĂ���B�u�ČR�̂Ƃ����[�u�ɂ�������炸�������Ȃ��Ԃ̏��L�҂ł��������ǂ����̖��́A�m��I�ɓ������Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�D�D�D�n�[�O�K����53���2�i�ɏ]���A���l�̏��L�ɂȂ�A����i�ŁA��̌R�ɂ�蒥�����ꂽ���̂́A�a���̒������Ɋҕt����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�]���āA��������Y�̒����͎��p�ړI�ɋ����Ă͂Ȃ炸�A�g�p�҂̂��߂ɂ̂���������̂ł���A���ʂƂ��āA����ɂ��e�������l�͂��̏��L��������Ȃ��v�B�����āA�Ԃ��g�p���Ă����퍐�͂��̕ی�̂��߂̑[�u��ӂ����Ƃ��āA�����ӔC��F�߂�(Loss
of Requisitioned Motor Car (Germany) Case, H. Lauterpacht
ed., International Law Reports 1952,1957, pp.621-622)�B
�G�h�C�c�R���t�����X���̒��A�t�����X�̉�Ђł��錴������A����߂ĕs�\���Ȋz�̎x�����������ČR�p��������������A��Ƀt�����X���{�@�ւɂ��G�����Y�Ƃ��Ėv�����ꔄ�p���ꂽ���߁A����������̕����߂������߂����ĂŁA�t�����X�j�ʉ@��1957�N�A�h�C�c�̍s�ׂ͗��D�Ƃ��Ĉ�@�ł���A�����͍��@�I�ȏ��L�҂Ƃ��Ċ��S�Ȕ����錠��������Ɣ�������(Etablissements
Bracq Laurent S.A. v. Service Central des Domaines, International
Law Reports 1957,�@1961, pp.978-979)�B�@
�@���̂悤�ȑ����̍����ٔ����̔���̑��݂Ɋӂ݂�ƁA�n�[�O�K��52���E53���͏Z�����̎x�����������߂����̂ł͂Ȃ��Z�����ɂ͂��̐N�Q�ɑ��č��ۖ@�セ�̋~�ς����߂��i���Ȃ��Ƃ̑��R�����y�є�T�i�l�̎咣�͍������Ȃ����Ƃ�������B���ƊԂ̏��Œ��ٍٔ�������肻���ւ̌l������F�߂���ꎟ����̃x���T�C�����̂悤�ȗ�������A�펞���ۖ@�Ɉᔽ�����@�Ȓ����E�����ɑ���l�̕ԊҁE���������́A�`���I�ɁA�قƂ�ǐ�獑���ٔ����ɂ����Ē�N����Ă����̂ł���B�����Č��Ɋe���̍����ٔ����́A��L�̔���̂悤�ɁA�n�[�O�K��52���E53����K�p���āA���L�҂ւ̍��Y�̕Ԋ҂┅���𖽂��锻���������Ă���B
�@���R�����y�є�T�i�l�̂悤�Ȏ咣�́A�l�́u���ۍٔ����v�ɂ����Ď��猠���咣���s���~�ς���@��̐��������Ȃ��Ƃ�����|�̎咣�Ƃ��l�����邪�A���ۖ@�̉��߁E�K�p�́A�����A���ێi�@�ٔ����̂悤�ȁu���ۍٔ����v�݂̂��s�����̂łȂ��Ȃ��ċv�������Ƃ͂����܂ł��Ȃ��B���{���܂ߑ����̍��ł́A���ۖ@�������@�Ƃ��Ă̌��͂�F�߂��A�����ٔ����ł����Ή��߁E�K�p����Ă��Ă��邪�A�����ł́A�l�̌����ɂ��������e���܂ލ��ۖ@���ٔ��������߁E�K�p���Čl�Ɍ����~�ς�^���邱�Ƃ������Ē������Ȃ��Ȃ��Ă���B�Ƃ���Ȃ�A���ۖ@��̌l�̖@��̐����A�u���ۍٔ����v�ɂ����鍑�ۓI�葱�����݂���ꍇ�ɂ̂��肷�邱�Ƃ́A���炩�ɑÓ��łȂ��B�R�{�����i���ۖ@�w��������A���݁A���A�C�m�@�ٔ��������j�������悤�ɁA���ۖ@��̖��ɑ���NJ����́u�K���������ۍٔ������̑��̍��ۋ@�ւɐꑮ����킯�ł͂ȁv���A�u�����ꂩ�̍��̍����ٔ����ł����Ă��A���̍����@�ɂ�荑�ۖ@��̖��i���Ƃ��A�푈�ƍ߂܂��͏W�c�E�Q�߂ɑ���Y���ӔC�̒Njy�j�ɑ���NJ������^�����A�����ۖ@�ɏ������Ă��̊NJ������s�g���Ă������́A���ۊNJ����̍s�g�S���Ă���Ƃ݂Ȃ����Ƃ��ł���v�i�R�{����w���ۖ@�i�V�Łj�x�L��t�A1994�N�A166�Łj����ł���B�u���������Ă��̏ꍇ�ɂ́A�����ٔ����ɂ���Ă��l�̍��ۖ@��̌����`���̎����Ǝ��s��S�ۂł��邱�ƂƂȂ�A�l�̌����\�͎擾�̏������[�����̂ł���v�i���j�B�l�����ۋ@�ւ̐����葱�ɒ��ڂɓ����ғK�i��^������̂́A����L�������ʂ̏����ꍇ�݂̂Ɍ����邱�Ƃ��炷��A�ނ���u�l�̍��ۖ@��̌����̎����́A�e���̍����@�ɂ��S�ۂ���A�����@�ւ̒�߂�葱�Ɉˑ�����ʂ����Ȃ��Ȃ��v�i���A168�Łj�B��ɂ݂��n�[�O�K��52���E53���Ɋւ��鍑���ٔ����̑����̔���͂܂��ɁA���ۖ@��̌l�̌������A�����ٔ����ɂ���Ď�������S�ۂ��ꂽ�T�^�I�ȗ�Ƃ����ׂ����낤�B�n�[�O�K��52���E53����K�p���Čl�̍��Y�̕ԊҁE�����𖽂�����L�̊e���ٔ����̔���́A�n�[�O��l�̌����~�ς̂��߂ɍ����ٔ����ʼn��p����Ă��Ă��邱�Ƃm�Ɏ����Ă���A���̓_�Ɋւ�����R�����̔����y�є�T�i�l�̎咣�͑Ó����������B
�i�R�j�����3���̋N�������̍��ۖ@���_�ɂ���
�@��L�i�Q�j�łӂꂽ�l�̍��ۖ@��̐��Ƃ��֘A����_�ł��邪�A��T�i�l�́A�n�[�O�����������ꂽ1907�N�����̍��ۖ@�ɂ�����l�̈ʒu�Â��́A�u�l�͍��ۖ@�̋q�̂ł���v�Ƃ����������x�z���Ă����̂ł����āA�l�����Q���Ƃɑ����Q������������F�߂���Ƃ������Ƃ͍l�����Ȃ����Ƃł������Ǝ咣����i9�Łj�B
�@�������Ȃ���A�n�[�O���ɂ��Ă͏�L�̂悤�ɓ��K��52���E53����K�p���Čl�Ɍ����~�ς�^���������̍������Ⴊ���݂���ق��A�K���Ɉᔽ�������Ƃɔ����ӔC�킹���R���̋K��ɂ��ẮA��������A���ꂪ���Q�����l�ɔ�����^���邱�Ƃ��F�߂��|�̋K��ł���Ƃ��錩�����L�͂ł������B��Ƃ��āA�R���ɂ��ăt�����X�̐�O�̒����ȍ��ۖ@�w�҂ł��郁���j���b�N�y�уt�H�[�V�[�����q�ׂ������������i�ȉ��A�����M�ҁj�B
�E�u�����Ƃ��āA�i�����N�����B��̎��i��L���Ă���̂́A���Q��^�����s�ׂ̔�Q�҂ł���v�iA. Merignhac,"De
la sanction des infractions au droit des gens commises,
au cours de la guerre europeenne, par les empires du centre",
24 Revue general de droit international public (1917), pp.8-9�j
�E�u����̖@�K����Ɉᔽ������퓖�����ɑ��A���̕s�@�s�ׂ̔�Q�҂ɑ���������(indemniser les
victimes)�`�����ۂ����A1907�N10��18���̃n�[�O���3���̍��ېӔC�́A�l�̍��Y�ɑ��ĉ�����ꂽ���Q�Ɠ��l�A�g�̂ɑ��ĉ�����ꂽ���Q�ɂ��K�p�����v�iP.
Fauchille, Traite de droit international public, tome II,1921,p.314�j
�@���{�̎�v�ȍ��ۖ@�w�҂ł́A1931�N�̏�C���ςɊ֘A���āA�M�v�~���́A�u�x�ߑ��y�ё�O���l�̖ւ肽��A���͖ւ肽��Ə̂���A���Y���Q�v�ɂ����̂悤�ɘ_���Ă���B
�@�u1907�N�̗���@�K���ដ���3���ɂ́A�w�O�L�K���m�����j�ᔽ�V�^������c���҃n���Q�A���g�L�n�V�K�����m�Ӄ����t�x�L���m�g�X�B����c���҃n���m�R�����g���X���l���m��m�s�׃j�t�ӔC�����t�x�Ƃ���B�O�L�K���Ƃ͓�����ɕ������鏊�̗���@�K����K�����w���B�̂ɑ��Q����ɕ���Ĕ����̐ӂЁA������횠���{�����̌R���̑g�����̍s�ׂɕt�ӔC�ӂ̂́A��痤��@�K����K���̋K�肷�鏔�����̈ᔽ�s�ׂł���B����ǂ��A���̌̂��Ȃē��K���ȊO�̌��@�K�̈ᔽ�ɏA�Ă͑S�R�ӔC�ӂɋy�����ĉȂ�Ƃ��ӌ��_�ӂ��̂ł͂Ȃ��B�}�����ۖ@����ƍ����@����Ƃ��͂��A䑂��И��̝|���Ɉᔽ����A�V�ɏA�Đӂӂׂ����̂��邱�Ƃ͑��Ă̏ꍇ��ʂ��Ĉ�т��錴���ł���B���@�K�͂��̗���ɌW��ƁA�C��ɌW��Ƥ�������ɌW��Ƃ��͂��A���Ă��̈ᔽ�҂ɛ����ĔV���ӔC�̕��^��v������B���T�J����@�K���ដ��́A���̖}��Ƃ��ē������̗���@�K����K���̈ᔽ�Ɋւ����ɐӔC�̋A���w�����܂ŁT����v�i�M�v�~���w��C��ƍ��ۖ@�x1932�N�A�ۑP�A357�|358�Łj�B�u��횠�̈�@�s�ׂɗR��đ��Q�����ƔF�ނ鎄�l�́A���̌�킪�@���Ȃ錴���Ɋ�ċN�����̂ɂ�����A�c�R�~�ς����ނ�̌���������B�D�D�D��Ɍ�횠�̈�@�s�ׁi���ɂɂ���Ƃ��āj�Ɉ��鑹�Q�������Ɋւ��ẮA�@���ɉ��Q�����Վ��̋��d�Ȃ錩��������Ƃ������ŁA�����������҂͕s�����Ǝv�ӏꍇ�ɂ́A�������{�ɑi�ւĔV��މ䐭�{�Ԃ̊O����ƈׂ�����̓�������v�i���A364�Łj�B
�@�n�[�O��̑����ꂽ��������A�������Ԋ��ɂ����Ă����A�����R���ɂ��āA���̂悤�ȗL�͂Ȍ��������O�ɑ��݂��Ă����B�܂��āA�l�̍��ۖ@��̐��Ɋւ��鍑�ۖ@���_����������A�����ٔ����ɂ����Čl�����ۖ@�����p���Č����~�ς��邱�Ƃ��u�l�̍��ۖ@��̐��v�̈�ʓI�Ȏ����`�Ԃł��邱�Ƃ����m�ɂ���Ă��鍡���A�l�͍��ۖ@�̋q�̂ł���Ƃ���������O��Ƃ������f���s�����Ƃ͑Ó��łȂ��B
�@�n�[�O���R���ɂ��ẮA�����ł�����L�̂悤�Ɍl�ւ̔�����F�߂�L�͂Ȍ���������������łȂ��A����ォ�獡���Ɏ����ẮA�������������͂���ʓI�ɂȂ��Ă���B�Ⴆ�A���ۖ@�E���ېl���@�̐��E�I���Ђł���A���݂͋����[�S���یY���ٔ��������ł��郁�������A�u�m�n�[�O���n�u�R���́A�����Ɋւ��邢���Ȃ�c�_�ɂƂ��Ă����ɏd�v�ł���B�Ƃ����̂́A���ہA���̋K��́A��Q�҂ɑ��A���ڂɍ��Ƃɑ��錴���K�i��^����悤�ɉ��߂���Ă�������ł���v�ƌ��������������Ă���(Th.Meron,"Discussion",A.
Randelzhofer and Ch.Tomuschat eds, State Responsibility
and the Individual, 1999, p.142)�B�܂��A���ېl���@�̏�����Ď�����@�ւł���ԏ\�����ۈψ���������A���炩�ɂ��̂悤�ȗ�����Ƃ��Ă���i��q�j�B
�@���{�̔���ł��A�I�����_�l�ߗ��̕⏞�����Ɋւ���1998�i����10�j�N11��30�������n�ٔ����i���^991��262�Łj�́A�n�[�O���3���̋N���ߒ����ڍׂɌ����������ʁA�����͔�Q�Ҍl�̋~�ς����ړI�Ƃ�����̂ł��������Ƃ͔F�߂���A�Ƃ����F����s���Ă���B
�i�S�j�����3���̉��߂Ɋւ���ԏ\�����ۈψ���̌����ɂ���
�@��T�i�l�́A�n�[�O���3���Ɋւ��āA���ꂪ�l�̑��Q������������F�߂Ȃ����̂ł���Ƃ̉��߂́A1952�N�����̐ԏ\�����ۈψ���̌����ɂ���Ă��x������Ă���Ƃ���ł���Ǝ咣���Ă���i11�Łj�B
�@�������A���ɁA��T�i�l�咣�̒ʂ�u1952�N�����v�̌����������ł������Ƃ��āA���݂͖̏��炩�ɈقȂ�B
�@1977�N�ɍ̑����ꂽ�A1949�N�W���l�[�u���̑��lj��c�菑91���́A�n�[�O������3���P�����A����Ƃقړ���̋K��ł���A���̂悤�ɋK�肷��B
�@���lj��c�菑91��
�@�@�@A Party to the conflict which violates the provisions
of the Conventions or of this Protocol shall, if the case
demands, be liable to pay compensation. It shall be responsible
for all acts committed by persons forming part of its armed
forces.
�u����͂��̋c�菑�̋K��Ɉᔽ���������������́A�K�v�ȏꍇ�� �́A�������x�����`�����B�����������́A�����̌R���̈ꕔ���\��
����҂��s�������ׂĂ̍s�ׂɂ��ĐӔC��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�v
�@�{���ɂ��A���̒lj��c�菑�ɂ��Đԏ\�����ۈψ�����s�������ߏ��́A�ȉ��̂悤�ɋL�q���Ă���i�ȉ��A�����M�ҁj�B
�@�u�������錠����L����҂́A�ʏ�́A�������������͂��̍����ł���B�D�D�D��O�I�ȏꍇ�������āA�����������̈�@�s�ׂɂ���đ��Q�����O���Ђ̎҂́A���玩�����{�ɑi�����s���ׂ��ł���A����ɂ���ē��Y���{���A�ᔽ���s�����������ɑ��Ă����̎҂̐\���Ă��o���邱�ƂɂȂ낤�B�������A1945�N�ȗ��A�l�̌����s�g��F�߂�X��������Ă��Ă���v�iY.
Sandoz, Ch. Swinarski et al. eds., Commentary on the Protocol
Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949,and
relating to the Protection of Victims of International�@Armed
Conflicts (Protocol I), International Committee of the Red
Cross, Geneva, 1987 [hereinafter: Commentary], pp.1056-1057�j�B
�@�܂��A�������ߏ��́A�ی삳�ꂽ�҂̏ɕs���ɉe������悤�ȕʂ̎挈�߂�����������邱�Ƃ��֎~����1949�N�W���l�[�u�S���̋K��i���`��l���̂��ꂼ��6�^6�^6�^7���j�ɂ��āA�ȉ��̂悤�ɏq�ׂĂ���B
�@�u���a���̒����ɂ������ẮA�������͌����Ƃ��āA�푈��Q��ʂɊւ�����y�ѐ푈�J�n�ɑ���ӔC�Ɋւ�������A�K���ƍl������@�ŏ������邱�Ƃ��ł���B�����ŁA�������́A�푈�ƍߐl�̑i�ǂ��T���邱�Ƃ�A�W���l�[�u�����y�т��̋c�菑�̋K���̈ᔽ�̔�Q�҂��������錠����ے肷�邱�Ƃ͂ł��Ȃ��v�iCommentary,
p.1055�j�B
�@����ɁA���A�l���ψ���ł�1990�N��ȍ~�A���ېl���@�y�ѐl���@�ᔽ�̔�Q�҂��~�ς��錠���ɂ��āA���ʕ҂�C�����Č������������A2000�N�ɂ́A�u���ېl���@�y�ѐl���@�ᔽ�̔�Q�҂��~�ϋy�ѕ⏞���錠���ɂ��Ă̊�{�����y�уK�C�h���C���iBasic
principles and guidelines on the right to a remedy and reparation
for victims of violations of international rights and humanitarian
law�j�v���l���ψ���ɒ�o���ꂽ���iE/CN.4/2000/62, Annex�j�A����ɂ��č��A�l�������ٖ������������J�Â���������c�ŁA�ԏ\�����ۈψ���̑�\�́A�n�[�O���3���͔�Q�҂ւ̔��������Ƃɗv��������̂ł���A�Ƃ̔������s���Ă���iE/CN.4/2003/63,
paras.50,118�j�B
�@���̂悤�ɂ݂Ă���ƁA�n�[�O���3������Q�Ҍl�̔���������F�߂Ȃ���|�̂��̂ł��邱�Ƃ�1952�N�̎��_�Őԏ\�����ۈψ���x�����Ă���Ƃ̔�T�i�l�̎咣�́A���ɂ��̎��_�ł��̂悤�ɍl���邱�Ƃ��ł����Ƃ��Ă��A���Ȃ��Ƃ�1980�N��ȍ~�ɂ��ẮA���炩�ɐ������Ȃ��Ƃ݂�ׂ��ł���B1987�N���s�̑O�f�̒��ߏ��́A���͕��a���̒����ɂ������Ă̓W���l�[�u�����y�ђlj��c�菑�̈ᔽ�̔�Q�҂��������錠����ے肷�邱�Ƃ͂ł��Ȃ��Ƃ���ƂƂ��ɁA�n�[�O���3���Ƃقړ����e�̑��lj��c�菑91���ɂ��āA�������錠����L����҂͓������̍����ł����肤�邱�ƁA�l�ɂ��̂悤�Ȍ�����F�߂�X��������ȍ~�͋��܂��Ă��邱�Ƃ��q�ׂĂ���B�܂��A���ŋ߂ł́A���ېl���@�y�ѐl���@�ᔽ�̔�Q�҂��~�ς��錠���Ɋ֘A���āA�ԏ\�����ۈψ���̑�\�͍��A�̉�c�ŁA�n�[�O���3���͔�Q�҂ւ̔��������Ƃɗv��������̂ł���Ƃ̖��m�ȗ���������Ă���̂ł���B
�@�]���āA�ԏ\�����ۈψ���̌����Ɋւ����T�i�l�̎咣�́A���݂̓��ψ���̌�����\�������̂Ƃ͓��ꂢ�����Ƃ��ł��Ȃ��B
�@�����āA�{���́A��Q�����͑��풆�ɔ����������̂ł���ɂ���A�����_�ɂ����Ė@�����߁E�K�p������̂ł��邩��A���ۖ@�̉��߁E�K�p�ɂ��Ă��A���s�̍��ۖ@�ɂ��Č��ݒʗp�E�Ó����Ă���@���߂������\���ɓ��܂������f���Ȃ����ׂ��ł���B
�R�@���ېl���@�ᔽ�̔�Q�҂̑��Q����������
�@�ȏ�̌����܂��A���A���R���������łɖ{���ې��1925�N�̃W���l�[�u�E�K�X�c�菑�y�ѓ����e�̊��K���ۖ@�Ɉᔽ����ƔF�肵�Ă��邱�ƂɊӂ݁A�����ł́A���̂悤�ȍ��ېl���@�ᔽ�̔�Q�҂���T�i�l�炪�n�[�O���3���i�O�q�̒ʂ�A�n�[�O���͑������������܂�ł������A����ɂ����ē�����K���ۖ@�Ƃ��ēK�p���ꂽ���Ƃ͖{�����܂ނ�������⏞�ٔ����ׂĂɂ����ď��^�̑O��Ƃ���Ă���A�����ł��A���K���ۖ@�Ƃ��Ă̓����3���������j�Ɋ�Â��āA���ۖ@�ᔽ�̍��ƐӔC����T�i�l�E�����瑹�Q�����錠����L���Ă��邩�ɂ��āA����Ɍ�����������B
�i�P�j���ېl���@�ɂ����鎄�����d�̌����̊m��
�n�[�O���̂悤�Ȑ펞���ۖ@�Ȃ������@�K(jus in bello�G�N���̗L���̂悤�ɐ푈�E���͍s�g�̊J�n�ɂ����鍇�@���ɂ������jus
ad bellum�ƈقȂ�A��퓖�����o�������S������퓬�s�ג��̋K���B�Ȃ��ߔN�́A�푈���܂ޕ��͍s�g�̈�ʓI��@���A�y�ьl�̕ی�̂��߂̐l���I�K���̑�������A�u�펞���ۖ@�v�̑���Ɂu���ېl���@�v�̌ꂪ�p�����邱�Ƃ������B�{�e�ł��A���ېl���@�̌��p����j�̗��j�͌Â����A���ł��A����ɂ������̎��́A�Z���̎����i���l�̐����A�g�̋y�э��Y�j���d�ɂ��ẮA18���I�A���ď����ɂ����鎩�R��`�o�ς̔��W��[�֎v�z�̓o���w�i�ɁA�ł��������獑�ۖ@�̋K�����m�������B
�G�����̎����̑��d��ԏ��ŏ��߂Ė����������̂́A1785�N�̕āE�v���V�A�Ԃ̏��i23���j�ł������B�č��i�g�}�X�E�W�F�t�@�\���A�x���W���~���E�t�����N������j�̒�ĂɂȂ�{���́A���Ԃɐ푈�����������ꍇ�ɂ��A�u������h��̒��A�����͏ꏊ�ɋ��Z���邷�ׂĂ̏����Ǝq�ǂ��A�����镪��̊w�ҁA�_���A�H�|�ƁA�����ƎҁA���t�A�y�ш�ʂɁA�l�ނ̋��ʂ̐����Ɨ��v�̂��߂̐E�Ƃł��邻�̑��̂��ׂĂ̎҂́A���ꂼ��̌ٗp���p�����邱�Ƃ�F�߂��˂Ȃ炸�A�푈�̎��Ԃɂ���Ă��̌��͉��ɗ����邩������Ȃ��G�̌R���ɂ���Ă��̐g�̂��N���ꂽ��A�Ɖ��������͕��i���R�₳��������͂��̑��̕��@�Ŕj�ꂽ��A�c�����r�p������ꂽ�肵�Ă͂Ȃ�Ȃ��B�A���A�����R���ɂ��g�p�̂��߂ɂ����ꂩ�̕��������̎҂����肽�Ă邱�Ƃ��K�v�ȏꍇ�ɂ́A�����I�Ȋz�Ŏx�������Ȃ���Ȃ���Ȃ�Ȃ��v�ƋK�肵��(H.Wheaton,
History of the Law of Nations in Europe and America, 1845,
pp.306,308)�B���������펞�ɂ����鎄�����d�̌����̗L�͂ȗ��_�I�����ƂȂ����̂́A�u�푈�͐l�Ɛl�Ƃ̊W�ł͂Ȃ��āA���Ƃƍ��Ƃ̊W�Ȃ̂ł��v��A�u�������N��́A�G���ɂ����āA���L���Y�͂��ׂĖv�����Ă��܂����A�l�̐����ƍ��Y�͑��d����v�Ƃ����[�֎v�z�ƃW�����E�W���b�N�E���\�[�̐��ł������i�|�{���K�w���ېl���@�̍Ċm�F�Ɣ��W�x1996�N�A39�|40�Łj�B
19���I�ɂ́A�����̑��d�́A1863�N�̕č��̃��[�o�[�K���A1880�N�̍��ۖ@�w��I�b�N�X�t�H�[�h�E�}�j���A���Ȃǂɂ�閾�������o�āA�펞���ۖ@�̈�ʌ����Ƃ��Ċ��K�@��m�����Ă����B���[�o�[�K���Ƃ́A�A�����J�̓�k�푈���A�����J�[���đ哝�̂��펞���ۖ@�̐��ƃ��[�o�[���m�i�R�l�ł�����j�Ɉ˗����A���{�R�̌P�߂̂��߂ɔ��s�������̂ł��邪�A�펞���ۖ@�̖@�T���̏��̎��݂ł���A���1899�N�E1907�N�̃n�[�O���̖@�T���̊�b�ƂȂ���(J.B.
Scott, The Hague Peace Conferences of 1899 and 1907,1972,
p.525�j�B1899�N�̑�P��n�[�O���a��c�ō̑����ꂽ�n�[�O������y�сA������Q��n�[�O���a��c�ō̑����ꂽ1907�N�̃n�[�O������́A�����̎�v���Ƃ̑啔���̎Q���̂��ƁA���K�@�Ƃ��đ��݂��Ă����펞���ۖ@�̋K����@�T�������W�听���Ȃ����̂ł������B
���[�o�[�K���Ɏn�܂�A�������d�����ɂ�������ȋK��͎��̒ʂ�ł���iD. Shindler and J. Toman,
eds., The Laws of Armed Conflicts, A Collection of Conventions,
Resolutions and Other Documents,1988. 1907�N�n�[�O���ɂ��Ă͐�ɂ݂��Ƃ���Əd�Ȃ邪�A���j�I�o�܂��������߂ɍČf����B�Ȃ��|��́A1907�N�̃n�[�O���ɂ��Ă͎s�̂̏��W�Ɍf�ڂ̌����ɂ��A���̑��̕����ɂ��Ă͉p�Ȃ�������������M�҂����j�B
�E1863�N���[�o�[�K��
37�� �A�����J���O���́A��̂����G���ɂ����āA�@���y�їϗ���F�ߋy�� �ی삵�A���L���Y�����i�ɔF�ߋy�ѕی삵�A�Z���̐g�́A���ɏ����̐g
�́A�y�э����W�̐_������F�ߋy�ѕی삷��B���̈ᔽ�́A�������� �������B...
38�� ���L���Y�́A���L�҂ɂ��ƍߖ��͈ᔽ�ɂ��v������Ȃ�����A�R ���̓A�����J���O���̈ێ����͂��̑��̕։v�̂��ߌR���I�K�v�ɂ��
�ق��́A�������꓾�Ȃ��B���L�҂����S���Ă��Ȃ���A�w�����́A�� �����ꂽ���L�ҁiowner�j������(indemnity)����悤�̎���
�s����B�v
�E1899�N�n�[�O���
�K��46�� �Ɓi�Ƒ��j�̖��_�y�ь����A�l�̐����y�э��Y�A���тɌl�̏@ ���I�M�O�y�ю��R�́A���d����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B���L���Y�́A�v����
�꓾�Ȃ��B
52�� ���i�����y�щۖ��́A��̌R�̕K�v�̂��߂������ẮA�s�������͏Z ���ɑ��ėv�����邱�Ƃ��ł��Ȃ��B�����y�щۖ��́A�n���̎��͂ɑ�
�����A���l���ɂ��̖{���ɑ���R�����ɉ����`���킹�Ȃ� �����̂��̂ł��邱�Ƃ�v����B�E�̒����y�щۖ��́A��̒n���ɂ���
��w�����̋��Ȃ���A�v�����邱�Ƃ��ł��Ȃ��B���i�̋����� ���ẮA�Ȃ�ׂ������Ŏx�����A�����łȂ���Η̎������s�����
���̂Ƃ���B
53�� ��n�����̂����R�́A���̏��L�ɑ����錻���A����y�їL���،��A ��������A�A���ޗ��A�ɕi�y�ѕ��i���̑��R�����ɗp����ꂤ�鍑
�L���Y�ȊO�́A�������邱�Ƃ��ł��Ȃ��B
�C���@�ɂ���ċK�������ꍇ�������A�S���{�݁A����d�M�A�d�b�A ���C�D���̑��̑D�A����������тɁA���ׂĂ̎�ނ̌R���i�́A��Ж�
�͎��l�ɑ�������̂ł����Ă��A�R�����̂��߂ɗp����ꂤ�铯�l�� �����ł���B�A���A�a���̒������Ɋҕt����A���������x�����Ȃ�
��Ȃ�Ȃ��B�v
�E1907�N�n�[�O���
�K��46�� �Ɓm�Ƒ��n�m���_�y�����A�l�m�����A���L���Y���@���m�M�y�� �m���s�n�A�V�����d�X�w�V�B���L���Y�n�A�V���v���X���R�g�����X�B
52�� ���i�����y�ۖ��n�A��̌R�m���v�m�׃j�X���j��T���n�A�s�撬�� ���n�Z���j�V�e�V���v���X���R�g�����X�B�����y�ۖ��n�A�n���m����
�j�����V�A���l�����V�e���m�{���j�X����퓮��j�����m�`�������n �V���T�������m���m�^���R�g���v�X�B�E�����y�ۖ��n�A��̒n���j���P
���w�����m���������j��T���n�A�V���v���X���R�g�����X�B���i�m�� ���j�V�e�n�A�����w�N�����j�e�x���q�A�R���T���n�̎����ȃe�V��
�ؖ��X�w�N�A�������w�N���j�V�j�X�����z�m�x�������s�X�w�L���m�g �X�B
53�� ��n������̃V�^���R�n�A���m���L�j���X�������A����y�L���،��A ��������A�A���ޗ��A�ɕi�y�Ɩ����m�����e��퓮��j���X���R�g��
���w�L���L���Y�m�O�A�V�������X���R�g�����X�B�C��@�j�˃��x�z�Z�� �����ꍇ�����N�m�O�A����A�C��y�j���e�m�`�����n�l��n��
�m�A���m�p�j���Z��������m�@�ցA�������푴�m���e��m�R���i�n�A ���l�j���X�����m�g�C�G�h���A�V�������X���������B�A�V�A���a�����j
�����A�V���ҕt�V�A���V�J����������X�w�L���m�g�X�B�v
�������āA1907�N�n�[�O�K���ɂ��A��̒n�̌R�̌��͎͂����d����`�����i46���j�A���D�͌��ւ����i47���j�B�̓`�B���͐l�������͕��̗A���̗p�ɋ�������̌�ʋ@�ցA�������킻�̑��̌R���i�́A���l�ɑ�����ꍇ�ł����Ă��������邱�Ƃ��ł��邪�A���a��ɕԊҋy�є������Ȃ���Ȃ���Ȃ�Ȃ��i53���Q�i�j�B�����ŁA��̌R�́A��̌R�̎��v�̂��߂Ɍ��i�����y�щۖ����Z���ɗv�����邱�Ƃ��ł��A����ɑ��Ă͂Ȃ�ׂ������Ŏx�����ƂƂ��ɁA�s�\�ȏꍇ�ɂ͗̎��s�����₩�ɑΉ����x�������̂Ƃ����i52���j�B���Ȃ킿�A����52���y��53���Q�i�ɂ�钥���E�����́A46���ɒ�߂�ꂽ�����̕s�N�̖����I�ȗ�O�ł���A46����⊮������̂Ƃ��Ĉʒu�Â�����iG.Schwarzenberger,
International Law as Applied by International Courts and
Tribunals, vol.II, 1968, p.266�j�B
�@���̂悤�ȁA�n�[�O���ɑ̌����ꂽ�������d�̌����́A�O���I�����獡���I�����ȍ~�A��v���ɂ���Ď�����L�����F�����悤�ɂȂ�B�Ⴆ�A�M���V����1830�N�̓Ɨ��ȗ�19�E20���I��ʂ��Ď��Ӎ��Ƃ̐�́E���̂̊W���J�Ԃ��Ă������ł��邪�A�M���V���͊��K�@�Ƃ��Ă�1907�N�n�[�O���ɍS������i�M���V����1899�N���͔�y������1907�N���͔�y���Ă��Ȃ��j�A�����ٔ������A���K�@����n�[�O���̓K�p���S�O���Ă��Ȃ������Ƃ����iG.Tenekides,
"L'occupation pour cause de guerre et la recente jurisprudence
grecque", 81 Journal de droit international (1954)822,
pp.828-831�j�B�e�l�L�f�X�ɂ��A��@�Ȏ��L���Y�ւ̐N�Q�ɑ���⏞�ɂ��ẮA�M���V���̍ٔ����͖����I�ɋ��K������F�߂Ă���B�e�l�L�f�X�̈��p����A�e�l�T�i�ٔ��������ɂ��A�����푈�̕K�v�㎄�L���Y�ɑ��Q��^�����ꍇ�ɂ́A��̍��͏\���Ȕ�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��iibid.,
pp.858-859, fn.72�j�B
�@�܂��A�č���1943�N�A�č�����̂����n��ɂ�����R���y�і����Ǘ��Ɋւ��ĕ�I�ȍs���w�j���̑����A���̒��ŁA��̒n�ŌR���v�����Z���ɗ^�������Q�ɑ��Ē�N����锅�������̏����ɂ��Ă��ڍׂȋK����������B����ɂ��ƁA�u����������v���ɒ����A���肷�邽�߁A�R�������͔ނ̊NJ��n��Ɉ�l�̎m�����č����鑹�Q��������ݒu���Ȃ���Ȃ�v���A���̒��͓��������̉^�c�ɐӔC���i�w�č����C�R�R���^�����}�j���A��
1943�N12��22�� FM27�|5 NAV50E�|3�x�i�|�O�h���E����B��A�݂������[�A1998�N�A65�Łj�B���������̏����葱�ɂ��ẮA���R�̏ꍇ�A�u���R�K��25-90���邢�͗��R�K��25�|25�̋K��Ɋ�Â��ĐR���������Y�̑��Q�A�������͑����܂��͔j��A�l�̏��Q�܂��͎��S�ɑ��锅�������̂��ׂẮA���̂悤�ȋK���y�ї��R�K��25�|20�̋K��ɏ]�����S�ɒ�������я�������Ȃ���Ȃ�Ȃ��v�Ƃ��ꂽ�i���A67�Łj�B
���Ȃ�ʓ��{���g�A19���I���ɊJ�������ێЉ�ɎQ������悤�ɂȂ��Ă���Ƃ������́A���������������d�̌������܂ސ펞���ۖ@�R�̂��ƂƂ��Ď���Ă����B���ɁA�J�����19���I������20���I�ɂ����ẮA�������Ƃ��ĉ��ėɌނ��邱�Ƃ��ӎ����āA�펞���ۖ@�̌��i�ȏ�����|�Ƃ��Ă��������ł���B�����푈�����鍑�C�R�w�Z�����ł���A�C�R�����̖@���ږ�ł�������������q���m�́A�p���̒����wCases
of International Law during the Chino-Japanese War�i�����푈���̍��ۖ@����j�x�i1899�N�j�ɂ����āA���{�������푈�̍ہA���[���b�p��������̉e�������A���n�����ɂ��ĕ����I�ȕ��@���Ƃ�悤�w�߂��|�ڍׂɋL�q���Ă���B����ɂ��ƁA���{�̗ɓ������㗤��Ԃ��Ȃ����z���ꂽ�����K���̊�b�ɂ��錴���́A�u�G�����̕��a�I�Z���́A�N�U�R�̈ێ��̂��ߖ��͌R���\�͂̑��i�̂��ߕs���Ȃ��̈ȊO�̎g����v������Ă͂Ȃ炸�A�܂��A�����钥���̂��ƂŐl�X�ɂ��Ȃ��ꂽ�g���͐����ɕ⏞����˂Ȃ�Ȃ����Ɓv�ł������iS.
Takahashi, Cases of International Law during the Chino-Japanese
War, 1899, p.158�j�B1899�N�n�[�O���̐�����ƂȂ�1904�N�̓��I�푈�ɂ��ẮA�������m�i�����A�����鍑��w�����A�O���Ȗ@���ψ���ψ��j�́A���{�R�̃T�n������̎��ɓ����K����47������56���܂ł��K�p����iS.Takahashi,
International Law Applied to the Russo- Japanese War, with
the Decisions of the Japanese Prize Courts,1908, p.225 ff�j�A�������B�n���̐�̂ɂ��Ă��A�������̓y�ł��邽�߂̈��̗�O�������Ă͓��{�̓n�[�O���̋K���ɍS�������Ƃ��Ă���iibid.,
pp.250-251�j�B
�܂��A�����I�O���̑�\�I�ȍ��ۖ@�w�҂̈�l�ł��������쑾�Y���m�́A�u�̎��ɉ��ēG���̎��L���Y���v�������ׂ���F�߂�ꂽ�邱�Ƃ�����A�����ɉ��Ă͎a�̔@���������ӂ�҂͖����̂ł���v�Ƃ��āA1907�N�n�[�O���̋K��46���E47���ɂӂ�A�u���L���Y�̖v���̍s�͂꓾����̌����̊��K���ۖ@��L���Ȃ邱�Ƃ́A�����ɉ��Ă͋^��e�ꂴ�鏊�ł���v�Ƃ��Ă����i���쑾�Y�w�펞���ۖ@�_�x���{�]�_�ЁA1944�N�A271�Łj�B
�@���̂悤�ɁA�펞�ɂ����鎄�����d�̌����͊e���ɂ��L���F�߂��Ă������A��O�Ƃ��Ẳ����⒥������ۂɂ͑Ή��̎x�����i���͗̎��̔��s�Ǝ���̊ҕt�E�⏞�j���s���ł��邱�ƁA�y�т܂��A�������̂́A���Y�̏��L�҂���l�i�ꍇ�ɂ���Ă͎s�����j���Ƃ������Ƃ��܂��A�L���F�߂��Ă����i�ȉ��A�����M�ҁj�B�����m�ɂ��A�旧���y�ђ����Ɋւ��鐧���͖��m���������Ă����Ƃ���A�n�[�O���ɂ���Ă��̐��������m�ɋK�肳��A�u�旧�����͒�ᢂ̐��x�̗��p�Ɉ��鎄�l�̋�ɂ�������Ƃ��A���ɒ�ᢂɊւ��ẮA�⏞�����ނ�̓������l���͎s�����Ɋm�ނ�̎�|�̋K���݂�������A�旧���y��ᢂ̐��x�͑����Ԃ����߂��̂ł���v�i���O�f���A279�Łj�B�t�F�����́A�n�[�O���52���ɂ����ė̎��̔��s�����߂��Ă��邱�Ƃɂ��āA���̖ړI�́A����ɔ������̎x��������Z���̌������m���ɂ��邽�߂ł���Ƃ��Ă���iG.
Ferrand, Des requisitions en matiere de droit international
public, 1917,p.207�j�B�V���o���c�F���o�[�K�[�͒����ɂ��āA�u���S�Ȏx�������Ȃ���Ȃ���A�����������Y�̎��I���L��(private
owner)�͗̎��錠����L����v�Ƃ��iSchwarzenberger,op.cit.,p.273�j�A��@�Ȓ����́u�⏞���s���`�����A����ɂ́A�X�̎���̏ɏ]���A�������ꂽ���Y�̏��L�҂ɑ�������s���`�����܂݂���v�Ƃ��Ă���iibid.,
p.282�j�B
�@����āA�����≟���̏ꍇ�ɂ́A���Y�̏��L�҂���l�i�Ȃ����@�l�A�ꍇ�ɂ���Ďs�����j�Ɏ���̊ҕt�⑹�Q�������錠�������邱�Ƃ͍L���F�߂��Ă������A���̌���͑����̏ꍇ�A�푈�̏I����A�����I�葱�i�����ٔ����ւ̏o�i�j�ɂ���ĂȂ���Ă����B��r�I�悭�m��ꂽ����Ƃ��ẮA1912�N�ɃM���V�����g���R�̃G�s���X���̐�̎��ɍs�����Z������̒������߂���G�s���X��������������B�Z�����M���V�����{����A�����ɑ��鑹�Q���������߂��̂ɑ��A�A�e�l�T�i�ٔ����́A�M���V���@�̓K�p�ɂ�萿�����r�������Ǝ咣�����M���V���̎咣��ނ��A�R����̂̎����͐�̍��̖@���̒n�ɋy�ڂ����̂ł͂Ȃ��Ƃ����B�����āA���ۖ@�̓M���V���@�̈ꕔ���Ȃ��Ƃ�����ʌ����ɑ���A�u���L���Y�̕s�N��F�߂鍑�ۖ@�̌������Ȃ킿�n�[�O��S���m1907�N�̃n�[�O���������n�����n�[�O�K��46���y��53���ɑ̌�����Ă��錴�����K�p�����ׂ��ł���v�Ƃ��āA�M���V�����{��s�i�����Z���̐�����F�߂��̂ł���iRequisitions
in Epirus Case, A.McNair and H.Lauterpacht eds., Annual
Digest of Public International Law Cases, Years 1925-1926,1929,
pp.481-482�j�B
���̂悤�ɍ��ڂɑ��������i���̂ق��ɂ��A�����⒥���Ɋւ���n�[�O�K���Ɍ�퍑���ᔽ���A���̌��ʁA���Y�̏��L�҂ł��鎄�l�ւ̍��Y�̊ҕt�┅����F�߂������ٔ����̔���́A�{�e�ł��łɂ݂��悤�ɔ��ɑ������݂��Ă���B
�@�������āA���ېl���@�ɂ����Ă͂��łɑ�������A�����̑��d�̌������m�����A�n�[�O���ɂ���Ă���ɖ��m�ɂ��͈̔͂�������m�ɂ��ꂽ�B�����ł́A�����̍ۂ̗̎��̔��s�┅���ɂ����āA���Y�̏��L�Ҍl�ڂɌ�����̂Ƃ����������L�����F����Ă���B�����āA�����̔����̎x�����̌���́A�e���̍����ٔ����ɂ����āA���ɕp�ɂɍs���Ă��Ă���̂ł���B
�i�Q�j�n�[�O���3���̈Ӌ`
�n�[�O���3���́A�����̃n�[�O�K�����āA�u�O�L�K���m�����j�ᔽ�V�^����퓖���҃n�A���Q�A���g�L�n�A�V�K�����m�Ӄ����t�x�L���m�g�X�B��퓖���҃n�A���m�R�����g�D�X���l���m��m�s�׃j�c�L�ӔC�����t�v�ƒ�߂�B�R���\�����ɂ���@�s�ׂɂ��č������ۓI�ȐӔC�����Ƃ͊m�����ꂽ���ۖ@�̌����ł��邪�iCh.Rousseau,
Droit international public,1983, p.41�j�A�n�[�O���3���͌�퓖�������R���\�����́u��̍s�ׂɂ��v�ӔC���Ɩ������ɋK�肵�A�\�����̎��i�A�ߎ��̑��ݓ��̗v���Ȃ��ɍ\�����̂��ׂĂ̍s�ׂ̐ӔC�����ɕ��킵�߂Ă���B�����āA���@�K���Ȃ킿�n�[�O�K���̈ᔽ�ɂ�����R���\�����̍s�ׂɂ��āA���Ƃ̐ӔC�y�сA�ᔽ�s�ׂɗR�����鑹�Q�ɑ�����K�������߂�i���c�v��w���ېl���@�i�V�Łj�x�L�M���A1993�N�A194�Łj�B�폟��������I�ɗv������u�����v�ƈقȂ�A��@�s�ׂɂ�鑹�Q�̔�����O��Ƃ���{���́u���Q�����v�Ƃ�����K��ł���i���]�[�l�Y�w���ۖ@��̔����⏞���x�������A1974�N�A27�Łj�B
�@�{�����܂ޑ����̐��⏞�ٔ��ɂ�����_�_�́A�{�����A�n�[�O�K���̈ᔽ�̔�Q�҂���l�ւ̔������܂݂��邩�Ƃ����_�ɑ�����B���̓_�ɂ��āA�܂��A���ۖ@�̒��ł����ېl���@���A��������펞�ɂ����鎄�l�̌������m�������Ă����Ƃ��������������A��ɂ݂��悤�ɁA�������d�̌����Ɋ�Â����Q��������Y�ҕt�Ƃ������s�����ێЉ�ɂ����ĖȁX�ƍs���Ă������ƂɏƂ点�A��@�s�ׂɂ�鑹�Q�����̑�����́u��Q�ҁv�ł���Ƃ������߂ɑ������x�̑Ó��������邱�Ƃ͔ے肵�������B�펞���ۖ@�Ɋւ���_�j�Ȓ����𑽂��c�����O�f�̃t�����X�̍��ۖ@�w�҃����j���b�N���A�����@�ɂ�����s�@�s�ׂ̑��Q�����`����z�N���A��Ɉ��p�����悤�Ƀn�[�O���R���ɂ��āu�����Ƃ��āA�i�����N�����B��̎��i��L���Ă���̂́A���Q��^�����s�ׂ̔�Q�҂ł���v�iA.
Merignhac, loc.cit.,�����M�ҁA�ȉ������j�Əq�ׁA�������t�����X�̒����ȍ��ۖ@�w�҃t�H�[�V�[�����A�u����̖@�K����Ɉᔽ������퓖�����ɑ��A���̕s�@�s�ׂ̔�Q�҂ɑ���������(indemniser
les victimes)�`�����ۂ����A1907�N10��18���̃n�[�O���R���̍��ېӔC�́A�l�̍��Y�ɑ��ĉ�����ꂽ���Q�Ɠ��l�A�g�̂ɑ��ĉ�����ꂽ���Q�ɂ��K�p�����v�Ɖ�����Ă���iP.
Fauchille, loc.cit.�j�̂́A���ېl���@�̉��߂Ƃ��Ăނ��뎩�R�ł���Ƃ������悤�B
�@����ɁA�����߂̕⑫�I��i�Ƃ��āA�����̋N���ߒ�����������A���̒�Ď�|�͖{���A��Q�Ҍl�ɔ�����^���邱�Ƃł��������Ƃ����炩�ɂȂ�B�{���́A��Q��n�[�O���a��c�ɂ����āA�h�C�c�̑�\�M�����f���ɂ���Ē�Ă��ꂽ���̂ł��邪�A�����̃h�C�c��Ă̏́A�ȉ��̒ʂ�ł�����(E.Lemonon,
La Seconde Conference de la Paix, La Haye (juin-octobre
1907), 1912, pp.299-300)�B�u��P�� �{�K���̋K��Ɉᔽ���A�����̎�(personnes
neutres)�ɑ��Q��^������퍑�́A�ނ�ɐ����������s�@�s�ׂɂ��A�ނ�ɔ�������(dedommager ces
personnes)�`�����B���Y��퍑�́A���̌R�����\������l���ɂ���čs��ꂽ���ׂĂ̍s�ׂɂ��ĐӔC���B���������Q�y�юx�����锅���̌���́A�����ɂ��x�������Ȃ���Ȃ���A��퍑�����̌��肪���ʂ̊ԌR���s���Ɨ������Ȃ��ƍl����ꍇ�ɂ́A����ɉ������邱�Ƃ��ł���B
��Q�� �G���̎�(personne de la Partie adverse)�ɑ��Q��^�����ᔽ�̏ꍇ�́A����(indemnisation)�̖��͘a���̒������ɉ����������̂Ƃ���B�v���̒�ẮA1907�N�V��31���ɏ��߂ĉ�c�Ō�������A�S�̂Ƃ��Ă͊e���̎x�������B�A�����̍ہA�C�M���X��t�����X���̑�\����w�E���ꂽ�̂́A�����������ƌ�퍑�����Ƃ̊Ԃɋ�ʂ������Ă���_���e�F�ł��Ȃ��Ƃ������Ƃł������B���̂��߁A�����̃h�C�c��ẮA��P���̢�����̎ҁv�Ƃ����������u�����ꂩ�̎�(personnes
quelconques)�v�Ƃ���C����������ꂽ��A�ŏI�I�Ɍ��݂̌`�ō̑��Ɏ������̂ł���(ibid.,pp.300-301)�B���������n�[�O���R���̋N���ߒ��ɂ��ẮA���ېl���@�̐��E�I���Ђł���I�����_�̃J���X�z�[���F�����m�����̏ڍׂȌ����ɂ����Ė��炩�ɂ����Ƃ���ł�����B�{���́A�n�[�O���̈ᔽ�ɂ�葹�Q�����l���������邱�Ƃ�ړI�Ƃ��Ē�Ă���A����ɑ��ẮA���������ƌ�퍑�����Ƃ̊Ԃň������قɂ��Ă����_�ȊO�͓��ɑ����̔ᔻ�͂Ȃ������B�܂�A�{���̒�Ď�|�͔�Q�Ҍl�ɔ�����^���邱�Ƃł���A���̊�{�I�Ȏ�|���̂ɂ��ẮA���̑�\������^�O�͒���Ȃ������̂ł���iF.
Kalshoven, "State Responsibility for Warlike Acts of
the Armed Forces", 40 International and Comparative
Law Quarterly (1991),pp.827-858�j�B
�@�J���X�z�[���F�����m���ڍׂɖ��炩�ɂ����n�[�O���3���̋N�����̎�|�́A�I�����_�l�ߗ��ɂ��⏞�����Ɋւ��鎖�Ăœ����m���Ӓ�ӌ������o���܂��ؐl�Ƃ��ďo�삵�����Ɠ���ʂ��āA���{�̔���ɂ����Ă����łɈꕔ�������Ƃ���ƂȂ��Ă���B��ɂ��ӂꂽ�ʂ�A1998�i����10�j�N11��30���̓����n�ٔ����i���^991��262�Łj�́A�����m�̎咣���ăn�[�O���3���̋N���ߒ����ڍׂɌ����������ʁA�����͔�Q�Ҍl�̋~�ρu�����v�ړI�Ƃ�����̂ł��������Ƃ͔F�߂���A�ƔF�肷��Ɏ����Ă���B
�i�R�j�����̓K�p�\���ۓI��@�ƍ����I��@
�@�������āA��Q�҂ɑ��锅�����܂߂��|�ňᔽ���ɔ����̐ӔC���ۂ�����ŁA�n�[�O���R���́A���̗��s�ɂ��Ĉ��̎葱���߂Ă͂��Ȃ��B���ۖ@�K�͂̑命���̂��̂������ł���悤�ɁA���Ƃɑ��ċ`�����ۂ��A�`���̋�̓I�ȗ��s���@�ɂ��ẮA���ɒ�߂������Ă��Ȃ��B
�@���̓_�ɂ��čl����ɁA�n�[�O���3���̏ꍇ�A�����ɂ́A�퓬�s�ׂ��I�����u�a����������ۂɁA���ƊԂœK���Ȏ挈�߂ɂ�菈�����邱�Ƃ����|�I�ɑ����Ȃ�ł��낤�B�����j���b�N���F�߂Ă���悤�ɁA�l���펞���Ɏ���ӔC�Njy�̎葱���Ƃ邱�Ƃ͌������Ƃ��ē���A����ɔ䂵�č��Ƃ��A����ɑ����̌l�̐������ꊇ���č��ƊԂŌ�����A��l���s�����͂͂邩�Ɍ��ʓI���o�ϓI�ɕ⏞�������������邱�ƂɂȂ�iMerignhac,�@loc.cit.�j�B���̂悤�ɍ��ƊԂŌl�̔����������킹�Đ�㏈�����Ȃ����ꍇ�A����́A���Ƃ��l�̐��������グ�č��ƊԂŌ�����Ƃ����O��ی쌠�̍s�g�ɗގ����������Ƃ������ƂɂȂ낤�i�����ɂ́A�O��ی쌠�́A�����ɂ����Ď����I�ӎv�ŊO���ɏ��݁E���Z���Ă��鎩�������s���Ȉ��������ʓI�~�ς��Ȃ������ꍇ�ɍs�g����鍑�Ƃ̌����ł���A�펞�ɂ����č������O���R����������Q�̐��������Ƃ����グ��Ƃ����ꍇ�ɓK������T�O�ł͂Ȃ��j�B�A���A�����̏ꍇ�A���ƊԂ̔����̎Z��́A��@�s�ׂɊ�Â����Q�̊z�Ƃ��������A�폟�����푈�̂��߂ɔ�������ׂĂ̑��Q�ɑ����I�x�����Ƃ����`���Ƃ�A�l�̋~�ς̂��ߏ\���Ȋz���z�������Ƃ͌���Ȃ��̂����Ԃł���B�܂��A�����Ύw�E�������_�Ƃ��āA�{���ɂ����ӔC�͖{���A���s�ɂ�����炸��퓖�������ꂼ�ꂪ�����̋K���ᔽ�ɂ��ĕ����ׂ����̂ł���ɂ�������炸�A�푈�I�����̈��|�I�ȗ͊W����A������A�s�퍑�̐ӔC�݂̂��Njy����Ă������Ƃ��ے�ł��Ȃ��i���c�O�f���A194�|195�Łj�B
�@�n�[�O��̑����ꂽ1907�N�ȍ~�̑�K�͂Ȑ�㏈���Ƃ��āA��ꎟ����̃��F���T�C�����̐��́A�n�[�O���3������߂�u���Q�����v�̎�|����荞�݂A���ƊԂ̏��ŁA�����̎����Q�ɑ��锅�������̂��߂̍��ۓI�Ȏ葱��݂�����ł���B�푈�̌��ʁA�폟�����s�퍑�ɗv�����锅���̓��e�́A�`���I�ɂ́u�����v(indemnite;
indemnity)�A���Ȃ킿�A�푈�ɂ����������̏��҂ł������i�Ⴆ�A1870�|1871�N�̕����푈��̃t�����N�t���g���B���]�O�f���A12�Łj�B���{�̗�ł����A�����푈��̉��֏��Ő������{�Ɏx����������������ɂ�����B����ɑ��A���Ԑl�̔�Q�����ĂȂ���K�͂ɂȂ�����ꎟ���ɂ����ẮA��㏈���ɂ�����A�폟�����s�퍑�ɑ����������߂�Ƃ��������̐푈�����̕��@�ɉ����A�V���ɁA�^�������Q�ɑ���u���Q����(reparation
des dommages; compensation�j�v�Ƃ����l���������������悤�ɂȂ�B���ꂪ�A��ꎟ����̃��F���T�C�����a��̈�A�̕��a���ł���B�@
�@��ꎟ����A�h�C�c�Ƃ��̓��������A�����ƒ����������a���ł́A�h�C�c�y�ѓ������́A���̐N���ɂ���ċ������푈�̌��ʁA�u�A�����y�ы��������{�A���тɂ��̍������������̑����y�ё��Q�v�ɑ��ĐӔC������Ƃ��ꂽ�i�h�C�c�Ƃ̊Ԃ̃��F���T�C�����231���A�y�т��ꂼ��̕��a���̊Y���K��j�B�����āA�h�C�c���������́A��풆�ɗ��A�C�A��̐N���ɂ���āu�A���y�ы������̖��Ԑl���тɂ��̍��Y�ɑ��ĉ�����ꂽ��̑��Q�ɑ��āA�܂���ʂɖ{�m��W�ґ�P�n���ւ̑�ꕍ�����ɋK�肳��邷�ׂĂ̑��Q�ɑ��āA�������s���v���Ƃƒ�߂�ꂽ�i���F���T�C�����232���Q�i�A�y�т��ꂼ��̕��a���̊Y���K��B��ꕍ�����Ƃ́A�퓬�s�ׂ̒��ړI���ʂƂ��āA���Ԑl�̐g�̂����Q���������Q�A���́A���S�������Ƃ��ɂ͂��̕}�{�Ƒ��ɗ^�������Q�i�P���j�A���Ԑl�ɑ��čs�����c�s�s�ׁA�\�͍s�ׁA�s�ҍs�ׁi�Q���j�A��̂Ȃ����N���n��ɂ����閯�Ԑl�̌��N�A�J���\�́A���_�ɑ���N�Q�s�ׁi�R���j�A�ߗ��̋s�҂ɂ���Ĉ����N�����ꂽ���Q�i�S���j�A�����J�����ۂ��ꂽ���Ԑl�̎����Q�i�W���j�A���Ԑl�ɉۂ��������A���ۋ����̑��̋��������ɂ�鑹�Q�i10���j��10���ڂ̎����ɂ��āA�h�C�c�ɑ������ł��邱�Ƃƒ�߂����̂ł���j�B����ɁA�A�����y�ы������̍����́A�펞���ɓG���̗̓y���ɂ������e���̍��Y�A�������͗��v�ɂ������Q�ɑ��A�h�C�c�����G�����{�����āA���Ő݂��鍬�����ٍٔ����ɒ��ځA���Q�����̑i�����N���錠����F�߂�ꂽ�i���F���T�C�����a���297���ie�j�y�ё��̕��a���̊Y���K��j�B
�@�x���T�C����̈�A�̕��a���ł��������K�肪�݂���ꂽ�̂́A��ꎟ��킪�A����܂ł̐푈�Ɣ�r�ł��Ȃ�����ȋ]���Ԑl�ɉ�������̂ł��������Ƃɂ��Ƃ��낪�傫���B�h�C�c���׃��M�[��t�����X�ő�K�͂Ȕj��s�ׂ�W�J���A���Ԑl�̍��Y�ɂ��r��Ȕ�Q��^�������Ԃ��āA�A������]�́A���ł�1916�N���܂łɂ́A���Ԑl��
����Q�ɑ��鑹�Q�������h�C�c�ɗv�����鐭������肵�Ă����Ƃ���邪�A�����̃C�M���X�ł��������C�h�E�W���[�W�͂���ɂ����̂悤�ɏq�ׂĂ���B�u�s�@�s�҂ɂ���ė^����ꂽ���Q�ɂ��Ĕ���(compensation)���x�����ӔC��...���ׂĂ̕��������ꂽ�Љ�ɂ����钆�j�I�Ȗ@�����̈�ł���B���Ƃ́A���̊�{�I�Ȗ@�����̓K�p����Ƃ�邱�Ƃ͂ł��Ȃ��v�iD.Lloyd
George, The Truth about the Peace Treaties, vol.I,1938,
pp.436-437�j�B�u�����́A���F���T�C�����ɂ���Ĕ������ꂽ�킯�ł͂Ȃ��B�D�D�D19���I�̏��߂ɂ́A�a�������Ƃ��Ďx����ꂽ�������A�m���D�Ȃǂ́n�e��Ŗ�ȕ��@�̑���ɂȂ����B�D�D�D�����́A�푈�ɂ͌���̐푈�̂悤�Ȕ���ȋ��z�͂����炸�A�������Q���A���E���ōs��ꂽ�j��ɔ�r����킸���Ȃ��̂ł������v�iibid.,
pp.439-440�j�B�u���̎��܂ł̐퓬�̗��j�S�̂̒��ŁA[��ꎟ��킪]��������p�y�т��ꂪ�����炵���j��̒��x�ƓO�ꐫ�ɔ䂵������̂͂Ȃ������B...1916�N�܂łɂ́A�����̖��́A1914�N�ɂ͍l�����Ă��Ȃ������قǂ̑傫�����Ȃ��Ă����iibid.,
pp.29-30�j�B
�����ɖ��炩�ɂ���Ă���悤�ɁA���F���T�C�����ŘA�����̍����ւ̕⏞���߂����Ƃ̍��{�ɂ������̂́A���Q�ɑ��锅���Ƃ�����ʌ����ł���A�n�[�O���R���̗v�����Ă��鑹�Q�������̂��̂Ƃ�����@���ł������B
�t�H�[�V�[���́A�s�@�s�ׂɑ��鑹�Q�����̌��������F���T�C�����ɓK�p���ꂽ�|�����̂悤�ɏq�ׂĂ���B
�u�푈���Q�̔�Q�҂ł���l�́A���͔ނ�̗��v���Ă��鍑�Ƃ́A���Q�������N��������퍑�ɑ��āA�~�ς����߂邱�Ƃ��ł���̂��A�܂��ǂ͈̔͂łł���̂��B�܂��A�����~�ώ�i������Ƃ���A���̍����͉����B�|�t���Ɋ�Â��A�܂�������ɂ��悷�ׂĂ̍��̎���@�ɒ�߂��Ă��鑈�����Ȃ����R�@�̋K���́A�w���l�ɑ��Q��������l�̍s�ׂ͂��ׂāA���̎҂ɑ��A���������`���킹��x�Ƃ������Ƃł���i�t�����X���@1328���j�B�s�@�s�ׂ̊ϔO���܈ӂ��邱�̋K���́A�l�Ɠ��l�A�����̂ɂ����Ă͂܂�B
...1914�|1918�N�̐��E���̏I���̕��a���ɂ����Ē����̒鍑�m���h�C�c�E�I�[�X�g���A�n�ɉۂ����̂́A�A��������L�̍l���Ɏ��������Ƃɂ��B�������āA1919�N�U��28���̃h�C�c�Ƃ̃��F���T�C�����́A�h�C�c���s�����푈���s���Ȃ��̂ł������Ƃ����������q�ׂ���A231����232���ɂ����āA�h�C�c�鍑�́w�A�����y�т��̍������푈�̌��ʔ�������ׂĂ̑����y�ё��Q�ɑ��āx�⏞�̋`�����Ɛ錾����...�v�iFauchille,op.cit.,pp.
309-310�j�B
����ɒ��B�ɂ́A�K�[�i�[�́A���F���T�C�����ɂ�����l�⏞�ƃn�[�O���R���̊W�ɂ��āA�ȉ��̂悤�ɕ]�����Ă���B
�u��Q��n�[�O��c�́A����̖@�K����Ɋւ���n�[�O���̋֎~�Ɉᔽ���Čl�ɗ^����ꂽ���Q�ɑ��A�l�ɔ�������(indemnify
individuals)��퍑�̋`�����m�����邱�Ƃɂ���āA�������ق̈�`�Ԃ��K�肵���B...���̐ӔC�́A���Q�����l���ڂɂł͂Ȃ��A���̖{���ɑ��Ă̂��̂ł���悤�ɂ�������B...���̋K��ɏ]���āA���a���̓h�C�c�ɑ��A�푈�@�̈ᔽ�ɂ���čs��ꂽ���Q�ɑ��Ă݂̂łȂ��A�u�A�����̖��Ԑl�Ƃ��̍��Y�ɑ��ė^����ꂽ���ׂĂ̑��Q�v�ɑ��Ă�����(compensation)��v�������B...����́A��L�̃n�[�O���̋K�������s���邽�߂̎��݂��Ȃ��ꂽ�ŏ��̗�ł���v�iJ.W.,Garner,
International Law and the World Order,vol.I,1920, pp.469-470�j�B
�@�Ȃ��A�������ă��F���T�C�����ɂ��A��Q�����l�ɂ͍��ۓI�葱�Ŕ��������߂铹���J���ꂽ���A�����ɁA�e���ł͂���ɑO�サ�āA�l�������邱�Ƃ��m�ۂ��邽�߁A�h�C�c�l���Y�̐��Z�ɂ�锅���ւ̏[�����Ɋւ��鍑���@�̐��肪�s��ꂽ�B�t�H�[�V�[���́A�u[��ꎟ���̔j��I���i�ɂ����]���C�R�̂��߂Ɂw�������錠���x��錾���邾���ł͏\���łȂ�����...���S�Ȕ������m�ۂ��邽�߂ɂ́A�N�����͐�̂��ꂽ���ɂ����Đ푈�ɂ�葹�Q�����Z��(habitants)�ɑ��A�ނ�l�����(dans
leur personne meme)�A�~�ς����߂錠����F�߂Ȃ���Ȃ�Ȃ������v(���������j�Ƃ��A����͂Ƃ�킯�t�����X�ŁA�����@�𐧒肵�l�̢�����v�����Ď��{���ꂽ�Əq�ׂĂ���(Fauchille,
op.cit., pp.312-313�j�B
�@���F���T�C�����ɂ�����l�ւ̔����́A�]���A�l�ɍ��ۓI�Ȑ����葱�ւ̃A�N�Z�X��F�߂��Ƃ����_�Œ��ڂ���邱�Ƃ��قƂ�ǂł������B�������A���F���T�C�����́A�l�ɂ�钼�ړI�Ȑ��������ŔF�߂����ł��邪�A����͒P�ɍ��ۓI�葱�̑n�݂Ƃ����ʂł̂ݕ]�������ׂ����̂ł͂Ȃ��A���̊�b�Ƃ��Čl�̎��̓I�����y�ё��Q�����̈�ʌ��������邱�Ƃ��Y����Ă͂Ȃ�Ȃ��B�u���Q����Ƃ���ɔ�������v�Ƃ������Q�����̖@�����n�[�O���R���̎�|�Ȃ̂ł���A���ۓI�葱���n���ď��߂āA�l�̎��̓I�����������ɔ��������킯�ł͂Ȃ��B���F���T�C�����́A�n�[�O���R���̎�|�����Ƃ����`�Ŏ�����������̗�ł����āA�����܂ł��l�̎��̓I������O��Ƃ��Ă����Ƃ݂�ׂ��ł���B
�Ȃ��A��ꎟ����̃��F���T�C�����̐��̂ق��A�����̑����̏����a���ɂ����Ă��A���Ԑl�̎���Q�ɂ��Ĕ�Q�Ҍl�ւ̔������F�߂��Ă��邱�Ƃ��t�L���ׂ��ł��낤�B��ꎟ���E��킪���̐��E�I�ȑS�ʐ푈�ł������Ƃ���A����͂���ɂ��������K�͂̉�œI�Ȑ푈�ł������B����䂦�A�����̕��a���́A�S�ʐ푈�Ƃ��Ă̐��i�A���Ԑl�ɉ�����ꂽ�O�㖢���̔�Q�̑傫���f���āA����܂ł̏���������ɍL�����������l�ɗ^���Ă���iRousseau,
Le droit des conflits armes,�@op.cit.,p.518)�B���Ȃ킿�A1947�N�ɁA�C�^���A�A�u���K���A�A�n���K���[�A���[�}�j�A�A�t�B�������h�ƘA�����Ƃ̊ԂɌ��ꂽ���a���́A���ꂼ��̍��i�C�^���A���j�́A���̗̓y���ɂ�����A���������̍��Y�ւ̔�Q�ɂ��āA�����̍��Y���w������̂ɕK�v�Ȋz�̎O���̓�̔������x�����`�����ƒ�߂��B�����Ă���ɔ����A�A�����e���͍����@�ŁA�����x�����A���Y�̍Č����͑�ւ̂��߂̕։v�Ȃǂ̕��@�ł̔����������K�肵��(A.Fraleigh,"Compensation
for War Damages to American Property in Allied Countries",
41 American Journal of International Law 748 (1947), pp.748-749�j�B���{�̏ꍇ�́A�T���t�����V�X�R���a���ɂ����ĘA��������������������A���������߂鍑�͌ʂɌ����邱�ƂƂ��ꂽ���A���̂悤�ɐ��{�ԂŔ�����������A�����l�ւ̔����[�u����߂Ȃ��Ƃ�����͌����Ēʗ�ł͂Ȃ��������Ƃɒ��ӂ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
�@�Ȃ����{�ɂ��ẮA���{��1931�N���璆���Ƃ̐퓬���J�n���A���Ԑl�ɂ��r��Ȕ�Q��^�������A���ł�1931�N�̏�C���ςɊւ��āA�M�v�~�����m���A�u�x�ߑ��y�ё�O���l�̖ւ肽��A���͖ւ肽��Ə̂���A���Y���Q�v�ɂ��A��ɂ��ꕔ�ӂꂽ�ʂ�A���̂悤�ɘ_���Ă������Ƃ����L�����ׂ��ł��낤�i�����M�ҁj�B
�u��@�̂��̂ł����Ă݂�A�����̐ӔC���c�R�V�ɔ��ӂ��Ƃ͂��ꖒ�_�Ȃ����ł���B�ނ��펞�̔����͖��Ȃ��̂ŁA�K�������Q�����V���s�ӂׂ����̂Ƃ͌��炸�A���҂͔s�҂���G�̐��{�����ĔV�������̐ӂ��c�炵�ނ邱�Ƃ�����B�u�a�k���ɉ��Đ폟�҂͐�s�҂Ɍ��đ����͏������ۂ��邪�A���̏����z�͐�s���̎��l�̍��Y���Q�ɛ�����폟���̔����ӔC�z���T�����ėv�����邱�Ƃ�����B���̏ꍇ�ɂ́A���Q�����͐�s���̐��{�����̐l���Ɍ��Ă������Ƃ��ӂ��ƂɌ��ǂȂ�̂ł���B����ǂ��A����͋��҂��e���̖N��ł�鏊�̓���̐ӔC�]�Ŗ@�ł���B�������z����ٗႠ��ƂāA��@�̍s�ׂɂ͕K�R�ӔC�����ӂƂ��Ӎ��{�̌����͓����Ȃ��v�i�M�v�O�f���A357�Łj�B
�@�u1907�N�̗���@�K���ដ���3���ɂ́A�w�O�L�K���m�����j�ᔽ�V�^������c���҃n���Q�A���g�L�n�V�K�����m�Ӄ����t�x�L���m�g�X�B����c���҃n���m�R�����g���X���l���m��m�s�׃j�t�ӔC�����t�x�Ƃ���B�O�L�K���Ƃ͓�����ɕ������鏊�̗���@�K����K�����w���B�̂ɑ��Q����ɕ���Ĕ����̐ӂЁA������횠���{�����̌R���̑g�����̍s�ׂɕt�ӔC�ӂ̂́A��痤��@�K����K���̋K�肷�鏔�����̈ᔽ�s�ׂł���B����ǂ��A���̌̂��Ȃē��K���ȊO�̌��@�K�̈ᔽ�ɏA�Ă͑S�R�ӔC�ӂɋy�����ĉȂ�Ƃ��ӌ��_�ӂ��̂ł͂Ȃ��B�}�����ۖ@����ƍ����@����Ƃ��͂��A䑂��И��̝|���Ɉᔽ����A�V�ɏA�Đӂӂׂ����̂��邱�Ƃ͑��Ă̏ꍇ��ʂ��Ĉ�т��錴���ł���B���@�K�͂��̗���ɌW��ƁA�C��ɌW��Ƥ�������ɌW��Ƃ��͂��A���Ă��̈ᔽ�҂ɛ����ĔV���ӔC�̕��^��v������B���T�J����@�K���ដ��́A���̖}��Ƃ��ē������̗���@�K����K���̈ᔽ�Ɋւ����ɐӔC�̋A���w�����܂ŁT����v�i���A357�|358�Łj�B
�@�u��횠�̈�@�s�ׂɗR��đ��Q�����ƔF�ނ鎄�l�́A���̌�킪�@���Ȃ錴���Ɋ�ċN�����̂ɂ�����A�c�R�~�ς����ނ�̌���������B�D�D�D��Ɍ�횠�̈�@�s�ׁi���ɂɂ���Ƃ��āj�Ɉ��鑹�Q�������Ɋւ��ẮA�@���ɉ��Q�����Վ��̋��d�Ȃ錩��������Ƃ������ŁA�����������҂͕s�����Ǝv�ӏꍇ�ɂ́A�������{�ɑi�ւĔV��މ䐭�{�Ԃ̊O����ƈׂ�����̓�������v�i���A364�Łj�B
�@���̂悤�ɁA��ꎟ���̖��Ԑl�̔�Q�Ƃ��̕⏞�ɂ��ē����̐����w���ҋy�э��ۖ@�w�҂��q�ׁA�܂�����̖��Ԑl�̔�Q�ɂ��Ă��T���t�����V�X�R���ȊO�̑����̏��Œ�߂��Ă����悤�ɁA���Ԑl�̐g�́E���Y�ւ̔�Q���r��ƂȂ�������̐푈�ɂ����ẮA���Ԑl�l�̎���Q�ɑ��鑹�Q�����͐�㏈���̂���߂ďd�v�Ȉ�Ƃ��Ď�舵���Ă����B���̂悤�Ȏ戵���́A����̐푈�ɂ����Ė��Ԑl�̔�Q�����債���Ƃ������Ƃ̂ق��ɁA���������A���\�[�̎v�z�̌n�����p��18���I���ȗ��̍��ېl���@�̔��W�ɂ����āA�������d�̌������m�łƂ��Ċm�����Ă������Ƃ�O��Ƃ�����̂ł��邱�Ƃ͂����܂ł��Ȃ��B����̐�㏈���́A�n�[�O���ɑ̌�����Ă��鎄�����d�̌����܂��A���̐N�Q�ɑ��鑹�Q�����Ƃ��āA�ꍇ�ɉ������ۓI�y�э����I��@���d�˗p���đΏ����Ă��Ă���̂ł���B���F���T�C�����y�т�������t�����X�����@�̂悤�Ȍl�����̑̐��́A�����āA����������ď��߂Čl�̎��̓I���������n�݂������̂Ƃ݂邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B����́A���ۖ@��m�������������d�̌����܂��A������N�Q���ꂽ�l�ɋ~�ς��錠�������邱�Ƃ�O��Ƃ��āA���̎����̎葱�Ƃ��č��ۓI�y�э����I�葱��݂������̂Ƃ݂�ׂ��ł���B�M�v���m����Ɉ��p�����Ō�̕����ŁA�����܂Ŕ�Q�Ҍl���~�ς��錠����O��Ƃ��A���̎�����i�Ƃ��Ď������{�ɑi���ĊO����Ƃ��铹�ɂ��ďq�ׂĂ���B
�i�S�j�ԋ���ƌl�������̊W
�@�����ŁA���Ɍ�������Ȃ���Ȃ�Ȃ��d�v�Ș_�_�́A�l�������Q�Ɋւ��āA�l�̖{���Ɖ��Q���Ƃ̊Ԃŋ��肪��������Ă���A�����ň��̉������}���Ă��邩���邢�͔�������������Ă���ꍇ�ɁA�l���Ȃ����Q���ɑ��鐿�������咣���邱�Ƃ��ł��邩�Ƃ������Ƃł���B
�@�]���A���ؐ������������������������Ƃ̊W�œ��{���{���Ƃ��Ă��������́A����������@�s�ׂɂ�葹�Q�������ꍇ�ɖ{�����Ƃ������ł���̂͊O��ی쌠�̍s�g�����ł����āA��Q�Ҍl�̈�g�ɐꑮ���錠�������ł�������̂ł͂Ȃ��A�Ƃ������̂ł������i�u��������ؐ���������ɂ����܂��ė����Ԃ̐������̖��͍ŏI�����S�ɉ��������킯�ł������܂��B���̈Ӗ�����Ƃ���ł������܂����D�D�D����͓��ؗ��������ƂƂ��Ď����Ă���܂��O��ی쌠�𑊌݂ɕ��������Ƃ������Ƃł������܂��v�i1991�N�W��27���Q�c�@�\�Z�ψ����c�^��R��10�Łj�B�����������́A�{���̂悤�Ȃ�������⏞�ٔ��ɂ����ẮA���{�͈�]���āA�l�����̖��͍��ƊԂ̋���ł��ׂĉ������݂ł���Ƃ̌������Ƃ邱�Ƃ������Ȃ����B����ɑ��A�O�����{�̑��A�Ⴆ�Β�����1995�N�A���������錾�ɂ����Ē������s�������������͌l�̐������̕������܂ނ��̂łȂ��Ƃ̌��������Ɏ����Ă���B
�@���̓_�ɂ��A���Ƃ��O��I�ɉ�����}�������Ƃɂ��A���ʓI�ɔ�Q�Ҍl�ɏ\���ȋ~�ς��^����ꂽ�ꍇ��ʂƂ��āA�~�ς��\���łȂ����A���邢�͍ŏ����甅������������Ă��܂��Ă���ꍇ�ɂ́A���ېl���@�ŕی삳��Ă���l�̌��������ƊԂ̋���ł��ׂď��ł������̂Ƃ݂邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B
�@���ɁA�n�[�O���͌l�̎������d�m�ɋK�肵�A�܂�����3���́A��@�ȍs�ׂɂ���Ĕ�Q�����l�̋~�ς��d�v�ȖړI�̈�Ƃ��ċK�肳�ꂽ���̂ł��������ƂɊӂ݂�A�ᔽ����3���̎�|�ɏ]�����������s�킸�A�~�ς���Ȃ���Q���������A3���̋`���͗��s����Ă��炸�A�l���炪���Q���ɐ������铙�̓K���ȕ��@�ł��̗��s�����߂�\���͔r������Ȃ����̂ƍl����ׂ��ł���B�n�[�O���R���́A���l�̌������߂����̂Ƃ܂ł͂������A�����̏ꍇ�͍��ƊԂŗ��s����邱�Ƃ�\�肵�����̂ł���Ƃ��Ă��A���Ȃ��Ƃ��A3���̒�߂�`���̗��s���ʂ�����Ă��Ȃ�����́A���Ƃƕ���Ōl�ɂ��A�K���Ȏ葱�ɂ�锅�����������������s���đ��݂���ƍl������B
���Ƃ̌����ƌl�̌����̕����Ƃ������������u�������̕��s��(Anspruchsparallelitat)�v�́A�ŋ߂ł́A1996�N�T��13���̃h�C�c�A�M���@�ٔ����������A�펞���̃��_���l�̋����J���Ɋւ��鎖�����߂���{���n���ٔ����̐R���v���ɑ��ďo�������f�Ŗ��炩�ɂ����Ƃ���ł�����B����ɂ��ƁA�|�[�����h�̔��������錾��h�C�c�E�C�X���G���Ԃ̐��{�ԋ���ɂ���Čl�̍����@��̐������͏��ł����A�l�̐������͍��ۖ@��̐������ƕ��s���đ��݂��A���ƊԂ̉����ɂ���Čl�̐�������F�߂鍑���葱�̐ݒ肪�W������킯�ł͂Ȃ��iBVersG,2BvL33/93,
EuGRZ(1996)407, S.411.�L�n����u�ߑ��`�E���⏞�E�@���_�v�@������68��11���A1997�N���Q�Ɓj�B�{�����́A���ƊԂ̔���(Reparation)�ƁA�l�����߂��锅��(Entschadigung)�Ƃm�ɋ�ʂ��A���Ɗԋ���ɂ����锅���̕����ɂ���Čl�̐������܂ŕ������ꂤ����̂ł͂Ȃ��Ɣ��������B
�@���ɁA���ېl���@�ᔽ�̔�Q�҂̌����Ɋւ��ẮA�����A���ېl���@���̂������I�ȋK��������Ă���B1949�N�̃W���l�[�u4���͂��ꂼ��6�^6�^6�^7���ŁA�ی삳�ꂽ�҂̒n�ʂɕs���ȉe�����y�ڂ��܂������̎҂̌����𐧌�����悤�ȕʂ̓��ʋ����������邱�Ƃ��֎~���Ă���B�����āA�ԏ\�����ۈψ���s���̒��߂͂����̏����ɂ��A�u���a���̒����ɂ������ẮA�������͌����Ƃ��āA�푈��Q��ʂɊւ�����y�ѐ푈�J�n�ɑ���ӔC�Ɋւ�������A�K���ƍl������@�ŏ������邱�Ƃ��ł���B�����ŁA�������́A�푈�ƍߐl�̑i�ǂ��T���邱�Ƃ�A�W���l�[�u�����y�т��̋c�菑�̋K���̈ᔽ�̔�Q�҂��������錠����ے肷�邱�Ƃ͂ł��Ȃ��v�iCommentary,�@p.1055.�����M�ҁj�Ƃ��Ă���̂ł���B�]���āA���ېl���@�̋K���̈ᔽ�ɑ��锅��������������邱�Ƃ́A���݂ł́A���̂悤�ȍ��ېl���@�̖����I�ȋ֎~�ɔ�������̂ɂȂ��Ă���iM.Sassoli,"State
Responsibility for Violations of International Humanitarian
Law", 84 International Review of the Red Cross 401(2002),
p.419.�j
�@���{�̔���ł́A����܂ŗႦ�A�I�����_�l�ߗ��̑��Q�������������ɂ�����O�f�̓����n�ٔ����́A�n�[�O���R�����l�̋~�ρu�����v�ړI�Ƃ��Ă������Ƃ͔F�߂���A�Ƃ��A���̈���ŁA�l�̐����ɂ͊O��ی쌠���u�O��Ƃ���Ă����Ɛ��������v�A�Əq�ׂ�ɂƂǂ܂��Ă����B�������A�����_���I�ɍl����A�l�̐����͊O��ی쌠��O��Ƃ���Ƃ������Ƃ͂��Ȃ킿�A�O��ی쌠�̍s�g�����ɂ���ĕ������ꂽ�������ɕs�\�ȏꍇ�A���͊O��ی쌠�̍s�g�ɂ���Ă���Q���~�ς���Ȃ��ꍇ�ɂ́A�l�����琿���ł���͂����A�Ƃ����_�������藧�Ƃ�������B
�@�������A���ŋ߂ł́A�Ƃ�킯�A�������{����L�̂悤�Ȍ����������Ă�����������錾�i�y�ѓ��錾���m�F�����������a�L�����j���߂����āA����������Čl�̐��������������������̂Ƃ͂����Ȃ��Ƃ̌����m�Ɏ������̂������Ă��Ă���B�Ⴆ�A�����n���ٔ����́A�����l�̋����A�s�E�����J�����߂��鑹�Q�������������ɂ�����2002�i����14�j�N4��26���̔����ŁA�u�T���t�����V�X�R���a�����������A�����́A�����������A���{���{�ɑ��āA�����푈�ɂ����Ĕ�������Q�̔����𐿋�������Ƃ̗�����̂��Ă������ƁA�܂��A���a62�N���납��A���������ł́A���{���{�ɑ��ď�L���Q�̔������s������Ƃ̌������x�������悤�ɂȂ�A�����̑K���[���O���́A����7�N3��9���A�������������ŕ��������͍̂��ƊԂ̔����ł����āA�l�̔��������͊܂܂ꂸ�A�⏞�����͍����̌����ł���A���{�͊����ׂ��łȂ��|�̌��������������ƂȂǂ̎�����l������ƁA�������������y�ѓ������a�F�D���ɂ��A���������ŗL�̑��Q�������������A�������{�ɂ���ĕ������ꂽ���ɂ��ẮA�@�I�ɂ��^�`���c����Ă������̂Ƃ��킴��Ȃ��B���������āA������̑��Q�������������A�������������y�ѓ������a�F�D���ɂ��A�����ɕ������ꂽ���̂ƔF�߂邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B�v�Ƃ��Ă���B
�@����ɁA�����n�ق́A���\�͂��������l�����̑��Q�������������ɂ�����2003�i����15�j�N4��24���̔����ŁA��L�̃h�C�c�A�M���@�ٔ����̌����Ǝ����I�ɓ�������ɂ����āA���ɂ���ĉ����ς݂Ƃ̓��{���{�̎咣��ނ��Ă���B����ɂ��ƁA�u�퍐�m���n�́A�������������������āA��Q�Ҍl�̉䂪���ɑ��鑹�Q�������������������ꂽ�Ǝ咣���邪�A���������A���ۖ@�̊�{�I�g�g�݂̂Ȃ��ʼn��߂����ׂ��ł����āA�����푈�ɂ�������Q���ł���䂪���ɑ��A���̑��荑�ł��钆�ؐl�����a���i�푈�����͒��ؖ����j�����Q���������A������w�푈�����x����������ɂƂǂ܂�A���荑�̍����ł����Q�Ҍl�̉䂪���ɑ��鑹�Q���������A������w��Q�����x�܂ŕ����������̂ł͂Ȃ��B��Q�����������l�Ƃ��ĉ��Q�҂ɑ��đ��Q���������߂邱�Ƃ́A���Y�����ŗL�̌����ł����āA���̉��Q�҂���Q�҂̑����鍑�ƂƂ͕ʂ̍��Ƃł������Ƃ��Ă��A���̑����鍑�Ƃ����̍��ƂƂ̊ԂŒ����������������Ĕ�Q�҂̑��荑�ɑ��鑹�Q�����������������������̂́A�������ł����Q�҂Ɏ��瑹�Q�����`���𗚍s����ꍇ�ȂǁA���̑㏞�[�u���u�����Ă���Ƃ��Ɍ�����ׂ��Ƃ���A���ؐl�����a���ɂ����ẮA�������������邱�Ƃɂ���āA�������ɑ��ē����푈�ɌW���Q�����甅�����邱�ƂƂ��āA�䂪���ɑ��鑹�Q����������������������Ƃ����`�Ղ͂Ȃ��A�퍐�̎咣�͍̗p�����Ȃ��B�v�Ɣ������Ă���B���̔����ł́A�u���̓_�́A���������A�䂪���ɂ����Ă��A�Ⴆ�A���\�����錾�ɂ��Ă��A���ؐ���������ɂ��Ă��A���{�����́A�����ł����Q�҂̑��荑�ɑ��鑹�Q�����������܂ŕ����������̂ł͂Ȃ��Ƃ��āA�����ے肵�Ă��邱�Ƃ�������t������Ƃ����ׂ��ł���B�v�Ƃ��āA���{���{�̉��߂̖������w�E���Ă��邱�Ƃ��d�v�ł���B
�@�{���ې�̎��ẮA�����̎��ĂƓ��l�ɓ������������y�ѓ������a�F�D���ɂ����锅���������W���Ă�����̂ł��邪�A���̓_�ɂ��ẮA��L�̓����n�ٔ������������Ă���ʂ�A�������������y�ѓ������a�F�D���ŕ������ꂽ�����͂����܂ō��ƊԂ̂��̂ł����āA��Q�҂��钆�������̌ŗL�̌����܂ŕ����������̂ł͂Ȃ��Ƃ݂�̂��Ó��ł���B���̂悤�Ȍ����́A�������{�̌����Ƃ��A�܂��A���{���{���]���Ƃ��Ă��������Ƃ���v���A���A���݂̍��ۖ@�̌����Ƃ����v������̂ł���B���ƊԂŔ�������������Ă���Ƃ��Ă��A��Q�Ҍl�̑��Q���~�ς��ꂸ�Ɏc���Ă������A�l���炪���p�����鍑���I��i�ɂ���đ��Q�̋~�ς����߂邱�Ƃ͉���W����ꂸ�A�����ٔ��������������l�̑i����R�����Čl�ɓK�ȋ~�ς�^���邱�Ƃɂ́A����̖@�I�Ȗ������݂��Ȃ��Ƃ����ׂ��ł���B
�i�T�j���ېl���@�ᔽ�̔�Q�҂��~�ς��錠��
�@�Ō�ɁA�{���ő��Q���������߂Ă����Q�҂͍��ېl���@�Ɉᔽ����ې�ɂ���ďd��ȑ��Q�������҂ł��邱�ƂɊӂ݁A���ېl���@�ᔽ�̔�Q�҂��~�ς��錠�����߂��鍑�ۖ@�̓W�J�ɂ��Č��y����B
�@�܂��A���ۖ@���܂ޖ@�ɂ���ĕی삳�ꂽ�����̐N�Q�ɑ��āA�l�������ٔ����ɋ~�ς����߂錠���́A���ꎩ�́A�����A���K���ۖ@�Ƃ��Ċm�����Ă���B���E�l���錾�͑�8���Ţ���ׂĂ̎҂ͤ���@���͖@���ɂ���ė^����ꂽ��{�I������N�Q����s�ׂɑ��Ĥ�����̂��鍑���ٔ����ɂ������I�ȋ~�ς��錠����L���顣�Ƃ��A�s���I�y�ѐ����I�����Ɋւ��鍑�ۋK���2��3���A���[���b�p�l�����13���Ȃǂ̐l���������ʓI�~�ςɊւ���K��������Ă��邪�A�����A�ٔ����ւ̃A�N�Z�X���ƁA����ɕt������A���ʓI�~�ς��錠���́A���K���ۖ@�Ɋ�Â���{�I�l���ł��邱�Ƃ��L���F�߂��Ă���iJ.Paust,
International Law as law of the United States,1996, p.199�j
�@����ɁA�ߔN�A�Ƃ�킯1980�N�㖖����1990�N��ȍ~�̍��ێЉ�ł́A���E�e���ɂ�����̐��ύX�i����ď����ɂ�����R�����疯���ւ̈ڍs�A���Љ��`���̑̐�����Ɩ��吧�ւ̈ڍs���j�ɔ����A�ߋ��̐l���N�Q�ւ̑Ώ������ƂȂ��Ă������Ƃ���A�d��Ȑl���N�Q�̔�Q�҂��~�ς��錠���ɂ��č��ۖ@��̌������W�听���铮�����}���ɍ��܂����B���A�l���ψ���̉����@�ւł���l�����ψ����1989�N�A�d��l���N�Q�̔�Q�҂̋~�ςɊւ�����ɂ��ē��ʕ҃t�@���E�{�[���F����C�����Č������s�킹�邱�ƂƂ��A1993�N�ɂ́A�t�@���E�{�[���F���ɂ��A�l���y�ъ�{�I���R�̏d��ȐN�Q�̔�Q�҂��~�ς��錠���ɂ��Ă̌������Ă���o���ꂽ�i1996�A1997�N�����j�B�����āA1998�N�ɂ́A�l�����ψ���́A�t�@���E�{�[���F���̌������Ăɂ��āA���y�є{�c�̂���̃R�����g�A���тɐl���N�Q�̉��Q�҂̕s�����Ɋւ�����ʕ҃W�����l�̍�Ƃ��l���ɓ���ĉ��������Ƃ̔C�Ƀo�V�I�[�j��C�������B���̌��ʁA2000�N�ɁA�u���ېl���@�y�ѐl���@�ᔽ�̔�Q�҂��~�ϋy�ѕ⏞���錠���ɂ��Ă̊�{�����y�уK�C�h���C���v���l���ψ���ɒ�o���ꂽ���iE/CN.4/2000/62,Annex�j�A�������E�K�C�h���C���́A���ׂĂ̍��Ƃ͍��ېl���y�ѐl���@�K�͂d�A���d���m�ہA���s����`��������A����ɂ͈ᔽ�̖h�~�A�ᔽ�̒����A��Q�҂ɑ���K�ȋ~�ς��܂܂��Ƃ���ƂƂ��ɁA��Q�҂��⏞�i����A�����A�T�e�B�X�t�@�N�V�����y�эĔ��h�~�i�����̌��I�J���A��̂̑{���E�����A��Q�҂̑�����������I�錾�A�Ӎ߁A���ېl���E�l���@�̌P���⋳�ނɂ����鎖���̐��m�ȋL�q�̂悤�ȍĔ��h�~����܂ށj���錠�������Ă���B����́A���ł͂Ȃ����̂́A�e���������R�����g����荞�݂쐬����Ă���A���̖��Ɋւ��錻�i�K�̍��ۖ@�̔��W�������d�v�ȕ����ł���B�����āA��ɂ��ӂꂽ�悤�ɁA���A�l�������ٖ������������J�Â����{�����̌�����c�ŁA�ԏ\�����ۈψ����\�́A�n�[�O���3���͔�Q�҂ւ̔��������Ƃɗv��������̂ł���Ƃ̗���m�ɔ������Ă���̂ł���iE/CN.4/2003/63,paras.50,118�j�B
�@�d��Ȑl���N�Q�̔�Q�҂���������ׂ��ł���Ƃ��������̍��ۖ@�I�ȏ��F�́A���یY���ٔ��̑��ʂɂ��e����^���Ă���B1998�N�ɍ̑����ꂽ���یY���ٔ����K����75���ŁA��Q�҂ւ̔����Ɋւ��鏔�������߂邱�ƁA�ٔ������L�ߔ��������҂ɑ��Ĕ�Q�҂ւ̔����ږ������邱�Ƃ��߁A�葱�؋��K���ł́A��Q�҂����ڂɖ��͑㗝�l��ʂ��Ĕ�����\���Ă錠����F�߂Ă��邪�A�����́A�l���N�Q�̔�Q�҂̌����Ɋւ��鍑�A�l���ψ���ł̋c�_�f���đ}�����ꂽ���̂ł���B�܂��A�����[�S�X���r�A���یY���ٔ����̍ٔ����c��2000�N�A�u��Q�҂̔����ƎQ���v�Ƒ肷����ŁA��Q�҂��������錠���͍��ۖ@��F�߂���X���ɂ���A�ٔ����̊NJ��ɑ�����l���ɑ���ߓ��̔�Q�҂ɂ͔������錠��������Əq�ׁA���ې����ψ���̂悤�ȋ@�\�̐ݒu����Ă���iVictims'
compensation and participation, Letter dated 2 November
2000 from the Secretary-General addressed to the President
of the Security Council, Appendix,S/2000/1063�j
�@�{�����Ăɂ������Q�҂́A�ې�̔�Q���̂͐펞���ɔ����������̂ł��邪�A���Q���ł�����{�������Q�҂̋~�ς��s��Ȃ��܂ܐ��\�N�����u���A���݂ɂ����čٔ����ɋ~�ς����߂Ă�����̂ł��邩��A���̋~�ς́A���ېl���@�̈ᔽ�ɂ��d�傩�p���I�Ȑl���N�Q���~�ς���Ƃ����ϓ_����A�����̍��ۖ@�ɂ����锭�W�����l���ɓ���ĂȂ����ׂ��ł���B���Ȃ킿�A�����̍ې�ɂ���Q�͂��邱�ƂȂ���A����[�u���Ƃ邱�ƂȂ��������u���Ă������Ƃɂ���Q�҂̋ꂵ�݂��A���킹�ċ~�ς̑ΏۂƂ����ׂ��ł���A���̋�̓I�ȓ��e�́A���Q�����̂ق��A���₩�ȎӍ߁A�����̌��I�J�����A�V��̔�Q�҂ɂӂ��킵���K�ȓ��e�̂��̂ł���ׂ��ł���B
�S�@����
�@�{�����Ăł́A�����ې�ɂ���č��ېl���@�Ɉᔽ���Ĕ�Q�҂ɑ���ȑ��Q��^�������Ǝ��̂͑��R�����ł��F�߂��Ă���A���̏�ŁA��Q�҂ɑ��鑹�Q�����̉ۂ����Ƃ���Ă��邪�A�����������_�Ƃ��āA�n�[�O���R������e�Ƃ��銵�K���ۖ@�������������A��Q�Ҍl�����Q�����瑹�Q�����邱�Ƃ�W����@���͉��瑶�݂��Ȃ��B�n�[�O���R���́A���̗��s�̂��߂ɂ����Ȃ�葱�I�ȉ\�����r�����Ă��炸�A��Q�Ҍl�����荑�̍ٔ����ɂ����Ĕ����������N���邱�Ƃ����r�����Ă��Ȃ��B�ᔽ�̏ꍇ�̔����ƐӔC�Ƃ������̗v���̎����ɏd���������Ȃ�A���ꂪ��������Ă��炸�A���A�����̊O��I�����Ɋ��҂��邱�Ƃ��s�\�ł��錻�݁A��Q�Ҍl�����Q���Ō����~�ς����߂邱�Ƃ́A������B��̂��肤���i�ł���B�܂��A�������������y�т�����m�F�����������a�F�D���ɂ����鍑�ƊԂł̔����̕����́A��Q�Ҍl���L����ŗL�̑��Q�����������܂ł�����������̂Ƃ͂����Ȃ��B����ɁA���ېl���@�̈ᔽ�ɂ���ďd��Ȑl���N�Q�����҂����̋~�ς��錠����L���邱�Ƃ́A�ߔN�̍��ۖ@�ōL���F�߂�����A�Ƃ�킯�{���̂悤�ɁA�d��Ȕ�Q���㐔�\�N�����u���Ă������Ƃɂ��p���I�Ȑl���N�Q�������Ă���ꍇ�ɂ́A��������܂߂���Q�ɑ��Ď����I�ȋ~�ς�^����K�v���Ɛ������͂���߂č����Ƃ�����B�M�ٔ����ɂ����ẮA�l���ۏ�̍Ԃ���i�@�{�Ƃ��āA��Q�҂Ɍ����~�ς�^���A���ېl���@�̈ᔽ��Ԃ��������锻�f���������Ƃ��������߂��Ă���B
�\�@��?�i���� �ւڂ�j����
���N���� 1966�i���a41�j�N1��16�������ɂďo���i38�j
���E �R�w�@��w�@�w��������
��U ���ۖ@�A���ېl���@
�ŏI�w�� �@�w���m�i������w�j
��v��E�@�@ ���ۖ@�w��]�c���A���ېl���@�w���
���Z�� �����s������v��R4�|29�|31
���o����
1988�N3���@ �R�w�@��w�@�w�����@�w�ȑ���
���N4�� �@������w��w�@�@�w�����w�����ȏC�m�ے����w
1990�N3�� �@���C��
���N4�� �@ ������w��w�@�@�w�����w�����Ȕ��m�ے����w
1991�N10���@ ���x�w�A�W���l�[�u���ۍ����������C�m�ے����w
1993�N8�� �@ ���C���A���������f�B�v���}�i�c�d�r�j�擾
���N9�� �@ ������w��w�@�@�w�����w�����Ȕ��m�ے����w
1995�N�S���i�`1996�N3���j ���{�w�p�U������ʌ�����
���N11���@ �u�l������̍��Ƃ̋`���v�Ŗ@�w���m�i������w�j�擾
1996�N4�� �@�R�w�@��w�@�w����C�u�t
1997�N4�� �@���������A���݂Ɏ���
����v�Ɛс�
�m����]
�E�w�l������̍��Ƃ̋`���x���{�]�_�ЁA1999�N
�@�@�@�@1999�N�x�R�w�@�w�p�J�́A2000�N�x���B���Y�L�O��
�m�_���n
�E�u�l�����̐l�I�E�̈�I�K�p�͈́|�w�NJ����x�ɂ���l�̐l���ی�v �R�@�w�_�W��38����3�E4�������A1996�N
�E�u�l������̍��Ƃ̋`���|�����{�ɂ�����l���_�̍čl�i��j �i���j�v���ۖ@�O���G����96���P�E�Q���A1997�N
�E�u���B�����Ɛl���\����ɂ�����l���ی�v�u�d�t�̑ΊO����Ɛl���v
���c�Ǖ��ҁw�d�t�|21���I�̐����ۑ�x�i�������[�A1999�N�j����
�E�u�l������ɂ����鍑�A�̑g�D�Ɗ����v�w���ۖ��x474���A1999�N
�E�u�l�ʕx�v�@�w�Z�~�i�[530���A1999�N
�E�u�Љ�K��̎��{�ɂ����鍑�Ƃ̋`���|�w�l���x�Ƃ��Ă̎Љ���Ӗ��� ����́v�A�W�A�E�����m�l�����Z���^�[�ҁw�A�W�A�E�����m�n��ɂ�
����Љ�K��̗��s�Ɖۑ�x�i����l���ЁA2001�N�j����
�E�u�j���[�W�[�����h�̐l���@�Ɛl���ψ���|�����̑n�ӂƎ��т���w�Ԃ��́v �m�l�o������E�R����m�Ғ��w�����l���@�ւ̍��۔�r�x�i����l���ЁA
2001�N�j����
�E�u�l�퍷�ʓP�p���̌l�ʕx�̉^�p�\�ψ���ɂ����@�̓W�J�v�� �R�@�w�_�W��44����3�E4�������A2003�N
�E�u���ېl���̋~�ϕ��@�v�W�����X�g1244���A2003�N
�E�u�l���ƊJ���̎����I�����Ɍ����ā\�l���ۏ�y�ъJ���ɂ�����Љ�I�E�� �x�I��Ղ̏d�v�����߂����l�@�v�@�w�V���109����11�E12���A��
����w�@�w��A2003�N
�m�|��E����n
�E�u���|��E������w�o�ϓI�A�Љ�I�y�ѕ����I�����Ɋւ���ψ���x�̈� �ʓI�ӌ��v�R�@�w�_�W��38����1���A1996�N
�E�u���|��E������w�o�ϓI�A�Љ�I�y�ѕ����I�����Ɋւ���ψ���x�̈� �ʓI�ӌ��i2�j�v�R�@�w�_�W��39����3�E4���A1999�N
�m����]�߁n
�E�u�O���l�̏o�����Ɗ��K���ۖ@�|�}�N���[�������v�R�{����E�Ð�Ɣ��E�� ��F�Y�ҁw���ۖ@����S�I�x�ʍ��W�����X�g156���A2001�N
�E�u�ދ������葱�ɂ�������e�Ɠ���v�w����13�N�x�d�v�������x�W�� ���X�g1224���A2002�N
�m�ٔ��ӌ����n
�E�u�ӌ����@���ېl���K��тh�k�n���ɂ�����J���g�����̕ۏ�ɂ� �āv�i�S��J�����������������A�����n�فj2000�N�A�J���@���{��1505
���A2001�N
�E�u�ӌ����v�i�o�q�ɑ���@����̋�ʂ̏��K�����ɂ��āj�i�ːБ� ���L�ڒ��������������A�����n�فj2002�N�A�R�@�w�_�W��45��3���A
2003�N
|